| No.78 冬の基礎練習〜ゴロ捕球〜(2008.1.16) | ||||||||
|
さて、よくもここまでほったらかしにしたな〜…というくらい久しぶりに更新しますが、今回は冬の基礎練習ということで、「ゴロの捕球」について考えてみたいと思います。最近うちのチームに若い子が増えてきたので、この冬はオバチャンも一緒になって基礎練習に取り組もうと思うのですが、果たして体力的についていけるか心配です…。みなさんも童心に返り、(老体にムチ打って)基礎練に明け暮れましょう!
ゴロ捕球をマスターしようわたくし、女子野球界にけっこう長く生息していますが、女子では初めて野球する人も多いためか、いろんなところで試合や練習を見ているとゴロの捕球のときに腰が高くなってしまってる姿をよく見かけるんです。軟球はよく跳ねて高いバウンドが多くなるため、低い捕球姿勢が身に付きにくいのかもしれませんね。別に捕れてるからいいやんと思ったりもするんですが、でも、せっかく野球を始めたなら「おっ、なかなかやるやんか、あの子!」と言われるような、かっこいいプレーがしたいですよね。そのためには、まず基本的なゴロの捕球をしっかりと身に付けて、そしていつかスタンドからキャーキャー騒がれるようなスタープレーヤーになりましょう! ●腰が高いとこうなります まずは、「腰が高い」とはどういうことかみてみましょう。【写真1】を見ていただくとわかりやすいと思いますが、ボールを捕るときにヒザが伸びていて腰の位置が高くなっています。この捕り方をすると、グラブを上から下へ押し付けるような動作で捕るクセがついてしまいます。また、目線が高いのでボールをトンネルをすることも多くなります。なので、できるだけヒザを曲げて腰を落とし、低い姿勢での捕球をこころがけましょう。
●こんなに簡単!低い姿勢を身につけるコツ それではゴロを捕るときに姿勢を低くするコツをご紹介しましょう。めちゃくちゃ簡単ですよ。まず以下のような動作をして、捕球の姿勢を覚えましょう。
これは「股割り」と呼ばれる種類のものですね。某高校の女子硬式野球部が冬季に徹底して練習した結果、なかなか効果があったそうですよ。よかったらみなさんもお試しくださいませ。
ゴロ捕球の練習法では最後に、股割りを使った練習方法をご紹介して今回は終わりにしたいと思います。 ●耐えて忍んで筋肉痛!「股割り捕球」
●基礎を制するものが世界を制す!「ゴロ転がし」 っちゅうことで、偉そうなタイトル付けましたが、ただ単にさっきのメニューをアレンジしたものです。1人がボールを転がす役で、他の人は数メートル離れた場所に集まり転がってきたボールを素手で捕球します。ボールを捕る時はさっきの「股割り」の状態を意識して腰を落として捕球してくださいね。ボールを投げる方向がファースト方向なので、捕球の時はボールに対して少しふくらんで斜めから入りましょう(体は正面を向いたまま切れ込むように入ります)。捕球する時は、左足を一歩前に出して左足の前あたりでゴロを捕ると送球がスムーズにいきます。また、転がってきたボールに対して、歩幅を広くしたり狭くしたりしてボールに対する入り方を身に付けましょう。 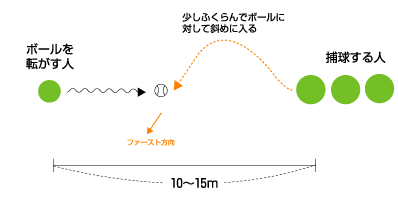 冬は基礎練習が中心になると思いますが、わたくしもこれを機会にテキトーに覚えていた捕球の形を見直そうと思います。やっぱ大事っすね、基礎練習! ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
最近、ちょっと前にここで取り上げた「野球占い・3」を自分でもやってみたのですが、かなり気分を害する結果が出まして、我ながら何を作っとるんだと思いました。次回作はもっと気分がよくなるものを作ろう…。さて、久々復活したこのコーナーですが、今年こそ少しずつ定期的に更新していきたいと思います。でも果たしてどうなることやら…。次回はたぶん近いうちに更新するはずです…。 |
| No.77 リスクマネジメント(2007.5.18) | |||||||||||||
|
先日大阪・岸和田市の高校で、試合中に胸に打球を受けた投手が一時的に心肺停止になり、偶然居合わせた救急救命士がAED(自動体外式除細動器)を使って蘇生させたという話がニュースになりました。野球では大きな事故はない、と思う方もいるかもしれませんが、実際にはこのような「心臓しんとう」による突然死、熱中症による死亡事故、落雷による事故、頭部への事故(脳挫傷、外傷性くも膜下出血)、失明、骨折…と大きな事故が起こっています。野球をする限り、いつどこで大きな事故にあうかわかりません。これからはリスクマネジメント(危機管理)について考えることも必要になってくると思います。今回は堅苦しい内容になりますが、スポーツと安全について考えてみましょう。
「心臓しんとう」を知っていますか?●心臓しんとうとは? みなさんは「心臓しんとう」というものをご存知ですか?冒頭にご紹介した岸和田での事故も胸部に衝撃を受けたことで起こる「心臓しんとう」です。心臓しんとうとは胸部に衝撃が加わることにより心臓が停止してしまう状態で、AEDなどで適切な処置を施さないと10分で死にいたるそうです。また心臓しんとうは、骨などが十分に発達していない子どもや若い人におきていて、その多くはスポーツ活動中の事故によります。日本でも10数件の発症例があり、そのほとんどが野球やソフトボールでの事故によるもので、ボールやバットが胸に当たったことが原因なんだそうです。このように野球でも死にいたる危険な事故が潜んでいます。もし機会があればみなさんのチームでも「心臓しんとう」について考えてみてくださいね。少年野球チームや小・中・高校のクラブ活動はもちろんのことですが、小・中・高校生が所属するクラブチームでも注意が必要です。 ●予防するには? さて、心臓しんとうを予防する手段ですが、身体が未発達の小中学生には胸でボールを受け止めるという指導を避けたり、硬いボールほど心臓しんとうを起こしやすいので小中学生の間はなるべく硬球ではなく軟球を使うようにするといった対応をした方がよいそうです。また、当たり前のことなんですが、小さい子どもがいるような場所ではキャッチボールや素振りをしないということもチームで確認しておいた方がよいでしょう。市民広場のように一般市民も利用するような場所で練習するときは特に周りに注意を払いながら練習する必要があると思います。さらに、最近ではスポーツメーカーのミズノが「野球・ソフトボール用胸部保護パッド」というものを発売していますので、興味のある方は導入も検討してみてくださいね。 ■参考
●もしも「心臓しんとう」がおきてしまったら? それでも、もし「心臓しんとう」がおこってしまったら、どうすればいいのでしょうか。「心臓しんとう」は心室細動による心停止なので、AED(自動体外式除細動器)による電気ショックが唯一の治療方法(救命処置)と言われています。心停止してから1分ごとに10%ずつ救命率が下がるので、救急車が到着するまで待っていては間に合わないそうです。つまり「現場」にいる人たちの素早い救命処置が必要不可欠なのです。以下に心肺蘇生の手順を簡単にご説明しますが、詳しいことは本やネットで調べたり講習会などで教えてもらって下さいね。
これからは利用する野球施設のAEDの設置状況を確認したり、チームでAEDを購入またはレンタルしたり、AED使用方法の講習を受けたりすることも必要になってくるかもしれませんね。心臓しんとうの多くは「野球」で起きているので、できればすべての野球施設にAEDを設置してほしいと思います。
●AEDは誰でも使えます
○日本赤十字社 救急手当
●救命講習について また、AEDの使い方を含む救命処置についての講習会が、地域の消防署や赤十字社などでおこなわれていると思います。もし興味のある方は、そちらの方へ参加してみてはいかがでしょうか。ちなみに大阪市の消防局では市内在住・在勤・在学者に対して無料で講習をおこなっていますので、また利用して下さいね。 ○大阪市消防局「普通救命講習」(3時間・無料)
安全の確保と事故の防止を!さて、「現場」でのリスクマネジメント(危機管理)で一番大切なことは安全の確保と事故の防止だと言われています。具体的には各個人の体力や持病などを把握して練習計画を立てたり、活動中の監視・監督をおこなったり、また緊急時への対応を計画したりといったことです。 ●危険回避能力を高める でもリスクマネジメントと言っても、何からどう始めたらいいかわからないと思いますが(管理人もわかりませんが)、まずはチーム全体でスポーツ事故に対する危機意識を高めることからはじめてみてはいかがでしょう。もし時間があれば、「活動するにあたってどんな危険があるのか」、そして「その危険を回避するために何をするべきか」ということについてチームで話し合う機会を持ってみてください。例えば「熱中症による死亡事故」に対しては「30分ごとの水分補給や活動中の監視の徹底」といった具合に、安全に活動するためのルールや環境を整えることもリスクマネジメントとして大切なことです。クラブチームでは、メンバーはみんな大人だから自己管理できると思うかもしれませんが、危険を回避する知識があいまいなこともありますし、また小中高校生が所属するチームでは体力差や自己管理能力の差があることを考えて、チーム全体の危険回避能力のレベルを高めることも必要となってくると思います。 ●緊急時に備える とはいえ、スポーツでは予測不能な事故が起こるものです。そこで大切なことが「緊急時の対応」です。まさかそんな大きな事故は起こらないよと思う人もいるかもしれませんが、緊急の事態に備えることもリスクマネジメントの1つです。緊急事態にちゃんと対応できるかどうか、また普段から緊急時に備えての準備が出来ているかどうか、確認してみて下さいね。下に例を挙げておきましたので参考にして下さい。
クラブチームでは主に医療機関が休みの日曜日などに練習をしていることが多いと思いますが、救急箱の中に休日・救急医療機関連絡先を入れておいたり、携帯に休日・救急医療機関の連絡先を登録しておいてはいかがでしょうか。また、救急処置の方法をなどをプリントアウトして救急セットの中に入れておいてもよいかと思います。以下に大阪府下の休日・救急医療機関が載っているHPをご紹介しておきますので、よろしければ参考にして下さいませ。 ○大阪府医療機関情報システム…休日・夜間急病診療所・救急病院(診療所)一覧が掲載 ○大阪府医療機関情報システム(携帯用)…休日・夜間急病診療所・救急病院(診療所)一覧が掲載
●スポーツ保険 もちろんみなさんも「スポーツ保険」に入っておられると思いますが、この保険に加入することもリスクマネジメントとして大切なことです。一般的には(財)スポーツ安全協会のスポーツ安全保険が利用されていると思いますが、(財)スポーツ安全協会のHPをご紹介しますので、また機会があればスポーツ保険についても知っておいてくださいね。 ○ (財)スポーツ安全協会 http://www.sportsanzen.org/
●免責について スポーツにおいては自己責任が原則であり、自分の不注意で起きた事故は自分で責任を取らなければなりません。よく入部届(入会届)に免責同意条項(ウェーバーフォーム)というのが書かれていることがあると思いますが、これは「活動中にケガをしたのは自己責任であり、指導者(責任者)側には責任を求めない」という内容を定めたものですね。ただ、日本の裁判ではこの免責条項が法的な紛争の時に効力を生じることはほとんどないそうです。いくら免責を求めても、指導者側が注意義務を怠った場合など指導時の事故に対する法的責任は逃れられないわけです。もし免責についてきちんとしたいならば、インフォームドコンセント(説明と同意)により、具体的な危険について説明し書面によって事前の承諾を得ることが必要なのだそうです。ただ、スポーツ活動には避けることのできない「本質的な危険」というものがあり、ルールに従って活動していても予測不能で避けられない事故が起こることもあります。こういう場合、指導内容と事故との間に因果関係がなければ免責されることがあるそうです。 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
さて、そろそろ暑い夏が近づいてきます。熱中症による事故も増えてくる時期なので、気をつけて下さいね。特に小中学生のいるチームでは大人との体力差がありますから、十分に配慮して活動してほしいと思います。と言うか、うちのチームでは若い子の方が断然体力があるので、むしろ危ないのは私たちかもしれません…。オールナイトで飲んで歌ってそのまま練習へ来る不摂生なバカ者(管理人)がときどき熱中症にかかったりしてますからね。若い子もいるから、そういうおバカなことはもう卒業します…。さて、今回も中途半端な知識で書いてるので、ちゃんとしたことは必ず専門の方に聞いたり調べたりして下さいね。また、かなり堅苦しい内容になってしまいましたが、できればこれを機会にみなさんのチームでもスポーツ活動におけるリスクマネジメント(危機管理)について話し合い、取り組んでいただけたらなぁと思います。 ▼参考文献:「コーチングクリニック2006年6月号」(ベースボールマガジン社)他 |
| No.76 ランナー2塁でのバントシフト(2007.4.11) | |||||
|
今回は「ランナー2塁でのバントシフト」について考えてみたいと思います。女子野球の試合などを見ていると、「ランナー2塁・送りバント」というケースで守備がうまくいかないのをよく見かけるんです。私もどう動いていいかわからず右往左往してはミスを大量生産してました。っちゅうことで、今回はバントされるたびに内野を大混乱に陥れる管理人とともに、まともなバント処理ができるようオベンキョーしていきましょう!
ランナー2塁でのバント●なぜランナー2塁でバントをするの? まず、ランナー2塁(1・2塁)での送りバントについて、ちびっとお話ししましょう。ランナー2塁で送りバントが使われるケースは、「とにかくランナーを3塁へ進めて犠牲フライやスクイズで1点を取りたいねん!」という企みが背景にあることが多いです。2塁というスコアリングポジションにランナーがいても、このピッチャーからはなかなかヒットが打てないな、というときに使うわけですね。なので、「ランナー2塁で送りバント」の延長上にある作戦も守備側は頭に入れておいた方がいいと思います。とくにノーアウトでランナー2塁(または1・2塁)の時にバントをするケースが多いので、そういう時は要注意ですよ! ●あなたが狙われている!
こんなミスに気をつけて!では、ランナー2塁でときどき見かける失敗をご紹介しましょう。って、偉そうに書いてますけどね、実はうちのチームが大昔こういう失敗をしたことがあったんで、ぜひとも教訓にして頂こうと思って書いております。女子野球ではまだ守備面が未整備の新しいチームもあるので、もしよければ私たちの昔の赤っ恥を参考にして下さいませ。 ●猪突猛進はいけませんよ
●斜めに構えて盗塁対策 じゃあ、バントか盗塁かわからないのに、サードはどうやって守ればいいのよ!ってことなんですが、ふつうサードはバッターに向かって構えますが、2塁にランナーがいるときサードはバッターと2塁ランナー両方の動きが見えるように斜めに構えます(写真)。そしてランナーが盗塁をしてきた場合はベースに入り、ランナーが盗塁をしてこない場合はバッターに対する守備に入ります。
ランナー2塁でのバントシフトそれでは最後にランナー2塁(または1・2塁)でのバントシフトについてまとめておきます。大きく分けて2つのパターンがあるのですが、1つはバッターがバントかヒッティングかわからない場合のバントシフトと、もう1つはバッターが確実にバントをしてくるとわかる場合のバントシフトです。 ●バッターがバントかヒッティングかわからない場合 まずはノーアウト・ランナー2塁(または1・2塁)でバッターがバントをしてくるのか打ってくるのかわからない場合のバントシフトについて説明します。これは確実にアウトカウントを増やそうという守り方で、ランナー2塁での基本的な守備隊形になります。(番号は各野手の守備位置を示しています)
●バッターが確実にバントをしてくる場合 次にノーアウト・ランナー2塁(または1・2塁)で、試合展開からバッターが確実にバントをしてくるとわかる場合のバントシフトについて説明します。この守り方は2塁ランナーを3塁でアウトにすることが最大の目的です。そしてここで「キー・プレーヤー」となるのはショートです。
●まとめ 試合などを見ていて思ったんですが、このバント守備が混乱する原因は、内野陣がそれぞれどの守備隊形を取るか確認できていない時におこっているようです。わかりやすくいうと「アウトカウントを増やすための守備隊形」なのか「絶対にランナーを進めないための守備隊形」なのかということをプレーの前に確認していないため、バントをされても内野手がそれぞれバラバラ動きをしてしまってるんです。なので、もしチームで「ランナー2塁でのバント守備」があいまいならば、ちゃんと確認練習をしておいた方がいいと思います。そもそもこういうパターンで連係のミスがでると、「何やってんだよ」的な冷た〜い空気が流れちゃいますが、これはミスをした人が悪いのではなく、チームでちゃんと確認練習をしていないことが一番悪いのです。つまりはチーム全体の責任、ちゃんと練習しましょうね。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
っちゅうことで、「ランナー2塁でのバントシフト」いかがだったでしょうか。連休もあることですし、一度長い練習時間が取れるならば、ランナー2塁からのバント処理の確認練習をしておいた方がいいと思います。2パターンしかないのでやりやすいと思いますよ。さて、今回も若干アヤしげな知識で書きましたが、なんとかごまかしきれました。ただ、最近長い文章を書くことがなかったので、たまにこういうのを書くとものすごく疲れますね。しかし今年は心を入れ替えて、これでもか!これでもか!と更新していきますので、よろしくおつきあい下さいませ。 ▼参考文献:「野球指導の手引き」スポーツ科学トレーニングセンター編集 「アマチュア野球教本」功力靖雄・著(ベースボールマガジン社)他 |
| No.75 野球占い・3!(2006.12.2) ▲上に戻る |
|
お待たせしました、占うたびに気分を害する「野球占い・3」!若干グレードアップして登場です。毎回申し上げますが、この占いは管理人が思いつくままに作ったいい加減モノなので、気にせず一喜一憂してくださいね。
■2007年の運勢は?以下の野球に関する質問に答えて最後に「占う」ボタンをクリックして下さい。占いの結果が別画面で表示されます。2007年のあなたの運勢を占ってください。
■理想のお相手占い!普段は野球ばかりに没頭して色恋沙汰には無縁なのでは?そんな野球バカたちに贈る「理想のお相手占い」。以下の野球に関する質問に答えてあなたにぴったりのお相手を探してみましょう!
■プレースタイル占い!あなたのプレースタイルを徹底分析。以下の野球に関する質問に答えて、あなたの来年の野球運を占ってみましょう!
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
いかがだったでしょうか。今回は息抜きということで恒例の野球占いをぶちかましてみました。前回かなりマジメにやってしまったので軌道修正です。最近はほんまに忙しくて時間がなかったので、会社の昼休みにコソコソ作ってました。そういえば昔は忙しくても昼休みなどを使って月2回更新してたなぁと思うと、時間がないんじゃなくて気力がなくなってきたんでしょうね。また若いモンと遊んでリフレッシュして、ガッツンガッツン更新していきたいです! |
| No.74 野球肩は治る!(2006.9.30) ▲上に戻る | |||||||||||||||
|
さて、今回取り上げるのは「野球肩」。管理人もずいぶん長い間この野球肩による投球障害に悩まされてきたんですが、昨年冬から徹底して治療にあたった結果、けっこうあっさり治っちゃいました。っちゅうことで今回は、同じように肩痛で苦しんでいる人のお役に立てればと思い、「管理人の野球肩歴」と「病院の選び方」、そして「簡単なトレーニング」の3つにしぼってご紹介したいと思います。
コレで肩が治りましたまずは、管理人が肩を痛めてから治るまでの経過をご紹介します。そんなもんどうでもええねんという方は、すっ飛ばして先へ読み進んでくださいませ。 ●8年間痛かったんですが… 私が初めて肩を痛めたのは今から8年前、22歳の時でした。最初はそれほど痛くもなく、ムリをすれば投げられたので、病院にも行かずそのまま放置していたんです。ところが年々その痛みはひどくなり、次第に思い通りに投げられないようになりました。ここ数年は塁間を投げるのがやっとという状態で、思うようにプレーできなくて練習もままならず、この時期は本当に野球をするのがつらかったです。 それでも痛いのをごまかして強引に投げ続けたため、最終的に大きな故障へとつながりました。昨年7月、試合前のキャッチボールでボールを投げた瞬間、肩の後ろから横にかけてビリッ!!!という強い電流のようなモノが流れたんですね。その時はあまりの痛さにボールも投げられませんでした。後で病院に行ったら三角筋損傷とのこと。それからはますます肩の状態は悪くなって、さらに10月の試合でヘッドスライディングをしたときに肩をうって同じ箇所を故障してしまったんです。この時はかなりひどく痛めたようで、2ヶ月経っても痛くて肩がまわせず、つり革も持てないような状態でした。もちろんボールも5メートルくらいしか投げられず、もうこれで野球はムリかもと半分あきらめていたんです。 ●スポーツクリニックで半年かけて野球肩を克服 その後、ともかく一度専門の病院でみてもらおうと、スポーツ障害の治療をしている「パンジョスポーツクリニック」にお世話になることにしました。すると診察に行ったその日からリハビリ開始。いろいろトレーニングのメニューを組んでもらって、春までに全力投球をめざそうということになりました。私の場合、長期間痛いのを放置していたせいもあったでしょうし、インナーマッスルの他にアウターマッスルも痛めていたので回復するに時間がかかったのですが、1ヶ月、2ヶ月とリハビリを続けるうちに、5メートルくらいしか投げられなかったのが、10メートル、20メートル、30メートルと投げられるようになり、半年後の春には肩を痛める8年前とほぼ同じくらい、60メートルの遠投が出来るまでに戻ったんです。まさかここまで回復するとは思ってなかったので本当にうれしかったです。 ●あきらめずにトレーニングを 私の周りでは「肩が痛いのはもう治らないよ」と思っている人はけっこう多いんですね。私も昔はその一人でした。でもそれはちゃんとした治療方法があることを知らなかっただけなんです。毎日10分もかからないトレーニングをするだけで肩の状態はだいぶ良くなると思います。まずは専門の病院に行って治療を受けてくださいね。また、病院ではリハビリがあると思いますが、これも途中で放り出さずに続けて下さい。私も最初は思うように治らず、もうやめようかと思うこともありましたが、ここで中途半端にやめたら絶対治らんわと思って、徹底してリハビリに通いました。大切なのは「本当に野球が好きなら、練習と同じくらい治療も頑張れる」っちゅう気持ちだと思います。みなさんも、肩が痛くても、あきらめずに治ることを信じて治療を受けて下さい。そして思いっきり野球が出来る喜びを感じて下さいね。(→通院中の肩の状態の記録です)
病院を選ぼうそれでは次に、ケガや故障をしたときの病院選びについて考えてみましょう。これからは、ケガや故障をした時にすぐ診てもらえて、しかも大事な試合の前に相談できるような「かかりつけのスポーツ病院」を見つけておく方がいいと思います。みなさんも機会があれば、かかりつけのスポーツドクターを探してみてくださいね。 ●病院には行きましょう それではまず、病院を選ぶ前にケガや故障に対する正しい対処法を確認しましょう。よく言われることですが、私の経験からしても、故障をした時に一番大切なことは「自分で判断しない」ということです。なるべく病院に行って治療を受けて下さい。昔は私も病院嫌いだったので、肩が痛くても参考書などを読んで自分でトレーニングなどをしてみたんですが、一向に成果があがりませんでした。これは痛めている箇所(筋肉)を正確に把握できていないことや、それに対する正しい治療やトレーニングをしていなかったからだと思います。あたり前ですけどね、絶対に素人判断では治さない方がいいですよ。時間がかかる上に結局治らないし、ヘタしたら悪化します。ともかくケガや故障がある場合は、まず病院に行ってくださいね。それでは次にその「病院」について考えてみましょう。 ●一般の整形外科では不十分? スポーツ専門の病院へ 最近自分がケガをしてからは、野球肩や野球肘の人に病院へ行くように勧めるんですが、「どうせ病院に行っても、レントゲンとられて、湿布渡されるだけやん」という答えがよく返ってきます。確かにそうなんですよ。私も過去に肩や膝などの故障でいろんな病院の整形外科に行ったんですが、レントゲンやMRIをとって、顕著な異常がなかったら「様子を見ましょう」で終わりなんです。あとは湿布を渡されるだけで、何も解決しないんですよね。本当にガッカリします。これでは「病院に行こう」という気にならないし、自分でトレーニングして治した方がいいんじゃないかと思うわけです。 ●病院のご紹介 それでは、どんなスポーツ病院がいいのかということですが、やはりスポーツドクターのもと、理学療法士やトレーナーがそろっていてアスレチック・リハビリテーションを行っているような病院がいいと思います。あとは病院のスタッフがチームドクターやチームトレーナーとして活動しているところがいいそうですよ。スポーツの現場で場数を踏んでる分、知識や経験も豊富で信頼できるというわけです。 それと、私が通っている「パンジョスポーツクリニック」(大阪府堺市)ですが、大阪では有名な病院ですね。プロや社会人チームの選手も通っていたので敷居が高いのかと思ったんですが、そこらへんの中学生や近所のおじさんおばさんも通院していて、けっこうアットホームな感じですよ。リハビリのシステムが確立されていて自分のペースでやれますし、スタッフの先生がみんな親切なので通院しやすかったです。私からはオススメです。
トレーニングを続けようそれでは最後に簡単なトレーニングをご紹介しておきます。せっかくいい病院を見つけて野球肩が治っても、そのあと何もしなければインナーマッスルが弱ってまた肩を痛めてしまいます。なので、野球をする限りはトレーニングを続けることが大切です。今回紹介するのは簡単なチューブトレーニングなので、毎日歯を磨くのと同じ感覚で続けられると思いますよ。ストレッチも含めて10分もかかりませんので、ケガの予防という意味でもお試し下さいませ。また、練習前のアップや練習後のダウンに取り入れるといいかと思いますので、興味のある方はやってみてくださいね。 ●インナーマッスルトレーニング それではチューブトレーニングを簡単に説明します。3種類ありますが、それぞれ15回×3セットずつ行います。そしてチューブトレーニングが終わったら、肩まわりのストレッチをして下さい。インナーマッスルを鍛える時は、その「動かす角度」が非常に重要で、正しい角度で動かさないと目的の筋肉を鍛えることは出来ません。でもここではけっこうええ加減に説明してますんで、正しい動作は必ず病院の先生やトレーナーに聞いて確認してから行ってくださいね。
●参考になる本 それでは最後になりますが、「肩」に関係する本をいくつか紹介しておきます。知識として知っておけばトレーニングをする時に役に立つこともありますよ。でも投球障害のある人は本を読んで治そうとせず、まずは病院に行って下さいね。 ●「ショルダーズ・バイブル」手塚 一志・著(ベースボールマガジン社) ●「野球肩・野球ひじを治す本」川島堅・著(マキノ出版 ) ●「野球のパワーアップトレーニング練習法」立花 龍司 ・著(西東社) ● 雑誌「ヒットエンドラン」2006年1〜7月号 特集“真下投げ”(ベースボールマガジン社)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
私が肩を痛めてから8年…。今思えば、もっと早く専門の病院に行って治しておけば、私の過去の8年間はもっと楽しくて有意義な野球生活を送れたのかもしれませんね。選手として一番いい時期を棒に振ってしまったようにも思います。ただ、30歳になってから自己の遠投記録を更新しようかという勢いなので、むしろ今から鍛えればもっと上をめざせるという希望も出てきました。だから今、肩が痛くてあきらめている人も、希望を捨てずに治療してほしいと思います。「本当に野球が好きなら、練習と同じくらい治療も頑張れる」そういう固い決意で故障を克服してください。最後になりましたが、お世話になった病院の先生方、そして冬季に個人練習に付き合ってくれたメンバーNとTに心から感謝します。 ▼参考文献:「コーチング・クリニック2006年8月号」ベースボールマガジン社編集 他 |
| No.73 バントシフト(2006.8.28) ▲上に戻る | ||||||||
|
今回は「バントシフト」について考えてみようかと思います。と、いっても女子野球ではそんなに極端なバントシフトはあまり見ないんですよね。だから別に詳しく掘り下げなくてもいいんですが、次のネタまでのつなぎということで、「ランナー1塁でのバントの攻防」について考えたいと思います。っちゅうことで、守備ではバントをされるたびに捕球を譲り合い、相手に内野安打を献上するアッフェ内野陣の“主犯格”管理人とともに、バント処理の大切さについて思い知らされましょう。
バントシフトとは●バントシフトって何? まず「バントシフトて何じゃ?」ということですが、相手が送りバントをしてくると予想される時、あらかじめバントを処理しやすい守備隊形をとって相手の攻撃を封じる作戦です。よくみかけるのはランナー1塁でのバントシフトですね。投球開始と同時にサード・ファーストが前に突っ込んでバントを処理し、2塁でアウトにしてランナーをスコアリングポジションに進めないという守備です。他にもランナー2塁や1・2塁でのバントシフトもありますが、今回はとりあえずランナー1塁でのバントシフトを紹介します。 ●ランナー1塁でのバントシフト ランナー1塁でバントシフトをとる目的は「1塁ランナーを2塁へ進ませない」ということです。つまり内野手は2塁でアウトを取る守備隊形をとらなければなりません。それでは具体的にその動きをみていきましょう。だいたい以下のような感じだと思います。 ■ランナー1塁でのバントシフト(番号は各野手の守備位置を示しています)
女子野球とバントシフト●極端なバントシフトは少ない? ところで管理人、大きな大会のたびにできるだけたくさん試合を見るためバックネット裏でストーキングを繰り返しているんですが、女子野球ではプロ野球や高校野球で見るような極端なバントシフトはほとんどみかけないんです。というのも、「純粋な送りバント」が少ないからかもしれません。私が見た限りですが、女子野球ではランナー1塁で送りバントをするとき「犠牲バント」ではなく「セーフティバント」を使うことが多いんですね。ランナーを送るときにバッターが最初から送りバントの構えをすることはほとんどなく、バントなのかヒッティングなのかわからないことが多いので、極端なバントシフトはとりずらいのだと思われます。またバントシフトをとっても、最初からバントの構えをする時は盗塁援護のエバースの時が多いですし、バスターやヒットエンドランもかなり多いので、女子野球特有の攻撃パターンを考えると極端なバントシフトをとることは少ないのかもしれません。ただ、ここは確実にバントしてくるとわかる場面では、どんどんバントシフトをかけて相手にプレッシャーを与えるだけでも効果はあるんじゃないかな〜と思うので、また興味のある方はお試し下さいませ。 ●バントかヒッティングかわからない時のバント処理 さて、女子野球に限らずランナー1塁でバントかヒッティングかわからないことが多いと思いますが、そのときは「バッターがバントの構えをしてから内野手が前にダッシュする」という一般的なバント処理の形になると思います。野手の動きは上で説明したのとだいたい同じですが、ファースト、サード、ピッチャーはバッターがバントの構えをしてから前にダッシュします。
バントシフトをかいくぐるそれでは最後にバントシフトに対抗するワザをご紹介しましょう。ワザといっても、前に突っ込んでくる守備にはバスターやプッシュバントなどが有効な手段だと思います。このへんはみなさんよくご存じだと思いますし、書くのがめんどくさいから省略しちゃいますね。今回紹介するのは、少年ソフトボールチームの監督をしていた叔父に教えてもらった必殺技です。当時ソフトボール部だった私は送りバントをしても決められないことがあったので叔父に相談したところ、機械的に送りバントをするんじゃなくて打席の中でもっと工夫してやってみたらとアドバイスを受けました。以下紹介するのがその方法ですが、お気に召したらお試し下さいませ。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ここ数回は連発更新で、PICK UP!というよりピックアップアップという状態ですが、なんとか今回もうまくごまかせました。まぁ、でもたぶん「ランナー1塁」のバントシフトより「ランナー2塁や1・2塁」でのバントシフトの方が興味のあるところだと思いますが、それはまた冬にでも取り上げたいと思います。そして次回は「投球障害」についてです。半年間通院し長年の肩痛から見事カムバックした管理人の体験記を、別に知りたくもないでしょうが大公開しちゃいます。投球障害はちゃんと治していきましょうってだけの話ですが、なんとかうまくまとめあげたいです。 ▼参考文献:「野球指導の手引き」スポーツ科学トレーニングセンター編集 他 |
| No.72 連戦を乗り切る「クールダウン」(2006.8.9) ▲上に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
さて、前回に引き続き「連戦を乗り切るための疲労回復法」について考えてみましょう。今回は「クールダウン」について取り上げます。クールダウンは疲れを翌日に残さないためのものですが、今回はアイシング等を含めたコンディショニングということで考えてみたいと思います。まれにみる連発更新でアタクシすでに疲労困憊ですが、この全国大会では自らのカラダでこの疲労回復法をこころみて、若手芸人なみにカラダを張ってきたいと思います。
クールダウンをしよう●なんでクールダウンをするの? まず「クールダウン(クーリングダウン)て何じゃい?」ということですが、ひとことで言うと『整理運動』です。ウォーミングアップ(準備運動)の反対に当たるものですね。「じゃあ、なぜこのクールダウンをするの?」ってことですが、まぁ主には「疲労回復」が目的です。
●野球選手は何をすればいいの? では、野球選手はどんなクールダウンがいいのかというと、だいたい以下のような感じです。クールダウンというと、簡単な整理体操やストレッチを思い浮かべるかもしれませんが、今回はアイシングや軽運動なども含めた広い意味でのクールダウンについて取り上げていきます。 アイシング ⇒ 軽運動(ジョギング 、チューブなど)⇒ ストレッチ まずここでのクールダウンは試合や練習の直後に肩などをアイシングして炎症を広げないようにします。次に軽くジョギングや軽運動で血行を良くし、ストレッチで柔軟性を回復させます。これがだいたい一般的な形だと思いますが、ただ、クールダウンは他にもいろんな方法があると思うので、自分にあった方法を見つけていただくのが一番かと思います。今回ご紹介するのもあくまで参考程度に読んでください。それでは次からは上記のクールダウンについて順を追って説明していきましょう。
連戦を乗り切るクールダウンさてここからは連戦を乗り切るためのクールダウンについて詳しくみていきたいと思います。試合の翌日は和式トイレが拷問のように思えるほどの筋肉痛で苦しんでいる管理人ですが、リハビリに通っている時に理学療法士の先生にアドバイスを受けてこのクールダウンを試してみたところ、疲労感や筋肉痛がかなり軽減されました。そんなわけでみなさんにちょっとオススメしたいクールダウンメニューを、流れに沿って説明していきます。 ●まずはアイシングを ▼なぜアイシングが必要なの? まず、なぜアイシングをするのかということですが、たとえばたくさん投げる動作をした後には、繰り返しておこなわれる投球動作によって関節内の腱や靱帯、その周辺の筋肉に微細な損傷を受けています。そしてその損傷によって炎症反応がおこるわけですが、損傷を受けた細胞は周囲の正常な細胞まで悪影響を及ぼし損傷の範囲を広げてしまいます。それを防ぐのがアイシングです。アイシングをすることで、細胞を一時的に冷凍保存状態にして損傷が広がることを防いでいるのです。 ▼試合後すぐにアイシングを そして大切なポイントは試合後(練習後)にすぐアイシングをするということです。炎症の範囲は時間を追うごとにどんどんひろがっていくので、試合などでは投げた直後にアイシングをして下さい。ゲームセットの整列が終わると同時にアイシングに入るくらいの気持ちでいた方がいいですよ。冷やす時間は10〜20分で、アイシングに使う氷は0℃の氷がいいです。溶けかけの氷か、あるいは水を混ぜた氷水状態のものが一番周りの熱をたくさん奪って冷却効果も高いそうですので、ぜひともお試し下さい。最近、試合後にちゃんとアイシングをしていないチームもけっこう見かけるんですが、投手に限らず肩に不安のある選手にはチームでアイシングを義務付けた方が私はいいと思いますので、みなさん一度考えてみてくださいね。
●軽運動(チューブトレーニング)で血行をよくしよう アイシングが終わったら、次はジョギングや軽いキャッチボール、チューブ・トレーニングに入ります。ジョギングや軽いキャッチボールでアイシングによって冷えた筋肉の温度を上げると、前述したリバウンド効果で血管が拡張し、血液循環がよくなります。そしてその効果で 疲労物質を取り除いたり、傷ついた筋肉組織を修復したりして回復力を高めるわけですね。
●ストレッチ それでは最後にストレッチについて取り上げます。練習や試合で酷使した筋肉は硬く縮こまっていて柔軟性が低下している場合も多いのですが、ストレッチはその筋肉を伸ばすことで血液循環をよくし、筋肉内に蓄積された疲労物質や老廃物を取り除いたり、傷ついた筋肉組織を修復する働きを促進します。まぁ、ストレッチに関してはみなさん取り組んでいることなので特に書くこともありませんが、ただ、忙しいからといって試合や練習後のケアを怠っていると、知らず知らずのうちに筋肉の疲労が蓄積され、筋肉中の収縮力が弱まったり、筋肉本来の弾力性が失われたりして、結果的に肩やひじを痛める原因にもなりますのできちんとやってくださいね。
連戦を乗り切る最強プログラム?それでは最後に連戦を乗り切るための栄養補給とクールダウンを合わせたモデル・プログラムを、実際の試合を設定して考えてみました。全国大会を想定したダブルヘッダーのパターンで組んでいます。みなさんも連戦を乗り切る独自のプログラムを組んでみてくださいね。 ■ダブルヘッダー[1試合目10:00〜、2試合目14:00〜]の場合
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
さて、今回と前回で「連戦を乗り切る疲労回復」について取り上げてきましたが、いかがだったでしょうか。実は7月の練習でこの栄養補給やクールダウンを試してみたんですが、私個人的にはかなり効果がありました。試合後の疲労感はまったくナシですし、翌日は必ずおこる筋肉痛もほとんどありませんでした。マジでここまで成果が出るとはビックリです。個人差はあると思うのですが、みなさんもぜひとも自分に合った疲労回復法を見つけ出してみてくださいね。で、関係ないんですが最近いろいろ調べていて思ったことは、スポーツ界でもどんどん新しい情報がでてきて既存の事実が更新されていくんだなということです。何が良くて何が悪いかなんてわかんないですね。私がここで書いていることも、あと何年かしたら古くさい情報になってるのかもしれませんなぁ…。 ▼参考文献:「スポーツ生理学」根本勇著(山海堂)、「スポーツ科学バイブル」高畑好秀監修(池田書店)、季刊PENTA33号、34号(株式会社ワールドスポーツネットワーク発行) 他 |
| No.71 連戦を乗り切る「栄養補給」(2006.7.29) ▲上に戻る |
|
さて、全国大会も近づきつつありますが、今回は連戦を乗り切るためのコンディショニングについて考えてみましょう。大きな大会になると連日の試合やダブルヘッダーは必須。でもいくら技術が優れていても、気力が充実していても、体がついてこなければベストパフォーマンスはできません。そうなると連戦を勝ち抜くキーポイントはやはり「コンディショニング」ということになるのではないでしょうか。ということで、試合が終わるたびに体がボロボロになる管理人とともに、疲労回復をテーマに考えてみましょう。ただ、今回調べているうちに定説が覆ったりしてて、よくわかんなくなっちゃいました。っちゅうことで、あくまで参考程度にお読み下さいませ。
疲労回復で連戦を乗り切ろう●なんで疲れるの? 全国大会など大きな大会ではダブルヘッダーが何日か続くこともありますが、その連戦を乗り切るキーポイントは「疲労回復」だと思います。疲れのメカニズムを知ることで、疲労を予防したり取り除いたりすることができるかもしれませんね。ところが、「運動による疲れの仕組み」については実はまだハッキリとはわかっていないそうですよ。今のところ「疲労物質の蓄積」「脳からの指令の阻害」「筋中のグリコーゲン不足」「筋繊維の破壊」などの説がありますが、ハッキリ「これだ!」と言えるものはまだないそうです。
●新説・乳酸は疲労物質ではない!
●疲労回復には「クールダウン」と「栄養補給」 「じゃあ、乳酸は疲労に関係ないからクールダウン(クーリングダウン)はしなくていいのか」というと、そういうわけでもありません。運動による老廃物は乳酸だけでなく、二酸化炭素やアンモニアといったものもあるそうです。とくにアンモニアは脳神経に働いて筋肉を硬直化させたり、神経系の機能を低下させて判断力・集中力・反応速度を鈍らせると考えられています。なのでやはり運動後にクールダウンをして血液循環を良くし老廃物を取り除いたり、筋肉の柔軟性を回復させることは必要なんじゃないかと思いますよ。また、クールダウンで行われる軽運動(ジョギング)などの有酸素運動は乳酸から新しいエネルギー生み出してくれるそうです。そういう意味でも運動後に何もしないより、クールダウンをした方が疲労回復につながるということですね。
連戦を乗り切る栄養補給それでは連戦を乗り切る栄養補給について考えてみたいと思います。毎年夏場の全国大会では、アタクシ昼も夜も全力を尽くすため、とんでもなく体力を消費してしまって最後の方はヨレヨレになってしまいます。せめて昼の部だけでも満足に動けるにはどうしたらよいかと思って、今回は試合の前後でのベストな栄養補給について調べてみました。
と、いうことで連戦にはガソリン満タンで臨みたいところですが、それにはいったいどうしたらいいでしょうか。実は、筋肉運動の主なエネルギーはグリコーゲンですが、これを試合前に体にため込んでおくことで長い時間運動することができます。この食事法をグリコーゲン・ローディングといいます。具体的には、大会の3日前くらいからうどんや白米、パスタ、パン、じゃがいも、バナナなどの糖質(炭水化物)を多く摂取し、体内にグリコーゲンをたくさん貯蔵しておきます。またこのとき、オレンジジュースなどを同時に摂取するといいそうです。これはみかんやりんご、レモンなどに含まれるクエン酸が炭水化物の分解を阻害するので、グリコーゲンを体内に多くためることができるからです。また、炭水化物の代謝に不可欠なビタミンB群(豆類、牛乳、レバー、にんじん、ほうれん草、ピーマン、めざしなど)を多めに摂ったり、脂質を控えたりということも必要です。ただ、野球ではマラソン選手ほどエネルギーを消費しないので1日前からグリコーゲン・ローディングをしてもいいそうですよ。でも大きな大会では数日間フルで動くことになるので、私は3日前からグリコーゲンを貯蓄しておこうと思います。いきなりうまくいくかどうかわかりませんが、興味のある方は全国大会前にお試し下さいませ。
●試合の当日は? 次に試合の当日の食事ですが、たくさん食べた直後は胃に体中の血液が集中して運動しづらくなるため、試合が始まる3時間前には食事を済ませておくことがベストです。この時の食事内容も糖質(炭水化物)の多いおにぎりやあんぱん、うどん、カステラ、果汁100%オレンジジュースなどがよいそうです。また試合直前や試合中の栄養補給についてですが、試合の1時間前ならバナナや市販のエネルギーゼリーやアミノゼリー(キムタクがCMでやってた10秒チャージのゼリーですな)がいいそうです。野球は試合の競技時間が長い方なので、試合中もエネルギーが不足することがあります。そのため試合中にはスポーツドリンク(水で半分に薄めたモノ)やエネルギーゼリーを摂取することで運動を持続することができます。
●運動直後の栄養補給が疲労回復のキーポイント それでは試合後の栄養補給について考えましょう。ここでは疲労回復が大きなポイントですが、前述したように筋中のグリコーゲンが枯渇して筋活動のレベルが低下することが筋疲労の1つの要因となっています。つまり、試合後に栄養補給をして筋中のグリコーゲンをたくさん作り出すことが疲労回復につながるのです。そのために必要な栄養は糖質、アミノ酸、あとは筋肉修復のためのタンパク質などです。糖質とタンパク質は3:1の割合で糖質を多めに摂って下さい。ここで重要なのは摂取するタイミング。試合後2時間もあいてから栄養補給をするより、試合後30分以内に栄養補給をした方がグリコーゲンがたくさん作り出されるそうです。なので、できるだけ試合直後に栄養補給をしてください。ただ、試合直後になかなか食事は出来ないと思うので、こういうときもやはり市販のゼリーや果汁100%のオレンジジュース、リンゴジュースなどでの栄養補給になると思います。
●ダブルヘッダーに備えよう それでは最後にダブルヘッダー時の栄養補給についてですが、次の試合までに3〜4時間ある場合は、ゼリーなどではなくおにぎりやパンなど糖質のものを多く摂り、クエン酸を含むオレンジジュースを一緒に飲むといいそうです。また試合までに1時間程度しかない場合は、それほど多くは食べられないと思うのでバナナ、エネルギーゼリーなどで補給するのがいいそうです。全国大会ではダブルヘッダーでの連戦が続きますが、これまた興味のある人はお試し下さいね。
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
と、いうことで今回は疲労回復と栄養補給について考えてみましたが、けっこう薄っぺらい知識で書いてるんでね、ちゃんとしたことはみなさんの周りにいるトレーナーや栄養士さんに確認して下さいね。で、今回の特集にあたっていろいろ調べてたんですが、ある記事を読んだ時にその著者の顔に見覚えがあったんですね。どこで見たのかな〜と思いながらプロフィールを見ると、なんと大学時代の同級生でした!某スポーツ科学センターの研究員になってたんですね。いや〜、そういえば昔から熱心に勉強してたもんなぁ。まさかこんなところで巡り会うとは思いませんでしたが、まぁ同窓会でのいいネタになりますね。それでは次回は疲労回復とクールダウンについて考えたいと思います。 ▼参考文献:「スポーツ生理学」根本勇著(山海堂)、「スポーツ科学バイブル」高畑好秀監修(池田書店)、季刊PENTA33号、34号(株式会社ワールドスポーツネットワーク発行) 他 |