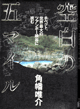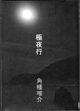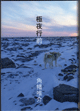|
「空白の五マイル−チベット、世界最大のツアンポー峡谷に挑む−」 ★★☆ |
|
|
2012年09月
|
チベットの奥地にある秘境、ツアンポー峡谷。 早大探検部が行った探検行のひとつを描いた高野秀行「幻獣ムベンベを追え」とは、同じ早大出身者の探検とはいえ、かなり趣を異にします。その理由は、本探検が単独行であること、それに尽きます。 1回目2002〜03年の探検では、ツアンポー渓谷の最深部に至り、滝、大洞窟の発見という成果を上げる。しかし、それだけでは納得ができなかったと6年後の2009年、勤めていた会社を辞めてまでして角幡さんは2回目の探検行に向かいます。 実際は大変なことばかりなのでしょうけれど、角幡さんはそれをあっさり、淡々と記しています。冒険・探検である以上、そんなことはそもそも当たり前のことだという風に。 第一部 伝説と現実の間:1924年/憧憬の地/若きカヌーイストの死/「門」/レース/シャングリ・ラ ※岩波文庫にF・キングドン=ウォード著「ツアンポー峡谷の謎」あり。 |