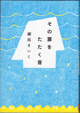| 「その扉をたたく音」 ★★ | |
|
|
このところ好作品を連発してきた瀬尾さん、今度は一体どんなストーリィだろうと思っていたのですが、中心となる舞台は老人ホーム。 主人公の宮路は、29歳にして無職。学生時代からずっと音楽活動を続けてきたと言えば格好良いのですが、大して才能もなく、要は親からの仕送りに頼ってぶらぶら過ごしてきてしまった、というのが正直なところ。 その宮路、老人ホームの余興に呼ばれた時、自分の後に若い介護職員の渡部が吹いたサックスに驚愕、「天才」「神さま」だと興奮し、その演奏を再度聞くために毎週、その老人ホームに通うようになります。 その宮路に目を付けたのが、入居者の水木静江。お互いに「ぼんくら」「ばあさん」と遠慮ないやり取りをしつつ、静江ら入居老人たちに買物を頼まれては生真面目に届けるということを繰り返しながら、宮路と渡部、入居老人たちの交流が繰り広げられていきます。 スタートを切りそこない、ずっと足踏みし続けだった宮路が静江たちに背中をどやされてやっとスタート地点に立とうとする。一方、人生の最後になってもまだ新しいスタートを切ることはできるのだと、宮路との交流で気づかされた老人たちという、新たな&再びスタートするまでのストーリィ。 宮路と老人たちとのやり取りが年代を超えた漫才のようで楽しいのですが、最も魅力を感じるのは、瀬尾さんの優しい掌の中で皆が転がされているようなストーリィであるところ。 たとえどんなに遅くなろうと、新たなスタートを切るというのは嬉しいものです。 |