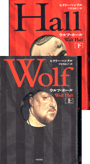|
「ウルフ・ホール」 ★☆ |
|
|
2011年07月
|
ブッカー賞ならびに全米批評家協会賞を受賞した話題の歴史大作とのこと。 離婚禁止のカトリックの教えに反して王妃キャサリン・オブ・アラゴンと離婚、愛人アン・ブーリンとの再婚を果たし、その過程で英国教会を設立して自ら首長となったヘンリー八世の時代。下賤の生まれながらその秀でた才覚で国王の厚い信頼を得て秘書長官にまで上り詰めた政治家=トマス・クロムウェルを描いた歴史大長編です。 ヘンリー八世、アン・ブーリン、クロムウェルの登場する物語とはこれまでも無縁だった訳ではなく、戯曲にはシェイクスピア「ヘンリー八世」がありますし、映画では「ブーリン家の姉妹」がありました。その2作はともかくとして、ヘンリー八世の時代については元々興味津々です。 しかし、正直言って読むのは辛かった。とにかく長い、その割に事態が進まない、そのうえクロムウェルの姿勢はどちらかというと受け身かつ冷静な観察者風で積極的な行動というのが余りないのです。 その上、登場人物がやたら多いうえに似た名前が多く(例えばメアリ:王女メアリ、アン・ブーリンの姉、国王の妹)て混乱しがち。また多く用いられる「彼」という表記が誰のことを差しているのか判りにくくて参りました。 王妃キャサリンとの離婚問題を処理できるまで7年もかかり、その間ずっとアン・ブーリンは愛人関係だったというのですからその執念は恐れ入りますが、その後の運命はあっという間というのもまた納得いくような気がします。 気まぐれな君主の怒りを買わず、信頼を勝ち得るには慎重にも慎重な行動が必要なもの。そのためトマス・クロムウェルを描くに綿密で長大な物語となり、英国等では高く評価されたということに納得できるところもありますが、英米人なら飽きずにいられても日本人としては辟易してしまうのはやむを得ないところではないかと思う次第。 それにしても本書で描かれたアン・ブーリン、欲深くて執拗、その我の強さ、尽きることない執念には全く恐れ入ります。 アン・ブーリンという女性、結局は後のエリザベス女王を生み出すためだけの存在だったのかと思うばかりです。 なお、題名の「ウルフ・ホール」とは、後にヘンリー八世の三番目の妻となったジェーン・シーモアの実家の呼び名だということですが、作者のマンテルはヘンリー八世の宮廷全体を象徴する言葉として使ったとのこと。訳者のあとがきによると、近親相姦と弱肉強食がはこびる場所といった意味だろう、とのこと。 第1部.海峡の向こう(1500年)/父たること/オースティン・フライアーズ 第2部.訪問/ブリテンの神秘の歴史/いちかばちか 第3部.いかさま賭博/最愛なるクロムウェル/埋葬に関する死者の不満 第4部.顔を作れ/「ああ、愛のためにわたしはどうすればよいのでしょう?」/早朝ミサ 第5部.アンナ・レジナ/悪魔の睡/画家の眼 第6部.最高位/キリスト教世界の地図/ウルフ・ホールへ(1535年7月) |