注 以下の内容は、思い付き・思い込みや、想像の産物です。
内容についての責任は負いません。引用不可
- 2012. 1.22 車の燃費表示について
2009. 7.12 車の内・外気切替操作について (オートエアコンのおせっかいを解消)
2005. 4.11 中越地震震源から約20kmには天然ガス田
2003. 8. 1 「電子レンジでチンする」を言い始めたのは! TVリモコンの呼名は・・・
2003. 1.19 風邪をひいたかなと思ったら、使い捨てカイロを首の近くに!
2002.11.10 ADSLモデム電源アダプタと無線LAN電源アダプタの干渉
2001. 2.28 車のアース(接地配線)について
2000.11.18 ACアダプターの融通性、安全性について
2000. 8.20 キムチにイモムシが入っていてもおこるな、農薬の方が怖い
2000. 7.23 七の読み方について、ら抜き言葉について
2000. 6. 9 量販店の駐車場で(岩綿、一方通行)
2000. 3. 9 正反対の目的が同じ行動に結びつく?(危険表示、他)
2000. 2.23 かぜとの攻防
2000. 2. 1 田んぼのあぜ道でへび! (祖先の記憶?)
2000. 1.28 建物の排煙設備について(役に立ったことはあるか?)
2000. 1.27 車両事故と火災(燃料ポンプ圧力)
2000. 1.25 ノートパソコンの機械的なこと
2000. 1.11 電磁波について(電磁波と磁界を混同せず)
1999.12.23 落雷の被害について(とほほ・・)
1999.12.21 都市ガス原料の輸送について(ガスは良い面ばかり?)
1999.12.15 ダムと地震について(さらに・・)
- 車の燃費表示について 2012.1.22
ハイブリッド車の40km/Lとかの数字を良く耳にしますが、燃費の値が高いほど高燃費?低燃費?
燃費とは燃料消費を示す指標であって、燃料消費ではない。
中途半端な略語のため、言葉と、その意味が反転している。
平均燃費の計算が変。
ある車で、スイスイ走れる 500km離れたA地点へ1往復したら 20km/Lでした。
また、峠越えで渋滞のある 500km離れたB地点へ1往復すると 5km/Lでした。
この車の2回走行の平均燃費はいくらでしょうか。
走行距離が同じなので、20km/Lと、5km/を平均して (20+5)÷2=12.5km/L になります。
↑これは実は間違いです。正解は、
燃料の消費量はそれぞれ、50Lと200Lになりますので、1L当たりの走行距離=平均燃費は、
(1000+1000)÷(50+200)=8.0km/L です。
今の逆数を使う燃費表示方法だと、こんな単純な平均燃費の計算でも勘違いが起こります。
国の提唱する新燃費基準による燃費改善率も、100%の改善が1/2の燃料消費になるだけなのです。
日本の燃費表示は ○○km/Lですが、ヨーロッパでの燃費表示は○○L/100kmだと聞きます。
私は、○○L/1000kmが月間の走行距離との近似から実感の伴う数字として適切かと思います。
しかし、新たな表示を作るのも混乱のもとになりますので、
ヨーロッパに合わせて、○○L/100kmを採用すべきだと考えます。
- 不整脈との付き合い方について 2009.12.31
私のことですが、年齢を重ね、ある頃から時々不整脈が出るようになりました。
鼓動が一気に2倍位になったり、時々脈が飛ぶような症状です。
心臓のあたりの苦しさを伴うこともあり、医院で診察を受けたところ
肩こりが原因の一つかもしれないとのことでした。
2週間くらい後、1日中、心電計を胸に貼り付けデータを確認してもらいましたが、
特に危険なタイプの不整脈ではないことがわかりました。
特に薬の処方もなく、その後の経過確認となったわけですが、
心電計の連続測定の時、すでに私なりにある方法を試していました。
それは、市販のサプリメント「カルシウム・マグネシウム」を飲むことです
主成分は「ドロマイト」、石灰石に似た堆積岩 CaMg(CO3)2で、商品は健康食品に
分類されていますが、元々は食べ物ではありません。
私の場合、なぜか症状を抑えることができました。
プラシーボ(偽薬)効果を、否定できませんが。
その後、普段は、サプリメントの袋に記載の用量の1/2程度を摂っています。
このサプリメントは、他の不整脈を抱える方々にとって、有効か、効果がないか
はたまた逆効果なのかは、わかりません。
人それぞれ、ひとくくりにされる病名でも原因や症状は様々でしょう。
一人だけの素人療法として温存していたのですが、最近、似た症状の人に
勧めてみたところ、発症がなくなったとのことでした。
もし試される場合は、健康食品として自己責任で確認してください。
カルシウムなどの電解質が、心筋の動きに関係していることはわかりましたが、
体内の過不足がどう関与しているかは、私にはわかりません。
少し知識のある人に聞いても、「一時的にカルシウムが不足しても、骨から供給される」
とのことが常識のようでした。
私の不整脈の原因につながったかもしれないと思うのは、ペットボトル飲料の過剰摂取。
特に夏場のペットボトル入りの茶やスポーツドリンクの多飲があります。
汗をかく、→ 水分を多くとる、→ 汗や尿で電解質が失われる。
しかし、安売りでよく買うアクエリアスには、ナトリウム、カリウムはともかく
カルシウムの含有量は表示されていない。
当地の水道水にはカルシウム等がたっぷり含まれているのに。
経験的には、野菜ジュースなども多飲すると良くないように感じています。
- 車の内・外気切替操作について (オートエアコンのおせっかいを解消)
2009.7.12
- ダイハツ ミラ(オートエアコン付き)を購入後にわかったことですが、エンジンを切って再度かけるたびに、
それまでの設定にかかわらず送風が内気循環になることに気が付きました。
送風をマニュアル設定にしていても、エアコンコンプレッサーをOFFにして送風だけにしていても同じです。
設定温度を外気温度に近づけると外気導入に切り替わることは確認できましたが、通常の設定温度では
常に内気循環になります。設定温度と室温の差が少なくなれば外気導入になる設定とはおもいますが、
基本的にチョイ乗りばかりなので確認できていません。
取扱説明書を見ると、「通常は外気導入で使ってください」と記載されています。
エアコンの効きと燃費への影響を重視しているのでしょうが、取扱説明書と矛盾した動作になります。
(外気導入と比較した)内気循環の長所、短所
長所
1. 冷暖房の熱負荷が少ない。(エコランでは推奨される)
2. 外気の汚れ・臭いの影響を受けない。
短所
1. 窓が曇りやすい。 曇りを取るのにはエアコンを使う必要がある。
2. 外気温の低い時の外気冷房ができない。
3. 気密性の高い車の場合、徐々に二酸化炭素濃度が上がり、酸素濃度が低下する。
そのためか、頭が痛くなることがある。
4. 室内吸込み口が有る足元の土やホコリは衛生的とは言えない。
5. 複数乗車時には、呼気の臭いがこもって気になる。
内気循環には長所もありますが、私の運転環境では短所の方が多いため、常時は外気導入で使いたい
のです。なので、エンジンをかけるたびに内・外気切替スイッチを操作しており、車に乗るたびにイライラ
させられていました。
そこで、ダメ元で購入時の営業担当に相談したところ、メーカー側に対応を確認したうえでサービス担当が
設定の変更をしてくれました。
その結果「常時は外気導入、ボタンを押すと外気導入・内気循環の切替」となりました。
当たり前と言えば当たり前ですが、これが一番良いです。
営業担当に感謝!
天然ガス田、巨大ダムと地震について 2009. 1. 4
| 4年前に書いた下記の「中越地震震源から約20kmには天然ガス田
」及び、10年前に書いた「ダムと地震について 」の関連です。
2007年の中越沖地震はこの場所(37° 33′ 24″ N, 138° 36′ 30″ E)が震源でしたが、そう遠くないところにガス田が有ります。 アジアのガス田開発に関して、石油天然ガス・金属鉱物資源機構資料 で概略が示されています。
2008年の アジアの巨大プロジェクトには必ずと言っていいほど、日本の商社や企業の参画があり、場合によっては日本国の資金的な援助があります。もしこれらの巨大プロジェクトが災害に何らかの関係があるとしたら・・・。
|
- 中越地震震源から約20kmには天然ガス田
2005.4.11
| 以前より気になっていたことの関連ですが、
積極的な採掘を行っているガス田が近くにあると知ると、やはり気になります。 南長岡ガス田は1984年より生産を開始しているガス田ですが、近年にはMHF(Massive Hydraulic Fracturing:大規模水圧破砕)技術を使って天然ガスを採取しています。 場所は http://www.teikokuoil.co.jp/work/n_gas/pro_01.html に示されています。 具体的な工法の説明には、(抜粋)
1997-2001年にかけて実施した石油公団との共同研究を通じ、地下4,500m付近に分布する低浸透性の緑色凝灰岩層に対し水圧破砕法を改良して適用した結果、生産性を8倍に増加することに成功しました。
東京大学地震研の震源域地殻構造推定断面図を見てみると、余震分布は4,000m位の深さより始まります。
ガス資源確保のためとはいえ、地下4,500mで注水にて岩を破砕し人為的な刺激を与える工法に対して、疑問を感じています。
|
上記のうち、帝国石油ページへのリンクは切れています。参考までに新しいページの代表的なものを示します。
http://www.inpex.co.jp/business/japan/index.html
- 「電子レンジでチンする」を最初に言い始めたのは! TVリモコンの呼名は・・・
2003. 8. 1
| このことについては、「それは私だ」と言う人が五万と存在することを想像する。たぶん、同時多発的に生じた言い回しと思う。
1975年頃 父のコップ酒の燗を頼まれることが多かった私。例の「チーーン」という音で燗が終わる。ターンテーブル式になっていたとはいえ、上だけ熱いのは仕方が無かった。 当時、家では常に「チンする」を使っていたし、職場での雑談で「レンジでチン」を使っても意味が通じたので、どこのメーカーの製品も「チーン」なんだ、と思った。 (最近のものは「チーン」ではないですね) テレビのリモコンについて、我家では1984年頃から「チャンネル権」と呼んでいる。
ほかにも、変造語や逆さま言葉を常用していたため、うちの子供はよそで大恥をかいたことが何度も有るそうな。
|
風邪をひいたかなと思ったら、使い捨てカイロを首の近くに!
注:素人療法につき、自己責任で。 2003.1.19
| 以前にも、かぜとの攻防 を書きましたが、組合わせることにより更に効果的と思う方法がありました。
それは、貼るカイロを挟みこんだタオルを首に巻き付けることです。 貼るカイロでなくても良いのですが、比較的小さめの使い捨てカイロ等をタオルなどで包み、首の後ろにあてがいます。 熱すぎると少し苦しいのと、寝入ってしまうと低温やけどの恐れがあるのでタオル等の厚みは様子を見ながら調整します。脳は熱を嫌うようで頭に近いところを加熱するのは不適切かもしれません。ですからなるべく肩に近いほうを暖めます。 私と私の家族の例では、ひきはじめと思ったとき、この方法+加熱したにんにくのひとかけらを食べて、一晩十分に睡眠をとると、翌朝には劇的な改善がありました。 インフルエンザウイルスは、体温が38度C以上になると活動を弱めるようです。風邪(インフルエンザ含む)をひいたかなと思った時に、インフルエンザウイルス等の活躍の場となっている「首」を重点的に暖めることが効果的だったようです。 もちろん上記の方法は、あくまで効果があったと思うだけの「素人療法」ですから、結果に責任は持てません。早めに医師の診察を受けることをお勧めします。
|
ADSLモデム電源アダプタと無線LAN電源アダプタの干渉(速度低下) 2002.11.10
| 先日、使用している無線LAN(メルコ製)の電源アダプタのリコールがあった。メーカーに連絡をすると電源アダプタの新品を送って来たので早速交換したが、ADSLの速度が通常の1/3程度に低下した。
いろいろ調べているうちに、ADSLモデムの電源アダプタと無線LANの電源アダプタの位置関係で速度が大幅に変動する事を見つけた。下の写真の位置関係でもかなり干渉する。
上がADSL用、下が無線LAN用で、無線LAN用はこれまでADSL用と同様の大きく重いタイプだったが、リコール対策品は小型に変わっている。
古いセラミックコンデンサを見つけ、ADSLモデムの電源ソケット部分にバイパスコンデンサとして付けてみた。結果はおおむね良好で、接近させた場合の著しい速度低下は改善したが完全には解消しない。
無線LANのアダプタをアルミ箔で包んでも干渉状態における波形の振幅変化はほとんどなく、磁束が漏れている模様。磁気的なシールドを行うなど、EMI/EMC/VCCI に対する対策が不十分とおもわれる。
|
パンクか、パンクでないか 2002. 7. 1
| 6月29日、車の右前輪にタッピングビスが真直ぐに刺さっていることに気が付きました。
そのまま台所洗剤をかけて見ても空気漏れは無いようでした。しかし、ネジを回して抜きかけると小さな気泡が出てきました。 タイヤを買ったカーショップで見てもらうと、貫通していないので大丈夫とのこと。でも、実際に気泡を確認しているのでタイヤをリムから外してもらって確認したが、確かに貫通部分が見当たらず、穴に先の細い棒を突っ込んでも貫通しない。念のため内側からゴムのパッチを当ててもらった。
洗剤をかけて15分位後の状況です。小さな、カニの泡のような泡が少しずつ湧き立っています。タイヤの山は5〜6mm程度と思います。
1. もし、もう一方のタイヤに比べてエアの減りがあきらかに早い場合。
2. エアの減りが他のタイヤと比べあまり差が無い場合。
エアと書きましたが、窒素充填してもらっています。(純度の高い工業用ボンベより)
観察1日目、特に圧力の差は無し。走行後なので左右とも2.6kg/平方センチ。指定空気圧に下げたいけれど、窒素充填に行くのが面倒なので高めのまま管理。
できるだけ正確な圧力を知りたくて、カー用品店にあったデジタル式のゲージを買い、以前に使っていたゲージを含めて指示値を比較してみると、同じ圧力を測っているにかかわらず0.2kg/平方センチ位の差がありました。あまり差が大きいので、やむを得ず中間的な指示値を示す現行のゲージを継続して使うことにしました。 |
水平対向エンジンの不思議 2001. 11. 3
| 先日、インプレッサの排気側のマニホールドを交換しました。県内のショップA社に依頼しました。
DIYとするつもりでしたが、関係者の間で有名なS社の物での交換は、プロでも1日仕事と聞いて躊躇しました。今回取付けた写真のA社の物は、DIYも比較的容易なようです。(残念)  AQUAのページより AQUAのページより
交換後の状態としては、2気筒エンジンのバイクが4気筒エンジンになったようで、きわめてスムーズかつ、普通になりました。同じスバルでいえば、レガシーの静かさに近づいたと言うところでしょうか。 ドロドロ、バタバタといった、スバルらしさがほとんど消えたのですが、走行上のデメリットは感じられません。 写真の上部右端が、ターボへつながる部分ですが、各排気管を出来るだけ等長にして集合させています。(完全な等長ではないようです) 排気を合流させる場合には、点火(爆発)順の離れたもの同士を組み合わせるか、または同時に(等長で)集合させると干渉が少なく、状況により吸い出すような効果があるようです。 スバルの水平対向エンジンの点火順序は、1−3−2−4で、右-右-左-左となっています。
隣同士をすぐに合流させると、720度(2回転)において180度の間隔で出る排気を合流させるため、排気干渉を生じます。これがスバルの音の正体で、ほめられたものではないようです。有名なS社のマニホールドは、工賃を入れると25万円位?もかかりますが、それでも交換する人がかなりいるようです。
|
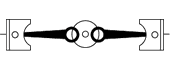 スバルの広告ページより
スバルの広告ページより

