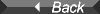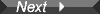日曜日、欲しいCDがあったので出掛けようとしたら、同じように出掛ける準備をしいたが居た。
なので、当然一緒に出掛ける事にする。
一人で出掛けたらナンパされるって、分かっているのに何で前もってオレに話してくれないのだろう。
まぁ、今回はちゃんと一緒に出掛ける事になったんだから、問題ないんだけどね。
「もー帰っちゃうんですか?」
用事も終わって帰ろうとした所で、突然抱き付いて来た存在にうんざりとしてしまう。
折角と二人でデートを楽しんでいたのに
その腕を振り切って帰ろうとしたオレに、抱き付いて来た人物が不満そうに声を出す。
「当たり前だろう、オレもも、用事終わったんだからな」
「あっ!さんもご一緒だったんですね」
不満の言葉に、当然のように返せば今更のように隣に居たに気付いて声を掛ける。
ハルに声を掛けられて、が苦笑を零した。
「こんにちは、ハルちゃん。綱吉、ハルちゃんに付き合って上げなよ。俺は先に一人で帰るから」
「一人でなんて帰せる訳ないでしょ。前にここでしつこい奴にナンパされたの忘れた訳?!」
勿論声を掛けられたが相手を無視する事などなく、ハルに挨拶してからオレに言ったその言葉に呆れたように返してしまう。
オレが何でと一緒に来てるか、考えて欲しいんだけど
絶対には、分かってないんだよね。
「さん、それじゃ一人は危険です!では、二人でハルの買い物に付き合ってください!」
「俺は別にいいんだけど……」
「なんで、そんな面倒な事……」
オレが呆れるように言ったその言葉に、ハルも状況を理解したのだろう、当然のようにを誘う。
それは、オレにとっては厄介な内容。
ハルもが一緒に行くといえば、オレが断れないのを分かっていて、を誘ったのだろう。
予想通り、はハルに同意して心配そうにチラリとオレを見てくる。
だけど、素直に頷くなんてオレには出来るはずもなく、そっけなく返せばが苦笑した。
「そう言わずに、付き合ってあげようよ。女の子一人だと色々危ないからね」
そうすれば、が何とかして一緒に行くように話をする事なんて分かりきっている。
オレがに誘われて、断る事なんて出来ないんだから……
「行くんだろう、さっさと終わらせて帰るよ」
それに小さくため息をついて、先に歩き出す。
これは、ハルの為じゃなく、君の為だけに動いているんだって、きっと知らないんだろう。
ハルは気付いてるんだろうけどね。
少し離れた場所で、ハルとが話しているのが見える。
流石に何を話しているのかまでは分からないけど、がオレ以外の隣に居る事が許せなくて邪魔をするように声を掛けた。
「ハル、目的の場所は何処だよ!」
不機嫌な声になるのは、仕方ないだろう。
オレが声を掛ければ、二人の視線が自分へと向けられる。
「この近くにあるケーキ屋さんです!」
そして、にっこりと嬉しそうな笑顔でハルがオレの質問に返してきた。
「ケーキ屋って事は、ケーキ買うのか?」
「そーですよ。今日は月に一度ハルが定めたハル感謝デーですから」
言われた内容があまりにも意外がったので、思わず聞き返したオレにハルがニコニコと嬉しそうに笑いながら説明してくる。
いや、感謝デーとか言われても、訳分かんないぞ。
「へぇ、自分へのご褒美か、そう言うのいいね」
言われた言葉に複雑な表情をしてしまったオレと違って、が感心したように呟く声が聞こえてくる。
ああ、そう言われてちょっと納得した。
自分へのご褒美の日ねぇ……同意は出来ないんだけど
「そうですよね!いいですよね!!」
感心したように呟いたに、ハルが嬉しそうに返す。
勢い良くに迫っての同意に、多分迫力に負けたのだろうが力無く頷いた。
が頷いた事で、更に上機嫌になったハルが目的のケーキ屋さんへと入っていく。
「大丈夫、?」
「うん、ちょっと迫力に負けちゃったけど、大丈夫……ついでだから、お土産にケーキ買って行こうか」
「そうだね。母さんやチビ達が喜ぶだろうね」
それを見送ってから、ため息をついたに声を掛ければ、苦笑しながらも返事を返してくる。
更についでとばかりに言われた内容に、思わず笑ってしまった。
本当には、そう言う所は女の子みたいに気が回るよね。
勿論、口に出しては言わないけど
オレが返事をした事で、が嬉しそうに笑顔を見せてくれる。
「ツナさんは生クリーム大丈夫ですか?」
ニコニコと機嫌の良さそうなを見ていて思い出す。
そう言えば、も甘いもの大好きだったっけ
そんな事を考えながら、二人並んで店の中へと入れば、ハルが行き成り声を掛けてきた。
「ツナは、あんまり甘いもの好きじゃないんだ。チーズケーキは食べるけどね」
「そうなんですか?それじゃ、ツナさんはレアチーズケーキにしましょう!さんは、どうしますか?」
「うーん、どうしよう」
「ツナくん?」
ハルの質問には、オレの変わりにが答えてくれる。
の言葉に、オレのケーキが勝手に決められて今度は二人並んでショーウィンドウを見始めた。
それを一歩後ろから見ていたオレは、誰かに名前を呼ばれて声のするほうへと視線を向ける。
そこに居たのは、笹川京子。
「こんにちは」
「あ…あの!こっ、これは、月に一度!」
声を掛けられたので、挨拶をすれば突然訳の分からないことを言われてしまった。
言われた言葉の意味が分からず、疑問符が浮ぶ。
「第3日曜日は、ケーキ好きなだけ食べるって決めてて、毎日ケーキ3個も食べてるわけじゃないから……!!」
「……そ、そうなんだ…」
そんなオレに気付かず、笹川京子が更に説明してきた内容に、ただ複雑な表情で返事を返す事しか出来ない。
誰も、そんな事聞いてないんだけど
「ハルと同じですー!」
それ以上、どう反応を返せば良いのか分からずに困っていれば、ハルが勢い良く笹川京子との間に割り込んできた。
「ハルも第3日曜は、“ハル感謝デー”と言って自分へのご褒美にケーキをいっぱい買うんです!」
「わーっ、いっしょだ!」
更に、訳の分からない内容を再度口に出せば、笹川京子が嬉しそうに返事を返す。
に、似た者同士。
ああ、確かに、この二人は訳が分からない所が、似ているかもしれない。
「えっと、確かに、ここのケーキは美味しいけど……流石に、俺も話しについていけない」
「が、それなら、オレはもっとついていけないんだけど……」
目の前では、女子二人が嬉しそうにケーキの話をしている。
それを遠巻きに見ていたオレに、が声を掛けてきた内容に思わずため息をついて返す。
が話について行けないのに、オレが付いていける訳ない。
「立ち話もなんだから、うちにきてゆっくり話せ」
ため息をついて彼女達の話が終わるのを待つかとうんざりとしていれば、ここに居るはずの無い嫌な声が聞こえてきた。
「リボーン!!」
声のした方へと視線を向ければ、予想通りの人物が何故かお茶を点てている。
驚きに、思わず名前を読んだオレは完全無視。
「茶ぐらいだすぞ」
「なんで、和茶なんだよ!!!」
そして更に続けられた内容に、思わず突っ込みを入れてしまった。
「リボーンちゃん」
「久しぶりーっ」
「ちゃおっス、さー行くぞ」
だけど女子二人はそんなこと気にした様子はなく、そこに居るリボーンに普通に挨拶をしている。
更にリボーンは、もう決定事項だというように二人を促すように立ち上がって店から出て行った。
「……と、とりあえず、ケーキ買った方がいいよね?ツナは先に帰とく?」
「オレも、と一緒に帰るよ」
そんな女子を見送った後、が疲れたようにため息をつきながら質問してくる。
まぁ、流石のでも、あのノリには付いていけなかったのだろう、気持ちは分かるけど……
の質問に、オレもため息をつきながら返す。
を一人で帰せるはずないし、何よりもあのメンバーの中には、絶対に入りたくないから
オレの言葉には苦笑を零すと、言ったようにケーキを買い始めた。
確かにね、お土産にケーキを買うって言ったのは聞いたけど、次々と言われるケーキの名前にぎょっとしてしまう。
「そんなに買うの?!」
漸く店の人に欲しいものを伝え切ったに、思わず驚いて質問すれば素直に頷いて返されてしまった。
どう考えても、多いと思うのは気の所為じゃないよね。
店員にお金を払っているを見ながら、不思議に思ったけどそれは直ぐに理由を知る事になる。
ますます、の超直感は冴えているという事だろうか?
「モンブランもうめーな」
「よかった」
「イーピンちゃんも、どーぞ」
帰り着いた家では、勝手にオレの部屋へと通された女の子達が、自分の買って来たケーキをみんなにお裾分けしていた。
母さんが嬉しそうにお茶の準備をしていたのを受け取って、部屋に運んでから、も2階へと連れて行く。
勿論、オレがを一人で階段上らせる訳ないだろう。
そして、直接床に座るのはの足に負担が掛かるから、勉強椅子に座らせた。
オレは、その直ぐ足元に座って、人間爆弾にケーキを勧めているハルと嬉しそうに笑っている笹川京子を見て小さくため息をつく。
「ハルちゃんも京子ちゃんも、自分の分が減っちゃったけど、いいの?」
「いいですよーみんなで食べた方がおいしいですしー!」
「うん!ツナくんち、にぎやかでうらやましーなー」
も、そんな二人を見ていたのだろう、心配そうに二人へと質問。
その質問に大して、女の子二人は嬉しそうに言葉を返してきた。
「そうかなぁ、欲しいなら全員喜んで引き取ってもらいんだけど」
笹川京子の言葉を聞いて、思わず漏らしてしまう本音は仕方ないだろう。
本気で、こいつら引き取ってくれるのなら、熨斗つけて譲ってやるのに
ボソリと呟いたオレの言葉は、どうやら女の子達には聞こえなかったらしく、だけが苦笑を零しただけだった。
「で、なんでランボは大人になってるんだ?」
そして一番気になっていた、オレの隣でモクモクとケーキを食べている大人になっているバカ牛へと質問。
「子供のオレが10年バズーカーを誤射したっぽいですね」
オレの質問に、あっさりと返事を返してくる大人ランボ。
あいつ、また誤射したのか?!
本気で何時か、あいつが持っている武器を全部取り上げて置かないと、その内が危ない目に……
「ハルは今日、自分感謝デーを持つ仲間にめぐり会えて幸せです!」
「私も、ハルちゃんに会えてよかったー!!」
ブツブツとバカ牛の武器をどうやって取り上げるかを考えていたオレの耳に、嬉しそうな声が聞こえてきて現実へと引き戻されてしまった。
どうやら、女の子二人組みは、同士が居た事で盛り上がっているらしい。
「!どう、イーピンちゃんここのミルフィーユは?」
そして、恐る恐るケーキに口を付ける人間爆弾に気付いたハルが、すかさず質問。
その質問に対して、人間爆弾の目から涙が……
「みんな通る道です」
感動しているらしい人間爆弾に、ハルが満足そうに頷く。
「やっぱり女の子ねー…」
笹川京子も、ニコニコとした笑顔で満足そうだ。
「京子ちゃん、イーピンちゃんが女の子って知ってたの?」
「えっ?見た目の印象で女の子だと思ってたけど……」
笹川京子があっさりと言ったその言葉に、が疑問に思って質問する。
ああ、そう言えば迷いも無く女の子って言ったっけ?
獄寺は、人間爆弾が女の子だと気付いてなかったよな、確か
「獄寺は、笹川京子よりも劣っているって事だね」
つまりは、獄寺は一般人である笹川京子よりも核下という事になる。
呟いたオレの言葉に、が苦笑を零した。
どうやら、同じ事を考えていたらしい。
『ケーキのお礼に、秘伝の餃子饅を差し上げたい!』
そんな中聞こえてきたその声に、顔を上げる。
人間爆弾の言葉が分からなかったのか、笹川京子とハルが不思議そうに首を傾げた。
「えっと、何て言ったの?」
それは、も同じようで通訳するようにお願いしてくる。
「『ケーキのお礼に、秘伝の餃子饅を差し上げたい!』と言ったんだぞ」
の質問に答えようとした瞬間、オレよりも先にリボーンが通訳した。
そのまんまの直訳だな、いや、間違ってないけど……
それにしても、ケーキ食っているのに、餃子饅を勧めるのは……
「えっと、餃子饅は後でいいと思うよ。ほら、今はキーキ食べているから」
「おいしそーっ」
リボーンから聞かされた内容に、が少しだけ困ったように人間爆弾に言おうとしたその言葉を遮って、女の子二人が嬉しそうに差し出された餃子饅を手に取る。
その勢いは、呆気に取られるほどのモノ。
「……凄い食欲だね。にも少しは見習ってもらいたいかも……」
嬉しそうに餃子饅を手に持っている二人の女の子に、思わずポロリと呟いてしまうのは仕方ないだろう。
は、自分では食べていると言い張っているけど、どう考えても食が細いのだ。
オレの半分、食べるか食べないかなのだから、明らかに少ない。
「そりゃそうですよ、若きボンゴレ。女性というのは、神秘的な胃袋を持つ仔猫ですよ」
「……確かに、神秘的な胃袋みたいだね。ケーキ食べている最中に餃子饅を食べる気は起きないよね、普通は!」
オレの呟きが聞こえたのだろう大人ランボが当然だと言うように口を開いてくる。
言われた内容に、『いただきまーす』と受け取った餃子饅にカブリ付く二人を見ながら呆れたように呟いてしまうのは止められない。
デザートは別バラと言う言葉を良く聞くが、今はそのデザートを食しているのに、ニンニクたっぷりの餃子饅を一緒に食べるのはどうかと思うんだけど
「じゅーしーですーっ」
「おいひーっ」
嬉しそうに餃子饅を食べている二人を見ていれば、傍目で見ていてもその顔色が悪くなったのが分かる。
『何だ?』と思った瞬間、パタリと二人同時に倒れてしまった。
「な、なに、何で二人が倒れちゃったの?!」
突然二人が倒れた事で、が驚いたように声を上げる。
椅子から勢い良く立ち上がるのは感心しないけど、二人が突然倒れたのだからの行動は仕方ないだろう。
「一種のポイズンクッキングね」
「えっ?」
続けて聞こえてきた声に、が分からないというように聞き返した。
「ビアンキ、どう言う事?」
当然声の主なんて確認しなくても分かっているので、理由を問いただそうと質問する。
開いたドアから顔を覗かせたビアンキは、オレの質問に答える気があるのかその口を開こうとした瞬間、大人ランボを視界に入れてしまったらしくその顔が驚いたようなものへと変わる。
「ロメオ!」
そして呟かれた名前に、やはりと思ってため息を付いた瞬間、大人ランボが鬱陶しい子供の姿へと戻った。
目の前にあるケーキに喜んでいるバカ牛を鬱陶しく思いながらも、面倒が起きなかった事に内心ホッとする。
「あ、あの、一種のポイズンクッキングって……」
だがそのお陰で、オレの質問が完全に無視された状態になっていた為、再度がビアンキへと質問。
「餃子拳用に使う餃子饅は、秘伝の製法で作られた特殊なものよ。一説には一個に500万のギョウザエキスが入っていると言われているの。餃子拳の鍛錬をつんだ拳法家だから食べられるのであって、一般人がそんなもの口にしたらひとたまりもないわ」
が質問した内容に、ビアンキが淡々と説明する。
説明された内容に、納得。
まぁ、確かに一般人にとっては毒以外の何ものでもないな……が食べなくて、本当に良かった。
「こ、このままじゃ、二人が死んじゃうってこと?!」
「イーピン、おまえ師匠に餃子饅を他人にやるなって言われなかったか?」
がそれを口にしなかった事にホッとしていれば、焦ったの声が部屋の中に響く。
それに続いて、リボーンが人間爆弾へと質問した。
その質問内容には心当たりが合ったのだろう、サーっと人間爆弾が慌てた表情を見せる。
「この様子では、時間の問題ね」
「ど、どうすればいいの?」
ビアンキが、二人の様子を見てから、あっさりと状態を口にした。
その言葉を聞いて、が震える声で質問。
明らかに、今の状況に動揺しているのが分かる。
小さく震えているに気付いて、オレはその体を抱きしめた。
「大丈夫だよ、」
そして、出来るだけ安心出来る様にその背中を優しく撫でる。
「こんなおっちょこちょいの殺し屋だぞ、師匠が解毒剤をもたせてるはずだ」
安心させるために言ったオレの言葉にが不安そうに見詰めてくるのに対して、オレが口を開くよりも先にリボーンがその口を開く。
それは、オレも考えていた事だ。
まぁ、誰が言ってもいいんだけど、リボーンに台詞をとられたのは少しだけ面白くない。
リボーンに言われて、人間爆弾が慌てて持っていた荷物をあさり始めた。
そして取り出されたのは、丸に解と書かれた紙袋。
「それで、二人を助けられるんだね?」
自信満々に差し出されたその袋に、が確認するように問い掛ければ人間爆弾がコクリと頷いて返す。
「それじゃ、早く飲ました方がいいね」
明らかに、それにがホッとした表情を見せるのを確認してから、促すように口を開けば、もう一度人間爆弾が頷いて持っていたその袋から薬を取り出した。
だが、出てきたのは一粒の解毒剤。
「も、もしかして、一個しか入ってないの??」
その後も何度か袋を振るが、中からは何も出てこない。
その様子を見守っていたが、確認するように質問する。
「一人分だな」
更に、不安を煽るように、リボーンが現実を突きつけてきた。
「ひ、一人分だなんて、ど、どうするの?だって、二人居るんだよ?!」
「まぁ、運が無かったって事で、どっちかには諦めてもらうのが」
「そんな訳にはいかないから!!!」
無常にも口に出された内容に、が慌て出す。
それにオレが口を開けば、その言葉を遮ってが突っ込みを入れてきた。
動揺しているのに、しっかりと突っ込んでくるところが流石だよね、。
「仕方ねぇぞ、こうなりゃ死ぬ気の生命力にかけるしかねーな」
困惑状態のに、リボーンが2丁の拳銃を取り出す。
仕方ないと言う割には、その顔が嬉しそうに見えるのは気の所為じゃないだろう。
そして、構えた拳銃から同時に弾が飛び出して倒れている二人の額に当たった。
「なっ!えっ、なに、もしかして、死ぬ気弾??」
「初の同時撃ちだぞ。同時撃ちすると、死ぬ気弾の共鳴により復活の生命力はパワーアップするんだ。そのかわり2人の後悔がシンクロしてねーとだめだけどな」
行き成り撃たれたそれに、が驚きの声が上げるのにリボーンが簡単に説明する。
つまり、リボーンの説明から考えれば
「って事は、シンクロしてなかったら死ぬんだ」
「なっ!?」
「仕方ねーだろ、2人を平等に助ける方法だ」
あっさりと言ったオレの言葉に、信じられないというようにが声を上げる。
の驚きの声に、リボーンが少しだけ不機嫌な声で返してきた。
リボーンとしても、素人の女の子を巻き込んでしまったことが気に入らないのだろう。
「ツナ、俺が買って来たケーキ!」
「あっ!ああ、そう言えば、いっぱいケーキ買ってたね。可笑しいと思ったんだけど、そう言うこと」
「何だ?」
そんな事を考えていれば、が突然声を上げる。
その内容に一瞬何を言われたのか分からなかったけれど、が何を言いたいのかを理解して、思わず納得してしまった。
そんなオレ達に、リボーンが意味が分からずに問い掛けてくる。
だがそれを説明する前に、女の子二人の体がモコモコと膨れたと思った次の瞬間には、下着姿の二人が同時に起き上がった。
「いかなくちゃ」
そして、ポツリと呟かれたのは二人とも同じ言葉。
「まっ、待って!ケーキなら、ここにいっぱいあるから!!」
その言葉が聞こえた瞬間、が慌てて買って来たケーキの箱を二人の前に広げる。
「ケーキです!」
「一個じゃ足りなかったんだよね」
「はい、ハル感謝デーなんですから、一個じゃ足りません!」
予想通り、ケーキを見た二人がの持っているケーキへと伸ばされる。
そして言われたその言葉は、が考えていた通りのもの。
「超直感か」
「…みたいだね。可笑しいと思ったんだよ、あんなにケーキ買うの」
「で、でも、流石に5分なんて時間は持たないよ」
その光景を見て、リボーンが納得したのだろう、ポツリと呟く声が聞こえてきたので同意する。
その瞬間、焦っているの声が聞こえてきた。
確かに、の買った量では5分間を凌げるものではない。
「しよーがねーな」
の言葉に取り出されたのは、何時か見た事がある1tと書かれているハンマー。
前にも思ったんだけど、このハンマーはどこから出してるんだ、こいつ。
「リバース1t」
そのハンマーを軽々と振り上げて、二人同時にその頭を容赦などせず殴った。
殴られた拍子に、打ち込まれた弾丸が二人の額から飛び出してきて、それと同時にその体が崩れ落ちる。
「これで死ぬ気タイムを夢だと思うぞ」
そう言ったリボーンの言葉と同時に、が力なくその場に座り込んでしまう。
「、大丈夫?」
「な、何とか……超直感が役に立って良かったって言うべきなのかなぁ?」
それに気付いて慌てて声を掛ければ、苦笑しながら返事が返ってきた。
その手に持っていたケーキの箱の中身は、綺麗になくなってしまっている。
「ダメにしては、お手柄だったな」
疲れているに、リボーンが珍しくもその頭に手をやって感心したように呟かれた内容。
は褒められて嬉しそうだったけれど、そもそも女の子二人組みがこんなにも卑しくなければ、こんな事にはならなかったんじゃ……
が、二人みたいに神秘の胃袋を持ってなかったことに感謝したのは言うまでも無い。