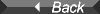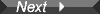一人で抱え込むのを知っているからこそ、苦しくなる。
どんな些細な事でも、君の事なら何でも知りたいと思うのは、オレの我が侭だと分かっていても
君が、オレの知らない所で傷付いてしまうのが嫌だから
だからこそ、ちょっとした変化でも直ぐに気付く。
だって、俺が見ているのは、君だけなんだから
「ツナくん」
の後姿を見送っていたオレに、京子ちゃんが声を掛けてくる。
「うん、聞えたよ」
多分、先程が伝言を頼んでいた事だろうと察して口を開けばどこか、ホッとしたような表情を見せてから、その表情が戸惑いの色を浮かべた。
「くん、何かあったの?」
そして質問されたのは、を心配した言葉。
何かあったのなら、多分自分でも気付けたと思う。
だけど、思い返してみても気になる事は何一つない。
「……残念だけど、オレにも分からないんだ………」
本当は、の事ならなんだって知っていたいのに、現実は何でこんなにももどかしいのだろう。
オレにも、が考えている事が分かればいいのに……
「そう、なんだ……何か心配事があるなら、話してくれるといいのにね」
オレの言葉に、京子ちゃんがどこか寂しそうな表情を見せて、が出て行ったドアの方を見る。
もうそこには、その姿を見つけることは出来ないけど
「くんが、傷付かなきゃいいんだけど……」
心配そうに呟かれたその言葉に、オレもそっとが出て行ったその方を見詰めた。
本当は、片時だって離れたくないのに、何故同じクラスじゃないんだろう。
それが、もどかしくてもどかしくて仕方ない。
「ツナ!俺らのクラスも集合だってよ」
そんな中聞えて来た山本の声に、顔を上げる。
「分かった」
短く返事を返して、小さく息を吐き出す。
そうでもしなければ、この心に支配されたまま動けなくなってしまいそうだったから
「集合だって、行こうか」
隣に居る京子ちゃんに声を掛けて、他のクラスメンバーが集まっている場所へと急いだ。
「なぁ、あの子供は?」
集まった場所で、先に来ていた山本が、不思議そうに質問してくる。
そう言えば、気付けば居なくなってるな、あの赤ん坊。
あいつも、何も知らないと言った。
でも、あいつはオレと違って、読心術が使えるのなら、きっとオレよりも沢山の事を知ることが出来るのだろう。
それにさえ、嫉妬している自分に気付いて、苦笑してしまった。
の事になると、心が狭くなるのは、仕方ない。
「さぁ、気が付いたら、居なかったけど……帰った…は、ないだろうね……」
帰ってくれれば、有難いんだけど、あの赤ん坊がすんなりと帰るなど、どう考えても無理だろう。
本当に、迷惑な赤ん坊だ。
「んじゃ、の方に行ったのか?何か様子が可笑しかったから、心配なんだろうな」
オレの言葉に、山本が京子ちゃんと同じように心配そうに口を開く。
ああ、本当に皆が君に惹かれるのはどうしてだろう。
本当は、誰にも見せないで、オレだけのモノにしてしまいたい。
「……そうだとしたら、憎らしいんだけど……」
片時も離れないで、君の事を護れたら、いいのに
リボーンが今、の傍に居ると考えるだけで、イライラする。
ああ、やっぱりオレはの事になると、こんなにも心が狭くなってしまう。
だって、を誰にも渡したくないのだから
「えっ?もう帰った?」
心配で心配で、クラスの用事を全て終わらせての教室に行けば、既にその姿はなかった。
そして、質問したのクラスメートの言葉に、思わず聞き返してしまう。
「ああ、俺達のクラス、1時間も前に終わってたからな」
ああ、球技大会で敗退したクラスは、直ぐに終われるんだった。
その事実を思い出して、オレは頭を抱えてしまう。
なら急いで帰れば、は家に居のだろうか。
「有難う」
教えてくれたクラスメートに礼を言って、急いで靴箱へと向う。
兎に角、早く帰ってが無事な姿を確認したい。
だって、あの表情をする時、が傷付く。
だからこそ、今直ぐが無事で居る姿を確認したかった。
「ただいま!母さん、は?」
急いで家に戻ってキッチンに居る母さんへと質問。
「あら、お帰りなさい。そんなに慌ててどうしたの?」
の事を質問したのに、暢気に返してくる母さんにオレは内心イライラしてしまう。
「だから、は?」
「ちゃんは、まだ帰ってきてないわよ。ツっくん一緒じゃなかったの?」
そんな母さんにオレはもう一度の事を問い掛ければ、逆に聞き返されてしまった。
まだ、帰ってきてない?
でも、随分前に帰ったって言っていたのに……
「オレ、を探してくるから!」
持っていた荷物をテーブルに置いて、オレはそのまま飛び出そうとした瞬間、微かな気配を感じて視線をそちらへと向ける。
「リボーン!」
「ちゃおっス、何を急いでんだ?」
視線の先に居たのは、黒いスーツ姿の赤ん坊。
暢気に挨拶して来た上に、質問してくるその言葉。
「おまえ、と一緒じゃなかったのかよ!」
「一緒じゃねぇぞ」
もしかしたら、一緒に居ると思っていた相手が目の前に居る。
それに対して口を開けば、あっさりと返される言葉。
それが嘘か本当かは、この子供の表情からは読み取れない。
「だったら用事はない」
「一緒じゃねぇが、何処に居るのかは知っているぞ」
これ以上この赤ん坊に構っていても拉致があかないとリビングから出て行こうとした瞬間、後から聞えて来た声にその足を止める。
「何処に居る?」
ゆっくりと振り返って、短く質問。
「あいつなら、病院だぞ」
質問したオレに、リボーンが短く返事を返して来た。
言われた言葉に、一瞬自分の耳を疑いたくなる。
何で、が病院に……
「どうして!」
「どうしても何も、今日は定期検診だと言ってたぞ。違うのか?」
一瞬取り乱して問いただそうとした自分に、リボーンがあっさりと返し、逆に問い掛けられてしまう。
「あら、そう言えば、今日は月に一度の検診日ね……すっかり忘れてたわ」
リボーンのその言葉を聞いて、母さんが思い出したというようにカレンダーを見て納得したように頷く。
ああ、確かに今日は検診日……オレも忘れてた。<BR>
でも、朝には何も言ってなかったんだけど……もしかして、も忘れていたんだろうか?
「あいつも忘れてたみてぇだぞ、慌ててたからな」
疑問に思った瞬間、リボーンが心を読んだように続ける。
それが分かっただけで、ホッとした。
「なら、は大丈夫なんだ……」
ホッとして、息を吐き出し直ぐ傍の椅子に座れば、スッと差し出されるコップ。
「はい、ツっくん」
お茶の入ったコップを渡してくれたのは母さんで、それにお礼を言って受け取ってから一気に飲み干す。
ずっと緊張していたから、確かに喉が渇いていたので、冷たい飲み物は本当に有難い。
「病院なら、迎えに行った方がいいかな?」
「そんな事したら、いつまでも子ども扱いするなって、ちゃんに怒られるわよ」
冷静になったお陰で、何時ものように軽口が言える。
半分冗談、半分本気で言ったオレのそれに、母さんがクスクスと笑いながらオレが飲み干したコップにまたお茶を入れながら楽しそうに言葉を返してくれた。
確かに、ならそう言いかも……
でも、ここでが戻ってくるのを待っているのがもどかしい。
だって、まだが本当に無事なのか、確認した訳じゃないから
「そうだね、戻ってくるまで大人しく待ってるよ」
過保護過ぎだって怒り出すを考えて、小さくため息をつき母さんが入れてくれたお茶を飲む。
その直ぐ傍で、リボーンが母さんにコーヒーを頼んで却下され、渋々出されたオレンジジュースを飲んでいる姿があって思わず笑ってしまう。
「リボーンちゃん、コーヒーは大人になってから飲むものよ!子供のうちから飲んじゃダメ」
何て言う母さんの言葉をどこか遠くに聞きながら、オレはゆっくりと進んでいる時計の針をボンヤリと見詰めた。
が、戻ってくるのを待ちながら