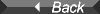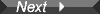君は、本当に誰からも好かれる。
どうして、皆君に惹かれるんだろう……
その都度に思う。
誰にも、君を見せたりしたくない。
オレの腕の中だけに閉じ込めていたいと……
「何を、仰ってるんですか?」
気に入らないヒバリさんのその言葉に、オレは相手を睨み付けた。
絶対に、そんな事許す訳がない。
だって、オレにとって、は絶対の存在。
「もう一度言った方がいいなら、繰り返してあげるよ」
「聞くつもりはありませんけど!」
オレの問い掛けに、不敵な笑みを浮かべてヒバリさんが口を開くけど即座にそれを拒否した。
あんな言葉を、二度も聞きたくはない。
「俺を貰っても多分、役に立たないと思うんですが……書類整理も風紀の仕事も俺なんかよりツナの方が役に立つと……」
ヒバリさんと睨み合っている中、聞えて来たその声に驚いてそれを言った張本人を見てしまう。
きっと、なりに考えたんだろうとは思うんだけど、どうしてそんな考えに行き着く事が出来るのだろうか。
オレにとっては都合がいいんだけど、それを言われたヒバリさんは複雑な表情をしている。
きっと、こんな突拍子もないの行動は、ヒバリさんにとっては未知の領域だろう。
「俺、変な事言った??」
オレ達3人に一斉に見られた事で、変な事を言ったのだと思って焦って質問してくるは、本当に何も分かってない。
そんなにため息を付けば、同じように周りからもため息をつく声が聞えて来た。
どうやら、皆同時にため息をついたらしい。
こんな二人と、シンクロはしたくはなかったんだけど、今回は仕方がないと諦めよう。
「……本当にダメダメだな」
そして聞えて来たのは、呆れているのが十分に分かるリボーンの呟き。
気持ちは分かるけど、多分それをに言っても本人は無自覚だから意味がないと思うんだけどね。
「何だか、気が削がれたよ……もういいから、君達さっさと帰ってくれる?」
リボーンに呆れられて、ヒバリさんまでも深々とため息をつきディスクへと歩いて行く。
こんな事ぐらいで戦意喪失するようなら、を相手にするなんて出来ないと思うんだけどね。
オレ達を疲れさせた張本人であるは、訳が分からずに首を傾げている。
本当、そう言う所は鈍いよね、は……
「そうだ、それは君にあげるよ」
疲れて椅子に座ったヒバリさんが、思い出したと言うように口を開く。
突然の事に、が一瞬訳が分からないと言う表情をしたけど、テーブルに置かれている紅茶の袋を手に持ってヒバリさんの方を向き首を傾げれば、相手がコクリと頷く。
「えっと、でも……」
「まだ沢山あるからね、気にしなくてもいいよ。そんな事より、さっさと出て行ってくれる。群れてるとみなして咬み殺したくなるんだけど」
紅茶の袋を持ったまま困惑しているに、ヒバリさんはもう用事はないと言わんばかりにトンファーをチラつかせる。
本当に、暴力で何でもかんでも解決できると思っているんだから、性質が悪い。
を脅しているヒバリさんに、反応して構えようとした瞬間、がオレの手を掴んで慌てて部屋を出ようと振り返った。
に手を引かれた事で、オレも否応無しに振り返った瞬間思い出す。
そう言えば、ここに入る時にオレがドア壊したんだっけ?
振り返った瞬間、は壊れたドアを前に呆然としてしまった。そんなに、オレが声を掛けようと口を開く前にヒバリさんの声が響く。
「さっさと消えてくれる?ああ、ドアは、そのままでも許してあげるよ」
まぁ、修理しろといわれても、無視するけど……
これは、今日二度もをこんな所に連れて来た報復なんだから
「し、失礼しました!」
ヒバリさんの言葉で、がオレの手を掴んでそのまま応接室を後にする。
その手には、ヒバリさんがあげると言ったあの紅茶をしっかりと握られていた。
「!何でそんな物貰ってきてるの!!!」
そんなに、オレはしっかりと説教。
下心アリアリの人間から、物を貰うのだけは止めて欲しい。
「しっかり賄賂を受け取りやがって……」
オレの言葉に続いて、リボーンも呆れたように口を出してくる。
賄賂と言われれば、確かに賄賂かもしれない。
に気に入られる為の貢物……
「賄賂って……意味違うように思うんだけど……」
「違わねーぞ。本当に、おまえはだめだめだな」
リボーンの言葉に、は考えるように口を開くけど、それに対してもリボーンは深々とため息をつく。
オレも、ため息つきたいよ……。
大体、賄賂とか、そんな事どうでもいい。
オレにとって、今一番気になる事は……
「賄賂とかそんなのどうでもいいよ。なんで、がヒバリさんなんかとお茶してたのかが、一番気になるんだけど!」
不機嫌な声そのままに、へと問い掛ける。
ずっと気になっている事。
嘘ではなく、本当の事を話してもらいたいから……
「美味しい紅茶があるって言うのは聞かないからね」
だから、が言い訳に使ったその言葉をしっかりと受付拒否。
だって、それはどう考えてもありえない理由だから
「ねぇ、部屋の前で話してないで、さっさと行ってくれる。目障りなんだけど」
応接室の前でそのまま話していれば、ヒバリさんの不機嫌な声が内から聞えてくる。
その声を聞いて、オレは小さく息を吐き出す。
「す、すみませんでした……って、ツナ!」
「邪魔みたいだから、さっさと移動した方がいいんだよね。暴れないでよ、」
が謝罪する声を聞きながら、その体を抱き上げる。
オレだって、何時までもこんな場所には居たくない。
それに、がヒバリさんに話し掛ける事さえ気に入らないのだから
を肩に担いで、その場を急ぎ足で離れる。
「多分、てめーの考えてる事は、見当外れだと思うぞ、ダメ」
何も話さずに歩いていれば、呆れた声でリボーンがへと声を掛ける。
また、何を考えていたのか……まぁ、大体予想は付くけどね。
の事だから、オレが不機嫌な理由を考えているんだろうけど、多分それが全部見当違いな事しか考えてないんだろう。
「リボーン」
「余計な事は言わなくてもいいよ。それよりも、しっかり説明してもらうんだから、ちゃんと考えておいてね」
リボーンの名前を呼ぶに、キッパリと言えばが口を閉じる。
本当、どうして分からないんだろう、オレが不機嫌な理由が……
「ダメに決まってるぞ。お前とヒバリは、そんなに親しい仲じゃねーみたいだしな」
真剣に考えているに、またしてもリボーンから突っ込みが入る。
今度は、言い訳について考えてるのかな?
本当、は分かりやすいよね。
「騙されてくれる訳ないんだ……」
そして、ポツリと呟かれたそれに、オレはにバレないほど小さく息を吐き出した。
本当、アレで納得出来るなんて、どうしてそんな馬鹿な事を考えられるんだろうね。
まぁ、そこがの可愛い所ではあるんだけど……
「だから、ダメダメなんだぞ」
納得したに、リボーンが呆れたようにため息をつく。
オレを無視して、リボーンと話しをするのも、正直言って面白くないんだけど
「!このまま連れて帰るからね」
だから、腹いせとばかりに口を開く。
は軽いから、このまま家までの距離を担いで帰ったとしても、オレには何の苦にもならないからね。
それどころか、ずっとに触れていられるから今日だけじゃなく、毎日こうやって峠こうしたいぐらいなんだけど
「ちょっ、ツナ!!」
「聞く耳は持たないよ。大丈夫靴はちゃんと履き替えさせてあげるから、心配しないでいいからね」
キッパリと言ったオレに、が慌ててオレの名前を呼ぶ。
それに、心配させないように言えば、ブンブンと大きく首を振っているのが伝わって来た。
が何を言いたいのか分かってるけど、今は敢えてそれに気付かないフリをする。
「リボーン。の靴を履き替えさせてあげてくれる?」
「………仕方ねーな……」
直ぐにのクラスの靴箱に移動して、リボーンへと声を掛けた。
そうすれば、渋々と言った感じでリボーンがの靴箱から靴を取り出して上履きと履き替えさせる。
「お、降ろして!自分で履けるから!!」
「言った筈だよ。このまま帰るからって」
まず片方を履き替えさせた瞬間、が慌てたように暴れ出した。
それを片手で簡単に押さえ付けて、拒絶する。
「諦めろ、今のこいつに何をいっても無駄だぞ」
の靴を履き替え終えたリボーンがため息をつきながら口を出して来た。
まぁ、それは否定ないから、別に気にしない。
本当、もさっさと諦めればいいのに、そうすれば楽だと思うんだけど……
「ずっと、俺を抱えたまんまなんて、重いだろう!」
「………そんな心配しなくって大丈夫だよ。は軽いんだから」
「つーか、そんな心配してる場合じゃねーと思うぞ……」
リボーンの言葉に、が真剣に口を開く。
それは、全く見当違いの内容で、オレは一瞬ため息をついてしまったけど、しっかりと言葉を返す。
やっぱり、リボーンには心底呆れられてるみたいだけどね。
の靴を靴箱に戻して、思わず笑ってしまうのはの鈍い所が可笑しかったから
「まぁ、そこがのいいところなんだけど……」
そこが可愛いとは思うんだけど、心配の種でもあるのは否定しない。
そのままを抱えたままで、今度は自分の靴箱へと移動しながら、思わずポツリと呟いた言葉はきっとには聞えていないだろう。
そんなだから、オレは何も言えないままなのだから
「ツナ?」
「沢田くん!!明日、バレーの試合出るんだって?!」
後少しで自分のクラスの下駄箱に辿り着くと言う所で、一人の女子が話し掛けてきた。
ジャージ姿から考えて、部活生なのだろう。
「……一応、球技大会のバレーの補欠選手だからね。選手に怪我人が出れば、否応無しに出なきゃいけなくなるよ」
全く、どうして誰も彼もが同じような事を聞いてくるんだろうか、オレは元々バレーの補欠選手なんだから、人が足りなくなったら嫌でも出なきゃいけないと言うのに……
皆が覚えてなかったのなら、断っとけば良かったんだろうか?
「応援してるから、頑張ってね」
「……有難う」
ため息混じりに言ったオレの言葉に、女子が応援の言葉をくれる。
素直にそれに礼を言えば、そのまま手を振って遠去かっていく。
それを見送ってから、再度盛大なため息をついてしまった。
「ツナ、球技大会出るんだ……」
「ああ、仕方ないけどね」
その瞬間、のポツリと呟く声が聞こえてきたから、返事を返す。
本当に、仕方なく出る球技大会。
出来れば、補欠のまま終わりたかったんだけどね。
「うん、俺、応援に行くから!」
「……相手がのクラスじゃない事を祈っとくよ」
「大丈夫!俺のクラスが相手でも、ちゃんとツナを応援するから!」
返事を返したオレに、が嬉しそうに口を開く。
オレとしても、が応援してくれるのは嬉しいけど、それはオレ達のクラスの対戦相手がのクラスじゃないと無理な話だ。
注意するように言えば、キッパリと返ってきた言葉に思わず苦笑してしまう。
本当に、オレの事を応援してくれる気満々なに嬉しくなった。
「あのね、それは嬉しいんだけど、クラスメートの前ではちゃんと自分のクラス応援してよ」
「うんうん、大丈夫!ちゃんとツナの事は心の中だけで応援するから!」
それでも、がクラスで浮いてしまうのが心配だからしっかりと釘を刺すように言えば元気良く頷いて返される。
本当に分かってるのか分からないのその態度に、オレは思わず盛大なため息をついてしまった。
「ツナ?」
「何でもないよ。早く帰ろうって、思っただけだから」
「やっぱり、重いん……」
「訳じゃないからね!早く帰ってにちゃんと説明してもらわなきゃと思ったんだよ」
ため息をついたオレに、が心配そうに名前を呼ぶ。
そんなに返事を返して、素直に言えば不安そうな声。
それにキッパリと返事を返して、自分の靴箱から靴を取り出し履き替える。
「オレも、興味があるぞ」
その瞬間、後から声が掛けられた。
しっかりと、オレとの鞄を持ったリボーンが居るのを確認して、アイコンタクトが成功していた事を知る。
まぁ、心が読めるならそれぐらい簡単だっただろうけどね。
「って、訳だから。急いで帰るからね」
オレの言葉に便乗するようなリボーンの言葉にニッコリと笑顔を見せてさっさと歩き出す。
オレの言葉に、が数回頷いたのが気配で分かった。
本当、は軽すぎなんだけど……
オレが、心配するぐらい…
そう思いながら、ただ家路を急いだ。