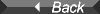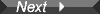本気での危機感の無さには困ってしまう。
きっと、自分が簡単に言った事の重要性も分かってはいない。
こうやって、オレが怒っている理由さえも……
でも、それが君らしくて、安心する。
でもね、ちゃんとしっかり怒っておかなくっちゃ、その内強盗にまでお茶を出しそうだから、心配で堪らないんだよね。
「で、ズーズーしくそこでが入れたコーヒー飲んでる君は、何のつもりで寛いでいる訳?」
気の済むまでに説教してから、オレはが入れたコーヒーを暢気に飲んでいる子供へと声を掛けた。
何でそんなに寛いでいられる訳!人の家で!!
しかも、にコーヒーを入れて貰っているのに、お礼も言わないなんて、失礼なガキなんだけど!
「お前の入れたコーヒーは旨いぞ」
オレの質問を完全に無視して、子供がに声を掛ける。
その内容は、お礼を言う訳でもなく、余りにも偉そうな内容だった為にピクリとオレの米神が反応した。
「えっと、有難う?」
子供に誉められて、が疑問系で御礼を言う。
チラリとオレの方へと視線を向けて来るのは、オレの反応が恐いからだろう。
に、してもこの子供本気で腹が立つ。
こいつがお礼言うのなら分かるけど、なんでそこでが、お礼を言うのかが分からない。
「!なんでそこで御礼なんて言ってるの?!」
オレに一度怒らた後なので、かなりビクビクしているを思わず怒鳴ってしまうのは仕方ないだろう。
が悪い訳じゃないと頭ではちゃんと分かっているんだけど、どうしてもイライラしてしまうのだ。
そう、が子供に近付く事さえも許せないくらいに
「兎に角、はそいつに近付かないで!ここに座ってて」
自分の気持ちを落ち着かせる為に息を吐き、オレは今だに子供の直ぐ傍でお盆を持って立っているの腕を掴んで無理矢理移動させる。
そして、子供から一番離れた席へと座らせて、自分がその間に入るように座った。
は一瞬驚いたような表情を見せたけど、結局その場に落ち着いて、自分で入れた紅茶を飲み始める。
それを横目で確認してから、オレは今だに寛いでが入れたコーヒーを飲んでいる子供へと視線を戻した。
「で、家庭教師さん、何度も言うけどウチには必要無いから帰ってくれない」
そして、もう何度か言っている言葉を再度口にする。
「オレも何度も言っているぞ。お前等には必要だってな。しつけー男はモテねぇんだぞ」
だけど、オレの言葉に返されたのは、やっぱり同じ言葉。
もう何度も聞かされたそれにプラスされて、しっかり嫌味で返された。
「あいにく、モテたいなんて願望はないから、ご心配なく」
それに小さく息を吐き、しっかりと嫌味で返す。
大体、本当に好きな相手に好かれなきゃ意味がないだろう。
オレには、が居ればそれだけで十分だから、好きだと言ってくる女の子達が正直言って鬱陶しいくらいなのだ。
好きな人が居るのだと言っているのだから、さっさと諦めてくれればいいのに……
オレが好きなのは、だけ。
が居れば、他には誰もいらない。
「そうだろうな、好きなヤツが隣に居てくれりゃそれでいいんだろう……」
オレの言葉に、子供がチラリとを見てから納得したように口を開く。
それは、今正にオレが考えていた事。
どうやら、この子供は人の心を読む事が出来るようだ。
別段それに対して、何とも思わないが、厄介な事に変わりはない。
「その通りだよ……ふーん、どうやら読心術まで使えるみたいだね……また厄介な」
「まぁ、俺の特技の一つだかんな」
それが分かって、オレは複雑な表情で相手を見て再度ため息をつく。
それに、子供が得意気な表情で返事を返してきた。
まったく、本当に厄介な子供だ。
いや、こうなってくると、子供なのかも怪しくなってくる。
「おい、お前!オレにさん付けしなくてもいいぞ、普通に呼べ」
面倒だと考えていたオレの耳に、子供の声が聞えて来て顔を上げた。
多分その言葉は、オレではなくへと向けられた言葉。
は、こんな奴をさん付けしてたの?
こんな奴は、子供で十分だと思うんだけど……
「心配すんな、ずっと読んでる訳じゃねぇぞ。今は、お前等の様子を正確に観察しているだけだ」
呆れたようにを見た瞬間、またしても聞えて来たその声に、オレは再度子供を睨み付けた。
明らかに、心を読んでをからかって遊んでいると分かるだけに、面白くないんだけど
「で遊ばないでくれる。それよりも、さっさと本題に入ってくれると有り難いんだけど」
もう何度も聞かされている言葉ではなく、この子供がここに来た本当の目的をまだ聞いてはいない。
どうせ、ロクでもない内容だと分かっているが、聞かないままでは話が進まないから、真意を聞くために相手を促す。
本当は、聞きたくないんだけどね。
「話が早くて助かるぞ。オレの本当の仕事は、お前等をマフィアのボスにすることだ」
オレの言葉に、子供がニヤリと笑って、それを口にした。
言われた言葉に、自分の眉間に皺が寄るのが分かる。
予想していた言葉なだけに、複雑な気持ちは拭えない。
本気で、あのバカ親父を抹殺したくなってきたんだけど……
「そんな事だと思ったけど、興味ないから帰ってくれる」
余りにも予想通りの言葉だった為に、オレはニッコリと笑顔を見せてそれを拒否する。
誰が好き好んでそんな面倒な役職に尽きたい奴が居るって言うんだ?
大体、オレにはの足を直すと言う使命があるのだから、そんな、下らないモノになる気はサラサラない。
「お前等に拒否権はねぇぞ。オレはある男からお前等を立派なマフィアのボスに教育するよう依頼されてんだ」
「んじゃ、その男に言っといてくれる。オレももマフィアのボスになるつもりはないから」
だが返されたのは、否の言葉。
それに、オレは相手を睨みながらさらに拒絶の返事をする。
本当に、堂々巡りで嫌になってくるんだけど……
「言ったはずだ、お前等に拒否権はねぇぞ。お前が嫌なら、弟だけでも連れていく。ボスは一人でも問題ねーからな」
「俺?」
本気で殺気立ってきそうになった瞬間、言われたその言葉にオレは驚きで動きを止めてしまった。
そう言えば、こいつはずっと俺達と言っていたのだ。
それは、オレだけじゃなく、もその資格を持つと言う事……。
突然話を振られたが、不思議そうに首を傾げる。
何も知らないまで巻き込もうなんて、本気で何考えてるんだ!
「を連れて行くと言うのなら、赤ん坊でも容赦しないからね」
ふざけた事を言い出した子供に、オレは椅子から立ち上がり、本気で相手に殺気を向ける。
まともに動けないをそんな危険な事に巻き込もうとするなんて、絶対に許せる訳が無い。
「……えっと、でも、俺はなんて言うか、まだ状況が全く見えてないから、説明してくれると嬉しいんだけど……」
「は知らなくてもいい事だよ!」
一人事情の分からないが、説明を求めるのをオレは否定した。
そんな事、は知らなくってもいい事なのに……
こんな子供が来なければ、このままは何も知らずに居られたのだ。
必死で、オレが隠していた事なのに……
「でも、リボーンは、俺も関係あるみたいに……」
「そうだぞ。お前にも関係してる事だ。なんなら、オレが説明……」
「説明する必要はないよ!お前がここから出て行ってくれれば、全て問題なくなる事なんだからな」
オレが否定した事に、が困ったように口を開く。
確かに、今の状況はも関係している。
だけど、結局はこいつが居なくなれば、全ては丸く収まるのだ。
説明すると言う子供の言葉を遮って、オレはただ子供を睨み付けた。
「ただいま」
そんな中聞えて来たのは、母さんの声。
その声に、は一瞬迷ったみたいだけど、母さんを迎える為に部屋から出て行く。
それをチラリと見送ってから、オレはもう一度子供を睨み付けた。
「何度も言うが、お前等に拒否権はねーぞ」
「それでも、オレ達は拒否するよ」
オレはそんなモノに興味ないし、をそんな危険なモノになどさせられない。
だからこそ、断固拒否する。
「いい加減、その問答は飽きたぞ……」
「奇遇だね。オレも同じ意見だよ」
ため息をついて言われた子供の言葉に、オレも笑って言葉を返す。
「もう一度言う、お前等に拒否権はねーぞ。ボンゴレ10代目には沢田綱吉、お前が最優力候補として上げられている。オレは、ボンゴレファミリーのボス・ボンゴレ9代目の依頼でお前をマフィアのボスにする為に日本へきたんだぞ」
真剣に言われたその言葉を、オレはただ黙って聞くが、明らかに可笑しい事に気が付いた。
「ちょっと待って!オレをボスにするなら、何でを連れて行くとか……」
言われた事に対しての矛盾点。
話を聞いていれば、は候補として上がっている訳じゃないと言う事。なのに、そのを連れて行こうとするなんて、明らかにおかしいだろう。
「弟に関しての情報もちゃんと聞いているぞ。足が不自由な事もな」
「なら、何で巻き込もうとする?」
分かっていると言うのなら、を連れて行こうとする理由が分からない。
いや、分かるが、それを認めたくない。
「それは、お前を見て分かったからな」
オレの質問に、子供がフッと笑う。
その笑みは、嫌な笑み。
その続きを聞きたくないと思うが、聞かなければ話は進まない。
「……何が、分かったって言うんだ?」
頭では、質問するなと命令してくる。
だが、それを無視してその続きを急かすように問い掛けた。
「弟を連れて行けば、お前は確実に動くって事に決まってるだろう」
そして言われたのは、予想していた通りの言葉。
こいつは、オレがを大切にしている事を逆手に取って、行動を起こそうとしているのだ。
それだけ、こいつの行動は本気だと言う事。
だけど、そんな理由でを使おうとしている事に関しては、かなり腹が立つ。
そんな下らない理由に、オレが一番大切にしているを使おうなんて、絶対に許せない。
「いい表情だな。その表情が出来るなら、立派なボスになれるぞ」
本気で相手を睨み付けたオレに、満足そうに呟かれた言葉。
誰が、そんなもんになるか!!
そう思ったが、それは近付いてくる母さん達の気配に、言葉を飲み込まざる終えなかった。