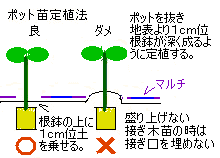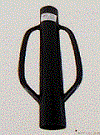肥料
堆肥類を適量投入し、元肥の化成肥料等を表面にばら撒き耕す。耕し方も大切で土が湿っている時は耕さない。必ず土が乾いてから備中鍬で耕す事。湿っている時に耕すと単粒構造の壁土の様な根はりの悪い固い土になる。ホカホカの団粒構造の土にする為に、これは守らねばならない。耕土深さは20cm余りあれば十分。又常に畦の耕作部を踏まない注意も必要。この様ないわゆる土作りは基本の基本。肥料は慣行成分量を有機肥料でまかなうと高価になり又使い勝手も悪い為化成肥料を使っている。
化成肥料には 8-8-8 や 14-14-14、 CDU複合燐加安S682。 IB複合燐加安S604 等多種ある。市販品にはオール8やオール14が多い(名前の数字は成分含有量%表示が多い。前から窒素、リン酸、加里の順)
又別に最後まで追肥の必要がないロング化成も(珪酸加里併用)使用している。 本文で化成肥料の数量表示は全て CDU又はIB化成 での数量である。
CDUとオール8-8-8では窒素の形態が一部違い価格もCDUはオール8のおおよそ倍以上する。その為肥効も違うのでオール8等の場合は施肥量も追肥回数も若干多くする。
石灰類。苦土石灰、消石灰、有機石灰等あるが石灰としては苦土石灰(炭酸苦土石灰)粉状で充分。有機石灰は良いように言われるが成分は苦土石灰と同じで成分量はやや少なく、商品により石灰含有量にばらつきがある。
普通石灰類は化成肥料と同時にまかず、別々に耕すのが基本(化成肥料の窒素分の効率が落ちる)
ようりん(BMようりん粒状)は目に見えて効果は期待できないが農家ではやはりプラスになると言う人が多い。但し多量に使用する事はマイナス面もある。ただ価格が高い。
正しく安全に
使用する為
使用法を
よく読み
農薬取締法
順守の事
|
粒剤 夏野菜(主にアブラムシ等の対策に定植前(時)に株元に使用する)オルトラン粒剤が有名)主に使用しているのは、オルトラン以外にアドマイヤー1、 アルバリン(スタークルも同一) 、プリロッソ各粒剤。アブラムシには全て有効だが特に有効と思う物に、モスピラン粒剤があるがまず必要はない。 秋冬野菜 近年秋冬野菜は気候が高温の為アブラムシの発生は遅くなりアブラナ科のハイマダラノメイガ(シンクイムシ)が多発している。この為効果の長いプリロッソ粒剤を使用している。 生育期にも使用できるのがアルバリン(収穫何日迄)以上大半の物が1作物1回の使用のみ。 実際の使用には夏野菜の場合アブラムシ等の発生期間が長く一回の使用では対処出来ない事があるので生育期にも使用できるアルバリン粒剤は置いておき定植後一か月位の再発生期に使用している。 散布剤等、アブラムシにモスピラン顆粒水溶剤(劇物)4000倍にしたのが同液剤、最高8000倍でも有効とか?。キュウリ等のアザミウマにアルバリン顆粒水溶剤。小玉スイカのウドンコ病にモレスタン水和剤(ハダニにも有効なので使っている) トマト、ウドンコ病にジーファイン水和剤(重曹剤で不思議と他の合成剤より効果) 冬野菜のアオムシ等鱗翅目害虫に安全なのがBT剤(トアロー、フローバック等多数)スピノエース顆粒水和剤。 他にプレバソンフロアブル、フェニックス顆粒水和剤。トルネーエースDF。プレオフロアブル等々、、、普通の散布農薬で10~12日間位有効。 プレバソンフロアブルは育苗時は潅注でも長期有効。 家庭菜園では四季に合わせ栽培する事が普通で園の例では4月から夏野菜を始める。 4~5月にまず発生するのがアブラムシ、次にアザミウマ、5月の乾燥期にはハダニが。病気はこの時期まず発生しない。 6~7月になるとウドンコ病が出だす。キュウリにはベトやウドンコが普通は多発するが今は耐性種が出回っているので家庭菜園ではまず気にしないで済む。 8~9月はダニの季節ハダニ、ナスホコリダニ、トマトサビダニ。近年はミニトマトにサビダニが多発する。 この時期から冬野菜の育苗が始まるのでアブラナ科のキャベツ、白菜等のハイマダラノメイガ(シンクイムシ)の被害が多い。 9~11月になると気温が下がりナス等にウドンコが出だす。又アブラナ科にはアオムシ等の鱗翅目害虫が多くなる。 もう少し気温が下がると又アブラムシが出始める。特に白菜キャベツには中の方につきだすと厄介である この様に四季に合わせて発生するものが替わるので、前もって注意する事も大切である。 家庭菜園では連作するので下記の被害が多くなるので注意する。 |
| 農薬使用の可否は別にして、今はネット購入が当たり前になり、農薬も小袋でも販売されているので毒劇物薬は、さておき普通薬は気軽に購入できるようになりました。まず初めのアブラムシの粒剤ですが、定植時1回使用のみが殆どなので夏野菜の場合約一か月位で効果が落ちるので、場合により生育期使用可のアルバリン粒剤が必要になる時があります。 又粒剤1gの計量は1gの計量スプーンが付いてれば楽ですが、ない場合は台所用計量スプーンの2.5ccのスリキリが約2.5gなので、そこから1gは解ります。台所用デジタルキッチン秤も1gがわかる物もあります。 散布薬その他では水和剤、水溶剤、ドライフロアブルタイプはデジタルキッチン秤で計量できるし。乳剤、液剤、フロアブルの計量はスポイドが便利です。 散布器具も小規模の場合、4Lタイプの蓄圧式2頭口が使いやすいです。 |
| 散布する時はゴムかビニール手袋をはめマスクをし、長袖、長ズボン着用し、散布中気持ちが悪くなれば即中止し休む。終了後はうがい、手洗いをする。 各薬の適用病害虫と使用法をよく読み順守する。農薬の保管にも注意し、鍵のかかる所で保管する。等事故のないように充分注意する事が大切です。 |
支柱
紐
| 黒マルチは一夏持てば良いので0.02mmの薄いポリマルチ、畦は固定幅なので150cm幅のマルチを使用。畦裾を少し削り落とし、マルチを張って、落とした土で裾を抑える。出来れば所々にマルチ押さえピンを使用する。 |
| 農家では一般的に支柱は定植、活着後生育が始まってから支柱を立てるが、家庭菜園のマルチ栽培では先に支柱を立てる方が作業が楽なので先に立てている。 夏野菜の主支柱は直径19mmのコンジットパイプ(パイプハウスの直管)を約1.8mに切断して使用している。上部も同じパイプ又は竹を組み合わせ使用。 下図左より、一本型は主にナスに使用。W型はキュウリ、インゲン、小玉スイカ。合掌型はトマト。 残渣(ゴミ)を分別処理(野焼き禁止)する関係で誘引にネットは使用しないで全てビニール紐を使用 |
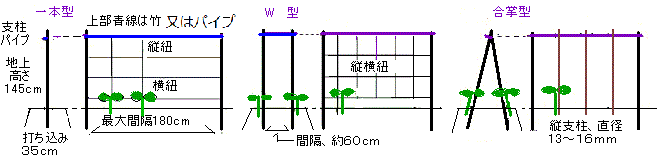
| ナス、畝幅が広い場合はV字型にする。狭い時は下の一本型にしている。 |
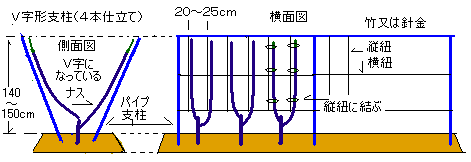 |
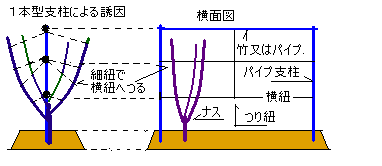 |
| 畦幅は固定した方が作りやすい。出来れば右図のように1.5m~1.7m位が作りやすい。それぞれ上部の型で平畦、M型畦としている。平畦は中央をやや高くかまぼこ型にし、通路も広くした方が通風も良く病気の予防にもなり好ましい。 | 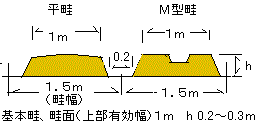 |