はじめに
一般に福祉の対象としての精神障害者は、各法律によって規定されている「疾患」に基づいた分類がなされている。さらに、その中でも統計的に統合失調症が他の疾患よりも圧倒的に多く、精神障害者の福祉施策は統合失調症を主な「対象」とされている。
本章では、そもそも障害とは何かということを中心に考察する。このことは一見自明に見えることであるが、障害者とは「障害しか持っていない人」と見られがちな一般概念がある。まず、その観念からの区別を図ること。そして、精神障害者の何が障害なのかどの様なアプローチがあるのかを明らかにする。
第1節.障害者の定義
第1項.障害の意味
一般に障害者は、様々な要因や形態等を内在していたとしても、渾然一体として語られ、何が疾患なのか、そして何が障害なのかを区別することなく認識されている。例えば、視覚障害者に対して、『めくら』という言葉がよく使われてきた。この意味は、「失明」「物事をきちんと判断できない人」「盲人」などを意味していた。このことは、単に差別としての言葉として用いられてきたということだけではなく、「盲」という視覚障害状態がその人の能力や社会的価値まで決定するという認識があったと見るべきである1)。さらに精神障害者は一般に精神病者(あるいは『きちがい』))として捉えられ、、障害者であるという認識はさらに低い註)(佐藤〔2000,P.40〕)などから。学術論文として『めくら』、『きちがい』は用語として不適切であるが、批判的な意味合いから文脈上使用する)。
しかしながら昨今、障害者福祉施策は、障害があったとしても本人の生活能力や自信を高め、環境改善(福祉サービスを含む)を通じて生き甲斐とその人らしい社会参加を支援しようとする傾向にあることは確かである。この目的達成のためには、実態において病気と社会参加や生き甲斐を切り離すには、まず観念において区別する必要がある。上記の「めくら」にしろ「きちがい」にしろ、すべてのものを渾然一体に見る認識は、近代医学導入以前から生活の中から発生してきた観念である。これに対抗するには、病気とそれに関連する要素・次元的な構造的・総合的な見方が必要となっている。それは「「障害しか持っていない人」という意味ではない。実は障害者は障害の他に、正常な機能や、様々な能力や、独特の個性を持った、他の人と異なった、ユニークな存在である。つまりたまたまある種の障害を持っていると言うほかには、まったく我々普通の人間と変わりのない、それぞれの個性や特徴を持った人々なのである」(上田*1〔2001,P.90〕)という認識を持つことに他ならない。
このような渾然一体に障害者を見る認識から対抗するために、国際障害分類(International Classification of ImPairments,Disabilities,and Handicaps,ICDIDH)が生まれたと考える。次項において、このICDIDHに基づいて障害とは何かについて論じる。
第2項.ICDIDHの成立背景などについて
世界保健機構(WHO)は従来、国際疾病分類(ICD)によって人々の病気や死因の状況を分析し、医療の効果を計ってきた。しかし、健康問題の変化発展に伴ってICDだけでは不十分だとされるようになった。つまり疾病の後遺症(変調)への対応や効果測定をしようにも、病気の分類だけでは役に立たなくなった。そこで「疾病の諸帰結(consequences of disease)」(=障害)の分類が求められた。また、より公平で一貫性のある障害者関係政策・制度の確立するための基礎概念が必要とされた。これは、どの国でも、次第に社会保障制度が多様な形で成立してくると、身体・感覚・知能・精神などの様々な障害者、労災や交通事故による障害者、要介護老人など、多種多様な障害者は「つぎはぎ的」な制度の下で分断されがちになっていた。つまり、多様なっていた障害者に対してある程度定義し、整理をする必要が生じてきたのである。
ICDIDHは1972年から始まった検討作業を経て第一版が1980年に出版された。この分類の大きな特徴は、障害(病気の諸帰結)を心身機能レベル(機能障害)、個人の活動能力レベル(能力障害)、社会的レベル(社会的不利)の3つの次元に分け、それぞれに詳しい分類を作ったことである。それは、障害減少を質や次元を異にするいくつかの要素と関連性、さらに環境との関係において捉えるものである。これはある要素や環境を変化させることによって他の要素または障害者全体を変化させることが出来るという意義がある。
いずれにしろICDIDHは、リハビリテーションなどの援助実践、実態調査と統計、政策などの分野で広く活用されるようになった。しかし活用されてくると問題点もより強く意識され「医学モデルであり、環境の役割が軽視されている」「児童や精神障害分野で使いにくい」などの批判が寄せられる2)。こうして国際障害分類第2版(International Classification of Functioning,Disability and Health,ICF)は1990年から始まった世界的な改訂作業の成果として2001年5月22日WHO総会で正式決定された。
以下、ICFの障害の構造を基に考察する。
第3項.障害構造について
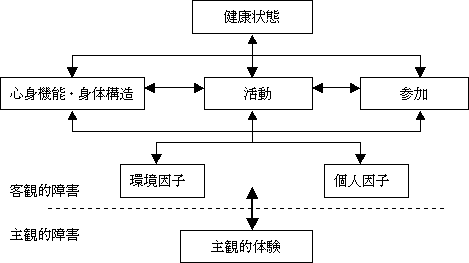
図4-1 ICFの考えを発展させた生活機能と障害構造 出所(上田*1〔2001,P.101〕)
(1)ICFによる障害区分について
ICFは、ICDIDHと同じく障害を3つの階層において捉えるという基本的な視点は変わりはない。しかし、否定的な名称・概念から中立的・肯定的な名称・概念へと変化していった。「機能・形態障害」は「心身機能・身体構造」に、「能力障害」は「活動」に、「社会的不利」は「参加」へと変わる。これらが障害された状態は、心身機能・構造はICDIDHと同じく、「機能・構造障害」であるが、活動は「活動制限」、参加は「参加制約」となる。これに伴って、従来の疾患も「健康状態」という中立的な用語に変わった(病気やけがだけでなく、妊娠、高齢、ストレス状態も含まれる)。なお、ICDIDHでは障害構造の一つの要素であった能力障害(disability)が、ICFでは障害全体を示す包括用語になる。
ICDIDHでは、各要素が疾病→機能障害→能力障害→社会的不利と矢印が一方向的であったため「運命論的なモデル」「逆方向の交互作用を認めていない」などの批判があり、ICFでは両方向の矢印に変わる。さらに、環境因子が背景因子として詳しい分類が追加される。また、ICDIDHが医学モデルであったという根拠に、機能障害(心身機能・身体構造)の分類が一番詳しく、能力障害の分類項目はそれよりも少なく、社会的不利に至っては7項目しかなかった。ICFは、逆に心身機能・構造の分類は簡素になり活動と参加の項目が詳細になっている。さらに障害者の全体像を捉える際に上田*1(〔2001,P.104〕)は「客観的な障害区分の他に、主観的な要素も大きい」ということで「体験としての障害」を加えている。
(2)障害構造の各要素について
障害要素(レベル)の一つ一つは具体的な症例を基に分類がなされている。例えば、
心身機能・構造レベルでは、運動障害や廃用症候群・過用症候群が代表的である。他、知覚、自律神経機能、高次脳機能、形態障害などがある。構造上において、運動障害は、活動レベルにおける日常生活動作(ADL)、社会生活行為(ASL)に深く関わる機能・構造障害として捉えられ、さらに運動障害は、複合動作障害、基本動作障害、要素機能障害に細目化される。複合動作とは重いものを運ぶなどの連動した動作を指しており、それを支えているのが基本動作、要素機能といえる。しかも、これらの構造は単なる寄せ集めではなく、複合動作を支えている各要素を分解して一つ一つ改善できるものではない。つまり、全体は「部分のある特定の構造(空間的・時間的)を持った組み合わせ」(上田*2〔2001, P.61〕)であり、その組み合わせこそが全体を特徴づけているといえる。廃用症候群は長い間、病床にいたために筋萎縮、心肺機能の低下などであり、他に抑うつなどが引き起こされている状態(精神神経性)、あるいはトレーニングのしすぎによる筋力の損傷、間違ったトレーニングによる関節の炎症や可動域の制限などの障害である。
これまで日本において、活動制限とはADLの障害としか考えなかった傾向があるが、家事や外出といった面でのASL、対人関係の生活技能(SS)、各種の身体的・知的職業技能(VS)、スポーツや旅行などに必要な余暇活用技能(AS)がある。これらは、機能障害が良くなれば自然と付随して出来るようになるという考えがある。再学習を必要とし、姿勢や手順、適切な道具などを使うなどの模索を必要とする。
参加制約に関しては、地域生活=退院先の確保、あるいは、就労が主な制約であると捉えられてきた。しかし、参加制約には、経済状況に関すること、交友、市民活動などの社会参加、余暇活動、家庭生活、生活の場など多種多様に存在する。さらに、(上田*2〔2001,P.74〕)によると「家族などの第三者の不利」もあり、介護者の介護疲れ、介護のために職を辞める、介護上での心理的な葛藤なども含まれていく。
また、上田が提唱する「体験としての障害」とは、客観的な障害と密接に結びつきながら、主観的に、障害を持った事による自尊心の喪失、劣等感、不全感などが存在していることを明らかにしている。
環境因子に関しては、自然環境や障害機器の有無や発展の程度など物理的環境、直接的な介助やコミュニティとの人間関係などの人的環境、サービスを支える制度的環境など広い範囲で包括的に捉えらている。
(3)障害の相互依存性、相対的独自性について
運動障害で若干触れたが、一つ一つの構造の要素、レベルなどが微細に組み上がって障害者としての全体像が作り上げられる。それは、階層性を有し、相互に影響しあい、しかもそれぞれが特徴を持って構成されている。この構造上の特徴は、相互依存性、相対的独自性といわれる。以下、このことについての論述と共に、例えとして「働く」という一つの「参加」レベルがどの様な構造を持っているのかを概説する。
相互依存性についていえば、「たとえば脳卒中で脳の中に起こった脳組織の破壊範囲(健康状態)が大きいほど、麻痺の程度(機能障害)も強く、歩行やADLの障害(活動制限)も大きく、復職や自宅復帰(参加制約)が一層困難になる」(上田*1〔20001,P.98〕)といった具合である。
相対的独立性は、その中にあって、回復の余地、各レベルの改善によってたとえば、機能の再編成、活動の再学習等を通して、障害の残っている部分があったとしても活動制限が解消されることができるという意味である。
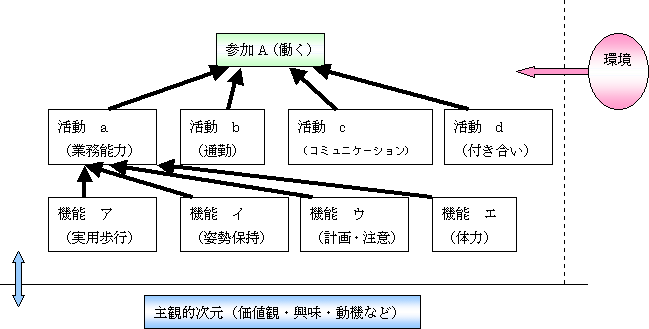
図4-2 生活機能と障害における階層構造 出所(図4-1,P.105)
たとえば働くということを可能にしているのは、その職種にあった業務能力やエスカレーターを利用する、雨の日に傘を差して歩く(ADL,ASL)、同僚との人間関係やコミュニケーション(SS)がそれぞれの要素で独立しながら存在し働くことの要素を構成する。そして、業務能力一つにとっても、機能・構造の姿勢保持(運動−基本動作)や複合動作が支えている。さらに、コミュニケーションになればそれを支える「機能」はまったく違う要素や組み合わせによって構成される。また、業務能力があってもコミュニケーションに障害があるとか、参加と活動の間にも相対的独自性が存在する。同時に主観的次元で働くことにどの様な価値観を持っているのか、興味や関心をどれだけ持っているのか、動機の強弱もまた存在しているといえる。
また、たとえ働くことが可能になっても、それは生活の一つが実現されたことにすぎず、さらに多くの参加制約が存在している。このように、一つの「参加」に対して、活動・心身機能が階層的につながり構成されていることが分かる。いずれにしろ、ICFでは、ICDIDHの障害概念を押し広げ、多様な障害構造について定義した。特に障害の各要素間の相互作用、相対的独自性について着目したことは大きいと考える。このようなICFの概念を実際に展開するのは、リハビリテーション理念が主になると考える。また、ICFの提唱によって、その理念もまた枠を押し広げて解釈することが必要となる。
次節において、このリハビリテーション理念について考察する。
第2節.リハビリテーション理念について
はじめに
障害構造には、リハビリテーション理念が背景にある。疾患によって引き起こされる様々な障害の克服、解消はリハビリテーションがこれまで引き受けてきたし、これからもその役割は重要である。しかし、一般にはリハビリテーション=訓練といった認識が強く、リハビリテーションとは、理学療法士、作業療法士が行うものと考えられている面もある。
しかしながら、これまでの論述で、障害者には様々な障害要素や構造があり、単にADLだけが障害として捉える事ではないことが明らかにされた。そして、これまでのリハビリテーション(=訓練)とは、ADLの回復に焦点が置かれてきた。しかし、本来のリハビリテーションの意味合いは、様々な職種が連携し、障害の克服・解消をとおして、全人間的な復権やその人らしい新しい人生を創造することを目指す3)ものといわれている。つまり、QOLの実現に焦点が置かれたトータルな理念といえる。
さらにQOLとは、主に「参加」における社会レベルのQOLが「人生の質」として一般に強調されている。しかし、心身機能・構造は生物レベルとしての「生命の質」、活動は個人レベルとしての「生活の質」があり、主観的体験としての「体験としての人生の質」などが相互に影響しあい、構成されており、それが全人間的なQOLを形作っているといえる。
一般に訓練といわれる病院内でのADLの回復に限定した(実際にはそれだけではないが)リハビリテーションを医学モデル、QOLの実現に向けた包括的なリハビリテーションをトータルリハビリテーション、あるいは生活者モデルとして区別し、障害構造を基にトータルリハビリテーションとしてどの様に各専門機関などがアプローチするのがのぞましいのかなどについて以下論じる。
・基底還元論から目的指向的アプローチへ
これまでの医学モデルにおけるリハビリテーションは、まず病気は根本的に治さなければならなく、対症療法ではいけないとする基底還元論4)的な考えが根強く、そうした考えに基づいてアプローチがなされてきた。例えば、精神障害者はまず、疾患としての精神病が治らなければ機能障害や活動制限が良くならない。そして活動制限が良くならない限り「働けない」「社会参加が出来ない」といった参加制約など解決できるはずがないという視点で図られてきた。それは、障害構造の一方的な流れ沿って一つ一つ解決していかないといけないというきわめて治療的なリハビリテーションであるといえる。
さらに各種機関や制度の連携については、これまで、それぞれの立場(Dr.Nrs,OT,PT,SWなど)の目標を並列的に述べて、それぞれの見方、立場、責任範囲から妥協的な結論に達することがチームワークの統一性であると見られていた。しかも、そのチームワークは「縦割り分業的」(上田*2〔2001,P.82〕)である。それは一見総合的であるが、障害の各レベル間の相互依存性を無視しているし、非常に狭い専門性に閉じこもりパターナリイズムに陥って障害者の自己決定を尊重することはあまりなかったといえる。しかし、障害構造は前述の通り、多様であり、重層的である。それぞれの職種がバラバラな目標から妥協的で単一な目的を設定してもリハビリテーションが成立することは難しい。しかも、トータル・リハビリテーション理念に基づけば、障害者の将来の人生の様々な可能性まで見通せるだけの包括的で広いビジョンを専門職が持つことによって、その専門性と障害者の自己決定権を両立させるだけの力量が必要である。そして、チームワークは障害者本位(自己決定権の尊重)の視点に立てば、どうしても分業ではなく協業によってチーム全体での共通の目標、基本方針、プログラムを十分に議論した上で、最も効果的に行うためにきめ細かい役割分担をしていくことが必要になる。
トータルリハビリテーション理念に基づいたアプローチとして上田敏が提唱する「目的指向的アプローチ」5)がある。以下、大まかに、目的指向的アプローチの流れを述べる。
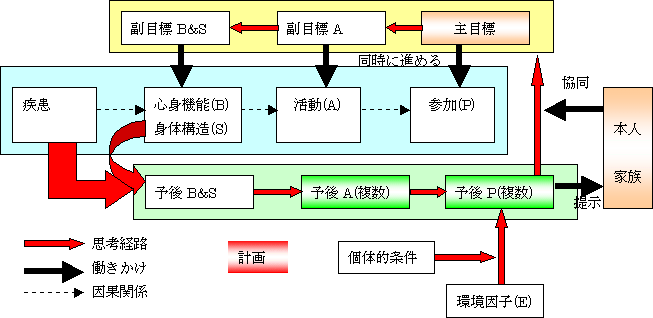
図4-3 目的指向的アプローチ 出所(上田*2,〔2001,P.83〕)
このアプローチは、参加のレベルが「主目標」となりどの様な人生を作るのかが最優先される。その主目標の設定から逆にそれを実現するために必要な活動レベルの副目標Aを決め、さらに機能障害レベルのB&Sの副目標を決めていく。それは基底還元論とは逆の方向性を取ることになる。
副目標Aについては、ADL,ASL,SS,VS,ASのうちでどれをどの様(場所、手順、用具など)に高めるのかなど具体的な一日単位の生活行為として設定されるし、B&Sについても同様である。また、主目標は最終目的ではなく、いわばその時点で最初に目指す山であり、第2,第3の主目標と続いていく。
予後の推測に関しては、B&Sの予後は疾患との関係で機能障害の回復と潜在的な健常機能の増大を視点にした予後を立てる。活動レベルでは、相対的独立の視点に立って、リハビリテーションを行うことによって「活動」レベルでのプラスの増大の予測をたてるこれは、副目標Aの具体的なプランとして複数たてられる。参加レベルでは、個体的条件や環境的条件から達成可能な最良の参加レベルでの予測をたてる。しかも、具体的に「どの様な生活をするのか」とデザインすることが必要で、それはそのまま主目標の「候補」となる。そしてここで重要なことは、この主目標と副目標Aの候補を本人や家族に提示し、説明し、選択してもらい確定する。この本人や家族が選択するということは、単にインフォームドコンセントではなく、協力関係の基で行われるインフォームド・コオポレーション(十分な説明を受けた上での協力関係)が採用されることである。
このように、一般的に認識されているリハビリテーション(医学モデル)は、トータルリハビリテーション理念のほんの一部であったといえる。そうした意味で、目的指向的アプローチは包括的な視点でチームワークの積極的で建設的な、そして支援者としての専門職の在り方を示しているといえる。
ただし、参照したモデル、特に図2,3は上田敏の理論からであり、その理論はどちらかといえば身体障害者を中心に視野が置かれているため、精神障害者において具体的に適用できるのか難しい面もあると考える。しかし、そのアプローチ〜参加制限の解消を第一にめざし、さらに障害構造の総合的分析によるQOLの実現に向けたチームワークの在り方などは、身体障害者のみならず精神障害者にも重要な示唆を与えている。
次節においてこれまでの論述を踏まえ、精神障害者の障害構造を適用し、その特色について論述する。
第3節.精神障害者の特色
はじめに
精神障害者は、疾患の治療を中心とした「病者」として長い間見られていた。また近年病院内において「障害」に焦点を当てた取り組み(リハビリテーション)が施されてきており、入院「患者」であっても「障害者」として捉えられているといった言説がある。このことは、時代と共にいくらか疾病と障害の区別が図られてはいたものの、まだまだ精神障害者は、精神病者と明確に分離されず、ひとくくりに入院患者として捉えられてきたといえる6)。このことについて、上田(1987,P.91)は「障害者と疾患者の曖昧さが混乱を招いている」と述べており、さらに精神障害者の呼称は「精神病という言葉のひびきの悪さ」を解消する事にも使用され、不快な言葉を別の言葉で取り替えるだけで不快さを取り除こうとするものがあることを指摘している。
以下、概括的に精神障害の特色について述べる。なお、精神障害は統合失調症、躁鬱などの気分障害、アルコール使用による精神及び行動の障害など多様にあることは、第1章(表1-8)において述べたとおりである。しかし、精神障害者福祉施策は主な対象を統合失調症に焦点を当てていること、入院患者の多くが統合失調症であることから、本論文では、統合失調症を精神障害として述べることとする。
第1項.精神障害者の特色
精神障害者は他の障害者と比べ、前述のとおり疾患者(病者)なのか障害者なのか曖昧な点がある。現在も精神症状などは機能障害なのか疾病なのかどうか不分明であり、さらに精神症状は、個人差が大きいこと。他の障害に比べ、波(前駆期、急性期、安定期など)があり介入の判断が難しいこと。再発を繰り返すことによって機能が徐々に低下していき、回復が困難(陰性反応が増加し、陽性反応が持続するなど)になり易いこと。また、見た目やIQなどによって測定ができず、精神症状などに苦しんでいても一見すると普通に見えること。あるいは治療によって、精神症状が消失あるいは残っていたとしてもまったく普通と変わらない状態になることなどが他の障害と大きく違う特徴である。
しかしながら、病者と障害者の区別はリハビリテーション理念に従えば、生活上の困難性の克服を目指した取り組みとして捉えることが障害者であり、疾病の原因などの減少を目指した取り組みとしての視点が病者であると考える。疾病と障害が共存しているのは他の障害でも同じであるが、前述の理由から精神障害は、障害者として固定的に位置づけることが困難であることが大きな特色といえる。
ICFの障害構造を精神障害者に適用したとき、他の身体疾患に比べて目立って困難ないくつかの特徴がある。