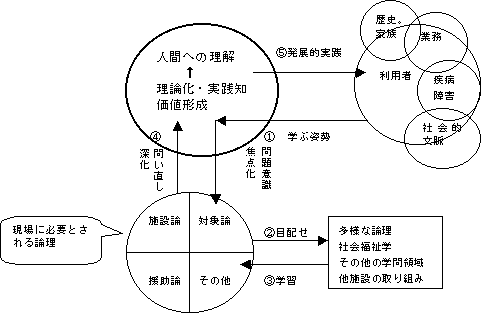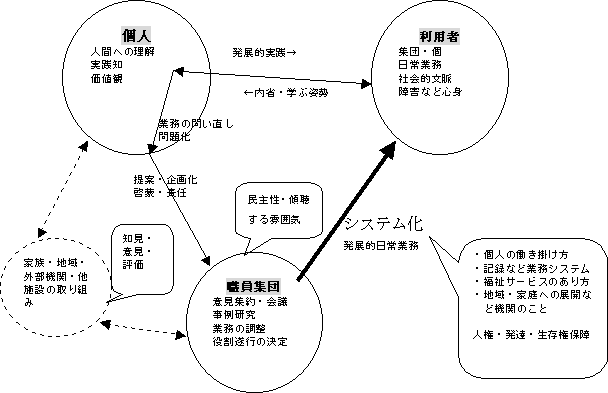第8章 現場の専門性
はじめに
これまで(第2部)は、社会福祉、福祉施設を巡る専門性の所在や存在の根拠についてと個人の専門職性についても述べてきた。また、個人の専門職性を身につけるとは、利用者から学ぶ態度で、自分なりに人間理解への道筋を探し当てることが大事であると述べた。では、具体的にどのような方法で、学んでいけばよいのだろうか。
本章では、福祉施設の現場についてと個人の専門職性の獲得について、具体的に述べる。そして、最後に、個人と集団がどのような形で関わり、現場が成り立っているかを論じる。
第1節 現場について
はじめに
現場に勤めていると、毎日の業務が、同じ作業、同じ内容で繰り返しに映る。この日常について論じ、日常業務に潜む現場職員の専門性について考察し、日常的に利用者と職員との間に立ち現れる対人援助の奥深さを第1部で論じた感情労働の側面から考察する。
第1項 日常業務について
1.日常とは何か
日常といえば普通、当たり前のこと、決まり切ったこと、なれ親しまれたもの、あるいは、よほどのことがない限り揺らぎもしない安定したもの、けれども何となくつまらない陳腐なものであると捉えられる(鷲田〔1997,PP.24-25〕)。しかし、日常=当たり前のこと(自明性)とは何かと説明することは難しい。例えば、日常の反対は、非日常であるが、「非日常性の最たるものである死も、葬儀や法要、あるいはその準備を通して、我々がいつからともなく親しんできた日常世界に吸収される」1。言い換えると、日常は、死や天災など日常あり得ないと思えることが起こっても、時間が経つにつれ、慣れ、その出来事を忘れる等、いつの間にか「何もかも元通り」と思うようになる。
例えば、新しい何かをチャレンジしているとき、それは自分にとって新鮮な出来事に思え、日常を忘れ夢中になる。しかし、時間が経てば、その出来事はいつの間にかこなす作業と化す。あるいは、旅行に行き、いつもの日常から一瞬離れても帰ればすぐに記憶だけになり、日常の覆われる。だから、あらゆる主題(出来事)は日常によって覆われるがゆえに、日常の中(形成している要素)や裏(本質など)に何があるのか説明することは難しい。
ところで、個人の現在の行為選択、未来への予測は、これまで自分が経験してきた過去の行動、認識を主観的な論理でもって体系的に構成しているからこそ成り立つ2(加茂〔2003,P.6〕)。そして、過去の選択を反省し、論理的に体系付け、現在に結びつけることができるのは、日常という先行する基盤・世界があるから可能なのである(鷲田〔1997,P.40〕)。
例えば、身近な人の死という衝撃的な出来事があっても、「葬儀」や「法要」といったすでに歴史や共同体の中で、「妥当なもの」として認められた事柄・思想・概念・伝統〜生活世界3があるからこそ、死の悲しみを安定的に処理することができる(鷲田〔1997,P.45〕)。このように考えると、日常とは、個人の経験や判断に「意味」を与え、その人の現実を構成させる(自己を定立させる)先行的・歴史的な地盤である。
しかし、その地盤(日常)は、固定的なもの、変化のないものではない。日常は多様な概念・言説・経験則・歴史などを絶えずダイナミックに編成し、作り替えていく、終わることのない運動体である。「それは、新奇なもの、異質的なもののうちへも増殖し、それらを併合しながら絶えず変形していく可塑的な運動」(鷲田〔1997,P.49〕)である。
そのような意味で、日常は安定的な雰囲気に包まれながらも、多元的な領域を雑多なまま混在させている。そして、それぞれの領域の知識は決して統一的でもないし、部分的にのみ明晰ではあるが、いつも何らかの矛盾を含んでいる。日常とはその意味で、「その様々な構成契機がある程度、つまり、相対的に一貫して編成された緩いシステム」(鷲田〔1997,P.65〕)である。
個人は、この緩いシステムである日常を自分なりに解釈を施し、自らの現実を構成し直して生きている。それは、自分は他者(一人〜多数、社会)をどう把握するか。そして、他者は自分をいかに認識するのかという自己解釈を通して自分を位置づける4。ここで言う日常は、自分自身が現実で生きる上での環境や社会状況となる。そこには、ある一定の大いなる物語(貨幣・資本・イデオロギー・伝統など)が存在している。しかし、日常はそれ以上に多元的で矛盾を含んでいる。だから、同じような環境にいて、同じように振る舞っていても、現実の構成の仕方が人によって違い、感情・知覚・行為の選択のプロセスは人それぞれである。
繰り返しになるが、日常と日常に生きる人々を語る場合、何か退屈なこと、問題意識が無い没個性的なことと捉えられる。しかし、日常は同じようなことの繰り返しに見えながら、実際には絶えず変化している。「日常のおける自分の在りよう」を自覚的に捉えることはできないが、多様な言説やまだ知らない先行経験が日常に含まれていることを意識するならば、考えることは常に日常の中にあり、解釈の仕方によっては、自分の生き方を変化させることは可能である5。
2.現場の専門性
1のような視点に立つなら「現場の仕事がルーティンワーク化した進歩のない、決まりきった退屈な仕事であると日常性の意味と共に簡単に片づけるべきではない」(須藤〔2002,P.29〕)ことは分かる。しかし、日常には様々なシステムがあり常に可変しているが分かっていても、やはり、毎日は同じリズムや内容に映る。さらに、日常がもつ歴史的・経験的先行性を自分なりに解釈し、自己認識を改変し、「自分自身の日常」を変えられると分かっていても、実際には何一つ変化していない気がする。しかし、それでもやはり、我々は日常業務の中で、何かを考え、一瞬一瞬に判断を下しては忘れ、経験を積み重ねている。この経験がどのようなものか、説明しようとしてもうまくできないところに日常としての現場があり、そして援助者がいる。
自分が行っている仕事(行為)とは何かを説明する場合、しばしば、自分がこれまで学んだ「一理論」に裏付けられたと思える「実践」を持ち出すことがある。しかし、理論とは「現場の日常性の中から意図的に、客観的に、理論化できるもの、すなわち取り扱いやすい部分だけを取り出した」6(須藤〔2002,P.31〕)ものである。ある面では、自分の行いをうまく説明はできるかもしれない。しかし、理論が説明できる実践は日常業務の中では限局的なものである。よって、日常業務の行為は、理論や説明できる実践とは別の仕方で積み重ねられている(横田〔1999〕)。
むしろ現場は専門的な技術や理論というより、常識的な規範を大切にする。そして、この日常の行為を成立させているのは、「暗黙知」と言われるものである。暗黙知とは「記述しようとすると戸惑ったり、あるいは明らかに不適切な記述をしてしまう」(須藤〔2002,P.49〕)ものである。いずれにしろ援助者は暗黙知に基づいて対象の認識や判断、技能、振る舞いを無数にしている。つまり、暗黙知は日常と似て、なんとなく自分の行為や認識を裏付ける何かである。
よって、自分の仕事を深めようとする場合、援助者は適当な理論仮説を持ち出し、安易に自分の行為を理由づけてはいけない。暗黙知によって行っている、自らの認識・振る舞いを振り返り、経験を読み解くことである7。それは、自分の内面の声に耳を澄まし、利用者との関係(権力・制度・コミュニケーション等)、ある場面での対応の反芻と反省、業務内容とその意味への考察など、ありとあらゆる日常業務を問い直すことである。
とはいえ、問い直したところで日常は破綻しないし、一足飛びに劇的な変化があるわけでもない。しかし、その問い直す作業は、利用者との関わりは、単に「問題の解決」という皮相なものではないことに気づいていく。そして、その問い直しは、援助者の日常にもはね返り、自分(援助者)の価値や生活、役割を静かに、不断に終わり無く浸食する(加茂〔2003,P.209〕)8。それは、日常の中にこそ自分も現場も豊かになる可能性を秘めている事を教えてくれる。
第2項 感情労働と専門性について
1.感情労働について
福祉従事者は常に利用者と対面的に関わるが故に、自己の感情をコントロールし、利用者に対し細やかな配慮を示すことが要請される。こうした感情の管理や感情を商業的利用する労働を「感情労働」と呼ぶ(渋谷〔2003,P.29〕)。
福祉従事者の感情労働の特質は、「愛情」が強調されやすい(松川〔2005〕)。あるいは利用者を「受容」や「共感」するとか「対等な立場」など、心のありようと共にそのように振る舞うことが要請される。言い換えると、利用者に対して専門職としての適切な感情表現や態度がとれるかが職業の熟練度として一つの指標になる。こうした「福祉職」に求められる感情や態度のありようの枠組みを「感情規則」という。
福祉職ではこうした感情規則が多数に存在する。中には、人間のあらゆる存在をも包括して接しないといけないかのような言説がある。また、言い過ぎかも知れないが、福祉従事者の専門性を問うもののほとんどが感情規則のバリエーションと考えても過言ではない。先に述べた受容や共感のほか、のぞましい態度や感情のコントロールの仕方などは理論(特に対人援助技術論)の数だけ多様に生み出されている9。
のぞましい態度や心のありようは、基本のようなものがあるかに見える。しかし、感情規則は、時代と共に変遷し、多様な言説や文脈がひしめき合っている。だから、これでいいという規則は常に存在しないし、説明はしきれない。せいぜい、「代表的には…」と説明できる程度である。そして、感情規則には正解も決定版も存在しない(尾崎〔1997〕)。なぜなら、援助者は常に流動的で不確かな環境の中で、複雑で多様な問題を抱えた利用者を相手に一瞬一瞬の判断をしているからである。だから、その時の対応が、のぞましい態度を取っていたのかと反芻しても確証を得ることは難しい(尾崎〔1997〕)。
それでも、感情規則は、日常業務に潜み、あるいは暗黙に、「社会福祉で働く」自分の心身の細部へ働きかける。逆に言うと、感情規則(のぞましい態度や情動)に照らし合わせて反省をする態度にこそ、福祉労働者としての主体性がある10。そして、この感情規則を深く理解(探求)できるかが専門職としての成長につながると考えられている(松川〔2005〕)。
たしかに、人間は職業によって規定されることが多い。また、人は仕事を通じて自分の人生や価値観を形成する側面がある。しかし、感情労働は、社会福祉に限ってのことではない。客と対面をするあらゆるサービス業の中にあるし、最近では工業とか直接客と対面しない製造業分野でも見られる11。一義的に、感情労働(あるいは感情規則)は、あくまでも職業上の「商業的利用」のために形作られていることを確認しておく。
2.現場における感情労働と専門性の関係
施設業務は、利用者に言葉が無かろうが、身振り手振りすら困難であろうと12、長期間・持続的に感情の交流が行われる。そのため、職員として(感情規則にもとづく)ふさわしい態度をとり続けることがより求められる(松川〔2005〕)。よって、感情規則に基づく商業的な振る舞い(演技)に窮屈さを感じ、ストレスを感じることがある(松川〔2005〕)。また、利用者と毎日顔を合わせるために、相手との関係の距離を測り損ねると、自分も相手も混乱し、職務として機能できなくなる13。しかし、この不断の感情交流・利用者との関係から生まれる葛藤や矛盾の悩まされながら、自分なりにその葛藤などを吟味することが専門職として向上する契機になるとされる。尾崎(1999:2002)はそれを「ゆらぎ」と表現する。
「ゆらぎ」の要素やゆらぐ結果生じる現場職員の専門職性向上の道筋は多様にある。詳細は、尾崎(1999:2002)を参照することとして、本論では利用者との関係でゆらぐ〜悩まされるものの例を示せば、
- 施設に勤めていると度々利用者から「施設を出て家に帰りたい」「どうして施設に入ったのか」と振り絞るような声で言われることがある。施設にいることは、本人も了承していることである。しかし、時々問わずにはいられない本人の気持ちを職員が斟酌すれば、答えることがためらわれる。そのとき、職員も利用者も立ち止まる。
- 家族の内紛や親の生活が苦しいことを利用者(子ども)を盾に何とかしてほしいと言われることがある。また、施設に我が子(利用者)を預けることに対しての複雑な感情をぶつけられる。そして施設のサービスが悪いなど注文を付けたり、自分の思い通りのようにやってもらうことを強く要求する。さらには子どもが元気になるには親が元気ではないといけない。だから親のケアもしなければならないと言われる14。結局、家族の調整・ケアも引き受けるも、失敗すれば、家族と利用者の召使いあるいはイエスマンになる。
- 利用者に過度に依存されたり逆にまったく原因が分からないのに拒否されたりと感情移入と逆感情移入が渾然一体となる。このような対人間の葛藤は枚挙にいとまがない15。
かといって、1.には業務の範囲を明確に示し、そのような質問に答える必要がないと話す。2.には家族のこと施設に持ち込まないで欲しいときっぱり言う。3.には甘えないでほしいと突き放す。…こうした態度は社会福祉労働としてのぞましくない、専門的ではないとされる。ここに、労働から感情をクールに切り離せない側面〜感情労働がある。
1〜3にはそれぞれ感情規則に基づいた商業的で模範的な振る舞いが一応用意されている(傾聴・受容・共感にふさわしい笑顔・言葉がけなど)。しかし、特に1のような問いは、感情規則では括れない要素を見いだすことができる。あるいは、個別性を考慮したとしても、その問いそのものが発する背景には模範的な答えが存在しない。
知的障害児施設に限って言えば、どうして施設に入ったのかは、本人はなんとなく分かっている。しかし、「どうして施設に入ったか」と振り絞るように援助者に訴えるその背景には、ここに居続ける見通しのなさや、普通に暮らせない悲しさややるせなさ、自分一人の力ではどうしようもないと思う無力感が渦巻いている。
利用者は日常的には施設で生活をしようと前向きに考えている。しかも、親がなかなか会えないことも分かっている。けれども、いくら虐待をしたとか、養育放棄をしたと分かっていても、親への思慕がわき上がる。そのとき、つい「施設を出て家に帰りたい」と言ってしまう。
こうしたことを思い描くと、援助者が客観的に本人へ、なぜ施設に入ったのか説明をしたところでその言葉はむなしい。そして、この発せられた言葉の後ろには、親の生活困難性を生み出す社会、障害児を生んだことによる様々な苦労、施設の社会的統制の機能と保護の役割からくる限界。子が親を思う気持ちなど、考えるべきことが多様にある。もちろん、これらのことに、評論家然として講釈をたれることは簡単である。しかしその言葉は軽い。
結局、援助者ができることは、利用者に寄り添って言葉に耳を傾け、少しだけ勇気づけるような言葉を探すことではないだろうか。もちろん、その言葉は「がんばれ」でも「元気になれ」と言って終わりではない。もし言葉を探して、見つからない場合は、下手に言葉を紡がない方がよい。肝腎なことは、その問いを発する利用者の気持ちを受け止めることである。そして、その言葉の意味を吟味することである。それは、感情規則で決められは模範的態度を取ることを越えて、援助者の役割や存在理由などを深く考える契機になる。
1.のみならず、2.も3.も突き詰めると実は模範的な答えは用意されていないのかもしれない。その発生した対人間の葛藤や衝突には、感情とは別の所に背景があるかも知れない。あるいは、答えようのないことが含まれていて、答えた途端、何か空々しいものになる場合もある。さらに、対人間の距離の取り方も答えはない。上述のこととやや矛盾するも、例えば、2の場合も、家族の葛藤から距離をとり、突き放すことで、家族と職員の関係が良くなる場合がある。さらに、笑顔や沈痛な面もちなど感情豊かに、受容や共感をしながら熱意を持ってじっくり話を聞くよりも、利用者によっては深く踏み込んでもらわずに流して聞いてほしいだけの場合もある16。
それをケースバイケースとかその職員の個性とか経験の積み重ねによって身に付くと言ってしまえばそれまでである。しかし、経験とは、体験をいかに考えたのかを検証する中で形成される。そして、対人間の葛藤という体験−「ゆらぎ」と丁寧に向き合い、検証し、反復することで経験は再生産され、新たな認識や発想を生み出すからである(尾崎〔1999,P.8〕)。葛藤や矛盾に出会うと、職員は、その時無力感を味わい、挫折感を抱くなど苦痛である。しかし、葛藤や矛盾に逃げず向き合う態度は、利用者との関係性を育て、深める。そして、それは援助・支援として「どのような助言をいかに伝えるのか、いかなるサービスをどのように提供するかは、育ちつつある関わりの中ではじめて答えを見いだすことができる」(尾崎〔1999,P.293〕)。新たな認識や発想は結局、職員自身と利用者への理解を豊かにする出発点であり、援助における創意工夫を生み出す基礎を作る17。
最後に、感情規則に照らし合わせ、自分の行為を反省することで向上した専門性は結局、感情規則の増強(商業的・模範的態度のレパートリーを増やすこと)でしかないのではないかという疑問が残る。しかし、社会福祉は職業として成立している以上、感情規則からは逃れられない。むしろ、感情規則を意識しないがゆえに、利用者の全てを受容したり理解しないといけないと錯覚し、利用者との距離感や自分が果たすべき役割を見失うのではないだろうか。あるいは、研修とかセミナーや学校で、表層的な模範的態度を学ぶ。しかし現実には葛藤や矛盾が渦巻いていて、学んだとおりにできない自分に苛立っているにすぎないのではないだろうか。
援助者は、まず目の前の矛盾や葛藤を感じ、向き合うことからはじめないといけない。その上で、その時、どうすればよいかを感情規則に照らし合わせ、自分で考えないといけない。場合によっては、社会に対する学習などを通して葛藤や矛盾を解きほぐしていく必要がある。その道のりは長く、答えはない。体験が経験になり、積み重ねられ、反芻され、少しずつ熟成していくのである。
とすれば、現実に生起する葛藤や矛盾が「ゆらぎ」ならば、感情規則は援助者の「ゆるがない」根拠の一つと言える。つまり感情規則は、援助者の判断や思考の源泉の一つとも言える。
第3項 まとめ
現場の業務の背景に潜む日常の豊かさについて論じ、感情労働の内実について論じてきた。現場には矛盾や葛藤がひしめいており、さらに問題が山積みである。ここで述べたかったことは、解釈の仕方で日常業務をいくらでも深めることができること。また、感情労働はたしかにやっかいであるが、考えようによっては自分自身の仕事を豊かにしてくれることである。
日常の多様さには矛盾や答えのない問いが含まれている。だからこそ、利用者との感情交流の中に曖昧さや深さがある。その曖昧さを簡単に決めつけず、じっくり考えられるか。感情交流の襞に踏み入っていけるかどうか。それは自分にとっての日常業務とはなにか、利用者への関わりを深めていくことにつながっている。
第2節 個人の専門性獲得について
感情労働の豊かさや日常の複雑さを知っていても、実際にそれをどう解釈したらいのか分からない。資格取得やセミナーへの参加は専門職確立の自信につながるが、そこから先、どう勉強すれよいか分からない人が案外多い。本論では、専門性を確立するためには自分なりの理論を形成することが大切だと述べている。しかし、どうしたら自分なりの理論形成ができるのか。本節ではこうしたことを念頭に置きながら、モデルを提示する。
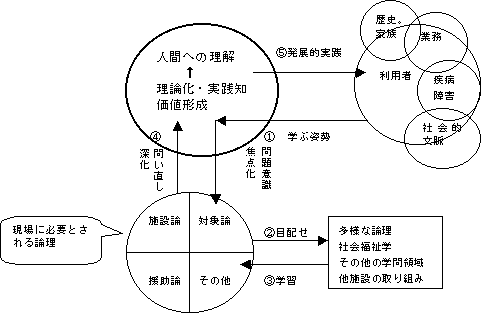
図2-2 個人の専門性取得のプロセス
第1項 1.学ぶ姿勢、問題意識、焦点化
・学ぶことの難しさ
第7章で、利用者から学ぶ姿勢について等を述べてきた。しかし、実際には何をどう学んだらよいのか分からないのではないだろうか。じっくり観察してとか、問題意識を持ってと言うのは簡単であるが行うのは難しい。あるいは、日常業務を問い直すこともなかなかできることではない。また、社会概念まで広げて一般論を自分なりの論理を把持することが重要であると述べたが、どこからはじめて良いか分からない。
筆者の経験の範囲であるが、高校や大学では自分で課題を見つけて何かを掘り下げるという学習があまりされない。常に誰かに与えられ、その範囲で調べる程度である。だから、テーマを自分なりに見いだせないし、何をどう調べたらよいのかが分からない。社会人になっても、セミナーや研修で、あるいは資格取得の勉強をするが、それもまた誰かに与えられた範囲に過ぎない。
あるいは施設職員の中で活字を読むのは辛いし、専門書に拒絶反応を示すいわゆる活字嫌いが案外多い。その人達も、本当は、学ぶことは大切だし、勉強をしたいと思っている。その反面、1冊読んだ程度では仕事にも役に立たないし、何もならないとも思っている。
まずは、こうした活字嫌いの人は、福祉に関する何かを読んで、興味を持つことから始める必要がある。それには、福祉をテーマにした漫画でも良い。あるいは、新聞の福祉関連記事を読むだけでも良い。とりあえず、活字に目を通すことから始める必要があろう。
蛇足であるが、反対に、勉強をしている人が、こうした活字嫌いの人たちを見下し、相手にしないことは簡単である。しかし、同じ職場で働く仲間として、その態度はどうなのか。勉強をしたいけどやり方が分からない人にどう教えるのか。あるいは、本を勧める際のセレクトや学ぶことの大切さや面白さなど、利用者に学ぶ態度と同じくらい相手の立場になる必要がある。一緒に学び合う仲間を増やすこともまた勉強している人の役割だと思うが、どうだろうか。
・学ぶ方法について
何をどう学んだらよいかであるが、その一つとして、日常業務の一こまを記録として書き留める方法がある(久保〔2004〕)。日常業務で気がついたこと、心に引っかかった利用者との日常の会話、日常行動を簡単でも良いから書きとどめる18。例えば、関わりに失敗したこと。なぜか成功したこと。あるいは、日常業務で巻き込まれている葛藤や理不尽な言いがかりなどを丁寧に掘り返していく19。書きとどめる行為は、「スローモーションの映画を見るようにゆっくりと振り返らなければ、なかなか心に留まらない」(久保〔2004,P.163〕)。いずれにしろ、書き留めることを糸口に、なぜ心に引っかかったのかを考える。引っかかりは、利用者の障害特性のせいだったのか、あるいは自分の行為が引き起こした反応だったのかを考えていく。時には、その記録された利用者の社会背景に興味が拡がり、社会への学習を始まるかも知れない。その積み重ねが、施設・援助者の役割や利用者への認識が深まっていく。こうした日常業務の記述化は地道で目に見えにくい。しかし、どんなに稚拙でも自分なりに日常を書きとどめ、それに対し丁寧に調べてていく行為は、学習の第一歩になる。
・問題意識・焦点化について
問題意識や焦点化では、筆者は【施設論】【対象論】【援助論】【その他】と枠組みを設定した。日常を記録するといっても、対象をどう見ているのか、自分はどう振る舞うべきなのか、家族や社会背景、施設業務のありかたなど複合的に交差している。そのため、枠組みがないと何をどの範囲で考えたらよいか分からなくなる。この枠組みは便宜上であるが、筆者は、現場(自分)に取って必要な論理のカテゴリーと考える20。このように自分なりに枠組みに照らし合わせて、いま心に引っかかる利用者との関わりを考えると、何が問題(興味)としているのか整理されると考える。
第2項 2.目配せ→3.学習について
【現場に必要とされる論理】は、自分なりに【施設論】として、あるいは【対象論】として編成し把持することである。そして、その目的は日常の関わりにある背景を読み解くことにある。
例えば、いま、自閉症とのコミュニケーションがとれないことに困っているとした場合、ただ会話のズレを取り上げ、そのまま記述してもあまり意味はない。この会話のズレの中にある原因を探ることである。例えば、自閉症の障害理解が足りないためなのか。自閉症に対する偏見差別からくる援助者の振るまいが問題なのか。あるいは、適切な関わり方のノウハウが施設にないからなのかを推測することである。
仮に、自分自身の障害理解が不足していることが特に問題だとして、学習をはじめたとする。そして、障害特性について本一冊を読めばそれなりに学習になる。しかし、できれば多くの本を読み、多くの意見に目配せをした方がよい。なぜなら、障害を理解すると言っても、様々な解釈の仕方(医学的・心理学的・社会学的見地など)のほか、ふさわしいコミュニケーションの具体的な方法(治療・療育・訓練・マニュアル)など学ぶことがある。
本論に即して言えば、例えば【施設論】は、昨今、脱施設と盛んに言われているが、本当に施設は不要なのかという問題意識から出発している。それを読み解くためには、制度の他に、施設を取り巻く世相の変化、施設を根拠づける思想や批判などに目配せをした。とはいえ、本論の【施設論】で使用した多様な言説は、その時々で変化するし、構成の仕方でまったく違う結論になる。さらに施設論は脱施設だけではなく多様な切り口があるし、自分が知らない事がたくさんある。
しかし、現場に必要な論理を身につけるには、何か問題意識や調べたい興味〜指向性が無いと「あれもこれも」となり、ただ知識を詰め込むだけになる。そのため、指向性は必要であり、それは常に素朴な疑問〜日常ふと思うことから出発する。そして、少しでもその疑問や問題に対して見通しを持てるように学習を積み重ねることである。その学習の積み重ねは、論文やレポートなど書く行為が効果的である。しかし、書く行為は読む以上に訓練が必要であり、なかなかできることでもない。よって、ある問題意識・興味から一冊本を読むとか、気になっていることがテレビで放映されていて観て、感じたところはじめるだけでも良いと考える。
まずは、素朴な疑問を持ち、その解消を目指して持続的に調べ、自分なりの見通し(言葉)をもつ所から学習が始まる。
第3項 4.問い直し・深化
3.によって学習したことは、日常の関わりに解釈を与える。分かりやすい例で言うと、障害理解のためにした勉強は、日常の関わりで利用者への解釈として働く(障害にふさわしい関わり方など)。また、中には、直接業務に関わりにないことも学習に含まれるが、そうしたものを引っくるめて自分が施設現場で働く意味や価値に影響を与える。こうした学習の積み重ねから、いま自分が何をしているのか、どうするべきなのかを問い直すようになる。そして、利用者への認識や日々の実践が深まっていく。
ところで、制度を事細かに調べて、どのように運用したら利用者も施設も利益が上がるかに焦点が行きすぎている人を時折見かける21。確かに、制度に精通することは悪いことではない。しかし、制度を適切にマッチングすれば利用者の問題は解決すると考えるのは早急すぎる。あるいは、こうすることが利用者にとって良いことだと決めつける危険性がある。
まずは、利用者をどう観るのか。翻って、自分はどう振る舞うべきなのかを考えるべきである。そのためには、迂遠であっても、1から3までの地道な学習が必要である。もし、地道な学習をせずに、うまい制度運用=問題解決と考えるようであれば、それは援助者の独善でしかない。
更に3で構成した【現場に必要とされる論理】は常に作り替えられ、多様な論理に結びついて深められていく。例えば、障害理解の学習は、利用者への関わり方を変化させる。と同時に、その変化が本当に良い関わりなのかを吟味し始める。そして、違った言説へ目配せをしていく。その結果、より障害理解の学習は深まり、違った関わり方へ進めることができるようになる。さらに同じ障害理解でも、例えば、【対象論】(認識)だけではなく、【援助論】(方法)や【施設論】(業務)の方面で考察を進めていった場合、それらを加味することでより繊細な振る舞いや具体的なサービスの提供へ見通しが持てるようになる。つまり、学習の深化と自分の行為や認識の深化は常に相互作用にある。
第4項 5.発展的実践
日常の関わりでの「ゆらぎ」(対人間の葛藤や衝突)は学習への動機付けとして強い作用を及ぼす。しかし、それだけではなく、むしろ何気ない日常行為の中で問うことはたくさんある。その問いに丁寧に考えることが大切である。考えることは自分の日常の関わり方を少しずつ変えていく。それは結局1.へとつながり、絶えず自分自身に問いが返っていく。そしていつの間にか、何も考えていなかった頃、あるいは、考えはじめた頃に比べると、自分の振る舞いや認識は深まっている。つまり、実践は発展していく。
さらに、日々の実践には、画一的でも固定的なものが無い。それでも関わりの根幹には「福祉職として適っているのか」を据えて考えることが大事である。でなければ、専門職としての自己を定立できない。福祉職として適っているかどうかを考えるには、3.のような学習が必要になる。そして、学習と4.の問い直しを通して、自分独自のスタイルを確立していく。
自分独自のスタイルを獲得しようとする思考や実践の試行錯誤は、ただ施設業務のメニューをこなす従属的な実践から、自律的で創造的な実践に変化させる。従属的か自律的かは、実際の業務では傍目には違いがないかのよう映ることがある。しかし、何かに興味を持って学習をしながら業務を行っているのと、そうでないのではやはり違う。さらに、福祉職に適った振る舞いとは何かと模索して利用者と接しているのと、無意識に何も考えずに接しているのでは違いがある。それは、小さなことかも知れないが、そこにこそ、個人の専門性がある。
次に、こうした個人の専門性獲得のプロセスを前提に、施設が発展的実践を行うにはどうしたらよいかをモデルを提示して述べる。
第3節 組織としての専門性について
前節では、自主学習や利用者への観察を通して自己のスタイルを確立していくことを主眼に論じた。しかし、福祉施設の業務はチームワークを中心としたものである。よって、自分のスタイルをチームワークの中に組み込まないと意味をなさない。では、どのような方法で組み込めばよいのだろうか。これまでの論述を踏まえながらモデルを提示し、説明を加える。
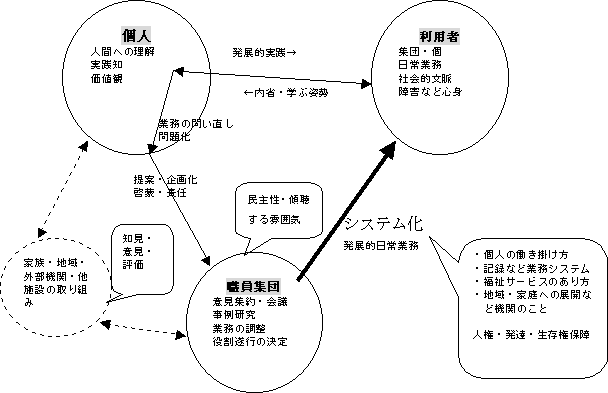
図2-3 チームワークによる発展的業務のプロセス
第1項 利用者と個人
個人の学習や利用者から学ぶ態度で自己の振る舞いを変えていく〜自己研鑽による専門性獲得については、前節で述べたとおりである。では、自分が考えてきたことや認識、援助の方法などを具体的な業務の中でいかに発揮できるのか。それは、今行われている業務の「当たり前」を疑い、「本当にこれでいいのか」、「別の方法はないのか」を、まず小さな事から考えることである(久田〔2004,P.122〕)。また、障害者との関わり方や認識の仕方は、自分の振る舞いから気づくこともあるが、大抵は、他の職員の行いから気づくことが多い。
小さな視点からは、例えば、他の職員が、障害の特性に合わせた適切なコミュニケーションがとれていないと感じるときがある。少し障害理解の学習をすれば気をつけるようなことも、その職員が学習をしないばかりに、利用者を無駄に怒らせ、苛立たせている場合がある。あるいは、人間の理解への洞察が足りずに、高圧的に福祉サービスを押しつけている人から反面教師として学ぶところが多い。その一方で、自分自身の学習不足を他の職員から学ぶこともある。その時、その職員の良いところをまね、その人の価値観やコツを吟味する中で自分自身を問い直すことができる。
大きな視点では、施設は職員配置の規定や勤務形態によって、常に人手不足になりがちである。その一方で、利用者の個別性の尊重、生活の質向上のためにサービスの多様化と豊富化が求められている。その結果、ただでさえ人手不足なのに、サービスが「あれもこれも」となり、過重な業務をこなさないといけない。そのため、常に忙しく動き回らざるをえず、利用者の話をゆっくり聞くとか本人のささやかな要望が実現できなくなっている。
よって、利用者にとって何が大切なのかを考えるには、まず自分の実践知・価値観の形成が必要である。その上で、業務自体を具体的に見直していくことが求められる。そして、具体的実現の知見として、文献・研修の自己研鑽も大切だが、他の職員から学ぶことも多い。さらに、大きな視点として他施設の取り組みや家族からの要望から学べるといえる。
第2項 個人と集団の関係
集団とは、現場職員全員という意味ではない。2〜3人の小集団で事例研究をしたり、勉強会を開くことも集団として捉えている。第1節でも述べたが、現場職員は専門文献を読んだり、自主学習をしている人が少ない。問題意識を持っていても、不平不満としては言えるが、具体的なビジョンはなく、あっても場当たり的なものが多い。さらに、過重な労働内容や配置の分散化によって話し合える場がないという問題がある22。
そのため、まずもって必要なのは、日常業務や利用者のことを語り合える仲間を作ることである。そして、お互いの話を傾聴しあえる関係を作ることである。それは、「一人で悩み考えるよりも二人で悩み考えた方が、よりより対応ができるかも知れない。やる気ができるかも知れないといった発想」(副田〔2003,P.102〕)のもとで行われる。結果、自分が思ってもみなかった利用者への視点や仕事のあり方に気づく。つまり、集団(外)からの働きかけによって、個人の主体性や潜勢力が触発されるといえる(中井〔1998,PP.244-242〕)。とはいえ、話し合える仲間だけでは施設内の業務そのものを見直し、具体化していくことは難しい。そのためには、小集団から始まっても最終的には、施設全体で傾聴する雰囲気を形成していかないといけない。それは「会議を単に上意下達の事務連絡からケーススタディに変革」(中井〔1998,P.241〕)することである。言い換えると、施設長や管理部門だけで施設業務が決められるのではなく、現場職員が自らの手で業務を作り上げていくことである。それは、事例研究のみならず、業務の細かい気づきから大きな事までも「何でも話し合える」ことが重要である。こうした話し合える雰囲気のある職場では、自分たちの専門職性を高めていくことができる。なぜなら、
- 問題意識を持って発言することは、発言に対して責任を持つことになる。それは、自分自身を奮い立たせることになる。
- 小集団で話し合った問題意識を具体的に提案するために、皆が分かるように企画化することが大切である。相手に、「これくらいはできそうだ」と思わせることで、少しずつ業務を改善していく。それは、自己のプレゼンテーション力が養成される。
- 事例研究は、管理職からの命令ではなく、自発的に行うことで、自分自身の課題の明確化や他の職員への啓蒙や問題意識を触発させる。なお、事例研究の仕方については、たくさんの文献が出ているので参照のこと23。いずれにしろ、事例研究の良さは、まずもって利用者の状況や問題解決の方策について皆で考える契機を作ることである(相澤〔2005〕)。
- 職員間のチームワークもさることながら、外部機関の評価や保護者、地域、他施設の取り組みなど、いわゆる外からの働き掛けも業務内容を見直す契機となる。職員間の話し合いだけでは、自分たちの持つ権力性に気づきにくい。外からの働きかけは、職員の主体性の健全化が図られる(金子〔2000〕)。あくまでも利用者の人権尊重など援助原理を根底に据える取り組みを行うことを確認する。
- 最後に、蛇足であるが、会議などで承認されたこと、決められたことをしっかりと履行する意識が必要である。中には、発言をせず、皆で決めたことを陰で批判し、業務の遅滞や低下を促進させる職員がいる24。そして、えてして、足の引っ張る人は仲間を作る傾向がある。このような逆の意味での協働はあってはいけない。むしろ、こうした陰の批判者を糾弾し、許してはいけない。
いずれにしろ、こうした発言・提案・企画化は面倒である。さらに、抑圧的な職場環境ではなおさらエネルギーを要する。しかし、こうした主体的に何かをなそうとする態度こそ、専門性の獲得と向上それによる自分自身の自律性が養われると言える。
第3項 集団から利用者へ
最後に、会議で決められたことなどは、利用者にシステムとして働きかけることになる。当然、それは個人の援助者の働きかけにも影響を及ぼす。そして、一旦みんなで決めたことを実践する中での自己の創意工夫が業務を問い直し、集団へ問題提起・話し合いとして循環される。
皆での話し合いは、利用者への障害理解や振る舞い方の他、記録の取り方や家族や地域との関わり方まで広汎に及ぶ。それらは全て、質の良いサービスの提供に結びついている。そして、発展的日常業務は、常に利用者への発達権・生存権を押し進めるものである。
システムとして働きかけるにあたって、最後の問題は、それが利用者に何を及ぼすのかである。日常業務は、利用者の生存権・発達権を促進するために行う一方で、利用者へ社会適応や統制として働きかける。一見、これらは矛盾しているかのように見える。しかし、筆者はこの二つの側面はバランスの取り方で両立すると考える。
例えば、日常業務の中で自閉症特有のパニック・問題行動の減少を目指したとする。そのためには、問題行動への一時的抑制や時には罰規則を必要とする場合がある。しかし、問題行動が減少することは、それだけ社会適応状態が維持さる。維持されることで、行動の選択肢の拡大が図られ、生活の質を高める援助に重点を置くことが可能になる(望月〔2001,P.17〕)。さらに、取り組み次第では、問題行動に対して罰規則を設けずとも行えることは可能である。
発達権保障とは、大多数の人々が享受している様々な権利を獲得することである(望月〔2001,P.14〕)。そのためには、社会適応によって獲得する能力というものは存在する。もちろん、統制が利用者の心身あるいは自由の規制や拘束を意味する場合もある。これらには、繊細に配慮をすることが求められる。
いずれにしろ、システムは具体的に利用者に働きかける。ゆえに、自分たちが設定したサービスが利用者にとってのぞましいと推測してもそれが単なる押しつけではないと言い切れるかどうか。それは利用者とのコミュニケーションから不断に問い直されている。
最後に、繰り返しになるが、業務は現場職員の手によって作られる。そしてそれは職員の経験年数の序列よりも、新人もベテランも対等になって業務を考える民主的な場から生み出される。新人の問題意識は素朴であるが、その根拠や具体性に欠けている場合がある。その問題意識を稚拙だと切り捨てるのは簡単である。しかし、その問いをベテランも一緒になって考える中で具体的解決の道筋を探る。こうした姿勢にこそ、発展的日常業務があるといえる。
第4節 おわりに
福祉の仕事は熱意とやる気があれば誰でも出来ると思われている。しかし、他の職業、例えば、セールス・営業など熱意とやる気があれば一見出来るような仕事がある。しかし、営業でも、勉強・研究を重ねるのとそうでないのでは、昇進や給与などに雲泥の差が開く。しかし、福祉の仕事は、努力をしなくても給与が貰えるとか経験年数だけで昇進することが可能な場合が多い。
利用者を知ろうとすることや自分なりの理論を把持することの重要性を考えながら、やりがいや生きがいに還元されない形で、「何のために勉強するのか」という問題になかなか答えることが出来なかった。ありきたりかも知れないが、結局、福祉施設職員は「良い仕事をして1日を終えること」を願う事にあるのではないかと考える(野地〔2003〕)。良い仕事とは、単なる自己満足や、仕事をこなすことではない。それは、まず「福祉の仕事として適っているか」を確認することである。確認することが出来なければ良い仕事をしたと感じられないだろう。そして、確認するには日々の業務や人間を見つめ、考えないといけない。さらには自分の仕事を巡る様々な言説を勉強することで確認作業は深まっていく。
結局、こうした勉強もやりがいや生きがいに還元されそうである。しかし、この良い仕事とはストイックに仕事のあり方を自分の中で問うことにこそ見いだすものである。つまり、「この仕事に賭ける」覚悟が必要であろう(田中〔2001〕)。しかし、それは他の職業でもいえる。給料や昇進も大切だが、良い仕事をしようと思うことこそ大切にされるものである。
また、福祉施設は集団での成長があってこそ自分を高めることができる。もっとも、自分が専門職として自律したいと思わなければ、いくら集団が発展的実践を行っていても気づくことはないだろう。逆に言えば、まわりのモチベーションが低いがゆえに、自分自身の専門職性を発展させることなく働いている人も多い。いずれにしろ、自分自身が良い仕事をしたいと思うこととまわりのモチベーションは連関しあっている。
最後に、本論では、個人の専門性獲得を中心に、様々な論理や事象、利用者への認識や思考方法について論じてきた。そのため、集団における専門性のあり方は枠組みの提示に留まっている。また、様々な論理にも目配せ程度で論じきれなかったことや説明不足なものが多くある。それらのことについて、今後じっくりと論じていく中で、自分自身の専門性を磨いていきたい。
註
1 鷲田(1997,P.26)は、この他、戦争の最前線であっても、強制収容所にいても、日常生活はあると述べている。そこには、どんな状態であっても、人々は諸々の生活遂行の土台となるような生の安定層を手に入れるとされる。
2 この他、現在、未来についても加茂(2003)は言及し、「日常性は翻訳とは行き作業によって成立し、それ故それは構成され続ける構造である」(P.6)と述べている。ほか、日常性については、主観性・間主観性・共生起など分析を行っている。本論では、そこまで立ち入らないが、筆者はどちらかと言えば、日常の構造について容易に答えは出せないとする鷲田(1997)の見解を指示する。
3 歴史的・共同体として妥当な生活世界どのように構成されるかは、鷲田(1997,P.60)によると、ある物語〜誰が書いたか分からないシナリオを人々は同じような口調で読み上げないといけない。そして、シナリオを覚えたら、ますます大声で復唱しないといけない。そうして、同一の物語が共同的に反復され、規範として自分の行動に浸透させるとされる。
4 いわゆる間主観性の問題である。このことについては(原田〔1999〕)参照。主体(個体)が日常の共同性(堅さ)と解釈の多様性を許す緩さ(もろさ・隙間)において、コミュニケーションの成立過程を考えることである。常に主体は主観的であると同時に相手もまた主観的であるがゆえに、それがコミュニケーションとして成り立つには、相手への推測や理解が相互間で成立必要がある。日常が単一の言説だけであるなら、相手へ伝えることは容易である。しかし、日常は多様で解釈が多様にできる言説で満ちているがゆえに、相手へのメッセージが、相手の解釈とあわなかったりずれたりと違ったメッセージになる。
5 この論文もまた先行する経験や知見の自分なりの現実構成の一つの形式〜相対的に一貫して編成されたものである。
6 別の見方として、横田(1999)は、理論形成をするのは研究者であり、施設従事者の実践は研究者の理論形成のための道具でしかない。本質的に、研究者と福祉従事者には権力関係にある。実践者が理論泣き実践を行えば、「暴力だ」と非難されるが、その反面研究者の方に実践の視点が欠けている場合、せいぜいその理論は「無力である」と言われる程度である。さらに、いくら実践者と親密な関係を研究者が築いても、その現場に様々な影響を残したあげく、結局はその場を去っていくのである。
7 横田(1999)では、リフレクティブ・アプローチとして紹介されている。須藤(2002)もこのリフレクティブアプローチを引き合いに出し、自分なりに分析をしている。
8 加茂陽と横田恵子の日常性におけるソーシャルワークについての議論。参考にした部分は、横田の言説。横田は、利用者の持つ価値観や認識が日常に微妙に亀裂を入れ、相互作用をもたらしていること。そして、援助者も利用者も相互に変容していくことを述べている。
9 尾崎(1997)では、こうしたのぞましいあり方の枠組みは時代と共に「流行り廃り」があるとされる。それは、歴史的に注目されてきた専門職のあり方としての枠組みを指す。この枠組みの流行り廃りは、その時代主流だった理論だけではなく、政策上求められている専門職性も影響する。例えば、医学モデルが主流であった時代は、援助者は、利用者にとって教師的、治療的立場が求められ、対等とか共感あるいは受容はあまり重視されていなかった。よって、普遍的な福祉職としてのあり方〜感情規制のありようはない。
10 例えば、中井(1998)参照。中井は、感情労働を、精神労働として論じている。精神労働とは端的に「人間労働の持つ創造性こそが精神労働を規定する」(中井〔1998,P.270〕)とし、福祉労働の内実を豊かにすると述べている。施設の内容を良くしようとする創意工夫が内実を豊かにするものの、そのきっかけは、日常業務のあり方や利用者とのコミュニケーションのあり方に悩む職員によるとされる。
11 渋谷(2003,PP.34-39)参照。製造業部門でも、経営者側が顧客の要望などを労働者側へ主体的に意識づけることによって、企業文化への労働者を包摂する。想像上の顧客と労働者が向き合うこと。これは、労働者が単なるものづくりから感情や精神までも労働として自己を投入しなければいけない(顧客の立場に立つ)ことを意味する。
12 例えば、田中みわ子(2005)を参照。この他、重症心身障害とのコミュニケーションの取り方などについての間主観性の問題などは原田(1999)を参照。田中みわ子は、重症心身障害者のふるえる動作や声のトーンを援助者が感応する様を共同化する身体と述べている。
13 尾崎(1997)を参照。関係性が混乱する原因として幾つか在るが、援助者の熱意が相手にとって大きなお世話になることがあること、専門的な裏付けや考察がない援助者の自然体的対応は結局、偏った自分の人生観や価値観を押しつけることになることなど。
14 実際に、とあるセミナーで重度の知的障害と自閉症がある子どもの母親がそのように力強く話していた。また、筆者の経験からもそのように言われ、拒絶したところ、施設長も巻き込んで悪い職員とレッテルを貼られたことがある。
15 具体的な記述やそのことについての対応など、尾崎(1999:2002)を参照のこと。
16 尾崎(1997,P.22-43)で自然発生的な自然体から吟味された自然体について考察が加えられ、その中で、「援助者の専門的成長とは、クライエントや社会資源・制度に対する知識を獲得し、生活問題に対する社会的視点を育て、更に共感・傾聴などの基本的な援助技術を身につけること」(PP.40-41)に全ての援助者がまったく同じ態度を身につけることを求めすぎているように思うと述べている。自分のスタイル(自然発生的な自然体)を吟味し、自分のスタイルを尊重し傾聴・共感ながらも、多様な思考形式を持つ柔軟性を身につけることが専門職として求められるとされる。
17 この他、ゆらぎは他者性を自覚するとか社会の構造や仕組みを見通すなどがある。詳しくは尾崎(1999,PP.291-325)(2002.PP.379-387)を参照。
18 日常に埋もれた会話をどう聞き取り、書きとどめる方法として、久保(2004)の他、久田(1996)が参考になる。特に、利用者主体の援助テクニック(PP.80-146)は具体的で分かりやすい。
19 特に、尾崎(2002)から学ぶことは多い。ある一人の利用者の関わりからいかにその心情を斟酌し、専門職として応えようとしているか、葛藤やゆらぎの中から書かれている。ケース記録のように淡泊に書くのではなく、その瞬間をフィルムのように再現できるように書くように心がける必要がある。その方法論として、田中(1993)が提唱する、介護過程分析表など示唆に富む。
20 これが地域福祉サービスを供給する仕事であれば、枠組みは変わる。例えば、【施設論】よりもむしろ【地域論】が枠組みになるだろう。さらに、対象論や援助論も施設業務とは違った観点で考察が加えられていくだろう。
21 加茂(2003,PP.136-175)において、これまで社会福祉職は、社会正義や人権擁護を大義としてきたが、最近では、経済合理主義、マネージャリズム、近代的な枠組みを支えている思想、コンピタンス至上主義によって社会正義など大義が見失っていることを指摘している。本文の例で行くと、コンピタンス至上主義やマネージャリズムが当てはまり、「ソーシャルワーカーは、特定の価値・倫理を持った人間として雇用されるのではなく、単に「特定の決められた仕事をこなす機能」として採用されることになる」(加茂〔2003,P.139〕)
22 松川(2005)は、ホームヘルパーの労働過密や分散化(例えば、直行直帰など)ついて論じている。第1部でも述べたが、施設職員の勤務形態(シフト)の多様さから慢性的な人手不足に陥ること。人手不足は、同じ施設内であっても、エリアで区切られて少人数で配置されること。会議への参加も過重なサービスメニューをこなすため、時間も限られていることなどで話し合う場が確保されていない。
23 例えば、相澤(2005)、北川(2005)、岩間(1999)が基本的な事例研究のあり方について示唆に富む。最近は、沖倉(2005)や副田(1994)のように利用者と協働で事例報告やケースカンファレンスの必要性が主張されている。
24 詳しくは、久田(2004,PP.155-158)を参照。概して、変革を訴える発言に対し、会議の後で、無理だとかできる分けないよと否定的である。あるいは、利用者の要望をわがままと決めつける。問題提起をする職員に秩序を乱す人とレッテルを貼る。あるいは机上の空論と決めつける。自分の後ろ向きの援助に同調しない人を仲間はずれにするなど。