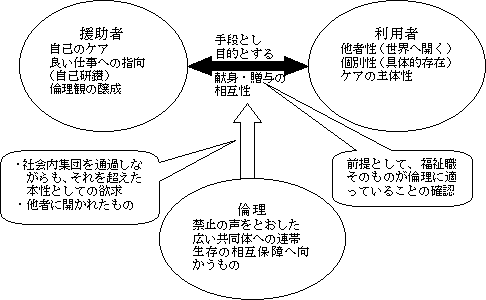第12章 施設職員の倫理
はじめに
これまで倫理・労働倫理・生命あるいはケアの倫理について論考してきた。結論を先取りすれば、労働倫理もケアの倫理も密接に結びついていると考える。そして、実際に働く一職員と一利用者の間に倫理が存在している。本章では、これまでの論考をまとめながら、福祉施設でいかに倫理が働いているのかをモデル化する。
第1節 第3部のまとめ
はじめに
第3部では、「福祉職は倫理性が高い仕事である」とよく言われる意味について、
1. まずもって何が倫理なのかが分からなければいけない。
2. そして、倫理が人間にとって肯定的なものであることを納得できないといけない。
という視点で論考を加えていった。本節では、第3部で述べてきたことを上記の問いに応える形でまとめる。そして、施設職員の倫理について若干の補足・考察を加える。
第1項 倫理について
倫理が何であり、倫理が人にとって肯定的ものだと納得できたかという問いについて。本論では、細かい部分で課題を残しながら、倫理は人が生きていく上で必要なものであり、肯定できるものであると納得できた。
課題の一端として、
- 倫理そのものは、広大な意味を持ち、本論では論じきれない点が多々あり、論の進め方も抽象的になりがちであった。
- 労働倫理は、広い共同社会に適用できることされるが、それでも倫理そのものとして措定できないのではないかという疑問が残った。
- 生命倫理に関しては、生殖技術は人を生かす技術という点で肯定できる。しかし生殖技術は科学であり、最後には科学と倫理の衝突は避けられないことに論究できなかった。
それでも、
1.倫理は、他者へ条件もなく献身や贈与をしたい欲求であること。そしてその欲求は人として自然なことであり、人のある本性であることを[1]再確認できた。そして、倫理は例えまわりが「しなくてもよい」と言うことでも、因習や慣例とは違った意味で、人の奥底から発せられる声として存在し、人を駆り立てる(前田〔2001〕)。つまり倫理的でありたいと向かう(為す)ことは、誰かに言われて行うのではなく、自分の行為に責任を課し、主体的に動くことなのである。
2.倫理が人の本性の一つだとすれば、「人間の知性は、その発生時から倫理との協力や葛藤を本性にしている」(前田〔2001,P.33〕)と考えることができる。知性〜合理性、客観性、操作性等を特徴とした科学技術の進展が[2]人々の生活を豊かにしてきた。しかし、人が生きることは、単一の技術やルールで説明できるものではなく、より複雑で、豊かで、深遠である。だから、「行為としての知の責任は、何よりも他者がよりよく生きることに対して向けられないといけない」(小林〔1996,P.10〕)。よりよく生きるには明確は判断基準がないが、そこに倫理と知性が深く結びついていることを確認した。
3.なぜ倫理と知性が深く結びついているのか。それは、人は、一人では生きていけず、他者と結びついていく中でしか生きられないからである[3]。もし、他者を自分の道具のように使えば、他者をモノと扱うことになる。モノ化は他者の生を否定することである。そして、自分の生もまた他者の道具として使われることを許すことになる。逆に、他者がよりよく生きるように願い、振る舞うことは、他者の生を尊重?肯定することになる。ということは、自己の生も肯定できることに結びつく[4]。とはいえ、倫理は具体的な互酬性や対価は期待できない。あくまでも、自分が倫理的たろうとすること。あるいは知性をよりよく生きるように振り向けることによって、自分の生をどうにか肯定できるのである。
4.そして、他者とは常に具体的で直接的なものである。それは日々接する利用者であったり、手を差し伸べたいと思う個人である。よって、倫理的欲求は常に個人的なものに差し向けられる。その行為の根源には1で述べた欲求がある。そして、3のような自己と他者の生の肯定を確認する行為であり、その行為を通じて人は広い共同体(人類)につながっているのである[5]。
当初、倫理はどこか説教めいていて、社会の善悪基準や人としての善い行いのあり方を決めている総体だと思っていた。しかし、本論を編む中で、倫理は、善悪基準を超えて人が生きるために欠かせない“根源”であることに気づくことができたと言える。
第2項 施設職員としての倫理の出発点
次節のモデルによる利用者と援助者のあり方を述べる前に、本項では、援助者としての倫理の出発点を取り上げる。
€自分の非を認めること
援助者としての望ましい振る舞い、利用者の権利擁護はいかにして出来るのかという模索、あるいは専門知識の積み重ねは大切である。しかし、だいたいは自分の非倫理的な行為(体罰や不適切対応など)や自分の未熟さに気付くことから倫理へ、あるいはよりよく働くことを志向するのではないだろうか。
虐待や差別的発言は、知らず知らずのうちに行われていることが多いことは第11章で述べた。虐待や体罰が「場面の再定義」(体罰→躾)や上司などへの「責任転嫁」(みんなもやっているなど)によって、虐待行為が集団内で正当化されやすい(空閑〔2001〕)。そして、虐待が日常繰り返され、許されることで、いま自分の行為が虐待なのかどうかすら分からなくなってしまう。しかし、やはり虐待や体罰は明らかに悪いことである。そして、虐待や体罰はよく考えれば、それがどのようなことなのか誰もが思い当たることである。
とはいえ、自分の行為が悪いことだと指摘されることは、ひどく抵抗感を抱く。その指摘のおおかたが正しいと認めれば認めるほど、今までやってきたことの全てが否定されたような気になる。そして、ついつい「悪いことをしているつもりはない」とか「私は私の考えでやっていると」と言い訳をしてしまう。つまり、自分自身を見つめることの大切さはよく分かるが、実際行うのは難しいのである。
しかし、自分が悪いことをしているのに気づいてしまったのなら、これまでの自分の行為を真摯に反省する勇気が必要であろう。その反省の作業は非常につらい。だれでも人は傷つきたくないからである。それでも、他者の忠告や指摘に心や目を開くことは、自分が専門職であるからだけではなく人として大切な態度であるといえる。それが倫理に向う出発点になると考える。
仕事に誇りと持つと言うこと
福祉施設の仕事は誰でも出来て、単調な作業の繰り返しだとよく言われることは繰り返し本論の中で取り上げてきた。福祉施設(職員)の専門性については第2部で考察し、第4部でも論じるので、本節では、労働倫理の観点から概説する。
労働倫理上では、どんな職業においてもやりがいや自己実現を見出すことができる。第10章では、その一例として靴磨きやトンカツ屋を引き合いに出している。トンカツ屋の親父が、自分の職業に誇りを持つのは、その職業がえらいと社会的に認められているからではない。ただ、おいしいトンカツを客に食べてもらうことが自分の喜びであり誇りなのである[6]。そして仕事に誇りを持っている人、あるいは良い仕事を体現している人は、良い仕事を志そうとする人を感化する。そうして、自分もまた良い仕事をしようと人が人に密かに約束するのである。
この視点に立つと、誰がなんと言おうが、施設で働くことにやりがいを見出すのは自分自身ということになる。もし周りに良い仕事をしている〜感化させてくれる人がいなくても、福祉施設の存在(役割)そのもの、目の前にいる利用者への関わりの中に倫理を見出すならば一人でも歩いていくことができるだろう。とはいえ、トンカツ屋や靴磨きはどちらかといえば個人で行う職業であり、自己の裁量権が非常に高い。逆に福祉施設は個人の自己裁量権はあるが、どちらかといえば、チームワークによる労働集約型であり、仕事の成果は個人では測れない。よって一人で技倆を磨いても仕事に反映させることが難しい。しかし考えようによっては、自分が良い仕事を積み重ねている姿は、チームワークであるがゆえに伝わりやすいと考える。
そして良い仕事とは、常に具体的な形で現れる。例えば、€のような不適切対応を一切許さない丁寧な仕事ぶりとか、ケアの倫理に向かっている姿だったりする。あるいは専門知識と倫理が良い具合でバランスが取れた言動に現れる。そしてその結果は、利用者を見れば分かる。援助者に安心して体を預けている姿。その援助者へ向けるまなざしや表情などに見られる[7]。かくして、まずもって自分が良い仕事をしようと歩み始める中に仕事への誇りが芽生えると考える
次にモデルを使って、援助者と利用者の間にある倫理の働きを述べていく
第2節 援助者と利用者間の倫理
はじめに
前節で大まかに援助者はどのように倫理を志向すればよいのかを論じた。本節では、利用者と援助者の関係の中にどのような倫理があるのかをモデルとして提示し、説明と考察を加える。
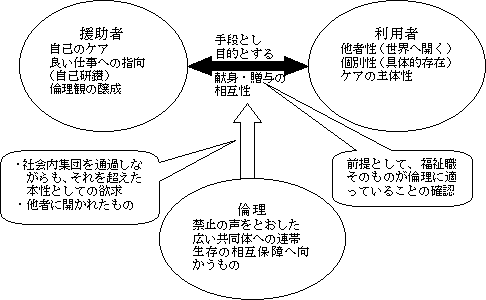
図3-2 援助者と利用者の倫理的関係
第1項 労働倫理として
良い仕事とは何かについては前節で論じた。また、良い仕事を志向する出発点に自分の不適切な行いを見つめることの重要さについて論じた。
それ以上に、援助者は、利用者から賃金をもらって生活ができている事実をもっと実感しないといけないと考える[8]。毎日の仕事はルーティンワークで、賃金をもらうのは当たり前と思うし、給料は使用者からもらっているとついつい考えがちである。しかし、まずもって賃金は、利用者がいて彼らへサービス提供を行うから得られるのである。それは、第10章で論じたように、他者(利用者)から自分はお金をもらうという意味では他者は手段である。しかし、もし他者に見向きもされなくなれば、自分が賃金を得られないだけでなく、他者から自分が不要であることを知らしめられることになる[9]。前田(2001,P.57)は、「私が人様のおかげで食えるのは、人様を手段としているからであろう。その手段に様をつけるのは、そのことを恐れるのである。なぜか。人様は、親と違うから、まず無条件に私に好意など持っていない」のである。利用者は善意の人でもない。あるいは、ただケアされる人ではない。だから他者を手段としながらも、他者にとって良いサービスを提供しようと努力が求められるのである。自分(援助者)は他者を目的として研鑽する(良い仕事をする)ことでしか他者に応えることができないのである。それが人様へ義務を果たすことなのである。
福祉施設に勤務することが良いことなのかどうかは特に第10章あるいは第5章で考察をしたので繰り返さない。ただ一点、福祉そのものが倫理として適った職業であること。それは、社会と人間に開かれた職業であることを確認しておく。
第2項 生命・ケアの倫理として
第11章では、援助者は利用者の体の動きや働きかけに感応してケアを行っていることを論じた。その意味で、援助者〜ケアする側は受動的であるとした。ところが実際の日常業務にはやるべきこと(ケアの内容)があり、利用者に従ってもらうことで日常生活〜集団生活を維持しているのが実情である。利用者からの働きかけや要求の全てにいちいち応えてケアをすることは、少ない職員数で集団生活を支えているため無理がある。
確かに施設は集団生活であり、普段は利用者の個別性に意識することなく、流れ作業のように業務をこなしがちである。しかし、それでもやはり援助者は利用者の目の動きや言葉の端々に感応している。そしてサービスの個別的な加減や適当な距離感を模索している[10]。それは、一職員と一利用者の距離感でありお互いの加減である。その意味で利用者と援助者の関係は常に個別的である。あるいはケアの主体は利用者にあり、援助者は受動的な立場にある。
他者性については、福祉施設で働くとは誰かのお世話をすることである。自分の知り合いが利用者でいるからではない。その意味で、そこに努めるまで誰をケアするか分からない。援助者は確かに個別に例えばAさんをケアする。援助者はAさんをケアするにあたって、Aさんの障害特徴や個性、あるいは存在自体をオーダーメイドする。とはいえ、ケアの関係においてAさんだからケアするのではない。援助者にとってケアに向かうべき人(他者)としてたまたまAさんが目の前に現れたのである。
援助者にとってAさんがいなくても生きていけるし、Aさんも特定の援助者がいなくても生きていける。しかし、Aさんも援助者も一人では生きていけない。誰かの助けなしでは生きていけない。その意味で、Aさんをケアすることを通じて、援助者は人と人が繋がっていくことを知るのである。あるいは、他者をケア〜献身することは他者の生を肯定することであり、それは翻って他者から自己の生を肯定(贈与)されることに気付くのである。と、日常業務において、そこまで感得し得ないとしても、ケアの関係にはそうした要素があると考える。
またケアの関係において、他者へのケアもさることながら、自分が燃え尽きたり、体をこわしたりしては元も子もない。そういう意味で、自己へのケアは欠かせない。このことについては、これまであまり詳しくふれなかったが、しばしばケアとは自己犠牲であり、身を粉にしてケアすることが美徳とされる。しかし、まずもってケアとは「汝自身を知る」ことが重要である。そして、自己へのケア(配慮・気遣い)ができてこそ他者に関わることができるのである[11]。鷲田(2001,P.220)は別の視点から、「他人とのつきあいの中でここが引き際だと判断すること、じぶんの身体がそろそろ限界だと感じること、…中略…、これらの判断や感覚は、科学者や技術者の下す判断に劣らず精密である」と論じる。いずれにしろ、自己の保身や自己中心主義とは別にセルフケアは他者をケアする以上に必要な要素であるといえる。
第3項 労働倫理と生命・ケア倫理の連関
結局、福祉施設において、ケア倫理に向かって利用者に接することが、良い仕事に繋がるという意味で労働倫理に適っているとも言える。あるいは、生命倫理が何を問題にしてどう考えるべきなのかを紐解き深めていく中で、良い仕事やケアの大切さに気づいていくとも言える。
共通して言えることは、まず他者と自己の生を肯定すること。そして、そのことを通じてよりよく生きていくことである。そしてよりよく生きるのは、他者を手段としながらも、目的とすることで他者に自己を開いていくことである。以上は第1節で述べたので繰り返さない。
倫理に向かって人が生きようとすることは難しい。しかし、倫理に向かって生きていくことで人は自分を奮い立たせる。第9章で人に席を譲る例で述べたように、それは些細な日常の中に宿っている。倫理は同様に日常の仕事の中に、ケアの関係の中に宿っている。倫理を志し、自分の行為に責任を持ち、自分を賭けて歩むこと。これにまさる喜びはないのである(前田〔2001〕)。
第3節 おわりに
倫理について職場で話しあっている中で、ある職員が、「きれい事は遠くにあれば万人が納得するが、自分に引き寄せた場合、そのきれい事を実践することはかなり難しいことだ」といったような内容のことをポツリと話した。
ケアの倫理に向かってとか、やりがいを持ってと言うことは簡単である。しかし、やはり、どこかで自分の行っていること(業務)に妥協したり、やぼることの言い訳(大変だとか)をして日々をやり過ごしてしまう。逆に、妥協を許さない仕事ぶりは、自分一人でするなら良いが、往々にして、他の援助者の仕事ぶりに妥協を許さないようになる。それは時にトラブルや人間関係の破綻まで発展することがある。また、文献で非倫理的な対応〜虐待や体罰をする援助者の事例を読んで、とんでもないことだと思っても、実際身近にいることが多々ある。あるいは自分がやっていることすらある。
それでも、だからと言うべきか、倫理について考える必要があるのではないか。これが本論を書く原動力になった。日々の言い分けや妥協の中にも、よりよく生きたい気持ちがあるのだと。それがどのように考えれば、そこに行き着くのか皆目分からず、手探りのまま本論を進めてきた。
また第1部から2部で論じきれなかった問いや積み残した来た課題に応える形で第3部を編み込んだ部分がかなりある。そのため、論の進め方が行ったり来たりして煩雑なものになってしまった。さらに、本論の展開も拙速なところが多々あった。いずれにしろ、倫理は論ずることが多様にあり、それらについては更に詰めていきたい。
ある職員の「きれい事…」の発言についてだが、確かに倫理はきれい事かもしれない。しかし、人は現実的に生きる上で、きれい事が人間らしく生きる原動力になっていると私は応えることにした。打算や計算だけではなく、真っ当に生きようとした場合、その根拠には、良心や人への配慮や気遣いがある。時に、きれい事は日常に埋もれて無力なときもあるけれど、それは確かにあるのである。だから倫理に向かって生きることは遠いことではなく、自分の中にもあると考える。
そういう意味でも、本論ではかなり狭い範囲ではあるが、倫理とは何か、そして現実的にどう考えるべきかについて考察できたのではないかと考える。
註
[1] 前田(2001)参照のこと。倫理は疑うことはできないと言うのは、前田は、和辻哲朗やカントなどから引用している。
[2] 小林(1996)参照。科学の操作性などは生命倫理の章に詳しく論じている。
[3] 人は他者と共にあることや開かれていることなどは、ケアの倫理で詳しく論じている。あるいは、倫理を語るときは、この他者?自己が連綿とつながっていることが原則にあることは間違いない。知もまた同じであろう。「知が知にとっての他者と出会うところに、知の問題が提起される」(小林〔1996,P.10〕)
[4] 前田(2001)を全体的に参照。
[5] 人類の肯定については、第9章参照。特に、小泉(第9章)(2003)のレヴィナスについての省察を参考にしている。
[6] トンカツ屋の事例については、前田(2001)参照のこと。
[7] 利用者の体に触れることについては、川西(2003)や鷲田(1999)参照。川西は看護士が患者の体に触るときに起こるコミュニケーションの深さを。鷲田も同様に体を触ることの奥深さを伝えている。皮膚に手を「ふれる」ことは有機的な統合や相互確認的な働きであるとされる。
[8] 田中(2004)において、援助者と利用者の等価性に関して、信田さよ子『アディクションアプローチ』(医学書院,1999)を参照にしながら抄録している。その中で、援助者の脱価値化、支配性の自覚、援助をすることの必要性を問うことをあげている。そして、援助者が、被援助者の支払う金銭によって生活している事実認識が大切であると。
[9] 田中(2004,P.36)において、「社会福祉実践及び社会福祉学において、最も危惧することは、その対象を担う利用者及び家族などから、そっぽを向かれることである」と述べている。はたしてそんなことがあり得るのだろうか。筆者はあり得ると考える。実際、福祉業界はすでに措置による行政処分ではなく、選択と契約が主流である。実際に、入所を勧められても断る家族、体験的に利用してもすぐに去っていく利用者本人など多数存在する。
[10] 鷲田(2001,P.219)では、対人関係の中で〈まみれ〉ながら、その〈まみれ〉を畏れず、〈まみれ〉を自らの意志で選びなおしたひとたちには、「加減とか塩梅、潮時とか融通、ほどほどとか適当ということを、対人関係の中でいやというほど知っている人たち」に見られ、それは深い智慧とされる。そのコツは、熟練してはじめて可能になる術に近いものだと考察している。
[11] 森岡(2000,P.224)では、「フーコーによれば、〈自己へのケア〉が〈他者へのケア〉に先行し、〈自己〉が自分自身の対して存在論的に関係して初めて、他者への関係性が成立する」とされる。