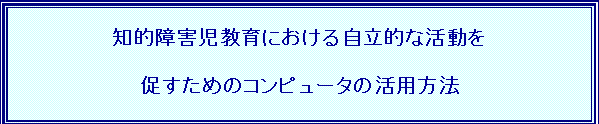
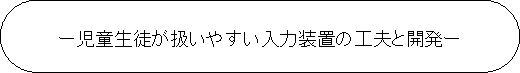
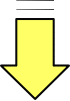
情報教育講座 特殊教育専門 「パソコン講習会Ⅱ」
平成12年11月27日(水)
馬場 光司
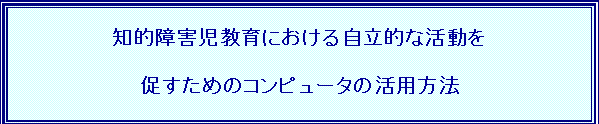
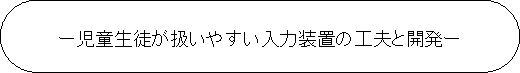
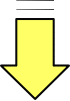
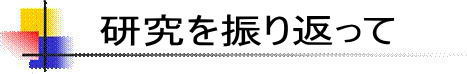
1.子ども達の活動のニーズに合わせて
2.試作にとどまった、
入力装置・ソフトウェアの実用化
3.関係諸般と連携を密に 等
子ども達が必要性を感じる、
学習内容・環境を大切に考えて行きたい。
平成12年度 船橋市立船橋養護学校での実践事例
1.「子ども達の活動のニーズに合わせて」
○「宿泊学習に向けて」の高学年としての活動
「宿泊のしおり」作り → 文字の入力 写真(挿し絵)貼り
○「アニメ絵本」の製作
「パワーポイント」を利用した絵本活用 → 紙芝居・効果音・動き
「文字入力」と感想・言葉 → 会話・教師へ・友達同士へ
「アニメ画」を利用しての文章化 → 「作文」
「視写」(文字のていねいさ・正確さ・漢字の使用)
「音読」(絵本 → 国語の教科書 → 童話へ)
「型はめ」(ポケモンの型はめ → 各作業の手元の確認・教師への要求へ)
「音楽・主題歌」→「楽器・合奏」
平成12年度 「 知的障害児の学習意欲を高めるコンピュータの活用方法と支援のあり方 」
― 生活単元学習『アニメ絵本を作ろう』を通して ー
詳しくは、上記のレポートを参照してください。
○「Wordのマクロで遊ぼう」食べ物編・動物編・動物鳴き声編
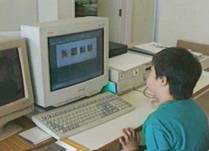

ワープロソフトの「Microsoft office Word」を利用したソフトを紹介します。
Excelでは有名なVBA(Visual Basic for Application) マクロを利用した学習ソフトです。
Wordに画像と音声を貼り付けます。子どもがマウスで画像をクリックすると、名称や鳴き声がなるように
したものです。最近では、Wordがインストールされたコンピュータが多くなっているのでどこでも利用できると
思い作って見ました。
使用方法も簡単で、マウス操作がある程度できる児童は大変興味深く活動できるた物でした。
2.「試作にとどまった、入力装置・ソフトウェアの実用化」
☆Windows上での外部機器の制御(入力)
○「ドラやきいくつ」(画面の数字に合わせて、スイッチの上に具体物を載せる)
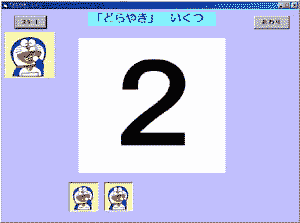

○「数量あわせ(1)」

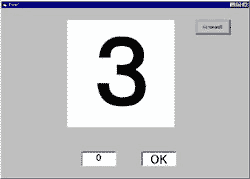
これまでコンピュータを利用した「かず」の学習では、画面に映った図形(○.リンゴ等)の
数をテンキー(数字キー)を使って選ぶものやマウスで選ぶものがほとんどでした。
しかし、数字(文字)と 数詞(音・読み) 数量(具体的な量)を一致する必要がある
「かず」に関する学習は重度の障害がある児童等には大変難しく、興味を持つことの少ない学習の
一つだったと思います。
そこで、コンピュータを用いて数字や数詞・数量を一致するように工夫したり、学習する子どもに応じて
好きなキャラクターや食べ物を利用したりするのがこのシステムです。
ソフト「どらやき いくつ」 ・ 「数量合わせ(1)」等を参照してください。
○「動物の鳴き声」・「効果音とグラフィック


この他に、子どもに合わせた入力スイッチと画面・音声を組み合わせて、「動物の画像と鳴き声」が
同時に出るようなものや効果音とグラフィックを組み合わせたものを利用して「生活単元学習」の遊び場に
設置もしました。
○「スケールボックス」と「ドレミファドン!」(ソフト)

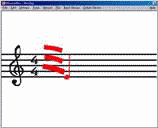
「スケールボックス」は、PS/2コネクタに接続できる簡易スイッチBOXです。
一般的に、子どもに会わせた入力装置を接続するには、インターフェースが必要です。
そこで、もっと容易に外部入力スイッチを接続できるようにしたのがこの「スケールボックス」です。
キーボード用のコネクタにこのボックスを接続した後、子どもに合わせたスイッチを接続するだけです。
教師用の入力キーボードは、USBキーボードなどを利用すると便利です。
ソフト「ドレミファドン!」は、決められたキーを押すと音階が出ます。更に、画面に画像が表示します。
子どもの書いた絵を表示させることもかのです。演奏するイメージに合わせた物も楽しいと思います。
 戻る
戻る