 �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@
�@�@�@�@�@
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�w�p���`�x�̈ꗗ�@ �p�P�@���ށE����́u���S�v���Ăǂ��������ƁH �`  �@�؍H��i�ł́A�┠���̊p�𗎂Ƃ��Ċۂ݂����܂��B�T���h�y�[�p�[�i���₷��A�z�₷��j��d���T���_�[���J��Ԃ������邱�ƂŖ؍ނ̕\�ʂ��A�y���L��j�X��b�N�X����h�邱�ƂŁA�؍ނ̂��������h���悤�ɂ��܂��B�������邱�ƂɎ���Ȃ����ƂŁA���S�Ŕ������ϋv���̂��鋳�ށE�������邱�Ƃ��ł��܂��B �@�؍H��i�ł́A�┠���̊p�𗎂Ƃ��Ċۂ݂����܂��B�T���h�y�[�p�[�i���₷��A�z�₷��j��d���T���_�[���J��Ԃ������邱�ƂŖ؍ނ̕\�ʂ��A�y���L��j�X��b�N�X����h�邱�ƂŁA�؍ނ̂��������h���悤�ɂ��܂��B�������邱�ƂɎ���Ȃ����ƂŁA���S�Ŕ������ϋv���̂��鋳�ށE�������邱�Ƃ��ł��܂��B�@���̒��ɓ���댯����������̂́A�r�����邩�q�ǂ������̎�̓͂��Ȃ����ɕۊǂ���悤�ɂ��܂��B���ł����̒��ɓ���Ă��܂����q�����܂�����A���ݍ���Ŏ��̂������Ȃ��悤�ɁA���ݍ��߂Ȃ��傫���̂��̂ɂ��邩�w�����ɏ[�����ӂ��܂��B���͂������������ނ͐E�����ɒu�����A�����ɒu���ꍇ�͌��������ĕۊǂ��Ă��܂����B�q�ǂ������͋��������镨�₨�َq�Ȃǂ̐H�ו��́A�������炢�����I�ɓ���Ă��B���悤�ɕۊǂ��Ă������Ɍ����Ă��܂�����ł��B �p�Q�@�X�̎q�ǂ��ɍ������u���ށE����v���Ăǂ�Ȃ��́H �`  �@�q�ǂ�������l�ЂƂ肪���i��Ⴊ���̒��x������Ă��܂��B�Ⴆ�u�{�[���R��v���s�����A�p�ӂ����T�b�J�[�{�[�����d���Ǝv���ƁA�����ɂ��Ȃ邩��Ɨ]��R�肽����Ȃ��q������ł��傤���A������F�B���R�����{�[���������ɂ����Ȃ��Ɠ]�����čs���{�[����ǂ�Ȃ��q�ǂ�������ł��傤�B �@�q�ǂ�������l�ЂƂ肪���i��Ⴊ���̒��x������Ă��܂��B�Ⴆ�u�{�[���R��v���s�����A�p�ӂ����T�b�J�[�{�[�����d���Ǝv���ƁA�����ɂ��Ȃ邩��Ɨ]��R�肽����Ȃ��q������ł��傤���A������F�B���R�����{�[���������ɂ����Ȃ��Ɠ]�����čs���{�[����ǂ�Ȃ��q�ǂ�������ł��傤�B�@�{�[���̓T�b�J�[�{�[�������ł͂���܂���B�r�[�`�{�[���ł��������A�V�������K���e�[�v�Ŋۂ߂��{�[���ł������̂ł��B�_�炩�{�[���ł���ΏR���Ă����͒ɂ��Ȃ�܂���B�܂��A�V�������ۂ߂ăK���e�[�v�������č�����{�[���̂悤�ɗ]��]����Ȃ��{�[���ł���A���낱��Ɠ]�����Ă����Ȃ��̂ŁA�{�[����ǂ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����ł��傤�B �@��l�ЂƂ�̓������l���Đ���ނ̃{�[����p�ӂ��邱�ƁA���ꂪ�X�̎q�ǂ��ɍ��������ނ�p�ӂ���Ƃ������Ƃł��B�d���{�[����������q����炩���{�[�����珙�X�ɍd�߂̃{�[���ɕς��Ă����A���ʂ̃{�[�����R����悤�ɂȂ��Ă����܂��B �p�R�@�q�ǂ��̎��Ԃ̔c���͂ǂ�����́H �` �@���Ԕc���Ƃ����ƐF�X�Ȍ����@�������т܂����A���\�Ȃ�����������Ώ����������u���B�v�̊w�K��������A�����̐搶���ł��̂��q����̂��Ƃ�O��I�ɘb�������������A�������Ԕc�����ł��܂��B�i�����A�����̐搶���Ƃ����Ă��A���ʎx������̌o����������A�w�K�s���̐搶����������W�܂��Ă����Ԕc���͐[�܂�܂���B�j �@�������̂����Ƃ���́A�ǂ̒n��ɍs���Ă����ʂ̌������ł���_�ɂ���܂��B�������ɂ��Ă͂��̕��@�⌟�����ʂ̊���������m��Ȃ��Ă͍���܂����A���͌��������ɂ͎��Ԃ������肷���邱�Ƃł��B�o�����猾���Ɗw�N�̂��q����B�̌������I���܂łɂ��悻�R�����߂�������A���ʓI�Ɋw�K�����Ɏx�Ⴊ�o�܂����B�����̂����_�͔F�߂܂����A�搶�������X�b�������āA�q�ǂ������̎��ԂƖ��_�̉��P���@���������������A�g������Ԕc���ɂȂ�Ǝv���܂��B�u����H�v�Ǝv������w���ɍ�������A��ɉ��ɂ��̓��̂����ɃN���X��w�N�̐搶�Ƙb���������Ƃł��B �p�S�@�ۑ�ɏW���ł��Ȃ��q�̎w���͂ǂ������炢���́H �` �@��b�w�K�͏Ⴊ���̏d���q�ǂ��B���s���w�K�ł��B�Ⴊ�����d���ƌ������Ƃ́A�W���͂⎝���͂̌��@�E��̑��쐫�̖��n���E���̂��������茩�邱�Ƃ����Ȃǂ̓���������Ă��܂��B�Ⴊ�������قǏd�x�łȂ��q�ǂ��B�ɂ��A�ۑ�ɏW���ł��Ȃ��q�ǂ��B�����܂��B���̏W���ł��Ȃ��̂��Ƃ����ƁA���ɂł��邱�Ƃ��ۑ�Ƃ��Ă�����A�ۑ肪�������ȂǁA�ۑ莩�̂����̎q�ɍ����Ă��Ȃ��ꍇ�����������܂��B�܂��A�����ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��A���ނ̎g�����i����j���킩��Ȃ��Ăł��Ȃ��Ƃ������Ƃ�����܂��B �@�q�ǂ��̎��ԂƉۑ�ƃX���[���X�e�b�v�̐ݒ肪���܂��g�ݍ��킳���Ă��邩�A���ނ̒̎d�����q�ǂ��B�ɂ킩��₷�����̂ɂȂ��Ă���̂��l���܂��傤�B�܂��A�ٕʂȂǂ̊w�K�ł́A�q�ǂ��B�ɐ������Ă��炢�����āA�搶�������̕���m�炸�m�炸�Ɍ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B��������Ǝq�ǂ��B�͉ۑ���l���Ȃ��Ő搶�̎����̐悪�������ʁi�����j���ƁA�搶�̌��Ă������f���悤�ɂȂ�܂��B����ł͊w�K�ɂ͂Ȃ�܂���B �@���ގ��̂ɖ��͂��Ȃ����i�J�[�h�ł���Ώ����������蔖�������肵�Ď����Â炢�E�C���X�g���킩��Â炢�E�F���͂����肵�Ă��Ȃ����X�j�ɂ��W���ł��Ȃ����Ƃ̈���ƂȂ�܂��B �@���ނ����L�������Ȃ�悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂��A�ۑ�ݒ肪�����Ă���̂��E�̎d�����킩��₷�����Ȃnj������Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�W���ł��Ȃ��͎̂q�ǂ��̂������ȂǂƎv���Ă�����A���ʎx���w�Z�̋����Ƃ��Ă͒p��������������ł��B �p�T�@�_�C�i�~�b�N�ɉ^�����������B�ł��A������Еt������ρH �` �@���̕s���R�̎q�ǂ��B�ł��m�I�̎q�ǂ��B�ł��A�u�̈�v��u�����сv�ł͉��Ƃ��̂�傫�������������⊴�o�^����g�߂Ȃ����Ɛ搶���͋�S����Ă��邱�Ƃł��傤�B�_�C�i�~�b�N�Ȋ������s�������ƍl   ����ƁA�G�A�[�g�����|�������Ԃ��^�����������̃L���X�^�[�{�[�h�ȂNj�����傫�Ȃ��̂��K�v�ɂȂ����萔���K�v�ɂȂ����肵�ď�����Еt������ςɂȂ�܂��B ����ƁA�G�A�[�g�����|�������Ԃ��^�����������̃L���X�^�[�{�[�h�ȂNj�����傫�Ȃ��̂��K�v�ɂȂ����萔���K�v�ɂȂ����肵�ď�����Еt������ςɂȂ�܂��B�@�ЂƂ̗�ł����A���̕s���R�̏Ⴊ���̏d���O���[�v�Ń{�[���V�т��s�������́A�Ђ��������Ē݂��Ă��锠����{�[���ۂɗ��Ƃ�����A�{�[�����������ɕ~���߂ăV�[�c�u�����R�Ŋ��o�V�т��s���܂������A��Еt���������ςł����B �@�����Ńu���[�V�[�g�̌��Ƀ��[�v��ʂ����ƂŁA������ƂЂ��������u���[�V�[�g�̏�̂�������̃{�[����搶����l�ł��ȒP�ɏW�߂���悤�ɂ��܂����B �@������Ƃ����H�v������A�Z���ԂŕЕt�����ł���悤�ɂȂ�܂��B������Еt������ς��Ȃ��Ǝv������A������ƍl���Ă݂܂��傤�B�����̕��@�́A�݂�Ȃ̒m�b�ŏo�Ă�����̂ł��B �p�U�@�u���ށE����v�̍ޗ��͂ǂ��Ŕ��������́H �` �@���́A�����̏Z��ł��鑾�c�s���ɂ���W���C�t���z���_�ƃ_�C�\�[�łقƂ�ǂ̍ޗ����w�����Ă��܂��B�W���C�t���z���_�Ǝs���ɐ��X�܂���_�C�\�[�ɂ͂悭�o�|����̂ŁA�ǂ��̓X�̂ǂ��ӂ�ɉ������邩�͖w�ǂ킩���Ă��܂��B�����̍����قږ��T���s���Ă��܂����B �@�ǂ��ɉ�������Ƃ������Ƃ���̕������Ă���ƁA���ށE�������낤�Ƃ���Ƃ��ɁA�u����Ƃ���Ƃ��ꂪ������邾�낤�v�Ƃ����ڈ��������ɗ����܂��B������낤�ƍl���Ă��Ȃ��Ƃ��ł��A�z�[���Z���^�[��_�C�\�[�Ȃǂ����ĕ������Ƃŋ��ލ�̃A�C�f�A��������ł���悤�ɂȂ�܂��B �p�V�@�y���L�ƃA�N�����G�̋�̎g�������H �` �@�u�y�O�����v��u�F�ٕ̕ʁv�E�u�`�ٕ̕ʁv�Ȃǂ̋��ނł��y���L�ł͂Ȃ��A�N�����G�̋���g���܂��B�d�オ��̔��������Ⴄ����ł��B�q�ǂ��B�͏Ⴊ�����d���Ă����ꂢ�Ȃ��̂̕��Ɏ��L���܂��B�p�r�ɍ��킹�Ďg���킯��Ƃ����ł��傤�B �p�W�@����̂Ȃ��q��O���l�̎q�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����͓���H �` �@�����q�̒��ɂ́A�m�I�ɏd�x�Řb���Ȃ�������A����g�ق�S���g�ق̂��q�����O���l�̂��q����œ��{�ꂪ�s���R�Ȃ��q��������܂����B�����������q�ǂ��B�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������ǂ����邩�Ƃ������ƂƂƁA���{���S���b���Ȃ��O���l�̕ی�҂ւ̑Ή����ǂ����邩���� �@��ʌ��ł́A���̋`������ۂɋA���������k���x���A�h�o�C�U�[�����āA������ɒʖ�̕��̎x�������肢���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B�ƒ�K��⏑�ފW�E�ʒm�\�̖|��ȂǁA�����u���W���Ђ̂��q����̒S�C�ɂȂ����Ƃ��͐��������Ă��炢�܂����B���Ƃ��ʂ��Ȃ��ƌ������Ƃ����������A�w�Z����z���鑽�ʂ̃v�����g���|���g�K����ɖ|�ēn���͖̂w�ǎ����ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ŁA�����[��܂ň���ꓬ���܂����B�@ �@�E�E�E���āA�q�ǂ������Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ł����A�����̌f���ł́u�P���̊w�K�̗���v�̃J�[�h�i����E�̈瓙�̋��Ȗ��j�ɃC���X�g�Ƃ��̎��Ƃ��s���u�ꏊ�̎ʐ^�J�[�h�v��\�邱�ƂŁA�Ⴊ�����d���q���O���l�̎q���ړ��͖�肪�Ȃ��Ȃ�܂����B�q�ǂ��B���ł��S�̂��鋋�H�́A�����E�p���E���сE�ʕ��E�������E�˗ނȂǑS�Ďʐ^�ɂ��Č����\����邱�ƂŁA�����̋��H�͉��E�����͉����Ȃ��Ɗy���݂ɂ��Ă���q�ǂ��B�����Ă킩��悤�ɂ��܂����B  �@�����\�͑O���̏I��荠�ɂ͋��H������v�����g���͂��܂����A�ی�҂ɂ͂������ł��A�������ǂ߂Ȃ��q�ɂ͈Ӗ����Ȃ��̂ł��B���H�̌�����ʐ^�ɎB���Ă������ɂP�N�ȏォ�����ĊԂɍ���Ȃ��̂ŁA�C���^�[�l�b�g�ŗႦ�u���c�g���v���Ō������Č����̎ʐ^�Ɏg���܂����B�ꃖ�����̃J���[�̎ʐ^�̌����\�́A�N���X�����łȂ��w�N�̎q�ǂ��B�S���⑼�w�N�̎q�ǂ������E�O���l�̕ی�҂ɂ���D�]�ł����B �@�����\�͑O���̏I��荠�ɂ͋��H������v�����g���͂��܂����A�ی�҂ɂ͂������ł��A�������ǂ߂Ȃ��q�ɂ͈Ӗ����Ȃ��̂ł��B���H�̌�����ʐ^�ɎB���Ă������ɂP�N�ȏォ�����ĊԂɍ���Ȃ��̂ŁA�C���^�[�l�b�g�ŗႦ�u���c�g���v���Ō������Č����̎ʐ^�Ɏg���܂����B�ꃖ�����̃J���[�̎ʐ^�̌����\�́A�N���X�����łȂ��w�N�̎q�ǂ��B�S���⑼�w�N�̎q�ǂ������E�O���l�̕ی�҂ɂ���D�]�ł����B�@��b�Ɋւ��ẮA�R�~���j�P�[�V�����u�b�N��J�[�h���P�����g���悤�ɂ��邱�ƂŁA��̉��������������킩��悤�ɂȂ�܂����B�ȒP�Ȉӎv�̑a�ʂ��͂����悤�ɂȂ�ƁA�M���W���ł��Ă��Ƃ̗������i��ł����܂����B �@�O���l�̕ی�҂��g�َ��̕ی�҂��Ⴊ���̏d���q�̕ی�҂��A�q�ǂ����w�Z�ł̐������y����ł��邱�Ƃ��킩��ƒS�C�ɍD���������Đڂ��Ă����悤�ɂȂ�܂��B�f���̃v�����g�ނ�R�~���j�P�[�V�����u�b�N��J�[�h�Ȃǂ̋��ނ��H�v���邱�ƂŁA�q�ǂ��B�Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����͂��܂��ł���悤�ɂȂ��Ă����܂��B��������邱�Ƃɑ����Ȃ�Ƃ����Ԃ͂�����܂����A����ƂȂ��Ƃł͓V�ƒn�قǂ̍����o�Ă���ł��傤�B�R�~���j�P�[�V�����́A�q�ǂ��B�ɂƂ��Ĉ�ԑ�Ȃ��̂ł��B �p�X�@����̊w�K�\�t�g�����͖̂����H �` �@���́A�u���Ԃ̊w�K�v�łP�O�b��P���Ȃǂ��q�ǂ��B���ڂŌ��đ̊��ł���悤�Ɍ�����u�^�C�}�[�v�����[�r�[���[�J�[�ō��܂����B���̃^�C�}�[�͍�Ɗw�K���ł��g������̂ł��B�z�[���y�[�W�r���_�[���g���č�������̂ɂ́A�u�����̊w�K�v�E�u�d��̊w�K�v�E�u���Ƃΐ}�Ӂ���b�𑝂₷���Ƃ̊w�K�v�E�u���̉��H�@�����ҁv�E�u���̉��H�@���퐶���ҁv�E�u�N���̊w�K�v�Ȃǂ����܂����B �@�q�ǂ������̂��Ƃ��悭�m���Ă��鋳�������ȒP�ȃ\�t�g�́A�d�q�����^���j�^�[�ƃp�\�R�����Ȃ��邱�ƂŎg���鎩��\�t�g�ɂȂ�܂��B�v���O���}�[�����悤�ȓ���\�t�g�łȂ��Ă������̂ł��B�ނ���ȒP�����炱���A�q�ǂ��B�ɂ��������₷�����̂ɂȂ肦��̂ł��B �p�P�O�@���ށE������g�����i�q�ǂ������j�ɗ����čl������Ăǂ��������ƁH �` �@������č�������炢���̂ł͂Ȃ��̂ł��B�g���q�ǂ��B�����L�������Ȃ�悤�Ȃ��̂ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B����͓�����Ƃł͂Ȃ��A��`���ŏ��ȃC���X�g���`���Ȃ��̂ł���A�t���[�̃C���X�g�W���g������ʐ^���g�����肷������̂ł��B �@�؍ނō�������̂͊p�𗎂Ƃ��Ċۂ݂�������T���_�[�ʼn���������ēh�����邱�ƂŁA�d�オ�����������������Ŏq�ǂ��B���P�K������悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂��B�ǂ�ȋ��ށE����ł������y���L��A�N�����G�̋���g���Ă��ꂢ�ȐF��h�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�g���͎̂q�ǂ��B�ł�����A�ł��邾�����S�ł��ꂢ�Ȏd�オ��ɂȂ�悤�ɁA�ł���͈͂ł����̂ł�����Ƃ�����Ă݂܂��傤�B �p�P�P�@���ނ̍H�v�ʼn����ς��́H �`  �@�w�K�ł��V�тł��A�u�ł��Ȃ��v���Ƃ������ƌJ��Ԃ��Ă����q�ǂ������́A���C���Ȃ������藝�����悤�Ƃ��Ȃ������肵�܂��B����͓��R�̂��Ƃł��傤�B�ł��A���ނ��H�v���邱�ƂŁA�u�ł��Ȃ��v���u�ł����I�v�ɕς����邱�Ƃ�����܂��B �@�w�K�ł��V�тł��A�u�ł��Ȃ��v���Ƃ������ƌJ��Ԃ��Ă����q�ǂ������́A���C���Ȃ������藝�����悤�Ƃ��Ȃ������肵�܂��B����͓��R�̂��Ƃł��傤�B�ł��A���ނ��H�v���邱�ƂŁA�u�ł��Ȃ��v���u�ł����I�v�ɕς����邱�Ƃ�����܂��B�@�Ⴆ�A�N���X��w�N�ŃV���{���ʗV�т����悤�Ƃ��Ă��A�������Ƃ����Ȏq�̓V���{���ʂ����܂���B�܂��A�j���ő傫�ȗւ��������ю������������̎g�킹�Ă��A�V���{���t����ւ����������o���Ƃ��Ƀp�`���Ɗ���Ă��܂����Ƃ������ł��傤�B �@�Ⴊ�����d���q�قǂ��܂��ł��܂��A������̍����g���ΏႪ���̏d�����q����ł��ȒP�ɂ�������̑傫�ȃV���{���ʂ���ɔ�����Ƃ��ł��܂��B���̕s���R�̂��q����ł�������������Ă��邾���ŕ����傫�ȃV���{���ʂ��ʂɍ���Ă���܂��B �@�܂��u�N�ł����ׂ�꒵�сv�́A�v���X�e�B�b�N���i�������j�̓꒵�тŁA�̂ǂ��ł�����~�߂邱�Ƃ��ł���̂ŁA�꒵�т��ł��Ȃ��q�ł����ׂ�悤�ɂȂ���̂ł��B�u�ł��Ȃ��v���u�ł����I�v�ɕς��Ƃ��̎q�ǂ������̊y�������ȏΊ�͍ō��ł��B����ȏΊ�����ނ̍H�v�ň����o���Ă����܂��傤�B �p�P�Q�@�q�ǂ������́u�������v���������Ȃ����Ăǂ��������ƁH �`  �@�X�v�[���┢�𐳂����������Ŏ��ĂȂ��E��������ӎv�\����]�肵�Ȃ��E�^����������E�ΐH�������E���̂������ɉE���������ނɌ����Ă����Ȃ��E���������Ă��܂����X�A�����������̗��ꂩ�猩����u�q�ǂ������̍������v���Ƃ͂�������ł��傤�B �@�X�v�[���┢�𐳂����������Ŏ��ĂȂ��E��������ӎv�\����]�肵�Ȃ��E�^����������E�ΐH�������E���̂������ɉE���������ނɌ����Ă����Ȃ��E���������Ă��܂����X�A�����������̗��ꂩ�猩����u�q�ǂ������̍������v���Ƃ͂�������ł��傤�B�@����Ƃ͔��Ɂu�ԃC�X�ɍ����Ă�����Q����Ԃł���ƁA�ˊO�ł͑��z����ɓ������ĂƂĂ��炻�����v�E�u�O���̎q�Ȃ̂œ��{�ꂪ�܂����ɘb���Ȃ�����A�C������`�����Ȃ��Ă��ǂ����������v�Ȃǂ́u�q�ǂ��B�̍������v�����������Ƃ͂���܂��H ����Ȏ��Ɂu�q�ǂ��B�̍������v�������Ă��������Ȃ��̂ł���A�������͉������P����܂���B �@�ŋ߂���ƎԃC�X�p�̓��悯������o�����悤�ɂȂ��Ă��܂������A�R�O�N�قǑO�ɂ͂���܂���ł����B�����ŁA�Ȃ��̂ł���Ȃ�Ƃ����悤�ƍl���č�邱�Ƃɂ��܂����B�ԃC�X�p�̓��悯�́A�g��Ȃ��Ƃ��ɂ͂͂����ď�߂�悤�ɂ������̂ł��Bῂ����E�����Ƃ����̂ł���A�P�������Ă���������̂ł͂Ǝv���邩������܂��A���̕s���R�̊w�Z�ł́A��̐搶�P�l�ŎԃC�X�Q��������̂ŁA�P�����Ƃ������Ƃ͂ł��Ȃ��̂ł��B �@�܂��A���ꂪ�Ȃ��q���g�ق̎q��O���l�̎q�ɂ̓R�~���j�P�[�V�����u�b�N�����g���悤�ɂ��Ă��܂����B�Ȃɂ��u�����Ă���v�q�ǂ��B�̗l�q������ꂽ��A�l���Ă݂܂��傤�B�����ʼn����v�����Ȃ��Ă��A�搶���Ƙb�����苳�ށE����̃z�[���y�[�W���瓚�������邩������܂���B �p�P�R�@�s�̂̋��ށE����Ǝ���̋��ށE����̈Ⴂ�́H �` �@�w�Z�ł͗\�Z�������Ă��܂�����A�D�揇�ʂ̒Ⴂ���̂͂ǂ����Ă��w�����Ă��炦�Ȃ��Ȃ�܂��B�܂��A�w�����Ă��炦�Ă���]�̐������낦�邱�Ƃ͓���̂�����ł��傤�B���`�̔������ł͗���Ă��A�H�v��������P���~�ȏシ��s�̕i�Ɠ����@�\�̋��ށE��������P�O�O�~�ō��܂��B �p�P�S�@�X���[���X�e�b�v���ĉ��H �` �@���̊w�K�ł��̎q�ɂ͂����܂ł����Ăق����Ƃ����ڕW���l����Ƃ��A�ŏI�I�ȉۑ�B���܂ł̒i�K�𐔒i�K�ɂ��āA�u�ł����v�E�u�킩�����v�Ƃ����o�����܂��Ă����邱�Ƃ���Ԃ̑����ł��B �@���̎q�̂������悭�ق߁A�����S�ʂɎ��M�����Ă�悤�ɂ��邱�Ƃ��A�����𑣂������Ƃ���Ȃ��Ƃł��B���ށE������X���[���X�e�b�v���l���āA�ЂƂ̊w�K�Ő���ނ̂��̂��l���ėp�ӂ��ׂ��ł��B���ꂪ�ł����玟�͂���Ƃ����悤�ɁB �p�P�T�@�؍H���ł��Ȃ��B�ł��A���ށE�������肽���Ƃ��́H �` �@�E�̎ʐ^�́A���ʂł��ƔɌ�����������A��d�����̂����Ł�����E���ɐ��č��`�ٕ̕ʔՂł����A �����Ƃ͂��݂ƃA�N�����G�̋�ō�������̂ł��B���̃X���C�h�Ղ������ō�������̂ł��B �@���̔����g�����J�[�h�̖��̓��̏o��u�p���`�{�b�N�X�v�͎s�̕i�͂P���~�ȏサ�܂����A���삷��R�O�O�~���x�ō��܂��B�H�v����ʼn\���͍L����܂���B �p�P�U�@�Ȃ��Ȃ����ސ���̃A�C�f�A�������Ȃ��B�ǂ������炢���́H �` �@�S���̐搶���F�X�ȋ��ށE���������Ă��܂��B�C���^�[�l�b�g�ł́A�l��F�X�Ȋw�Z�Łu���ށE����̏Љ�v�����Ă��܂��B�܂��A���ʎx������̋��ށE�����̔����Ă�����c�m�s�̋��ރJ�^���O�i�������ɒu���Ă��鋳�ރJ�^���O�Ɠ����ł��B�j�����邱�Ƃ��ł��܂��B �@�����A�w�ǂ̏��͂����̋��ށE����̍����܂ł͍ڂ��Ă��܂���B���������Ă݂悤�Ǝv���Ă��������킩��Ȃ��Ă͍��܂��A���̃z�[���y�[�W�u���ʎx���w�Z�̎��Ƃɖ𗧂��ށE����v�ł́A�������ڂ��Ă��܂��B �@Internet�Œ��ׂ���{���āA�������̂�^���邱�Ƃ���n�߂�Ƃ悢�ł��傤�B�_�C�\�[�Ȃǂ̂P�O�O�~�V���b�v��`���̂��A�C�f�A���̖��ɗ����܂��B�����A�ΏۂƂȂ邨�q����͓��R�Ⴂ�܂�����A�����̒S�����邨�q����ɍ����悤�ɂ�����Ƃ������ǂ��K�v�ɂȂ�ł��傤�B �p�P�V�@���ގ�����t�ō����Ă��邯��ǁA�ǂ������炢���́H �`   �@�w�Z�ł́A�w���̏I��育�Ƃɋ��ގ��̕Еt�����s���āA�����g��Ȃ��悤�Ȃ��̂͏��������肵�Ă���Ǝv���܂����A����ł����̊Ԃɂ���t�ɂȂ��Ă���̂����ގ���������܂���B �@�w�Z�ł́A�w���̏I��育�Ƃɋ��ގ��̕Еt�����s���āA�����g��Ȃ��悤�Ȃ��̂͏��������肵�Ă���Ǝv���܂����A����ł����̊Ԃɂ���t�ɂȂ��Ă���̂����ގ���������܂���B�@����̋��ށE�������鎞�ɂ́A���[�X�y�[�X���Ƃ�Ȃ��Ƃ����_���d�v�ɂȂ�܂��B����������G��`������p��������������I�́A���ɓ\��X�y�[�X���Ƃ�܂���B�g��Ȃ��Ƃ��ɂ͐܂肽���߂�̂ŁA�X�ɃX�y�[�X���Ƃ�Ȃ��Ȃ�܂��B�N�ł����ׂ�꒵�т��g�ݗ��Ď��Ȃ̂łR�{�̖_�ɂȂ�܂��B �@�܂��A�܂肽���߂��Ԃ́A�g��Ȃ��Ƃ��ɂ͏��ŘL���̋��ɒu���Ă����܂��B �@���ށE����̍H�v�ŃX�y�[�X���Ƃ�Ȃ����ށE��������悤�ɂ���A���ގ��͂����ɂ͈�t�ɂ͂Ȃ�Ȃ��Ȃ�ł��傤�B �p�P�W�@���ށE������Ɏq�ǂ��B�ɉ������Ȃ����Ăǂ��������ƁH �` �@���ށE������Ɏq�ǂ������ɉ������Ȃ��B�ł��A�����ɒ��߂Ȃ��B�E�E�E�ꌩ��������悤�ł����A�܊p��J���č�������̂�����Ƃ����ČŎ������肵�Ȃ��Ƃ����̂́A���q����B��l�ЂƂ肪��������̂ŁA���̋��ށE����`����ɍ����Ă��Ă��a����ɂ͍���Ȃ��Ƃ������Ƃ͂悭���邱�Ƃł��B �@�܂��A�����������炢�ł́A���̑���@���킩��Ȃ��Ȃǂ̗��R�ňꌩ�S���Ȃ��悤�Ɍ����邱�Ƃ�����܂��B�g�������킩��₷�������铙�A�w���̎d�����悭�l���Ă�����߂Ȃ��Ŏg���Ă����܂��傤�B �p�P�X�@�Ⴊ���̏d�����q����ɂ́A�����w���̎肪����Ƃ�������́H �` �@�Ⴊ�����d�x�̂��q����ɂ́A���̎q�̍D���Ȃ��́i���⊴�G��F��e���r�̔ԑg��G�{��D���ȐH�ו����j���w�K�⋳�ށE������̃q���g�ɂ���Ƃ����ł��傤�B �@���q����B�̍D���Ȃ��Ƃ��肪����Ƃ��Ă����A���̒��Ɋw�K�ۑ��ݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B�������点�����ł͂Ȃ��A���ꂩ������Ă������Ǝv���ΔY�ނ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�q�ǂ������́A�����̍D���Ȃ��Ƃ͌�����܂��A�����������Ă���܂�����B �p�Q�O�@�f�W�^���@��̊��p�Ɩ��_���ĉ��H �` �@���o������d�q���E�X�}�z�E�p�\�R����f�W�J���Ȃǃf�W�^���@�킪�w�Z�ł��g�߂Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂������A�����͍����Ȃ��̂Ȃ̂Ŋe�w�Z�ɕK�v�Ǝv���鐔�̓����ɂ͎����Ă��Ȃ��̂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B���̕s���R��ӁE�W�w�Z�Ȃǂ̊w�Z�ł́A���ށE����Ƃ��ĐϋɓI�Ɋ��p����悤�ɂ��Ă����������̂ł����A�m�I�̊w�Z�ł͂��̂����q����������̂ŁA����ł͓���ʂ�����ł��傤�B �@�f�W�^���@��̊��p�ɂ��ẮA����ʼnĂɍs���Ă���u�M�B���ʎx������J���t�@�����X�v����X�搶�i�������ʎx�����瑍���������j�������ǒ������Ă���u�}�W�J���g�C�{�b�N�X�v�̎�Â��錤�C��i�e��̃X�C�b�`���̎��Z�u�K��j�ɎQ�������ƁA�f�W�^���@��̊��p�̍ŐV����X�C�b�`�̐�����w�Ԃ��Ƃ��ł���ł��傤�B �@�ŋ߂͓�����w�̐�[�Ȋw�����Z���^�[�̛ܟ��搶�̊J������Microsoft�̃Q�[���@�̃L�l�N�g�����p������ԃX�C�b�`�i�ǂ��ł��X�C�b�`�j�Ȃǂ�����܂��B����X����E���������E�w�����ق�̏������������A��ԂɃX�C�b�`���ݒ�ł���f���炵�����̂ŁA�㎈�ɏd�x�̏Ⴊ���̂���q�ǂ������ł��X�C�b�`�����`�悪�X���[�Y�ɂ��ł�����̂��J������܂����B�����A���o�V�тɏI�n���Ă���F���ʂ̏Ⴊ�����d�����q����ɂ́A����͓���悤�ł��B �p�Q�P�@�����̊w�K�̋��ނ͖{���H�U���ǂ����������H �@��������̂�����{���Ƒ傫�����ɂ������ō�����������g�������Ƃ�����܂����A�q�ǂ������̏W���͂�w�K�ɑ���^�������A�{�����g���������e�i�ɗǂ���������ł��B���A�v�����g�w�K�ł����̉摜���g���ꍇ�́A�ł��邾���{���̂����i�P�O�~�E�P�O�O�~���j�Ɠ����T�C�Y�ɂ���Ƃ����ł��傤�B �@����ނ��̃T�C�Y�ň�����Ė{���ƍ��킹�Ă݂āA�����傫���̂��̂�I�ׂ��������ł�����A��Ԃ͐ɂ��܂Ȃ����Ƃł��ˁB�搶���A���ɂ����̎ʐ^��\���Ă����̐���������悤�ȂƂ��́A�q�ǂ��B�������₷���悤�ɑ傫�����̂��g���Ƃ����ł��傤�B �p�Q�Q�@�ǂ����āu���B�v�̊w�K���K�v�Ȃ́H �`�E���̕s���R�̎q�ǂ��B�́A���̂������Ƃ���Ɖߋْ�����������A�����Ă��Ȃ�������ƒʏ�̔��B�ߒ��Ƃ͈�����X���������܂��B�Ⴊ�����d���Ȃ�ƐQ������Œm�I�ɂ��d���ڂ������Ȃ�����Ȃ��Ƃ����q�ǂ��������������܂��B�]�ɑ傫�ȃ_���[�W���Ă��邱�ƂŃX���[�Y�Ȕ��B���W�����Ă��܂��Ă��邩��ł��傤�B �@�E�E�Ƃ͂����A���i�搶�����C�ɂȂ�͎̂��ǎ��̎w���@�i���c�X�e�[�W�j�╶���␔���l�������邽�߂̎w���@�A���o�w�K��}�H�E���p��̈�̎��Ɠ��e���ǂ����邩�Ȃǂ̂��Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�u���B�v�̊w�K�Ȃ�Ă��̖Z�����̂ɖ����B����낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃɖ��ɗ��́H�E�E�Ǝv���邱�Ƃł��傤�B �@�����A��b�w�K��̈�⊴�o�w�K�E����Z���E���H�w���i�������X�v�[���̎������Ȃǎ����̎g�����j����i�߂��ŁA�Ⴊ�����d���q�ǂ��قǁu���B�v�̊w�K�͏d�v�ȈӖ��������Ă��܂��B��ԊT�O�̔��B�E���̊T�O�̔��B�E��̎g�����̔��B�A���Ƃ̔��B�Ȃǂ�m��Ȃ��ƁA�u�ǂ����Ăł��Ȃ��́H�v�Ƃ��̗��R��������Ȃ�������A���̉��P�����Ă��Ȃ�����ł��B �@���i�͖Z�����ł��傤����A�ċx�݂Ȃǂ̎��Ԃ�����Ƃ��ɓ�����c���̔��B���w�ׂ�Ƃ����ł��ˁB�ŋ߂́A�{������œ��ʎx������̖{�I�i�R�[�i�[�j�����c���ۈ�Ȃǂ̖{�I�Ɂu���B�v�̖{���u���Ă���̂�ڂɂ��܂��B���́A�匎���X�́u�����̔��B�Ɛf�f�P�E�Q�v�E�u�c���̔��B�Ɛf�f�v�Ƃ����{��~�l�����@���[�₩������o�ŁE�S�ጤ�E�Ԃǂ��Ђ̖{�ŕ����܂������A�܂��͂킩��₷���{�����ɂ��Ă݂�Ƃ����ł��傤�B�u���B�̊w�K�v�́A���ʎx������Ƃ��������̍ł��d�v�ȓy��ł��B �p�Q�R �@�P�O�O�~�V���b�v�̗ǂ��Ƃ���Ƃ����łȂ��Ƃ���E�E�H �`�E�P�O�O�~�V���b�v�͋��ލ��̍ő�̖����Ƃ����Ă������Ƃ���ł��B���ލ���}�H�̍�i���{���ɕK�v�ȃJ���[�{�[�h�E�F���E��p���E�M�E���E�A�N�����E���ԁE�B�E�˂��E�_�E���[�v��S���E�G�̋�E���S�y�E��E�H��X�Ɖ��ł������Ă��܂��B�ɒ[�Ɍ����A�����Ă���������ׂ邾���ł����ނƂ��Đ��藧���Ă��܂��܂��B �@���X�搶�����g���i�{�[���J�b�^�[���A�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă�����̂̕����l�i�͏��X�����ł����A�X���[�Y�ɒi�{�[����邱�Ƃ��ł��܂��B�꒵�т̓���������̂��͓̂���ۂ߂đ܂ɓ���Ă�����͎̂g���Â炢�ł��B�ꂪ�˂���Ă��܂��Ă���̂ŁA���̂˂��ꂪ�Ȃ��Ȃ��Ƃ�Ȃ�����ł��B �@�܂��A�u���ԕ����v���̊w�K�Ŏd��̓����Ă���v���X�e�B�b�N�̔������p����̂͂����߂ł��܂���B�������Ɏd�肪�����ĂR������S�������ꂽ���̂́A���E��O�ƌ��Ƃ�������Ԃ��������āA�Ⴊ���̏d���q�ǂ������ɂ͂킩�肸�炢����ł��B�Ⴊ��������قǏd���Ȃ��q�ǂ��̏ꍇ�́A�d��̂������͂������ނɂȂ�Ǝv���܂��B�Ⴊ���̏d���q�ǂ������̏ꍇ�́A�P�̔��̎d����g���Ē��ԕ���������̂ł͂Ȃ��A�����̔����Ԋu�������ĕ��ׂ�ق��������ł��傤�B �@���i���ǂ��g�ݍ��킹�邩�ǂ��g�����l���鎞�ɁA�q�ǂ������̎��Ԃ��v���Ȃ���l����K�v������܂��B�P�O�O�~�V���b�v�́A���ɉ����ĕ����悤�ɂ���ƁA���ލ��̃q���g��������ł��傤�B �p�Q�S�@����������ċ��ނɂȂ�́H  �`�E�O�`�R�E�S�Ύ��̋���ł́A�ۈ�҂̍�邨�����Ⴊ���ނƂ��ė͂����Ă��܂��B�q�ǂ��������ڂ��P�����ėV�Ԓ��ŁA��ԔF�m�E�{�f�B�[�C���[�W�E��̑��쐫�E���ƂE�W�c�ł̋������Ȃǂ̗͂����߂Ă����܂��B �`�E�O�`�R�E�S�Ύ��̋���ł́A�ۈ�҂̍�邨�����Ⴊ���ނƂ��ė͂����Ă��܂��B�q�ǂ��������ڂ��P�����ėV�Ԓ��ŁA��ԔF�m�E�{�f�B�[�C���[�W�E��̑��쐫�E���ƂE�W�c�ł̋������Ȃǂ̗͂����߂Ă����܂��B�@�ł́A���ʎx���w�Z�̏��w���ł͂ǂ��ł��傤�B�s�̂̂�������́A��l�ŗV�Ԃ��̂������̂ŋ��ނɂ͂Ȃ�Â炢�ł��B �@���ނɂȂ邨������Ƃ����̂́A�F�B�ƈꏏ�ɗV�ׂ���̂������ł��B�I���Ă�{�E�����O�E�V���{���ʁE�{�[������E�ʏR��E�ςݖؗV�тȂǂ́A��l�ł���Ă����قNJy�����͂���܂��A�F�B��搶�ƈꏏ�ɂ��Ɗy�������̂ł��B�w�Z�ɂ���Â��Ȃ��Ă��܂����ςݖ́A�F��h�邱�ƂŎq�ǂ��B�̌����ėV�т����L����܂��B �@�I���Ă�{�[�������V���{���ʍ��Ȃǂ́A�r�̃R���g���[���̋��ނɂȂ�܂��B���܂��ł��Ȃ��q������ł��傤���A������������������̋��ނ��͂����܂��B�V���{���ʂ����Ȃ��q���A������̍��ŒN�ł���������̑傫�ȃV���{���ʂ�����ȂǁA�u�ł��Ȃ��E�V�ׂȂ��v���u�ł����E�y�����v�ɕς�����̂ł��B �@�F�B�ƈꏏ�ɂȂ��ėV�ׂ�Ɗy�������A�������낢����ꐶ�����ɂȂ�܂��B��������͂������ނ̂ЂƂƌ�����ł��傤�B �p�Q�T�@������w�ׂ͂����́H �`�E���ʎx������́A�w�K���Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ��c��ł��B�ǂ�Ȗ{��ǂ߂����̂��{������ł�������̖{��O�ɂ��ĔY�ނ��Ƃł��傤�B�w���Ⴊ�����̒S�����Ă��邨�q����B�ƈႤ����Q�l�ɂȂ�Ȃ��i�H�j�ȂǂȂǁA�{��I�Ԃ̂����J�ł��B �@���̓~�l�����@���[�E�W�A�[�X����V�ЁE�������ЁE��������o�Łi�N���G�C�c��������j�E�匎���X�E�S�ጤ�o�ŕ��E���w�p�o�ŁE�Ԃǂ��ЁE�w���E�����}���Ȃǂ̏o�ŎЂ̖{����I�Ԃ悤�ɂ��Ă��܂����B�����̏o�ŎЂ̖{�Ȃ�I��ŊԈႢ���Ȃ�����ł��B �@�܂��A��b�w�K�̋��ސ���Ɋւ��ẮA�̐����搶����Â���Ă����u��Q����b���猤����v�ɏ������Ă���搶�̖{��I�т܂��B �@������ԕ��ɂȂ����Ɗ������̂́A��y�⓯���Ƃ̉�b�ł����B�����Ɛg�߂ȂƂ���ɗǂ��搶������͂��ł��B�d���ŖZ�����������y�̐搶�Ƙb�������鎞�Ԃ��Ȃ��Ȃ����ĂȂ��ł��傤���A��w�̐搶�̘b���i�u���j�������A��������ɂ��Ďq�ǂ������̂��Ƃ��悭�m���Ă���g�߂Ȑ搶�̂ق����w�ׂ邱�Ƃ������̂ł��B �p�Q�U�@�����̊������ĉ�����n�߂�����́H �` �E���j�o�[�T���f�U�C����o���A�t���[���ӎ����������⋳�����̍\�����������Ă��܂����A�\�Z��ӎ��̖��������Ċw�Z�̋����̊����͂Ȃ��Ȃ��i��ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�������Ȃ��Ƃł��Ȃ��̂ł͍���܂����A����l���Ȃ��Ők�Ђ��z�肵���������ڂ��܂��s���K�v������܂��B�I�̏�ɂ��̂�u���Ȃ��E�L���ɂ��̂�u���ĒʘH�̕������߂Ȃ��ȂLjȑO���猾���Ă������Ƃł����A���ꂪ�O�ꂳ��Ă���̂��`�F�b�N���K�v�ł��B �@�Ⴊ���̏d�����q����̏ꍇ�́A�C���X�g�������Ă����̎��Ƃ����邩�킩��Ȃ����Ƃ������̂ł��B�ł���A�����ƃC���X�g�̓������J�[�h�̉��Ɏ��Ƃ��s���ꏊ�̎ʐ^�J�[�h���\���Ă���Ƃ����ł��傤�B�u���͂����֍s����B�v�Ǝʐ^�������Ȃ���b���Ƃ����ł��傤�B�ꏊ���킩��Ƃ����ʼn������邩�͏Ⴊ���̏d�����q����ł����\�킩����̂ł��B �@���̎��Ɩ���\���������E�C���X�g�J�[�h�́A���w���E���w���ӂ�ł͂����Ă��������ɂȂ�Ɠr�[�ɂȂ��Ȃ�܂��B�m�I�Ȗʂō������q����B�����w�Z�̓��ʎx���w����������Ă��邱�ƂŁA��������������q�ɌW�����Ƃ��ĔC����悤�ɂȂ邩�炩������܂���B �@�E�E�ł��悭�l���Ă��������B���w���E���w���Ŏ����ǂ߂Ȃ����q����͍������ɍs���Ă����͂킩��Ȃ��̂ł��B�Ⴊ���̏d���q��m�炸�m�炸�ɒu������ɂ��Ă��Ȃ����悭�l���Ă����������̂ł��B�q�ǂ������ɂƂ��ėǂ����Ƃ́A�m�I�ɍ����q�������łȂ��q�ɂ��킩��₷�����S�ȋ�Ԃ��Ӗ�����̂ł�����B �p�Q�V �}�H�E���p�̎��Ƃ͓���H  �`�E���p�n�̑�w�o�Ő}�H����p����ɂ��Ă���搶�͕ʂɂ��āA���������p�����łȂ����ʂ̋����ɂ́A���������邩�l����Ɠ��̒ɂ��Ȃ�̂��}�H�E���p�̎��Ƃł��B��̂����N�s���Ă����悤�Ȋw�K���e�����Ȃ��ĉ��Ƃ����Ă���Ƃ����̂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B�w�N���オ���Ă������悤�Ȏ��Ƃł����̂ł��傤���H�@��l���u�������낢�v�E�u�y�����v�Ǝv��Ȃ��悤�Ȏ��Ƃ͎q�ǂ������ɂ����N���N���͂�����Ȃ��ł��傤�B �`�E���p�n�̑�w�o�Ő}�H����p����ɂ��Ă���搶�͕ʂɂ��āA���������p�����łȂ����ʂ̋����ɂ́A���������邩�l����Ɠ��̒ɂ��Ȃ�̂��}�H�E���p�̎��Ƃł��B��̂����N�s���Ă����悤�Ȋw�K���e�����Ȃ��ĉ��Ƃ����Ă���Ƃ����̂�����ł͂Ȃ��ł��傤���B�w�N���オ���Ă������悤�Ȏ��Ƃł����̂ł��傤���H�@��l���u�������낢�v�E�u�y�����v�Ǝv��Ȃ��悤�Ȏ��Ƃ͎q�ǂ������ɂ����N���N���͂�����Ȃ��ł��傤�B�@�����͌����Ă��}�H�E���p�̒S���i�W�j�ɂȂ�A�u���ނ̈����o���v���Ȃ����Ƃ�Q���悤�ɂȂ�ł��傤�B��O���X�ł͂���܂����A���̃z�[���y�[�W�ɂ͗l�X�ȍ�i���{�ƍ������ڂ��Ă��܂��̂ŁA���̃z�[���y�[�W��{�Ȃǂƍ��킹�ĎQ�l�ɂ��Ă���������Ǝv���܂��B �@�܂��͐^���āu�����o���v�������������Ă����܂��傤�B���ނɂ��Ắu�����o���v��������A�}�H�E���p�͊y�������ƂɂȂ��Ă����܂��B �������̂͐^���āA�S������q�ǂ������ɓ��e�����킹�Ă����A�����̂��́i�u�����o���v�j�ɂ��Ă������Ƃł��B �p�Q�W�@����̋��ށE����̗ǂ��_�Ɩ��_���Ăǂ�Ȃ��ƁH �@�s�̂̂��̂�������̕����ǂ��_�́A�N�����q�ǂ��������߂��Ō��Ă��āA���̎q��̎��Ԃ�ۑ��m���Ă���搶������邩��ł��B�܂��A�w�Z�̗\�Z�����Ȃ��ė~�����Ă������Ȃ����ށE������H�v����łP���~����悤�Ȏs�̂̋��ށE������H�v����łR�O�O�~�`�T�O�O�~�ʂō�邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂�����̂����Ƃ���ł��傤�B�w�Z�Ŕ����ė~��������Ǘ\�Z�̊W�Ŗ����ȋ��ށE�����w�Z�ɂ͂��邯��ǐ������Ȃ��̂ŁA�w�K�O���[�v�̎q�ǂ������̐l�����~�����Ƃ������������ł��܂��B �@�Ђ邪�����Ė��_���l����ƁA����̋��ށE����͑�^�����Ȃǂ̑傫�����͕̂����̐搶�����͂����킹�č��Ȃ���ł��܂��A�w�ǂ̋��ށE����́A�l�ŊJ���E���삵�Ă��܂��B�l�������̂ł�����A������g���̂����̐搶�Ɍ���ꂪ���ł��B�������̂ł���A�N���X��w�K�O���[�v��w���S�̂ŋ��L�ł���悤�ɂ��Ȃ��ƕ�̂���������ɂȂ�܂��B �@��������������ނ����玩�������Ŏg���̂ł͂Ȃ��A�����̐搶�����A�e�l����������ށE����������Ƃ������̂ɂ���悤�ɘb�������A�݂�Ȃ̂��̂ɂ���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B���ꂪ�q�ǂ��B�ɂƂ��Ă��ɂȂ�ł��傤�B �p�Q�X�@�h���肪�����ւ�B�Ȃɂ��������@�͂Ȃ��́H �@�h��͏o�������Ƃ������̂ł͂���܂���B��l�ЂƂ�̂��q����̊w�K�ۑ�͈Ⴄ�̂ł�����A���R��l�ЂƂ�̏h��̓��e���ς���Ă���͂��ł��B�����������q�ǂ��B�̂��Ƃ�z�����Ă��Ȃ��s�̂̃v�����g��C���^�[�l�b�g�Ō������v�����g�ɏh��Ƃ��Ă̈Ӗ�������̂��悭�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �@�v�����g���́A��������������ނƂ��Ď����́u�����o���v�𑝂₵�Ă������̂ɂȂ�܂��B���߂͂����ւ�ł�������f�[�^�͐ς���ς����č��Y�ɂȂ�킯�ł��B�E�E�Ƃ͂����A�����������S������Ȃ����̂��Ƃ����v���͎c��܂��B �@���́A���w���ɂ������ɍ���E���w�O���[�v�̐搶���Ƙb�������Ċw�K�O���[�v�̎q�B���u��b�w�K�E���ƕ����̊l���E�P��ƊȒP�Ȍv�Z�v�̂R�i�K�ɕ����A�����Ńv�����g�����s���A���̃f�[�^���w���S�̂ŋ��L����悤�ɂ��܂����B�v�����g�̓��e��b�������Ă���̂ŁA���̒i�K�̎q�ɂ͂��̃v�����g���g����Ƃ������Ƃ��킩���Ă��܂��B����œ��X�̏h���ċx�݂̏h��ȂǁA��l�ł���邱�Ƃ�����h���]�蕉�S�Ɋ����邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B �p�R�O�@���ޥ�������鎞�ɁA����ƕ֗��ȓ�����Ăǂ�ȓ���H �`�E���ǂ܂��i�T���X�^�[����j  �E�����p���₻�����p�E�`�������̂̊p���ۂ��J�b�g���Ă���铹��Ńz�[���Z���^�[�╶�[��X�ɔ����Ă�����̂ł��B���ɂƂ��ăJ�[�h���Ɍ������Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B�͂��݂ŃJ�[�h�̊p��藎�Ƃ��Ċۂ݂�����̂͌��\��Ԃ�������܂��B��������p�������Ă����v�Ǝv���Ă���ƁA�J�[�h�̎l���̊p�Œɂ��v�������邨�q��������܂��B�����Ȃ�Ȃ��悤�Ɋp���ۂ����Ă����܂��傤�B �E�����p���₻�����p�E�`�������̂̊p���ۂ��J�b�g���Ă���铹��Ńz�[���Z���^�[�╶�[��X�ɔ����Ă�����̂ł��B���ɂƂ��ăJ�[�h���Ɍ������Ȃ����̂ɂȂ��Ă��܂��B�͂��݂ŃJ�[�h�̊p��藎�Ƃ��Ċۂ݂�����̂͌��\��Ԃ�������܂��B��������p�������Ă����v�Ǝv���Ă���ƁA�J�[�h�̎l���̊p�Œɂ��v�������邨�q��������܂��B�����Ȃ�Ȃ��悤�Ɋp���ۂ����Ă����܂��傤�B���I���t�@�̃J�b�^�[�}�b�g �@������J���[�{�[�h�Ȃǂ��J�b�^�[�Ő�Ƃ��ɁA���ɕ~���Ďg���}�b�g�ł��B�P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j�ł��������J�b�^�[�}�b�g���Ă��܂����A�����������Ďg���܂���B�T�C�Y�͐F�X����܂����A�`�R�T�C�Y�ȏ゠��Ɖ�p�����ۂɂ��g���₷���ł��B���[��X��z�[���Z���^�[�̕��[��R�[�i�[�Ŕ����Ă��܂��B�V������G�������}�b�g�ւ��Ɏg���Ă���l��������g���悤�ɂȂ�Ɨǂ����킩��܂��B ���t�H�X�i�[�r�b�g �@�w�Z�ɂ��؍H���ɂ���Ǝv���܂����A�F�X�ȃT�C�Y�������Ă͂��Ȃ��̂ŁA�l�ōw�����邵���Ȃ���������܂���B���̓���͊�b�w�K�̋��ލ��ł͕p�ɂɎg���܂��̂ŁA�����Ă���ƂƂĂ��֗��Ȃ��̂ł��B ���m�M�X  �E�m�M�X�́A���̑傫���𑪂�����ۖ_��X�e�����X�̊ǂ�����̊ǂ̂̑����𑪂����肷�鎞�Ɏg������ł��B�P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j�ł��v���X�`�b�N���̂��̂������Ă��܂��B�y�O�������ł́A�y�O�ɂ���ۖ_�̑����𑪂�����A���̃y�O�����錊�̑傫�������߂�̂Ɏg���܂��B�ʐ^�̂̂����́A�z�[���Z���^�[�Ŕ��������ł����A�_�C�\�[�̂��̂ł����v�ł��B�B �E�m�M�X�́A���̑傫���𑪂�����ۖ_��X�e�����X�̊ǂ�����̊ǂ̂̑����𑪂����肷�鎞�Ɏg������ł��B�P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j�ł��v���X�`�b�N���̂��̂������Ă��܂��B�y�O�������ł́A�y�O�ɂ���ۖ_�̑����𑪂�����A���̃y�O�����錊�̑傫�������߂�̂Ɏg���܂��B�ʐ^�̂̂����́A�z�[���Z���^�[�Ŕ��������ł����A�_�C�\�[�̂��̂ł����v�ł��B�B�����\�n�T�~ ���v�̎��  �E�v�̎�܂̓z�[���Z���^�[�̍H��ނ̏��Ŕ����Ă�����̂ł��B�l�i���������̂̕����A�v�����炩�Ŏ�Ƀt�B�b�g���܂��B�����̍��z�Ƒ��k���Ď荠�Ȃ��̂����߂�Ηǂ��ł��傤�B�v��܂́A�J�b�^�[�i�C�t��H����g���ۂɗ�����łȂ����ɂ͂߂�ƈ��S���������܂��B������ŃJ�b�^�[�i�C�t�����Ƃ���ƁA������łȂ����Œ�K��J���[�{�[�h�����p�����������邱�ƂɂȂ�̂ŁA������J�b�^�[�i�C�t��̂����蓙�������Ă��v��܂����Ă���ƃP�K���邱�Ƃ�����܂��B�f�肾�Ɛn�����ړ���������肷�邩��ł��B �E�v�̎�܂̓z�[���Z���^�[�̍H��ނ̏��Ŕ����Ă�����̂ł��B�l�i���������̂̕����A�v�����炩�Ŏ�Ƀt�B�b�g���܂��B�����̍��z�Ƒ��k���Ď荠�Ȃ��̂����߂�Ηǂ��ł��傤�B�v��܂́A�J�b�^�[�i�C�t��H����g���ۂɗ�����łȂ����ɂ͂߂�ƈ��S���������܂��B������ŃJ�b�^�[�i�C�t�����Ƃ���ƁA������łȂ����Œ�K��J���[�{�[�h�����p�����������邱�ƂɂȂ�̂ŁA������J�b�^�[�i�C�t��̂����蓙�������Ă��v��܂����Ă���ƃP�K���邱�Ƃ�����܂��B�f�肾�Ɛn�����ړ���������肷�邩��ł��B�@���܂Ŏg�������̂ň�ԗǂ������̂͊O�����̃X���j�[�̊v��܂ł����A����͂P�O���N�O�ɔ����ς����Ƃ��ɂV�O�O�O�~�߂������̂ŁA���ł͂Q�O�O�O�~�ʂ̂��̂��g���Ă��܂��B���\���Ղ��������̂ŁA�]�荂�����͍̂��z���������ł�����B �����~�l�[�^�[ �@�����I�Ȏd���������Ă����w�Z�ł́A�J�[�h�Ƀp�E�`�����Ă���ɂ��Ȃ���������܂���B�E�E����Ȃ�A�����������p�ɔ����Ă��܂����ق��������ł��傤�B�������̂ł͂���܂���A�Ƃɂ�����ł��F�X�ȃJ�[�h����邱�Ƃ��ł��܂��B  ���d���W�O�\�[ ���d���W�O�\�[�E�̂�����Ŕ��������̂͂���ǂ��ł��B�ۋ��́A�x�e�����̖؍H�̐搶�ł��P�K�����邱�Ƃ�����܂��B�d���W�O�\�[�͊ۋ��قNJ댯�ł͂���܂��A�d���W�O�\�[������A�̐ؒf����Ȑ��̐ؒf�A�v���X�`�b�N������ނ̐ؒf���ł��܂��̂ŁA���삷����ɂ͂����߂ł��B���͉��Ђ��g���܂������A���[�U�[�K�C�h�̂��Ă���{�b�V���̃W�O�\�[����Ԏg���₷�������ł��B ���N���t�g�̂�  �E�̂�����ɂ́A������Ƃ����Đn�����݂Ɍ�����ς��ĕ���ł��܂��B���̍H��p�̂̂�����́A�u�N���t�g�̂��v�Ƃ����悤�Ȗ��̂Ńz�[���Z���^�[�ɔ����Ă��܂����A���̃N���t�g�̂��͂����肪�Ȃ��̂ŁA�ʐ^�̂悤�ɔ�яo�����������Ƃ��ɉ��̔������邱�ƂȂ���яo����������ؒf���邱�Ƃ��ł��܂��B �E�̂�����ɂ́A������Ƃ����Đn�����݂Ɍ�����ς��ĕ���ł��܂��B���̍H��p�̂̂�����́A�u�N���t�g�̂��v�Ƃ����悤�Ȗ��̂Ńz�[���Z���^�[�ɔ����Ă��܂����A���̃N���t�g�̂��͂����肪�Ȃ��̂ŁA�ʐ^�̂悤�ɔ�яo�����������Ƃ��ɉ��̔������邱�ƂȂ���яo����������ؒf���邱�Ƃ��ł��܂��B�@�����ł͖_�����̔ɖ��ߍ��ގ��̎g�������Ƃ��Ă����܂������A�̔�������Ă���Ƃ��ɏ��ɂł��Ȃ��Ŕ��͂ݏo���Ă��܂������ɂ��g���܂��B�n�͂ƂĂ����Ȃ₩�Ŏʐ^�̂悤�ɉ����Ȃ���悤�ɂ��Ďg�����Ƃ��ł��܂��B�P�O�O�O�~�ʂō������̂ł͂Ȃ��̂ŁA���ށE����̐���Ŗ𗧂v���܂��B �p�R�P�@�Ђ炪�Ȃ̕����́A�u���ȏ��́v�H�E�u�S�V�b�N�́v�H 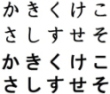 �`�E�Ђ炪�ȗ��K���s������Ђ炪�ȃv�����g����鎞�ɁA�����u���[�����B�v�E�E�Ǝv�����Ƃɏ��̂�����܂��B���ʎx���w�Z�Ő搶�����悭�g���Ă���̂́u�S�V�b�N�́v�̂悤�ł����A���w�Z�Ȃǂł́u���ȏ��́v���g���Ă���悤�ł��B�u���ȏ��́v�ɂ��F�X��ނ�����̂ŁA���Ăǂꂪ�����̂�����ƔY�݂܂��B�u���ȏ��́v�́A�����Ɂu�Ƃ߁E�͂ˁE�͂炢�E�ނ��сv�Ȃǂ�����A���ʎx���w�Z�̂��q����B�ɂ͕����l���̃n�[�h�����グ��ǂɂȂ�悤�Ȃ̂ŁA�Ƃ߁E�͂˓����ȗ��������悤�Ȍ`�́u�S�V�b�N�́v�̕����悭�g����悤�ł��B �`�E�Ђ炪�ȗ��K���s������Ђ炪�ȃv�����g����鎞�ɁA�����u���[�����B�v�E�E�Ǝv�����Ƃɏ��̂�����܂��B���ʎx���w�Z�Ő搶�����悭�g���Ă���̂́u�S�V�b�N�́v�̂悤�ł����A���w�Z�Ȃǂł́u���ȏ��́v���g���Ă���悤�ł��B�u���ȏ��́v�ɂ��F�X��ނ�����̂ŁA���Ăǂꂪ�����̂�����ƔY�݂܂��B�u���ȏ��́v�́A�����Ɂu�Ƃ߁E�͂ˁE�͂炢�E�ނ��сv�Ȃǂ�����A���ʎx���w�Z�̂��q����B�ɂ͕����l���̃n�[�h�����グ��ǂɂȂ�悤�Ȃ̂ŁA�Ƃ߁E�͂˓����ȗ��������悤�Ȍ`�́u�S�V�b�N�́v�̕����悭�g����悤�ł��B�@�����ō���̂́A�S�V�b�N�̂́u���v�E�u���v�̂̂悤�ȕ����ł��B���ȏ��̂ł���Η���Ă��镔�����A�����Ă��Ă������Ă��܂��B�����ŃS�V�b�N�̂��g���ꍇ�́A�u���v�u���v�Ȃǂ̕����́A�A�����Ă��Ȃ��`�ɕς��Ďg����   ���ɂ��Ă��܂����B ���ɂ��Ă��܂����B�@�������邱�ƂŁA���ȏ��̂Ƃ̈Ⴂ�����Ȃ�����悤�ɂ����킯�ł��B���q����B���S�V�b�N�̂Ƌ��ȏ��̂̈Ⴂ�Ɍ˘f�����Ƃ����炻���ƍl��������ł��B���̓_�Ɋւ��Ă͖����ɓ��͌�����Ȃ��̂ł����A���͕����l����ڎw���Ă���q�ǂ��B�ɂ킩��₷���Ƃ������R�ŁA�v�����g�ł̕������K�̓S�V�b�N�̂��g���悤�ɁA�m�I�ɍ����w�K�O���[�v�̏ꍇ�́A���ȏ��̂Ŏw�����܂����B �p�R�Q�@�J�[�h�̓p�E�`���Ȃ��Ƃ����Ȃ��́H �`�E�����J�[�h�E�����̃J�[�h�E�G�J�[�h�Ǝ��ƂŃJ�[�h�����ނƂ��Ďg����ʂ͑����ł��傤�B���̃J�[�h�ł����A�g�����q����̐��i�i���₩�Ȑ��i���C���������������j��Ⴊ���̒��x���l���č��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B���₩�Ȑ��i�̂��q����̏ꍇ���́A���ɃJ�[�h�Ƀp�E�`���Ȃ��Ă������Ǝv���܂��B���ʁA�C�������������q�����Ⴊ���̏d�����q����̏ꍇ�́A�J�[�h������j�낤�Ƃ���̂ŁA�J�[�h�̓p�E�`���Ďl�����ۂ߂�K�v������܂��B �@�p�E�`���Ă���Ɣj�����Ƃ��ł��܂���̂ŁA���x���j�����Ƃ��Ă��j���Ȃ��Ƃ킩��ƁA�����j�����Ƃ͂��Ȃ��Ȃ�܂��B�J�[�h���p�E�`���������������ǂ����́A���q����̏�Ԃ����čl����Ƃ������Ƃł��ˁB �@���ꂩ��A��w�̎g�������������Ȃ����q����̏ꍇ�́A�J�[�h�Ɍ��݂��Ȃ��Ǝ��Â炢�ł��傤���A�J�[�h�̑傫�����l����K�v������܂��B����́A�X�̂��q����ɍ��������ނƂ����ϓ_����l����Ƃ������Ƃł��B �p�R�R�茳�����Ȃ��q�̎w���͂ǂ���������́H 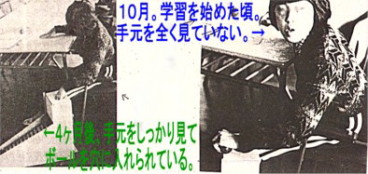 �`�E�Ⴊ�����d���Ȃ�ƁA�������ӂ���Ď��i�茳�j�����悤�Ƃ��Ȃ����q�����܂��B�����Ă���Ƃ�����������O���������ĕ����̂ł͂Ȃ��A�V��̕������Ă��Ď��U���Ă���̂ŁA�ǂ������Ă���̂��킩��Ȃ��悤�Ȋ����ŁA�ǂ���̂ɂԂ���̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ɂȂ邨�q����B�ł��B �`�E�Ⴊ�����d���Ȃ�ƁA�������ӂ���Ď��i�茳�j�����悤�Ƃ��Ȃ����q�����܂��B�����Ă���Ƃ�����������O���������ĕ����̂ł͂Ȃ��A�V��̕������Ă��Ď��U���Ă���̂ŁA�ǂ������Ă���̂��킩��Ȃ��悤�Ȋ����ŁA�ǂ���̂ɂԂ���̂ł͂Ȃ����ƐS�z�ɂȂ邨�q����B�ł��B�@��b�w�K�ŋʓ����`�ٕ̕ʂ��s�����Ƃ��Ă��A����ȏ�Ԃł�����w�K�ɂȂ�܂���B�E�̎ʐ^�̂��q����̏ꍇ�́A�u�ʓ���v�œ��ꂽ�ʂ���������̓S�Ղ̏��]�����ĉ�����悤�ɂ����Ƃ���A�����o�邱�Ƃɂ���Ă͂��Ɖ�ɕԂ����悤�Ɏ�������悤�ɂȂ�܂����B���ꂪ�y���������̂��A�x�ݎ��Ԃɂ���肽����悤�ɂȂ�A�������������Ă��̋ʓ���̏��܂ōs���悤�ɂȂ�܂����B���̎ʐ^�̉E�����茳��S�����Ă��Ȃ��Ƃ��̂��̂ŁA�����͌��̈ʒu�����čs���悤�ɂȂ������̂��̂ɂȂ�܂��B �@ �@���̋��ނ́A�����̐搶�i���w�N�j����u�������Ȃ��q�����č����Ă���̂ł����A�������ނ͂���܂����H�v�Ɨ��܂�č�������̂ł��B �@�w�����n�܂�ƁA���܂Ŏ茳��w�nj��Ȃ��œK���ɑ召�ٕʂ�F�ٕʂ�����Ă������k���A�u����H�v�Ƃ����\��ɕς������������茩��悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B���̂��Ƃ��_�@�ɂȂ��āA���퐶���S�ʂŎ������ړI�����������茩��悤�ɂȂ�A�ی�҂��ƂĂ�������ł��B�茳�����Ȃ����q����ɂ́A�茳�����悤�Ƃ������ނ���̔������K�v�Ƃ������Ƃ�������܂���B �p�R�S�@iPad��^�u���b�g�ŗǂ��\�t�g���g���Ă��邾���ł����́H �`�E���ʎx���w�Z�ł́A�p�\�R�������łȂ�iPad�̂悤�Ɏg���₷���f�W�^���@�킪��������������Ă��Ă��܂��BiPad��Windows�̃^�u���b�g��Nintendo�̂R�c�r��X�}�z�Ŏg����Ђ炪�ȁE�J�^�J�i�̏��������K��R�~���j�P�[�V�����Ɏg����A�v����^�C�}�[�ȂǁA�D�ꂽ�A�v�����N�X�o�ꂵ�Ă��Č���ł��d�Ă��邱�ƂƎv���܂��B �@�L���̃A�v������t���[�̃A�v���ƐF�X����܂����A����i�K�Ŏg����̗v�]���W�߁A���ǂ����̂��ƍl���č���Ă��Ă��A���q����B�͐獷���ʂł�����S�Ă̂��q�����������悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł��B���葤�́A�F�X�ȗv�]���čX�ɗǂ����̂�����Ă��������ƍl���Ă���͂��ł�����A�搶�������X�����Ă���v�]�𐧍삷�鑤�ɓ`���Ă������ׂ��l���鎞���ɂȂ��Ă��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@�ЂƂ̊w�Z�ł�����l���ďW�Ă��ǂ��ւȂ���Ηǂ��̂�����Ƃ���ł��B�S���̍Z�����S���A�Ȃǂ��������ƂŁA�g���葤�ƍ��葤�i�x�m�ʂȂǂ̊�Ƃ�t���[�\�t�g������Ă���l�j���Ȃ��d�g�݂��ł��Ȃ����̂��Ǝv���܂��B���ǂ����ނ�A�v���́A�����̐l�̈ӌ���]�����琶�܂�Ă������ł��B �p�R�T�@�p���̈����q�ς���ɂ́H  �@�ƒ�K��ɍs���Ƃ悭��������̂́A�S�����邨�q�����K�����藎����悤�ɂ��ă\�t�@�ɍ����Ă���p�ł��B���ꂳ��E����������킩���Ă��āu�����ƍ���Ȃ����B�v�ƌ����܂����A����I�ɂ��������������p���ł��邱�Ƃ��킩���ʂł��B �@�ƒ�K��ɍs���Ƃ悭��������̂́A�S�����邨�q�����K�����藎����悤�ɂ��ă\�t�@�ɍ����Ă���p�ł��B���ꂳ��E����������킩���Ă��āu�����ƍ���Ȃ����B�v�ƌ����܂����A����I�ɂ��������������p���ł��邱�Ƃ��킩���ʂł��B�@�܂��A�����̃C�X�ɍ���ƁA���K�����艺��������Ԃő���O�ɂǁ[��Ɠ����o���Ă�����A�������ɏ悹�Ă�����Ƃ������Ƃ����w���̒�w�N�ӂ�ł͓��ɖڂɂ��܂��B�����p���Ƃ����̂́A���ʂŌ����������ւ��܂����̂Ă����ɑS�g���s���ƈ���������悤�ȏ�Ԃ������ł��B�����Ă���ꍇ�́A�����ꂪ���ʂɂ���������A�w������ɔw���ƍ������s�^�b�Ƃ��č�����オ�s���Ə�Ɉ���������p���������ł��B �@�܂��A�q�ǂ��B�̑̌^�ɍ���Ȃ��֎q����ɂ��ẮA�w�Z�̈֎q�ł̓l�W�̏ꏊ��ς��ăC�X����̍�����ς��܂����A����ɂ͌��x������̂ŁA�������q����ɑ̂̑傫���q�ɂ͍���Ȃ��֎q������o�Ă��܂��܂��B�̂��傫���q�̏ꍇ�́A��̊w������傫���T�C�Y�̊��ƃC�X�B���邵������܂���B���������q����̏ꍇ�́A�C�X�ɍ����đ������Ȃ��ꍇ��z�V�Ŋ����������Ďg���Â炢���ɂ́A���̉��ɑ�ɂȂ����u���悤�ɂ��Ă����܂��B�G���▟��{�ȂǑ傫���⍂���������ł�����̂������ł��傤�B �@�悭�̔����g���Ă����ʂ����܂����A�����̑������ł��Ȃ��̂Ŗ{���g�����������ł��B�܂��A���ʂ��L�����Ĕw���E����w������Ƀs�^�b�Ƃ����Ȃ��ꍇ�́A�G�����ō�������̂�u���Č��Ԃ��Ȃ����悤�ɂ���ƁA�w�����s�b�g�L�тĂ����܂��B �@�q�ǂ��B������I�ɂ����p�����ӎ��ł���悤�Ɏw�����Ȃ���A�q�ǂ��B�ł͂ǂ����邱�Ƃ��ł��Ȃ������͐搶�����J�o�[���Ă����Ă����܂��傤�B �p�R�U�@�u�J���^�V�сv�̍H�v���ĂȂɁH   �`�E���Ƃ̊w�K�i��b�𑝂₷�j�₨�����̗V�тƂ��āu�J���^�v�͂悭�s������̂ł����A�K���ƌ������炢�ɖ�肪�N����܂��B����́A�J���^�̎D�������������q�Ɨ]����Ȃ��q���o�Ă��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B �`�E���Ƃ̊w�K�i��b�𑝂₷�j�₨�����̗V�тƂ��āu�J���^�v�͂悭�s������̂ł����A�K���ƌ������炢�ɖ�肪�N����܂��B����́A�J���^�̎D�������������q�Ɨ]����Ȃ��q���o�Ă��Ă��܂��Ƃ������Ƃł��B�@�������������ɂ́A���ɂU�l�̂��q����B�ŃJ���^���s���ꍇ�́A�J���^�̎D�͓������̂��U�����p�ӂ��܂��B�i�G�D���Q�O��ނ���̂ł͂���A�Q�O��ށ~�l�����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�j �@�����āA��x�Ɏ���D�͂P�l���P���Ƃ���悤�ɂ��܂��B�������邱�Ƃł������D�����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��q���A�]�T�������ĎD������悤�ɂȂ�܂��B�ܘ_���X�Ƒ҂킯�ɂ͂������܂���A������x�҂��Ď��̎D�ɂ����悤�ɂ��܂��B���ʂƂ��Ď���D�̖����́A�����������q�Ƃ��̔����Ƃ��P�^�R���炢�̎q���o�Ă��܂����A���Ȃ������q�ɂƂ��ẮA���ꂪ���Ɋ撣��ۑ�ɂȂ�킯�ł��B�����������q�ɂ́A�搶�����Ă���ǂݎ�ɂȂ��Ă�����Ă������ł��傤�B�X�̂��q����̉ۑ���l���āA�ǂ��i�߂Ă����������z����������̂ł��B  �@�J���^�Ƃ������ނ̐���ł́A���w���ł͎q�ǂ��B���D���ȃ��[������J���[���C�X�E�݂��́u�H�ו��v��①�ɂ�d�b�E�d�q�����W�Ƃ������u�g�̉��̐g�߂ȓ���v�Ɓu�F�B��搶�̊�̃J�[�h�v�����܂��B �@�J���^�Ƃ������ނ̐���ł́A���w���ł͎q�ǂ��B���D���ȃ��[������J���[���C�X�E�݂��́u�H�ו��v��①�ɂ�d�b�E�d�q�����W�Ƃ������u�g�̉��̐g�߂ȓ���v�Ɓu�F�B��搶�̊�̃J�[�h�v�����܂��B�@�q�ǂ��B�������̂Ȃ��悤�Ȃ��̂��b�Ƃ��đ��₵�Ă��������Ȃ�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����̂͏����܂��B�F�B��搶�̃J�[�h������̂́A�N���X��w�N�̈Ⴄ�q�B���W�܂�w�K�O���[�v�ł́A�S�C��N���X���C�g�ȊO�͂悭�킩���Ă��Ȃ�����ł��B�J���^��ʂ��āA�搶��F�B�ɂ������������Ă��炢��������ł��B �@���w���̍��w�N�⒆�w���Ŏg���J���^���ł́A�J���^�ɃC���X�g��ʐ^�����łȂ�����������悤�ɂ��܂��B���������܂������Ȃ��ł���q�ɂ͕�������J�[�h���g���悤�ɂ��A������������悤�ɂȂ����q�ɂ͕����̗��������Ă��Ȃ��J�[�h�Ɏ����ŕ������������ނ��ƂŎ��������̃J�[�h����邱�Ƃ��ł��܂��B �@ �@�܂��A�e�J�[�h�͌����₷�����₷���悤�ɑ傫�߂ɂ���Ƃ����ł��傤�B���\�Ɉ����Ă��j�ꂽ��܂�Ȃ������肵�Ȃ��悤�Ƀp�E�`���āA�l���̊p�͒ɂ��v�������Ȃ��悤�Ɋۂ����܂��B �p�R�W�@�@�C���X�g����肭�`���Ȃ��B�����Ƃ��ꂢ�ɕ`������@�͂Ȃ��́H   �@�G�����ӂȐ搶�͏��Ȃ��ł��傤����A�C���X�g�����ĕ`�����Ƃ��Ă���肭�����Ȃ��̂��Y�݂̎�ɂȂ��Ă��܂��܂��B��ԊȒP�Ȃ̂́A�L�����N�^�[�̃J�����_�[���̊G���n�T�~�Ő��ē\��t���Ă��܂����Ƃł��B���̃h���S���{�[���͂�������č�����u���̏o��I���āv�ł��B�������A��������킯�ɂ͂����܂���A�����ƊȒP�ɂ�����������Ȃ����@���K�v�ł��B �@�G�����ӂȐ搶�͏��Ȃ��ł��傤����A�C���X�g�����ĕ`�����Ƃ��Ă���肭�����Ȃ��̂��Y�݂̎�ɂȂ��Ă��܂��܂��B��ԊȒP�Ȃ̂́A�L�����N�^�[�̃J�����_�[���̊G���n�T�~�Ő��ē\��t���Ă��܂����Ƃł��B���̃h���S���{�[���͂�������č�����u���̏o��I���āv�ł��B�������A��������킯�ɂ͂����܂���A�����ƊȒP�ɂ�����������Ȃ����@���K�v�ł��B�@�E�̃m���^���́A�u�L���X�^�[�{�[�h�v�p�ɕ`�������̂ł����A���@�̓_�C�\�[�ł������Ă���u�J�[�{���y�[�p�[�v���g�����Ƃł��B���̊G���������ꍇ�̓f�W�J���ŎB���Ĉꑾ�Y��Word�Ɋg�債�ē\��t���܂��B���̊G�����������A�J�[�{���y�[�p�[�̏�ɊG��u���ă{�[���y���łȂ���ΔɊG��]�ʏo���܂��B��͐����y���L�ŐF�t�����s���Ί����ɂȂ�܂��B �p�R�X�@�@���ނɂȂ�u�G�{�v���Ăǂ�Ȃ��̂Ȃ́H  �`�E�u�G�{�v�́A�c�����q����B���ǂނ��́E�Ⴂ��������₨�ꂳ�c���q�ǂ��ɓǂ�ŕ���������́A�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�݂Ȃ���͂������������Ǝv���܂����A�D�ꂽ�G�{�͂��q����B�͖ܘ_�̂��Ƒ�l���ǂ�ł��������̂ł��B �`�E�u�G�{�v�́A�c�����q����B���ǂނ��́E�Ⴂ��������₨�ꂳ�c���q�ǂ��ɓǂ�ŕ���������́A�Ƃ����ӂ��Ɏv���Ă��܂��B�݂Ȃ���͂������������Ǝv���܂����A�D�ꂽ�G�{�͂��q����B�͖ܘ_�̂��Ƒ�l���ǂ�ł��������̂ł��B  �@���ʎx���w�Z�ł́A�Ⴊ����N��ɉ����ĊG�{��I��ł���Ǝv���܂��B�Z���킩��₷�����b����Y�~�J���Ȃ��Ƃ̎g�����Ȃǂ̖ʔ����͖ܘ_�̂��ƁA�F�g���̔��������G�{�͍H�v����Ă��܂��B �@���ʎx���w�Z�ł́A�Ⴊ����N��ɉ����ĊG�{��I��ł���Ǝv���܂��B�Z���킩��₷�����b����Y�~�J���Ȃ��Ƃ̎g�����Ȃǂ̖ʔ����͖ܘ_�̂��ƁA�F�g���̔��������G�{�͍H�v����Ă��܂��B�@���w���̍��w�N���炢�ɂȂ�Ɓu�́v��u���N�v���킩��₷�������Ă����G�{�������ł��傤�B�P�K�����Ă��e�����ł�����Ă����ƁA�����𐅂Ő����E���ʼnt�ŏ��ł���i�����݂ł́A���ʼnt�͎g�킸��BAND-AID�̃L�Y�p���[�p�b�h�̂悤�Ȃ��̂��g�����������߂ł��B�j�Ƃ������Ƃ����킩��Ȃ��q���ł��Ă��܂��܂����A�������������Ƃ������Ă����G�{������܂��B���̊G�{�̘b�����A����ʂ��Ď����Ō��N�ɋC�Â�����ɂȂ�ł��傤�B �@�w�N���オ���čs���ɏ]���u���킢�����Ȃ����v�E�u�����肶�����v�Ȃǂ̐푈���l����������G�{��u���J��N���炢��v�ȂǏႪ�����l����G�{�ɐG���̂������ł��傤�B�m�I�Ⴊ���̂��q����B�́A���̕s���R�̂��q����B�̂��Ƃ�  �ǂꂾ���m���Ă���̂ł��傤�B���������炢�ɂȂ�����A���������̏Ⴊ����m�邾���łȂ��A���̏Ⴊ���ɂ��Ă�����x���グ�邱�Ƃ���Ȃ��Ƃ��ƍl���܂��B �ǂꂾ���m���Ă���̂ł��傤�B���������炢�ɂȂ�����A���������̏Ⴊ����m�邾���łȂ��A���̏Ⴊ���ɂ��Ă�����x���グ�邱�Ƃ���Ȃ��Ƃ��ƍl���܂��B�@���b�������łȂ��A���̊G�{�₨�Ă̊G�{�E���j�̊G�{��F�X�Ȃ��X�̊G�{�E�M���⍑���̊G�{�ȂljȊw�I�E�Љ�I�Ȗڂ���Ă�ǎ��ȊG�{����������܂��B�Ⴊ���̏d�����q����Ⴊ���̌y�����q����܂œǂ߂�ǎ��ȊG�{�́A������Ƃ��Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ǝv�킳���قǁA�f���炵�����ނƌ�����ł��傤�B�������ނ͊��p���Ȃ��Ƒ��ł���B �p�S�O�@�w�Z�ōs���u�{�̓W����v���ĉ��H �`�E�Ⴂ�搶���́A���ޥ����Ɋւ�炸���ʎx������̖{�I�тɂ͋�J����Ă��邱�Ƃł��傤�B�傫�Ȗ{������ɍs���Γ��ʎx������̃R�[�i�[�ɂ͐��P�O�O���̖{������ł��܂����A��ɂƂ��ē��e�������ǂ��炢�ł́A���̖{���{���Ɏ����̖��ɗ��̂��i���ɂȂ�̂��j������Ƃ킩�肸�炢�ł��傤�B �@������������������Ă����w�Z�ł́A�ċx�݂Ɍ�������ÂŁu���ʎx������̐}���̓W����v�N�s���悤�ɂ��Ă��܂����B�E�����ׂ̗ɋx�e��������A���i�͂����ʼn�c�����s���Ă��܂������A�ċx�݂̊��Ԓ��͓��ʎx������Ɋւ���{���Q�O�O���قǓW�����Đ搶������ɂƂ��ēǂ߂�悤�ɂ��܂����B �@�{�́A����������S�Z�̐搶���ɐ��|�����Ă킩��₷���ǂ��{���W�߂�悤�ɂ��܂����B�Ⴂ�搶����x�e�����܂ŁA�������ǂ�œ��e���ǂ������Ƃ����F�X�Ȗ{���Љ���̂ŁA�{������̃R�[�i�[�łǂ��I�ׂΗǂ��̂��v�Ă��邱�Ƃ�����܂��B���̎��g�݂́A����������Ă��Ď��{����悤�ɂ��Ȃ��Ɠ���̂ł����A�搶���̖��ɗ����ƂȂ̂ł��Ȃ��̊w�Z�ł��n�߂Ă͂������ł��傤���E�E�B�������̎d���͌��C�����C���ł�����A���C��E�u�������悷�邾���łȂ��A�������������g�݂��K�v�ł��傤�B �p�S�P�@�����W�c�̗͂��グ��ɂ́H �`�E���ށE����̐���Ɗ��p�Ƃ����ϓ_����l����ƁA���ʂȋZ�ʂ��������搶�����Ă��A����͋����W�c�̗͂ɂ��w����w�Z�S�̗̂͂ɂ��Ȃ�܂���B����ȗD�ꂽ�搶�����Ă��A���̉e���i���b�j����̂͒S������N���X��w�K�O���[�v���炢�ł����Ȃ�����ł��B �@�܂��A���̐搶���]���Ă��܂��A���ށE������D�ӂŊw�Z�Ɏc���Ă���Ă��A�������g�������킩��Ȃ�������C�����ł��Ȃ��Ȃ邩��ł��B��l���ł��邱�ƂȂǂ���������Ă���Ƃ������Ƃł��B �@�u�����W�c�̗́v���グ��ɂ́A�N��������Ď��ƂŎg�������ށE������݂�ȂŘb�������āA�X�ɗǂ����̂ɂ��邱�ƂƁA�������������ށE����𑼂̐搶���ɂ����p�ł���悤�ɂ��Ă����i���L����j���Ƃŋ����W�c�Ƃ��Ă̗͂��グ�Ă������Ƃł��B�����A�����͑S���ƌ����Ă悢�قNj��ލ����s�킸�A�l����������̂𗘗p���邾���Ƃ����̂ł́A���ʎx���w�Z�̋����Ƃ������l�ԓI�ɖ��ł����E�E�B �@���ށE����ȊO�̖ʂł��A�݂�ȂŘb�������Ă����d��������悤�ɂ���킯�ł�����A���ޥ������݂�Ȃł����`�Ŋ��p����悤�ɂ���Ƃ������Ƃ́A�������Ƃ�������Ǝv���܂��B �p�S�Q�@�q�ǂ����ۑ���ԈႦ�������A�����`�����X���Ăǂ��������ƁH �`�E����w�Z�̌��J���Ƃ����Ă�����A����̂��q���Q�����̃p�Y��������Ă��܂����B�}�W�b�N�e�[�v�̂����䎆�ɏ㉺�ɕ����ꂽ�G�i�Ⴆ�����S�j��\���Ċ���������Ƃ����ۑ�ł������A���̂��q�������̊G����ɓ\���Ă��܂�����A�搶�������ɂ��̊G�̃J�[�h�������Ɉڂ��Ă��܂����̂ł��B���R�A���q����͎��ɏ㑤�̊G����ɓ\��t���Đ����ɂȂ�܂������A��������Ă��āu���[���������Ȃ��B�v�Ǝv���܂����B �@���̂��������Ȃ����Ƃ����ƁA���s���邱�ƂŐ������l���邱�ƂɂȂ邩��ł��B�搶�͎q�ǂ�����̂�����Ƃ����܂������x���������肩������܂��A���̂��q���ǂ����ԈႢ�Ȃ̂��E�����͂ǂ������`�Ȃ̂����l����`�����X��D���Ă��܂������ƂɂȂ�̂ł��B �@���q����B�����s����͈̂������Ƃł͂Ȃ��̂ł��B�ł��邱�Ƃ��肵�Ă���Ύ��s�͂Ȃ��ł��傤���A���̐�ɐi�ޗ͈͂炿�܂���B���s������A�����~�܂��čl���邱�Ƃ���ɐi�ޗ͂���Ă�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��������l�����Ă����ł����́B �p�S�R�@�q�ǂ��B�����Ɠ����o���B���̎��̐搶�̍������s�����ĉ��H �`�E����͋��ޥ����̘b���ł͂���܂��A��Ȃ��ƂȂ̂ōڂ��邱�Ƃɂ��܂����B�̈瓙�ŏ��w���̎q�ǂ��B���W�c���������Ă���ƁA�ړ��̍ۂɎq�ǂ��B�����ɓ����o�����Ƃ�����܂��B�搶���̐l�������Ȃ����Ƃ������āA��яo�������Ȃ��q����₮�����Ă����ɓ����Ȃ����q�����搶������ł��܂��Ď��̊����ɓ������Ƃ���̂ł����A���X��������ʂ�ڂɂ��܂��B�q�ǂ��̎������̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ��̎���������Ƃ���ł���̂ł��B �@�Z�O�w�K���Ō�ʗʂ̌������ꏊ������ۂɂ́A��яo���Ă����Ȃ��悤�ɁA�ꍇ�ɂ���Ă͎������邱�Ƃ������Ă������ł��傤�B��������Ă���Ƌ}�ɂӂ�قǂ��Ă��܂����Ƃ����X���邩��ł��B�����A�Z���ł͎�����邱�Ƃ��厖�ł��B��l�ł����Ă���������ꂽ�猙�ł��傤�B���́A��������Z���^�[�̐V�C���ōu�t���s�����ɂ́A�K�������搶���ɑ̌����Ă��炢�܂����B�u����������̂Ǝ��������̂ł͂ǂ��Ⴂ�܂����H�v�E�E�ƁB���C�Ȃ�����Ă��܂��Ă��邱�ƂɋC�Â��Ȃ��ƁA�q�ǂ��B�ɍD�����₳�����搶�ɂ͂Ȃ�܂���B �p�S�S�@���̕s���R�̎q�ɂ��A�I���Ă⎆��s�@�����y���݂�̌�������������ǁE�E�E�B �`�E�㎈�i�r�j�������Ȃ����q����́A���R���̂𓊂��邱�Ƃ͂ł��܂���B����ł����ނ̍H�v�œI���Ă⎆��s�@�������Ƃ͂ł���悤�ɂȂ�܂��B�I���ẮA�{�[���i�_�C�\�[�Ŕ����Ă���e�j�X�{�[���⏭�����Ԃ�̃{�[���������ł��B�j�ɂЂ���ʂ��A���̂Ђ��̒[��V��ɂ����@��Ɩ��J�o�[�̘g�ȂǂɌ��т��邾���ł��B �@�܂��A����s�@�́A����s�@�˂������������̂ł��B���ʂ̎���s�@�̔��ˑ�́A����ő�̍��E�������đ���g���Ȃ��Ǝ���s�@�͔��˂���܂��A������������ˑ�́A��O�̍�����̕�������O���ɂ�����Ɠ|�������ŁA����s�@���r���[���Ɣ��˂��邱�ƂƂ��ł���悤�ɂȂ��Ă��܂��B���ނ̍H�v�ō��܂łł��Ȃ��Ǝv���Ă������Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B���q����B�̏Ί炪���܂��悤�ɂ����܂��傤�B �p�S�T�@���������Ă���q���A��l�Ń}���\�����ł���悤�ɂ���ɂ͂ǂ������炢���́H �`���̃}���\���ł����Ă��Ă��ƕ����Ă���x�N�B�搶�����Ĕ�������Α���o���܂����A�P���ʑ������苳���������Ƃ܂��Ă��Ă��B�����łR������ڕW�ɂ��Ďw�����n�߂܂����B �@���߂͔�������X�s�[�h��������炢�̑����ł������s���A���Ԃ����ς����肫��悤�ɂ��܂����B���̎��́A�������Ȃ���O�𑖂��Ă���F�B��ڕW�ɂ��āu�����N�̏��܂ő���E��������̏��܂ő���v�Ƃ��A�ǂ������炵�炭�͂������������J��Ԃ��悤�ɂ��܂����B�u��ꂽ�炢�ł������Ă�����B�v�ƌ����Ɓu���v�v�ƌ����Ă��܂������A�����͂������ɂ������y�[�X�����悤�ɂ��܂����B �@�P�����قǂŊ���Ă����悤�Ȃ̂ň�l�ő��点��ƂP�����炢��������܂���B�܂��A�������đO�𑖂��Ă���F�B�̏��܂ő����Ă͂������������Ƃ��J��Ԃ����܂��B���������菭���������ꂽ����J��Ԃ��ƈ�l�ł�����鎞�Ԃ����тĂ����܂����B �@�Q�������炢�o�Ɣ������Ȃ��Ă��������y�[�X�ł͂���܂������A�Ȃ�Ƃ���l�Ŋ����B����Č��Ă��邾���ɂ���Ǝ��X��������������o���̂ŁA�u�O�ɂ��遛������܂ł����v�Ɛ��|������ƃX�s�[�h�A�b�v�B �@�X���[���X�e�b�v�Ɛ�����𑖂��Ă���F�B��ڕW�ɂ������Ƃ����ʓI�������悤�ł��B�x�N�́A�������ɐi��Œ��������𑖂�悤�ɂȂ��Ă��A�搶���������Ȃ��Ă����v�ɂȂ�܂����B �p�S�U�@�꒵�т��ł��Ȃ��q�����ׂ�悤�ɂȂ���@�́H �@�u�N�ł����ׂ�꒵�сv�́A�R�{�̎������̊ǂɍׂ��������̊ǂ������Ă�����̂ł��B�g�ݗ��Ď��Ȃ̂Ŏg��Ȃ��Ƃ��ɂ͂͂����ĂR�{�̊ǂɂȂ�܂��B�ʐ^�̌u���̊ǂ͂��������Ă��܂��A���̊ǂł������悤�ɍ��܂��B�܂��A�R�{�̊ǂ̑g�ݗ��Ď��ɂ��Ȃ��̂ł���A�z�[���Z���^�[�̔_���|�R�[�i�[�Ŕ����Ă���S�`�T����������̖_�ł������ł��傤�B�����̖_�͓�炩���Ă��Ȃ���̂ɂ��܂��B�d�����Ă��Ȃ�Ȃ����͎̂g�����炢�ł��B �@�A�������̓꒵�т͂ǂ�Ȉʒu�ł��~�߂邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ������܂��B���邮�鑁����]���Ȃ��Ƃ������Ƃ��킩��Ǝq�ǂ��B�����S���܂��B �@�B�q�ǂ����}�b�g�̏�ɂ����ԂŁA�������̓꒵�т�O�������瑫���܂Ŏ����Ă����A�u����ŁI�v�ƌ����܂��B�q�ǂ������яオ������Ȃ����]�����܂��B���̎��A�q�ǂ����}�b�g�̏ォ��O�ɏo�čs���悤�ł�����A�u�}�b�g�̏�Œ��т܂��v�Ƙb���܂��B �@�C�B�̃W�����v���J��Ԃ��܂��B �@�D�W�����v���}�b�g�̏�łł���悤�ɂȂ�����A���X�Ɏ������̓�̉�]�𑬂߂Ă����܂��B�E�E�E���̕��@�ő�̂̂��q����͕|���邱�ƂȂ����ʂɓ꒵�т��ł���悤�ɂȂ�܂��B�����A�̏d�����肷���ăW�����v���̂��ł��Ȃ����q����́A�꒵�т͂ł��܂���B �p�S�V�@�}�H�ł��ʍ������鎞�A���D���|���q�͂ǂ���������́H �@�����}�H�̎��Ԃɂ��ʍ����s���ꍇ�́A�_�C�\�[�̉��|�i�R�[�i�[�łŔ����Ă���u�p�[���}�b�g�v���g���悤�ɂ��܂����B�p�[���}�b�g�͞��q�̎��̑@�ۂłł��Ă���e��̂悤�Ȃ��̂ł��B���̃p�[���}�b�g�� �@���D�Ƃ����]���̕��@�ł͍��������Ƃ��A�f�ނ�ς��邾���Ŗ�肪�����ł���̂ł��B�P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j������ď��i���悭���Ă���ƁA�����A�C�f�A��������ł��܂���B �p�S�W�@�V�������ޥ����́A�ǂ��������ɂ��č����́H�i����̃|�C���g�ƃA�C�f�A�j �@ �@�z�[���Z���^�[������Ă�����A�v���X�`�b�N�J���[�i�{�[���Ƃ������i���������̂ŁA������������Ȃ��Ĕ�ɂ��đ��ɓ\��������낤�ƍl���܂����B���傫���܂܂��Ǝ��[���ɂ�����̂ŁA���c�����ɃJ�b�g���ĔƔ̊Ԃ�܂邱�Ƃ��ł���悤�ɊԂ����������J���āA�z�K���e�[�v��\��悤�ɂ��܂����B �@���߂͋z�Ղő��K���X�ɓ\��`�ɂ��܂������A�����Ɗy�ɂł��Ȃ����Ǝv���A�c�����P�p�قǂŒ������P�W�O�p�̊p�ށi���ۂɂ͂P�W�O�D�T�p�ʂ���܂��B�j�̏㉺�ۏ�ɂ��āA�p�l���ɉ������Ă�悤�ɂ��ĉ�]������ƃs�^�b�Ƃ͂܂邱�Ƃ����܂����B����Łu�p�l�����Ö��Q�v�������B �@���̈Ö��́A�搶���Q�l����Q���Ƃ�����Ȃ��ŋ����ɈÖ���ݒu���邱�Ƃ��ł��܂��B�Ö����v���C���[�����玝���Ă���̂͑�ς�����A�Ö����g���悤�Ȏ��Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ����Ă������w�N�̐搶�����A���̈Ö������邱�Ƃł���Ȏv�������Ȃ��Ă����ނ悤�ɂȂ�܂����B���������������A�V�������ޥ������܂��Ƃ��ɂȂ�܂��B������l�ł͂����A�C�f�A���o�Ȃ��Ƃ��́A���l���̐搶�����W�܂��Ęb�������A�C�f�A�����܂�Ă���ł��傤�B �p�S�X�@�G�J�[�h�̃C���X�g�͂ǂ�Ȃ��̂������́H   �`�E�G�J�[�h�́A��b�w�K�⍑���Z���ł��悭�g������̂ł��B�G�J�[�h�̃C���X�g�ɂ��ẮA�F�X�Ȉӌ�������Ǝv���܂����A���ꂪ�����Ƃ������͕̂��������Ƃ�����܂���B���̏ꍇ�́A�Ⴂ�Ƃ��ɂ͎������D���Ȃ��̂��C���X�g�W�i�b�c�j����I��Ŏg���Ă��܂����B�ǂ������C���X�g�������̂��ȂǍl�������Ƃ�����܂���ł����B�l�I�ȍD�݂��D��Ƃ������Ƃł��ˁB �`�E�G�J�[�h�́A��b�w�K�⍑���Z���ł��悭�g������̂ł��B�G�J�[�h�̃C���X�g�ɂ��ẮA�F�X�Ȉӌ�������Ǝv���܂����A���ꂪ�����Ƃ������͕̂��������Ƃ�����܂���B���̏ꍇ�́A�Ⴂ�Ƃ��ɂ͎������D���Ȃ��̂��C���X�g�W�i�b�c�j����I��Ŏg���Ă��܂����B�ǂ������C���X�g�������̂��ȂǍl�������Ƃ�����܂���ł����B�l�I�ȍD�݂��D��Ƃ������Ƃł��ˁB�@�S�O��̍�����́A�C���X�g�͍D�݂ł͂Ȃ����{���ɋ߂����́E���A���Ȃ��̂��ʐ^��I�Ԃ悤�ɂȂ�܂����B�E�̎ʐ^�ƃC���X�g������Ƃ킩��悤�ɁA�C���X�g�̌������킢����������܂��A����͌����Ƃ킩���Ă��邩��G�ɏȗ��������Ă����Ɨ����ł���킯�ł��B���Ƃ̊w�K���n�߂��q�ǂ��B�̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ�   �ł��傤�E�E�B���扻���ꂽ�悤�ȊG�̌��Ǝʐ^�̌��i�܂��́A�ƂĂ����A���ɕ`���ꂽ�C���X�g�̌��j�ł͎���Ⴄ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �ł��傤�E�E�B���扻���ꂽ�悤�ȊG�̌��Ǝʐ^�̌��i�܂��́A�ƂĂ����A���ɕ`���ꂽ�C���X�g�̌��j�ł͎���Ⴄ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@�E�́u���ǂ�v��u�o�X�v��u�L�����v�̃C���X�g�͌������̃J�[�h�̂��̂ł��B���Ƀ��A���Ŏʐ^�̂悤�Ɍ����܂��B���͎ʐ^���Ȃ��Ƃ��ɂ͌����̊G�J�[�h���f�W�J���ŎB���ăf�[�^�����A�G�J�[�h��J���^��Z���E���w�̎��Ƃ�v�����g���Ŏg���Ă��܂����B�������̃J�[�h�́A�u�H�ו��v�u�����v�u�g�߂ȓ���v�u��蕨�v�u�����v�u�L���E�W���v�ȂǐF�X�Ȏ�ނ������ĂȂ��Ȃ��D�ꂽ���ނɂȂ��Ă���Ǝv���܂��B  �@�����A�R�~���j�P�[�V�����J�[�h�̂悤�ɍZ���̂��̂�{�݂͎����Ŏʐ^���B���Ďg���悤�ɂ��܂����B�Ⴆ�g�C���̃C���X�g��ʐ^�ƌ����Ă��A���i�g���Ă�����̂ƈႤ�ƃJ�[�h���g���q�ǂ��B���˘f�����Ȃƍl��������ł��B�q�ǂ��B�́A���̕ӂ͗]��e���͂Ȃ��悤�ł������A�q�ǂ��B���g�߂Ȃ��̂ŗ������₷������悤�ɐS�|���܂����B�ǂ�ȃC���X�g�������̂����ɂ������͂킩��܂��A���Ȃ��Ƃ������̍D�݂őI�Ԃ̂Ƃ͈Ⴄ�C�����܂��B���Ȃ��Ȃ�ǂ����܂��H �@�����A�R�~���j�P�[�V�����J�[�h�̂悤�ɍZ���̂��̂�{�݂͎����Ŏʐ^���B���Ďg���悤�ɂ��܂����B�Ⴆ�g�C���̃C���X�g��ʐ^�ƌ����Ă��A���i�g���Ă�����̂ƈႤ�ƃJ�[�h���g���q�ǂ��B���˘f�����Ȃƍl��������ł��B�q�ǂ��B�́A���̕ӂ͗]��e���͂Ȃ��悤�ł������A�q�ǂ��B���g�߂Ȃ��̂ŗ������₷������悤�ɐS�|���܂����B�ǂ�ȃC���X�g�������̂����ɂ������͂킩��܂��A���Ȃ��Ƃ������̍D�݂őI�Ԃ̂Ƃ͈Ⴄ�C�����܂��B���Ȃ��Ȃ�ǂ����܂��H�p�T�O�@�����Ί�́A�搶���q�ǂ��B���K���ɂ�����Ăǂ��������ƁH �`�E�搶���q�ǂ��B�����鎞�i���ӂ���Ƃ��j�A�����ɂ͕K�����闝�R������܂��B�����A����Ȃ���C���C�����Ă��鎩���������ɂ��܂��H�@�������������Ō�̔N�̒��R�̒S�C�������Ƃ��A�N�x���߂̊w���̎��ԂɁu�N�Ԃ̖ڕW�v��u�P�w���̖ڕW�v�k�ɍl�������܂����B�F�X�b�������Ă���ƁA�����k�̂h����u�搶�̖ڕW�͂Ȃ�ł����H�v�ƕ�����܂����B����Ȃ��Ƃ͋��������ŏ��߂Ă̂��Ƃł������A�u�������ˁB�搶���ڕW���l���邩�v�Ɖ����A�����l���Ă���w�����Ί�ł���x�������̖ڕW�ɂ��܂����B�q�ǂ��B�����ꂼ��̖ڕW����p���ɏ����č��̏�̕ǂɓ\�����Ƃ��ɁA���̖ڕW�����ׂē\��܂����B �@���X�A�q�ǂ��B�Ƃ���Ƃ��͏Ί�ł��邱�Ƃ����������̂ŁA���Ɉӎ����邱�Ƃ��Ȃ������̂ł����A�����Ί�ł��悤�Ƃ���Ƃ������ɐF�X�ȏ�ʂňӎ�����悤�ɂȂ�܂��B���k����������������A�F�B�������邱�Ƃ����C�Ȃ�����Ă��܂������ɒ��ӂ����莶�鎞���A�u�����Ί�ł���v�ƈӎ����Ă���Ɨ�Âɂ��̂��Ƃf�ł��A����قǂ�������Ȃ��Ă��w���̎d���͂���Ȃ��Ɨ]�T�������čl���s���ł���悤�ɂȂ�܂����B �@�����̃X�g���X��m�炸�m�炸�Ɏq�ǂ��B�ɂԂ��Ă�����A����Ƃ��ɂ���ɂ͂��ƋC�Â��Ēp���������q�ǂ��B�ɐ\����Ȃ��v���ɂȂ�ł��傤�B���ꂳ���C�Â��Ȃ��搶�́A�N���X��w�N�ɂ��ė~�����搶�ł͂Ȃ��A���Ȃ��ق��������搶�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�搶���l�Ԃł�����A�l�ԊW��d����ƒ�ŃX�g���X�����܂�܂��B�ł��A�Ί�ł��悤�Ƃ���Ǝq�ǂ��B�ɂ��������g�ɂ��Ƃ��Ă������S�̏�Ԃ����܂��B�����Ί�ł�����Ɨ݂͂��Ƃ��āA�����R�c�R�c�Ƃ����܂��傤�B�q�ǂ��B�ɂƂ��Đ搶�����ޥ����ł�����B �p�T�P�@�����̑|���Ŏg���̂͂ق����������H �`�E������|������ۂɎg����̂́A�ق����₿��Ƃ�ł��B�����̋��ɑ|���̓��������|���p����ꂪ����܂����A�����Ă���̂̓o�P�c�E�ق����E����Ƃ�E���b�v���炢�ł��傤�B����A�ƒ�ł̑|�����l����ƁA�ق������g���̂͌���̑|�����̑|�����炢�ł͂Ȃ��ł��傤���B�ƒ�Ŏ����̑|���̍ۂɎg���p�x�������̂́A�u�|���@�v�ł��B �@�|���@�̂����Ƃ���́A�w�Z�Ŋo�������Ƃ��ƒ�Ŏg���邱�Ƃł��B�ق����Ƃ͈Ⴂ���݂��z�����Ƃ��낪�킩��₷���������낢���Ƃ��q�ǂ��B�����C�ɂ����܂��B����������Ƒ傫�Ȃ��݂͂킩��₷���̂ł����A�����ق���͂Ȃ��Ȃ��������炢�̂ŁA�K���|���@�������Y���X�y�[�X���ł��܂��B���̏ꍇ�́A�e�B�b�V��1�`�Q�����ׂ����������ċ����S�̂̏��Ƌ��ɂ܂������̂ł��B����łǂ�����������|�����邩���킩��܂��B�Ⴊ���̏d�����q�����ق����E����Ƃ���g���̂�����Ȏq�ł������̑|�����ł���悤�ɂȂ�܂��B �@�E�E�Ƃ͌����A�����ɑ|���@���Ȃ��̂����ʂ̏�Ԃł��傤�B�؍H���Ȃǂɂ͒u���Ă���܂��A�w�Z�S�̂ł͐������Ȃ��̂łǂ̋����ł��g���Ƃ�����ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B���͉ƂŎg��Ȃ��Ȃ����Â��|���@���w�Z�Ŏg���悤�ɂ��܂����B���̃N���X�ł��g�������Ɨv�]���������̂ŁA�|���@�͖����t����]��Ԃł����ˁB�w����Łu�g��Ȃ��|���@����������݂��Ă��������B�v�Ɛ����|����A�Q�`�R��ʂ͌��\�݂��Ă����Ƃ����������o�Ă��܂��B �@�q�ǂ��B�̎��ۂ̐������l���āA�o�������Ƃ��ƒ됶���ł���������悤�ɂ��Ă������Ƃ��厖�ł͂Ȃ��ł��傤���B�ܘ_�A�ق����̎g�������o���Ă��đ��͂Ȃ��ł��傤�B��Ə��Ȃǂł́A�܂��ق����͂悭�g���Ă���ł��傤����E�E�B �p�T�Q�@�������Ɓi���J���Ɓj�́A�����̒ʂ�ł�����ł����H �`�E�V�C���ȂǂŌ������Ƃ������Ȃ��܂����A�Ⴂ�搶�̒��ɂ́u���i�ʂ�ł�����ł���B�v�Ƃ�����y�B�̃A�h�o�C�X�����Ⴂ���Ă���l�����܂��B�u���i�ʂ�E�����Ɠ����v�Ƃ������ƂŁA�I�̒������G�Ȃ܂܂�������A�q�ǂ��B�̎����̐�ɐF�X�Ȃ��̂��������ڂ���Ȃ��܂ܒu����Ă����蓙�A�������������܂܂�������A���ތ������������肨���Ȃ����l�q�������Ȃ��ȂǁA����ȕ��i�ʂ�ł͋����Ƃ��Ă̎������^���Ă��d��������܂���B ���������搶�́A�������y�B�̃A�h�o�C�X�����ɓ���Ȃ��ł��傤�B����Ȃ��ƂC�ł���Ă���ƁA�N���e�g�ɂȂ��ăA�h�o�C�X�����Ă���Ȃ��Ȃ�܂��B���͂̐搶���́A�\�ʓI�ɂ͕t�������Ă���Ă��A�{���́u�����ʂ̊w�Z�ɍs���Ă���Ȃ����ȁE�E�B�v�Ǝv���Ă��܂��ł��傤�B �@���i�Ɠ����Ƃ������Ƃ́A���i���狳�����𐮂��A���ތ�����������Ă���Ƃ����̂��O��ł��B�V�C��Ⴂ�搶�Ȃ�A�ł��Ȃ����Ƃ������ē�����O�ł����A�撣���Ă���l�݂͂�Ȃ��m���Ă��܂��B�撣���Ă���Ⴂ�搶�ɂ́A������̓������y�̐搶�������̍ۂɂ͎�������L�ׂĂ����ł��傤�B�������Ƃ̎������͂����ċ��ށE���������Ă���悤�ł́A�����͂ǂ��Ȃ́H�E�E�Ǝv����ł��傤�ˁB�Ⴂ�搶�ɂƂ��ẮA�������������Ƃ̂悤�Ȃ��̂ł��B�u���i�ǂ���E�����ǂ���v�̎����グ�Ă����܂��傤�B �p�T�R �u�҂��Ɓv�́A�ǂ����đ厖�Ȃ́H �`�E�u�҂��Ɓv���ĉ���҂̂����킩��ł����H�@�����搶���͂킩���Ă���Ǝv���܂����A�q�ǂ��B�̊����i���ꂩ���낤�Ƃ��邱�Ɓj��������Ƒ҂��Ƃł��B�搶���͎q�ǂ�����ƂP�P�ł��Ă���قǐl���͑�������܂���A�����̂��q����̗l�q��w�K����l�Ō��Ȃ���Ȃ�܂���B�N���X��O���[�v��w�N�ʼn����s�����Ƃ���ƁA���R�̂��Ƃ��u�����I�����I�v�Ǝv���Ă��܂������ł��B �@�Ⴂ�搶���̍s�����J���Ƃ⌤�����ƂȂǂ����Ă���ƁA���������~�܂��Ă���q�ɑ��Ă��������҂��Ă�����A���̎q�͂��̎q�Ȃ�Ɋ撣�ꂽ�̂ɂƎv�����Ƃ����X����܂��B���̎q�Ȃ�̓��⓮�����Ԉ���Ă����Ƃ��Ă��A�u���߁I�v�ł͂Ȃ��āu����������ǂ��H�v�E�u��������Ă���ˁB�v�Ƃ������|����҂p������������A���̎q�͂�����肩������Ȃ�����ǎ����ōl����͂����Ă����ł��傤�B �@�q�ǂ��B�̂������������ɑ��āA�҂��Ă�������S�̗]�T�������Ă����܂��傤�B �p�T�S�@�ʓ|���̂����搶�́A�����搶�H �`�E��ʓI�ɂ́u�ʓ|���������v�Ƃ������Ƃ̓v���X�Ɋ�������܂��B�����Ō����ʓ|���������Ƃ����̂́A�ʓ|����������Ƃ������Ƃł��B�V�C�̐搶�����߂ẴN���X��w�N�ɓ���ƁA�Ⴊ���̏d���q�̖ʓ|�����g�I�ƌ����Ă����قnj���ꍇ������܂��B�l�ԓI�ɂ͂����Ƃ����l�Ȃ�ł��傤�B �@�ł��A�悭�l���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��ɂ��̎q�̂�낤�Ƃ��邱�Ƃ�v�������i����j���Ă���Ă����Ă��܂��ƁA���̎q�͎����ōl���čs�����Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃł��B�搶�ɂ��čs���Ή����l���Ȃ��Ă��E�撣��Ȃ��Ă����ނ̂ł�����A�q�ǂ��ɂƂ��Ă���Ȋy�Ȃ��Ƃ͂���܂���B�q�ǂ������������l���Ăǂ��������̂����킩������Łu�҂v���Ƃ��厖�ł��B�������Ȃ��Ǝq�ǂ������̎������͍��߂��܂���B �@�{���ɖʓ|�����ǂ��搶�Ƃ́A���̎q�̊w�K����̉ۑ���l���āA���̎q�������ōl���������s�����ł���悤�Ɏx������搶�ł��B�搶���́A�q�ǂ��B�̂����b�W�ł͂Ȃ��̂ł�����E�E�B �p�T�T�@���Ȏq�����D���ɂȂ���Ăǂ��������ƁH �`�E���ޥ����̘b���ł͂���܂��A�������ʎx���w�Z�̐搶�ł��悤�Ǝv���悤�ɂȂ����b���ł��B�V�C�œ����`�����ɂȂ�������̗{��w�Z�ɋ߂�悤�ɂȂ�܂������A�{��w�Z�Ƃ����Ƃ��낪�ǂ����������w�ǒm��Ȃ������̂ŁA���w�Z�̋����ɂȂ肽���Ǝv���Ă����̂��{���ł����B �@���̕s���R�̊w�Z�ɋ߂�悤�ɂȂ��������̂��Ƃł��B���w���ɔz������q�ǂ��B�Ə��߂đΖʂ������ɁA���R�̎ԃC�X�̋W�X�̂��q����Ɂu����ɂ���v�ƌ������r�[�A��ɂ�f����܂����B�G���Ȃ��Ă����݁A�q�ǂ��̎����Ƌ߂Â��悤�ɂ��Ă����̂ŁA���̎q���f�����͎��̊�Ƀr�V���b�Ƃ�����܂����B���ʂ���Ȃ��Ƃ�������Η�Â��������Ă��܂��܂����A�ǂ����Ă������ł��킩��܂��A�u���������q�����D���ɂȂ�Ȃ�������Ȃ��B�v�Ǝv���܂����B �@�����S�C�ɂȂ������̎q�̂���w�N�i���R�j�́A�{��w�Z���`�����ɂȂ�ɍۂ��āA�Ⴊ�����d�x��d���ŏA�w�Ə��i�Ⴊ�����d�x�d���ŋ���̑Ώۂł͂Ȃ�����A�w�Z�ɗ��Ȃ��Ă����Ƃ������Ɓj�ɂȂ��Ă��܂��悤�ȑ�ςȎq�B������w�N�ł����B���̊�ɂ�f�����q�́A�m�I�ɂ��d�����q����ł�������A�搶�����u���������E�������v�ƌĂ�ł��܂����B����Ȏq�ł������A�D���ɂȂ낤�Ǝv���Đڂ��Ă���Ɩ{���ɍD���ɂȂ邩�炨�����낢���̂ł��B �@���N���炢�o�ƁA�搶���͂��������E����������̂ɁA�Q�l�̐搶�����́u�����i���j�v�ƌĂ��悤�ɂȂ�܂����B���̎q�̒S���́u���ˁ��搶�v�́u���[���v�ŁA�ʂ̎q�̒S�������������ђ˂́u���[���v�ł��B �@�E�E���͂��̊w�N�ł��������Ɍb�܂�A�������w�Z�ɍs�����Ƃ͎v��Ȃ��Ȃ�܂����B���N�ケ�̎q�͖S���Ȃ�܂������A�Y����Ȃ����킢�������q�̂ЂƂ�ł��B���Ȏq�����D���ɂȂ���āA�ĊO���Ă��Ȃ��Ƃ��҂��Ă��܂���B�E�E�E�搶�ɂȂ��Ė{���ɗǂ������ƁB �p�T�U�@���̋��ނŖ{���ɂ����́H �`�E���i������O�̂悤�Ɏv���Ďg���Ă��鋳�ށB�ǂ̊w�N�ł��������Ă��邩��Ƃ������R�ŋ^��������Ȃ��ƁA�����Ƃ������̂����������ƂɂȂ邩������܂���B  �@�Ⴆ�A���̃}���\���Ŏg���Ă������m�鋳�ށB���������w�Z�ł́A���w���͐��k������m����@�Ƃ��ăS���o���h���g���Ă��܂����B������w���̕��́A�z���C�g�{�[�h�Ɏ������}�O�l�b�g��\��悤�ɂ��Ă��܂����B���̋��ނ́A�����̖��O���ʐ^�J�[�h�̉��Ƀ}�O�l�b�g��\������A�������ƂɐF��ς����}�O�l�b�g��\��Ƃ������̂ł��B�}�O�l�b�g���g���̂́A�F�X�Ȋw�Z�ł悭��������i�ł��傤���A����͗]�肢�����@�i���ށj���Ƃ͎v���܂���B �@�Ⴆ�A���̃}���\���Ŏg���Ă������m�鋳�ށB���������w�Z�ł́A���w���͐��k������m����@�Ƃ��ăS���o���h���g���Ă��܂����B������w���̕��́A�z���C�g�{�[�h�Ɏ������}�O�l�b�g��\��悤�ɂ��Ă��܂����B���̋��ނ́A�����̖��O���ʐ^�J�[�h�̉��Ƀ}�O�l�b�g��\������A�������ƂɐF��ς����}�O�l�b�g��\��Ƃ������̂ł��B�}�O�l�b�g���g���̂́A�F�X�Ȋw�Z�ł悭��������i�ł��傤���A����͗]�肢�����@�i���ށj���Ƃ͎v���܂���B�@�E�E�Ƃ����̂́A�������P�����邲�ƂɃz���C�g�{�[�h�̏��ɗ����~�܂��āA�ǂ��Ƀ}�O�l�b�g��\������̂��Ƃ��炭�̊Ԗ����Ă��܂��Ă���̂ł��B �@����A���w���̃S���o���h�͑̈�̐搶���l�������@�ŁA���̕��@�������Ƃ���͂P�����邲�ƂɃN���X���Ƃ̃o�P�c��傫�Ȕ��ɃS���o���h�𓊂�����邾���Ȃ̂ŁA�����~�܂�K�v���Ȃ����Ƃł��B�܂��A����ڕW���P�O���Ȃ�A�P�O�{�̃S���o���h��r�ɂ�������̂ŁA����Ȃ��炠�Ɖ��{�ŏI��邩���킩��₷���ł��B�S���o���h�́A�_�C�\�[�Ŕ����Ă���F���̒����S�����͂��݂Ő��Ă����������̂��̂ŁA���k���ɐF�������Ďg���܂��B�ǂ���̂ق��������̂��A������ƍl���Ă݂�Ƃ�����������܂���ˁB �@���ꂪ������O�Ǝv���ƌ����������Ȃ��Ă��܂��܂��B �p�T�V�@�X�v�[���̎w���͂ǂ���������́H  �@�E�̃X�v�[���́A������̕�����ō���Ă���܂��B�����̃X�v�[���́A�H�ו����������₷���悤�ɃX�v�[���̎�̕������Ȃ��ăO�[�X�l�b�N�ɂ������̂ł��B���̎g���������܂��Ȃ��q�́A���ʂ̃X�v�[���̃X�g���[�g�̎�̌`��ł͂��܂��H�ו������������Ƃ��ł��܂���B�X�v�[���̎�ɕ������O�[�Y�l�b�N��̌`�ɂȂ��Ă���Ƃ��������Ƃ��y�ɂȂ�܂��B�X�v�[���������Ďg�����Ƃ����ʂɂł���悤�ɂȂ�����A���͕��ʂ̐l���g���悤�Ȏ��������w�K���Ă����܂��B �p�T�W�@ �ď����̂ɁA�v�[���ɓ���������Ȃ��B����Ȏ��ɂ������@�͂���́H  �`�E�ĂɂȂ�Ɗe�w���Ƀv�[�����g���j���⎞�ԑт����蓖�Ă��܂����A�v�[���̂Ȃ����ł��]��ɂ������ƁA���w���̎q�ǂ��B�ɂ͐��V�т������Ă�肽���Ȃ���̂ł��B���������钆��ӂ�Ƀ~�j�v�[����c��܂��Đ��V�т����悤�Ƃ�����A���g�����猊���J���Ďg���Ȃ��Ȃ�Ƃ��������Ƃ͂���܂��H�@ �`�E�ĂɂȂ�Ɗe�w���Ƀv�[�����g���j���⎞�ԑт����蓖�Ă��܂����A�v�[���̂Ȃ����ł��]��ɂ������ƁA���w���̎q�ǂ��B�ɂ͐��V�т������Ă�肽���Ȃ���̂ł��B���������钆��ӂ�Ƀ~�j�v�[����c��܂��Đ��V�т����悤�Ƃ�����A���g�����猊���J���Ďg���Ȃ��Ȃ�Ƃ��������Ƃ͂���܂��H�@ �@��������̒S�C���������A�ĂɊw�Z�̃~�j�v�[�����܂��j��Ďg���Ȃ��Ȃ�A���̌�A�D�ӂŎ����Ă��Ă��ꂽ�搶���̉ƒ�p�̃~�j�v�[�����R�_���ɂȂ��Ă��܂������Ƃ�����܂����B�~�j�v�[���͋�C������̂Ɏ��Ԃ�������̂ƁA�q�ǂ��B�������Ɍ��������Ă��܂��̂ŁA�w�Ǘp���Ȃ��Ȃ����Ƃ������H�I �@��������̒S�C���������A�ĂɊw�Z�̃~�j�v�[�����܂��j��Ďg���Ȃ��Ȃ�A���̌�A�D�ӂŎ����Ă��Ă��ꂽ�搶���̉ƒ�p�̃~�j�v�[�����R�_���ɂȂ��Ă��܂������Ƃ�����܂����B�~�j�v�[���͋�C������̂Ɏ��Ԃ�������̂ƁA�q�ǂ��B�������Ɍ��������Ă��܂��̂ŁA�w�Ǘp���Ȃ��Ȃ����Ƃ������H�I�@�@�E�E�����œ����̐搶���p�ӂ����̂��r�[���P�[�X�B�r�[���P�[�X���S�`�W�l�p�ɕ��ׂĂ��̏�Ƀu���[�V�[�g���悹�Đ����������@�ł����B���̃~�j�v�[���͂悭�g���܂������A�������Еt�����y�������o��������܂��B �@�r�[���P�[�X���Ȃ��ꍇ�́A���Ẫ^�C���ł������悤�Ɏg���܂��B�r�[���P�[�X�����Ẫ^�C�����p�ӂ���̂�����ꍇ�́A�傫�߂̂������肵���r�j�[���܂ɐV�������ۂ߂Ă�����Ƌl�߂Ă���r�j�[���܂̌���߁A����𐔌���ă^�C����r�[���P�[�X�̑���ɂ���Ƃ����ł���B�q�ǂ��B������ł���Ȃ��Ȃ����A��������Еt�����ȒP�ł��B���ɓ���鐅�͐��p�̐[���ł��q�ǂ��B�͊�т܂��B �p�T�X�@�}�H�E���p�Ń����v�V�F�[�h����鎞�́A�f�ނ͘a���������́H �`�E�}�H����p�̎��ƂŁu�����v�V�F�[�h�v����鎞�ɁA�܂��l����f�ނ͘a���i��q���j�ł����A�a���͌`������₷���̂ŁA�q�ǂ��B�ɂ͂��Ȃ����f�ނł��B�a�����g���ꍇ�́A�a���Ō`�����̂ł͂Ȃ��A�F���߂����a�����̂o�o�ŕ�ނ悤�ɂ��Ă����Ƃ����ł��傤�B  �@�ȒP�Ŕ����������v�V�F�[�h������̂́A�P�O�O�~�V���b�v�̃_�C�\�[���Ŕ����Ă���u�N���A�t�H���_�[�v�ƃA�N�����G�̋�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł��B�A�N�����G�̋���N���A�t�H���_�[�̓����ɓh��ƁA�O�����猩��ƌ��̂���F�����ɂȂ�܂��B�܂��A���C�g���_�C�\�[�ɔ����Ă���v�b�V�����C�g���g�����Ƃ��ł���̂ŁA�ޗ��W�߂��y�ɂł��܂��B �@�ȒP�Ŕ����������v�V�F�[�h������̂́A�P�O�O�~�V���b�v�̃_�C�\�[���Ŕ����Ă���u�N���A�t�H���_�[�v�ƃA�N�����G�̋�Ƃ̑g�ݍ��킹�ł��B�A�N�����G�̋���N���A�t�H���_�[�̓����ɓh��ƁA�O�����猩��ƌ��̂���F�����ɂȂ�܂��B�܂��A���C�g���_�C�\�[�ɔ����Ă���v�b�V�����C�g���g�����Ƃ��ł���̂ŁA�ޗ��W�߂��y�ɂł��܂��B�@�N���A�t�H���_�[�ȊO�ł́A�J���[�i�{�[���i�_�C�\�[�j���l�����܂����A�܂�E��ɓ���ʂ�����̂ŁA������͒��w���⍂���������̑f�ނɂȂ�Ǝv���܂��B�S�����Ă��邨�q����B�̋Z�ʂ��l���āA�ǂ�ȑf�ނ��g���������̂����邩�l����Ƃ����ł��ˁB �@�a���E�N���A�t�H���_�[�E�J���[�i�{�[���ȊO�ɂ��o�o��A�N�����ȂǐF�X�ȑf�ނ�����܂�����A�܂��͐搶�����삵�āA����Ȃ�q�ǂ��B�ł�����Ƃ������̂������Ă����܂��傤�B������ƕς�����Ƃ���ł́A�����l�����O���[�K�����g�����z�b�g�{���h�̃����v�V�F�[�h������܂��B�K���X�H�̂悤�Ŕ������ł���B�ꌩ������Ɍ����܂����A�����ȏ�̂��q����B�ł���A�Ⴊ�������ɏd���q�ȊO�Ȃ����ł��傤�B�܂��́A�搶�������삵�Ă݂Ȃ��Ă͎��Ƃ�i�߂��܂���A�����Ă݂Ă��������B�����́A�u�}�H�E���p�v�̃y�[�W�ɍ�����ޗ��Ȃǂ��ڂ��Ă���܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��Ă��������B �p�U�O�@�u����̋��ޥ����v�̉������Ă��������|�C���g�́H �`�E����̋��ޥ��������ۂɉ������Ă��������|�C���g�͂���������܂����A������S���܂߂č��̂͂Ȃ��Ȃ�����ł��傤�B�|�C���g�͓��̕Ћ��ɒu���āA�������q�ǂ��B�ɂ������̂�����悤�ɂ��Ă����܂��傤�B �@���S�ł��邱�ƁB�i�q�ǂ����P�K�����Ȃ��悤�Ȕz�����K�v�ł��B�j �A�q�ǂ��̉ۑ�ɍ��������̂ł��邱�ƁB �B�F��`�����������ƁB�i���삾����Ƃ����č�肪�G�Ȃ��̂́A�g�����̎q�ǂ��B�̂��Ƃ��l���Ă��Ȃ����ƂɂȂ�܂��B�j �C���[���l����B�i�g��Ȃ��Ƃ��ɂ̓R���p�N�g�ɂȂ�Ƃ����ł��ˁB�Ƃ⋳�ގ��͂����Ɉ�t�ɂȂ�܂�����E�E�B�j �D�X���[���X�e�b�v���l�������̂ɂȂ��Ă���B�i���ꂪ�ł����玟�͂���Ƃ������ɁB�j �p�U�P�@�ʏ�̃R���p�X�ł͕`���Ȃ��傫�ȉ~��`�����@�́H �`�E�ʏ�̃R���p�X�ł́A������x�̑傫���̉~�����`���܂���B���ށE��������ۂɁA�傫�ȉ~��`�����Ƃ���ꍇ�́A����ȕ��@������܂��B  �@��������p�ӂ��܂��B�i���H�����₷���̂ŁA�o���T�ނ������ł��傤�B�z�[���Z���^�[�̍ޖ؊W�̏��ɔ����Ă��܂��B�j�̒����͉��P�O�p�ł������̂ł����A�傫�ȉ~��`���̂ŁA�T�O�p�ʂ͂���Ƃ����ł��傤�B����ŁA���a�T�O�p�i���a�P�O�O�p�j�܂ł̉~���`���܂��B�i�����ۂ́A�̒����ɂQ�`�R�p�v���X���������̔B�j�̕��́A�Q�`�R�p����悢�ł��傤�B�̌����́A���o����n�j�ł��B �@��������p�ӂ��܂��B�i���H�����₷���̂ŁA�o���T�ނ������ł��傤�B�z�[���Z���^�[�̍ޖ؊W�̏��ɔ����Ă��܂��B�j�̒����͉��P�O�p�ł������̂ł����A�傫�ȉ~��`���̂ŁA�T�O�p�ʂ͂���Ƃ����ł��傤�B����ŁA���a�T�O�p�i���a�P�O�O�p�j�܂ł̉~���`���܂��B�i�����ۂ́A�̒����ɂQ�`�R�p�v���X���������̔B�j�̕��́A�Q�`�R�p����悢�ł��傤�B�̌����́A���o����n�j�ł��B�A�̒[�Ɍ�������ł����܂��B���̕�������]����̒��S�_�ɂȂ�܂��B �̐^�ɐ��������܂��B�̒[�̌����O�p�i�N�_�j�ɂ��A�Ɉ��������ɂP�p�Ԋu�ň����āA����Ō��������܂��B�P�O�p�ʂ̂Ƃ��납�����������ł��傤�B�i����ȉ��̑傫���̉~�Ȃ�A�R���p�X�ł��n�j�ł�����E�E�B�j   �B��������ł����鎞�́A���M��{�[���y���̐悪�������߂���x�̂P�`�Q�o�̌����J���܂����A�����_�o���ɂȂ�Ȃ��Ƃ����v�ł��B �B��������ł����鎞�́A���M��{�[���y���̐悪�������߂���x�̂P�`�Q�o�̌����J���܂����A�����_�o���ɂȂ�Ȃ��Ƃ����v�ł��B�C�~��`���B�O�i�N�_�j�̏��̌��ɉ�e�₫��������܂��B����Œ��S�����܂�܂��B�`�������傫���̏��̌��ɉ��M���{�[���y���̐��˂�����ŁA�N�_�̉�e�₫���Ў�ʼn������Ȃ���A�~��`���܂��B���̕��@�Ȃ�A�P���̉~�����ĊȒP�ł��B���ɑ傫�ȉ~��`���ꍇ�́A�ʐ^�̂悤�Ɏx�_�̂������������l�ƃy���ł����Ɖ~��`���l�̂Q�l�ł����Ȃ��Ƃ����ł��傤�B �p�U�Q�@�y���L��h��Ƃ��́A�i�{�[����������Ƃ������ĉ��H  �`�E�y���L�h��i�͂��Ńy���L��h��E�X�v���[�Ńy���L��h��j�����Ă��鎞�ɕ��������Ƃق��肪�����オ��A�܂������Ă��Ȃ��y���L�ɂق���₲�݂����č��邱�Ƃ�����܂��B �`�E�y���L�h��i�͂��Ńy���L��h��E�X�v���[�Ńy���L��h��j�����Ă��鎞�ɕ��������Ƃق��肪�����オ��A�܂������Ă��Ȃ��y���L�ɂق���₲�݂����č��邱�Ƃ�����܂��B�@�������������ɂ́A�i�{�[�������g���ƕ֗��ł��B�i�o�[�������������ɂ��āA�y���L��h�����i�{�[�����̒��ɓ���܂��B�i�ł���Βn�ʂɒ��ڒu�����ɁA�H��䓙���������ʒu�ɒu���������A�悢�ł��傤�B�j���̐����Ă�������ɏo������i�H�I�j�����Ȃ��悤�ɂ��ăy���L��h��A�S�~���y���L�ɂ����Ƃ�����܂����A���ɃX�v���[�œh��ꍇ�́A���̉e����]��Ȃ��œh�邱�Ƃ��ł��܂��B �p�U�R�@���S�ȓh�����Ăǂ�Ȃ��̂Ȃ́H �`�E���[���b�p�̂�������ɂ́A�q�ǂ����������ɂ��Ă����S�ȓh�����g���Ă���Ƒ��q�����܂ꂽ���ɕ����܂������A�����̂�������⋳�ނ̏ꍇ�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�H�@ �@���i���������g���Ă��鐅���E�����̃y���L��j�X�́A������ɂ����S�Ȃ̂��ȂƂ����ƋC�ɂȂ��Ă��܂����B�ȑO�����ēǂ؍H�̎G���Ɂu�I�X���J���[�v�i�O�r�l�n�@�b�n�k�n�q�j�Ƃ����A�����܂�̖����Q�h�����o�Ă��܂����B�K�������悭�s���z�[���Z���^�[�́u�W���C�t���{�c�v�ɂ������Ă��܂��B�q�ǂ��������g�����̂́A���S�Ȃ��̂�I��Ŏg���Ă����������̂ł��B �@�Z�p�̐i���ň��S�Ȑ��i���o�ꂵ�Ă��Ă���̂Ȃ�A�������������̂�m���ĐϋɓI�Ɏg���Ă����������̂ł����A�I�X���J���[�͓����傫���̕��ʂ̃y���L�̊ʂ̒l�i�̂Q�{�ȏサ�܂��̂ŁA�傫�ȋ��ނɎg���̂ł͂Ȃ��A�q�ǂ���������ɂƂ��Ďg���悤�ȏ����ȋ��ނɎg���Ƃ����ł��傤�B�i������Ɍ��Ɏ����Ă����Ă����v�ɂ������Ƃ��Ɏg���悤�Ȏg�����ł��ˁB������Ɖ��i�������̂ŁA���i�g���͓�������B�j �p�U�S�@���M�Ȃǂ̉~�̒��S���ȒP�ɒ��ׂ���@�́H   �`�E����������⋳�ލ��̍ۂɁA���M�Ȃǂ̉~��̂��̂̒��S�ׂ邱�Ƃɋ�J���邱�Ƃ�����܂��B �`�E����������⋳�ލ��̍ۂɁA���M�Ȃǂ̉~��̂��̂̒��S�ׂ邱�Ƃɋ�J���邱�Ƃ�����܂��B�@�Ⴆ�A���M�̒��S���o�������Ƃ��́A���M��V�������̎��̏�ɒu���āA�O�������Ƀy���łȂ����ĕ`���܂��B �A�~���`���ꂽ�����͂��݂Ő���܂��B   �B����������^�łQ�܂�ɂ��܂��B�~�̔����ɂȂ������̂��܂��A�܂��Ďʐ^�̍����̂悤�ɂ��܂��B�i�܂�ڂ�����������悤�ɐ܂�܂��B�j �B����������^�łQ�܂�ɂ��܂��B�~�̔����ɂȂ������̂��܂��A�܂��Ďʐ^�̍����̂悤�ɂ��܂��B�i�܂�ڂ�����������悤�ɐ܂�܂��B�j�C�����L����Ɖ~�̐^���܂�ڂ̌��������Ƃ���ɂȂ��ĕ\��܂��B  �D���M�ɐ������~�̎����d�˂āA�y�����疇�ʂ��̂悤�Ȃ��̂ŏォ�獷�����߂A���M�̒��S�����܂�܂��B �D���M�ɐ������~�̎����d�˂āA�y�����疇�ʂ��̂悤�Ȃ��̂ŏォ�獷�����߂A���M�̒��S�����܂�܂��B�p�U�T�@�t���[�̂��̂�����̂ɃC���X�g�W�i�b�c�E�c�u�c�j�͔��������������́H �`�E���̓C���^�[�l�b�g�Ńt���[�i�����j�̃C���X�g����ɓ���邱�Ƃ��ł��܂����A���ލ���w���ʐM�ȂǂŎg���鎿�̍����C���X�g�͂Ȃ��Ȃ�����܂���B�w�Z�Ƃ������e�ŐF�X�ȃC���X�g�̃T�C�g�����ĉ�������Ƃ�����܂����A�g������̂͐��_���炢�����Ȃ���������ł��B�p�\�R���V���b�v�ɂ́A�u�X�N�[���C���X�g�W�v�Ȃǂ̂悤�Ɋw�Z�ɍi�������e�̂b�c�E�c�u�c�������Ă��܂��B �@���̓X�N�[���C���X�g�W�i�P�E�Q�E�R�j�Ƒ��̑f�ޏW�̂b�c�̃C���X�g���g���Ċw���ʐM��w�K�O���[�v�ʐM�E�e��̃J�[�h�����܂����B�C���X�g�W�̂b�c�E�c�u�c�͂X�O�O�O�~�ʂ��Č��\�������̂ł������A������Q�O�`�R�O�N�قږ����̂悤�Ɏg�����Ƃ��l����A�����č������̂ł͂���܂���B�K�v�ɉ����ĉ����������Ă��Ă��������̂ł��B�������C���X�g�̗ʂ��������ƂƎ��̍������Ⴄ�ƌ������Ƃł��B�w�Z�ɍi�����C���X�g�W�́A�w�K��w�Z�����ȂǐF�X�ȏ�ʂ�`���Ă���̂ŁA�w�ǂ̎��ƂŎg���܂��B�����g�����̂́A�����������������Ă��������̂��g���܂��傤�B���̂ق������ʓI�Ƀv���X�ł�����E�E�B �����݂ł́A�C���X�g�W���Ă���̂����Ȃ��Ȃ�܂����B���̂P�O�N�قǂ́A�u���炷�Ƃ�v�̃C���X�g�������̂Ŏg�킹�Ă�����Ă��܂��B �p�U�U�@���ޥ����̃f�[�^�x�[�X���āA���ۂ̂Ƃ���g������̂Ȃ́H 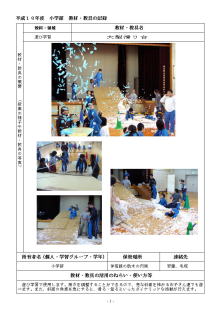 �`�E�@���ʎx���w�Z�i�{��w�Z�j�ɂ́A�s�̂̋��ށE����ȊO�ɐ搶�����H�v������������̋��ށE�������܂����A�N���ǂ�ȋ��ށE����𐧍삵�i�܂��͏��L���j�A�ǂ�ȕ��Ɋ��p���Ă���̂��́A�����w�K�O���[�v�ɂł����Ȃ��ƑS���ƌ����Ă����قǂ킩��܂���B �`�E�@���ʎx���w�Z�i�{��w�Z�j�ɂ́A�s�̂̋��ށE����ȊO�ɐ搶�����H�v������������̋��ށE�������܂����A�N���ǂ�ȋ��ށE����𐧍삵�i�܂��͏��L���j�A�ǂ�ȕ��Ɋ��p���Ă���̂��́A�����w�K�O���[�v�ɂł����Ȃ��ƑS���ƌ����Ă����قǂ킩��܂���B�@�܊p�������ށE�������̂ɁA�l�������p���ł��Ȃ��̂͂Ȃ����������Ȃ��B�������̕s���R�̊w�Z�Ō������������Ă���Ƃ��ɂ́A���������u���Ƃ̋L�^�v�̃f�[�^�x�[�X�Ƌ��Ɂu���ށE����̋L�^�v�̃f�[�^�x�[�X������āA�w�Z�̃T�[�o�[�ɓ���Ă��܂����B �@�u���ށE����̋L�^�v�́A���ށE����̎ʐ^�A���ށE����A���Ȃ�̈於�A�������Ă���l����O���[�v���A�ۊǏꏊ�A�A����A�ȒP�Ȏg�����A�q�ǂ������̕ϗe���L�ڂ��܂��B �@���̊w�Z�i�܂��͊w���j�̋��ށE����̃f�[�^�x�[�X���ł��Ă���A���Ƃ��s���ۂɂ킴�킴�O���狳�ށE��������Ȃ��Ă��A���Ɏ��ƂŎg���Ďg������̗ǂ��_���킩���Ă��鋳�ށE�����݂��Ă��������݂��Ă������肪�\�ɂȂ�܂��B �@�Ⴆ�p�l���V�A�^�[�Ȃǂ̋��ނ́A�l�Ŏ����Ă���ꍇ���w�ǂł����A�����݂��Ă��炦��Ύg������q�ǂ������ւ̏��Ȓ̎d���������ċ����Ă��炦�邱�Ƃł��傤�B�l�ŐF�X�ȋ��ށE�����p�ӂ��邱�Ƃ́A�����Z���������Ă�搶���ɂ͂����ւ�ł��B�X�̐搶���̗͂��c�E���ɂȂ���A�����Ƒ傫�ȗ͂ɂȂ��Ďq�ǂ������ɊҌ������͂��ł��B�Z���ɂ����l�b�g���[�N���\�z�ł���Ίw�Z�̗͂��A�b�v���邱�Ƃł��傤�B �@�E�E�E�����A��������܂��B�܊p�f�[�^�x�[�X������Ă��A�����ł͑S���ƌ����Ă����قNj��ނ����Ȃ��ŁA���̐搶���̘J��ł��鋳�ޥ����𗘗p���邾���Ƃ����l���o�Ă��Ă��܂����Ƃł��B���������l�́A�����ł���O�ɐl�ԂƂ��Ė��ł��ˁB �@�܂��A�f�[�^�x�[�X���ł����̂ɂ��ւ�炸�A�搶���̊Ԃŋ��ޥ����݂̑��肪�ł��Ȃ��܂܂�������A�G�ɕ`�����݂ŏI����Ă��܂��܂��B�f�[�^�x�[�X�͍��̂��ړI�ł͂���܂���B���p�ł��ď��߂Ċ�������̂ł�����B �p�U�V�@���o�V�тŁA�����Ă���q��Q�Ă���q�����R�ɗh�炷�ȒP�ȕ��@���Ă���H   �`�E���o�V�тŎq�ǂ��B�̑̂�h���Ԃ낤�Ƃ���ƁA���̕s���R�̊w�Z�ł̓N�b�V�����`�F�A�ɍ��点�ėh�炵����A�g�����|�����ɏ悹�ď㉺�ɗh�炵����A�V�[�c�u�����R�ō��E�ɗh�炵���肵�܂��B �`�E���o�V�тŎq�ǂ��B�̑̂�h���Ԃ낤�Ƃ���ƁA���̕s���R�̊w�Z�ł̓N�b�V�����`�F�A�ɍ��点�ėh�炵����A�g�����|�����ɏ悹�ď㉺�ɗh�炵����A�V�[�c�u�����R�ō��E�ɗh�炵���肵�܂��B�@�����̕��@�́A�h�炷�搶�����͎d���Ō��\��ςł��B�܂��A�𐔖{�̃��[�v�Œ݂��Ă����Ɏq�ǂ����悹�ėh�炷�Ƃ����A�傪����ȋ��ޥ���������܂��B�F�X�ȕ��@�E���ނ�����܂����A�����ƊȒP�Ő搶�������Ȃ��悤�Ȃ��̂���������ł���ˁB �@�E�̎ʐ^�́A�m�I�̊w�Z�Œn�k�̗h����ȒP�ɑ̌����邽�߂̂��̂Ƃ��čl�������̂ł��B�p�ӂ�����̂́A�X�`�[���̋ʐ��ƕz�K���e�[�v�ƂP�W�O�p�~�X�O�p�E�������P�Q�o�ȏ�̃x�j�������ł��B�X�`�[���̋ʁi�Q���R���炢�j���K���e�[�v�������ĂȂ��A�x�j���̉��̐^�ӂ�ɒu�������ł��B�q�ǂ����̒��S�ӂ�ɍ���i�N�b�V�����`�F�A���n�j�j���Q�]�ׂA�d���̃o�����X���Ƃ��̂ł���Ȃ��͂����Ȃ��Ă��A���E�̉�]�E�O��E�㉺�ւƗh�炷���Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B�x�j���Ƌʂ����Ȃ̂ŁA���ɊȒP�B �p�U�W�@�������͊�Ȃ��Ďg���Ȃ�����ǁA���ʼn��肢�����̂͂Ȃ��́H �@���w���̎q�ǂ��B�ł����������g�킹�邱�Ƃ́A������Ƃ��߂炢�܂��B���ہA���Ƃł�������Ƃ�����܂����A�F���͂̍������q����ł���Ȃ����������Ƃ��̂����Ȃ��ł����B�������͊�Ȃ��Ďg���Ȃ�����ǁA���ʼn���������Ɩ{���̔ʼn�ɋ߂����̂��ƍl�����Ƃ��ɂ́A�u�X�`�����ʼn�v�������ł��傤�B �@�_�C�\�[�Ŕ����Ă���J���[�{�[�h�i�\�ʂɎ����\���Ă��Ȃ��^�C�v�j�ɖ����y���ŊG�����`���ƁA�{�[�h���n���ĔŖ̂悤�ɂȂ�̂ł��B���G���{�[�h�̏�ɒu���ă{�[���y�����c �p�U�X�@�Ⴊ����m����Ăǂ������Ӗ��H 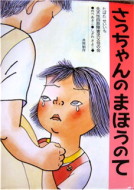 �@�����̏Ⴊ����m�邱�Ƃ͑厖�Ȃ��Ƃł����A�m�I�Ⴊ���̎q�ǂ��B�́A�ڂ̕s���R�Ȏq�B�⎈�̕s���R�̎q�B�̂��Ƃ�w�ǒm��܂���B�����̂��Ƃ�m���Ď�����F�B��Ƒ���厖�ɂ���悤�ɁA���̏Ⴊ���⍂��҂̐�����̖��i�]�|���₷���Ƃ����̂������ɂ����Ȃ�Ƃ��L���͂������铙�X�j���m�邱�Ƃő��҂⍂��҂��厖�ɂ���悤�ɂȂ��ė~�����Ǝv���܂����B �@�����̏Ⴊ����m�邱�Ƃ͑厖�Ȃ��Ƃł����A�m�I�Ⴊ���̎q�ǂ��B�́A�ڂ̕s���R�Ȏq�B�⎈�̕s���R�̎q�B�̂��Ƃ�w�ǒm��܂���B�����̂��Ƃ�m���Ď�����F�B��Ƒ���厖�ɂ���悤�ɁA���̏Ⴊ���⍂��҂̐�����̖��i�]�|���₷���Ƃ����̂������ɂ����Ȃ�Ƃ��L���͂������铙�X�j���m�邱�Ƃő��҂⍂��҂��厖�ɂ���悤�ɂȂ��ė~�����Ǝv���܂����B�@�E�̋��ޥ����́A�u�r�⑫�����R�ɓ������Ȃ����Ƃ�̌�����v���̂ł��B�I��G���Œ肳��Ă��܂��̂ŁA�v���悤�ɘr���������Ȃ��Ȃ�����A�����̂�����Ȃ����肷��̂�̌����܂��B���ۂɑ̂ł��̕s���R����̌�����ƁA���k�B������Ȃɂ���ςȂƗ����ł��܂��B�܂��A�G�{�ł��F�X�ȏႪ���ɂ��Ēm�邱�Ƃ��ł��܂��B �@�Ⴊ�������������g�̂��Ƃ��܂߂Ďア����̐l�̂��Ƃ�m�邱�Ƃ́A���ƌ�̐����̒��ł������Ă���ł��傤�B���ʎx���w�Z�̎q�ǂ��B���A���������܂����A�����Đl�ɗD�����q�ɂȂ��Ă����ė~�������̂ł��ˁB �p�V�O�@�s�̕i����肭�g�����āA�ǂ��������ƁH 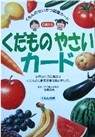 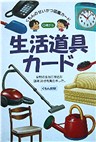  �`�E�E�̎ʐ^�́u�͂�������ނ��v�̐l�`�́A�{������Ŕ����Ă������̂ł��B�����ł������낤�Ƃ���Ƃ�����Ƒ�ρB�v���������������̂ł������A�����ō�����̂ł͂���قǂ������͍̂��Ȃ��̂ŁA�����Ď��ƂŎg���Ă��܂����B����ɂ������Ȃ��Ƃ����̂́A���̂��ʓ|������Ɣ����Ă�����̂��g���Ƃ������Ƃł͂���܂���B�������������u�������́v�ł���A�g�����Ƃ������Ƃł��B�������̊e��̃J�[�h���A���ނƂ��Ẵ��x������������g���܂����B�����������Ƃ������̂���ꂽ�̂ł���A�g�����Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B �`�E�E�̎ʐ^�́u�͂�������ނ��v�̐l�`�́A�{������Ŕ����Ă������̂ł��B�����ł������낤�Ƃ���Ƃ�����Ƒ�ρB�v���������������̂ł������A�����ō�����̂ł͂���قǂ������͍̂��Ȃ��̂ŁA�����Ď��ƂŎg���Ă��܂����B����ɂ������Ȃ��Ƃ����̂́A���̂��ʓ|������Ɣ����Ă�����̂��g���Ƃ������Ƃł͂���܂���B�������������u�������́v�ł���A�g�����Ƃ������Ƃł��B�������̊e��̃J�[�h���A���ނƂ��Ẵ��x������������g���܂����B�����������Ƃ������̂���ꂽ�̂ł���A�g�����Ƃ͂Ȃ������ł��傤�B�@���ނ͎q�ǂ��B���g�����̂ł��B�q�ǂ��B�ɂł��邾���u�������́v���g�킹�Ă����������̂ł��B����̋��ޥ����ɂ��Ă��A���S�Ŏq�ǂ��B�����L�������Ȃ�悤�Ȃ������̂ɂ��������̂ł��B�E�E�����āA�q�ǂ��B���g����ł�����B �p�V�P�@����C�X���������������ė��������Ȃ��q������B�ǂ������炢���H  �@�����������낢�̂Ȃ�A���̉��������Ă��܂������̂ł��B����C�X�̋r�Ƀ_�C�\�[�Ŕ����Ă���e�j�X�{�[�����͂�������A�z�[���Z���^�[�Ŕ����Ă���ڒ��܂̂�����炩���S���̔��C�X�̑��ɂ���ƁA�C�X������K�^�K�^�������ĉ����o�����Ƃ��Ă��w�lj������Ȃ��Ȃ�܂��B �@�u����H�v�Ƃ����\��������ĉ��x������Ă��A�ȑO�̂悤�ɃK�^�K�^�Ɖ����o�Ȃ��Ƃ��̂������߂Ă��܂��܂��B��������Ƃ�������C�X�����Č��ȉ����o�����Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�i�ܘ_�A�苭���q�����邩������܂��A��̂��̕��@�ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�E�E�B�j �p�V�Q�@����̃V�i�x�j���̍����́H   �`�E�\�ʂ���邵���V�i�x�j���́A�e�[�u���������Ƃ��ɏd�܂����A���i�������̂ƌ��݂�������̂���ɓ���Ȃ��̂����_�ł��B�������������Ɍ����̂���V�i�x�j���������@�ł��B �`�E�\�ʂ���邵���V�i�x�j���́A�e�[�u���������Ƃ��ɏd�܂����A���i�������̂ƌ��݂�������̂���ɓ���Ȃ��̂����_�ł��B�������������Ɍ����̂���V�i�x�j���������@�ł��B�@��肽���傫���̃T�C�Y�́u�x�j���v�Ɓu�R�o�`�T�o�����̃V�i�x�j���v��p�ӂ��܂��B��肽���V�i�x�j���̌��݂́A�x�j���̌��݂ƃV�i�x�j���i�R�o�`�T�o�j�̌����𑫂������̂ɂȂ�܂��B�@��F�V�i�x�j���T�o  �ƃx�j���P�Q�o�Ȃ�A�o���オ��́A�P�V�o�̌����ɂȂ�܂��B���ʂ��V�i�x�j���ɂ��Ȃ��Ƃ��A�ڂŌ�����������̕ЖʂŎg���܂��B �ƃx�j���P�Q�o�Ȃ�A�o���オ��́A�P�V�o�̌����ɂȂ�܂��B���ʂ��V�i�x�j���ɂ��Ȃ��Ƃ��A�ڂŌ�����������̕ЖʂŎg���܂��B�i���ꂩ��A�؍H�p�{���h�E�N�����v�S�E�x�j���̕��Ƃ���Ⓑ�߂̒����̔𐔖��E�E�E�W���ʁj   �A�x�j���Ƀ{���h��h��܂��B�x�j���S�ʂɂ܂�ׂ�Ȃ��h��ɂ́A�f��Ń{���h��L���Ƃ��ꂢ�ɔG��܂��B��́A���̌�Ό��Ő�ɂ���Α��v�ł��B�i�{���h��h��O�ɁA�x�j���̉��ɒ[���瓙�Ԋu���炢�ɔ�u���Ă����܂��B�x�j���͂��̔̏�ɍڂ�`�ɂȂ�킯�ł��B�j �A�x�j���Ƀ{���h��h��܂��B�x�j���S�ʂɂ܂�ׂ�Ȃ��h��ɂ́A�f��Ń{���h��L���Ƃ��ꂢ�ɔG��܂��B��́A���̌�Ό��Ő�ɂ���Α��v�ł��B�i�{���h��h��O�ɁA�x�j���̉��ɒ[���瓙�Ԋu���炢�ɔ�u���Ă����܂��B�x�j���͂��̔̏�ɍڂ�`�ɂȂ�킯�ł��B�j �B�x�j���̏�ɃV�i�x�j����[�i���E�E�㉺�j�������悤�ɏ悹�܂��B���̌�A�x�j���̉��ɕ~�����ɍ��킹�ăV�i�x�j���̏�ɂ����悹�܂��B���Ə�̔ɃN�����v�����āA��������͂���ŌŒ肵�܂��B�x�j���ƃV�i�x�j�������̎��ɂ����悤�Ȃ�A�����E�܂��͏㉺�̒[�ɂ҂�����ƂȂ�ׂ����p�ɓ��ĂāA�Â������ȂÂ��Œ@���Ă�����܂��B �B�x�j���̏�ɃV�i�x�j����[�i���E�E�㉺�j�������悤�ɏ悹�܂��B���̌�A�x�j���̉��ɕ~�����ɍ��킹�ăV�i�x�j���̏�ɂ����悹�܂��B���Ə�̔ɃN�����v�����āA��������͂���ŌŒ肵�܂��B�x�j���ƃV�i�x�j�������̎��ɂ����悤�Ȃ�A�����E�܂��͏㉺�̒[�ɂ҂�����ƂȂ�ׂ����p�ɓ��ĂāA�Â������ȂÂ��Œ@���Ă�����܂��B�C��ӂ�������ł�������ł��B�N�����v�ƃV�i�x�j���͂��ނ��ƂɎg�����������͂����ďI���B �p�V�R�@���ޥ����̐���́A�V���v���ɍl����H �@�E�̎ʐ^�́A�̈�̎��ƂŎg�����u�t�[�v���āv�ł��B�̑��������ق��́A���w���E���w���E�������Ŏg���Ă��܂��B�ƃ{���g��i�b�g�ōׂ��t�[�v�����ނ悤�ɂ������̂ł��B�ϋv�����l����ƁA�����������`�ō��̂������ł��傤�B����ł��ƁA�P�O�N�ʂ͎g����Ǝv���܂��B �u�t�[�v������v��̈�̃T�[�L�b�g�̎��Ƃł�낤�Ƃ��Ă��A�����ɏ�̂悤�Ȗƃ{���g��i�b�g�ő������������̂͗p�ӏo���܂��A�y�b�g�{�g�����t�[�v�ɂ�����邾���ł������悤�Ɏg���܂��B�����V���v���ɂ���ƁA������̂Ǝv���Ă��邱�Ƃ��ĊO�ȒP�ɂł���悤�ɂȂ�킯�ł��B �p�V�S�@�u�A�����v�͓���E�E�B �`�E���������u�A�����v�́A�ی�҂ƒS�C�Ƃ��Ȃ��厖�Ȃ��̂ł����A�A�����������Ńg���u���������邱�Ƃ�����܂��B�ی�҂̕��X�Ƃ����W�������Ƒ����Ă�������̂ł����A�w�N���ς�����肵�ĕی�҂��ς��Ƃ��́A������ƒ��ӂ��K�v�ł��B�A�����́A�N���X���ɑΉ����o���o���ɂȂ�Ȃ��悤�Ɋw�N�ō��ڂ����߁A����������̂��g�����Ƃ��w�ǂł��傤�B���Z�O�̒Z���Ԃŏ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�`�F�b�N�����ōςނ��̂́����������ނ悤�ɂ��Ă��肵�܂��B �@���́A���̓��̂��q����̗l�q���L�����镶�͂ł��B�ł��邾�����̎q�̃v���X�ʂ����ď����Ă����悤�Ƃ���ƁA�ی�҂ɂ���Ắu�����̎q�͂���Ȃɂ������Ƃ���̎q����Ȃ��B�����ƌ��Ă���̂��H�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�e�̐S�q�m�炸�Ȃ�ʁA�搶�̐S�e�m�炸�E�E�̂悤�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�ܘ_�A���̓��������������Ƃ⁛�����ł��Ȃ����A���_���菑���Ă���A�q�ǂ��ɑ��鎋�����₽���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��܂��B�u�������ł��Ȃ��v�ȂǂƂ������Ƃ́A�ی�҂͏[���m���Ă��邱�Ƃł��B���X���������Ă���̂Ƃ��������Ŏ~�߂�ł��傤�B �@�ی�҂����S���A�搶��M�����Ă����A�����̏������́A�u���̎q�̃v���X�ʂ�]������̂���{�ł����A�������Ƃ��菑���Ȃ��Ƃ����o�����X���K�v�v�E�u��肪�������ꍇ�́A�������Ă����Ηǂ��Ȃ�Ǝv���܂��Ƃ����������������A�ی�҂̋��͂����肢����B�v�E�u�ی�҂̗���ɂȂ��čl����v�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��ł��傤���E�E�B �@�����X�y�[�X�����Ȃ��Ďq�ǂ��B�̊w�K�̗l�q��S�C�̎v�����`������Ȃ��Ƃ����ꍇ�́A�u�N���X�ʐM�v���T�ɂP��Ƃ��Q�T�łP��͏o���Ă����悤�ɂ���Ƃ����ł��傤�B���̓N���X�ʐM���T�ɂP��͏o���āA�s�����������ꍇ�͓��W���o���悤�ɂ��܂����̂ŁA��̏T�ɂQ��͕��ς��ďo���Ă������������܂��B�Z��������Ƃ����āA�Q�T�ԂɂP����x�̒ʐM���������ȂǂƎv���Ă�����A���܂ł����Ă��ی�҂̋C�������킩��Ȃ��܂܂̐搶�ŏI����Ă��܂��܂���B �p�V�T�@�ȒP�ɍ���u�I���ėp�̓I�v���Ă���́H  �@�o�����X�������悤�ȂƂ��ɂ́A�_�u���N���b�v�������݂�ʂ̂��̂ɕς��Ď����܂��B�ʐ^�̃K�`���s���E���b�N�̓I�́A�_�C�\�[�Ŕ����Ă����J���[�{�[�h�ɃK�`���s���E���b�N�̎������̂܂Ȕ𗼖ʃe�[�v�œ\���������ł��B����ȏ�ȒP�ȓI�͂Ȃ��ł��傤�B�I��傫������Ƃ��́A�_�u���N���b�N�������݂�傫�����̂ɂ���n�j�ł��B �@�o�����X�������悤�ȂƂ��ɂ́A�_�u���N���b�v�������݂�ʂ̂��̂ɕς��Ď����܂��B�ʐ^�̃K�`���s���E���b�N�̓I�́A�_�C�\�[�Ŕ����Ă����J���[�{�[�h�ɃK�`���s���E���b�N�̎������̂܂Ȕ𗼖ʃe�[�v�œ\���������ł��B����ȏ�ȒP�ȓI�͂Ȃ��ł��傤�B�I��傫������Ƃ��́A�_�u���N���b�N�������݂�傫�����̂ɂ���n�j�ł��B�p�V�U�@��w�̐搶�͈̂��́H �`�E�u��w�̐搶�͈̂��́H�v�E�E�ƁA���܂��Ă���킯�ł͂���܂���B��w�̐搶�E�������̐搶�E����Z���^�[�̐搶�Ƃ������������̂��킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�l�ԓI�Ɉ̂��搶������A�l�ԓI�Ɉ̂��Ȃ������Ȑ搶�����邩��ł��B �@���͎��̕s���R�̊w�Z�ƒm�I�Ⴊ���̊w�Z�łP�O���N�������������Ă����̂ŁA���N���l�̑�w�⌤�����̐搶�Ɍ��C���u����ɗ��Ē����āA�F�X�Șb��������@�����܂����B���̐搶�̏����ꂽ�{���ǂ������̂ōu�������肢������A�b�����S���ʔ����Ȃ�������A���e����b�I�����ăx�e�����̐搶���ɂ͑ދ��ł�������A�����]��m��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���������搶�����܂����B�����������搶�Ƃ͈���āA�����Ŏq�ǂ��B�̂��Ƃ���M�������Ă킩��₷�����p�ɓ���������v���������搶�����܂����B �@���ʎx���w�Z�ł̋Ζ��N�������Ȃ��Ⴂ�搶���̒��ɂ́A��w�̋����⋳��Z���^�[�̐搶�Ƃ������ЂɎア�l������̂ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�B��w�⌤�����̐搶���̂��̂ł͂Ȃ��̂ł��B�̂��搶������Έ̂��Ȃ��搶������Ƃ������Ƃ̕Ћ��ɒu���Ă����܂��傤�B�{��������ڂ������Ȃ��ƁA�����搶�ɂ͏o��Ȃ��ł��傤����B �p�V�V�@���s���s����Ȏq�ɂ́A�r�������Ďx���Ȃ��E�E�H �`�E���̕s���R�̎q��m�I�Ⴊ���̏d���q�ŁA�̊����������肵�Ă��Ȃ��������ӂ�ӂ�ƕ����q�┭����N�����ċ}�ɓ|���q�����܂��B��������Ƃ��̎q�ɂ��Ă���搶�́A���̎q�̕Иr�������̗��r�ł����������Ŏx���悤�Ƃ��܂��B�������邱�Ƃ́A�����ꂻ�̎q���]�|�������ɂȂ������ɁA�r�����łȂ����߂ɑ傫�ȕ��S���|���Ă��܂����ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�q�ǂ��̘r������Ŏx���Ă���l�q������ƁA��̎q�ǂ��̘r�������グ���Č����s���R�ɏオ���Ă��܂��B����ȏ�Ԃł܂�������]�肵����A�x�����Ȃ������łȂ��A���̎q�̌��ւ̃_���[�W���傫���ł��傤�B �@�����������q�ւ̎x�����́A�̂���▧��������Ԃł��̎q�̔w�����Ɏ��L���āA���̃x���g��Ў�ł���������ނ悤�ɂ��܂��B��������Ǝx������q���y�ł����A������]�|�������ɂȂ����������₭�Ώ��ł��܂��B�����A�r�͂̂Ȃ������̏ꍇ�́A�q�ǂ��ƈꏏ�ɓ|��₷���Ȃ�̂ł����߂ł��܂���B����̂���q����s���s����Ȃ��q����ɂ́A�j�����������̂������ł��傤�B�q�ǂ����P�K������ƕی�҂���M������Ȃ��Ȃ�̂ŁA�w�N��N���X�̒S�C�Ԃł悭�b�������Ă����Ƃ����ł��ˁB �p�V�W�@���ޥ������ȒP�ɍ����@�́H 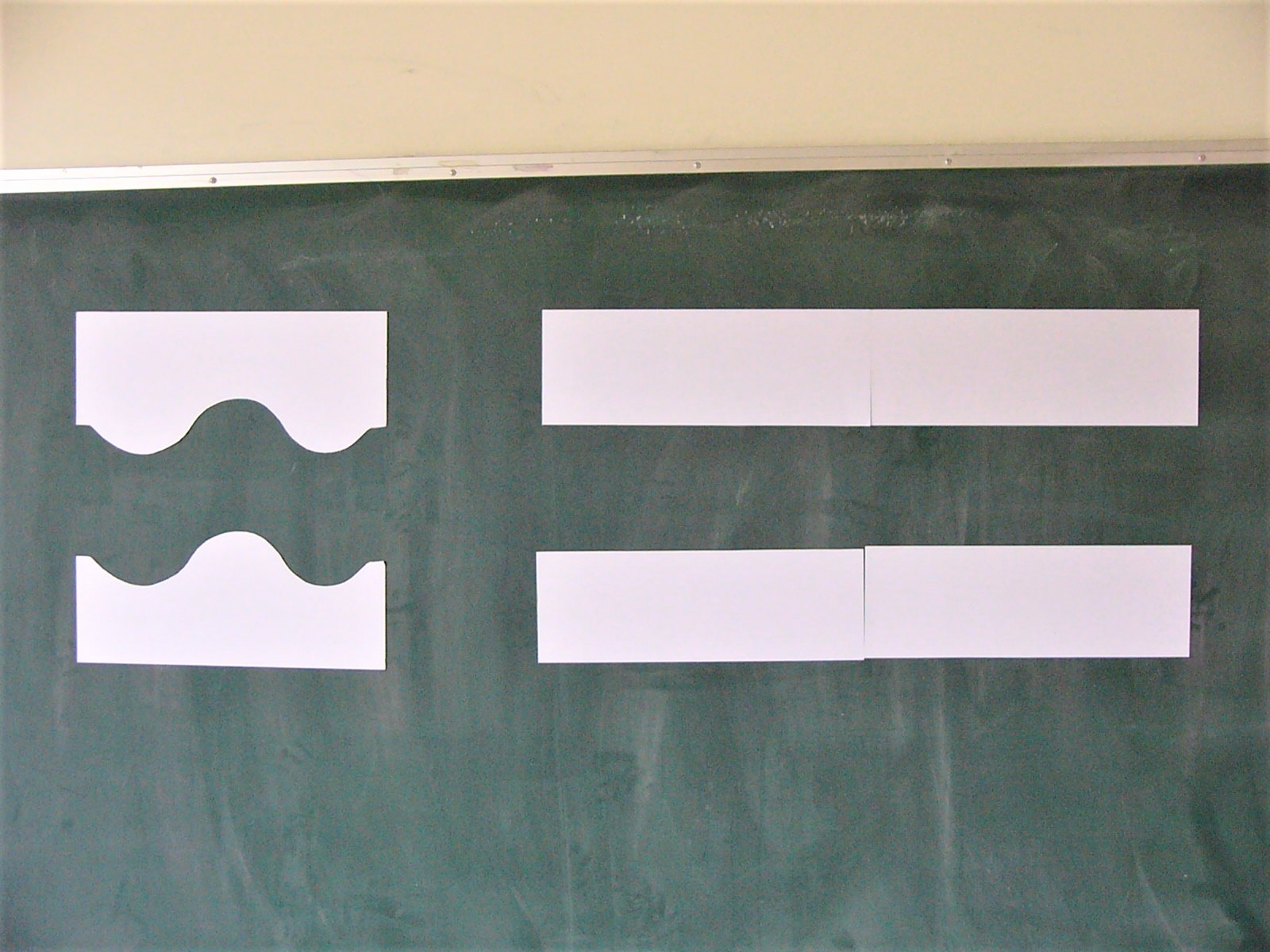 �@�Ԃ����̂́u�I�[�V�����h�����v�i�g�̉����o���y��j�Ń_�C�\�[�ɔ����Ă����|���̂�����W������悤�Ȍ`�ɂ��ĂQ�g���A���ɏ�������ꂽ�����ł��B �@����������ł���͍̂����̒�����B����G���̏��N�W�����v���d�˂ĕz�K���e�[�v�������Ă��邾���ł��B�g�߂ɂ�����̂��g������A�P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j�̏��i��g�ݍ��킹�邱�ƂŁA���ޥ����͊����ȒP�ɍ��܂��B �p�V�X�@�̂ĂȂ��łƂ��Ă����Ƌ��ލ��Ɏg������̂��ĉ��H �@���b�v�̎��̐c�E�v�����̃J�b�v�E��̃y�b�g�{�g���E�X�`�[�����̋ʁE�L���b�v�t���̋ʁE�X�[�p�[�̃g���C�E�����p�b�N�E����G���ӂ�́A�F�X�ȋ��ނ�}�H�̍�i���{�̍ޗ��ɂȂ�܂��B �@�E��̎ʐ^�́A�w�̒Ⴂ�q�p�̍����̒�����i�G�����g���Ă��Ă��܂��B�j�Ƙa���̃g���C�i�^�g�Ƃ��ăX�[�p�[�̃g���C���g���Ă��܂��B�j�B���̎ʐ^�́A����̊y��u�J�Y�[�v�i���b�v�̎��̐c���g���Ă��܂��B�j�ƃX�|���W�̃X�^���v�i�v�����J�b�v���g���Ă��܂��B�j�ł��B����ȊO�ɂ��u�y�b�g�{�g���̕����ցv�E�u�ʓ���v�E�u�n�k�̌��Ձv�Ȃǂ�������܂����A���肪�Ȃ��̂ŏЉ�͂��̕ӂŁB�@�F�X���邱�Ƃ��킩��܂������H�@�E�E�E�ց[�����ȂƎv��ꂽ�ł��傤�B�ĊO�F�X�Ȃ��̂����ނɉ����Ă����܂���B �p�W�O�@�C�R�����ׂȂ��q�̎w���́H �`�E�C�R�̌��ѕ����o���Ă��炤���Ƃ́A�ƂĂ�������Ƃł��B�F�X�ȂЂ����т̋��ނ�p�ӂ��Ă��A�������k���ł���悤�ɂȂ�����͏��Ȃ��ł��B�Ⴊ���̒��x���傫���e������̂ň�T�ɂ͌����܂��A������x�F���͂������Ȃ��Ɩ����Ȃ̂�������܂���B�����Łu��������Ƃ����ł���v�ƌ����Ȃ��̂��c�O�ł��B �@�C�R�����ׂȂ��q�͂ǂ������炢���̂��ƍl����ƁA�N�ł��v�����̂̓}�W�b�N�e�[�v��W�b�p�[�t���̌C�ł��ˁB�������Ђ����тɃ`�������W���Ă��ł��Ȃ��ꍇ�́A�Ђ����тɂ͂������Ȃ��Ă����Ǝv���܂��B�Ⴊ���̂Ȃ��l�B�ł��A����҂ɂȂ�ΐF�X�ȖʂŏႪ���������悤�ɂȂ�A���ł��邱�Ƃ��ő���������悤�Ȑ����ɂȂ�킯�ł�����E�E�B �p�W�P�@�ʓ���̊ʂ��A�����������Ȃ����́H �`�E�u�ʓ���v�̋��ނ���鎞�ɁA�ʂ��ʂ̒�ɗ��������ɂ�����������悤�ɋ������̊ʁi�Ⴆ�����̊ʂ�100�~�V���b�v�Ŕ����Ă���ʂȂǁj���g���܂��B�����������邱�ƂŎq�ǂ������ɂ��C��������悤�ɂ��悤�Ƃ��Ă���킯�ł����A���ۂɋʂ�����Ɗ��҂ǂ���̉��͂��܂���B �@���������o���ɂ́A�ʂ̒ꂪ�ʂ�u���������班�������悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�܂���B�ʂ̒�̂S���ӏ��ɏ����������i�P�p�����炢�j��\��t���邱�ƂŌ��Ԃ�����Ă�����A�u�J�[���v�Ƃ������������o���܂��B�u�������������Ƃ��o�Ȃ��v�ƔY��ł��鎞�ɂ́A���̕��@�������Ă݂Ă͂������ł��傤���E�E�B���A���������o��ʂ̓X�`�[�����̂��̂ŁA�P�O�O�~�V���b�v�ł悭�����Ă���A���~���̂��̂͂������͂ł܂���A�����ۂɃX�`�[�������A���~�������m�F����Ƃ����ł��傤�B �p�W�Q�@�N���A�t�@�C���i�N���A�t�H���_�[�j��r�j�[���P�ɐF��h�肽�����́H �@�A�N�����G�̋�͐��X�Ŕ����ƌ��\���܂����A�_�C�\�[�Ŕ����Ă�����̂ő��v�ł��B�N���A�t�H���_�[��r�j�[���ɓh��ꍇ�́A�N���A�t�H���_�[���̕\���̖ʂł͂Ȃ������̖ʂɓh��Ƃ����ł��傤�B��������ƕ\�����猩���Ƃ��Ɍ���̂��邫�ꂢ�Ȏd�オ��ɂȂ�܂��B�����v�V�F�[�h�ȂǍ�i���Ŗ𗧂��܂�����A��x�����Ă݂�Ƃ����ł���B�܂��͐搶���������Ŏ���������Ȃ��Ǝ��Ƃɂ͂Ȃ�܂���B �p�W�R�@���܂Œʂ�ɋ^������H �`�E�u���܂Œʂ�v�ɋ^������Ƃ����̂́A�Ⴆ����Ȃ��Ƃł��B���P����s�R�ґΉ��P���͖��N�s������̂ŁA�S�����镪���̌W�ł������茟������Ă�����̂ł����A���N���e���ς��Ȃ��̂͂ǂ����Ăł��傤�B���e����������K�v���Ȃ��قǂ������̂ɂɂȂ��Ă��邩�A�S���҂���N�ʂ�ł����Ǝv���Ă��邩��ł͂Ȃ��ł��傤���E�E�B �@��������ł����Ƃ����Ƃ́A�w�ǂ̎����ɂ����Ă���܂���B���P���ł́A�Ђ̔����ꏊ�����N������������A�n�k�Ŕ��Ɏg���Ȃ��Ȃ�ꏊ�������������肵����A���ۂ̉Ђ�n�k�őΉ��ł��Ȃ��Ȃ�ł��傤�B�ǂ�Ȃ��Ƃ������邩�킩��Ȃ������������Ђ�n�k�ɑΉ�����ׂɂ́A�F�X�ȃV�`���G�[�V�������l���Ȃ���Ȃ�܂���A���N�����ƌ������Ƃ͂��肦�Ȃ����ł��B �@�s�R�ґΉ��P���ł́A�ʕ��������Ɋe�K�̘L���������W�����܂����A�����܂��������Ă��Ă���l�̋����ł͐n�����������s�R�҂ɂ͑Ή��ł��Ȃ��̂ɁA�e�K�P���̂܂܂̌v��ł͖w�LjӖ����Ȃ��ƌ�����ł��傤�B �@�P���ׂ̈̌P���ɂȂ��Ă��Ȃ����A���܂Œʂ�ł����̂��^��������Ȃ��ƁA�u���̎��������Ă����Ηǂ������v�ƌ�����邱�ƂɂȂ�܂��B�h���w�K��Z�O�w�K�Ȃǂ���������Ƃ��ɂ��A�O�N�x�̌v��Ă͎Q�l�ɂ���Ƃ��Ă��A���܂Œʂ�Ƃ������Ղȍl���͎̂Ă܂��傤�B�������̂͐搶�ł����A��Q�ɑ����͎̂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��q�ǂ��B�ł�����B���܂Œʂ��]��������̂́A�Ⴂ�搶���̐V�N�Ȕ��z�͂ł��B �p�W�S�@ �p�W�T�@���̊w���E�w�N�̐搶�Ƙb��������͉̂��������́H �`�E�w�N���Ⴄ�Ɗw����炢�ł������w�N�̐搶���Ƙb���@��Ȃ��Ƃ����搶�͂��܂��H�@�܂��Ă⑼�w���̐搶�Ƃ͖w�ǘb���������ƂƂ��Ȃ��Ƃ����l�͂����Ƒ�����������܂���ˁB�w���Ƃ����c�̂Ȃ��肪�A���قǂȂ��̂����ʎx���w�Z�ł��B�Ȃ��肪�ł���̂́A�������ψ���⓯���̐搶�����炢�ł��傤�ˁB���ʎx���w�Z�́A�E�����������Ƃ����̂��Ȃ��肪���Ȃ����R��������܂���B�����Ζ��������̕s���R�Z�͐E�������P�U�O���ʂ͂��܂�������E�E�B �@���w�N�ɂ́A�����Ȃ����S�C���Ă��邨�q����̌��̒S�C�������搶��M���ł���E���h�ł���搶�����邩������܂���B����Ȑ搶���Ƙb�����Ƃ́A���Ȃ����S�C���Ă���q�̎w���ɖ𗧂��A���Ȃ����g�̕��ɂ������ƂȂ�ł��傤�B�܂��A���w���̐搶���Ƙb���ƁA���������������Ă���q�ǂ��B�����w���łǂ�Ȋw�K���e���s�����E�s���Ă��������킩��܂��B�q�ǂ��B�ɂƂ��Ĉ�ԑ厖�Ȃ��̂̓R�~���j�P�[�V�����̗͂ł����A��l�����ē����ł�����B �p�W�U�@�ی����Ƃ̘A�g���ĉ��H  �`�E�ی����Ƃ����ƁA�g�̑���̎��Ɛ��k����������������Ƃ����炢���������b�ɂȂ��Ă��Ȃ��搶������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���܂ɗp���Ȃ��̂ɕی����ɂ��傭���傭����o���āA�ی��������܂��̂悤�ɂ��Ă��܂����ӂ���Ă���搶���������܂����E�E�B �`�E�ی����Ƃ����ƁA�g�̑���̎��Ɛ��k����������������Ƃ����炢���������b�ɂȂ��Ă��Ȃ��搶������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���܂ɗp���Ȃ��̂ɕی����ɂ��傭���傭����o���āA�ی��������܂��̂悤�ɂ��Ă��܂����ӂ���Ă���搶���������܂����E�E�B�@�ی����Ƃ̘A�g�Ƃ́A�얞�����ŘA�g���Ƃ�ƌ������Ƃ����ł͂Ȃ��A�������w����C���t���G���U��A�����M�[�̖�蓙�A�l������q�ǂ��B�̌��N�ʂ̑S�ʂɂ��āA���X�b�����悤�ɂ��邱�ƂƒS�����Ă���q�ǂ��B�̏���`���邱�Ƃł��B�ی����̐搶���́A���������������������������ʂ̒m�����L�x�ł�����A�킩��Ȃ��_�₱�ꂩ��C��t���Ȃ���Ȃ�Ȃ��_�ȂǁA�F�X�Ƌ����Ă��炤�Ƃ����ł��傤�B�܊p�A�ی���������̂ł�����A���݂��Ɋ�����������ǂ��W������Ă����܂��傤�B �p�W�V�@�V��̓_���͒N������́H �@�Œ�V��̖w�ǂ́A���̊w�Z�����ꂽ�Ƃ��ɐݒu���ꂽ���̂ł��B�n���R�O�N�̊w�Z�ł���A�Œ�V������t�����Ă���R�O�N�Ԃ͌o���Ă���ƌ������Ƃł��B�����`�F�b�N����K�v�͂���܂��A�������Ă��Ȃ����E�{���g�i�b�g������ł��Ȃ����E�������������H���Ă��Ȃ������A���܂ɂ̓`�F�b�N���Ă����܂��傤�B�C������Ζh���鎖�̂��Č��\����܂���B�@ �ʐ^�̋���́A�u�����R�̃��[�v��������������̂ł��B�J���r�i�̂悤�ɂȂ��Ă���̂ŁA�������Ȏq�ł��o�[��������Ɖ����ƕ��Ă��镔���������Ă��܂��܂��B�����Ńr�j�[���̊ǂ��c�ɐ������̂����ăr�j�[���e�[�v�ŌŒ肵�����̂ł��B�������邱�ƂŎq�ǂ��B���G���Ă��댯���Ȃ��Ȃ�܂����B �p�W�W�@�k�Ђ��l����H  �@�w�Z�ł͐k�Ѓ}�j���A�������肵�P�����ȑO������������s���Ă���悤�Ɏv���܂����A�k�Ђ͍����E�������邩���킩��܂���B�����̒I�̏�ɂ��̂�u���Ȃ��E���o�H�ɂȂ�ꏊ�ɂ��̂�u���Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ́A�݂�Ȃ��킩���Ă��邱�Ƃł����A���ꂪ�O�ꂳ��Ă��Ȃ���ΊG�ɕ`�����݁B �@�g���������J�[�h�������Ă��A�����Ƃ����Ƃ��Ɏq�ǂ��B���g�ɂ��Ă��Ȃ���Ζ𗧂��܂���B�X�N�[���o�X�̒��ɂ���A�Ƃ肠�����A�������Ĉ���S�A�Ƃ�����̂ł��傤���B�l���o�����炫�肪�Ȃ����Ƃł��B�ł��A�q�ǂ��B��a�����Ă���搶�����l���Ȃ���A�q�ǂ��B������Ă��Ȃ��Ƃ������o�������܂��傤�B�q�ǂ������̂͑�l�̖�ڂł�����B �p�W�X�@�C���t���G���U�̗\�h�ڎ� �`�E�~�ɂȂ�ƃC���t���G���U���͂�肾���A�N���X�̎q�ǂ��B���|�c�|�c�Ƌx�ނ悤�ɂȂ�܂��B���ɂ͍��M���o���Ă���ɂ��ւ�炸�A�ی�҂��o�Z�����Ă��܂��Ƃ����������P�[�X�������܂��B�q�ǂ��B�ɂ��ẮA�e�ƒ�̔��f�ŗ\�h�ڎ���s���킯�ł�����A�S�C�Ƃ����ǂ����͏o���܂���B�ی�������u�ی��������v���ōL�Ă��炤���炢�����ł��Ȃ��ł��傤�B �@�����Ō����C���t���G���U�̗\�h�ڎ�Ƃ́A�搶���ɂ��Ăł��B�����͂����邵�ʓ|�������ȂǂƂ������R�ŗ\�h�ڎ���Ă��Ȃ������ׂɁA�q�ǂ��B�ɐ搶�̃C���t���G���U����������ǂ��ł��傤�B���ꂾ���ŕی�҂���̐M���͎��Ăł��B�������ی�҂�������ƍl����킩�邱�Ƃł��B�q�ǂ��B�̂��Ƃ���ɍl���āA�܂��͐搶���C���t���G���U�̗\�h�ڎ���܂��傤�B����ł��C���t���G���U�ɂ������Ă��܂����ꍇ�́A�������ی�҂��킩���Ă���܂��B �p�X�O�@���߂���ł���l�͂��Ȃ��H �`�E���̐搶�́A����ے��ɏڂ����E���̐搶�͋��ލ�肪�ƂĂ����܂��E���̐搶�͉p��b���ł��铙�X�A�E�E�E�����͉����ł��Ȃ��Ɗ����Ă���Ⴂ�搶�͂��܂��B�ł��A�搶�ɂȂꂽ�͎̂��������撣��������ł��傤�B�q�ǂ��̍��A���]�Ԃɏ���悤�ɂȂ����̂́A���x���]��ŏ���悤�ɂȂ�������ł��傤�B�͂��߂��牽�ł��ł���l�Ȃ�Ă��܂���B �@���ލ��Ō����A���̏ꍇ�͐�y�̐搶���̋��ށE��������悤���܂˂ō��o���Ă��A���߂̍��͎��s����ł����B�Ȃ�Ƃ��������̂�����悤�ɂȂ��Ă����̂́A�S�O�ʋ��ށE�������������ł��傤���B���s���Ă��A��������Ύ��s����Ƃ킩�邾���ł����n�ł��B�R�c�R�c�Ɗw�ё����āu�ڂ����l�E���܂��l�E�킩��l�v�ɂȂ邵������܂���B��������Ă��邱�Ƃ����N��Ɏ�������̂ł�����A��������ĂƂĂ��������̂ł��B�u�p���͗͂Ȃ�v�E�E�A�킩���Ă��邯��Ǔ���B �p�X�P�@�����������ł͂Ȃ��A�N�����������厖�H �`�E�E����c��w����E�w�N��E������E�w�K�O���[�v���̉�c�Ő��_�i�H�j���q�ׂĂ��A�����Ă���l���݂�Ȃ���M������Ă��Ȃ��搶��������A�N���u��������ˁB�v�Ƃ͎v���Ă͂���܂���B�Ԉ�������Ƃ������Ă��Ȃ��Ă��A���i�̍s�����悭�Ȃ��E�d���Ɏ蔲��������E������n���ɂ��Ă���E�q�ǂ��B�������Ă��肢��搶���������ƂȂǁA�������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B �@����Ƃ͋t�ɁA�݂�Ȃ���ς������肽���Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ������Ă��A���̈ӌ��ɂ͔����Ƃ����搶�����Ă��A�u�����搶�������Ȃ玨���X���܂��傤�B�v�ƁA������搶�����܂��B���̐搶�̐l����d���Ԃ���݂�Ȃ��m���Ă��邩��ł��B�����̒m����m�b���������ł����_�ۂ����Ƃ��������Ƃ͂ł��܂����A�l����d���Ԃ�́A�꒩��[�ɑU����悤�Ȃ��̂ł͂���܂���B �@�Ⴂ�搶���ɂ́A�����u�����搶�������̂�������E�E�E�v�ƌ�����悤�Ȑ搶�ɂȂ��Ă����ė~�������̂ł��B�����Ő����Ŏq�ǂ��B��厖�ɂ���搶�ɁB �p�X�Q�@�u����̒�������? �`�E�w�Z�ł́A��w�̐搶�⋳��Z���^�[���̐搶���Ă�Ŗ��N�u����⌤�C��s���Ă��܂����A���Ȃ��̐S�Ɏc�����u���⌤�C��͂ǂꂾ������܂����H�@�u���⌤�C��Řb�����āA���̌��ʂ������Ƃ��ł���悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ�����܂������H �@�E�E������ƃV�r�A�Șb�ɂȂ�܂������A���̌o�����猾���ƁA�����������o���͏��Ȃ������ł��B�ܘ_�A�O�ł͂���܂��A���Ȃ��������Ƃ͖{���̂��Ƃł��B����͉��̂��Ƃ����ƁA�u���̎��Ԃ��Q���Ԃ��炢�ƒZ�����Ƃ���̗v���ł��B�Z�����ԂŃe�[�}�ɉ����Ęb���Ă���ƁA�Œ���̎��������`���邱�Ƃ��ł��܂���B�ǂ�ȂɗD�G�ȍu�t�̐搶�ł��A���Ԃ�����Ȃ��̂ł͓`���������Ƃ��C�E���E�n�̃C�ŏI����Ă��܂��̂ł��B���g�̔Z���b�����n�܂�O�ɍu�����I����Ă��܂��̂ł�����A�S�Ɏc��͂�������܂���B �@�܂��A�u�����ꂵ����w�̐搶�Ƃ����ǂ��A�V�C�̐搶����x�e�����̂S�O�E�T�O��̐搶�܂ŁA�݂�Ȃ��ǂ������Ǝv����悤�ȍu���⌤�C�͓���ł��傤�B��̐^�̃��x����z�肵�Ă��b�����Ă���悤�ł����A��b�E��{�̂悤�Ȃ��b����{��ǂ߂킩��悤�Șb�������̂ł��B�������ōu�����ɃA���P�[�g���̂�ƁA�Q�O��̐搶���ɂ͍D�]�ł��A�R�O��ȏ�ɂȂ�ƕs�]�Ƃ������ʂɂȂ��Ă��܂��܂��B �@�u����⌤�C��́A���̃e�[�}�Ɋւ��Ă̊w�т̑����Ƒ�����̂��ǂ��Ǝv���܂��B�Ⴂ�搶���́A�u����������Ȃ������Ƃ������x���܂ł����悤�ɕ����Ă����܂��傤�B��b�E��{���Ċ��S���Ă���悤�ł́A�܂��܂��E�E�B �p�X�R�@�ی�҂Ƃ̖ʒk�����ɍs���ɂ́H �`�E�w�����Ƃɕی�҂Ƃ̖ʒk���s���܂����A�u���Ɂv�Ƃ����̂́A�u���܂��v�Ƃ����e�N�j�b�N�ł͂ł͂���܂���B�\�ߓ`���������Ƃ����Ă����A�Œ���`���邱�Ƃ�Y��Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃ��܂��厖�ł��B�ی�҂̗��ꂩ��l����ƁA�u�Ƃ̎q�̂��Ƃʼn���������̂��낤�H�v�ƐS�z���Ă��邱�Ƃ������悤�ł��B�ی�҂������b�N�X�ł���悤�ɏΊ�ő��A��{�I�ɂ͕������ƂɓO���܂��B �@�w�K�Ɋւ��Ęb���ꍇ�́A�����u������Ă܂�����B�v�ł͉����ǂ��撣���Ă��������킩��܂���A�ۑ�Ƃ��̂��ƂɊւ��Ăǂ�������Ă��ĕω��i�����j��������b���Ă�����Ƃ����ł��傤�B�S�C���q�ǂ��̐�����e�̂悤�Ɋ��ł���Ă���Ƃ������Ƃ��`���A�ی�҂̕��X�͈��S���A�����搶�ɏo����Ɗ����Ă���܂��B�搶���ْ����߂��Ă���ƁA���ْ̋����ی�҂ɓ`�����܂�����A�܂��̓X�}�C���E�X�}�C���ł����܂��傤�B �p�X�S�@�ŐV�̏���m���Ă���H �`�E�ی�҂̒��ɂ́A���̋����ȏ�ɍŐV�̓��ʎx������̏����L���[���m���Ă���������܂��B����́A�C���^�[�l�b�g�̕��y��ی�҂̕��X�̍��w����������̂ł��傤�B�܂�ɂ����������m����ɂ��悤�Ƃ��鍢�����ی�҂����܂����A�w�ǂ̕��́A���q����̏Ⴊ���ɂ��ĕK���ɂȂ��ĕ����Ă������X�ł��B�w�Z�ł́A�ی�҂Ƃ̘b�������̒��ł킩��Ȃ����Ƃ���������A�u�킩��܂���B�v�Ƃ͌���Ȃ��ŁA�u��ŕK�����`���i�������j���܂��B�v�Ƙb���悤�ɂ��Ă���Ƃ��낪�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@���̕��j�͊ԈႢ�ł͂���܂��A���x���������������Ƃ�����ƁA�ی�҂́u���̐搶�́A�����Ă��Ȃ��B�v�Ǝv���Ă��܂��܂��B���Ȃ��������ی�҂�������A�����悤�Ɋ�����ł��傤�B�搶�̎d���͓e�Ɋp�Z�����̂�����ł����A�ی�҂���M�������悤�ɂȂ肽���̂ł���A�ŐV�̏��ɂ��Ă��m���Ă��Ȃ���Ȃ�܂���B �@�搶�ɂȂ������肾����A�Ⴂ����E�Ս̂�����ł͒ʗp���܂���B�ی�҂��猩��݂�Ȑ搶�Ȃ̂ł�����E�E�B �ی�҂̕��X�������搶�Ƃ��肨�t�������o�����킯�ł͂���܂���B�u���x���������搶�Əo����炢���Ȃ��v�ƐȂ��]�݂������Ă����ł��B �@�V�������́A���ʎx������W�̌�������G�������瓾��Ƃ����ł��傤�B���b��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ₱�ꂩ��b��ɂȂ�ł��낤���Ƃ���ʎx������̌��ꂪ������ۑ��w���@�Ȃǂ̏������Ă��܂��B��������������ǂݍ���ł���A�u���̐搶�͕����Ă���Ȃ��v�ƕی�҂̕������S�ł���ł��傤�B�����ׁ̈A�q�ǂ��B�̂��߂ɂ��A�ŐV���͒m���Ă���ׂ��ł��B �p�X�T�@�u�w���ʐM�v�ŋC��t���邱�Ƃ͉��H  �`�E�u�w�N�ʐM�v�́A���T�́u�P�T�Ԃ̊w�K�̗\��\�v��s�����̂��m�点�Ŏ��ʂ���t�ɂȂ��Ă�����̂������ł��傤�B����A�w���ʐM�́A�N���X�ł̏o������w�K���̂��q����B�̗l�q��`������̂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �`�E�u�w�N�ʐM�v�́A���T�́u�P�T�Ԃ̊w�K�̗\��\�v��s�����̂��m�点�Ŏ��ʂ���t�ɂȂ��Ă�����̂������ł��傤�B����A�w���ʐM�́A�N���X�ł̏o������w�K���̂��q����B�̗l�q��`������̂������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@�w���ʐM�ŗ��ӂ��ׂ����Ƃ́A�q�ǂ��B�̗l�q��`����ۂɂ́A�ǂ̎q�����������グ�邱�ƂƎʐ^�̓N���X�̑S�����ʐM�̒��ɉf���Ă��邱�Ƃł��B�q�ǂ����Ƃɕ��̗͂ʂ��Ⴂ�����Ȃ��悤�ɂ��A�ʐ^�Ɏʂ��Ă��Ȃ��q����l�ł����Ȃ��悤�ɂ��邱�Ƃł��B�܂��A�q�ǂ��̖��O���ԈႦ�Ȃ����Ƃ�������O�̂悤�ł����厖�Ȃ��Ƃł��B �@�����̂��Ƃ��~�X���Ă��܂��ƁA���̎q�̕ی�҂́u����H�v�Ǝv������A�u�ǂ����āH�v�Ǝv���Ă��܂��܂��B����ȕی�҂̕��ł�����̏�͋����Ă����ł��傤���A�Q�x�ڂ͂����͂����܂���B�������b������ƃr�r���Ă��܂��搶�����邩������܂��A����ȂɃr�r��K�v�͂���܂���B�����ƃ`�F�b�N����Ζ��O���Ԉ���Ă��邱�Ƃ�ʐ^�Ɂ������ʂ��Ă��Ȃ��Ȃǂ́A�����ɂ킩�邱�Ƃł�����B�~�X���o��̂͑�́u�ʐM�v���̎d�����x���Ȃ��āA�`�F�b�N���[���ɂł��Ȃ���Ԃł�����܂��B�d���͑��ߑ��߂ɂ���悤�ɕ��i����S�|���܂��傤�B�ی�҂Ƃ̐M���W��z����̎�i�ł���u�w���ʐM�v�ŁA�M���W���Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɁB �p�X�U�@�m�邱�Ƃŕ|���Ȃ��Ȃ�H �`�E�V�C�̐搶��Ⴂ�搶�́A�w�Z�̒��ł̐F�X�Ȏd�������߂ĂÂ����ł��傤�B���߂đS�̂̒���Ń}�C�N�������Ĕ���������A�����ł�������Ƃ̂Ȃ��W�ɂȂ�����A�w�N�ʼn�����Z�O�h���w�K�̌W�ɂȂ�����ƁE�E�B �@�E�����������킩��Ȃ��Ƃ���ɂۂ�ƒu���čs���ꂽ�悤�ȕ|���������邩������܂���ˁB�N�ł��ŏ��͂����ł��B�킩���Ă��邱�Ƃł���Ύ菇��������ŃR�c�R�c��邾���ł����A������n�߂�Ηǂ��̂��킩��Ȃ�������A����^���Âł����́B �@�킩��Ȃ����Ƃ́A�킩���y�ɂǂ�ǂ��Ă��������ł��B�����Ȃ�ɂ킩��Ȃ����Ƃ����Ă��畷����Ƃ����̂ł����A���ꂳ���킩��Ȃ��ꍇ������܂���ˁB�������Ȃ��łǂ�ǂ��Ηǂ��̂ł��B �@��������ĂЂƂЂƂd�����o�����Ă����A�菇����邱�Ƃ��₪�Ă킩��悤�ɂȂ�A�킩��Ȃ��ĕ|���Ƃ͎v��Ȃ��Ȃ�܂��B�|�����Ă��Ȃ��Ŕ�э��ދC�����Ől��������W������Ă݂�ƁA�ǂ�ǂ�킩�邱�Ƃ������Ď��M�Ǝ��́i�d���́j�����܂��B�S�z���Ă���ɂ���������A�܂��͐�y���畷���E�����Ă��炢�܂��傤�B���Ȃ��̂��ɂ́A�l�ԓI�ɗD�ꂽ������y����������ł��傤�H �p�X�V�@�q�ǂ��B���������Ƃ��搶�́A�|���搶�H �₳�����搶�H �`�E�ŋ߂͂������ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă����C�����܂����A�ȑO�͂悭�̈�̐搶��j�̐搶�ŁA�q�ǂ��B�ɑ吺���o�����肷��Ј��I�ȑԓx���Ƃ�l�����܂����B����͂ǂ����Ă��Ƃ����ƁA�\�ꂽ�肷��q���������ƂĂ������������Ƃ�����܂��B���̎q�ǂ��B�́A�����Đ̂������₩�Ȏq���������������܂��B �@�E�E�E�|���搶�̌������Ƃ́A�\���悤�Ȏq�����̐搶���|������悭�������Ƃ��Ă��܂����B�����Ă����ƌ������]���Ă����ƌ������������ł��傤�B�x�e�����ɂ����������搶������ƁA�Ⴂ�搶�Ŋ��Ⴂ�����Ă��܂��搶���o�Ă��܂��B�q�ǂ��͐����ŁA�|���l�̌������Ƃɂ͕����܂����A�D�����l�̌������Ƃ͕����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����ł��B �@�u�����������Ό������Ƃ��v�ȂǂƊ��Ⴂ���Ă��܂��킯�ł��B�q�ǂ��͑�l�̊�F�����������Ă��邾���ŁA���̐搶�����������猾�����Ƃ��Ă���̂ł͂���܂���B�q�ǂ��B���Ј����ď]�킹�Ă��邱�ƂɋC�Â����A�������Ȏ��M�����������u�o�J�v�ƌ����̂ł��B�Ⴂ�搶�́A�o�J�ɂȂ�����o�J�����K��Ȃ��悤�ɁB�q�ǂ��B��l��l��厖�ɂ��錵�����D�����搶���A�Ⴂ�搶���̂���{�ł���B �p�X�W�@�̈�̃��[�_�[�̐搶�݂̍���́H �`�E���J���Ƃŏ���̑̈�̎��Ƃ������Ƃ��̂��Ƃł��B���[�_�[�̎Ⴂ�j�̐搶�𒆐S�Ɏq�ǂ��B���傫�ȗւɂȂ��č����Ă��܂��B�q�ǂ��B�̑��ɂ͐搶�����āA�搶�P�l�ɂ��q�ǂ��B���S�`�T���B���[�_�[�̒j�̐搶�̐��|���ŃX�g���b�`�̂悤�ɑ̂����܂����A�q�ǂ��B�ɂ��Ă��鏗�̐搶�̐������Ȃ��̂ŁA�����̎q���炢�������Ă����邱�Ƃ����ł��܂���B �@�q�ǂ��B�����[�_�[�̐搶�̖͔͂̓������ł���܂ŁA�Ⴂ�j�̃��[�_�[�̐搶�͂����ދ������ɂ��Ă��邾���ł����B����ł̓��[�_�[�ł��Ȃ�ł�����܂���B���|�����ė������邾�������[�_�[�̖������Ǝv���Ă���̂Ȃ�A�b���ɂȂ�܂���B �@�q�ǂ��B�ɂ��Ă���搶���̎肪����Ȃ��킯�ł�����A���R�w�ǂ̎q���͔͂̓����Ȃnj��Ă��Ȃ�����낤�Ƃ����Ă��Ȃ��̂ł��B���[�_�[���̎Ⴂ�j�̐搶������ׂ����Ƃ́A�����̗�������S�̗̂l�q�����āA�肪����Ȃ��Ƃ���ɏo�����Đ搶���̕⏕���s�����Ƃł��B�ځ[���Ƃ��Ă��邾���ŁA�q�ǂ��B�݂�Ȃ̓������ł���̂������҂̂ł̓��[�_�[���͖��܂�Ȃ��ł��傤�B �p�X�X�@�S�C�ԂŃt�H���[���������āA���Ƃ��ǂ�ȏ�ʂŁH �`�E�S�C���m���͂����킹�Ċw���o�c������͓̂��R�̂��Ƃł����A�悭����搶�Ƃ���Ȃɂ͎���Ȃ��搶���g�ނƂ�����Ɠ�����Ƃ�����܂��B����ꂽ�q��]�莶��Ȃ��搶����Ńt�H���[������Ă���܂��H�@ �@����Ƃ͕ʂ̂��ƂɂȂ�܂����A�N���X�̒��Œm�I�ɍ����q�������łȂ��q��n���ɂ���悤�ȑԓx��p�ɂɎ��悤�ȏꍇ�́A���̓s�x���ӂ��Ă����X���܂�Ȃ��ꍇ������܂��B������ƂȂ��߂����\�ߒS�C���m�Řb�������Ă����A���i�̎�����ł͂Ȃ���������������邱�Ƃ�����܂����B���̏ꍇ�A������Ƃ������Ȗ��͕��i�]�莶��Ȃ����̐搶�����߂܂��B��̂̎q�������o���Ă��܂����炢����܂����A���i�悭����搶���t�H���[�������邱�ƂŁA�q�ǂ��͑f���ɗF�B�⎶�����搶�Ɏӂ邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�A���̌�̓N���X�̕��͋C�������ƕς���Ă����܂��B �@����́A�q�ǂ��������قǎ���Ȃ����Ƃ������Ƃł͂���܂���B������E�t�H���[����������O�ɘb�������Ė������S����̂����ʂ�����Ƃ������Ƃł��B�悭����搶���A�����͂������Ȗ���肾�Ȃ��Ǝv���Ă��邩������܂����B �p�P�O�O�@�Z�O�ł́A�q�ǂ�����ڂ𗣂��Ȃ��͓̂�����O�H �`�E�w�Z���͖ܘ_�̂��Ƃł����A�Z�O�ɏo���ꍇ�͎q�ǂ��B����ڂ𗣂��Ȃ��͓̂�����O�̂��Ƃł��B�Z�O�ɏo��ۂɂ́A�搶�����C���Ďq�ǂ��B�����̂ɑ���Ȃ��悤�ɁA�ǂ����֍s���Ă��܂�Ȃ��悤�ɂ��܂����A���Ƃ���������Ƃ������Ƃ�m���Ă����܂��傤�B �@�E�E����́A�q�ǂ��B�̒N���������Ă������̂����ɓ���Ă��܂�����A�}�ɑ���o���Ă��܂�����A��������������肵����A�]��ŃP�K�������肵���Ƃ��ɕ\��܂��B �@�搶���S���̒��ӂ����̎q�̕��Ɉ�u�������Ƃ��ɁA�ʂ̎q�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ������Ƃ�������̂ł��B�������������Ă��A�S�̂ɖڂ�z�点��Ƃ������Ƃ�S�|���܂��傤�B�������邱�ƂŁA�������Ōx�@�܂ŌĂ�ł��Ȃ��Ȃ����q�ǂ���T���Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂���B �p�P�O�P�@�q�ǂ��B�͌������Ă���B�����H �`�E���i�͎q�ǂ��B�̑O�ŏΊ�ł��邱�Ƃ��Ȃ��A�q�ǂ��B�̑�������Ȃ����A���X�ی�҂̈����������搶���Ă��܂���ˁB���������搶�Ɍ����āA���J���Ƃ���ƎQ�ς̓������́A�₽��q�ǂ��B��ی�҂Ɉ��z�������Ƃ����̂��������Ƃ͂���܂��H�@���i����q�ǂ��B��厖�ɂ��Ă��邠�Ȃ����A���������搶������ƕ����������ł��傤�B�ی�҂̒��ɂ́A�����������U���̂����搶�ɂ��܂���Ă��܂��������܂��B �@�E�E�ł��A�q�ǂ��B�͏Ⴊ���������Ęb�������ɂł��Ȃ��悤�Ȏq�ł��A�����̂��Ƃ��ɂ��Ă���Ă���搶�ƋU���̐搶�Ƃ���������ƌ������Ă��܂��B�ނ����l�i�ی�ҁj�����������͂͂��邩������܂���B��l�ɂ��ׂ��͌����Ă��A�q�ǂ��ɂ͌����܂���B�ɂ����̂̐搶�̂���Ă��邱�ƂȂNjC�ɂ������A���Ȃ��͂����̂��Ȃ��ł�����ł��B �p�P�O�Q�@�T���_�������͔�펯�H �`�E���w���ł͗]�茩�܂��A�������̐搶�̒��ɍZ���ŃT���_�������̐搶���������邱�Ƃ�����܂��B���ʎx���w�Z�ł́A�q�ǂ��B���ǂ��������s�����Ƃ邩�킩��Ȃ����Ƃ������̂ŁA�搶���͍Z���𑖂�Ȃ���Ȃ�Ȃ���ʂ�}�Ɏp����ς����ʂ������邱�Ƃ�����܂��B �@�T���_�������ł́A������������ʂɑΉ��o���Ȃ��ł��傤���A�̈�̎w����s�R�҂̑Ή��E�n�k�̎��̑Ή��Ȃǂł͂ǂ�����̂ł��傤�B�T���_�����������Ă���̂́A�Ⴂ�搶���ł͂Ȃ��x�e�����ƌ�����l�������̂ł����A�Ⴂ�搶���͊Ԉ�������Ƃ�^���Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B�H������œ����l�����S�C�𗚂��Ă���悤�ɁA���̏ꂻ�̏�ɂӂ��킵���i�D������܂�����B�T���_�������́A���ʎx���w�Z�ɂ͂ӂ��킵������܂���B�����A����Ȑ搶�͂��Ȃ��ł��傤���E�E�B �p�P�O�R�@���H�̌W�������l����H �`�E���H�̌W�������l���鎞�ɁA�z�V�͂ǂ����Ă��܂����H�@���S���̉^���́H�@�N���X�̎q�ǂ��̎��Ԃ��l���ČW������U���Ă���̂ł��傤�ˁB�����A�l���Ȃ�������Ȃ��̂́A���̑Ή����ł��Ȃ��q�ɂ͔z�V��C�����Ȃ��Ƃ��A�ǂ��֍s���Ă��܂����킩��Ȃ��q�ɂ̓��S���̉^���͔C�����Ȃ��Ƃ����̂́A�w�K�̃`�����X���̂ĂĂ���悤�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B �@���H�̌W�����́A�����J��Ԃ��s������̂ł�����A�����e��g�ɂ��₷�����̂ł��B���̑Ή����ł��Ȃ��q�ɂ́A�����݂�Ȃ̊��Ƀp���⋍���₨�����Ȃǂ��ЂƂ��z��ǂ����ɂȂ�܂��B���S���̉^���́A���͂̏����ĂԂ��Ȃ��悤�ɒ��J�ɉ^�Ȃ���Ȃ�܂���B �@���߂͐搶���ꏏ�ɂ��čs���A���X�ɏ������ꂽ�ʒu�Ō����悤�ɂ��Ă����A�Ō�ɂ͂��̎q�ɔC���邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�ł��傤�B�����Ƌ����܂ʼn^�Ȃ���A�݂�Ȃ���D���ȋ��H��H�ׂ��Ȃ��킯�ł�����A�^���ɂȂ�܂���B �@�W�����͂ł���q�ɔC����̂ł͂Ȃ��A�ł��Ȃ��q�ɂ����C���邢���`�����X�Ȃ̂ł��B �p�P�O�S�@�g�C���w���͏��w���Őg�ɂ���H �`�E���w���⍂�����ɂȂ��Ă��A�j�q�g�C���ŃY�{����W���[�W�������Ă��K���o���Ĕr�A�����Ă���q�ǂ��B�����܂��B�e�w���ł��g�C���w���͍s���܂����A�g�C���w���͏��w���̒i�K�ł�������g�ɂ��邱�Ƃ��厖�ɂȂ�܂��B���ɏ���ł�������s���Ă����Ȃ��ƁA��̊w�N�ɏオ��قǎw��������Â炭�Ȃ邩��ł��B �@����̒i�K�ł�����A�j�̎q�̃g�C���w���ɂ������̋���������ł��傤����A���w�������w���Ɏ肪���₷���Ȃ�܂��B���w���̒j���������͏��Ȃ��ł��傤����A�j�̐搶����Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��̂ł��B�j�̐搶�����Ȃ��̂ɁA�����͒j�q�̕��������Ƃ����p�^�[���͂悭���邱�Ƃł��B���w���ɏオ��̂ɂ��K���o���Ĕr�A���Ă���q�ǂ�������ƁA�u���w���ł�������g�ɂ��Ă��Ă����Ȃ��B�v�ƒ��w���⍂�����̐搶���Ɏv���܂���B �p�P�O�T�@���ʎx���w�Z�̏펯�́A��ʎЉ�̔�펯�H �`�E�C�w���s�≓���ɍs���Ɓu�����������I�v�Ƃ�����ʂɏo����Ƃ�����܂��B�p�[�L���O�G���A�̃g�C����������̃g�C���ŁA���w���⍂�����̑̂̑傫�Ȑ��k�B���A�Y�{����W���[�W�����܂ʼn����Ă��܂����K���ۏo���̏�ԂŔr�A�����Ă���p����ʂ̕����s�v�c�Ȋ�����Ă��[���ƌ��Ă��鎞�ł��B �@�܂��A�ړ��̍ۂɑ傫�Ȏq�ǂ��B���S������Ȃ��ŕ����Ă���l�q�Ɉ�ʂ̕��X���u�����A�Ȃ�ŁH�v�Ƃ����\���������Ƃ��B�w�Z���ł͌����ꂽ���i�ł����Ă��A�Љ�ł͈�a���������i�ɂȂ�܂��B�����ꂽ�Ƃ������ƂɋC��t���Ȃ���A�w�Z���̏펯�͈�ʎЉ�ł̔�펯�ɂȂ��Ă��܂��ł��傤�B�q�ǂ��B�͑��Ƃ��Ă���̐l���̕���ꡂ��ɒ����̂ł�����E�E�B �p�P�O�U�@�����q�̐V�����S�C�ɂ͋C���g���H �`�E�����������������q�ǂ������̂��Ƃ͋C�ɂȂ���̂ł��B�V�������̎q�̒S�C�ɂȂ����搶�ɂ́A���̎q�̎w���̃|�C���g����Ԃ�ۑ�ȂǓ`���������Ƃ���������ł��傤�B �@�ł��A������Ƒ҂��Ă��������B�V�����S�C����̎��_���l���܂��傤�B���߂Đڂ��邻�̎q�̂��Ƃ�m�肽���Ǝv���A���S�C�ɐ��������Ă���悤�ȐV�����S�C�ł���A�ǂ��W�ł��̎q�ׂ̈ɂȂ���������ł���ł��傤���A���S�C�ł��邠�Ȃ����A�u�����͒N�������̎q�̂��Ƃ�m���Ă���E���̎q�����킢�����Ă����͎̂������E�E�v�ȂǂƃA�s�[������悤�Ȑ^���������Ȃ�A�V�����S�C�ɂƂ��Ă͍��������݂ł�������܂���B���������搶���Č��\���܂���ˁB�����������搶�ɂȂ�Ȃ��悤�ɂ��܂��傤�B �@�V�����S�C�̗͗ʂ��S�z�ł��A�u�����킩��Ȃ����Ƃ��������畷���Ă��������B�v�Ɛ�����������x�ɂ��܂��傤�B�V�����S�C�����S�C���A�q�ǂ��ׂ̈ɂƂ����v���ł��Ȃ��Ƃ��̎q�̂��߂ɂ͂Ȃ�܂���B �p�P�O�V�@�����o�@��ɋ����Ȃ�H �@�m��Ȃ�����g���Ȃ��łܑ͖̂Ȃ��ł���B�킩��l�ɕ���������Ǝv���Ă�����A���܂ł����Ă��u�킩��E�g����v�搶�ɂ͂Ȃ�܂���B �p�P�O�W�@�}�H�E���p�́A�����_�[�����h�H  �`�E�}�H�E���p�ł́A�G��`���Ƃ��ɉ�p�����g���܂��B�ł��A�q�ǂ��B����������Ώ������قǁA�G��͗l�ȂǍD���ɕ`���ꍇ�͉�p���ł͏��������܂��B�����Ǝ��R�ɑ�_�ɕ`��������������A�͑����ȂǑ傫�������g���܂��傤�B�ꍇ�ɂ���ẮA�L�����V�������������\�荇�킹�����̂ł������̂ł��B �`�E�}�H�E���p�ł́A�G��`���Ƃ��ɉ�p�����g���܂��B�ł��A�q�ǂ��B����������Ώ������قǁA�G��͗l�ȂǍD���ɕ`���ꍇ�͉�p���ł͏��������܂��B�����Ǝ��R�ɑ�_�ɕ`��������������A�͑����ȂǑ傫�������g���܂��傤�B�ꍇ�ɂ���ẮA�L�����V�������������\�荇�킹�����̂ł������̂ł��B�@�����g���Ă���i���͂ł���ł��傤�B���������Ȃ��ǂ��܂ł��L����̂��A�}�H�E���p�������_�[�����h����䂦��ł��B�q�ǂ��B���ڂ��p�`�N������悤�ȃ`�������W������Ă݂܂��傤�B�D���ɂ�����Ďq�ǂ��B�ɂ͖��͓I�ł��B �p�P�O�X�@�w������̂͊ȒP������ǁE�E�E�B �`�E�搶�����A�q�ǂ��B�Ɂu�O���狳���ɓ�������A���Ȃ����B�����������Ȃ����B�v�E�u�g�C���ɍs��������Ȃ����B�v�E�u�H���ɍs���Ƃ��̓}�X�N�����Ȃ����B�v���X�A�w�����邱�Ƃ͂�������ł��傤�B�F�X�Ȃ��ƂɋC�Â��Ďq�ǂ��B�ɂĂ��ς��Ǝw�����Ă���搶�����܂����A�悭�l���Ȃ��Ƃ��̂܂܂ł͒P�Ɍ����邳���搶�ł�������܂���B �@��������w�����Ă�����肩������܂��A�q�ǂ��B�̎��ɂ͓����Ă����܂���B�w��������e���q�ǂ��B�ɐg�ɂ��ė~�����̂Ȃ�A�w������O�ɐ搶���g���q�ǂ��B�̂������ōs���Ŏ����Ȃ���Ȃ�܂���B�܂��搶���s���A�u�����������낤�ˁB�v�Ɛ��|�����Ȃ�����߂ł��傤�B�w������̂ł͂Ȃ��A�ǂ��^�C�~���O�Ő��|�����邱�Ƃ��厖�Ȃ̂ł��B �@�w�����肵�ăC���C�����Ă��܂��H�w������̂͊ȒP�ł��B�ł��A����ł͎q�ǂ��B�͎g�ł����l���s�����܂���B�������̂Ȃ����ł��g�̎q����Ă����Ȃ�ʂł����B������Ɨ����~�܂��Ďw������Ƃ������Ƃɂ��čl���܂��傤�B �p�P�P�O�@���̐搶�͓����Ă���H �`�E�u���̐搶�͓����Ă���v�ȂǂƂ����A�u��k�ł��傤�I�v�Ǝ���ꂻ���ł����A�u���B�v�̊w�K�ł͏����Ȃ��q�������ĂĂ���}�}����搶�́A�{�̓��e������Ȃ蓪�ɓ����Ă����܂��B�����̎q��Ă̌o���Ɩ{�ɏ�����Ă��锭�B�̋ؓ����҂���ƍ����āA�u�������������Ȃ̂�B�v�Ɣ[���o����͂��ł��B�j�̐搶�ł́A������Ďq��Ă���`���Ă��Ă��Ȃ��Ȃ������͂����܂���B��J���Ďq��Ă��Ă��邩�炱���A�킩�邱�Ƃ���������̂ł��B�c���̕a�C�Ɋւ��Ă��A�j�̐搶����ꡂ��ɏڂ����Ȃ��Ă����܂��B �@�܂��A�G�{�̓ǂݕ��������j�̐搶�����Ȃ̂͏��̐搶�ł��B���͑��q�B���c�����A�����R�O���`�P���Ԃ͕K���G�{�̓ǂݕ����������Ă��܂������A���̐搶�ɂ͂��Ȃ�Ȃ��Ȃ��Ɗ����܂����B�q�ǂ��B�ɂƂ��ď��̐搶�́A�w�Z�ł̂��ꂳ��̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂�������܂���B�Ⴂ�搶�́A���o��������܂��E�E�B �@�j�̐搶���t�������Ă������Ȃ��悤�Ȃ��̂������Ă��鏗�̐搶������ƁA�S��A�܂����B��J�������A�d���ɂ������邱�Ƃ���������l�����Ă���̂����̐搶�ł��B�j�̐搶���q��Ă���������撣��Ȃ��ƁA���܂ł����Ă����̐搶���ɂ͂��Ȃ�Ȃ��ł��傤�ˁB �p�P�P�P�@�J�b�^�[�i�C�t�͑傫�������ǂ��́H 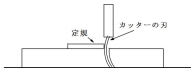 �`�E�J�b�^�[�i�C�t�́A���ނ̐���ł悭�g������ł��B�_�C�\�[�ɍs���Ηl�X�ȃJ�b�^�[�i�C�t�������Ă��܂��B�����_�C�\�[�Ŕ������i�C�t�𐔖{�����Ă��Ďg���Ă��܂����A�J���[�{�[�h���J�b�g����ۂɂ̓I���t�@�̑傫���J�b�^�[�i�C�t���g���悤�ɂ��Ă��܂��B �`�E�J�b�^�[�i�C�t�́A���ނ̐���ł悭�g������ł��B�_�C�\�[�ɍs���Ηl�X�ȃJ�b�^�[�i�C�t�������Ă��܂��B�����_�C�\�[�Ŕ������i�C�t�𐔖{�����Ă��Ďg���Ă��܂����A�J���[�{�[�h���J�b�g����ۂɂ̓I���t�@�̑傫���J�b�^�[�i�C�t���g���悤�ɂ��Ă��܂��B�@�傫���J�b�^�[�i�C�t�́A�n���d�����Ȃ肪���Ȃ����琂���ɃJ���[�{�[�h���J�b�g���邱�Ƃ��ł��܂����A�������J�b�^�[�i�C�t�͐n���_�炩�����Ȃ肪�傫���̂ŁA�E�̐}�̂悤�ɒ�K�����ĂăJ�b�^�[�i�C�t���g���Ă��A�J���[�{�[�h�̃J�b�g�����f�ʂ������ɂȂ�Ȃ��̂ł��B �@�p�Y���Ȃǂ���鎞�ɐ����f�ʂ��J�[�u���Ă��ẮA�͂ߍ������Ƃ����G�������Ǝ��܂�Ȃ��Ȃ�܂��B���i�g���͂P�O�O�~�V���b�v�̃J�b�^�[�i�C�t�łn�j�ł����A���ނ̐���ł̓I���t�@�̑傫���J�b�^�[�i�C�t���g�����������߂ł��B �p�P�P�Q�@�����݂��Ȃ��Ǝv����Ɛ��������Ă��炦�Ȃ��Ȃ�́H �`�E�Ⴂ�搶�����y�̐搶���͌��Ă��܂��B�q�ǂ��ւ̐ڂ�����d���ɑ���^�ʖڂ���i�ȂǁB�����Ă��邱�Ƃ���ʈӎ�����K�v�͂���܂��A���������Ȏd�������Ă���A�\�ʏ�͕t�������Ă���Ă��u���̐l�̓_�����ˁB�v�Ǝv���܂��B���܂��ł��Ȃ��Ă��Ȃ�Ƃ��撣�낤�Ƃ��Ă���Ⴂ�搶�ɂ́A��������̐�y�������Ă���܂����A�撣���Ă���Ȃ��Ƃ�����ۂ������Ă���܂��B �@�����ł��Ȃ��Ă��A���ɂł���悤�ɂȂ�����̂ł��B�撣���Ă��邾���ł͐i�����Ȃ��ƌ����Ă��܂����Ƃ����邩������܂��A�킩��Ȃ����Ƃ͔Y��ł��Ȃ��ł�����y�B���畷���Ηǂ��̂ł��B�������Ă���ƃA�h�o�C�X���Ă���邱�Ƃ������Ă����ł��傤�B���C���Ȃ��Ǝv����A���������Ă���Ȃ��Ȃ�܂��B���̍��A�Ȃ���y�B���悻�悻�����Ǝv�����Ȃ�A����͂��Ȃ��Ɍ��������邩�炩������܂����B �p�P�P�R�@��b�w�K�ł́A�����灛���������Ȃ��悤�ɂ���H   �`�E��b�w�K�ł́A�u�ʓ���v��u�R�C������v��u�����O�����v�E�u�^�͂߁v���̋��ނ��g����ʂ�����܂��B���̏���g���Ă�銈���ł�����A�q�ǂ��B���ʁi�r�[�ʂ�̋ʂ�X�[�p�[�{�[�����j��R�C���i������ۂ����j���𗎂Ƃ����Ƃ�����܂��B�ʓ������̏ォ�痎�Ƃ��ƁA�搶��������E��Ȃ���Ȃ�܂���B���̓s�x���������f���Ă��܂��悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B �`�E��b�w�K�ł́A�u�ʓ���v��u�R�C������v��u�����O�����v�E�u�^�͂߁v���̋��ނ��g����ʂ�����܂��B���̏���g���Ă�銈���ł�����A�q�ǂ��B���ʁi�r�[�ʂ�̋ʂ�X�[�p�[�{�[�����j��R�C���i������ۂ����j���𗎂Ƃ����Ƃ�����܂��B�ʓ������̏ォ�痎�Ƃ��ƁA�搶��������E��Ȃ���Ȃ�܂���B���̓s�x���������f���Ă��܂��悤�ɂȂ��Ă��܂��܂��B�@���͑傫�Ȃ��~�i�_�C�\�[���Ŕ����Ă���傫�ȃg���[�j���g���悤�ɂ��܂����B�g���[�ɂ̓J���[�{�[�h��~���āA���������̂����˕Ԃ�Ȃ��悤�ɁE�{�[�h�̖͗l�ɋC���s���Ȃ��悤�ɂ��Ďg���܂����B�q�ǂ��B���ʓ��𗎂Ƃ��Ă����̏ォ��]���藎���Ȃ��̂ŁA���������f����邱�Ƃ͂���܂���B���̎��͂Ɍ���p�����ŕǂ�\���Ă��ǂ���������܂���B�����ɏW���o����悤�ɂ��Ă����Ƃ����ł���B �p�P�P�S�@�ԃC�X�́A����ȏ��ł��u���[�L��������́H �`�E�搶���́A�ʉ������Ƃ����X���[�v�Ȃǂ̎Ζʂł́A�ԃC�X�ɕK���u���[�L�������邱�Ƃł��傤�B�ł́A����ȏ��ł͂ǂ��ł��傤�B���͎��̕s���R�̊w�Z�ɂ����Ƃ��ɁA���N�̂悤�ɎԃC�X�̎��̕��E����c�ŕ����܂����B���̂��N�������R�́A�w�ǂ��搶���̂�����Ƃ������f��~�X�ł����B���̎q�̓����ɋC���Ƃ��āA�ԃC�X�Ƀu���[�L��������O�Ɏ�𗣂��Ă��܂�����A���₩�ȍ�ɋC�������Ɏ���n���h�����痣���Ă��܂����肵�Ă����������̂ł��B �@�l�Ԃł�����~�X�͕K���ƌ����Ă����قǂ������ł��傤�B�ł��A�������Ă͂����Ȃ��~�X���Ă����ł��B���i����A����ȏ��ł������~�܂�����K���ԃC�X�̃u���[�L��������悤�ɂ���A�̂��o���Ă���܂��B������Ƃ����~�X���Ȃ��Ȃ�킯�ł��B�q�ǂ��B���P�K���������Ȃ��E�|���v�������������Ȃ��̂Ȃ�A�ʓ|���ȂƎv�킸�u���[�L�������邱�Ƃ��K�������邱�Ƃł��B�l�̃~�X��Ί݂̉Ύ��ȂǂƎv��ʂ��Ƃł��ˁB�u���̎��A�u���[�L�������Ă����Ηǂ������B�v�E�E�ƁA������Ȃ����߂ɁB �p�P�P�T�@�ɂ݂͓`���Ȃ����Ăǂ��������ƁH �`�E�q�ǂ��B�̒��ɂ́A�ˑR�搶�����˂��Ă���q�����܂��B���킢�����Ă���̂ɁA�ǂ����ĂƂ�����Ɣ߂����Ȃ�܂��ˁB�˂闝�R�͕K������܂����A�˂�����Ƃ��Ă͂��܂������̂ł͂���܂���B�搶���̒��ɂ́A�˂�����Ă���Ȃɂ��ɂ���Ƃ˂�Ԃ��āA�u�킩�����H�v�Ɖ�����l�����܂����A����͈Ӗ��������܂���B�Ӗ����Ȃ��ǂ��납�A�˂�Ԃ����搶���q�ǂ��B�͌����ɂȂ邾���ł��B�������Ă�����A�������Ȃ��Ƃ��v����������A�C���������Ƃ�����A�킪�܂܂�������Ɨ��R�͐F�X�Ƃ���ɂ���A�˂�Ԃ��Ă��u�ɂ݂͓`���Ȃ��v�̂ł��B �@�ɂ��Ƃ��ɂ́A�u�Ɂ[���v�Ɣ������邱�ƂƂ��炭��������Ȃ����Ƃł��̎q�Ƃ̋������Ƃ�܂��B�D���Ȑ搶����������Ă���Ȃ����Ƃ��A�˂��Ă���q�ɂ͈�Ԃ炢���Ƃł��B�˂����瑊������Ă��炦�Ȃ��Ƃ������Ƃ��q�ǂ��B���w�K����܂ő҂ׂ��ł��傤�B����ł��A�˂�����Ēɂ��������͂ł��邵�Ƃ���ǂ��ł�����ǁE�E�B �p�P�P�U�@�Ƒ��̏Ί�E�E�B �`�E�ی�҂͐F�X�Ȃ��ƂŔY��ł��܂��B�q�ǂ��̂��Ƃ�b���ƐS�z�����R�̂悤�ɂ���̂��킩��܂��B����ȂƂ��u�Ƒ����Ί炢��Α��v�ł���B�v�Ƙb���܂��B�q�ǂ��B�͎��̗͂l�q�ɑ��ĂƂĂ��q���ɔ������܂��B��������Ƃ��ꂳ���܂�������A���ꂳ�C���C�����Ă�����A�\��Â������肷��Ǝq�ǂ��B���s���ɂȂ�܂��B�F�X�S�z�Ȃ��Ƃ������Ă��Ƒ��̏Ί炪���ɂ���A�q�ǂ��B�͊Ԉ���������ɂ͍s���܂���B���݂͂������ł����Ă����������Ɛ^�������Ɉ���Ă����ł��傤�B �@�S�C���痣��Đ��N�o���Ă��A���ꂳ�������u�搶�A���̎��̂��Ƃ͖Y����܂���B�v�ƁA������ۂɂ͍��ł������܂��B�Ƒ��̏Ί�Ɛ搶���̏Ί炪�A�q�ǂ��B���Ί�ɂ���͂ɂȂ�܂��B �p�P�P�V�@���C��̎Q����p�������B�Q�����悤���ǂ����悤���H �`�E�s���ōs����l�X�Ȍ��C��̒��ɂ́A���Z�̂��߂̍ޗ��㍞�݂Ƃ͌����Q����Q���~�ȏ�Ƃ����悤�Ȃ��̂�����܂��B���̌��C��ɎQ�������搶���炱������Ƃ��ɁA�u���ׂ����E�E�v�ƕ����������Ȃ�܂��B�����u�t�ւ̎ӗ�ȂǂŎ�Îґ����傫�ȕ��S�������Ƃ��Ă��A�q�ǂ��B�֗ǂ��Z�p���L�߂悤�Ƃ������Ƃ��ɂ��Ă���̂��A���C��Ŗׂ��悤�Ƃ��Ă���̂��ǂ����Ȃ�ł��傤�B�������C��̓��e���Ƃ��Ă��A���̎Q����ɔ[���������Ȃ��Ƃ�����A�Q���͂��߂炤�ł��傤�ˁB �@�Q�����������ƌ����ē��e���ǂ��킯�ł͂���܂���B�Ȃ�ł��ׂ��ɂ��悤�Ƃ���c�̂�u�t�̐搶�Ɏ��݂��K�v�͂���܂���B����Ɋւ��錤�C��ɂ����Ďu�̒Ⴂ�Ƃ���ɐl���W�܂�A���ׂ��������l�B�̎v���ڂł��B����͋��ɂȂ�ƁE�E�ˁB �p�P�P�W�@�R�~���j�P�[�V�����J�[�h����������A�q�ǂ����g���Ă���Ȃ��B�g�킹��R�c�́H  �`�E���߂ăR�~���j�P�[�V�����J�[�h����鎞�́A���̎q���D���Ȃ��́i�������ᓙ�j�⋻�������镨�i�|���@�⋳���̂��Ă��郁�K�l���j���ꗗ�ɂ����J�[�h�����Ɨǂ��ł��傤�B���߂���F�X�Ƌl�ߍ��ނ͎̂g���Â炭�Ȃ邾���ł��B�܊p������R�~���j�P�[�V�����J�[�h���q�ǂ����g���Ă���Ȃ����R�́A�������炻�̂�������Ȃǂ����ɍs���邱�Ƃ������̂ЂƂł��B�����Ŏ��ɍs����̂ł���A�l�ɗ��ށE�u���ꂪ�ق����v�Ɠ`����K�v���Ȃ�����ł��B �`�E���߂ăR�~���j�P�[�V�����J�[�h����鎞�́A���̎q���D���Ȃ��́i�������ᓙ�j�⋻�������镨�i�|���@�⋳���̂��Ă��郁�K�l���j���ꗗ�ɂ����J�[�h�����Ɨǂ��ł��傤�B���߂���F�X�Ƌl�ߍ��ނ͎̂g���Â炭�Ȃ邾���ł��B�܊p������R�~���j�P�[�V�����J�[�h���q�ǂ����g���Ă���Ȃ����R�́A�������炻�̂�������Ȃǂ����ɍs���邱�Ƃ������̂ЂƂł��B�����Ŏ��ɍs����̂ł���A�l�ɗ��ށE�u���ꂪ�ق����v�Ɠ`����K�v���Ȃ�����ł��B�@�����ł����V��ł�������������B���Ă��܂��܂��B��������Ǝ����ŒT���Ă�������Ȃ��ƁA�u�搶�������ق����B�v�ƃJ�[�h�̒��ɂ��邨�����ᓙ�̎ʐ^���w��������悤�ɂȂ�܂��B�R�~���j�P�[�V�����J�[�h���g�킴������Ȃ������킯�ł��B �@���̌`���ł���ƃR�~���j�P�[�V�����J�[�h���g���A�����̎v�������҂ɓ`���Ƃ������Ƃ��w�Ԃ킯�ł��B���̎q�̋�����������́E�D���Ȃ��̂ɗF�B��搶�̃J�[�h��s�������ꏊ�̃J�[�h�E����̃J�[�h������̂́A�R�~���j�P�[�V�����J�[�h���g�����Ƃ�����I�ȍs�ׂɂȂ�悤�ɂȂ��Ă���ł��B�ł炸������������Ă����Ƃ����ł���B �p�P�P�X�@���ނ̑傫�����l���Ă���H �`�E���ނ̑傫���Ƃ����Ɓu���H�v�Ǝv���邱�Ƃł��傤�B�����Ō������ނƂ́A���̏�Ŏg���悤�ȃJ�[�h��u���ԕ����v�E�u�ʓ���v�E�u�^�M���K�v���̊�b�w�K�Ŏg�����ނ̂��Ƃ������܂��B �@�Ⴊ�����d�����q����̏ꍇ�́A�J�[�h�͑傫�������łȂ����݂��l���Ȃ�������܂���B�Ⴊ�����y�����q����̏ꍇ�́A���������Ȃ�����͑傫�������݂�����ȂɋC���g���K�v�͂���܂��A�Ⴊ���̏d�����q����̏ꍇ�͎�w�̑��삪���n�Ȏq�������̂ŁA�傫�߂̃J�[�h����݂�����J�[�h�̕����g���₷���ł��傤�B �@�܂��A���ԏW�߂Ȃǂł́A���q����̌������ӎ������傫���̃{�[�h�������ł��傤�B������������ɋ��ޥ��������ȏ�̑傫��������ƁA���삪����Ȃ邩��ł��B���̎q�ɍ������傫��������킯�ł��B �p�P�Q�O�@���ނɂ́A�ǂ�ȐF��h��Ηǂ��H �@�c�������̎G���Ȃǂ́A�悭����Ƃ����������N�₩�ȐF���g���Ă�����̂������ł��傤�B�Ⴊ�������قǏd���Ȃ����q����B���g�����ޥ����Ɋւ��ẮA���ꂢ�ł���ΒW�F�����g���Ă��n�j�ł��B ���F�̂R���F�i�G�̋�̐F�̎O���F�́A���Ă͐ԁE�E���Ƃ����܂������A���ł̓V�A���u�݂̐v�A�}�[���^�u�Ԏ��v�A�C�G���[�u���v�ƌ����Ă��܂��B�j �p�P�Q�P�@�������⋋�H���̐E���ƒ��ǂ��Ȃ�H �`�E���i�]��ւ�邱�Ƃ��Ȃ��������⋋�H���̐E���̕��X�ƒ��ǂ����Ă��܂����H�@���ǂ����Ă���ƌ������������l�ԊW��z���Ă��܂����H�@�Ⴂ�搶���ɂ́A�ǂ����������ƕ~�����������������邩������܂���ˁB������������A�q�ǂ��B�̋���Ƃ͊W�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��H �@�搶���͓������ǂ������l�����Ă���ł��傤�B�����搶����������łȂ��搶�����܂���ˁB�ǂ��搶�ɂ͌h�ӂ��܂����A�����łȂ��l�ɂ͂ł��邾���ւ��Ȃ��悤�ɂ���ł��傤�B �@�������⋋�H���̐E���̕��X�ɁA�������q�ǂ��B�����������b�ɂȂ��Ă���Ƃ����ӎ�������A���ӂ���C���������܂ꂢ���l�ԊW���z���܂��B�������⋋�H���̕��X���A�����̗ǂ��搶�ɂ͐e�g�ɂȂ��đΉ����Ă���܂����A�����̈����搶�ɂ͑f���C�Ȃ��Ή��������Ă���܂���B�x�e�����̐搶������ǂ��Ή������Ă����̂ł͂���܂���B���͋��H���Ɏq�ǂ��B�ƃ��S����Ԃ��ɍs���Ƃ��́A�K�����H�̕��Ɂu�����́����́A�q�ǂ��B���悭�H�ׂĂ��܂�����B�v�ȂǕ��Ă��܂����B���X�A�������̍����Ȃǂ������Ă�����Ă��܂������A�x�e���ԂȂǂɊ�����킹��Ƃ悭�b�������Ă��܂����B �@�w�Z�́A�搶�����ō���Ă���킯�ł͂���܂���B�������̐l�B�⋋�H���̐l�B��|���̐l�B��搶���ȂǁA�݂�Ȃ̗͂Ő��藧���Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B�搶�����̂��킯�ł͂Ȃ��A���̈���ł����Ȃ����Ƃ��ӎ����܂��傤�B �p�P�Q�Q�@���[�h���[�J�[��厖�ɂ��Ă���H �`�E�搶���̒��ɂ́A�d�������ʂł���킯�ł͂Ȃ�����ǁA�ƂĂ��d�v�Ȑ搶�����܂��B����͖��邢���͋C�������o���Ă���郀�[�h���[�J�[�̐搶�ł��B�����ǂ��搶�����W�܂��Ă��Ă��A�ӌ����Ԃ��荇���Ă�����ƋC�܂����Ȃ邱�Ƃ��Ă���ł��傤�B�����������Ƃ��ɖ��邢�搶�̑��݂ɏ������邱�Ƃ��Č��\����܂���ˁB �@�N���X�̎q�ǂ��B�ɂ����������������Ƃ������邩������܂���B�����q�ҁi�H�j���Ȃ��Ǝv����悤�Ȏq���A�����Ă���q�ɂƂĂ��D����������A���܂��Ă���F�B�̒��قɓ����Ă��ꂽ��E�E�B�搶�̌������Ƃ�f���ɕ����q�������ǂ��q�Ȃ̂ł͂Ȃ��A������Ƃ����q�҂ŕ��i�������Ƃ��Ȃ��悤�Ȏq�̒��ɂ��A�N���X�ɂƂ��đ�Ȏq�������ł��B �p�P�Q�R�@���Ɛ��ɕ����B�u�����v���Ăǂ�Ȃ��ƁH �`�E�������ł͌�����K�������Ȃ��A�S�C�����K��Ɏw���ɏo�|���܂��B���K��̉�Ђ̐l���Ə��̕��X����A�q�ǂ��B�̂��Ƃ�F�X�f���̂ł����A���Ƃ��ďA�E�������Ə��ɓ���ƃA�t�^�[�P�A�ʼn��K�₷�邱�Ƃ��炢�����ł��Ȃ��Ȃ�܂��B�������̐搶�����킩��̂͌�����K�̏�w�ǂŁA�A�E�������Ə��ɓ����Ă���̐����ɂ��ė]��킩��܂���B �@�����������ɂ������́A�i�H���̐搶������悵�ĔN�ɐ��Ɛ��ɗ��Ă��炢�A�u�d���̂��Ɓv�E�u�x�݂̓��̂��Ɓv�E�u��������������Ăǂ����Ă��邩�v�Ȃǂ��ݍZ���ɘb���Ă�����Ă��܂����B�搶�����������������A���Ɛ��̌��d���̂��ƁE�����̗l�q�ȂǍ������̐��k�B�͐^���ɕ����Ă��܂����B��Ə��̕��E��Ђ̕��ɗ��Ă��炤���Ƃ�����܂����A�������̐��k�B�Ƀ��A���ɏ�͂��̂́A���Ɛ��̂��Ƃł��B�u�����q�B�ɋ����v�̂��āA�Ȃ����ł��ˁB���[����Ȃɂ����������ƁA���炽�߂Ċ������Ȃ�܂��B �p�P�Q�S�@�����w�K�́A�y��������ǂ�����ƕ|���H  �`�E�����w�K�i�������K�j�ŕ|���̂́A�w�E�����E��ނ���i�s�[���[�j�E�����x�Ȃǂł��B������́A�q�ǂ��B���|�����ĐT�d�ɂȂ�̂ňӊO�Ƒ��v�Ȃ̂ł����A�|���ȂƎv���̂́u�����v�Ɓu��ނ��̃s�[���[�v�ł��B �`�E�����w�K�i�������K�j�ŕ|���̂́A�w�E�����E��ނ���i�s�[���[�j�E�����x�Ȃǂł��B������́A�q�ǂ��B���|�����ĐT�d�ɂȂ�̂ňӊO�Ƒ��v�Ȃ̂ł����A�|���ȂƎv���̂́u�����v�Ɓu��ނ��̃s�[���[�v�ł��B�@�q�ǂ��B�̓s�[���[���g�����Ƃ��]��Ȃ��̂��A�W���K�C����j���W���Ȃǂ������Ă����w�̂ق��Ɍ������Ď�O���ɍ���Ă������Ƃ������̂ŁA���w���Ȃ����ƐS�z�ɂȂ�܂��B�����������S�z����������̂��A�܂ȔɓˋN�����Ă���u��ނ������₷���܂Ȕv�ł��B���ꂪ����ΓˋN�̕����ɖ���������ĂČŒ�ł���̂ŁA��Ɏ����K�v������܂���B����̂��q����B�ł����S�E���S�ł��B �@�����̓����Ă����̂ق��́A�߂Â��Ȃ����Ƃ�O�ꂳ���邵���Ȃ��悤�ł��B����Ӗ������|���ł�����E�E�B���w���̒����ł́A���������Ȃ����q�������N���X��w�N�ł́A�d�q�����W���g���ĉ₨�����g��Ȃ��ōςޒ����������Ȃ��̂�������������܂���ˁB �p�P�Q�T�@�������̊w�K�́A�˂炢����������l���Ȃ��ƈӖ����Ȃ��H �`�E�������̊w�K�́A���w���ƒ��w���Ƃł͊w�K�̂˂炢������Ă���ł��傤�B�����ōs���������̊w�K�ƃX�[�p�[��P�O�O�~�V���b�v��R���r�j�⒬�̏��X�ōs���������̊w�K������Ă���ł��傤�B �@���w���ł́A�u������������I�ԁE�������Ăɏ��i������E���W�ł������v�Ƃ�����A�̗����̌�����̂���ȖړI�ɂȂ�܂��B�I���i�����W�ł�����Ȃ��܂܃|�P�b�g�ɓ���Ȃ��E�u���肢���܂��B�v�ƌ����E���W�Ń��V�[�g�����炤�Ƃ��������Ƃ��˂炢�ɂȂ�ł��傤�B�����ł̊w�K�̌�ɁA���ۂɃ_�C�\�[���̂P�O�O�~�V���b�v�ɏo�|���Ĕ�������̌�����ꍇ�́A�\�ߍ��z�ɂP�P�O�~��������Ď����Ă����A���i���P�����I��ł������Ƃ����`���Ƃ邱�Ƃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �@ �@�R���r�j��X�[�p�[�ł́A���i�̉��i�����Ȃ̂ŁA���i���P�I��ł�������ɂȂ邩�킩��Ȃ��̂ŁA�������̗����̌�����ɂ͗ǂ����@��������܂���B�ł��A�w�Z�̋߂��ɂP�O�O�~�V���b�v���Ȃ��Ƃł��Ȃ����@�Ȃ̂ŁA�߂��ɃR���r�j��X�[�p�[�⏤�X�����Ȃ��ꍇ�́A�T�O�O�~�ʂ͎����Ă����Ȃ��Ɠ���ł��傤�ˁB���w���̒i�K�ł́A�������̂̈�A�̗�����o�����܂������A���w���ł͂ǂ��ł��傤�B  �@���w���ł́A�I�ԏ��i�̐��������܂��B�������̐�͂P�O�O�~�V���b�v�ł͂Ȃ��A�X�[�p�[�ӂ肪�����Ȃ�܂��B�����̏��i��I�ԏꍇ�́A�ƒ납�甃�������ė~�������̂̃��X�g�������Ă��Ă��炤�Ƃ����ł��傤�B���������]�葽������Ǝ��ԓI�ɓ���̂ŁA�R�`�S�_���炢��������������܂���B �@���w���ł́A�I�ԏ��i�̐��������܂��B�������̐�͂P�O�O�~�V���b�v�ł͂Ȃ��A�X�[�p�[�ӂ肪�����Ȃ�܂��B�����̏��i��I�ԏꍇ�́A�ƒ납�甃�������ė~�������̂̃��X�g�������Ă��Ă��炤�Ƃ����ł��傤�B���������]�葽������Ǝ��ԓI�ɓ���̂ŁA�R�`�S�_���炢��������������܂���B�@�����ōD���ɔ�����������I�Ԃ̂ł͂Ȃ��A���߂�ꂽ���i����������̏��i�̒�����T���Ĕ��������s���Ƃ������Ƃ��˂炢�̂ЂƂɂȂ�܂��B�w�K�Ƃ��Ă����ۂ̔������ɋ߂��V�`���G�[�V����������Ă����܂��B���W�Ŏx�������ł���q�ɂ́A��������Đ搶���͌��Ă��Ă�点��悤�ɂ��܂��B�����̌v�Z���ł��Ȃ��q�B�́A���߂�ꂽ���̂���������̏��i�̒�����I�ׂ������厖�ɂȂ�܂��B�I�ׂ��̂Ȃ�˂炢�͒B�������ƍl���܂��B���W�łP�O�O�O�~�D���o���Ă�������炦��Δ������w�K�͏I���ɂȂ�܂��B�������̊w�K�́A�e�w���i�e�w�N�j�ŔN��ɉ������u�˂炢�v��������������Ă����Ȃ��܂��傤�B �p�P�Q�U�@�w�����ʼnԂ���ĂĂ��q�ǂ��B�������������Ă���Ȃ��H �`�E�t��Ɋw�����̉Ԓd�Ɏq�ǂ��B�ƉԂ�A���܂����A���ǂ��B�͂�邱�Ƃ͂��̂ł����A�A���Ă���͑S���ƌ����Ă����قǖ��S�B�����炪�Ԃ̐�����b��ɂ��Ȃ����炩�ȂƎv���A�����̂悤�ɘb�����w�ǖ��S��Ԃ͕ς��܂���B�d�����Ȃ��̂ŁA�Ԃł͂Ȃ��W���K�C����T�c�}�C���Ȃ�S�������Ă���邩�ȂƎv���܂������A�S�������Ă��ꂽ�̂́A���n�̎��̌@��Ƃ��ƐH�ׂ�Ƃ������ł����B�܂��A����Ȃ��̂�������Ȃ��ȂƎv���܂������A�ǂ���炻���ł͂Ȃ������ł��B �@�������Ə��w���̎��̂��Ƃł����A�Ԓd�ʼnԈȊO�Ɏ}������Ă��Ƃ��Ƌ����ł������卪�E�~�j�g�}�g����Ă��Ƃ��́A�q�ǂ��B�͖����̂悤�ɂ悭���Ă��܂����B�ǂ����y�̒��ň���̂́A�H�ׂ�����̂ł������Ȃ����狻�����N���Ȃ��悤�ł��B �@�܂��A�Ԃ͂��ꂢ�ł����H�ׂ��Ȃ�����S�������Ȃ�悤�ł��B�����������ɖڂɌ����A�����H�ׂ邱�Ƃ��ł�����̂������悤�ł��ˁB�w����������Ԃƌ��߂��Ȃ��Ă������ł��傤���A�������ň�Ă�����̂͂����Ƃ����Ƃ������Ƃł��傤���E�E�B�������卪�́A�q�ǂ��B���H�ׂ��疡�����������悤�ŁA���̌�͌�����������܂���ł������E�E�B �p�P�Q�V�@�L�^���厖�Ȃ̂͂킩���Ă��邯��ǁA�Ȃ��Ȃ��������Ȃ��B �`�E�q�ǂ��B�����Z���ċ����̑|�����I��鍠�A�搶�����x�e���ԂɂȂ�܂��B�E���������Ă���Ƒ����̏��̐搶���͋L�^�������Ă��܂��B�j�̐搶�́A����ƈ�x�݂Ƃ��������ł��傤���E�E�B���̓��̎��Ƃ̔��Ȃ�q�ǂ��B�̗l�q�����L�^���邱�Ƃ͂ƂĂ��厖�Ȃ��Ƃł����A���ꂪ�Ȃ��Ȃ��������Ȃ��E�E�B�����o���ƂQ�O���ʂ͂������Ă��܂��̂ŁA�x�e�����Ȃ��Ƃ����C�����ɂ��Ȃ�܂��B �@�Z���ԂŋL�^���ł���悤�ɂ���ɂ́A���炩���ߋL�^�p��������Ă����A������������悤�ɂ��Ă����Ƒ����邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�܂��B���Ȗ��̉��Ɂu��������E�ӂ��E�����Ȃ������v�Ƃ������ɍ��ڂ����A�Y�����鏊�Ɂ������܂��B���ׂ̗ɋX�y�[�X������Ă����ɋL�^�������悤�ɂ���ƁA�������Ƃ��邱�Ƃ������ɕ�����ł��܂����A���S�Ɋ����Ȃ��ŋL�^����葱���邱�Ƃ��ł��܂��B���t�����Ȃ������ɏ������Ƃ���ƒ��X�����܂���B �p�P�Q�W�@�j������A��������E�E�H �`�E�������王���o�@��̑���͖����E�j�����璲�����K�͋������Ȃ��B�E�E����Ȃ��Ƃ������Ă���̂́A�ǂ��̂����������E���������ł��傤���H�@�j�����珗������Ƃ����܂��ɁA�搶�Ȃ�ł��傤�ƌ��������Ȃ��Ă��܂��܂��B �@�搶�Ƃ����d���͎q�ǂ��B��ɂ���d���ł�����A�l�ԗ͂�������Ă���悤�Ȏd���ł��B���ʎx���w�Z�ł����w�Z�⒆�w�Z����Z�ł����Ȃ����Ƃł��B�d���̕�������̂��厖�ł����A���i�̐����̒��ŕK�v�ȃX�L���i���������E�������E�ٖD�E�Ɠd�̒m�����j��g�ɂ��Ă��Ȃ���A����������Ă����l��|�������Ă���Ă���l�Ȃǂɂɑ��銴�ӂ̋C�������킩��Ȃ��ł��傤�B �@�Ⴂ�搶���́A�N�z�̐搶�������L���͂��z���͂��������ł��B�j�����ė�������邵�A�������Ď����o�@����n�j�ƁA�q�ǂ��B�ɂ��Ȃ��̐l�ԗ͂������Ă����܂��傤�B �p�P�Q�X�@���Ⴂ���Ă��Ȃ��H �`�E�ŋ߂́A���ʎx��������w�Ő��ɂ��ē��ʎx���w�Z�ɋ߂�搶�������Ă��܂����B���̂��Ǝ��̂͂ƂĂ��������Ƃ��Ǝv���܂����A���ɂ͊��Ⴂ���N�����Ă���Ⴂ�搶�����܂��B��w�œ��ʎx�����������Ă����̂ł�����A���w�Z�⒆�w�Z����Z�̖Ƌ��̐搶���͒m���������͓̂�����O�ł��B�N��̂��ƂȂ����搶���������̕����ゾ�Ɗ��Ⴂ���Ă���悤�Ȍ��������āA�搶������Ђキ���Ă��邱�ƂɋC�Â��Ȃ��l�����܂��B���������l�قǎ��͂������Ă���搶�ɂ��т�悤�ȑԓx�����Ă��܂��B�m�����������ƂƎw���͂����邱�ƂƂ͌��т��܂���B�m�����������Ă�����قnj���͊Â����E�ł͂���܂���B �@�{�l�͈ӎ����Ă��Ȃ���������܂��A���т�悤�ȎႢ�搶��͂̂���x�e�����͑���ɂ͂��܂���B�x�e�����͗l�X�Ȃ��Ƃ�̌��������Ă��Ă��܂�����A���̒��x�̒m���Ŏ����͈̂��Ɗ��Ⴂ���Ă���悤�Ȑl���u�������ȁv�Ƃ����v���Ă��܂���B�Ⴂ�搶�Œm����o�������Ȃ��Ă��A�q�ǂ��B��厖�ɂ���^�ʖڂȐ搶��]�����܂��B�����ɂȂ��Ă������҂ɂȂ�Ȃ��悤�Ɍ����ł��Ȃ��Ă͂ˁB �p�P�R�O�@���ނ́A����Ďg���ďI��肶��Ȃ��H �`�E����̋��ނ́A���������Ă��鎞���w�K�Ŏg���Ă���Ƃ����A�u���̋��ނł悩�����̂��낤���H�v�ƐS�z�E�s�������̒����悬��܂��B�w�K�Ŏg���Ă݂āA���̎q�ɍ��������̂ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��킩��Ƃق��Ƃ��܂���ˁB�����A���̎q�ɍ��������̂łȂ�������A�ʂ̂��̂ɕς��邩���g���Ă�����̖̂��_�����P�������̂ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B �@�������ނ��ł����Ƃ��Ă��A�u�����Ƃ������̂́H�v�ƍl���܂��傤�B����ł����Ǝv������A�u�����Ƃ������ށv�͐��܂�Ă��܂���B�Ⴂ�搶�́A���ꂩ��R�O�N���炢�͎d���������܂�����A�������莞�Ԃ������Ă������ނ�����Ă����Ă��������B �p�P�R�P�@�e�̗���ōl������Ăǂ��������ƁH �`�E�������ی�҂͂ǂ��ɂł����܂����A�w�ǂ̕ی�҂͂������B�ł��B�Ⴊ���������Ďq�ǂ������܂�A���܂łǂꂾ����J���Ă������E�E�B�����搶�Ƃ���o����Ă����킯�ł��Ȃ��ł��傤�B���ɂ͂Ђǂ����������Ƃ��������ł��傤�B �@�������q�ǂ������Ƃ킩��܂����A�q�ǂ��͂��������̂Ȃ����̂Ȃ̂ł��B�q�ǂ����Ђǂ��P�K��a�C�ɂȂ�����A�������������̂Ȃ�����Ă�肽���Ǝv���̂��e�ł��B�e���ĐȂ����̂ł��B���̂��Ƃ������ł��z���ł���A�e�̗���ɂȂ��čl������悤�ɂȂ�܂��B�u�����搶�Əo����B�v�Ǝv���Ă��炦��悤�Ɋ撣��܂��傤�B�q�ǂ��B��ی�҂������ł���̂͂��Ȃ��Ȃ̂ł�����B �p�P�R�Q�@���Ƃ��L�^������ăm�[�g�ɏ������ƁH �`�E���Ƃ̂��Ƃ��L�^����̂̓m�[�g�ł����A���ꂪ��ςȎ��ɂ͎ʐ^����肭�g�키�Ƃ����ł��傤�B���Ƃ̗l�q���f�W�J���ŎB���Ă����uWord�v��u�ꑾ�Y�v�ɓ\��t���āA���̎��Ɋ��������ȓ_��q�ǂ��B�̗ǂ��������ƂȂǂ��������ނ悤�ɂ���ƒZ���ԂŋL�^���܂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��܂��B���̃m�[�g�ł��������A�p�\�R���ł������Ƃ������Ƃł��B�����̂��₷�����@�ŋL�^�����Ď��Ƃ��l���܂��傤�B �p�P�R�R�@��̏K���́A�Ό������́H  �`�E���̃}���\����̈��}�H���Ɗw�K���̎��Ƃ��I�������⋋�H�̑O�ɂ͎��܂���ˁB�����ł͐�����g���Ă��܂����H�@�����ݏ��g�C���ł͂ǂ��ł��傤�H�@�w�ǂ̊w�Z���Ō`�^�C�v�̐�����g���Ă���Ǝv���܂��B�ŋ߂̉ƒ�ł́A�Ō`�^�C�v�̐̂Ȃ���̐�������|���v���̐�����g���Ă�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �`�E���̃}���\����̈��}�H���Ɗw�K���̎��Ƃ��I�������⋋�H�̑O�ɂ͎��܂���ˁB�����ł͐�����g���Ă��܂����H�@�����ݏ��g�C���ł͂ǂ��ł��傤�H�@�w�ǂ̊w�Z���Ō`�^�C�v�̐�����g���Ă���Ǝv���܂��B�ŋ߂̉ƒ�ł́A�Ō`�^�C�v�̐̂Ȃ���̐�������|���v���̐�����g���Ă�����������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�@������A�ی��̐搶�Ɂu�w�Z�ł��A�|���v���̐����E�ۗ͂̍����~���[�Y����̂悤�Ȃ��̂��g���悤�ɂȂ�Ȃ��́H�v�ƕ������Ƃ���A�u�������������ł����炢���ȂƎv���Ă����ł�����ǁA�\�Z���Ȃ����疳���Ȃ�ł���B�v�ƌ����܂����B �@���ψ����������́A���̌��ɂ��Ċ��ψ���ł��b��ɂ��܂������A�u�����̂͂킩���Ă��邯��ǁA�Ȃ����͐U��Ȃ��Ȃ��v�Ƃ����̂����_�ł����B�������Ȃ��E�|���v���ł͎q�ǂ��B�����Y����̂ł͂Ȃ����E�l�ߑւ����Ō`�^�C�v�̐���ɔ�ׂĖʓ|�ȂǐF�X�ӌ����o�܂������A��X�����Ƃ��Ƃ��������悤���Ȃ���Ԃł����ˁB �@�w�Z�Ŏg���Ă�������ȌŌ`�^�C�v�̐���́A�����Ƃ��҂��҂ɂȂ��Ă��܂��A�q�ǂ��B�����炭��̒��ł�����������Ă��A�����Ȃ��̂ŁA�����Ƀ|���v���̐�����Ă��ăN���X�Ŏg���悤�ɂ��܂����B���炭�l�q���ώ@���Ă���ƁA���i�u������āv�ƎU�X�����Ă��Ȃ��Ȃ������Ȃ������q���A�������������Ă���ł͂Ȃ��ł����E�E�B �@�ꏏ�ɒS�C�����Ă��鏗�̐搶�Ƃӂ���Łu����H�H�H�v�ł����ˁB������������|���v���̐�������Y���邱�Ƃ��Ȃ��A�������I�ɂ��悤�ɂȂ����̂ŁA�u�Ă�����Y�ނ��Ղ��v�E�E�ł����B�|���v���̐���͊w�Z�ł͔����Ȃ��̂ŁA���̃N���X�ł��搶���������Ŕ����Ă��Ďg���悤�ɂȂ�܂����B�ܘ_�A�]���ʂ�̐�����g���܂������E�E�B �p�P�R�S�@�w���i�N���X�j���ɂ��ĉ��H �`�E�w�Z�ɂ͐}����������܂����A�\�Z���̊W�Ŗ��N�V�����{��������������Ă���Ƃ����킯�ɂ͂����܂���B�w�Z���ł��������炸���Ƃ���悤�ȌÂ��{�������Ȃ��Ă��܂��A���͂Ɍ�����}�����ɂȂ��Ă��܂��Ă���w�Z���������Ƃł��傤�B�q�ǂ��B��A��Đ}�����ɍs���ƁA�q�ǂ��B����Ɏ��{�̐������Ȃ����ƂɋC�����܂��B�������������Ƃ������āA�}�������瑫�����̂���ԂɂȂ��Ă��܂��܂����A�q�ǂ��B���{�������Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂ŁA���Ƃ��������Ȃ��Ɗ����邱�Ƃ͂���܂��H �@�����ŁA�}��������D���ȊG�{��}�ӓ�����Ă��āA�N���X�Ɏq�ǂ��B�p�̊w�����ɃX�y�[�X�����܂������A��ďI���Ƃ�����Ԃ����炭�����܂����B�q�ǂ��B�̍D���ȓS���⓭���Ԃ�A�C�h����A�j���͂킩���Ă����̂ŁA�w�N�̐搶���ɋ��͂��Ă��炢�}�����ɂ͂Ȃ������������{���ꏏ�ɕ��ׂ�ƁA�����x�ݎ��Ԃɖ{������q���o�Ă��āA����ɑ��̎q���ꏏ�ɂȂ��Č�����A�G�{����Ɏ��悤�ɂȂ����q���łĂ��܂����B �@�u�搶�A�ǂ�ŁI�v�Ɛ��͂����Ȃ��Ă��{�������Ă���q�����āA�{��ʂ��Ă�����҂萢�E���L�������C�����܂��B�D�ǐ}������ׂ�̂��w�����ɂł͂Ȃ��A�q�ǂ��B���{�ɋ߂Â���悤�ɂ���̂��w�����ɂ̖������Ǝv���܂��B�{���g�߂ȑ��݂ɂȂ�悤�ɁE�E�B �p�P�R�T�@�S���Ȃ��ėǂ������H �`�E���̕s���R�̊w�Z�ɋ߂Ă������A���̊w�N�̂��邨�q���S���Ȃ�܂����B���̎q�͑S���ł��R�Ⴕ���Ȃ��Ƃ�����a�̎q�ł����B���R�Ȃ̂ɑ̂͐Ԃ������̑傫���ŁA�ڂ������Ȃ��E�����������Ȃ��E�����o�Ȃ��E�m�I�ɂ��ŏd�x�Ƃ����q�ł����B����������i��������A�w�N�̐搶���Ƃ��ꂳ��ƂŘb�������܂������A���ꂳ���̎��ɁA�����Ȃ���u���̎q���S���Ȃ��Ăق��Ƃ����C�����܂����B�v�ƌ������̂��A�R�O�N�ʌo�������ł��Y����܂���B �@�Ⴊ���̂���q���������ی�҂́A�u��������Ɏ���A���̎q�͂ǂ��Ȃ�낤�H�v�Ǝv���Ă�������w�ǂł��B�ی�҂̐Ȃ��v����m��Ȃ��ẮA���̂��ꂳ��̌��t�͗����ł��Ȃ��ł��傤�B�ی�҂̗���ɂȂ��čl���A�q�ǂ��B�Ƃ̊w�Z��������X���ɂ��Ă����Ȃ���A�u�搶�v�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B�Ⴂ�搶�́A�q�ǂ��B�̐�����ی�҂Ƌ��Ɋ�ׂ�搶�ɂȂ��Ă��������B �p�P�R�U�@�q�ǂ��B�̍D���Ȃ��Ƃ�m���Ă��܂����H �`�E�q�ǂ��B���b��ɂ��Ă���e���r�̔ԑg��Q�[���̂��Ƃ�A�C�h���̂��ƂȂǁA���Ȃ��͂ǂꂾ���m���Ă��܂����H�@�u�搶�͒m��Ȃ��Ȃ��B�v�ƌ����ƁA�q�ǂ��B�͂������肵����������܂��H�@�x�ݎ��Ԃ⋋�H�ł̂�������A�搶�Ǝq�ǂ��B���Ȃ��厖�ȃR�~���j�P�[�V�����̂ЂƂł��B �@�搶���F�X�Ȃ��Ƃ�m���Ă��邱�Ƃ��킩��ƁA�q�ǂ��B�����i�ȏ�ɉƒ�ł̗l�q�⎩���̍D���Ȃ��Ƃ���������b���Ă���܂�����A�����ɂ͓��ɋ������Ȃ��悤�Ȃ��Ƃł��m���Ă����Ƃ����ł���B�A�����ł͂킩��Ȃ��q�ǂ��B�̈ӊO�Ȉ�ʂ��������邩������܂���B �p�P�R�V�@���]�Ԃ̎w�������Ă��܂����H �`�E�ߌ�̎��ԂɁA�Z����������̐��k�B���w�Z�̎��]�Ԃ�O�֎��]�Ԃɏ���đ������Ă��܂��B���]�Ԃɏ���Ă���̂́A���]�Ԓʊw�����Ă���q�B�ł͂Ȃ��A���i�̓X�N�[���o�X�Œʂ��Ă��鐶�k�B�ł��B �@�w�Z�Ŏ��]�ԏ�肷�邱�Ƃɂ��ẮA�ی�҂̒��ɂ́u�Ƃ̎��]�Ԃ���肽����悤�ɂȂ邩��A������Ƃ˂��E�E�B�v�ƌ����������܂��B�S�z����̂�����Ӗ����R��������܂���B���]�Ԃɏ��Ă���ʖ@�K��m��Ȃ������Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���]�Ԃɏ���y���݂͂Ȃ�Ƃ��m�ۂ��Ă����������̂ł����A�w�Z�Ŏ��]�Ԏw�����s��Ȃ��ƕЎ藎����������܂���B�N�ɂP��s����u��ʈ��S�w���v�����ł͂��ڂ��Ȃ��ł��傤�B���ƌ�Ɏ��]�Ԃ̎��̂ŖS���Ȃ������k�͏��Ȃ�����܂���E�E�B �p�P�R�W�@���w���̑̈�́A�y�����Ȃ���Ύq�ǂ��B�͐L�тȂ��H �@�̈�ł͑̑S�̂������Ƃ����߂��܂��B�u�����E����E�~�܂�E������E���ԁE�o��E�葫��A�������ē������v�Ȃǂ̊����ɂ́A���i�̐����ł͗]��s��Ȃ��̂̓���������܂��B�q�ǂ��B���̂������ƂɊ�ѥ�y���݁E�����������Ȃ���A�{�C�ő̂������Ƃ͎v��Ȃ��ł��傤�B�w�����ꂽ�������Ă��܂��Ƃ������e�̑̈�̎��Ƃł́A�^�����D���ɂȂ��Ă͂��炦�܂���B�̈�̓��e���l����ۂɂ́A�u�w�K�̂˂炢�v����ɗ���̂ł����āA�w�Z�ɒu����  �@�w�Z�̋���ł͂ł��Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ��w�K�̂˂炢�ƂȂ�Ȃ�A�q�ǂ��B�������ɂȂ��đ̂�����悤�ȋ�������K�v���o�Ă���̂ł��B�w�Z�ɂ��鋳��Ɋւ��ẮA����̃}�b�g�E�n�[�h���E���є��Ȃǂ�g�ݍ��킹�邱�ƂŁA�A�����Ċ������s����悤�ɂ���ȂǍH�v���K�v�ł��B�q�ǂ��B�������ɂȂ��đ̂����悤�ȑ̈�̎��Ƃ��s����悤�ɁA�搶���ŗ͂����킹�܂��傤�B �p�P�R�X�@�w�Z�̒��ɂ͐l�ނ���t�H �`�E���ʎx���w�Z�̒��ɂ́A�l�X�ȍ˔\����Z�i�H�j�������Ă���搶�������܂��B�����A���̐搶�̑��ɂ���ꕔ�̐搶���炢�������̂��Ƃ�m��Ȃ����Ƃ������悤�ł��B �@�p��b���ł���E�|���g�K����⒆���ꂪ�b����E�_���X���x���E�a���ۂ��@����E�p�\�R���ɏڂ����E�������x���E�����������E�y��̉��t���ł���E�������ł���E�v�H�|���ł���E�ǂݕ����������܂��E�������ł���E���ނ������������Ă���E�Ǐ��Ƃł���E�J�����ɏڂ����E�o���a�̂Ɋ��\�E���̂��Ƃɏڂ����E���̂��Ƃ��悭�m���Ă���E�̑��������E�E���X�A���Ȃ��̊w�Z�ɂ�����Ȑ搶��������ł��傤�B�����������搶���̗͂����p���Ȃ��Ȃ�Ėܑ̂Ȃ��B �@�������̕s���R�̊w�Z�Ō������������Ă����Ƃ��ɁA���ɂP��ʏ�̌����e�[�}�̌��C�Ƃ͕ʂɌ��C����݂���悤�ɂ��܂����B���̓��́A���Z��˔\�̂���搶���u�t���ɂ��āA�w�Z�̐F�X�ȏꏊ�Ō��C��i�u���j���s���Ă��炢�܂����B �@�u�t���ȊO�̐搶���́A�������w�т����搶�̏��ɍs���Ċw�K����悤�ɂ��܂��B�Ⴆ�A�a���ۂ���肽���搶���́A�a���ۂ������Ă����搶�̂Ƃ���ɏW�܂���1�N�Ԋw�Ԃ悤�ɂ��܂��B�ċx�݂ɂ́A���C�����e�u���Őݒ肷��̂ŁA���i�s���Ȃ��u���ɂ��Q���o���܂��B���̍u���́A�F�X�ƌ`��ς��Ȃ�����R�O�N�߂��o�������ł����̊w�Z�ő����Ă��܂��B�u�w���̊_�����z���Đl�̌𗬂��ł���E�l�ނ��@��N�����E�݂�Ȃ̗͂ɕς���Ƃ��������Ƃ��ł���v�̂������b�g�ł��B�O������l��N��1�`�Q��Ă�ł��A�p�������Ȃ����낤�Ƃ��邱�Ƃ����t���܂���B �p�P�S�O�@�؍H�p�̃{���h�́A�⎆��ڒ����邾������Ȃ��H   �`�E�؍H�p�{���h�́A�̔Ɣ�\�荇�킹��̂Ɏg���܂����A����ȊO�̎g����������܂��B�E�̎ʐ^�́A�}�H�̎��Ԃɍ�����u�H�F�̂��M�v�Ɓu�H�F�̃R�b�v�v�ł��B�g�t�����t���ς��{���h�œ\�邾�����ƁA�₪�ėt���ς́A�������ă|���|���Ƃ͂���Ă��܂��܂��B �`�E�؍H�p�{���h�́A�̔Ɣ�\�荇�킹��̂Ɏg���܂����A����ȊO�̎g����������܂��B�E�̎ʐ^�́A�}�H�̎��Ԃɍ�����u�H�F�̂��M�v�Ɓu�H�F�̃R�b�v�v�ł��B�g�t�����t���ς��{���h�œ\�邾�����ƁA�₪�ėt���ς́A�������ă|���|���Ƃ͂���Ă��܂��܂��B�@�����������Ƃ��ɂ́A�{���h�𐅂Ŕ��߂ėt���ς̏ォ��h��悤�ɂ��邱�ƂŁA�t���ςɃR�[�e�B���O������悤�ɂ��܂��B�������Ă����Ηt���ς��|���|���͂���Ă��܂��悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ��Ȃ�܂��B���ʍ�����v�V�F�[�h���ł��A�̂�ł͂Ȃ����Ŕ��߂��{���h���g���Ƃ����ł���B �p�P�S�Q�@�c������̖{�͖��ɗ��H �`�E�c�t���̐搶��ۈ牀�̐搶���ǂ�ł��錎�������{������Ŕ����Ă��܂����A�Ⴂ�j�̐搶�͎�Ɏ���Ă݂����Ƃ�����܂����H�@���̐搶�͂����������{�ɂ��ڂ������������̂ł����A�j�̐搶�ƂȂ�Ǝ�Ɏ�������Ƃ��Ȃ��Ƃ��������w�ǂł͂Ȃ��ł��傤���B �@�c������̌������́A�}�H��ǂ̑����E�G�߂̍s���̐i�ߕ��ȂǏ��w���⒆�w���̎q�ǂ��B�̎w���ɖ𗧂��Ƃ��F�X�ڂ��Ă��܂��B���ʎx������̖{�����łȂ��A�����������{�ɂ����L���Ēm�����L�߂܂��傤�B��̂ǂ�Ȗ{������ł����ʎx������W�̃R�[�i�[�ׂ̗��c�������ۈ�̃R�[�i�[�ɂȂ��Ă��܂��A�Ⴂ�j�̐搶�ɂ������߂��܂��B �p�P�S�R�@�ЂƂ̋��ށE����ŐF�X�Ȏq�ɑΉ��ł�����̂��ĉ��H �@�E�̎ʐ^�́A�W�����v���ċ����̊ǂɐG���Ɓu�V�������[���v�Ƃ��ꂢ�ȉ��F���o��Ƃ������̂ł��B�ׂ̎ʐ^�́A�W�����v���ăA���p���}�����̃C���X�g�̓\���Ă���{�[�h�Ƀ^�b�`���������Ŏ��Ƃ������̂ł��B�ǂ�������[�v�̗��[�ɗփS���̑������̂����Ă���̂ŁA�搶�����[�v�����Ɉ����Ύ肪�͂��Ȃ��q�ɂ��肪�͂��悤�ɂȂ�܂��B �@���̎ʐ^�́A�V��̃t�b�N�𗘗p�����P�̓I�ł��B����͑��߂̗փS���ŎP�ƂȂ����Ă���̂ŁA�{�[���𓊂���Ƃ��ɂ́A���̏�ł����ɍ�����ς�����悤�ɂȂ��Ă��܂��B�{�[����������������q�E�������Ȃ��q�ƁA�H�v����ŐF�X�Ȏq�ɑΉ��ł���悤�ɂȂ�킯�ł��B �p�P�S�S�@�S���w�N���悭�ς���搶���Ăǂ��Ȃ́H �`�E���N�̂悤�ɒS������w�N��ς���搶�����܂ɂ��܂��B���N�ł͂Ȃ��ɂ���A�悭�ς���Ȃ��Ǝv����搶�́A�w�Z�̒��ɂP�l��Q�l�͂���ł��傤�B�l�ԊW���ǂ��Ȃ�������A�ی�҂Ə�肭�����Ȃ��ȂǐF�X�ȗ��R�͂��邩������܂���A���ł��䖝����K�v�͂���܂���B�N�����č������l�Ƒg��ł��܂�����A���̂���ی�҂ɓ������Ă��܂����Ƃ��Ă���܂�����B�@ �@�����A�q�ǂ��B�Ɉ������N���Ȃ��ȂǂƂ������R�Ŋw�N���悭�ς���悤�Ȑ搶�́A�������������Ƃ����d���������Ă��Ȃ��Ƃ��������悤������܂���B�q�ǂ��B�ɂ������ɂ��������݂ł͂���܂���A���߂ɓ]�E�������������ł��傤�ˁB�w�Z�̐搶�ɂ͎q�ǂ����D���Ȑl���Ȃ��ė~�����Ǝv���܂��B���肵���d�����������Ƃ����̂ł���A���̌������̎d���ł��Ȃ�ł����̐l�ɍ��������̂�����ł��傤����B �p�P�S�T�@���̊w�K�Ŏg���u���ނ�v�̊Ƃ̎������܂��č���B����܂�Ȃ����@�́H �@���������������@�́A�փS�����Ђ˂��ĂQ�d�E�R�d�̗ւɂ������̂��ʐ^�̂悤�ɂЂ��̏ォ�����邾���ł��B��������Ɖ��\�{�Ƃ��܂Ƃ߂Ă��Ђ������ނ��Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂��B�ȒP�ŏ�������@�ł���B �p�P�S�U�@�����Łu�ʓ���v���������B�������ȒP�Ȃ��̂��Ă���H �`�E��ԊȒP�ȕ��@�́A�P�O�O�~�V���b�v�i�_�C�\�[�j�̎P�Ɛ��ʊ킩�o�P�c��p�ӂ��邾���ł��B���ʊ��o�P�c�̏�ɎP���L���Ă������ɂ��ď悹��Ί����ł��B�ܘ_�A�P����ʊ�́A�w�Z�ɂ��镨�łn�j�ł��B �p�P�S�V�@�G�{�̐��E��̌�����H   �`�E�u�ĂԂ���v�E�u�]�E����̂���ہv�E�u�������Ȃ��ԁv�E�u�߂������������ǂ���ǂ�v�E�u�̂��Ă̂��āv�E�u�p�I�����̂��ׂ肾���v���̊G�{�̓ǂݕ����������Ă���A�u�������Ȃ��ԁv�Ȃ炩�ԂɌ����Ă��V�����Ȃǂ��l�߂��傫�ȑ܂��������肽�肷��ł��傤�B �`�E�u�ĂԂ���v�E�u�]�E����̂���ہv�E�u�������Ȃ��ԁv�E�u�߂������������ǂ���ǂ�v�E�u�̂��Ă̂��āv�E�u�p�I�����̂��ׂ肾���v���̊G�{�̓ǂݕ����������Ă���A�u�������Ȃ��ԁv�Ȃ炩�ԂɌ����Ă��V�����Ȃǂ��l�߂��傫�ȑ܂��������肽�肷��ł��傤�B�@�q�ǂ��B�͊G�{�̐��E���ƂĂ��D���ł��B�u��������̂���ہv�Ȃ�A�搶���q�ǂ��B��w���ɏ悹�Ďl�����ɂȂ��Ă��邮��Ƌ����̒����Ă����ł��傤�B�u�߂������������ǂ���ǂ�v�Ȃ�A�꒵�т��������A�ۑ��Ɍ����Ă��}�b�g�ɏ� 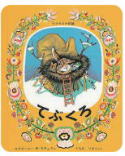  �����������ł��傤�B�u�ĂԂ���v�̎��Ƃ��s�������ɁA�����z�c��D�����킹�����̂Ŏ�܂����A�q�ǂ��B�����X�ƕz�c�̒��ɓ���ď��̐搶���ꏏ�ɉ��ɂȂ����Ƃ��̎q�ǂ������̊��������ȏΊ�����ł��v�������܂��B �����������ł��傤�B�u�ĂԂ���v�̎��Ƃ��s�������ɁA�����z�c��D�����킹�����̂Ŏ�܂����A�q�ǂ��B�����X�ƕz�c�̒��ɓ���ď��̐搶���ꏏ�ɉ��ɂȂ����Ƃ��̎q�ǂ������̊��������ȏΊ�����ł��v�������܂��B�@�G�{�̐��E��̌����邱�Ƃ́A���Ƃ̊w�K�ɂȂ����蓮��͕�̗͂�L������A��������������A�����Ă̗͂������肷�邱�ƂɂȂ���ł��傤�B���w���ł́A�搶�����y���݂Ȃ���q�ǂ��B�ɊG�{�̐��E��̌�������Ƃ�厖�ɂ��ė~�����Ǝv���܂��B���Ƃ̊w�K���˂炢�Ƃ��邩����͕���˂炢�Ƃ��邩�A�����������邱�Ƃ��˂炢�Ƃ��邩,�w�K�̂˂炢���͂����肳���Ď��g�ނƂ����ł��傤�B �p�P�S�W�@�}�H�̍�i���B�Ⴊ���̏d���q�ł�������i������H �@�Ⴆ���ʍ��ł́A���D�ɘa���i��q���j��\��͓̂���q�ł��_�C�\�[�̉��|�R�[�i�[�Ŕ����Ă���p�[���}�b�g���g���Ώ�q���������Ɠ\�邱�Ƃ��ł��܂��B���̐܂���߂Ȃǂ́A��q����܂�̂͏��w���̎q�ǂ��B�ɂ͓���̂Ő搶�������O�ɍs���܂����A�F�t���̕��͏Ⴊ�����d���q�ł��ł��܂��B�����߂��������g���Ă��ꂢ�Ȕ������\�ł��B���́u����{�b�N�X�v�́A���������ɐ疇�ʂ��ōD���Ȃ悤�Ɍ����J���邾���ō��܂��B �@�Ⴊ���̏d���q���ł��邱�Ƃ�T���̂ł͂Ȃ��A�ǂ��������ɂ��݂�ȂƓ����悤�ɂ��邩�H�v���邱�Ƃ��厖�ɂȂ�Ǝv���܂���B �p�P�S�X�@���g��Ȃ��ȒP�Ȓ����́H �@ �@�ʐ^�̃G�r����ׂ��́A���тƃN�b�L���O�V�[�g�Ɗۂ��_�ƃI�L�A�~�Ƃ��������ŊȒP�ɍ��܂��B���т̓p�b�N���ꂽ���̂�d�q�����W�Ń`������n�j�ł��B���т����q�Ɉ�t����T�`�U�l���͂ł���ł��傤�B�I�L�A�~���茳�ɂȂ��ꍇ�́A���тƏݖ����������ׂ��͍��܂�����A�Z���ԂŎq�ǂ��B������ĐH�ׂ邱�Ƃ��ł��܂��B �p�P�T�O�@���̋ؗ͂����߂�ȒP�ȕ��@�́H 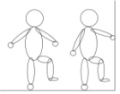 �@�����ƊȒP�ɒZ���ԂŖ����ł��邱�Ƃ�����܂��B�^�C�}�[���g���āu�Б������v�����邱�Ƃł��B�Б������������Ȏq�́A�Ў��ǂɓY���ė����܂��B���E�̋r�����݂ɂP�O�b�グ�ďI���ł��B����Ă�����Q�O�b�E�R�O�b�E�P���ƐL���Ă��������ł��傤�B�@ �����s���L�^������Ă����A�P�N�Ԃŋؗ͂��o�����X�͂����Ă����ł��傤�B�V���ꏊ�⎞�Ԃɉe�����Ȃ��ŁA�q�ǂ��B���V�ъ��o�ŊȒP�ɂł�����@�ł��B�e�ƒ�ɂ������߂ł���ȒP�ȕ��@�Ȃ̂ŁA��������₨�ꂳ��E�����������₨�������Ƃ��q����ŁA�Q�[���̂悤�ɂ���Ă͂ǂ��ł����Ƃ��b�����Ă������ł��傤�B �p�P�T�P�@�ӊO�ƋC�Â��Ȃ��C�̂��Ƃ��ĉ��H �`�E���A���q����B���X�N�[���o�X����~��ēo�Z���Ă��܂��B�o�X�̃h�A�̏��⌺�ւ̉��ʔ��ł��q����B��S�C�̐搶�����҂킯�ł����A�ǂ̕ӂ��������āi�ώ@���āj����̂ł��傤�B��̊�F�����Č��N��Ԃ��`�F�b�N������A�ƒ�ʼn������������\���@����悤�ɂ���Ǝv���܂��B���̎��ɌC�𗚂��l�q�����܂ɂŗǂ��̂Ō��Ă�����Ɨǂ��ł��傤�B �@���ɏ��w���̂��q����B�ł����A�e�䂳��͂��q����B���������邱�Ƃ��݂����đ傫�߂̌C��^���Ă��邱�Ƃ������̂ł��B�܂��A�C���̂̐����ɔ����������Ȃ��Ă���ꍇ������܂��B�e�䂳��B�͊w�Z�ł̗l�q�͂킩��Ȃ����Ƃ������̂ƁA���q����B�����Ȑ\���ł��Ȃ��̂Ŗw�njC�ɂ��Ă킩��܂���B�傫������C���������Ȃ��Ă��܂����C���A�̂�^�����ɗǂ��e���͗^���܂���A�S�C�̕�����`���Ă����悤�ɂ��������̂ł��B �@�o�ϓI�ɐV�����C���̂�����ƒ������ł��傤����A���̕ӂ͍l������K�v������܂����E�E�B �p�P�T�Q�@�{�����ӎ��������ޥ����Ƃ́H �@�����������⏬�w���ł���A�w���̔��͗X�փ|�X�g�ł͂Ȃ�����ǗX�փ|�X�g�̂���x�ƌ����Ă��ł��邩�炽���̌��̊J���Ĕ��ł��X�փ|�X�g�Ƃ��Ăn�j�ɂȂ�̂ł��B �@���ʎx���w�Z�̂��q����B�́A�����������u�����āv������q���������܂��B���b�̂悤�Șb���ł����A���w���R�N�̎����B�̒S�C���������A�����̐e�䂳��B����u�搶�A�Ƃ̗X�֎ɂ����̎q����̎莆�݂����Ȃ��̂������Ă�����ł���B�v�Ƃ����b��������܂����B�Z���������Ă��Ȃ����b�Z�[�W�̂悤�Ȃ��̂����������ł����A���ꂳ����ɂ͊����������悤�ł��B �@����̋��ޥ������͎��Ԃ�������ł��傤���ޗ���������ő�ς�������܂��A���ǂ����ޥ����Ŏ��Ƃ��s���ق����A�ꌩ�����̂悤�ōŒZ�̋ߓ��ɂȂ�Ǝv���܂��B��ʎw���̐M���@�ނ̋��ޥ����Ɋւ��Ă��A�Ȃ�ׂ��{���ɋ߂��悤�Ȃ��̂�p�ӂ��������A�q�ǂ��B�̊w�K�ɖ𗧂��Ƃł��傤�B �p�P�T�R�@�w�Z�ōł��厖�Ȃ��Ƃ��ĉ��H �`�E�w�Z�ł����Ƃ��厖�Ȃ��Ƃ́A�u��Ɏq�ǂ��B�E��Ɏ��Ɓv�ł��B�F�X�Ȏd���⌤�C������܂����A�S�Ă͂��̂��Ƃ̂��߂ɂ���Ƃ����Ă����ł��傤�B�����u���Ƃ��厖�v�Ƃ������Ƃ͂킩���Ă���̂ɁA�S�Z�̌����e�[�}�����N���Ƃɕς��u�L�����A����v���̎����ɉ������e�[�}�Ȃ̂͂ǂ������ƂȂ�ł��傤�ˁB�S���I�ɓ����e�[�}�Ō������邱�Ƃ͕K�v���������Ă���킯�ł����A�Ȃ����s��ǂ��Ă���悤�ȋC���ɂȂ邱�Ƃ�����܂��H �@�����̌����e�[�}�Ɋւ��Ă��ł��邾�����ʂ��Ă����Ȃ���Ȃ�܂��A�����̃e�[�}���K�v���Ƃ��Ă��A�w�Z�ɂ����āu���Ɓv�ȏ�̌����e�[�}�͂Ȃ��Ǝv���܂��B���ǂ����Ƃ��s���ׂɂ́A���ƌ�̐������������Ďq�ǂ��B�ɕK�v�Ȋw�K���e�̌������s�����Ƃ�w���@�̌����A���D�ꂽ���ޥ����̊J���┭�B�̊w�K�ȂǐF�X�Ȍ��C�ۑ肪����ł��傤�B �@���錤���e�[�}�ł�����������đS���̐�i�Z�ɂȂ��Ă��A�S���ł̃e�[�}���ς������������N���x���������Ȃ���i�Z�ł��B�u���Ɓv�ȏ�ɏd�v�Ȍ����e�[�}�͂Ȃ��Ǝv���܂��B �p�P�T�S �u������́v���ĂȂ낤�H �`�E�u������́v���ĉ����낤�ƁA���Ƃ��Ă����������q�B�̂��Ƃ��v�����⍑��E�Z���F���w�̎��Ƃ̏��������Ă���Ƃ��ɍl���܂��B�����邽�߂ɂ́A���N�łȂ���Ȃ炢���낤���A�������邽�߂ɂ͎������Ȃ���ΐH�ׂĂ����Ȃ����A�ǂ��l���𑗂邽�߂ɂ͊y���݁i��j���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�ƁB�l�Ɗւ��y������m������d������ŏ����Ă��炤�ۂɂ̓R�~���j�P�[�V�����\�͂��K�v�ł��傤�B �@�����̌v�Z���ł��Ȃ��q�ǂ������́A�ǂ�������玩���Ŕ��������ł���悤�ɂȂ�̂��낤�A�������ǂݏ����ł��Ȃ��q�ǂ������͐����Ă����̂��Ђǂ��s�ւő�ς��낤�ƁE�E�B�w�Z�ł́A�l�X�Ȏ��g�݂����Ďq�ǂ������Ɂu������́v���������悤�Ƃ��Ă��܂��B����ł��������ǂݏ����ł��Ȃ��܂ܑ��Ƃ��Ă������k���������܂��B�y���݂��H�ׂ邱�Ƃ����Ƃ����q�ǂ������������ł��傤�B �@�������ɂ������A���k�Ɂu���͉��H�v�ƕ����ƁA�u�Ƒ��ŗ��s�ɍs�������v�E�u�����ċ��������������A��������E���ꂳ��Ɋy�����Ă��������v�E�u�A�C�h���̃R���T�[�g�����ɍs�������v�ȂǁA�����\������Ďq�ǂ��B�����ɋ����Ă���܂����B �@�w�Z�łł��邱�Ƃ́A�������ǂݏ����ł��Ȃ��Ă������̌v�Z���ł��Ȃ��Ă��A����炪�ł���l�Ɨ]��ς��Ȃ��悤�Ȑ��������Ă�����悤�Ɋw�K���e���l���邱�Ƃ�������܂���B�v�����g�Ōv�Z���ł��Ă��������Ŏg���Ȃ��v�Z�\�͂ł͈Ӗ�������܂���B���ށE����̍H�v�œǂݏ������ł��Ȃ��q�ł����ꂪ�Ȃ��q�ł����҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�������Œ���Ƃ��悤�ɂ��邱�Ƃ́A����̌g�тł���R�~���j�P�[�V�����u�b�N���̊��p�ʼn\���ƍl���Ă��܂��B �@�X�}�z�������Ȃ��Ă��X�}�z�̎g������������Ȃ��Ă��A�������Ɋւ��Ă͂O�`�X�܂ŕ������Ă���A�x�����͉\�ɂȂ�܂��B���ނ̍H�v�ō��܂��������낤�Ǝv���Ă������Ƃ��A�ł���悤�ɂȂ邱�Ƃ���������ł��傤�B�����̓��ʎx���w�Z�ł̓J�[�h�̊��p�������Ă���Ƃ��������܂��B�v�Z���ł��Ȃ��Ă��x�������ł���Ƃ������Ƃł��ˁB������ЂƂ̕��@��������܂���B �@�Ⴊ������r�I�y�x�̂��q����B�ɂ��ẮA�A�E�ł�������̂��Ƃ����ƁA�����Ă��ꂾ���ł͂Ȃ��ł��傤�B�w�Z�𑲋Ƃ��Ă������q�ǂ��������A�����l���E�S���L���Ȑl���𑗂�ɂ͂ǂ������炢���̂����l���Ȃ��ẮA�w�Z�����̒��ʼn����K�v�Ȃ̂��������Ă��Ȃ��ł��傤�B �p�P�T�T�@���S�Y��ׂ��炸 �`�E���߂Ďq�ǂ��B�ɐڂ������̂��Ƃ��o���Ă��܂����H�@���ꂩ��A���߂ĒS�������w�N�̂��Ƃ�d���̂��Ƃ��E�E�B�Q�N�E�R�N�ƌo�ƒi�X�d���Ɋ���āA������������O�̂悤�ɉ߂��Ă����܂��B���������S��Y�ꂪ���ɂȂ�܂��H �@���́A�V�C�Ŏ��̕s���R�̊w�Z�ɋΖ����܂������A�����Ȃ�ŏd�x�̂��q����̒S���ɂȂ�܂����B���ʂ́A�V�C�̐搶�͏Ⴊ���̌y���q�̒S���ɂȂ�̂ł����A�w�N��C�̐搶����u�ђ˂���A��ς��Ǝv������ǁA���ꂩ��̋����l���ɕK�����ɗ�����撣���Ă��������B�v�ƌ����܂����B�P�N�ԁA�����[��܂ŏ�Q������̖{��ǂ݁A�x���͋��ނ�����ĕ����܂������A�����ł��Ȃ������Ƃ����v�������c��܂���ł����B���������炤�̂��p���������Ǝv���P�N�B���̎��̎v���͍��ł��Y��܂���B �@�q�ǂ��B�������Ǝv�������ł́A�q�ǂ��B�̗͂ɂ͂Ȃ�܂���B�q�ǂ��B�̗͂ɂȂ��搶�ɂȂ낤�Ƃ����̂����S�ł��B �p�P�T�U�@�ł��D�ꂽ���ށE����Ƃ́H �`�E�q�ǂ������̂��Ƃ��D���ŁA�\�ꂽ�芚��ł�����}�ɓ��H�ɔ�яo������A���������J��Ԃ��悤�ȑ�ςȎq�ɂ����Y���邱�ƁE�q�ǂ������ƈꏏ�ɂ���Ƃ��ɏΊ�����₳�Ȃ����ƁE�q�ǂ��̒B�̐�������������ׂ邱�ƁE�ی�҂̗���ɂȂ��čl���邱�ƁE������Ȃ����Ƃ͐�y�⓯����{����w�ڂ��Ƃ��邱�ƁE�u���̐搶�Əo��ėǂ������v�Ɠ�����ی�҂�q�ǂ��B����v����i�M�������j���ƁE�E�E���������搶���ō��̋��ށE����ł��傤�B�l�ԂقǗǂ����ށE����͂���܂���B |
�s�n�o��