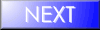江戸時代に大臣柱の前に舞台が前進した時、この舞台を前舞台と名づけて、主にここで演技が行われたが、
後に大臣柱が左右に移動したので鏡通りができてこの前後で演技が行われた。
プロセニアム・アーチより前の舞台スペースをエプロンステージまたはフロントステージと云う。
舞台に幕が現れたのは能舞台頃か不確実。古来の控えの場を仕切っていた幔幕が、
舞台に登場したように見える。
舞台と客席を分ける幕の登場は17世紀半ばと言う。
左右の袖の羽目板には竹の絵を描いている。
上手の臆病口の板戸には竹の絵を描かない。下手に能舞台と同じように揚幕があり、
橋掛りのごとく高欄を置く。
正面松には根や熊笹も描かれるが、その前に置かれた山台で隠される。

松羽目物
舞台左右の奥が客席から見えないようにさえぎる張物、切り出し、幕類のこと。
寒冷紗の様な目の荒い布でつくられた幕。紗幕ともいう。
これを下げると奥がかすんでみえるので霧の雰囲気などを出すのに用いられる。
また奥の照明を消すと前明かりで奥がまったく見えなくなり、
前明かりを消して奥だけ照明すると夢幻的な場面を印象づけられる。