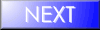家屋などの高さを言い表す建築用語が転じたもので、例えば背景の張物や屋体、
舞台床から簀の子までの高さなど、すべての高さの測定に用いる。

「段幕」
演技の主屋台の上手に障子2枚を嵌めた一部屋が付いて、これを付け屋台と呼び、
種々に用いる。別室の情景を一望できる工夫と見る。
舞台上の吊り物を操作する綱を舞台の上手、下手の両端に集めている所。
昔は木製棒状の物で、これに綱をつけて簀の子より吊りさげて、上下の操作ができるようになっていた。
これに色々の舞台装置の吊り物をつけて操作した。今日では鉄製でバトンと呼び、機械操作が多い。
張物の一部を方形に切り抜き、同型の張物をはめ込み、この中心に軸を通して回転させて舞台転換する。
田楽に似ていることから名がついた。また回転時に演者が張物について出入りする仕掛けで、
妖怪変化の登退場に利用する。
布地に浪の絵を描いて使ったのが初めで、これを浪幕といった。絵によって名称が数々ある。

浪幕

道具幕
木製の堤の形に切り出した道具。造花の草花等を差し込む台とする。
最近は大劇場程立派なものを用意する様になった。開閉が引幕と異なり上下であるから、別種の効果がある。

緞帳