全く仮空の人物であるとすれば、いったい「誰が」道成寺を建立したのであろうか。
現在、小高い丘の上を平らにした、四千五百坪という広大な敷地を持ち、
過去においては『紀伊続風土記』(前出『古事類苑』所収)における記述によれば、
「境内、東西二町南北一町半」坪に直せば一万八百坪にも相当する領域を占め、
今日こそ主な建物は、本堂・三重塔・書院・客殿・護摩堂ぐらいであるが、その昔は、
数多い宿坊を従えた七堂伽藍を備える雄大な寺であった道成寺を、
個人の力によって建立するためには、ある程度の権力と資力を必要とする。
その点から推測すれば、道成寺の建立者は権力者かその眷属であり、
資力を貯えているだけの旧家あるいは名門であり、加えて、
記録に残らない点から察するに、歴史上に目立つ人物でないことが推理できる。
また、「紀大臣道成」という名を、道成寺という寺の名称が定まってから創意された名とすれば、
本当の謎の道成寺建立者の名も、道成寺という名とつながっていると考えられるのではないだろうか。
「道成寺」という名を、音読にせよ訓読にせよ、その伝承に或る誤りがあったと考えて本の姿へ辿って行けば、
文武天皇御宇のある人物につきあたるのではないかと云うのが、第一仮説の導き出す方法である。
道成寺の名を、MiChiNaRiDeRa→MiChiNaRuDeRa→MiChiTaRuDeRaあるいはMiChiTaRuNoTeRaと
分析して行けば、推論ながら「ミチタル」の音を導き出せる。
「ミチタル」の音によって、文武天皇御宇の人物と照合してみると、「道足」という人物が浮かび上ってくる。
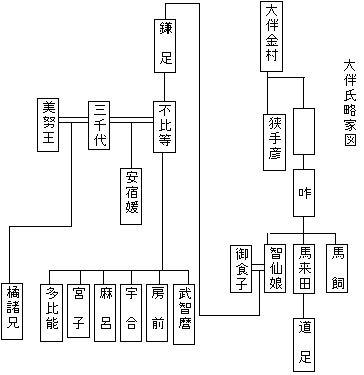
大伴馬飼・馬来田・智仙娘三兄妹の次男、馬来田の息子・道足である。
道足は、藤原不比等の親戚にあたり、持統天皇時代から文武天皇時代に生きた人物である。
文武天皇治世と云うのは、藤原京を中心として、藤原鎌足の息子不比等を執政とし、
律令制を整え、年号を定め、都を造営し、文武官の衣服の色まで定めた時代であり、
政治体制強化期の最終段階の時代であった。
しかし、文武天皇自身は、若冠25才にて崩御し、天皇在位わずか11年であった。
(『神皇正統記』『日本史資料集』『日本人名小辞典』『日本史年表』等に拠る)
大伴道足を、道成寺の建立者と仮定するには、三つの理由がある。
一つには、上述した道成寺の名の分析による。
一つには、大伴道足の経済力とその背景にある権力。
一つには、道成寺が建立された要因の推論による結果である。
『万葉集』巻一・五四に、大宝元年九月、太上天皇たる持統前天皇の、
紀伊国御幸が記されている。
そこにおいて、持統天皇と関係の深い藤原不比等の親族大伴道足が、御幸以前に、
御幸路にあたる矢田庄土生村付近へ「宿舎」として、道成寺を建立したのではないかという、
推論が出来るであろう。
仮に寺院の形態を備えた「宿舎」であったとすれば、寺としての開山・開祖が明らかでない事は当然であり、
寺院として欠くべからざる付属建物を備えていない事も、「宿舎」としての機能を考えれば、
納得出来ることであると思われる。
だが、現在の道成寺を訪れると、小高い丘の頂を小さな石垣で囲み、広い平らな敷地を道成している事が分る。
太古の「宿舎」が同じ場所にあったとすれば、こうした道成の事業は、一朝一夕で出来ることではないと考えられる。
道成寺は、文武天皇の御宇に、本当に新らしく建立されたものだろうか。
もし、道成寺という名ではなくとも、その場所に古くから一つの建物があり、
その建物を基として道成寺「宿舎」が建てられたと仮定すれば、
道成寺の規模の大きさなど、説明出来るのではないだろうか。
その仮定によって次の仮説を展開する。
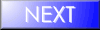 |
[次へ] |
| 【道成寺攷 参考資料一覧】 |
| 隠居部屋あれこれ |
| 伝統芸能 |