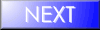
|
文武天皇治世前後の、飛鳥の都・藤原の都・熊野神社を結ぶ道の熊野参詣や 紀伊国の温泉へ通う道としての重要性を想い、 ほぼ一日行程と思われる約三十キロの間隔を置いて、長保寺・道成寺・牟婁温泉 ・熊野本宮・熊野新宮が存在している事なども合せて考えると、 道成寺などが当時の旅人の宿地としてかなりの重要性を持っていたと思える。 特に、長保寺・道成寺は、その旅路のすぐ先が、熊野三社の聖地であると考えられる 牟婁郡・無漏の篭に続いているために、 熊野参詣人の、清めの場・禊の場、去垢の場であったと推測出来るだうう。 つまり、太上天皇の御幸のために道成寺を建立したと考えるより、 それ以前にすでに道成寺が存在していたと考えられる。 道成寺という名はなくとも、将来道成寺となるべき建物が、彼の地に存在していたであろうと 仮定するわけである。 道成寺が、太上天皇の御幸に前後して建てられたとする考えは、 道成寺の寺伝などによって導き出されたものであるが、 その寺伝は名も無い建物が仏教に帰依して道成寺と名乗ったことを指しているのではないか。 では何故道成寺と成ったのか、また道成寺と呼ばれる以前には、 一体いかなるための建物であったのかという問題を再び考えて見たい。 道成寺の宗派について、前出の『南紀名勝略志』などに依れば、法相宗から天台宗に改められたとしている。 法相宗が道成寺の最初の宗派であったかどうかは若干の疑いもあるが、 道成寺の名称が定まったことを仏教の帰依によるとすれば、 その宗派を法相宗とするのも、法相宗が南都六宗の一つとして当時勢力を拡大しつつある時期と重なって、 多くの寺々に教えを説いたと思われるゆえに異論のない事と思う。 また、前出の各資料によっても、法相宗を最初の宗派として掲げているのである。 道成寺が「道成寺」と名を改めた、あるいは名を定めたのは、法相宗の寺院となったためであるとすると、 道成寺と法相宗の結びつきに何らかの必然性を探り得ないであろうか。 つまり、道成寺が法相宗と結びつくには、法相宗でなければならない理由があったのだと思われるのである。 言いかえれば、法相宗であればこそ道成寺と結びつくことが出来たのだと考えられるのである。 法相宗とは、南都六宗の一つであり、唯識宗などともいわれ、唐の玄奘が印度より伝え我国にも広まった宗派である。 その我国に初めて法相宗を伝えた人物が、「道照大僧都」である。 道昭とも書くという。 道成寺のDOUZYOの音と、道照大僧都のDOUSHYOの音に、共通する点があると思うのは早計であろうか。 道照大僧都は、629年、河内国丹比郡に生まれ、早くから出家して奈良七大寺の一つ元興寺に住み、 俗姓を丹とも船連とも言う。 留学僧として、孝徳天皇御宇に、吉子長丹吉子駒等と伴に653年入唐し、661年帰朝している。 このことは、『今昔物語集』に収められた「天智天皇に召されて宣旨を承り、 震旦へ渡る」と言う話と十年程の食い違いを見るが、 帰朝して来た時は、天智天皇の御宇であった。 (『日本国現報善悪霊異記』『今昔物語集』『日本史小辞典』『日本史資料集』等に拠る)。 この道照大僧都と言う人物は、徳の大きい信望の厚い人物であったようであり、広く宮中にも市井にも慕われ、 よく民利を尽した人物であったと思われる。 記録に拠れは、晩年諸国を巡歴した折に、井戸を掘り、架橋をなし、造船を教えたとある。 また、文武天皇御宇の700年72才で亡くなり、我が国で記録に残る「火葬された最初の人物」と伝えられる。 彼の弟子に行基などが育っていることなどから、この僧の人柄も計れると思う。 ところで熊野地方、特に熊野浦と呼ばれる地方は、太古より捕鯨などが盛んであったようである。 「万葉集」の歌などにも、熊野舟の名が見られる。 吉田東伍著初版『大日本地名辞書』熊野浦の項に依れば、「熊野舟は古より其名ありて、一種の船制をなししごとし。 日本紀神代巻、熊野諸手船…中略……さらばその様にならひて造れる船を何国にても熊野舟とぞいいけむ)。 道照大僧都が、その俗姓の船連の名のごとくに造船を学び伝えたとすれば、 必然的なこととして「熊野浦地方」を訪れたことは推測出来るだろう。 そしてその時に、矢田庄土生村の将来道成寺となる建物と何らかの関わりが生まれたのではないかと考えられるのである。 道照大僧都は、いったい道成寺といかなる関わりがあったのであろうか。 先ず、仏教寺院に変身する以前の道成寺について、どのような建物であったのか考察して見たい。 熊野地方は、熊野三社そのものが修験道の神社であることを見ても分る通り、特に古えから修験道の盛んな所である。 修験道とは、道教的思想と真言の法と古代日本山岳信仰とが結びついて完成されたものと言われる(『広辞林』等に拠る)。 しかし、それは修験道として一つに体系的に包含されてから後のことであって、文武天皇御宇前後には、 巫術的なものや族神を主神として祭るような実に様々な宗教的色調を帯びていたと思われる。 奈良時代にも、道教的な信仰がかなり広域に渡って流布されていたようであり、 例えば『万葉集』巻二・巻十二・巻十四に見られる「梓弓…略…。」よりはじまる歌には、 梓弓と言う呪術的用法に用いる器具の招魂の機能が含まれて歌われている。 また、『続日本紀』天平元年の項に、次の様な一文が載せられている。 「勅すらく、内外文武百官及び天下の百姓異端を学習し、幻術を蓄積し厭魅呪咀、 百物を傷害するものあり、首は斬に従は流さる。山林に停住し、詐りて仏法を道とし、 自ら教化を作れば、伝習業を授け書符を封印し、薬を合せ、毒を造り、万方怪を作し、 勅業を違犯する者有らば、罪またかくのごとし。」(『日本史資料集』所収)。 この一文から、道教的な呪術信仰が、為政者側にとっては重大な政治的障害として 見られていたことがわかる。 また、為政者側としては、それに対して、「首は斬に」と言う文に見られるように、 相当激しい弾圧を加えて行ったと考えられる。 『今昔物語集』に見られるように、寺として扱われながらも仙術などを修得する道場として 竜門寺等が上げられているごとく 紀伊国には多くの道教的な道場があったと推測出来る。特に天皇に近く多武峰の両槻宮、 吉野宮滝なども道教的な場と考えられている。 これらの記述により、道成寺も法相宗に帰依する以前は道教的な信仰の道場であったと推測するわけである。 道成寺の地理的位置を考えに入れると、牟婁郡の西方・乾にあたるために、 熊野参詣人にとっては清め、禊の場となり、 熊野神人にとっては外界との黄泉比良坂の坂本に相当するものであったと思われ、 道成寺の道教的色合をより濃く感じるものである。 ではなぜ法相宗に帰依したのであろうか。 私は帰依しなければならなかった理由として次のことを仮説する。 文武天皇の御宇は、前述のごとく政治体制強化の時代であった。 当時の為政者にとっては道教的な信仰は被征服者の信仰であり、非服従の現れと思えたであろう。 そして、支配者側の信仰「仏教」を押しつけることによって、さらに精神的にも支配を強化していった事は考えられる。 道教的な信仰は、支配者側にとって排撃する格好の目標となったであろう。 特に、熊野参詣の道程に在る道成寺は、熊野聖域に手を出せない支配者にとってまっ先に 改めるべきものであったのではなかろうか。 政治的圧力を加えられて改宗に迫られた道成寺が、道成寺自身にとって少なくとも結びつきやすい 宗派を選んだことは納得出来ることである。 道成寺と道照大僧都との結びつきには、ある必然性を推測出来るだろう。 道照大僧都と道家との交わりは、「役の優婆塞との逸話」にも見られるごとく、 密接な関係を保っていたのではないかと思われる。 『日本国現報善悪霊異記』上巻第二十八、『今昔物語』巻十一第四、所収。 従って、道成寺は道照大僧都の手によって法相宗へ帰依し、 義淵・玄バウ等によって寺として確立して行ったのだと仮定する。 では何故に道照大僧都が開山として記録に残らなかったのか。 その理由として道成寺が新しい寺ではなく改宗寺であった事。 また彼が諸国巡歴を終えた後にすぐさま元興寺の傍に禅院を建て、隠遁してしまった事などから 何らかの政治的要因があったと考えられる。 道照と安珍、ともに火葬されている事は、ある種暗示的では有ります。 |
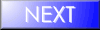 |
[次へ] |
| 【道成寺攷 参考資料一覧】 |
| TOPへもどる |
| 隠居部屋あれこれ |
| 伝統芸能 |