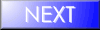
|
『あらためてスタニスラフスキー』 高山図南雄 (たかやま・となお) 演劇と教育 1995年No.475 1996年 No.479までの連載をまとめました。 前回に述べたように、モスクワ芸術座のヤルタ公演はスタニスラフスキーとチェーホフが互いに打ちとける大切な機会となった。 しかしその後も、さらに二人が親近感を抱くような出来事が起こった。 1902年芸術座のペテルブルグ巡演の間にクニッペルは腹膜炎で重態になり手術が必要といわれるほどだった。 一時は快方に向かったものの、巡演後さらに病状はぶりかえした。 チェーホフはクニッペルのベッドの脇に終日つきそって看病した(二人は1901年5月25日に結婚していた)。 スタニスラフスキーとリリナはクリミアに旅行中だったが戻ってくるとチェーホフと交替でクニッペルにつきそった。 「私が初めて私たちの関係に解放感を味わうことができるようになったのは、病室の隣で長い数日をアントン・パーヴロヴイチと一緒にいたときからだ。 あの日々は私たちをとても打ちとけさせ、アントン・パーヴロヴィチはときどき私の所へやってきては、自分がよく知っていることを親しげに聞いたりした。 たとえば、砒素の注射のしかたを私が知っていると言うと……私にすれば、手術の演技かなにかできると自慢してみせただけだが ……彼は自分に注射を打ってごらんと言ったりしたのだ。……」 チェーホフは自分の治療のために定期的に注射を尻に打っていた。それを当分の間はスタニスラフスキーが代わってやることになった。 ところがスタニスラフスキーは、やってはみたもののなかなか針を尻の皮膚に突き刺せない。針を新しいのにとりかえてやってはみたがうまくいかない。 その悪戦苦闘でチェーホフに相当の苦痛を与えたようだ。もっともチェーホフは短い咳をしただけだったが。 焦ったスタニスラフスキーは注射器を皮膚とは反対の方向に押し、注射をしたふりをして、空になるまで液をタオルにこぼした。 チェーホフはスタニスラフスキーに顔を向けると、親しげにほほえみながら「すばらしい」とひとこと言った。 だが、スタニスラフスキーはそれから二度と治療を頼まれなかった。 スタニスラフスキーは、クニッペルが十分回復したら、夫妻でリュビーモフカのスタニスラフスキーの別荘に移って療養するようにチェーホフにすすめた。 スタニスラフスキー夫妻はその頃外国旅行の予定があったのだ。 チェーホフはこの申し出を喜んで受けいれた。チェーホフが『桜の園』を思いついたのは、このリュビーモフカだった。 このように、たしかに二人は打ちとけていった。 しかしだからといって『かもめ』以来の戯曲をめぐる対立が解消したわけではない。 『桜の園』の稽古に入っても依然として未解決のままだった。 作品が芸術座に渡される以前の1903年9月15日付のリリナヘの手紙にあるように 「書かれた作品は、ドラマではなく喜劇だし、ほとんど笑劇と言ってもいいくらいです」という考えをずっと主張してきた。 それに対しスタニスラフスキーは作品を受けとったあと「これは、あなたが書かれた喜劇でもなければ、笑劇でもありません。 どれほどよりましな人生を求めて歩んでいても、土壇場には手放してしまうという悲劇です」と言っている。 舞台稽古に入ると、チェーホフは毛皮の外套に顎を埋め、咳きこみながら見守っていた。 そして気に入らないところはスタニスラフスキーに自分の考えを説明する。 だがスタニスラフスキーは頑固に作者の意見を退けた。 「ちょうど花々が開花しようとしていた時期に、作者がやってきて、なにもかも混乱させてしまうのだ」とある女優に嘆いている。 初日はチェーホフの誕生日にあわせて1904年の1月17日と決まった。誕生日の式典と公演が重なりあったために、必ずしも十分な成果とはいえなかった。 その後舞台は落ち着きをとり戻し、公演は数週間も延長されたがチェーホフはこの仕上がった舞台にも顔を見せなかった。 3月29日にクニッペルヘの手紙でこう言っている。 「きみたちときたら、十二分しか続かない幕を四十分もかけてやっている。 ぼくに言えるのはこれだけだ、つまりスタニスラフスキーは、ぼくの戯曲を台無しにしたということ。勝手にすればいいさ!だが彼を恨んではいない」 結局は『桜の園』が喜劇かドラマかという問題である。ドラマと見てとったのはスタニスラフスキーだけではなかった。 ゴーリキーは別としても、ダンチェンコや同時代の人々の多くがそうだったし、 二十年後にはスタニスラフスキーの後継者になるワフターンゴフもチェーホフの戯曲は本質的に悲劇そのものだと疑わなかった。 世間はチェーホフ劇を作者の意図通りには受け容れようとしなかったのだ。 文豪レフ・トルストイも、チェーホフの小説の方は高く評価しながらも劇作家としてのチェーホフを全く認めようとしなかった。 彼はチェーホフに面と向かって「作中の登場人物たちは、一体どこに君を導こうとしているのかね?寝そべった長椅子から、納戸までのいったりきたりじゃないか」と 戯曲に道徳の問題が提起されず、人生に対するなんの解決もみられないことを非難している。 その反面興味深いのは、小説『可愛い女』についてのトルストイの批評を見ると、 彼はチェーホフの作品の喜劇性の本質を的確に感じとっていたのではないかと思われる点がある。 「作者は語り出すと、呪おうとしたものを祝福してしまった。 わたし自身は少くとも、作品全体の、この素敵な、陽気な滑稽さにも関わらず、この驚くべき作品の、ある箇所には涙なしに読むことはできない」 チェーホフは同じ時代の無力な「余計者」たちを冷静に凝視しながらも、それらの人物たちに並々ならぬ愛情をこめて描いている。 その結果「ある箇所には涙なしで読むことはできない」とトルストイに言わしめたのではなかろうか。 多数の人々が悲劇と受け取った『桜の園』の喜劇性についても同じような見方ができると思われる。 『桜の園』やその他の戯曲が悲劇と受け取られることはチェーホフにとって甚だ不本意なことだった。 「ぼくは生活をあるがままに描く。しかしその先は……鞭で打たれたって、なにもない」とスヴォーリンヘの手紙で言っているように、 「よりよき未来に対する希望などということで自分をたぶらかそうとも思っていな」かったのだ。 ましてやトルストイやドストエフスキーのように「神」とか「死後の生活」「人類の幸福」といった「目的主義にひたされる」ことを嫌った。 「……神だとか、厭世観だのという問題を解決するのは、文学者の任務ではないと私は思います。 文学者の仕事は、かくかくの人が、かくかくの情況の下に、神または、厭世観について、かく語り、かく考えたということを提示するだけに止まります」 というのがチェーホフの考えだった。 人生に対して、希望を持つことなく、また絶望することもなく、刻々に生きるという、いわば、甚だ実存主義的な人生観をチェーホフの中に見ることができる。 そしてチェーホフ劇の中の人物たちは、トレープレフ(『かもめ』)であれ、ワーニャ(『ワーニャ伯父さん』)であれ、またマーシャ(『三人姉妹』)やロパーヒン(『桜の園』)であれ、 「憂うつな」時代の状況の中にあっても「刻々に生き」ているのではないか。 ところでスタニスラフスキーは人も知る熱心なトルストイ・ファンである。 だからチェーホフのように、主観とか客観という以前に、人が今ここに存在する、という認識はもちづらかったにちがいない。 それでも彼は生活実感と稽古場の試行錯誤を通してチェーホフの思想をしだいに理解していった。 一例をあげると『三人姉妹』の稽古が行き詰まり、全員が五里霧中になったことがあった。 「これから述べようとする興味ある事件は、ちょうどこうした悩ましい稽古中のことであった。 みんなは、あちこちの隅に坐ってはしょんぼりと黙りこくっていた。 電燈が二つ、三つ、ぼんやり照らしていた。われわれは薄闇の中に坐っていたのだった。 心臓は不安と絶望とでドキドキ鳴っていた。誰かが神経質にベンチを引っ掻きだした。ねずみがカリカリかじるような物音だった。 と、なぜか、この物音は自宅のかまどを連想させた。私は心が暖かくなり、本当に生活というものが感知され、直観が働きだした。 あるいは、ねずみのかじるような響が、暗闇と孤立無援の状態に結びついて、私の生活の中で自分にもわからない何かの意味を、いつの間にか持っていたのかもしれない。 誰が、創作上の超意識の道を決めうるであろう!私は、突然、舞台が楽しくなった。 チェーホフの人物たちが生きてきた。わかってみると、これらの人物たちは、決して自分に憂愁の気を帯びているのではなく、 むしろ反対に、陽気さ、笑い、勇敢さを求めているのだった。 凍えるどころか生きたがっているのだった。チェーホフの主人公たちに対する態度は、これでなくてはいけない、と私は感じた。 これが私を元気づけた。そして、どうすべきかということが、直観的にわかったのだった。」 スタニスラフスキーは、ロシア的「憂うつさ」の中にあっても人々は「凍えるどころか生きたがっている」ということを発見した。 そしてこれこそチェーホフ劇をとらえる鍵ではなかろうか。 チェーホフは多くの部分でスタニスラフスキーのビジョンを認め、稽古にも出席し、数々の書き直しにも協力した。 しかし芸術座の舞台への不満は最後まで消えなかった。その後、芸術座のチェーホフ劇はどのような変化を見せただろうか。 一例として、一九二三年アメリカで上演されたときの様子をニューヨーク・プレス紙にみよう。それによると、 批評家たちの多くはロシア語がわからなかったにもかかわらず、その大多数はこの作品のもつおかしさが実にはっきりと伝わってきて、 理解するのに言葉はいらなかったと口々に語っていたと報じている。 劇評家ヘイウッド・ブラウンによると「この劇団は、これほど繊細でしかも厳しい優しさをもつ喜劇を、 見事に創り出しているのに、全くといっていいほど無理なところがない」と述べている。 こうしたことから推しても、スタニスラフスキーは長い年月をかけながらチェーホフヘの道を辿りつづけたのだ。 この時代の他のどのような戯曲にもまして、チェーホフ劇は古い紋切型の演技や慣習化した演出の排除を要求してやまない。 このことが、サルヴィー二やミハイル・シチェープキンから得た教訓と結びついて、スタニスラフスキーの演技観を発展させる跳躍台となったのである。 シェイクスピアは『お気に召すまま』の中で、「全世界が一つの舞台、そこでは男女を問わぬ、人間はすべて役者に過ぎない、 それぞれ出があり、引込みあり、しかも一人一人が生涯に色々な役を演じ分けるのだ」(福田恆存訳)と言っている。 これは世代から世代へとうけ継がれ、果てしなく繰り返されてゆく「人間喜劇」を見つめるシェイクスピアの眼である。 思うに、チェーホフもまたシェイクスピアが見た同じ「人間喜劇」の舞台を見つめていたのではなかろうか。 確かに彼が描いたのは1880年代という限られた時代の中で、しかも限られた登場時間をもってひたすら生きつづけた人間たちだった。 視点をそこだけに絞ればチェーホフ劇はドラマであり悲劇であると言えるだろう。 だがここで視点をひろげて木下順二の言葉を借りれば「しばしば『おれの気持をそのまましゃべっているじゃないか』と思わせてくれるということ、 さらにその『おれの気持』をただその気持の範囲内でなぞってくれるというのではなく、もう一つ行きとどいて、 かつそこからもう一つの想像力を拡げて考えてみることが可能なように書かれているということ」 (『ワーニャ伯父さん』のカタルシス序説)のなかに時代性を越えた展望の可能性を感じとれるのだ。 つまり悲劇か喜劇かという二者択一の固定的な視点からではなく、時間的な流れの中で悲劇が喜劇となり、 喜劇が悲劇と変わってゆく可能性を孕むがゆえに喜劇的であるという視点が必要であろう。 下村正夫は「喜劇・『桜の園』の構造」のなかでこう述べている。 「……打ち克ちがたい時の流れと有限な実存とのあいだの緊張、そこに生れる、ただ笑っているだけでは済まされない人間喜劇…… つまり観客に究極のところ襲いかかってくるのは、戯曲に登場してくる群像たちが、 実は自分自身の実存を問うているのではないかという喜劇的〈怖れ〉を観る者に呼び醒ますような性質のコメディそれが『桜の園』であると言えるであろう。」 たしかに「有限な実存」としてのロパーヒンは、得意の絶頂であり、まさに「噴火山上に乱舞す」といえるだろう。 しかしひとたび世代が変わると、「桜の園」の持ち主だったガーエフ一家同様、凋落の渕に沈むであろうことを暗示している。 これはまさに「人間喜劇」にほかならない。かつてヤン・コットはシェイクスピアを「われらが同時代人」と呼んだ。 それと同じ意味においてチェーホフもまた「われらが同時代人」と言うことができるだろう。 チェーホフは芸術座への不満を墓場まで持って行った。にもかかわらずスタニスラフスキーや芸術座に対しては限りなく寛容だった。 それはなぜだろうか。一つには彼の公平さ、つまり曇りなき眼をもって芸術座のすぐれた面をも決して見落とさなかったということであろう。 1902年10月彼はヤルタからモスクワヘやってきて、『ワーニャ伯父さん』と『三人姉妹』を再度観劇している。 初演の時には色々問題を感じていたのだが、今回は演技に関する限り非の打ちどころがない、というのがそのときの彼の印象だった。 また同じ時、芸術座でやっている『どん底』の稽古を見たときも、その舞台装置の簡潔さが非常に気に入っていた。 つまり彼は常に是々非々を貫いて生きていた。親友のスヴォーリンに対しても、トルストイに対してもそうだった。 芸術座に対してもその原則は変わらなかった。認めるべきは率直にこれをうけいれたのだ。 第二の理由としては、「文学」としての彼の戯曲がスタニスラフスキーと芸術座によって「演劇化」されることの意味を十分に理解していたことがあげられる。 つまり「文学」と「演劇」という二つのジャンルの間の決定的な相違についての認識である。 「文学」はたとえその時代の読者に理解されなくとも、十年後、百年後の読者を期待することができる。 文学者がそのような信念に立ったとき、それは勇気ある行動として尊敬されるだろう。 しかし幕が下りた瞬間に消滅する「演劇」においてはそのようなことが成り立つだろうか。 「演劇」を支え、受けとめてくれるのはその時の目の前にいる観衆だけである。いったん芝居が終わると、あとに残るのは"Only Memories"だ。 もし演劇人が「いまの観客には期待しない。十年、百年後の観客はわかってくれるだろう」と考えたとすれば、それこそまさに演劇の自殺行為といえるだろう。 こうした、演劇が本来かかえている宿命的矛盾について、作家であると同時に演劇人であるチェーホフにはよく分かっていたにちがいない。 おそらくチェーホフは時代的状況や制約をわきまえつつも、「自分の真実の演劇」に一歩でも近づけるためにベストをつくしたのだ。 私はチェーホフの寛容さをこのように考えている。 スタニスラフスキーが、仕事と生活の両面においてチェーホフとかかわりをもったのはわずかに六年間だった。 しかしこの体験が彼の晩年までの芸術に決定的な影響を与えることになった。 彼はチェーホフから人間を一つの「人間的自然」として認識することを学んだ。 このことから彼は、それまでのロシアに支配的だったへーゲル流の形而上学的人間像と決別し、「行動」の場において人間をとらえ直す道を選んだ。 それはとりもなおさず彼の「システム」への道であり、「独裁的」演出家から、「創造的」演出家への変身の道でもあった。 文中の著名人 コンスタンチン・スタニスラフスキー コンスタンチン・セルゲーヴィチ・スタニスラフスキーは、ロシア革命の前後を通して活動したロシア・ソ連の俳優で演出家。 本姓はアレクセーイェフ。ロシア演劇の代表的人物の一人。 彼が創り上げた俳優の教育法は、スタニスラフスキー・システムと呼ばれ世界に多大な影響を与えた。 生年: 1863年1月17日 出生地: ロシア モスクワ 没年:1938年8月7日, ロシア モスクワ レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ 帝政ロシアの小説家、思想家で、フョードル・ドストエフスキー、イワン・ツルゲーネフと並び、19世紀ロシア文学を代表する文豪。 英語では名はレオとされる。 代表作に『戦争と平和』『アンナ・カレーニナ』『復活』など。文学のみならず、政治・社会にも大きな影響を与えた。 生年: 1828年9月9日 没年:1910年11月20日 セルゲイ・ラフマニノフ セルゲイ・ヴァシリエヴィチ・ラフマニノフは、ロシア帝国出身の作曲家、ピアニスト、指揮者。 生年: 1873年4月1日 没年:1943年3月28日, アメリカ合衆国 カリフォルニア州 ビバリー・ヒルズ マクシム・ゴーリキー ロシアの小説家、劇作家。本名はアレクセイ・マクシーモヴィチ・ペシコフ 幼くして孤児となり、極貧の放浪生活を送るうちに革命運動に接近。 社会主義リアリズム文学の創始者として活躍した。社会の底辺の人々の生活苦を描いた戯曲『どん底』が代表作。 作品に、革命を予告したとされる散文詩『海燕の歌』、小説『母』など。 生年:1868年3月28日 没年:1936年6月18日 メーテンリンク 生年:1862年 没年:1949 モーリス・メーテルリンク ベルギーの劇作家,詩人。メーテルランクとも。ヘントに生まれ,のちパリに定住。 フランス象徴派(象徴主義)の影響を受けて詩作。劇作においては《マレーヌ姫》(1889年)が最初 。以後,ドビュッシーがオペラ化した《ペレアスとメリザンド》(1893年)や《モンナ・バンナ》(1902年), 《青い鳥》など,神秘的な内容を劇に具象化した多くの象徴劇を書いた。 《蜜蜂の生活》(1901年)などのエッセーも知られる。1911年ノーベル文学賞。 フセヴォロド・メイエルホリド ロシアの演出家・俳優。ロシアおよび革命後のソビエトにおいて、挑戦的ともいえる不断の演劇革新運動を展開した。 ロシア演劇・現代演劇における最高峰の一人である。 生年:1874年 没年:1940年 スターリンの大粛清で銃殺された ネミロビチ・ダンチェンコ 生年:1858年 没年:1943年 ロシア・ソ連邦の演劇人。劇場芸術改革の必要を痛感し,まず低俗な世相劇にふさわしい職人芸の役者ではなく, 高い文学的内容をもつ戯曲を形象化しうる俳優の養成を志して,モスクワ・フィルハーモニー学校のドラマ科を主宰した。 これがまもなくスタニスラフスキーとの出会いを生む機縁となり,1897年にモスクワ芸術座をスタニスラフスキーとともに創設した アレクセイ・スヴォーリン 生年:1834年 没年:1912年 ロシア帝国のジャーナリスト、出版人、演劇評論家である。農民出身。 1868年、新聞『ノーヴォエ・ヴレーミャ』を買収。1872年起業し出版社を設立。 サンクトペテルブルク・モスクワ・ハルキウ・オデッサ・サラトフに書店を開設、鉄道駅などに新聞販売拠点を広げていった。 岡倉士朗 おかくらしろう演出家。 生年:1909年(明治42年)9月24日東京生まれ。 没年:1959年(昭和34年)2月22日死去。49歳 1931年(昭和6)立教大学英文科卒業。在学中から新築地(つきじ)劇団に参加、『土』『綴方(つづりかた)教室』の演出で評価された。 40年退団したが、新築地劇団員とともに治安維持法違反で検挙。1943年東宝入社。 1947年(昭和22)ぶどうの会と民衆芸術劇場(のち劇団民芸)の創設に参画、両劇団の中心的演出家として活躍、 スタニスラフスキー・システムの定着に努力し、歌舞伎(かぶき)、新派、オペラなどの演出も手がけた。 木下(きのした)順二作『夕鶴(ゆうづる)』の演出で49年度毎日演劇賞受賞。 著作に「演出者の仕事」。 八田元夫 はったもとお 生年:1903年(明治36年)11月13日生まれ。 没年:1976年(昭和51年)9月17日死去。72歳。 新築地(つきじ)劇団にはいり,「浮標(ブイ)」などを演出。戦後は新協劇団を再建。 昭和34年下村正夫と劇団東演を結成,三好十郎の作品や自作「まだ今日のほうが!」などを演出した。 東京出身。東京帝大卒。著作に「演出論」など。 下村 正夫 しもむら まさお 生年:1913年(大正2年)8月23日出東京生まれ 没年:1977年(昭和52年)7月11日 経歴昭和20年東京芸術劇場に参加、昭和22年第1次劇団民芸文芸部員、NHK論説委員を経て昭和27年瓜生忠夫らと新演劇研究所を創立、 リアリズム演劇の実践研究者として活躍、野間宏作の「真空地帯」の演出で昭和28年度毎日演劇賞を受賞。 昭和34年八田元夫と東京演劇ゼミナールを設立、穂高稔の「飯場」、木下順二の「風浪」などを演出、好評を博した。 著書に「新劇」「転形のドラマトゥルギー」など。 学歴〔年〕京都帝大文学部哲学科美学専攻〔昭和15年〕卒 主な受賞名〔年〕毎日演劇賞〔昭和28年〕「真空地帯」 牧原 純 まきはら じゅん本名、島地 純(しまじ じゅん)。 生年1926年東京生まれ。 没年:2015年3月26日、呼吸不全のため88歳没。 東京外国語大学ロシア語学科卒。文化放送でラジオ・ドラマ演出など、放送関連の仕事をし、同局の編成局長や営業局長などを務める。 その後チェーホフ関係の翻訳を行う。 三島 雅夫 みしま まさお 生年1906年〈明治39年〉1月2日 没年:1973年〈昭和48年〉7月18日 日本の俳優。本名・長岡 正雄(ながおか まさお) 著者・・・・高山図南雄 たかやま となお 生年:1927年(昭和2年)3月31日 熊本県生まれ。 没年:2003年(平成15年)12月31日 没。 演出家 日本大学芸術学部教授。日本演劇教育連盟顧問。 花田清輝「爆裂弾記」、秋元松代「常陸坊海尊」、 宮本研「うしろ姿のしぐれてゆくか」などを演出。 著書に「芝居ばかりが芝居じゃない」 訳書に「スタニスラフスキーシステムの形成』(マガルシャック)などがある。 |
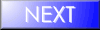 |
| TOPへもどる |
| 演劇ラボ |