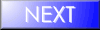
[◆身体動作のコミュニケーション]■目的…身体行動が言語行動を生み、言語行動が身体行動に再び影響を与えていく事を理解します。★課題 身体行動と言語行動のつながりを理解するための初歩の練習。 身体行動が言葉を生む場面の取材。 ・行動が言葉を産み出す瞬間を、生活の中から、観察と再現で事例採取していく。 例えば座って立ち上がる時、「よっこらしょ」など。 ・行動と言葉が矛盾する瞬間を、生活の中から、観察と再現で事例採取していく。 例えば、勉強すると言いながら、ゲームを続けているなど。 ●言葉と行為が矛盾しているとき、その人の真意、精神状態を知る鍵は、常に行為の側にあります。 日常的には、言語行動は身体行動に依存して、百パーセントそれに寄り掛かっているものです。 身体行動が言語行動を伴うというより、身体行動が言語の発声に先行しているのです。 言うべき相手を見るとか感じるとかしないうちに、つまり基本的な身体行動を果たさないうちは、 「こんにちは」という言葉さえ言わないものです。 言葉は、人間のコミュニケーションの最終的な表現方法です。 心にあふれた、あるがままを伝える事のみならず、全く反対の作為的なものさえも表現されることがあります。 ・舞台上や稽古場で、相手役に「百円貸してください」というのはそれほど難しいことではないかも知れない。 しかし、実際に駅や人通りの多い所で、「百円貸してください」というとすると、その困難さが理解されるでしょう。 周囲の大勢の人の中から、貸してくれそうな人物を捜し出し、話しかける切っ掛けを捜し、 近づいて自分に注意を向けさせ、好感をもってもらい、信用して貰うようにしなければならないのです。 このような予備的身体行動が整ってから、言葉が発声されるのですが、その時にもからだ全体、 目、表情、ポーズ、身振りすべてが頼み事を語りかけていなければならないのです。 ○注意点… 現実生活ではこれらの有機的過程は無意識に遂行されています。 ところが舞台では簡単に見落とされてしまいます。 そのためには行動の論理を繰り返し毎回改めて実現しなければなりません。 ■アイホールでは、生徒達の多くが社会人や学生であるため、実際の生活の中でも、言動と行動の違う人に 出会う機会が多かったようです。 それで言葉と行動が矛盾している事例を、自分達の生活の中から捜し出して、 それを実際に表現してもらうことにしました。 コントのようなケースが多いのですが、自分達の生活そのものを観察し、評価するいい事例となりました。 ★課題 自分より年上の人の注意を喚起する場合。年下の人の注意を喚起する場合。 上役の人の注意を喚起する場合。目下の者の注意を喚起する場合。見知らぬ人の場合。親しい人の場合。 例題 弟(妹)……にい(ねえ)ちゃん…… 兄(姉)うん? 弟(妹)今、何時? 兄(姉)二時すぎたところだよ 弟(妹)もう3時間だ……○○さん遅いね 兄(姉)心配しなくていいよ、早く○○ 弟(妹)うん…… (間) 弟(妹)……にい(ねえ)ちゃん…… 兄(姉)うん? 弟(妹)あれ、なんの音? (間) 兄(姉)風の音だよ ★課題 登場人物二人が、仲直りする練習。 ・身体行動のみで練習する。但し何故、言葉が使えないかを、納得できる状況設定(正当化)しておく。 (註:言葉を使わずに伝えたい意味の流れです。) 例題 話したいことがあるんだけれど、いい? だめよ、無駄よ どうして? 話したって何んにもなりゃしないわ あんなつまらないことで怒るのはやめて(くれ)よ ほっといて、むこうへ行って どの程度怒らせているのか、結末を決めずに様々な状況を楽しみましょう。 ○注意点… 話し言葉は、それを産んだ土台から分離すると、有機的であり得ないのです。 有機的な行為を作り出す沢山の要素の一つが、話し言葉という行為であることを理解しましょう。 ■アイホールでは、スタジオの中と外とか、教室、電車、銀行、博物館、図書館などが場面として選ばれ、 課題をプレゼンテーションする二人の生徒以外に、銀行の客や事務員などに扮する生徒達を巻き込んで行われました。 多くの場合、課題をプレゼンテーションする二人の生徒達がその場面設定や場面に必要な人々を演出していきました。 |
[◆ヴィジョンの流れ(フィルム)づくり]■目的…ヴィジョンとはなんでしょうか?ここでは俳優の内的な風景と考えてください。或る俳優は、「空に浮かぶ雲」という短い台詞だけで、夏の空の大きな入道雲、秋の空高く流れる鰯雲、 暗い恐ろしい雷雲などのイメージを、聞いている者に伝えることが出来ます。 これは、俳優の心に描かれた風景が、彼の言語行動…(声の色彩(明るさ・強さ)やその抑揚)によって、 私達の心の中にその風景を描いてくれたのです。 その心に描かれた風景を、ヴィジョンと呼びます。 ★課題 ヴィジョン伝達の簡単な事例 ・初めて大阪に来た人間に、JR大阪駅西口から阪急梅田駅までの道順を説明します。 (但し説明者が、聞いている者により早く駅へついて貰いたいという必然性を加える) ○注意点… ヴィジョンの正確さを求めます。おおよそ、だいたいというのはいけません。 ヴィジョンは、発声される言葉より充実し豊かでなければならないし、言葉の先を行くものです。 想像上の生活の末梢的な部分も、言葉では表現できない部分も、決して疎かにせず、それらが、 俳優の演技創造を助け、膨らませるものであることを信じなければなりません。 ★課題 ヴィジョンの変化による伝達 ・粗筋……『夜遅く、ある考えで頭が一杯のまま、私は人に逢いに急いで出掛けた。と突然、 よその家の門の内から、犬が吠えながら飛び掛かってきた。私はびっくりして懸命に犬を押さえようとしたが、 なかなかうまくいかなかった……』この粗筋に従って、相手役に言葉で説明しなさい。 ○注意点… 誰に話しているのか、何処で話しているのか何を考えていたのか、どんな道をどんな風に歩いていたのか、 大きい犬か小さな犬か等など、様々な状況を変えることで、その都度話の内容が違ってこなければならない。 ■アイホールでは、このヴィジョンの流れ(フィルム)づくりのためだけの練習は取り上げませんでした。 [オリエンテーションの確認]のときに、道を尋ねるという行為を基に、何時、誰が、誰に、何処で、どうやって、 何を、どうした、という項目の解答を組み立てながら、即興で表現することを求めて、 相互のヴィジョンの流れ(フィルム)づくりも求めました。 例えば、生徒達が作り出した、道に面した八百屋の店先で店員に、劇場を探しているOL二人が劇場までの道順を尋ねる、 という設定そのものが、相互にヴィジョンの明確なやり取りがなくてはならないものとなりました。 ■創造の現場で登場人物のヴィジョンの変化は、スーパーテーマとともに、俳優が観客に対して責任を持って表現して行く課題です。 登場人物のヴィジョンの変化は、相手役や状況の変化など、様々な要因で変わって行きます。 登場人物の心の風景を理解する上で、シーンやピース内のヴィジョンの変化を把握するのも、大切なことです。 例えば『罠』の幕開け、娘ベシーのヴィジョンは、「ブロードウェーの舞台から見た客席」かも知れない。 そのヴィジョンが、幕が下りる時にはどのように変わっているのだろう。 ヴィジョンのフィルムは、作品世界よりも濃い内容を持つかもしれない。 なぜなら俳優の想像力の作品だから。 |
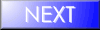 |
| TOPへもどる |
| 演劇ラボ |