赤いコードの、ウルトラ シリコーンパワープラグコード
プラグ&プラグコードの交換HKS イリジウム・プラグウルトラ シリコンパワープラグコード |
先日のクラッチ交換・LSD組み込みの時に、ディーラーにプラグコードの具合が悪いと指摘され、ようやく交換することになりました。交換したのは、MR2の購入当時からの交換したかった、イリジウム・プラグと、ウルトラ・プラグコードです。ノーマルからの変更で、イリジウム・プラグは、燃費が良くなり加速性もあがるというふれこみです。さすがに何馬力upとは宣伝されていませんが、低速トルクが上がるというユーザーレポートは有るようです。ウルトラのプラグコードは、説明書に3.8psのパワーアップなどと書かれています。なんだかマユツバに感じていますが、何分、プラグもコードも9年前の物で、劣化していて当然なので、ちょっと期待が持てます・・・
最終更新日 : 2001.2.24
赤いコードの、ウルトラ シリコーンパワープラグコード
永井電子のウルトラ シリコーンパワープラグコードです。付属する説明書には、コードを取り替えるだけで3.8psアップすると書かれています! 説明書のテスト結果によると、馬力は6000rpmで最大+3.8ps、最低なのは4000rpmで+1.27psとのことです。また、トルクは3500rpmで+0.61kg/m上がると書かれています。このデータはレジスター無しのプラグを使用した場合で、通常のプラグを使用した場合は少し低下するそうです。ちなみに、SW20/NA用は、1、2、3−4型と全部違うコードを使い、5型用はありません。何処が違うのか全く不明ですが、3−4型はコードをプラスチックのガイドに入れて保護するようです。1〜2型はむき出しのままで、エンジンも同じ型のハズなんですが、どっか違うのでしょうか? まあ、新品買うなら、購入時は年式を良く確認してから購入しましょう。
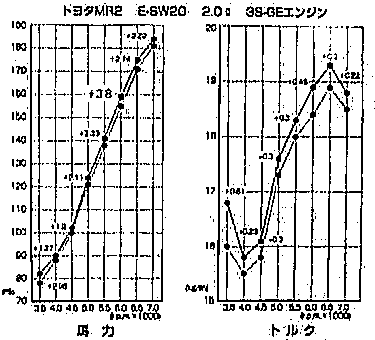
ウルトラの説明書より、馬力とトルクの向上のグラフ
初めから付いていたプラグコードには「YAZAKI 1992」と書かれています。やっぱり新車の時から交換されていないようです。ちょっと見た目には、プラグコード自体には、クラックとかリーク後は見られませんが、1番のプラグ周辺にリーク後がありました。コードには損傷が無いので、プラグ自体の絶縁不良だったのでしょうか? 純正のプラグコードは、カーボン線を使っているため、長さによって抵抗値が変わります。実測では、9.40K(1番)
7.03k(2番) 7.31k(3番) 5.04k(4番)、3.98k(coil)という結果でした。
ウルトラ プラグコードは、全てのコードが同じ抵抗になるように作られています。実測では、1.991k(1番)
2.044k 1.964k 1.994k(4番) 0.997k(coil) で、ほぼ全部2kに揃っていました。どの気筒でも同じ様に火花が飛ぶということなのでしょう。また、純正の半分以下の抵抗値です。もっとも、レジスタ付きプラグならば、それ自体に5kΩの抵抗が入っていますので、トータルでの抵抗値の軽減は50〜60%程度です。他社製のプラグコードには、抵抗値がほぼ0Ωというものもあります。抵抗値が少なければノイズをまき散らします。でも、プラグに5kΩ入っているのだから、0Ωでも問題なさそうに思えますね。ウルトラは、スポーツカーだけでなく、街乗り専用のドレスアップカーでも使われるので、このような中途半端な抵抗値でとどまっているのでしょう。
また、抵抗線に巻き線抵抗を使っているので安定性が高いとか、シリコンを使っているので絶縁性が高いという耐久性を唱っています。ちなみに、2番と3番は同じ長さなので、どっちがどっちだか分かりません。これは純正も同じなのですが、説明書によると、純正のコードと長さ比較をして、それに合わせた気筒に取り付けろと書かれています。なんとも面倒な話ですが、取り付けミスでトラブルを起こした時の逃げを作っているんでしょうか?
左:純正コード 右:ウルトラ
コードの取り付け
取り付けは、純正コードを1本ずつ外し、ウルトラと交換してゆきます。確かに、この方が誤りもありません。NAはインテークパイプがプラグの周りを通っているので、コードの取り替えは少しめんどうです。1番のコードなどは、4本全てのインテークの下をくぐらせてから取り付けることになります。エンジンルームを掃除した後ならいいのですが、汚れたままだと、折角の赤いコードも汚れてしまいます。汚れるだけならいいのですが、デスビキャップに取り付ける端子がむき出し状態ですので、このままでパイプの下をくぐらせると端子が汚れて接触不良を起こしそうです。そこで、コードの番数が書かれているタグの入ったビニールの小袋を端子に被せてパイプの下をくぐらせました。これなら、端子は汚れません。
2番と3番のコードは同じ長さなのですが、端子側の形状が違います。長さではなく、形状で区別することになります。ちなみに、L型の端子とI型の端子がありますが、L型の方には、抜け防止ようのキャップがありません。純正についているキャップを外しウルトラに付けて装着します。これも面倒な作業です。いかにコスト削減を狙っているかがうかがえます。キャップはウルトラに取り付けるまえに、よく拭いておきましょう。
2番のプラグホールは、パイプと少し干渉します。ですから、プラグキャップを少し斜めにして差し込むことになり、うまくプラグに刺さりません。プラグキャップのゴムの部分をパイプに押し当て変形させ、プラグと平行を保つようにして押し込みます。これがちょっと面倒です。あまり力を入れすぎると、コードを壊しそうです。気を付けて作業してください。1度差し込めれば、2度目からはコツも掴めるし上手く入るようになります。
最後は、デスビキャップからコイルまでのコードを取り付けます。このコードも止めキャップを流用しています。それに、コイル側が堅くて上手くささりません。力ずくで押し込みましたが、ちょっと気持ちが悪いです。
デズビ側の端子にはL型とI型の2種類がある |
ウルトラの端子の先にはバネが付いている |
ウルトラは端子の先にバネが付いています。きっと、振動や経年変化で接触不良になりにくくするためのように思われますが、逆に考えると、余計な機構のために、端子やバネが酸化した時に、接触抵抗を増やす原因にもなります。
HKSのイリジウム・プラグはデンソーのOEM
イリジウム・プラグには、デンソーの0.4mmタイプと、NGKの0.6mmタイプの2種類があります。デンソーは高性能を目指し、NGKは耐久性を目指しています。スポーツプラグなら、耐久性より性能重視ですから、デンソーの物を探しました。しかし、デンソーの製品を扱っている店は余りありません。しかし、HKSの製品はデンソーのOEMと聞き、さらにデンソーより安いので、これに決めました。ただ、既に、HKSの製品リストからは消えているので、在庫が無くなり次第、終わってしまう製品かと思います。ちなみに、TRDやブリッツも同じOEM製品を売っているようです。
デンソーのイリジウム・プラグは、純正相当の6番は、省エネタイプでギャップが狭くできています。逆にチューンアップ用の7番以降は、プラチナ・プラグのギャップと同じです。省エネより性能重視ですから、ギャップの広く、純正に最も近い7番相当を選択しました。それに、HKSは6番相当のプラグを出していません。番手は7番から始まっていて、7番はS35iという製品です。また、SW20のプラグはISO規格だそうです。S35とう「i」が付かないタイプも有りますので購入時には気を付けましょう。
ちょっと焼け気味の純正プラグ (ND PK20R-8) |
極細電極のイリジウム・プラグ (HKS S35i) |
ちょっと写真では分かりにくいのですが、純正プラグの電極の碍子部分と、接地電極(アーム)の部分は、白っぽい肌色で粉を噴いたように焼けています。金属のネジの部分はカーボンがこびりついている状態です。この状態だと、ちょっと焼け気味ながら正常な部類だそうです。右の写真はイリジウム・プラグで、電極が激細なのが良く分かります。接地電極の先の方も削ってあり、中に溝が掘ってあります。ちなみに、電極のギャップの長さは、純正が1mm、イリジウムが0.7mmでした、純正も本来は0.7mmほどなので、電極がヘタってギャップが広がったということなのでしょう。
プラグの取り外し
プラグの脱着には、枝の長いプラグレンチを容易します。私は、長さが35cmあるタイプにしました。ハンドルの片側にビニルテープを巻き付けておくと、何回回したらプラグが抜き差しできるか分かって便利です。それに、プラグの向きの管理も容易になります。
プラグを外すためには、プラグコードも外さねばなりません。コードはデスビキャップ側の端子を抜いて、ゆるめてからコードを外します。純正はプラグキャップの上がリング状になっていて、外しやすいのですが、挿しにくいのがたまにきずです。プラグホールは、キャップが密着して、中にゴミが入りにくいので結構綺麗です。でも、できれば、エアを吹いて中のゴミを飛ばしてからプラグを外した方が安全です。取り外しのためには、プラグレンチで12回ほど回します。磁石付きレンチなら、プラグも一緒に付いてくるので便利です。くれぐれもエンジンの中にゴミを落とさないように気を付けましょう。
プラグの取り付け
新品のプラグの取り付けは、プラグレンチにプラグを取り付け、軽くプラグを回していって、止まったところから、さらに1/4〜1/2程度締め込み取り付けます。ただ、漫然と1/2回せば良いと言う物ではなく、プラグの接地電極(アームになった部分)が、ガスの流れを妨げないように取り付けると良いようです。高速回転時に少しレスポンスが良くなる程度だそうですが、レースなどでは当然に行われている作業だそうです。
このためには、プラグの接地電極と、プラグレンチに貼ったビニルテープの向きが一致するようにレンチに取り付けます。これで、接地電極がどっちに向いているか一目瞭然です。そして、締め増しをするときに、ビニルテープがガスの流れを妨げない方向まで締め込みます。ガスはインテークからエギゾーストへ向かって流れます。ですから電極は車の左右方向に向けば良いことになります。この結果、1番は1/2回転締め増し、2〜3番は1/4回転、4番は1/2回転締め増しました。