絶望の言説ー『竹取翁物語』の物語る世界と物語世界
Ⅰ 絶望の『竹取物語』/『竹取物語』の絶望
『竹取物語』はあらゆる意味で絶望の言説である。たとえば、物語内容からして、どんなに公権力をふるっても、無力な人間達は、結局、かぐや姫を地上の論理に回収し得ず、天上界へと奪い取られてただ嘆く他はなかった。つまり、そうした人間世界への絶望感こそが物語の主題として描かれているのである。また、研究対象としても、伝本状況が悪く、古代文学研究のテクストと見ることには無理があって、おおよそ平安時代成立の言説としてこれを論じることは困難と言わねばならない。これは研究する側にとっては絶望的な状況にあるとも言えよう。さらには、作者もわからず、成立年代も漠然と九世紀末としかわからない、まったく謎だらけのテクストなのである。加えて、この物語はタイトルですら、この作品の存在が最もはやく刻印される『源氏物語』でさえ、蓬生巻の末摘花の愛読書としては「かぐや姫の物語の絵」とあり、絵合巻には梅壺の女御方から古物語の雄・「物語の出来始めの祖なる竹取の翁」の物語絵が出品されていて、すでに十一世紀初頭にはその題号すら揺れていたことが知られている。したがって、この物語は、まったく謎ばかりの言説であると言わねばならない。
しかしながら、この物語は私自身も幼少の時から親しみ、国文学月刊誌としては最も老舗である本誌の読者諸賢であるならば、漠然としてではあっても『桃太郎』や『一寸法師』とともにその話の断片は、誰しも脳裏に刻まれている物語であろう、いわば、我が国不滅の古典文学なのである。かくいう私の研究者としての始発もこの『竹取物語』の本文批判(テクスト・クリティーク)であったし①、その後の研究は、徐々に物語史全体へと拡散してはいるものの、自らの研究史の立脚点として、未だに伝本間の些細な本文異同すら諳んじていて、この物語に関する関心は倦むことがない。
そこで本稿では、「語彙の諸相」という本号のテーマに鑑み、この『竹取物語』の物語世界に関する研究史の上に、この物語世界を構築している、本文・物語る世界・ことば、という、従来では全く位相の異なる三つのエリアの研究をブリッヂし、統合する分析方法を模索をしつつ、最終的には古代物語のことばの世界へと限りなく隣接するためのアプローチとしたい。
Ⅱ 『竹取物語』本文史と古代世界との臨界線
では、私の研究史の立脚点である、『竹取物語』本文史からして、この物語の現存本文での古代世界への参入は可能なのであろうか。結論から言えば、かなり危うく絶望的ですらあるけれども、可能性は数パーセント残されている、と言ったところであるに過ぎない。 しかも、その数パーセントすら、それを証明するための外部徴証すらわずかで、私がかつて挙げた文献がほとんどすべてであるといった絶望的な状況にあると言ってよい。つまり、現存本文とは、「古本(こほん)」と命名され、『海道記』に和歌本文の断片が保存され、室町前期に遡る古筆切を擁しはするものの、古写本に恵まれない「古本系統」と②、それに対立する本文群を擁し、圧倒的な流布を誇る「流布本系統」とがあって③、より時代的先行性を有するという「古本系統」を支持するのが、私の一貫した立場である。もちろん私の一連の研究には厳しい批判・修正意見もあるが、私としては見解を変えるつもりはない④。すなわち、『竹取物語』の宗本本文(アーキタイプ)を再建するための優先順位は、A断簡本文B古本系統・新井本C流布本一類本…二類本…として、諸本の中より、最も善良な本文を基幹本文として、接ぎ当てする手続きであるとも言えよう。しかし、最も信頼すべき断簡からして全き本文ではなく、主に「目移り」などによる脱文、字形相似による本文転訛などが認められているわけであるから、当然これらの本文箇所を厳密に本文批判してゆく必要があるというのが現状であり、それゆえに、本稿のタイトルは、基幹となるべき本文ですら危ういテクストであるからこそ、「絶望の言説」と題したのである。
ところで、私の『竹取物語』の本文批判については、批判のみあって積極的に支持されたことのない、全く不幸な営みと言わざるを得ないものであるから、逆に私が批判する流布本が、なぜあまねく普及しているのかについての見解を簡略に言及しておく必要はあるだろう。
たとえば、最も親しまれていると言ってよい古活字十行甲本は、年記はないが慶長(1596~1611)の上木であり、流布本の源流となった本である。したがって、江戸時代の写本はかなりの本がこの本の写しであるといってよいほどの影響力を持っているが、奥付は「竹取物語秘本申請興行之者也」と見えるだけで素性の知られない明らかな校訂本文であり、中田剛直はこれを通行本系統の第三類に分類している⑤。地方の図書館に必ずといってよいほど所蔵されているいわゆる武家の必需品であった『絵入版本』もおなじ第三類であるから、その本文の通りの良さ、わかりやすさはそのあたりからも類推が可能であろう。それに加えじしんの架蔵となっているがゆえに、この版本本文が、『全集』『完訳日本の古典』『新編全集』の底本となったものかとも推測される。片桐氏によれば、「(古本・流布本)共に問題がある限り、圧倒的に多くの人に愛されてきた通行本(流布本)によりながら、それを徹底的に読み解いてゆくべきではないかと思うのである。〈完訳104頁()内は上原が注した〉」と、この物語の研究に関わる氏の指針を示している。しかし、こうした本文への姿勢では、厳密には古代世界へのアプローチを諦めているとしか言えず、古代物語の基本資料としては有効ではないこと、すでに自明なのである。では、第一類の『大系』『新大系』、第二類の『集成』の場合は実際どのようにその校訂本文を批評すべきなのであろうか。
第一類使用の校訂本文は、かつて最古の伝本とされていた武藤本(1592書写)そのものが本文として痛んでいるため、改訂しないと読めないのだが、叢書の性格上、底本本文をできるかぎり尊重するという編集の基本方針であろうか、本文はあまり校訂されていない。加えて、とくに『新大系』に顕著な姿勢であるが、脚注の解釈には田中大秀の『竹取翁物語解』の解釈と古本本文の文脈を紹介すると言った方法がとられている。これはすでに三谷栄一『評解』(1956)、松尾聡『全釈』(1961)にみられる解釈スタイルであった⑥。
では第二類での校訂本文はどのようなものであろうか。『集成本』はまだ叢書の本文として採用されていなかった二類本により、かつ、中田剛直の校本に未収録の高松宮家旧蔵の『竹物語』を底本としている。影印を見ても「あなあなをくしりかいはみまとひあへり」などという稚拙な書写にかかる独自本文が、きれいに訂されてはいるものの、野口元大による永年の蘊蓄と独自の知見によって、有名な語源譚のひとつ、「たまさかなる(底本・玉さかる)」のように、古本で改められたところもあるが、そうした例外の数カ所を除けば、比較的標準的な流布本本文となっていると言ってよかろう。
とすれば、本文史としてはわずかではあっても外部徴証から流布本のどの伝本にも先行すること、という一点において、本文として希有な価値を有する「古本」本文により、古代世界ならびに古代言説に、より近接できる数パーセントの可能性が残されていると私は考えるのである。
Ⅲ 物語る世界と物語世界の臨界線
では、こうした絶望を抱え込みながら、この物語世界と物語る世界との臨界線の具体例を示すこととしよう。
そこで、物語の時間構造と翁の年齢記述の齟齬というこの物語の基本問題について考えながら、こうした物語世界を枠取りする語源譚からこの物語の位相を考えてみよう。
以下、この物語の時間記述の本文を抄出する⑦。
・「翁、うれしくものたまふ物かな。翁、年七十にあまりぬ、けふあすともしらず。」〈求婚〉
・かやうにて、御心をたがひになぐさめ給ふほどに、みとせばかりありて、春のはじめより、かぐや姫、月をおも《し》ろうゐてみたるを見て〈八月十五夜〉
・「翁、ことし五十ばかりなりけれども、物おもふには、かた時になむ、おひになりにける」と見ゆ。
〈八月十五夜〉
・おきなこたへて申《す》、「かぐや姫をやしなひたてまつること、廿余年になりぬ。かた時とのたまふに、あやしく成《り》侍ぬ。又こと所に、かぐや姫と申《す》人ぞ、おはす覧」といふ。〈八月十五夜〉
『竹取物語』の時間構成は、個々の求婚譚そのものは一回完結型で、物語世界と物語る世界も緊密に呼応しているのだが、個々の物語を統一体としてとらえ返すと矛盾して括りきれなくなるという、摩訶不思議なテクストである。
そこで、この物語全体の時間の流れについてまず考えることとするが、翁の月の天人への返答に「二十余年」と語られてはいるものの、実際には杉野恵子の綿密な計算によって、都合「約十年」である⑧とする説が妥当であると東原伸明は認定している⑨。要するに、かぐや姫発見から垣間見三ヶ月+求婚者の名告りと脱落三年+難題物捜索三年+帝との交流三年+月への昇天八ヶ月=約十年という計算式の学説である。つまり、求婚譚は一斉に開始された「共時的な同時進行」であるという考え方ということになるであろう。しかし、高橋亨が指摘し⑩、奥津春雄が追認したように⑪、例えば「火鼠の皮衣」の段で「『この度は、かならずあはせむ』といひて、女〈=かぐや姫〉の、心にもおもひをり」とあって、はっきり「この度」と前段の求婚譚を受けており、さらに、五つの求婚譚すべてを受けて「御狩の御行」で帝が「おほくの人の身をいたづらになしてあはざなるかぐや姫」と述べてもいるところから、求婚譚は「事件そのものが配列順に継起して」行われ、それらの失敗を受けて帝が登場するという、二重構造があると考えるべきなのである。つまり、翁が天人に述べた「かぐや姫をやしなひたてまつること、廿余年になりぬ」という物語の実際の年月が、翁にも正確に把握されていたことになる。すなわち、求婚譚をのべ十五年とカウントすることで、前後六・七年を加えて二十余年にぴったりと附合するからである。言い換えれば、『竹取物語』 の年立は二十数年を基軸に作られねばならないことになるだろう。
こうした物語の大枠を規定した上で、この物語に極めて特徴的なテクストの位相(アスペクト)である竹取の翁の年齢について考えておこう。さきの東原論文では、八月十五夜時点の地の文「五十ばかり」を起点として、杉野論文の十年年立て説を支持し、かぐや姫発見時の翁の「四十歳という年齢が、青年(中年)と老年のひとつの境界に相当」する記号であるとし、さらにもうひとつの翁の年齢表記「七十」という記号を、『律令』のコードから「いちおう男性の範疇にあっても実質的には男ではなく『無性』に等しい存在」であると認定して、こうした翁の〈語り〉に「〈語り(=騙り)のディスクール〉によって閉じられ、差異化された 」『竹取物語』というテクストの位相を抉りだしたのである。同じく室伏信助も七十歳を会話の「大げさな表現」の修辞で「人生七十、古来稀」(杜甫詩)の引用とみている⑫。私も七十歳は翁じしんの発話による、娘に結婚を勧めるための誇張と見る説には賛同したい。ただし、年立二十年説とすれば翁は物語発端部では三十歳ということになるが、これは柳田国男に言う物語の「自由区域=説話者の空想の遊歩場」と見て、近代合理主義的な論断は謹しまねばならない⑬。というより私は、物語終末部時点での五十歳の翁は、物語世界では一貫して統一された人称として、冒頭部では年齢に先取りする形で「翁」と記されたものと見ておきたいのである。つまり、語り手の物語る〈現在の時間〉は、五つの語源譚を語る言説と、終末部の一文「いまだそのけぶり、くものなかへたちのぼるとぞ、いひつたへたる」だけなのである。言い換えれば、物語る世界の言説だけが、語り手の物語る〈現在の時間〉なのである。逆に言えば、「いまはむかし」から「ふしの山とはなづけゝる」までの〈…けり〉言説群が、線状的、継起的に出来事を語る「物語世界」のことと言うことになる。
加えて、「竹取翁」≠「老人」説の傍証として、翁の妻の表記を挙げておこう。それぞれ冒頭部の表記は古本「めのをんな」流布本「めの女」であって「媼」でない。ただし『全集』・『完訳』『集成』ではこれを改訂して「翁ー媼」と一貫してペアにしている(新旧『大系』は改訂せず、注で「媼のこと」とする)。しかし古本において、私に作成した新井本未校訂版の電子テキスト上での検索では、翁の妻としての「をんな」は、他に「八月十五夜」との二例で、これも表記は「をんなのいだきたるかぐや姫」とあり「媼」ではない。ただし、古本=新井本の場合は、「御狩の御行」の段に「かぐや姫」表記相互の目移りによる数行の明らかな脱文があって、古筆断簡本文と流布本諸本には「たけとりのいゑに、かしこまりてさうじいれてあ《へーえ》り。女に、ないしののたまふ(本文は断簡本文)」と見えているから、古本の宗本では翁の妻たる「をんな」は計三例だったということになる。
ついで、中田氏の労作・古活字十行甲本の索引で流布本本文を検索すると、「をんな(女)」と表記するのは一八例を数えるようである。うち、「男は女に会うことをす」のような抽象名詞としての「女」が三例。蓬莱山の仙「女」三例。竹取の家の「女ども」一例、かぐや姫を指すもの六例。翁の妻の「女」が以下の五例である〈諸本解釈による数値の異同あり〉。
①手にうち入れて、家へもちてきぬ。めの女にあづけてやしなはす。 一ウ
②竹とりの家に、かしこまりてしゃうじいれてあえり。女に、内侍のの給ふ。 三四オ
③女、内侍のもとに帰り出て「口おしく此のおさなき物はこはく侍る物にてたいめんすまじき」と申《す》。三五オ
④人はなくしてあきぬ。女いだきてゐたるかぐやひめとに出ぬ。えとゞむまじければ、 四八オ
⑤其後、翁・女、ちのなみだをながしてまどへどかひなし。五〇ウ
版本のみならず、武藤本も、表記はこの五例すべて漢字「女」に統一されている。うち、③の例は古本では「翁」であり、⑤には「女」がなく翁のみが「血の涙」を流している。つまり、古本で翁の「妻の女」が表記されるのは、「①めのをんな」「②女に、ないしののたまふ(本文は断簡本文)」「③をんなのいだきたるかぐや姫」とあって、新井本のみでは「をんな」とのみ見える。南波浩はこの表記について、「妻の女ー翁の妻女。諸註に、女を『媼』としてゐるが、女はをみな・をむな・をんな、媼はおみな・おむな・おうな・おんなである。ただし底本では諸本と同様かならずしもを・おの仮名遣の区別は厳密ではない。142頁『全書』補注」とあって、「を」に重要な意味性を指摘していたのである。加えて三谷『評解』には「妻の媼ー『妻』は和名抄に「白虎通云妻和名米」とあるように『め』のこと。…しかし『をうな』なら『をみな』(女)の音便で、若い女のこと。この『お』と『を』との区別は『おほ』(大)と『を』(小)との区別に関係があるといわれる。117頁」ともあって、本文の表記を信ずるならば、翁の妻は、老いのイメージが付与されていないことだけは確かであって、一部校訂本文に「媼」とするのは翁の呼称に規制された失考であるとさえ言えるのではあるまいか。こうした表記をもとに竹取の翁の夫婦像を再考してみると、古本ではむしろ「妻のをんな」不在の物語となっていることに気づかされるであろう。つまり、この物語の重要人物はやはり「竹取の翁」その人なのであった。目前の事態に対してあまりにもあからさまな虚言=誇張表現を簡単にしてしまう凡人が、一瞬手にした宝物を天人に奪還される物語の、猿回しの猿よろしく、あわれな喜劇役者としてこの翁は描かれているのであって、この翁が、老人である必然性は必ずしもないのである。つまり、物語冒頭部での「翁」なる呼称は、〈物語の現在時点〉で“「竹取の翁」と呼ばれていた男”の愛称と考えてもよいのではあるまいか。とすれば、翁から預けられたかぐや姫を養育し、天人から娘を守るためにのみ登場するだけの翁の妻は、物語上、終生「をんな」でよいのであって、老婆たる「媼」である必要はないのである。だからこの物語は「今は昔、竹取の翁といふ者ありけり」であって、「今は昔、竹取の翁といひける者、ありけり」とはないのである。
またこうした物語の手法は、かぐや姫の発見当時の大きさの認識のずれにも指摘できる。
・それをみれば、三寸ばかりなる人、いとうつくしうてゐたり。
・翁、「こはなでうことのたまふぞ。竹の中より、見つけきたりしかど、菜種のおほきさおはせしを、わがたけたちならぶまで、やしなひたてまつりたるわが子を、なに人か、む《か》へにこむ、まさにゆるさむや」といひて、「われこそしなめ」とて、なきのゝしること、いとたへがたげなり。
前者が冒頭の地の文と語り手の視線が融合する自由間接言説、後者が翁がかぐや姫の月への帰還を知った時の会話の発言である。山田俊雄は、この「なたね」は、今で言う「菜種」ではなく、罌粟(けし)粒程のことであり、芥子の実であると言うが⑭、これもまた、二十年も育てたかぐや姫じしんに去られることを嘆いた翁の極端な誇張表現となったものであり、このテクストもまた、先のテクストコードとともに、凡俗でケチな翁像を形成するのに参与している。つまり、『竹取の翁』の物語を〈物語る現在時点〉から捉え直し、再読してみると、求婚譚をはさんで冒頭と終末部を結ぶ翁の物語には、循環する〈矛盾の言説〉が二つ用意され、読書行為の度ごとに狡猾で滑稽な翁像が顕在化する構造が存在することになる⑮。
Ⅳ 臨界線としての〈○+ける〉と〈○+ぬる〉と〈○+たる〉
ところで、この物語の求婚譚は、三谷栄一が説くように、完全な机上の創作であって、物語の「自由区域」そのものであり、その構成も 二話+一話+二話のいわば三幅対で括られている構造であるとされている⑮。つまり、◎「奸計組」の皇子二人+◎金力に任せて偽物を掴まされる大臣+◎「愚鈍組」の納言二人、が「対蹠的に」描かれて、人間世界の欲望とその征服欲のありようを描いているわけである。しかも求婚者たちの名前(石作りの皇子・倉守(流布本ー持)の皇子・阿部の御主人・大納言大伴御行・中納言石上の麻呂足)と、求婚難題物・語源譚との有機的な連関も三谷論文の指摘する通りであるし、求婚者の官位も位階の順と登場順序が呼応して皇子→右大臣→大納言→中納言と並べられており、やはり「線状的、継起的に出来事を語る『物語世界』」そのものを端的に表象しているのである。
・はぢをすて、又いひけるをきゝてぞ、おもひなげきをば、『はぢをすつ』といひける。〈仏の御石の鉢〉
・としころは、『たまさかなる』とは、いひはじめける。〈蓬莱の玉の枝〉
◎(石作りの皇子・倉守(流布本ー持)の皇子)
・世中の人いひければ、これをきゝてぞ、とげなき事をば、『あえなし』とぞいひける。〈火鼠の皮衣〉
◎(右大臣阿部の御主人)
・「まなこ二に、すもゝのやうなるたまを、そろへていましたる」と、いひければ、「あ《なーる》たべがた」といひけるよりぞ、よにあらぬ事をば、『あなたへがた』と、いひはじめける。〈龍の首の玉〉
・これをきゝて、かぐや姫、〈すこしあはれ〉とおぼしける。それよりして、うれしきことをは、『かひあり』といひける。〈燕の子安貝〉
◎(大納言大伴御行・中納言石上の麻呂足)
さらに、こうした求婚譚そのものを、〈○…ける〉という語源譚で包み込むと言うことばのフレームは、〈あはれ〉という鍵語を発見する〈○…ぬる〉で承接され、「物語世界」と大団円の「物語る世界」とを連結させようとしているかのようである。つまり、最後の石(磯)上の中納言に、「かぐや姫、〈すこしあはれ〉とおぼしける」とある内話文は、かぐや姫に人間的な情愛の芽生えを示し、それがさらにこの物語のクライマックスの和歌、
「今はとてあまのはごろもきる時(流布本ーをり)ぞ君をあはれとおもひ出でぬる(流布本 ーける)」
に連接され、その五つの求婚譚を包み込む、帝との求婚譚というさらに大枠の「物語世界」と、それらをさらに包み込む「物語る〈○…たる〉の世界」とを連結させると言う、この物語の〈語り〉の支配構造が理解されてくるはずである。それは、どんなに卑俗で下品なことばを連発する狡猾な翁であっても⑯、かぐや姫にとっては親であり、その親や帝を愛する心を知ってしまったこのヒロインにとっては、月の都にはない、人を「あはれ」と思う心を育ててくれたという竹取の翁という男のアイロニーの物語の構造でもある。物語は、結局、八月十五夜には月に帰らねばならないかぐや姫と、かぐや姫という宝物を喪失する無力な地上の人間達の絶望の言説を、物語世界を徐々に囲い込みながら、「永遠の終わり」を物語るための準備は、五つの求婚譚の段階から着々と進められていたのである。
かくして、物語の「ふしの山」という最後の語源譚は〈○…たる〉で締めくくられる。特に流布本では「かの山」あたりの目移りからか、「ふしの山」の「富士」の語源の説明が不完全で、本文のより十全な「古本」の解釈で補われてきたことはよく知られてもいる。
・かのたてまつれるふじのくすりのつぼそへて、御つかひに給はす。ちよくしつかはす。月のいはかどゝいふ人をめして、かのするかの国にある、山のいたゞきへ、もてとつくべきよしおほせ給ふ。みねにてすべきやうを、をしへ給。文、ふしのくすりのつぼをならべて、火をつけてもやすべきよしをおほせたまふ。そのよしを、うけ給はりて、つはものども、あまたぐしてなむ、かの山へはのぼりける。そのふじのくすりを、やきてけるよりのちは(流布本ーナシ)、かの山の名をば、ふじの山とはなづけゝる。
いまだ、そのけぶり、くものなかへたちのぼるとぞ、いひつたへたる。
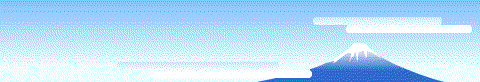
物語は、「ふじの山」で燃やされた文と不死薬の煙が、富士山の噴煙に点火リレーされて、しかも未だにその煙が立ちのぼっているという、〈物語の現在・〈○…たる〉〉を刻印することで、「循環する終わりの始まり」を語っている。つまり、その頃の富士山は、物語の冒頭部でももちろん噴煙の立ちのぼっているはずで、〈物語の現在〉は永遠に循環し続ける。であるからこそ、竹取翁が物語った〈物語世界のことば〉二つは、それぞれが一度だけの読みでは矛盾してその場かぎりの「誇張表現」にしかすぎないのだけれども、再読され、物語における意味が反芻されることによって、これら〈矛盾の言説〉にこそ、竹取の翁という人間の実像が如実に描き出され、〈人間そのものの真実の姿〉という、『絶望の言説』が生成されてくるはずである。
とすれば、今回の私のレポートは、「循環する『絶望の言説』の終わりの始り」として、読者諸賢にもう一度再読されることになるのであろうか。
注①私の『竹取物語』本文に関する研究は以下の通り。
・「〈伝後光厳院宸翰『竹取物語』小六半切〉本文に関する研究」(「日本文学研究」1991.1)
・「『海道記』『風葉和歌集』所引の『竹取物語』和歌本文の考察より鎌倉期流伝の物語古本系統の実在を論じ、流布本系統本文の批判に及ぶ」(「日本文学論集」1991.3)
・「『竹取物語』伝本の本文批判とその方法論的課題ー求婚譚の人称規定を例として」(「中古文学」1991.11)
・「〈伝後光厳院宸翰『竹取物語』小六半切〉本文に関する研究・続」(「ぐんしょ」1995.7)
②「古本」によるテキスト。
・南波浩『校異古本竹取物語』(ミネルバア書房・1953)底本・新井本
・吉川理吉『古本竹取物語校註解説』(龍谷大学国文学会出版部・1954)底本・三手文庫本
・南波浩『竹取物語・伊勢物語』(日本古典全書/朝日新聞社・1959)底本・新井本
・中田剛直『古本竹取物語』(大修館書店・1968)底本・新井本
・中川浩文『竹取物語の国語学的研究』(思文閣出版・1984)底本・三手文庫本・未完
③「流布本」による主なテキスト。
・阪倉篤義(日本古典文学大系/岩波書店・1957)底本・武藤本
・片桐洋一(日本古典文学全集/小学館・1972/完訳日本の古典・1983/新編・1996))底本・古活字十行本
・野口元大(新潮日本古典集成/新潮社・1984)底本・高松宮家本
・堀内秀晃(新日本古典文学大系/小学館・1997)底本・武藤本
④野口元大「竹取物語の本文」(「国文学」1993.4)・内田順子「偽玉の枝作りの工房ー『竹取物語』の本文と解釈」(「国語国文」1996.1)参照。
⑤中田剛直『竹取物語の研究校異篇・解説篇』(塙書房・1960)参照。
⑥三谷栄一『竹取物語評解』(有精堂・1956)、松尾聡『竹取物語全釈』(武蔵野書院1961)参照。
⑦本文は新井信之『竹取物語の研究本文篇』(図書出版株式会社・1944)の新井本により脱文・誤写を古筆断簡・流布本から補った電子テキストによる。(http://www.asahi-net.or.jp/~tu3s-uehr/take-txt.htm/)で実験的に公開中である。
⑧杉野恵子「竹取の翁と『二十余年』」(「平安文学研究」1985.12)参照。
⑨東原伸明「竹取物語の引用と差異ー〈話型〉のカタドリもしくは旧話型論批判」(「日本文学」1990.5)参照。
⑩高橋 亨「竹取物語論」『物語文芸の表現史』(名古屋大学出版会・1987.初出1976)参照。
⑪奥津春雄「『竹取物語』求婚譚の時間意識」(「まひる野」1984.9)参照。
⑫室伏信助「竹取物語の文体形成」『王朝物語史の研究』(角川書店・1996・初出1990)参照。
⑬柳田国男「竹取翁考」『昔話と文学』(創元社・1938 )『定本柳田国男集』第六巻所収参照。
⑭山田俊雄「『なたねの大さ』の論」山田孝雄・忠雄・俊雄『昭和校註竹取物語』(武蔵野書院 ・1953)参照。また、益田勝実がこの「菜種の大きさ」や「こがねある竹」に着目して「こ の物語の作者の生活感覚は貴族的よりも生産者的」であることを指摘している。「対談・フィクションの誕生」(「国文学」学灯社・1993.4)参照。
⑮三谷栄一『物語文学史論』(有精堂・1952)第四章参照。
⑯山口仲美「『竹取物語』『伊勢物語』の言葉」『平安朝の言葉と文体』(風間書房・1998・初出 1988)は『竹取物語』のことばの特性を以下の如く、「さが髪・尻・かなぐる、盗人・奴・ 殺す、青反吐・まる・ふる糞(荒々しいことば)、めらめら・きと(なまなましいことば)、しかるに・しかれども・たがひに(かたいことば)」に指摘し、泥臭さと漢文訓読語を交え ながらも「作り物語という新しい文学形態を作り上げた」と述べている。