 |
|
|
2008年6月18日・記
 |
|
|
 |
コンビニの帰り道、夏至の頃は午後の7時を過ぎてもやっぱり 明るいなあと思いながらふと空を見上げると、小野竹蕎の絵に出 て来そうな夕焼けの雲がたなびいてました。携帯のカメラでは無 理だろうなあと思いつつ撮ってみたところ、意外や意外いい色合 いに写っていました。 小野竹喬は日本画家の中で私の一番好きな画家で、特に一見稚 拙な形だけど、自分が幼い頃から見て来た様々な空を感じさせて くれる雲が好きで、一時期ためつすがめつ画集を眺めていました。 帰宅して早速、記憶していた絵を確かめたくて画集を繰って行 くとびっくりする程そっくりな雲でした。(この写真程ぼけてい ませんが・・)薄いピンクの綿菓子を無造作に千切って水色の空 にばら撒いたような彩色素描画で、写真から電線と半月を取り、 画面下に2〜3本のすっとした梢を描き足すと、まさしくこの竹 喬の空になるなあと何だか嬉しくなりました。 この絵のタイトルは「夕雲」で、それを見た時なんていい言葉 だろうと、今までこのタイトルを素通りして来た自分が悔しくな りました。 たった二文字なのに「夕雲」には夕方の空の色、気温、湿度、 音、それぞれの人の思い出など、全てを包み込むような膨らみが あり、言葉としてもとても新鮮で、竹喬が芭蕉の「奥の細道句抄 絵」を描いた動機、感性に初めて触れることが出来たように思え ました。 これから夕方の散歩で素敵な雲に出会ったら「竹喬の夕雲」と 呟きそうです。 |
|
|
 ●美術館のディスプレイウインドウ |
岡鹿之助展を観にブリジストン美術館へ行って来ました。 彼の絵は、同美術館の常設の部屋で左掲の写真の作品「雪 の発電所」を何回か観ただけで、いつかまとめて観てみたい と思いつつも何故かきちんと出会えずに来ました。 しかし第一展示室の最初の「信号台」という絵を観た瞬間、 これまで画集さえもまともに見なかった故にまっさらな状態 で彼の絵に対峙できる事を感謝したい気持ちになりました。 岡鹿乃助という画家はこんな凄い絵を描いていたのか・・・ と呆然としてしまい、しばらく動く事が出来ませんでした。 これ程までに自分自身が画面に溶け込んでしまいそうになった のは初めての感覚でした。 「信号台」は彼がパリに渡った翌年の1926年、28才の時の 作品で、画家・岡鹿之助誕生ともいうべく記念碑的な作品であ り、彼自身が「トリガステル描法」と名付け、後に、絵に迷い が生じた時に幾度となく立ち戻る原点である、という事をカタ ログの解説で知った時、この絵に感応した自分はまだ大丈夫か? (最近ちょっと制作意欲が・・・)と、励まされたような気持 ちになりました。 カタログと一緒に購入した「ひたすら造形のことばで」とい う彼の著書も初めて読みましたが、その中に「私は形をつくる ことに興味がある。それは色のマスによって形を定めてゆくや り方で始めるから、色が形に先行するともいえる。以下、略」 という言葉を見つけた時、まるで自分が絵をつくる際一番大事 にしている所と同じだ!(岡鹿之助という巨匠に対しておこが ましい言い方ですが・・)と増々彼の全てが自分の内部に沁入 ってくる嬉しさを感じました。 岡鹿之助の絵、思想は今後の私の人生のバイブルとなり ました。 |
|
|
 |
今年の4月、5月は雨がやたらと多くうんざりしていたが、 久し振りに気持ち良く晴れた日、密かに「ルノワールの庭」と 名付けている庭の側を通ったら、見事にバラを基調に色とりど りの花が咲き誇っていました。(写真よりはもっと華やかなん ですが・・・) この庭ではいつも老夫婦が揃って作務衣を着て、丹精を込めな がら作業をしていますが、時々華奢な奥さんがプロの庭師顔負け の力仕事をしているところに出くわすと、上品な雰囲気との落差 がカッコ良く、じっと眺めてしまいます。(決して、不審者じゃ ないですからね!) この家の門、玄関上部の壁面全体にも何種類かの蔦バラを組み 合わせて這わせてありますが、微妙に開花時期の違いを計算して あるせいか、長い間目を楽しませてくれます。 私の亡くなった父親も庭いじりが好きで、特に一重のオールド ローズを始め、様々な種類のバラを育てていました。 そんな事もあって、周りにはたくさん綺麗な庭がありますが、 特別にこの老夫婦の庭が好きなのかもしれません。 |
|
|
 |
今、私の住むマンションに大規模修繕工事が入ってい る。先日、三階の鉄柵部分が予想以上に疲弊しており、 住人を代表して視察をして欲しいとの要請を受け、外壁 に沿って組み立てられた足場を登る事になりました。 塗り直す内外壁のペンキの色を決めた後、成り行きの 軽い気持ちで引き受けましたが、最初に登る二階までの 地面から垂直に伸びる梯子を見た瞬間、恐怖と後悔の念 が過りました。男一匹、後には退けぬと意を決して登り 始めると、パイプと梯子の接合部に荷造り用のナイロン 製のテープ(薄手の縦に裂けるタイプ)を結わえている のが目に入りました。 接合の要がナイロンのテープなの?と驚きと不安を感 じましたが、これはきっと職人さん達が経験から割り出 した、日々の自分達の命を確かに預けられる一番丈夫な 素材なんだと、不思議な信頼感が胸に広がりました。 無事一段目の足場に立つ事が出来、三階まで冷や汗を かきながら辿り着きましたが、側面を覆う蚊帳より薄い ネットが安心感の強力な味方になる事に感心したり、ヘ ルメットの安全性の威力を(足許ばかりに気を捕られ、 二度程思いっきり頭をパイプ、足場にぶつけた)思い知 ったり、いろいろな発見をもらえた面白い体験でした。 でも、もう二度と登りたくない・・・ |
|
|
 |
時々側を通る小さな一軒家があっという間に、童話に その時、私も二十才の大学生でした・・・ |
|
|
 |
近所の空き地にタンポポの綿帽子がすっくという感じで生 *後日、友人から「ライオンの歯」の由来はタンポポ |
|
|
 |
日曜日の朝、床に掃除機をかけながらふと天井を見上げると、 壁(右下の三角形部分)との境目から放射状に影が出来てま した。一瞬、何の影か分らず形を探っていると植物の葉と茎 に見えて来ました。この部屋の植物は出窓に置いてある鉢植 類しかないと、そちらを見遣るとポトスと合致しました。 ポトスの位置から天井の影への角度を考えると、かなり下か らの光だなと思い、その角度で目を往復するとカーテンの僅 かな隙間から地面の反射光(4月にしてはかなり強い日差し でした)が差し込んで出来た影だという事が分かりました。 それにしても頭でいくら想像、計算しても、こんな位置にア ール・ヌーボー様式のステンドグラスのような影は創り出せ まいと感心しながら、ケータイで撮影しデータ保存などをし ている間に、影は消滅していました。 一瞬の光と影が織り成した幻想的なショー。 しばし、消え去ったあたりを見上げながら、一期一会・・・ なんていう言葉が胸を過って行きました。 |
|
|
 |
今日は私の○○回目の誕生日である。Happy
birthday to me.... おめでとう!の花束なんぞ望むべくもないので、先刻撮ったこの 花を自分に贈ろう。何か寂しいコラムの出だしになってしまった なあ・・・・・ さて、満開の桜は昨日の強風で大分花びらが飛ばされてしまった けれど、まだまだ迫力ある姿を見せています。そんな中、いつも の散歩コースからちょっと逸れた道を歩いていたら、玄関先の階 段に、花瓶の形をしたバスケットから溢れるように覗いている花 を見付けました。外の階段に置いてあるのだし、多分造花なんだ ろうと思いながら近寄って見ると、何と花瓶にきちんと活けられ た生花のバラでした。幽かに甘くいい匂いも漂っています。 石造り(大理石?)の階段と白い漆喰のような壁と黒い木の扉の コーナーに、一つだけオブジェのように置かれた様子はとても美 しく、昔、旅をした大好きなイタリアの空気感までをも思い出さ せてくれるようでした。 イタリアにはたくさんの楽しい思い出があり、久し振りにベロー ナのジャンニに手紙を出そうかな?などと、このコラムを書いて いる内に幸せな気分になって来ました。 今宵は、旨いイタリアンで自分を祝ってやるか! |
|
|
 |
コラムのページを始めてから、日々の散歩で何か面白い ネタはないかと、以前よりも上下前後左右キョロキョロ と見回すようになりました。掲載の写真の葉も、先週の 雨上がりの朝に散歩中の路上で見つけたものです。 風雨が強かったので、飛ばされた葉は雨粒の重さで地面 に押さえ続けられ、そのまま張り付いたのだろう。 カメラのファインダーでトリミングしてみると、きれい に葉脈を拡げた葉の周りの円い雨のシミと路面の質感が 相まって、まるで現代アートのような表情を持っていま した。こういう自然が何の作為もなく造った様の美しさ と力強さを前にすると、つくづく適わないなあと思って しまいます。 |
|
|
 満開のミモザ/2008年3月16日・撮影 何故か決まって思い出す本があります。未読の「ミモザ館の殺人事件」というアガサ・クリスティーか エラリー・クイーン作だと記憶していたミステリーです。掲載の写真の撮影後、今年こそ読んでみよう と近くの図書館へ行きました。書架で探しても検索パソコンでも見つからず、ガッカリして帰ろうとし ましたが、手ブラで戻るのも癪だし、何か一冊ミモザ関連の本を借りてみようと、再度、「ミモザ」で 検索しました。その中に「井伏鱒二全集第18巻」が目に止まり、井伏鱒二のミモザ絡みの小説なんか ちょっと面白いかな?と、中身も確認しないで借りて来たところ、エッセイ集でした。目次を繰って行 くと、このコラムのタイトルに借用した「古墳とミモザの環境で」がありました。作家「庄野潤三」の 作品の根底に関してのエッセイで、ミモザ絡みは僅かにこの一行「舎宅のまわりには、当時としてはめ ずらしいプラタナス、アカシヤ、ミモザの木が植えてあったという。」だけでした。肩透かしをくらっ たような欲求不満をなんとか解消したくて、「庄野潤三」という作家と出会ったのも何かの縁と、すぐ にまた図書館へ出掛けました。借りて来た本は、庄野潤三の他、三人の「第三の新人」世代の作家を併 録した全集で、久し振りに純文学に浸る時間を持ちました。ひょんな経緯で、読む事もなかっただろう 「庄野潤三」の小説に行き着いた事はとても面白く、今度は、木蓮(今、白木蓮も美しい)で検索して、 未知の作家と出会おうかな、と思っています。 *後日、詳しく調べたが「ミモザ館の殺人事件」なんていう本はこの世に存在していませんでした。 毎年、何故このタイトルを条件反射的に思い出したんだろう?・・・ |
|
|
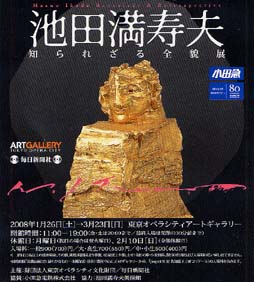 入場券・東京オペラシティアートギャラリー |
池田満寿夫の知られざる全貌展を観に、新宿の東京オペラ *陶芸の中に、花器として使ってみたいと誘惑に駆られる作品 |
|
|
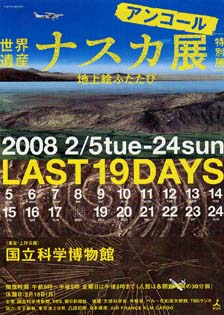 入場券・国立科学博物館 |
ナスカの地上絵をかなりの迫力でリアルに体験出来るとの 情報が入り、上野までナスカ展を観に行って来ました。 CGでナスカ平原を詳細に再現したものだが、それを知って なければ本当にセスナ機で上空から撮影したと錯覚する程、 良く出来てました。またこの展覧会で初めて、巨大な地上 絵の造り方が単純な数学(比例)の応用だったと言う事を 知りました。まず、造りたい場所の中央に人の背丈で俯瞰 出来る大きさの絵を描き(一筆書きの形)、その要所要所 にクイを打ち、そこから出来上がりの大きさに倍寸した距 離の所に新たなクイを打ち、それを繋いで行くと巨大な地 上絵になると言う訳である。成る程、宇宙人じゃなくても 造れるなあと、何か今まで色々想像してた謎のロマンが消 えてしまったような、ちょっと淋しい気分になりました。 また、地上絵の線にあたる所は、実際は砂地の50cm幅位の 浅い溝で、地にあたる所は平原に散在している拳大位の岩 石であると言う事も、現地の素材で会場に造られたサンプ ルで体験(溝の上を歩ける)して解りました。 さて、何の目的で巨大な地上絵は造られたのか? 神々への儀式の時に人々が歩く為の道説が、現在最有力と の事だが、ナスカの土地の過酷な自然や、土器の側面の絵 の由来や、首級の意味や、その他、色々知って行くと素直 に納得出来ました。 ナスカは年間降雨量ゼロの土地故に、2000年もの長い間 地上絵が破壊されずに残って来ましたが、最近雨が降り始 め、水害で近い将来消滅してしまう予測が出て来てます。 やはりナスカにも温暖化の影響が!・・・・・・・・ |
|
|
 |
某食品メーカーのレトルトカレーを「昔なつかし」のタイ トルに惹かれて買ってみました。 いつもレトルトカレーは、ちょっと値が高めの物でも食べ ている途中で食傷気味になり残してしまうのだが、これは 気が付いたら完食していました。 パッケージに表記の懐かしい赤い缶のカレー粉の匂いが食欲 をそそり、子供時代にタイムトリップさせたようです。 あの頃、母親が作ったり、給食に出たりしたカレーのルーは 小麦粉とカレー粉だけのシンプルなものだったけど、何か香 ばしくて旨かったなあと、空いた皿をしばし見つめていました。 「この白い皿も、給食の時はアルマイトの金属の皿だったし (必ずどこか凹んでた・・)、スプーンも匙(さじ)って言っ てたし、隣の席の(・・子)ちゃんはもう何人ぐらいの孫がい るんだろうか・・あの脱脂粉乳は・・」と際限なく思い出に耽 ってしまった午後でした。 |
|
|
 |
雪が降った9日の翌日、散歩の途中で出会った雪ダルマです。 道路の雪はすっかり溶け去りこの子(何故かこの子と言い たい・・)だけがケナ気な感じで踏ん張ってました。 石を置いた目鼻と小枝の口。携帯のレンズを向け画面を 覗いたら全体にグレーのシックな色調でまとまっていて 「オッ オシャレ!これこそ都会の雪ダルマ」とパシャリ と撮った次第です。 地面の一時停止の表示なんか大胆でモダンなカーぺットの 模様に見えませんか? |
| ←Column |