田辺氏は姓史(ふひと)、古来文筆を以て仕えた氏族で、氏(うじ)名は大阪府柏原市の田辺の地名に基づくという。大宝律令の撰定者として知られる首名(おびとな)・百枝(ももえ)はおそらく福麻呂の同族であろう。
天平十二年(740)の恭仁京遷都後から歌人としての活動が確かめられ、「寧樂故郷を悲しみ作る歌」(万葉集6-1047〜1049)、「久邇新京を讃ふる歌」(6-1050〜1058)などがある。難波遷都後には「難波宮にして作る歌」(6-1062〜1064)を作るなど、政情に応じて和歌を詠作しており、柿本人麻呂・山部赤人の流れを継承するいわゆる「宮廷歌人」的な立場にあったかと見られているが、橘諸兄の勢力退潮と呼応するかのように福麻呂の宮廷歌は見られなくなる。天平二十年(748)三月頃には、越中守として赴任していた大伴家持のもとを訪れ、家持の館での饗宴に参席した。この時の歌の題詞には肩書として「左大臣橘家之使者、造酒司令史」とあり、諸兄によって派遣されたことが判るが、用向きは諸説あり、確かではない。また制作年は不明であるが、「敏馬の浦を過ぐる時に作る歌」(6-1065〜1067)、「足柄坂を過ぎて死人を見て作る歌」(9-1800)、など地方での詠作も見られる。万葉集により『田辺福麻呂之歌集』と呼ばれる歌集があったことが知られる。万葉集に長短歌計四十四首を残している。ここにはそのうち十八首を抜萃した。
やすみしし 我が大君の 高敷かす 大和の国は
反歌二首
たちかはり古き都となりぬれば道の芝草長く生ひにけり(万6-1048)
【通釈】[長歌]我らの大君が高々とお治めになる日本の国は、皇祖神武天皇の御代から支配なさって来た国であるので、お生まれになる皇子が継ぎ継ぎに天下を治められるだろうと、千年万年の先まで見越してお定めになった奈良の都――この都は、陽炎のもえる春になれば、春日山の三笠の野辺に桜の花が咲き誇って木の下が暗くなるほどで、貌鳥はしきりに鳴き続ける。露が置く秋になれば、生駒山の飛火が岳に、萩の枝を体にからませ黄葉を散らして、牡鹿が妻を呼んで声を響かせる。山を見れば、山も見飽きることがないし、里を見れば、里も住み心地が良い。もろもろの大宮人たちがずっと思い続けていたことは、天と地が一つになる果てまで、無限に永遠に栄えてゆくだろうと、そう思っていた大宮であるのに、頼りにしていた奈良の都であるのに、ご一新の代であるので、大君のお導きのままに、春の花がやがて移ろうように都は新しい所へ移り、鳥の群が早朝飛び立つように人々は一斉に立ち去ってしまったので、大宮人たちが踏み均して通った道は、今や馬も行かず、人も行かないので、荒れてしまったことよ。
[反歌一]新旧交代して奈良は古い都となったので、道端の雑草が丈長く生い茂っているのだった。
[反歌二]馴れ親しんだ奈良の都が荒廃してゆくので、外に出て見るたびに嘆きがつのるのだ。
 |
【語釈】[長歌]◇やすみしし 「我が大君」の枕詞。「八隅を治める」、あるいは「心安く天下を治める」の意かという。◇皇祖の神の御代より 皇統の祖である神(神武天皇)の御代から。◇八百万 千年を兼ねて 千年も万年も先まで予定して。「八百万」は大きな数の例として言う。◇春日山 平城京東郊の山。◇桜花 木の暗隠り 桜がぎっしり咲いて木の下が暗く隠れる様を言う。◇貌鳥 ほととぎすとかと言うが、不詳。「かほ」は鳴き声であろうと言う。◇露霜の 「秋」の枕詞として用いる。◇生駒山 大阪府と奈良県の境をなす山。平城京の西方にあたり、東の春日山と対照させて取り上げている。◇飛火が岳 生駒山の一峰。飛火(烽火台)が置かれていた。◇しがらみ散らし 絡みつくように散らし。◇うちはへて ずっと長く。◇春花の うつろひ変り 春の花が移ろいゆくように、都が移り変わり。平城京から恭仁京(久邇京)への遷都を言う。◇群鳥の 「朝立ち」の枕詞。◇さす竹(だけ)の 「大宮人」の枕詞。「さす」は伸び出す意で、勢いよく生長する竹に繁栄の祝意が籠る。
【補記】天平十二年(740)十二月、聖武天皇は平城京より恭仁京(次の歌を参照)に遷都した。旧都がかつて栄え、その後荒廃した様を整然たる構成のうちに歌い上げている。
反歌二首
山高く川の瀬清し
【通釈】[長歌]現人神であられる我らの大君がお治めになる天下、大八島の内に、国は多くあるけれども、里はたくさんあるけれども、山が幾つも並ぶさまが結構な国であると、川が幾つも合流する里であると、山背の国の鹿背山の山あいに、宮殿の柱を堂々とお立てになって、高々とお治めになる布当の宮は、川が近いので瀬の音が清らかに聞える。山が近いので鳥の声が響く。秋になれば、山もとどろくばかりに牡鹿が妻を呼んで鳴き声を響かせ、春になれば、岡辺にぎっしり、岩の上に花が撓うほど咲いて、ああすばらしい、布当の原は。大変貴い、この大宮の地は。なるほどだからこそ、我らの大君は、いかにも大君らしく、臣下の言葉をお聞き入れになって、宮殿の場所をここにお定めになったらしいよ。
[反歌一]三香の原の布当の野辺は清らかなので、ここを大宮の所在地と定めたのだろうよ。
[反歌二]山が高く、川の瀬は清い。百代の後まで神々しくあるだろう、大宮の所在地は。
 |
【語釈】[題詞]◇久邇の新京 恭仁京とも。天平十二年(740)に新京となったが、同十六年に都は難波に遷され、結局十七年には平城京に戻された。
[長歌]◇現つ神 現実にあらわれている神。神々は普段は姿を隠しているものという考えが背景にある。◇川並の たち合ふ国 いくつもの川が合流する国。久邇新京は泉川(今の木津川)の南北に建設された。◇鹿背山 京都府木津川市の鹿背山。◇布当の宮 恭仁の宮の別名。
[反歌一]◇三香の原 京都府木津川市加茂町とその周辺の瓶原(みかのはら)盆地。
【補記】天平十二年(740)十二月、聖武天皇は恭仁京に遷都、同十五年には大極殿が完成する。久邇(恭仁)京については、家持アルバムの「恭仁京」も参照されたい。
【通釈】娘たちが績(う)んだ麻糸を懸けておくという桛(かせ)――その名に因む鹿背山は、時の移り行きで都となったことだ。
【語釈】◇続麻 つむいだ麻糸。
鹿背の山木立を繁み朝さらず来鳴き
【通釈】鹿背の山は木がぎっしり生えているので、毎朝毎朝やって来ては鳴き声を響かせる鶯の声よ。
狛山に鳴くほととぎす泉河渡りを遠みここに通はず(万6-1058)
【通釈】対岸の狛山で鳴く時鳥は、泉川の川幅があまりに広いので、渡ることができず、こちらへは通って来ない。
【主な派生歌】
五月雨はわたりをとほみ泉川こま山見えず雲ぞかかれる(藤原家隆)
泉河ははその梢見わたせばわたりを遠み紅葉しにけり(藤原信実)
泉河とほきわたりの月かげに声をつくしてなく時鳥(後宇多院[新千載])
いとどなほ渡りぞ遠き泉川ゆくへも見えぬ瀬々の夕霧(涌蓮)
春の日に、三香の原の都の
反歌二首
三香の原久邇の都は荒れにけり大宮人のうつろひぬれば(6-1060)
咲く花の色は変はらずももしきの大宮人ぞたちかはりける(6-1061)
【通釈】[長歌]三香の原の久邇の都は、山が高く、川の瀬が清らかなので、居心地が良いと、人は言うけれども、住み良いと、私は思うけれども、古さびた里であるので、あたり一帯を眺めても、人の往き来もなく、里を見れば、家も荒れている。ああ切ない。こんなものであったのか。神座(かみくら)の設けられた鹿背山の山々の間に咲く花は色美しく、たくさんの鳥の声は心に沁みて、いつまでも居着きたい、住み良い里が、こんな風に荒れていることが惜しまれることよ。
[反歌一]三香の原の久邇の都は荒廃してしまった。大宮人が他へ移ってしまったので。
[反歌二]咲いている花の色は変わらないが、大宮人は新しい都へ移ってしまってもう居ない。
 |
【語釈】[長歌]◇三香の原 既出。◇はしけやし 感嘆詞。「はしきやし」とも。いとしい、せつない。◇御諸つく 「みもろ」は神の降臨する所。祭壇等を設けた。「つく」は「築(つ)く」だろうという。
【補記】恭仁京遷都後まもない天平十六年(742)二月、都は唐突に難波へ遷され、さらに翌十七年正月には紫香楽遷都が宣される。ところがやがて紫香楽宮周辺で山火事が頻発し、また大地震が起こるなどして、結局同年五月、聖武天皇は平城京へ還御した。その後、うち捨てられ急速に荒廃した恭仁京のありさまを悲しんで詠んだのが上掲の長短歌であるという。
やすみしし 我が大君の あり
反歌二首
あり通ふ難波の宮は海近み
潮
【通釈】[長歌]我らの大君がいつもお通いになる難波の宮は、海に面していて、玉を拾う浜辺が近いので、朝には鳥が羽を振るわせるように波の音が騒ぎ、夕凪には船の楫の音が聞える。暁の寝覚に耳を澄ませれば、暗礁が引潮と共に現れる、その浦洲で千鳥が妻を呼んで鳴き、葦の生える岸辺では鶴が鳴き声を響かせる。見る人が語り草にすると、聞く人も見たくなる、この味経の宮は、いくら見ても飽きることがないことよ。
[反歌一]大君のいつも通われる難波宮は海が近いので、海人の娘たちの乗る船が見える。
[反歌二]潮が引いたので、葦の茂る岸辺に騒ぐ鶴のつれあいを呼ぶ声は、大宮も鳴り響くばかりだ。
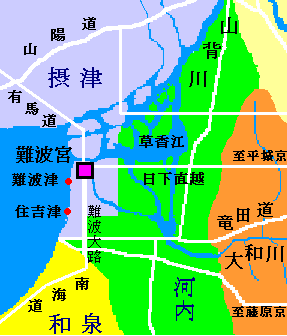 |
【語釈】[長歌]◇いさなとり 「海」の枕詞。「いさな」は鯨のことで、鯨のような大きな獲物が取れるところとして海を讃美する意が籠る。◇海片付きて 海が片方に面していて。◇朝羽振る 「羽振る」は、波が寄せる様を、鳥が羽を振る様に喩えて言う。◇海石 海中の岩。暗礁。◇御食向ふ 「味経」の枕詞。◇味経の宮 味経の原にある宮で、難波宮の別称。
[反歌二]◇白鶴 西本願寺本の訓は「あしたづ」。「白」を「百」の誤りとして「ももたづ」と訓む説もある。
【補記】天平十六年(744)閏一月、あるいは同十七年八月から九月にかけての聖武天皇の難波行幸に従っての作であろう。
足柄の坂を過ぐるに、
【通釈】屋敷の庭で育てた麻を引き抜いて干し、愛しい妻が織って着せてくれた白い着物の紐も解かないまま、一廻りの帯を三廻りに結ぶほど痩せ細って、辛い仕事に従事して務めを果たし、今すぐにも国に帰って、両親や妻を見ようと思いながら道を辿って行ったあなたは、東国の恐ろしい神の御坂で、やわらかな衣も寒々と、髪は乱れて、国を問うても国の名を告げず、家を問うても家の名も告げず、立派な男子が道を行くままにここに臥せっておられる。
【語釈】◇足柄の坂 駿河・相模国境の足柄峠。東海道の難所。◇小垣内 垣の内側。屋敷内。◇妹なね 死んだ男の妻。「なね」は肉親や恋人への愛称。◇畏きや 神の御坂 神の祟りが恐ろしい坂。◇和細布(にきたへ) やわらかい布。
天平二十一年春三月二十三日、左大臣橘家の使者、造酒司令史田辺史福麿を、
ほととぎす厭ふ時なしあやめ草かづらにせむ日こゆ鳴き渡れ(万18-4035)
【通釈】ほととぎすよ、おまえの声を厭う時などありはしない。しかし、菖蒲草を蔓鬘(かずら)にする日だけは、必ずやここを鳴いて渡ってくれよ。
【語釈】◇あやめ草 サトイモ科のショウブ。花の美しいアヤメ科のアヤメ・ハナショウブとは全く別種。邪気を祓う草として、五月の節句の蔓(髪飾り)などに用いた。
【補記】天平二十一年(749)三月二十三日、左大臣橘諸兄の使者として越中に赴き、国守大伴家持の館で饗応を受けた時に福麻呂が詠んだ四首のうち最後の作。時鳥の声はいつも待望されるが、とりわけ五月の節句にはこの館(家持の国守館)を通って鳴いてくれと呼びかけた。間近に迫った夏が主人家持にとって好き季節であるようにと予祝する心を籠めている。万葉集巻十の「霍公鳥 厭時無 菖蒲 蘰将為日 従此鳴度礼」(1955)と同一歌であり、題詞の「古詠を誦ひて」の「古詠」はこの歌を指すと見る説が一般的である。古歌に福麻呂自身のその時の心情を託したものであろう。
時に明日を
藤波の咲きゆく見ればほととぎす鳴くべき時に近づきにけり(万18-4042)
【通釈】藤波の咲き行くさまを見るにつけ、いよいよ時鳥の鳴く季節に近づいたのですねえ。
【語釈】◇藤波 風に揺れるさまが波打つように見えるので、藤の花房をこのように呼んだ。◇布勢水海 射水郡の越中国庁の近くにあった淡水湖。万葉集に詠まれたことから藤の名所として歌枕となる。今は富山県氷見市の田園に小さな池としてなごりを留めるのみ。
【補記】前歌と同じく天平二十一年三月二十三日の作。大伴家持らと翌日の布勢水海遊覧を約束した際の歌。実際景色を見て詠んだように作っている。
更新日:平成15年12月29日
最終更新日:平成21年04月22日