|
本章についての読者の感想文と質問は次の章 「K220. Q&A温室効果、読者の感想文と質問」 に掲載してある。 |
| トップページへ | 研究指針の目次 |
目次
219.1 まえがき
219.2 温室効果と大気・地表面温度
(1)地球平均の温度
(2)温室効果、大気1層モデル
(3)多層モデルと気温の鉛直分布
219.3 CO2濃度と地表面が受ける長波放射量
219.4 CO2濃度の増加と気候変化の原理
まとめ
付録
付録1 山本の放射図と利用方法
付録2 放射図の白図(W/m2 単位に書き換えた図)
付録3 地表面の熱収支計算
文献
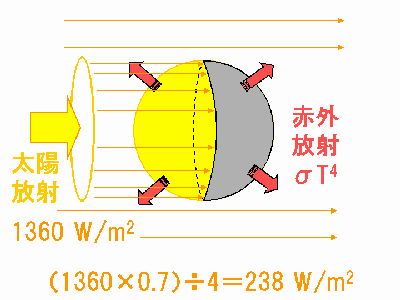
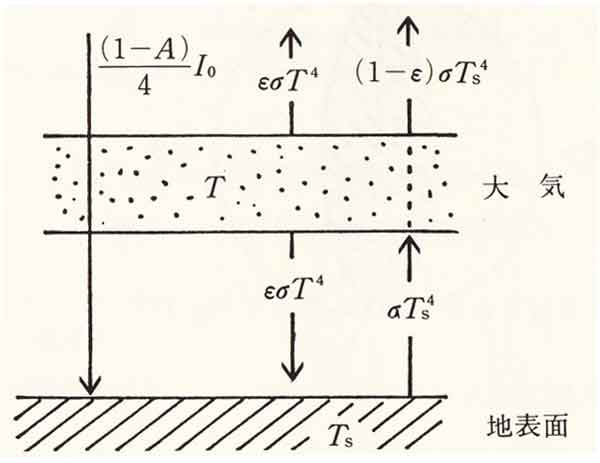
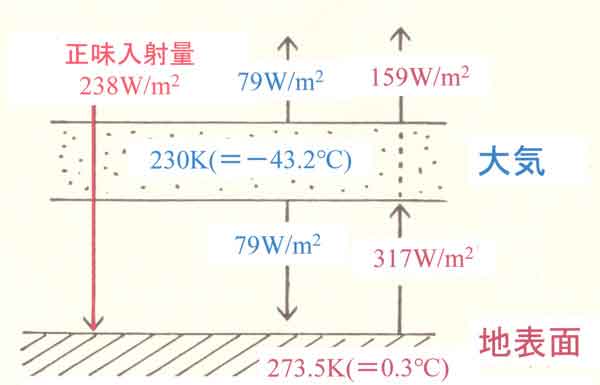
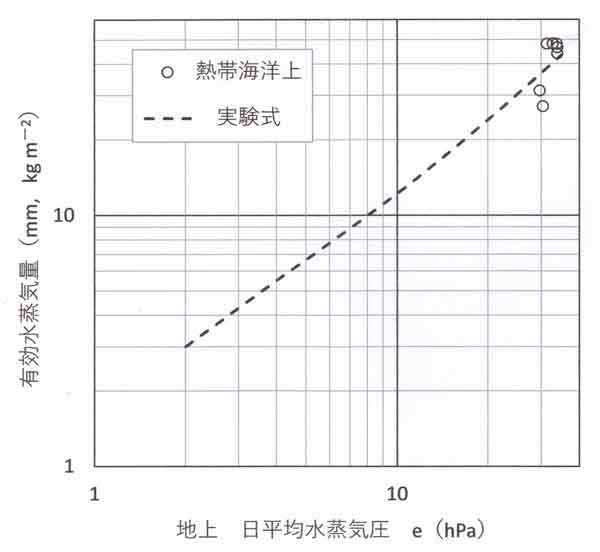
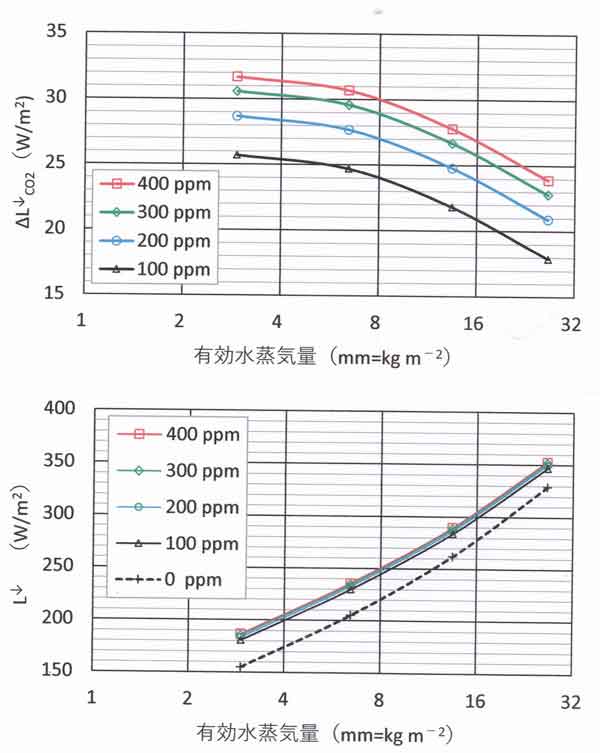
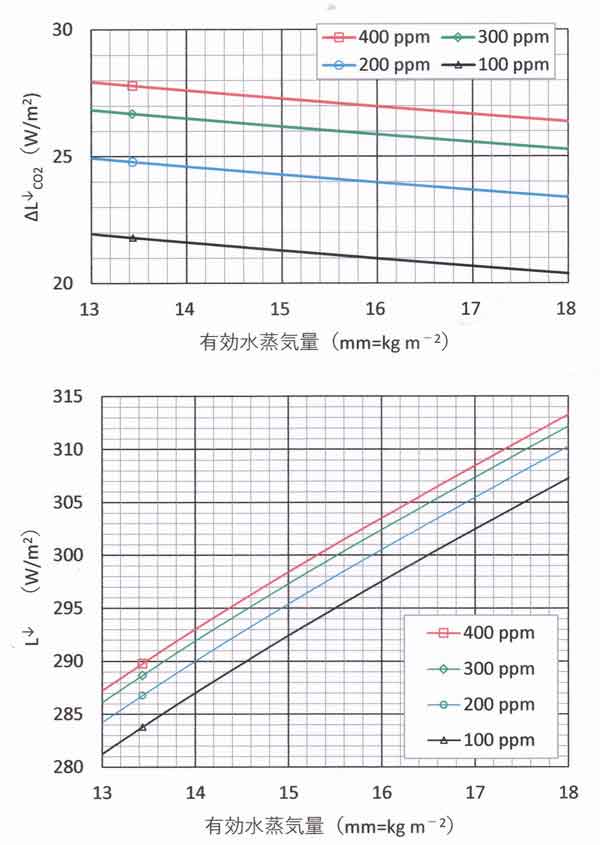
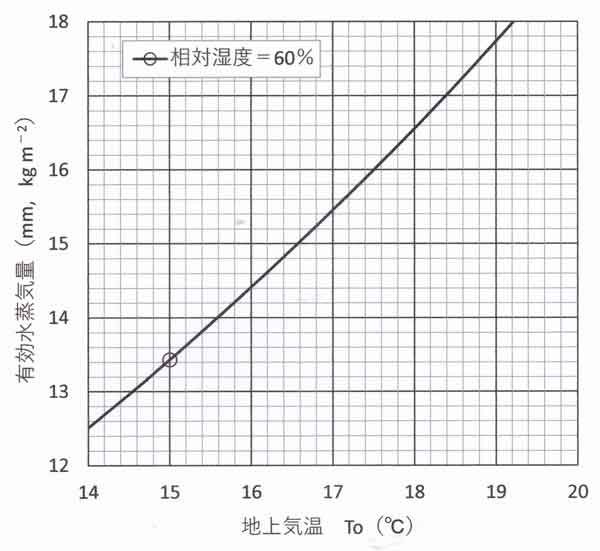
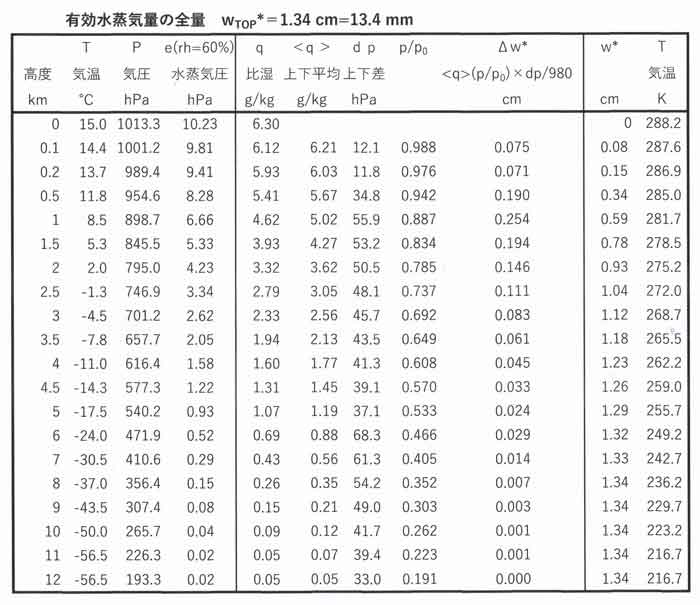
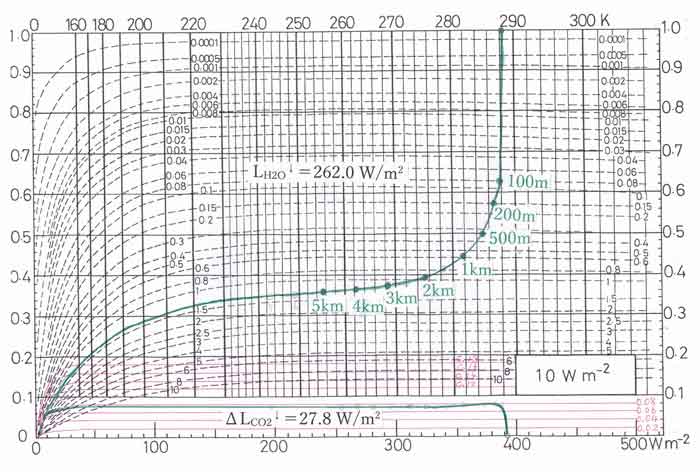
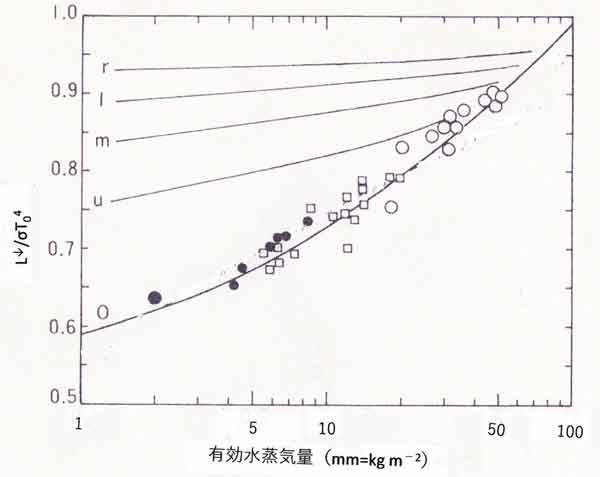
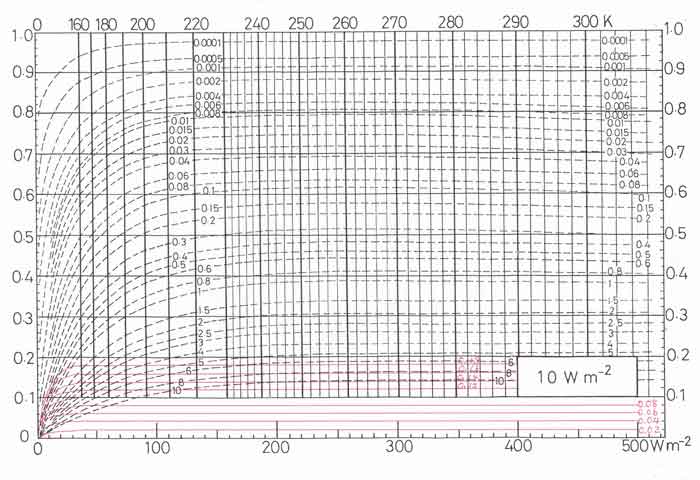
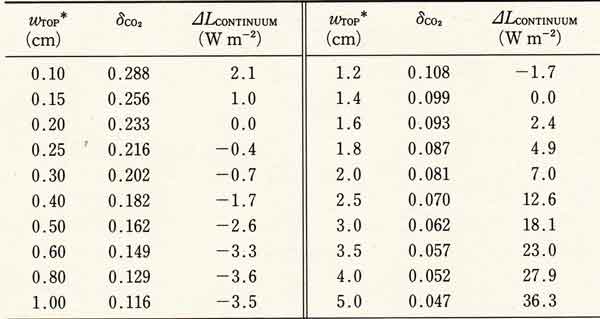
| トップページへ | 研究指針の目次 |