第127回 工房の 其処 と 此処 の 距離
「おっ、キノコが出たぞ!
1upのチャンスだぜ。」
「あっ、そ、そうだね。」
工房の食堂に、新しく大型液晶テレビが入ったのは、
先週の水曜日だ。
新しく出来た商店街のくじ引きで、くま女王さまが当てたのだ。
ただ、
工房の食堂にはアンテナの配線が来ていないため、もっぱらゲーム専用モニタになっていた。
「ね、ねぇ、甘栗くん。」
「う?」
「あのさ、甘栗くん。」
「なんだよ、よそ見しないでしっかりやれよ。」
「うん。 そうだけど。」
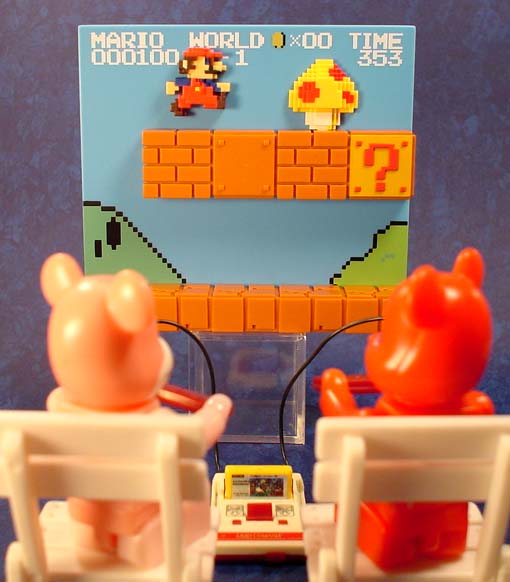
「えいっ、
ここで、きのこをとって、それから、3番目の土管に入って。」
「そうそう、そこのファイヤーバーに気をつけてな。」
「わかって、る、っ、あっ、って!」
「なんだよ、気を付けろって言ったのに。」
「ごめんなさい・・・・・・。」
「ねぇ、甘栗くん。」
「なんだよ。」
「あの、、その、、。」
「、、、、。 輝豸雄の事か。」
「う、うん。」
「気にするな。」
「えっ、でも、だって、。」
「俺たちが気にしたって仕方ないんだよ、、、。 だから、 気にするな。」
「でも、でも、でも、
もう3週間も帰ってないんだよ。」
「・・・・。」
「メロンの季節だって終わっちゃたし、桃だって、栗だって終わっちゃたし、
秋刀魚だって、茄子だって、紅葉饅頭だって、季節が終わっちゃうよ。
輝豸雄くん、帰ってくるって言ったじゃないか。」
「・・・・。」
「ねぇ、甘栗くんてばっ!」
次から次へと繰り出される麝弐猪の問い掛けを、甘栗は黙って聞いていた。
やがて、麝弐猪の口からも、何も出て来なくなった。
そのあまりの静けさに、麝弐猪は甘栗を見た。
モニタを眺める彼の横顔は泣いている様にも、笑っている様にも見えた。
ずっと、麝弐猪は、その横顔を見ていた。
すぐ隣にいるのに、麝弐猪は甘栗に声がかけられなかった。
” すぐ其処にいるのに、、、。 甘栗くんが遠い所にいるような気がする ”
” 寂しいよ、甘栗くん。 哀しいよ、輝豸雄くん。 ”
” 此処に、此処に、輝豸雄くんがいたなら ”
麝弐猪の頬を涙が流れそうになった時、甘栗が沈黙を破った。
「なぁ、麝弐猪。」
「・・・・・・・・。」
「輝豸雄だって、帰って来たいんだよ。
栗だって、桃だって、秋刀魚だって、あいつの好物だもんな。」
「う、うん。」
「帰って来たいけど、今はまだ帰れないんだよ。」
「・・・・・。」
「心の距離は、物差しじゃ計れないんだよ。
輝豸雄は此処にはいない。其処にもいない。
でも、ココにはいるだろう、麝弐猪。」
そう言って、甘栗は自分の胸を指差した。
そして、ゆっくりと、麝弐猪の胸をさわった。
甘栗の手はとても暖かかった。
「お前の その気持ちは、其処にいる輝豸雄には届いているはずさ。 きっとな。」
甘栗は、そう言うと、食堂から出て行った。
一人残された麝弐猪は、甘栗の手の温もりを思い出しながらも、
溢れ出る涙を堪える事が出来なかった。
第128回に続く