電気の森 The Forest Of Electric + Electronic Technorogy by Otoshibumi Craft Lab [Official] [2000]
電気用図記号 ZukgA-005
変圧器に関する図記号
Ver.1.1 2000/10/15版
 |
前節までで、新JIS電気用図記号についての全体的な私見を述べてきました。 |
1. 変圧器に関する図記号取り扱いの要点
変圧器に関する図記号は、「電気用図記号 第6部:電気エネルギーの発生及び変換」(以後、JIS C 0617-6:1999という)の「第3章 変圧器及びリアクトル」に掲載されています。
「第3章 変圧器及びリアクトル」の最初に、図記号の取り扱いに関する4つの説明があります。この中で、様式1と2についての要点をまとめると以下のようになります。
(1) 様式1は、円を使用して各巻線を表わしている。
(2) 様式1は、単線図表示の場合に限定することが好ましい。
(3) 様式1は、変圧器の鉄心を表す図記号と一緒に使用しない。
(4) 様式2は、図記号04-03-01を使用して各巻線を表している。
(5) 様式2において、特定の巻線を区別するために、半円の数を変えてもよい。
2. 単相変圧器の図記号
変圧器に関する図記号の要点から、次の結論を提案したいと思います。
| 提案1 | |
| 変圧器(正確には、「2巻線変圧器」)の単線図用図記号は、図.ZukgA-005-1(a)、複線図用図記号は、同図(b)とする。 |
| 06-09-01 | 06-09-02 |
| (a)単線図用図記号 | (b)複線図用図記号 |
図.ZukgA-005-1 2巻線変圧器の図記号
この提案のベースは、上記、「図記号取り扱いの要点」の「(2) 様式1は、単線図表示の場合に限定することが好ましい。」です。
円を用いた図記号は、複線図でも利用されていました。しかし、ここでは、それをしない方向で提案しています。JIS C 0301:1990は、この提案の方法が採用されています。
JIS C 0301:1990では、「2巻線変圧器=変圧器」と解釈しています。JIS C 0301:1990では、「変圧器」の図記号をあえてタイプCとし、II.3.1.1に記しています。
また、JIS C 0301:1990では、「2巻線変圧器=単相変圧器」と解釈しています。用語と図記号の完全なる一致を示しています。JIS C 0301:1990では、「単相変圧器」の図記号をタイプAとして扱い、II.3.1.2に記しています。
3. 単線図における導体数
単線図おける導体数の取り扱いについては、次の結論を提案したいと思います。
| 提案2 | |
| 単線図に用いる図記号は、導体数を除いた図記号をベースとし、必要に応じて、導体数を記入する。 |
JIS C 0617-6:1999の変圧器で扱われている図記号では、単線図に導体数を記入するように描かれています。特に、「第10節 個別に使用する変圧器の例」(第11節、第12節でも同様)では、必ず、導体数が記入されているのです。
導体数を表す図記号は、図.ZukgA-0005-2に示す(JIS C 0617-3:1997接続、接続群03-01-01、03-01-02、03-01-03を参照せよ。)「斜線」です。
| 03-01-02 | 03-01-02 |
| (a)斜線の数が導体数を表す場合 | (b)斜線の横の数値が導体数を表す場合 |
図.ZukgA-005-2 導体数を表す図記号
しかし、私は、単線図に導体数を記入するのは、難しいと考えています。日本という国だからでしょうか?他の国の事情は、わからないのですが、私が見た(日本の)高圧受配電設備の電気図面では、ほとんど見かけません。
JIS C 0301:1990では、導体数を記入していない図記号を、タイプBとして掲載していました。タイプBの図記号は、IEC規格の許容範囲内で図記号の一部を変更している図記号です。さらに、JIS C 0301:1990では、摘要に導体数の取り扱いについて記していました。
私は、この考え方を提案に採用しました。当然、JIS C 0301:1990は廃止になりました。と言っても実際、問題は解決しません。もし、この提案に変わる良い案を示していただけるなら、この提案を下げたいと思います。
以後、私のコンテンツでは、JIS C 0301:1990にならい、JIS C 0617の図記号から導体数を削除した図記号を用いることにします。またこのような図記号を、JIS C 0617と明確に区別できるように、図記号の下にIEC No.を括弧付きで表示したいと思います。
4. 三相変圧器の図記号
三相変圧器を示す図記号は、次の結論を提案したいと思います。
| 提案3 | |
| 三相変圧器の図記号は、図.ZukgA-005-1(a)単線図用図記号の円の内部にΔ又はYを記入した以下の図記号とする。 |
| (Otoshibumi) | (Otoshibumi) | (06-10-07) | (Otoshibumi) |
| (a)Δ−Δ結線 | (b)Δ−Y結線 | (c)Y−Δ結線 | (d)Y−Y結線 |
図.ZukgA-005-3 三相変圧器の図記号
この提案のベースは、「06-10-07 星形三角結線の三相変圧器(スターデルタ結線)」です。JIS C 0301:1990の「II.3.1.5 三相変圧器(2巻線)」を参考にしています。
他の結線の組合せは、JIS C 0617-6にはありません。図中の(a)、(b)、(d)については、私が図記号を組み合わせたものです。このような図記号を、JIS C 0617と明確に区別できるように、(Otoshibumi)と表示しておきます。
三相変圧器の結線方法は、Δ−Δ、Δ−Y、Y−Δ、Y−Yの4種類が考えられます。円の内部に記入する「変圧器の巻線の結線方法」は、「06-02-05 三角巻線、三角結線(デルタ結線)」、「06-02-07 三角巻線、星形結線(スター結線)」を用います。
5. 単相変圧器の三相結線に関する図記号
単相変圧器の三相結線を示す図記号は、次の結論を提案したいと思います。
| 提案4 | |
| 三相変圧器の図記号は、図.ZukgA-005-1(a)単線図用図記号の円の左側にΔ又はY、Vを記入した以下の図記号とする。 |
| (Otoshibumi) | (Otoshibumi) | (06-10-07) | (Otoshibumi) |
| (a)Δ−Δ結線 | (b)Δ−Y結線 | (c)Y−Δ結線 | (d)Y−Y結線 |
| (Otoshibumi) |
| (e)V−V結線 |
図.ZukgA-005-4 単相変圧器の三相結線の図記号
この提案のベースは、「06-10-11 星形三角結線の単相変圧器の三相バンク」です。JIS C 0301:1990の「II.3.1.7 変圧器の接続例 例1.単相変圧器Y−Δ接続」、「同 例6.単相変圧器V−V接続」を参考にしています。「変圧器の巻線の結線方法」を示す図記号Δ、Y、Vが、JIS C 0301:1990とは左右逆(JIS C 0617では、円の左側)になっていることに注意して下さい。
他の結線の組合せは、JIS C 0617-6にはありません。図中の(a)、(b)、(d)、(e)については、私が図記号を組み合わせたものです。このような図記号を、JIS C 0617と明確に区別できるように、(Otoshibumi)と表示しておきます。
単相変圧器の三相結線方法は、Δ−Δ、Δ−Y、Y−Δ、Y−Yの4種類の結線とV−V結線が考えられます。円の左側に記入する「変圧器の巻線の結線方法」は、「06-02-05 三角巻線、三角結線(デルタ結線)」、「06-02-07 三角巻線、星形結線(スター結線)」、「06-02-02 三角巻線、V結線(60°)」を用います。
図中、左側に記した「3」は、単相変圧器の台数(3台)を意味しています。
6. 単相3線式変圧器の図記号
単相3線式変圧器については、次節で詳しく述べたいと思います。以下のページです。
ZukgA-006 : HELP!単相3線式変圧器の図記号がわからない
現在、どの図記号を採用すべきかを悩んでいるところです。
7. JIS C 0617-6:1999とJIS C 0301:1990の比較
以下にJIS C 0617:1999とJIS C 0301-1990において、変圧器についての図記号の比較をしてみました。
表.ZukgA-005-1 JIS C 0617:1999とJIS C 0301-1990での変圧器の図記号
| No | 名称 | 図記号 | 新JIS C 0617-6:1999 |
旧JIS C 0301:1990 |
Otoshibumi からのコメント |
| 1 | 単相変圧器 1φ1W (単線図) |
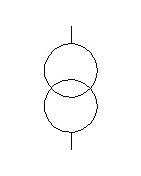 |
No.06-09-01 2巻線変圧器 様式1 [一般図記号] |
II.3.1.2 単相変圧器 (2巻線) 単線図用 ** 06-09-01 |
この図記号が、変圧器の単線図のベース。 |
| 2 | 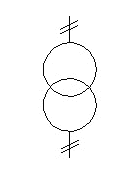 |
該当なし | 該当なし | 06-09-01に03-01-01の単線で導体数を表す記号を適応したもの。 組み合わせた図記号として私が作りました。 (Otoshibumi)。 |
|
| 3 | 単相変圧器 1φ2W (複線図) |
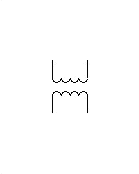 |
No.06-09-02 2巻線変圧器 様式2 [一般図記号] |
II.3.1.2 単相変圧器 (2巻線) 複線図用 ** 06-09-02 |
この図記号が、変圧器の複線図のベース。 |
| 4 | 単相変圧器 1φ3W (単線図) |
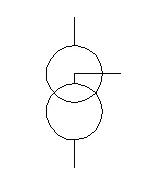 |
該当なし | II.3.1.7例8 中間点引出単相変圧器 単線図用 ** (06-10-03) |
No.06-10-03から導体数を表す記号をはずしたもの。 |
| 5 | 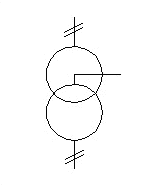 |
No.06-10-03 中間点引き出し単相変圧器 様式1 [例] |
該当なし | この図記号が、単相3線式の変圧器を示すようになるのだろうか? しかし、出力の導体数が2です。3であればよりしっくりくるのですが。 文献5では、「単相3線式」として扱われています。 |
|
| 6 | 単相変圧器 1φ3W (複線図) |
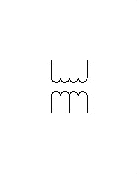 |
No.06-10-04 中間点引き出 し単相変圧器 様式2 [例] |
II.3.1.2 単相変圧器 (2巻線) 複線図用 ** 06-10-04 摘要に記載 II.3.1.7例8 中間点引出 単相変圧器 単線図用 ** 06-10-04 |
JIS C 0301-1990では、単相3線式の変圧器の複線図用に用いられた。また、中間点引出単相変圧器の複線図としても用いられていた。後者は、IEC規格に完全に一致。 |
| 7 | 単相変圧器 1φ3W (単線図) |
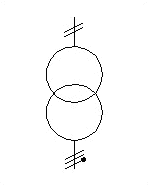 |
該当なし | II.3.1.2 単相変圧器 (2巻線) 単線図用 ** 日本独特のもの 摘要に記載 |
JIS C 0301-1990では、なぜ06-10-03が単相3線式の単線図用に採用されずに、日本独特のこの図記号を採用したのでしょうか? 単相3線式で用いる変圧器が中間点引出変圧器に分類できなかったからでしょうか? 今後、絶滅してしまうのでしょうか? |
| 8 | 三相変圧器 3φ3W (単線図) |
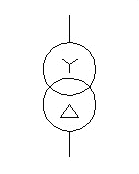 |
該当なし | II.3.1.5 三相変圧器 (2巻線) 単線図用 ** (06-10-07) |
No.06-10-07から導体数を表す記号をはずしたもの。 |
| 9 | 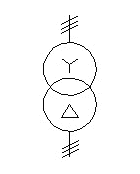 |
No.06-10-07 星形三角結線の三相変圧器 (スターデルタ結線) 様式1 [例] |
II.3.1.5 三相変圧器 (2巻線) 単線図用 ** 06-10-07 摘要4に記載 |
旧JISの摘要4では、No.8の図記号に導体数を加える例としてこの図記号を記載している。 | |
| 10 | 三相変圧器 3φ3W (複線図) |
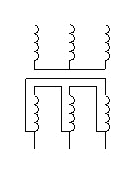 |
No.06-10-07 星形三角結線の三相変圧器 (スターデルタ結線) 様式2 [例] |
II.3.1.5 三相変圧器 (2巻線) 複線図用 ** (06-10-08) |
図記号において、旧JISでは、星形結線されたコイルの上に延長された線が追加されている。 |
| 11 | 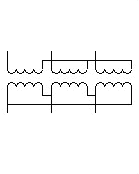 |
No.06-10-12 星形三角結線の単相変圧器の三相バンク 様式2 [例] |
II.3.1.5 三相変圧器 (2巻線) 摘要3に記載。 |
旧JISに利用にあたっての注意あり。摘要3を参照のこと。 |

 Version情報
Version情報
Ver.1.1 2000/10/15版
変圧器について、まとめてみました。解決したい点も多く、早く解説本がほしいです。ご存じの方、是非ご連絡を下さい。
Ver.1.0 2000/08/15版
とりあえず、作り上げることにしたコンテンツです。次回からは、今ページが分割されていきます。
 このコンテンツを利用される方へ
このコンテンツを利用される方へ
■ 内容に関して間違いがあるかもしれません。ですから、100%信じることはおやめ下さい。コンテンツの内容について、間違いにお気づきの方はご連絡いただければ幸いです。コンテンツに反映させたいと思います。このコンテンツが正確になるよう努力していきます。
■ もし、あなたがこのコンテンツによって、損害等が生じても保証はしません。必ず、下記の参考文献等を用いて、内容を確認し、納得された後に活用することを心がけて下さい。
■ このコンテンツは、日々変更していきます。最新のバージョンのコンテンツをご利用下さい。
■ このコンテンツの無断複写転載を禁止します。
![]() 参考文献
参考文献
■ このコンテンツは、次のコンテンツの文献を参考に作成しています。これらの文献にも必ず目を通して、私のコンテンツをご利用ください。
![]() Thank you.....(敬称略、順序不同)
Thank you.....(敬称略、順序不同)
M.Saito
ご意見・ご感想、誤字・脱字等の情報、内容の間違い、ご質問はこちらへ