更新履歴
8. 炭素のRamanスペクトル
8.1 炭素のRamanバンドの種類とその振動数
炭素のRamanスペクトルには、表1に示す3つのRamanバンドが存在する[1]。さらに、五員環に起因するとされるバンド(Pバンド、1470cm-1)も存在するといわれている[2,3]。 一般に、これらのバンドを解析する際に、DバンドおよびD'バンドのGバンドに対する強度比R値およびR'値を算出し、炭素の黒鉛化性を議論することが多い。 R値およびR'値を精度良く求めるためには、それぞれのバンド形状をプロファイルフィッティング法により波形分離することが重要である。 ここでは、Carbon Analyzer R seriesで採用されている数値処理方法を解析手順に沿って、解説する。
表1 炭素および標準シリコンのピーク位置
| 振動モード | Raman shift/cm-1 | |
| A1g | Dバンド | 1350 cm-1付近 |
| E2g | D’バンド | 1620 cm-1付近 |
| E2g | Gバンド | 1582 cm-1付近 |
8.2 実測Ramanデータの強度補正(平滑化処理とバックグラウンド補正)
Ramanスペクトルに限らず、一般にスペクトルデータの解析を行う場合に、データの平滑化処理とバックグラウンド補正がしばしば行われる。 前者に関しては、Savitzky-Golay法、後者に関しては、3次スプライン関数法が採用されることが多い[4,5]。Carbon Analyzerにおいても、これらの方法が採用されている。
8.3 プロファイルフィッティング法
8.3.1 概要
前述のように、炭素のRamanスペクトルにおいては、一般に3つのバンド(Dバンド、D’バンドおよびGバンド)が観測される。これらのバンドから、 R値を精度良く算出するためには、最小二乗法によるプロファイルフィッティング法によって、それぞれのバンドを分離する必要がある。Carbon Analyzerでは、最急降下法およびSimplex法を用いたプロファイルフィッティング法を採用している。
8.3.2 プロファイル関数について
一般に、ピークプロファイルを表現する関数としては、Voigt関数、Pseudo-Voigt関数、PiasonVII関数などが提案されているが、 ここでは比較的数値処理が簡便で非対称プロファイルも表現可能なPseudo-Voigt関数Pr(v)を採用した[6]。この関数は、ローレンツ関数とガウス関数の混合関数を面積が1となるように規格化した関数、すなわち
であり、ローレンツ関数とガウス関数のそれぞれの分率をη , (1-η)で表現する。ピークトップTより低角側(v <T) 、高角側 (v>T )では、プロファイルはそれぞれ
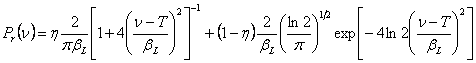 (2a)
(2a)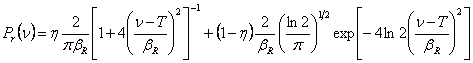 (2b)
(2b)で表現される。上式において、第1項がローレンツ関数項であり、第2項がガウス関数項である。T, βL, βR, RLRはそれぞれピークトップ、ピークより低角側および高角側のプロファイルの半価幅、両半価幅の比(非対称性)を表現している。 実際には、上述のプロファイル関数にさらに強度hが乗じられる。図1にローレンツ率および非対称性パラメータを変えた場合のプロファイル形状の変化を示す。 ローレンツ率が高くなると、プロファイルの裾がなだらかになり、非対称パラメータβL/βRが大きくなるとプロファイルの左側がなだらかになり、逆に小さくなると右側がなだらかになる。
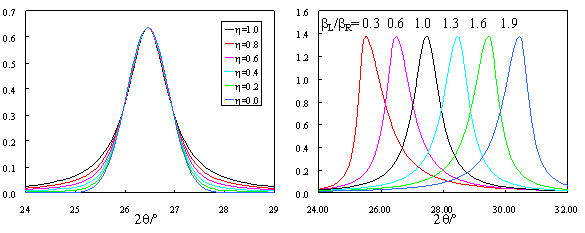
図1 プロファイル関数のローレンツ率、非対称性パラメータ依存性
この関数を用いて実測プロファイルをフィッティングすると、プロファイル全体を反映したピークトップおよび半価幅を直接決定することができる。 実測プロファイルからはおよそのピークトップ、半価幅、強度が求められるので、この値を初期値として最小二乗法を用いてR-因子((3)式)が収束するようにフィッティングしている。
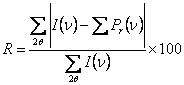 (3)
(3) ここで、I(v)は実測プロファイルを表す。T, h, b , h , RLRが決まるとプロファイル関数は一意的に決定される。
8.3.3プロファイルフィッティングとフィッティングパラメータ数
上記のプロファイル関数を用いて炭素のDバンド、D’バンドおよびGバンドプロファイルを表現し、実測データのフィッティングを行っている。 プロファイル関数は非線形式であるため、フィッティング方法として、ここでは表2に示す2つの方法(Simplex法、最急降下法)を採用している。 前述のように、1つのプロファイル関数は、ピーク位置、ピーク強度、半値幅、ローレンツ率、非対称性の5つのパラメータで決定されるが、Carbon Analyzer R seriesでは、 試料中にDバンド、D’バンドおよびGバンド以外に未知ピークが存在する可能性も考慮して、最大6本のピークに分離できるように設計されているので、 合計30個のパラメータを最小二乗法により精密化することになる。
表2 非線形最適化方法
| 分類 | 方法 | 特徴 |
| 直線探索法 | Simplex法 | 二乗残差和の関数の等高線中にいくつかの点を幾何学的に配置しそれらの点の高さを比較し最も低い点を採用していく方法である。偏微分計算がないため、計算を簡単かつ効率的に行うことができる。 |
| 勾配法 | 最急降下法 | 反復計算の各ステップでそれぞれのパラメータに関する二乗残差和の偏微分係数を計算し残差和の減少する方向を見つけて最小点を探索する方法である。 |
7.3.4フィッティングの際の注意点
最小二乗法を行う際に重要なことは、如何にして真値に近い初期値を設定するかということである。初期値によっては、収束しなかったり、あるいは本来求めようとする解から、かけ離れたプロファイル形状に収束する場合もあるので、注意する必要がある。
8.4. R値およびR’値の決定
Dバンド、D’バンドおよびGバンドの各プロファイルPrD(n),PrD’(n),PrG(n)よりプロファイルを決定する5つのパラメータを求め、R値を算出する。計算は次式を用いて自動的に行われる。面積積分法によるRa値およびRa’値の算出は、以下の式により求めている。
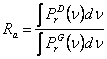 (4)
(4)また、高さ強度比によるRh値およびRh’値の算出は、Dバンド、D’バンドおよびGバンドの各ピークトップの比から算出している。 一般に、R値は、炭素の黒鉛化度の評価に広く用いられているが、その値の意味するものは、単純なものではないので注意を要する。 片桐は、R値の励起波長依存性や装置光学系依存性などとの関係について、詳細に議論しているので、R seriesで求めたR値およびR’値に関しては、片桐の文献を参照して慎重に吟味していただきたい[7]。
8.4 R/F値とIv/IG値
一般に、カーボンブラック、石炭あるいはピッチなどでは、ラマンバンドが極めてブロードとなり、R値も複雑に変化するため、 構造変化との間に一義的な対応が認められず、プロファイルフィッティング法によるピーク分離をもってしても、高い精度が得られない場合がある。 このような低黒鉛化性の炭素材料に対しては、片桐はR値やR’値のようなパラメータよりも、 むしろラマンバンドの強度(R)と蛍光によるバックグラウンドの強度(F)の比R/FやGバンドとDバンドの間の谷の高さ(V)とGバンドの強度比(Iv/IG)を見積もることがよいと提案している[8,9]。 R/F値は、Gバンドのピークトップ位置でのバンド強度とバックグラウンド強度比より自動的に算出される。Iv/IG値は1400cm-1〜1550cm-1の範囲における最小強度値と Gバンドの強度に比から自動的に算出される。
7.5.プロファイルフィッティング例
図2に解析結果の例を示す。
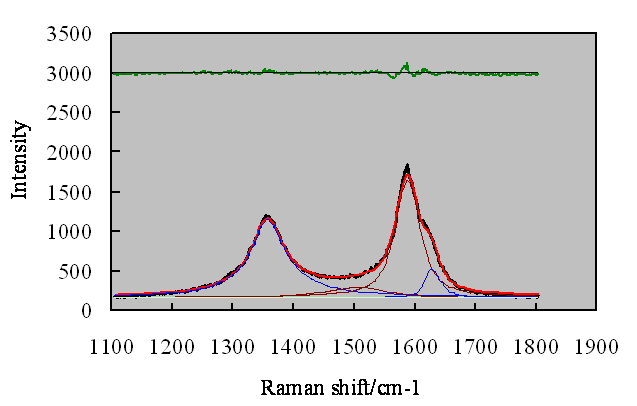
図2 解析例
参考文献
[1] 長田実、垣花眞人、ラマン分光法による炭素材料の評価、炭素 No.228(2007)174-184.
[2] 小鍛治和己,原和美,大谷朝男,山田能生,白石稔, “炭素化・黒鉛化過程における五員環芳香族炭素の作用”、第21回炭素材料学会年会要旨集, 1B09, 68-69(1994).
[3] K.Kokaji, A.Oya, K.Marunuma, Y.Yamada, M.Shiraishi, “Carbonization and graphitization behavior of deacacyclene”, Carbon, 35, 253-258(1997).
[4] A.Savitzky, M.Golay, Anal. Chem., 36, 1627(1964).
[5] 北川源四郎、阿部寛治、田栗正章共訳、数値解析、培風館出版、p.29-33.
[6] J. B. Hastings, W. Thomlinon and D. E. Cox, J. Appl. Cryst., 17, 85(1984).
[7] 片桐元、“炭素材料のラマンスペクトルおよびその新しい応用”、炭素 No.175(1996)304-313.
[8] 片桐元、”炭素材料のラマンスペクトル”、炭素 No.183(1998) p168-172.
[9] G.Katagiri, N.Takeda, “Application of laser raman spectroscopy to characterization of coals and kerogens”, Int. Conf. on Coals and Organic Petrology, Fukuoka 1996.11.14-16.