ことばをめぐるひとりごと
その28
魑魅魍魎(ちみもうりょう)
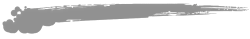 今回は、〈おそろいの漢字〉の話。
中学に上がったころ、「魑魅魍魎(ちみもうりょう)」ということばを知りました。筒井康隆氏の「俗物図鑑」に出ていました。
「今夜はこら、どこへ行ってもあきまへんな」本橋が苦笑してそうつぶやいた。「落ちつけそうにない」
「客引きになるというので、ああいう魑魅魍魎を歓迎する店もあるんです」と、享介が吐き捨てるようにいった。「魑魅魍魎割引きというのがあるそうです」
ここでは〈いかがわしい俗物〉というほどの意味で使われているのでしょうが、ほんらい「魑魅魍魎」とは〈化け物ども〉の意味です。この四字熟語にはそれぞれ同じ部首(鬼繞=きにょう)がついていて、視覚的に強烈でした。筒井氏は、ほかにはたとえば
西日を顔面いっぱいに受け、今や将軍に戻った金次郎は正気に返った嬉しさを鍾馗(しょうき)の如き形相にみなぎらせ顔中のヒゲひげ鬚髭髯をふるわせながらいつまでもいつまでも笑い続けていた。(「将軍が目醒めた時」)
というような書き方をしています。
こういう〈おそろいの漢字〉は、二字熟語ではあちこちで見かけるのですが、これが三字・四字となってくるとなかなかないものです。しかしこの際、ちょっと探してみましょう。
国語学の用語に「謙譲語」「訓読語」などというのがありますが、この2つは「言偏(ごんべん)」でそろっています。ほかに、病気の名ですが、「脂肪肝」というのがあったのをふと思いつきました。これは「肉月」でそろっています。
しかし、こういうものは次々と思い浮かぶものじゃありません。そこで、新聞や小説、テレビ番組などを見るときにちょっと注意していましたら、意外なものを拾うこともできました。
同じ部首というなら、「日曜日」「海水浴」「恐怖感」などもそうですが、これはちょっと面白くない。視覚的に共通する部分を持っていないからです。また、一見ピンとこないけれど、「商品名」なんてのはすべて「口偏」のようです。でもやはり、視覚的には統一性が感じられません。
探した例の中から、目で見て「字形がそろっている」と感じられるものばかりをピックアップして、下に並べてみましょう。
(1)人偏
任侠伝
(2)木偏
柑橘林 樫村機 植村様
このうち「樫村機」は戦闘機の名で、阿川弘之「山本五十六」に出てきます。「植村様」はインチキっぽいですが、樋口一葉の短編「うつせみ」に出てくるのです。
(3)さんずい
潤滑油 浪漫派 浪淘沙 滝津瀬 油溶液
洗滌液 清涼酒 温浴法 泡沫浴
「浪淘沙」は石川啄木「一握の砂」に出てきます。
浪淘沙
ながくも声をふるはせて
うたふがごとき旅なりしかな
たぶん、漢詩の文句ではないかと思うのですが、よく知りません。「滝津瀬」は「滝つ瀬」の当て字で、滝のこと。「温浴法」は、「ラドン温浴法」「ゲルマニウム温浴法」など。「泡沫浴」は泡立ったお湯に入る健康法のようです。
(4)ウかんむり
寄宿寮
(5)草かんむり
葡萄茶 葡萄蔓 蓮華蔵 菠薐草 薯蕷藷
蒟蒻芋
「葡萄茶」は「えびちゃ」、「菠薐草」は「ほうれんそう」、「薯蕷藷」は「とろろいも」、「蒟蒻芋」は「こんにゃくいも」と読みます。
そのほかには、
(6)病だれ
疱瘡病 瘰癧病(るいれきやみ)
(7)玉偏
珊瑚珠
(8)糸偏
紡績織 緋縮緬 絽縮緬 縞縮緬 紋縮緬
綿紡績
(9)肉月
腺腫脹 脂肪腺 膃肭臍(おっとせい)
(10)言偏
認識論 訴訟話 設計課 評論誌 談話調
誤認識
などが見つかりました。
4字以上の漢字連続のうち3字までがそろっている例としては、「肝臓肥大」、「船舶航行」、「逮捕許諾請求」、「銅鐸鋳造の炉跡を発見」(朝日新聞 1998.5.26 p.29)「商用で上京してきた折挨拶に来たので」(筒井康隆『敵』p.88)などが挙げられます。また、1979年には大蔵省で「綱紀総点検委員会」が設けられたことがあるそうです(朝日新聞「天声人語」1998.3.13)
四字熟語としては、まず「流汗淋漓(りゅうかんりんり)」。汗がだくだくと出てくる様子ですね。また、「袒裼裸[衣+呈](たんせきらてい)」(孟子)は、「諸肌を脱いで無礼な振る舞いをする」という意味。「世俗の間に傾側偃仰(けいそくえんぎょう)する」といえば、世の片隅で起き伏しすること。
部首としては4連続である例としては「悲憤慷慨」「思想感情」「温泉湯治」などがあります。
人名では、広島大学附属中学校に湯浅清治先生がおられます(ここに掲載していいのかどうか分かりませんが)。
地名の例としては、北海道の「珸瑶瑁(ごようまい)」「濤沸湖(とうふつこ)」、福岡県の「洞海湾」など。
最後に、実例は仮名書きであっても、漢字に直せば4字がそろう例。朝日新聞(1997.7.30 p.3)に「汚泥しゅんせつ終了」とありました。「しゅんせつ」の部分がひらがなになっていますが、「汚泥浚渫」と漢字で書けば、さんずいの4連続となるところ。水俣病を引き起こした水俣湾の水銀値に「安全宣言」が出されたという記事の中のことばで、グラフ「水俣湾の魚介類の総水銀値の推移」の1987年の項に書いてあったのでした。
(1997.05.20)
▼関連文章=「葉菖蒲」
●この文章は、大幅に加筆訂正して拙著『遊ぶ日本語 不思議な日本語』(岩波アクティブ新書 2003.06)に収録しました。そちらもどうぞご覧ください。
|