05.06.21
うでにわらべ おびゆるを
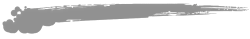
中学校では、1年生のときにシューベルトの歌曲「魔王」を鑑賞するはずです。どこの中学でもそうでしょう。というのも、今、音楽教科書を発行する出版社は2社あって(教育出版・教育芸術社)、どちらの教科書にも「魔王」は載っているからです。
私も中学生のころに「魔王」を鑑賞しました。いったい、いつごろから教材になっているのか、それは知りません。だいぶ昔からであることは確かです。
教科書の「魔王」の歌詞には、昔も今も大木惇夫・伊藤武雄の共訳が使われています。「おとーさーん、おとーさーん」という叫びが特徴的な訳です。教科書には楽譜しか載っておらず、音符に添えられたひらがなの歌詞しか分かりません。その出だしの部分を見ると、
かぜのよに うまをかり かけりゆくものあり
うでにわらべ おびゆるを しっかとばかりいだけり
となっています(「オンライン音楽室・魔王」でも読めます)。風の夜に、父が病気の子どもを抱いて、馬を飛ばしている場面です。
私は、この「うでにわらべ おびゆるを」の部分を「腕に童 怯ゆるを」だと解釈していました。「腕の中に子どもが怯えているのを」ということです。文法的に考えれば、それ以外の解釈はありえないでしょう。
ところが、松山裕士『簡易ピアノ伴奏による 中学の音楽』(ドレミ楽譜出版社)で大木・伊藤訳の「魔王」の歌詞組(漢字仮名交じりの歌詞)を確認すると、この部分は次のように記されています。
風のよに馬を駆{か}り 駆けりゆくものあり
腕{うで}に童{わらべ}帯びゆるを しっかとばかり抱{いだ}けり(p.240)
「怯ゆるを」ではなく「帯びゆるを」とあります。この漢字からすれば、訳者の意図としては「怯えている」ではなく、「帯びている」と言いたいらしいのです。
これはへんな話です。「怯ゆ」(怯える)ということばは日本語にありますが、「帯びゆ」なんてことばはないはずです。それを言うなら、「帯びたるを」、または、「抱(いだ)けるを」とでもなるでしょう。「おびゆるを」と歌っているのを、「帯びる」ということだと理解せよというのはどうしても無理です。
これは歌詞組の誤植じゃないかと思って、他の楽譜を探しましたが、大木・伊藤訳のテキストで、いっそう信頼できるものを見つけることはできませんでした。現在、よく目に触れる訳としては、『世界名歌110曲集 1』(全音楽譜出版社)の堀内敬三訳のものなどがあります。しかし、中学で扱っている大木・伊藤訳の元のテキストを探すのはたいへんな仕事になりそうなので、やむをえず中止にしました。
ゲーテの原文は「Er hat den Knaben wohl in dem Arm」となっています。これは「父は腕に子どもをしっかり抱えている」というようなことだと思います。「怯えている」という描写は出てきません。とすれば、「帯びゆるを」は「怯ゆるを」の誤植ではなく、訳詞者がほんとうに「帯びゆるを」のつもりで記したもののようです。
これが別の文章だったら、誤解はないかもしれません。たとえば、だれかが「腰に刀を帯びゆるを」などという言い方をしたとして、もちろんそんな言い方はないのですが、前後の文脈から「ああ、刀を帯びていると言いたいのだな」と推測できます。でも、「魔王」の詩は、実際に子どもが魔王に怯えている話ですから、前後の文脈を考慮すれば、なおさら、「怯ゆる」と解釈するのが当然となります。
どうしてこういう紛らわしい訳が出てきたのでしょうか。あるいは、訳者が2人いたため、両人の間で何かの誤解が生じたのではないかと思います。今のところ、真相は不明です。
ついでに言えば、「風のよに 馬を駆り」という詞も、聴いて分かりにくいですね。これでは、「風のように」かと思ってしまいます。原文は「durch Nacht und Wind」で、「闇と風を突いて」というようなことでしょうから、「風の夜に」と解釈するのが正しいのでしょう。
いろいろ分かりにくい「魔王」の訳詞ですが、これはこれで親しまれているのも事実です。今さらへたに改めるよりも、このまま次の世代に伝えていって、みんなで共有するほうがいいと思います。ある歌や詩が、一部の世代にしか知られないことほど、さびしいことはないからです。
|