05.05.11
「義経」のことば
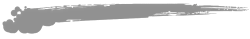
NHKの大河ドラマ「義経」を楽しく見ています。源平時代を扱った大河ドラマは、私にとってはなつかしい。何しろ、小学生の時、源頼朝と北条政子を扱った「草燃える」(1979年)を見たのが、日本史に興味を持った初めでしたから。
当時は、子どもだったせいか、ブラウン管の向こうに本当の源平時代があるような現実味を感じたものでした。今回もまた、液晶テレビの向こうに本当の源平時代があるような錯覚にとらわれます。これは、ドラマがうまくできているせいか、それとも、小学生時代のすなおな感覚がよみがえるせいか。
ただ、ことばだけは源平時代の流儀でやるわけにいかないのは当然です。せいぜい「源平時代らしく」聞こえるようにするしかないでしょう。かつて「草燃える」に出てくる御家人たちは、相手のことを「わぬし」と言っていました。武者ことばの感じを出そうとしたのでしょうが、当時の武士ならば「わ殿(わとの・わどの)」のほうが一般的だったろうと思います。
武士、町人など、ある種の人物像を思い浮かべさせるために用いることば遣いを、金水敏氏は「役割語」と名づけています。源平時代らしく聞かせるために用いられていることばであれば、必ずしもその時代のことばではなくても、「役割語」と言えるでしょう。大河ドラマのせりふは、丸ごと役割語で出来ているといってかまいません。
「義経」では、「かたがた(一同の者よ)、参る!」(第1回)という変わった言い方が出てきます。「かたがた」は「曾我物語」などにあることばです。しかし、源平時代のドラマにはちょっと早すぎるのではないでしょうか。大勢に呼びかけるには、「平家物語」にある「殿ばら」「わ殿ばら」のほうがよりふさわしいと思います。
また、注意が引かれる言い回しに「申す」があります。
・常盤御前(息子たちに)「ふたりに申す。お父上が亡くなられた。この上は我ら父上のもとへ参ろうと思う」(「義経」第1回・2005.01.09放送)
・静「いつぞや、私にここに残るように申されました。あれは、まことで……」
義経「まことじゃ」(「義経」第17回・2005.05.01放送)
現代ならば、上の例のどちらも「申す」は使わないところです。息子に言う場合には「ふたりに言っておきます」、位の高い人に対しては「ここに残るようにおっしゃいました」と言うでしょう。現代敬語では、「申す」は謙譲語(こちらがへりくだるときに使う)であって、上に挙げたような使い方は「誤り」ということになります。
歴史的にはどうかというと、へりくだる意味のない「申す」を使うことはあったようです。「義経記」(室町時代)では、敬う相手に対して「正直に申され候へ」(正直におっしゃってください)と言っています。松下大三郎はこの「申す」のような言い方を「荘重語」と名づけ、中世からあると指摘しました。しかし、源平時代にはやや早そうです。
もうひとつ、私にとってめずらしいのは「願わしゅう」という言い方です。
・常盤御前(平清盛に)「わたくしの一命に代えて、この子らと母の助命を願わしゅう、何とぞ、何とぞお聞き届け下さいまするよう」(「義経」第1回・2005.01.09放送)
・北条政子「鎌倉は目下、あちらこちらと普請の最中なれば、しばらくはご辛抱願わしゅう」
義経「夜露をしのげるだけでもありがたいことにございます」(「義経」第15回・2005.04.17放送)
「願わしい」は、私は使わないことばです。使うとすれば、「望ましい」に近い意味で「彼の助けが願わしい」などというふうには言うかもしれません。
ドラマでは、これとは違い、相手に向かって「お願いいたしたく」という意味で使っています。これは、それほど古い使い方ではないでしょう。「仮名手本忠臣蔵」には、「ただ御最後の尋常を願はしう存じまする」と出て来ます。
「かたがた」「申されました」「願わしゅう」などは、現代のふつうのことばでもないけれど、かといって源平時代そのままでもないことばです。何時代のことばともつかない、「時代劇語」と言ってよいでしょう。
|