04.05.09
「に続く」と「へ続く」
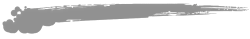
「に」と「へ」が変わると意味が変わるという話をしましょう。
岩淵匡『日本語反省帳』(河出書房新社)の中に、「に」「へ」の違いを説明しているところがあります。最初に「大学に行く」「大学へ行く」という2文を示し、「この二つの文の意味は同じでしょうか」と問いかけています。
「に」は、時間や空間における場所を表します。〔略〕これを移動の意味の動詞「行く」「移る」「進む」などと一緒に使うと、「郵便局に行く」〔略〕などのように目的地を表すことになります。
いっぽう、「へ」は、本来、「南へ向かう」「あっちへ行け」というように、目的地というよりも、漠然{ばくぜん}とした「方向」を指して用いていました。ところが現代語では、「郵便局へ行く」「南に向かう」とも言うようになったのです。(p.17-18)
この説明からすると、「なあんだ、現代語では、『大学に行く』と言っても『大学へ行く』と言っても、結局同じじゃないか」ということになりそうです。たしかに、こまかく言えば「大学に行く」は目的地を表し「大学へ行く」は方向を表すのかもしれませんが、指す事実は変わらないように見えます。
それでは「に」「へ」に用法の違いはないのか。同書では「宇宙への旅」は言えるが「×宇宙にの旅」は言えない、「遊びに行く」は言えるが「×遊びへ行く」とは言えないと説明します。なるほど、そのとおりですが、これは一方が日本語として完全に破綻しているため、(日本語を母語とする者ならば)使うときにまぎれる心配はありません。
そこで、今回は、「使うときに意味がまぎれやすい『に』と『へ』」について指摘し、あわせて「に」「へ」の違いを考えたいと思います。そのために、「○○に続く」「○○へ続く」という言い方を比べてみます。
ひとつクイズを出しましょう。日本の歴史区分は、奈良・平安・鎌倉・室町・江戸・明治などと大まかに分かれます。では、
江戸時代に続く時代
江戸時代へ続く時代
はそれぞれ何時代でしょうか。
まず、「江戸時代へ続く時代」は、上の区分で言えば、答えは「室町時代」ということになりそうです。明治時代ではありません。「○○へ続く」というとき、「○○」は時間的によりおそいものを示します。
一方、「江戸時代に続く時代」は何時代でしょうか。答えはややあいまいです。「室町時代」の可能性もあり、「明治時代」の可能性もあるというところでしょうか。「○○に続く」というとき、「○○」はより早いとも、よりおそいとも考えられます。しかし、どちらかといえば「明治時代である場合が多い」というのが答えであろうと思います。
それは、次のような例で考えるともう少しはっきりします。日本人のノーベル賞受賞者はこれまで12人います。湯川さん・朝永さん・川端さん・江崎さん・佐藤さん・福井さん・利根川さん・大江さん・白川さん・野依さん・小柴さん・田中さんです。ここで、
川端さんに続く受賞者
はだれでしょうか。それは「江崎さん」です。「朝永さん」ではありません。この場合、「○○に続く」の「○○」は、より早いものを示しています。
一方、「川端さんへ続く受賞者」という言い方はあまりしません。もし、言うとすれば、
田中耕一さんへ続く歴代の輝かしい受賞者たち
という文脈においてでしょう。この場合の「○○へ」も、「江戸時代へ続く時代」と同じく、「○○」の部分にはよりおそいものが来ています。
・「○○へ続く」の「○○」にはよりおそいものが来る。
・「○○に続く」の「○○」にはより早いものが来ることが多い。
こう覚えておくと、作文の上で便利な場合がしばしばあります。
蛇足ですが、昔は「京へ筑紫に坂東さ」と言って、京都では「へ」を、筑紫では「に」を、関東では「さ」をよく使ったと言います。しかし、昔も「へ」「に」の違いは単なる方言の違いというだけではなかったでしょう。
▼関連文章=「「に」と「を」」 「大湊を追う」
|