|
ファミリーレストランの「すかいらーく」ブランドが10月29日ですべて閉店する。1970年に1号店をオープンして以来39年ファミレス業界の先駆者として業界を牽引してきた「すかいらーく」ではあるが、創業業態が市場から姿を消し、「すかいらーく」は社名にのみ名を残すことになった。こうした「すかいらーく」の盛衰は、外食産業のみならず他のサービス業や製造業の戦略を考える上でも参考になる(注1)。 外食産業全体の市場規模をみると、1997年の29兆円をピークに最近では24兆円台に低迷している。実にピーク時に比べて10数パーセント市場が縮小しているのである。バブル崩壊後の不況期でさえも伸びていた市場が、なぜ1997年を境に景気の波に多少左右されたとはいえ縮小、横ばい傾向になったのか。この主な原因として考えられるのは、ちょうどこの時期に15歳未満の年少人口と65歳以上の老年人口の構成比が逆転した点である(下図を参照)。つまり、少子高齢化が進み、生産年齢人口がピークアウトした結果、これまで外食市場を支えていたファミリー層やビジネスパースンが減少に転じる転換点を迎えたのである(注2)。 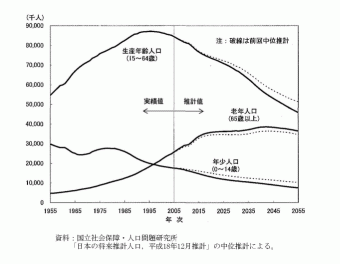 「すかいらーく」は上述した市場の構造変化による家族連れ客の減少などで低迷が続き、2006年にはMBOを実施し上場を廃止した。そして、野村プリンスパル・ファイナンスの傘下で創業業態「すかいらーく」の低価格店などへの業態転換が進められてきたのである。「すかいらーく」が何故このような結果になったのか。その原因は、筆者は次の5つに要約できると思う。
「すかいらーく」は上述した市場の構造変化による家族連れ客の減少などで低迷が続き、2006年にはMBOを実施し上場を廃止した。そして、野村プリンスパル・ファイナンスの傘下で創業業態「すかいらーく」の低価格店などへの業態転換が進められてきたのである。「すかいらーく」が何故このような結果になったのか。その原因は、筆者は次の5つに要約できると思う。
これまで古くは編み機や和文タイプライター、最近ではオートバイ(二輪車)のような衰退市場の典型例がある。代替品の出現とも関連するが、市場構造の変化が背景にあるとすれば衰退に歯止めをかけることは難しい(注3)。 しかしながら、市場全体が低迷もしくは縮小していても、伸びている市場セグメントもある。たとえば上述した二輪車市場は、80年代前半のピーク時の約8分の1といわれる衰退市場だ。だが、電動バイクは今後の需要拡大が期待され、衰退市場の中での成長セグメントである。外食産業でいえばファストフード業態や回転寿司であり、ファミレス業界の中では低価格イタリアFRなどである。主力の標準型FRの陳腐化に伴い、成長する市場セグメント、業態への転換が生き残りの定石である。「すかいらーく」はこの点でも意思決定が遅れた。 このように業態転換が遅れた背景には、企業戦略を考える際の事業ポートフォリオ発想の欠如があったと思われる。すなわち、成長性や収益性あるいはマーケット・シェアなどを基準に事業の最適な組み合わせを考え事業領域を設定する、これが事業ポートフォリオの考え方であり、企業戦略のエッセンスである。主力事業や主力業態の伸びや収益性をチェックしながら、次代を担う事業や業態に組み替えていくのが経営トップの役割なのである。日本企業のトップは一般に、ある事業・業態の事業戦略は得意だが、このような企業戦略は苦手だといわれている。「すかいらーく」のかつてのトップも例外ではなかったのである。 さて、上述した事業ポートフォリオを考えた場合、戦略オプションとしてM&Aを積極的に活用した方が効果的である。自社の成長性を補完する企業、あるいは成長市場に属する企業を一から育てる時代は終焉しつつある。さらに、国内市場が縮小していても海外市場は成長しているケースも多い。前述した二輪車業界が好例だが、超ドメスティック産業といわれたコンビニを含む小売業や外食企業も海外に成長市場を求めるケースが増えてきた。「すかいらーく」は小僧寿し本部などを傘下に加え少なからずM&Aを行ってきた。だが、主力業態の見直しを早め90年代後半からM&Aを積極化していれば、状況は変わっていたものと思われる。また海外展開という戦略オプションが希薄だった点は残念である。 「すかいらーく」のケースは他人事ではない。皆さんの会社の現状をみて、もし上記の5点に該当する点があれば、即現在の戦略を見直すべきだ。 注1: 下記の記事などを参照した. http://news.livedoor.com/article/detail/4402741/ http://sankei.jp.msn.com/economy/business/091026/biz0910262245017-n1.htm 注2: 「年齢3区分別人口の推移」のグラフはH20年度版『厚生統計要覧』(厚生労働省)の「第1編人口・世帯 第1章人口」の図1-2による. http://www.mhlw.go.jp/toukei/youran/index-kousei.html |