ひととおり弾けるようになったら仕上げにかかります。
ここではペダルの使用法と、楽想表現について細かい留意点をまとめたいと思います。
1.ペダル使用について
1−1.はじめに
ショパンは大変に繊細なピアノ奏法を身につけていました。それはペダルの使用についても同様で、神経の行き届いたペダリングで多彩な響きを作り上げていたと伝えられています。このようなショパンのペダリングを反映して、譜面に書かれたペダル指示は概して的確なものになっているのですが、我々がそのまま鵜呑みにできない事情を知っておく必要があります。
・明らかにペダル使用が想定される場面ではペダル記号は書かれていない。
・非常に細かくペダルを踏み変えなければならない場面ではペダル記号は書かれていない。
・フレージングが微妙で演奏者によってペダリングが左右される場面にはペダル記号は書かれていない。
もうひとつ重要なこととして、現代のピアノとショパンの時代のピアノの違いに留意する必要があります。1800年代前半のピアノは現代ピアノほど音が伸びず、響きも豊かではなかったために、ペダルを踏みっぱなしでもあまり問題なかったようです。そのためショパンの楽譜には長くペダルを踏む指示が書かれた箇所があるのですが、現代のピアノでペダル指示そのままに弾くと、不協和になったり響きが濁ることがあります。このような場合は、楽譜にかかれていなくても適宜ペダルを踏みかえる必要があります。
以上を要約すると、
・ペダル使用については楽譜の指示に準拠する。けれども
・楽譜にこだわることなく自分の弾いている音をよく聴いて、効果的な踏み方を考え練習する必要がある
ということになります。
「別れの曲」はペダル記号が少ない譜面ですが、実際はほとんど全編でペダルを使用します。したがって、この曲はペダルの使い方まで含めた練習曲と考えることができると思います。
1−2.一般的なペダルの踏み方
ペダルは、ただ踏めば良いのではなく、いろいろな踏み方をする必要があります。
踏み込む深さ
・余韻が増える程度にちょっとだけ踏む(レガートの補強になる)
・わずかにダンパーが開放されるように踏む
・半分程度ダンパーが開放されるように踏む
・完全にダンパーが開放されるように踏む
踏み込むタイミング
・打鍵前に踏む
・打鍵と同時に踏む
・打鍵直後に踏む
踏み込み時だけでなくペダルを離すときの速度や深さやタイミングにも留意しなくてはなりません。以上のように、ペダルの踏み方にはいろいろな可能性があるのですが、自分のイメージする音色や響きを作り上げるために使うことを意識するのが大切です。自分の思ったとおりに鳴っているか、ピアノの音をよく聴きながら常にペダルの効果を吟味しなくてはなりません。そのような意識を持たずに漫然とペダルを使うのが最も良くないことだと思います。
1−3.「別れの曲」でのペダルの踏み方
基本的には以下の方針で行きます(この方針は別れの曲以外にも通用します)。
・和声が変わるときにはペダルを踏みかえる。
・フレーズの切れ目ではペダルを踏みかえる。
・ピアノでは浅めに、フォルテでは深めに踏む。
・フレーズの頂点となる音やsf、ff、アクセントが付いている場合は打鍵と同時にドンと踏み込む(強音ペダル)
・リズムやアーティキュレーションを明瞭に表現したいときは、余韻が伸びすぎないようにする。
・ペダルを離すポイントの設定をよく考える。
ペダルを使うときに注意することは、ペダルの効果を耳で確認することと、ペダルを離すポイントを守ることです。初心者の場合、ペダルを長く踏みすぎる傾向になります。フレーズの終わりできちんとペダルを上げて余計な余韻を消すことで、すっきりとした終止感を演出することができます。
さて。
実際この曲のペダリングで一番問題になるのは、A部の主題だと思います。この部分はかなり難しく、いろいろ悩むところです。できるだけ自分で考えていただきたいですが、初心者には大変だと思います。いろいろ考えるのが面倒な人は、ペダリングについて詳細な解説の書かれたコルトー版の楽譜を参照するのも一つの手です(コルトーが補完したペダルは、ほぼ完璧だと思います)。
主題以外の部分、特に音符が細かく動くところでは16分音符1つ1つに対してペダルを割り当てます。すばやく確実な上げ下げができるように練習しなければなりません。このテクニックをビブラートペダルと呼びます。B部の4度半音進行などでもビブラートペダル使います。
2.楽想表現について
ショパンさまざまな言葉で濃やかな表現を演奏者に求めています。これが「別れの曲は音楽表現の練習曲である」と言われるゆえんでもあります。しかしポリフォニーを確実に処理しながら豊かな表現を盛り込んでいくのはかなり難しく、楽譜に書かれた音を鳴らすだけで精一杯になりがちです。ここで、発表会など他人の前でこの曲を披露することを想像してみてください。世の中のほとんどの人がこの曲を知っているわけですから、適当にごまかすわけにはいきません。また、単に音を鳴らすだけの演奏では何の感銘を与えることもできません。有名曲だからこそ、自分なりの表現を盛り込んだ演奏が求められるのです。
アゴーギク(速度表現)、デュナーミク(音量表現)については、ショパン自身が楽譜に詳細な記述をしていますので、これに従えばほとんど問題ないと思います。しかしこれだけでは普通の演奏にしかならないので、さらに高いレベルを目指したいと思います。それが私がこの曲で最重要課題と考える和声変化を意識したポリフォニーの立体的表現になります。和声の移り変わりをポリフォニーの中で表現することで、どこかロマンティックで甘い寂寥感を持った仕上がりになるのです。
2−1.調性とポリフォニーの関係
譜読みの最初で述べたように、調性や和声に対するショパンのこだわりは大変強いものがありました。この曲でも主題のホ長調トニカに戻る展開にいろいろな技法が使われていますが、ポリフォニーに埋もれているので見落としがちです。そういったディテールをさりげなく強調することで、美しいメロディだけが印象に残りがちなこの曲に、新鮮な立体感をもたらすことができると考えました。
ショパンが楽譜に書かなかったことで、私自身が「こう弾いた方が良いのではないか」と考えたものを以下に紹介します。
2−1−1 6〜8小節(第1主題第2句)
第1主題の始まりは和声的にそれほど面白みがありませんし、まずはメロディの表現に注力したいところです。しかし第2句は和声的に面白くなります。特に7〜8小節にかけて、半音進行で下がる内声(赤い音符)がきれいに出るように弾くと、9小節目にホ長調で主題が戻る展開にロマンティックな説得力を持たせることができます。また、その前ふりとして、7小節目でクレシェンドしながら厚みを増す(タッチを深くしていく)と、より効果的でしょう。
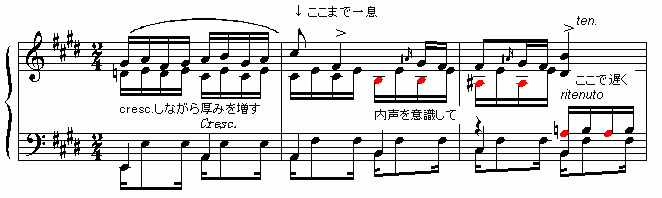
なお、14〜16小節も同じようにクレシェンドしながら厚みを増し、17小節に頂点を作ります(これがA部の頂点となる)。右手の4−5指が弱いと十分なクレシェンドができず、旋律が弱くなります。予備練習をしっかりやって、指を強くしておく必要があります。
2−1−2 30〜31小節
内声のシンコペーションによる転調をおもしろく表現したい箇所です。
旋律とバスはしっかりテヌートしますが、内声16分音符の裏拍をスタカート気味に弾くことでリズムの違いを明確に表現します。これで重くなりがちな和声に軽さを出すことができますし、ポリフォニーもわかりやすくなります。このような細かいアーティキュレーションは楽譜には書かれていませんが、バッハの曲を勉強していれば自ずと理解できる部分でもあります。
また、リズムパターンの同じ声部はアーティキュレーションも同一なので、この場合はA(旋律+バス)、B(右手内声+左手内声)、という2グループに分けることができます。30〜31小節はAとBが互いに呼応していますので、作曲技法上は一種の対位法と言えます。別れの曲はポリフォニーの練習曲ですが、あからさまに対位法的に書かれた部分は少ないのです。したがって、このような箇所でははっきりとフレーズの呼応を表現して、「私は対位法的書法を理解した上で弾いてるんですよ〜」とアピールしましょう(笑)。
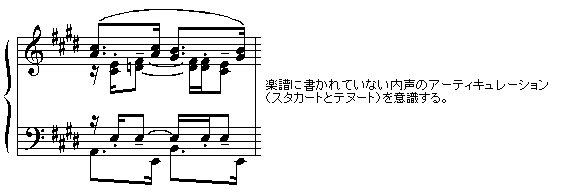
2−1−3 54〜59小節
ここも2−1−2と同様に、微妙に対位法的な書法になっています。2−1−2と異なるのは、ショパンによってことごとくアーティキュレーション指示が書かれている点です。細かく付けられたスラー、スタカート、アクセントはすべてアーティキュレーションの指示ですから、明確に表現しなくてはなりません。この部分は再現部へのつなぎということでさらっと弾いてしまうピアニストが多いのですが、気を抜かずにしっかり弾きたいところです。そうすることで、再現部のホ長調トニカへつながるまでの緊張感を維持することが可能となります。
|
−今回のポイント−
|
2003.10.19