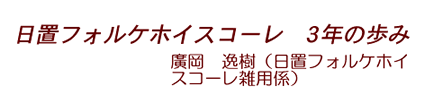

それは、「りっぱなこと」を言う専門家は山ほど居るのにちっとも良くならない「不登校」という子どもの問題、「ノーマライゼイション」が大事だとみんな言うのにちっとも改善しない (それどころか入所型施設は今だに増え続けている)貧しい日本の障害者福祉の問題などなどに対する私なりの解決的介入でもあります。いつも心に留めていることは、「生きた言葉を生きた耳に」と「さざなみ効果 (ほんの小さな変化がやがては大きな変化となる) 」です。
今回は清水 満さんの依頼で、3年間の活動をご報告いたします。まず、始めるにあたって目指した目標を少し詳しくお伝えしておきます。まだ形をなしてはいないのですが、私自身再度確認しておきたいと思いますので、そこから始めさせていただきます。
1、目指しているもの
知的障害や自閉症といわれる人々との対話、重症心身障害者といわれる人々との対話 (コミュニケーション)がどのようにしたら可能なのか、このテーマが私の最終テーマです。私も含めて、障害児・ 者現場で働く人々の多くが、まだまだ障害を持つ人と、ひとりの対等な人として関わりきれていないという現実があると思います。 (もちろん、数は少ないですが、きちんとそうしている人々もいます)。そうした現実を、地域に暮らす者として、どう変えていくのか、またそうした活動が新しい地域文化をも創り出していく、そうした活動でありたいと思います。

(1)「どんぐり文庫」と名付けた、自宅の一室を使った文庫活動。
開館は、月曜日から金曜日の16:OO-18:OO。第2, 4 土曜日の午後もオープンしています。
(2)「表現と対話の集い」という、20 - 30人の小さな集まり。土曜日の午後行うようにしています。今年の5月末までに15回実施しました。現在は2か月に1回程度のペースで無理なくやっています。内容的には、絵本の読み聞かせ、イドラットフォルスクというデンマークの民衆遊び、焼き芋会〈1月に3年連続〉、貝がらを使った作品づくり、福祉の実践活動や海外の福祉事情の報告会などをやってきました。自分自身のことばや身体で表現し、それをきちんと聴く (受けとめる)ということを大切にしています。また、できたらお茶や食事をいっしょに楽しむということも心がけています。また小人数であることも大事な要素で、対話が成立するためには10人前後が理想だと思います。
(3)1998年7月17日には、神奈川県の小学校教諭名取弘文さんの「おもしろ学校公開講座」を、地域の研修室を借りて行いました。普段の「集い」とは違った新しい出会いを町内の人々といっしょに経験することができました。
(4)「CAP北浦」の活動
CAP (子どもへの暴力防止プログラム)を北浦地区の小、中学校の子どもたちに提供することを目標にしています。1998年12月から月1回 (第4土曜日午後)のぺースで勉強会を始めました。妻は下関の小学校まで出かけて行って (こちらの学校ではまだ依頼がありません)ファシリテーターもこなすようになりました。この秋には、熊本人権テーブルの砂川真澄さんをお呼びして、公開講座を開く予定です。
(5)「レゴ・ロゴ」ルーム
1999年4月から月2回。原則第2,第4土曜日午前中。住谷俊樹さんの「ラーンネット」でやっている、子ども向けコンピュータープログラミング言語 (Logo)と、デンマークで作られたレゴブロックによる作品とをドッキングさせた、創造的おもちゃ「レゴ・ロゴ」を楽しむ部屋。一緒にやっているのは、まだわが子 (小4と保育園年長組)のみです。
(6)小さな「旅するホイスコーレ」
これは高砂市で地球学校を開いていた小島一裕さんがアメリカ合衆国を舞台にやっていることなどにヒントをえて、99年2月と3月に、「地球学校」、「ラーンネット」を訪ねる旅 (わが息子と3人でした)と長崎の「でてこいランド」を訪ねる旅 (わが子二人を含め6人でした)を行ないました。12月には、沖縄の伊江島を訪れたいと思っています。息子との旅を楽しんでいるだけの様でもありますが、それだけでも私にとっては十分ですし、仲間が加わればもっと楽しくなります。
(7)5月26日には、協会の「春のセミナー」でお会いした松本英揮さんが大阪に行く途中で、日置の我が家に立ち寄られ、「表現と対話の集い - 番外編」を行ないました。火曜日の夜ということで、5人の参加でしたが、スライド上映がおわった後、時の経つのも忘れて、環境問題について語り合いました。
また、6月1日には、10年来の友人である滋賀県甲賀郡 (知的障害者との生活ということでは名実共に最先端を行っています)で障害者の生活支援センター「レガート」の所長牛谷正人さんが遊びに来るというので、山口市内で「表現と対話の集い - 番外線その2」を行ないました。連絡があってから10日あまりの準備期間でしたが、「障害を持った児童、大人への地域生活支援」に対する関心、ニーズが山口県内でも高まっているようで、26人の人が県内各地から集まりました。牛谷さんの話を少し聞いた後、5,6人の小グループに分かれて豊かな対話が操り広げられていました。松本さん、牛谷さんのようにふらっと立ち寄ってくれて、そこから新しい出会い、対話が生まれるというのも、とても生き生きとしていてよいものです。
(8)その他:高校生や大学生が、紹介されて、泊まりにきます。不登校であったり、親子関係に悩んでいたり、あるいはおもしろそうだからちょっと寄ってみただけであったりです。 (一泊2食付き無料。ただし、私の知人からの紹介に限っています。)この3年間でやってきたことは以上です。最終目標にしていること (重症心身障害の人々への地域支援、地域生活)はまだ形になっていませんが、ぼちぼちとやっていければと思っています。7年後にはなんとかなるだろうと気軽に考えています。 (原発事故や新ガイドライン法などの延長線上に破壊的な事態が起こらなければ)。
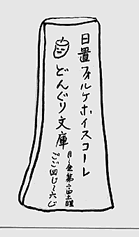
最後に、この3年間の活動の中で考えたことを整理してみましたので、思いつくままに書いてみます。みなさまの活動のヒントになるとうれしいのですが。ご意見をぜひお寄せください。
- 小さな変化を大切に。 (千里の道も一歩から)。ただし、さざ波を立て続けるだけの「情熱」を持って。
- 自らの情熱を枯渇させない工夫を (そのひとつは「本物」と出会うこと。そのためには、協会のセミナーはとても大事です。デンマークにも2、3年に1度くらい行けるともっとよいのでしょうが)。
- 去るものは追わず、来るものは拒まず。
- 対話には、人数の限界がある。小さな集まりをたくさんやろう。3人集まればなにかができる、何でもできる。 (3人寄れば文殊の知恵)
- (できるだけ) 敵をつくるな。嫌だと思う相手に対し、否定的な言い方はしない。よいことはやってみせる。
- マスコミよりも口コミを大切に。でも時にはマスコミも利用しよう。マスコミ関係者もひとりの人間。
- 学ぶということの唯一の証は「変わる」ということ。 (これは確か林竹二さんのことばでした)
- 共に食べること、飲むことを大切に。でも残り物が少なくなるように。 (ひとり、ひとり分の一品持ち寄り、缶ピールでなくビンビール)これが意外と難しい。
4 最後に - これから新たに活動に加えたいこと -
- 多くの人々の意欲を失わせるような競争がはやくから仕組まれた日本のありように抗するために、トロプスやイドラットフォルスクなどをもっと地域の子どもたちとも楽しめるように学んでいきたいと思っています。
- 音楽を生活の場に。
- 自給自足率のアップ。
- 風力発電などクリーンなエネルギーによる自家発電。
- 民衆主導の地方政治に。
夢はどんどんひろがります。妻にはしばしば「妄想だ」と言われます。 (私もそう気づくことがたまにありますが)一歩ずつ確実に歩んでいることを確認しつつ、夢を話りあえることは、それ自体とても楽しいものです。これからも、グルントヴィ協会の方々ともたくさんの出会いと対話を積み重ねたいと思っています。お近くをお通りの際は、ぜひ「日置フォルケホイスコーレ」にお立ち寄りください。
(求む)
古くなって使わなくなったレゴブロック (パラパラで結構です)と家で眠っているコンピューター (Windows3.1または95) があれば譲って下さい。
日置フォルケホイスコーレ連絡先
〒759-4401 大津郡日置町堀田 廣岡綾子 TEL/FAX:0837-37-5005