
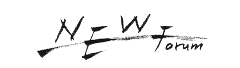
ノースウエスト・アース・フォーラム
川上私記
お答え

 |
ノースウエスト・アース・フォーラム川上私記お答え |
 |
あれはあくまで、私記、回想です。
最終の一節に、アフガンと日本の関係に触れたのは、少し場違いだったかとも思います。余り普段は報道されない、報道されても誰も注意を払っていないであろうアフガン・日本関係(経済以外にはほとんどない)について、小生の手元にあった最近の「情報」(というほどのものでもない)を記述したまでです。眼目は、アメリカ自らの世界戦略に基づいてアフガンに侵攻し、破壊と殺戮を繰り返し、またしても日本がアメリカの後始末に狩り出されている、という点です。それ以上でもそれ以下でもありません。
この数十年、「援助」については実に多くの論議が、世界的に、なされてきました。小生も1972年の国連貿易開発会議 (チリ・サンチアゴ) を取材して以来、元経済部記者ととして、各国訪をれるたびに、大きな関心を抱いてきた次第です。総論的には、私は次のように分析します。常識といえば常識です。これ以上のことは、専門家に質問してください。
援助とは何か。
1)世界には、貧しい国が多い。人が困っていたら助けるのが当然である。人道的観点。
2)貧しい国を金銭で援助すれば、そのカネはその国の物資輸入につながる。従って先進国の製品が売れる。先進国の経済に、ひいては世界経済の発展に役立つ。
3)国威発揚と諸国への影響力拡大としての外交の手段。
民間援助と政府開発援助
1)民間会社は利益追求が目的だから、本来、援助にはなじまない。
2)従って被援助国である後進国は,先進国の政府開発援助のほうを望む。そのほうが金利も安い。ある場合には、無利子。
ヒモ付きとヒモなし(この項目以降は主として政府開発援助にかかわる)
1)ヒモ付きは援助のカネの使い道を指定して、援助する。
2)ヒモなしは、使い道を、被援助国に任せる。
援助額と援助対象国はどう決まるか
国家予算の配分の中で、外務省が要求する.他の省庁との予算争奪戦になる。援助対象国と額ははそれまでの実績やその時々の援助国と被援助国の経済情勢、国際情勢によって決める。
だが、どんぶり勘定と批判されることも多い。担当者の声の大きさと交渉術にも左右されるだろう。日本の場合は、国際社会あるいは米国の要請に左右されることも多い。(今回のアフガン援助も例外ではない。米国の肩代わり、と呼ばれる)。拙稿私記に記したアフガン援助などはその例でもある。
援助はどう使われるか(ヒモなしの場合)
被援助国の政府による工事の発注とか、製品の輸入とか。使い方は、commercial base だから、これに援助国(むろん他国の会社と競争の場合もある)の民間会社が応じる。
援助の問題点
援助は基本的には、本来の目的のその国全体の経済発展や民生の向上、インフラ構築に使われている。だが、無駄遣いも多い。小生が実際に見聞した例では、エジプトのカイロに日本援助でオペラハウスを作った。食うや食わずのエジプト人にオペラハウスとは、心ある人々の失笑を買った。
そのくらいならまだ良い。カネが要路の政治家や経済人のポケット、あるいは一族経営の会社の利益に回ってしまうことがままある。現在も構造はさして変わっていないかもしれない。古くは、銀座の根本某という女がインドネシアのスカルノ大統領に献上され( 同国はイスラム教国だから法律上は妻4人までOkではあるが )、大統領死後数十年デビという名で派手に暮らしている、のも日本のインドネシア援助と無関係ではないだろう。
「援助」というと、誇り高い後進国が嫌がるので、最近は「経済協力」と言い換えているようだ。日本の援助は当初、特に東南アジアが中心で、戦場にして申し訳なかったという「賠償」の意味が濃かった。
だが、20世紀末には、西欧列強が食い荒らした後の、アフリカにもばら撒いた。「国連安保理の常任理事国選出の際はよろしく」という選挙運動の意味が濃かったのだが、そのときになると、アフリカ諸国は中国の指示に従って、日本の常任理事国就任反対にまわった。
(終わり)
March 21, 2010