

 |

画像の取り込みにデジカメとともにイメージスキャナーへの関心も高くなっています。スキャナーにはいろいろなタイプがあり、その中でフラット・スキャナーが中心です。しかし、このタイプはかなり机の面積を占めます。
キャノンではこのたびカラーのシートフィード・スキャナー「CanoScan 300S」を発売しました。300(幅)×70(奥行)×73.5(高さ)mmで1.5Kgと小型軽量ながら、300dpi×600dpi(主走査×副走査)と標準並の解像度でA4用紙まで取り込みができます。同社によればセンサー部と原稿が接触する独自開発の密着型カラーイメージセンサーを採用することで、機器本体の大幅な小型化ができたそうです。
このタイプの何よりも便利なことは、使用しないときには簡単に取り外して片づけられることです。しかもパラレルポートから入力できるタイプですから、デスクトップだけでなくノートパソコンにも取り付けが可能です。価格は39,800円ですので、おすすめできる商品といえるのではないでしょうか。

ビデオカメラの楽しみ方(1)
(1) 宝の持ち腐れ
最近のニューファミリーは、第一子が誕生するときまでに半数近くの家庭でビデオカメラを持っているそうです。多分このコーナーの読者では、大半の方が持っているのではないでしょうか。
しかし所有している皆さんに聞いてみると、使ったのは最初だけで最近はあまり写していないという人がほとんどです。その理由は撮るのが難しい、うまく写せない、面倒だ、が大半を占めます。どうもこれはビデオカメラの本質的なことがわからなくてうまく使いこなせないのが原因のようです。せっかく高価な買い物をしたのに残念なことですね。
ということで、このような方のために、ビデオカメラについてあれこれを書いてみたいと思います。
(2) ビデオカメラの発展
筆者とビデオカメラのつき合いはもう25年になります。残光性のブラウン管を使ったSSTV用に、業務用として使われていたモノクロのカメラを入手したのが始まりです。それから最初のカラーカメラは、プロのカメラマンと同じような肩置き型の大げさなものでした。
このVHSカメラのおつき合いは結構長く、VTRは分離したセパレートタイプのものです。かなりの重量で、それに大げさですから野外で撮るときは結構勇気がいるものでした。
そこに登場したのはソニーのパスポートサイズの「ハンディーカム」です。8ミリビデオテープを使って小型化した画期的なマシンでした。スチールカメラと同じ程度の大きさでビデオが撮れるのですから、機動性が抜群でした。その後、各社の製品は小型で高性能になり、今度はシャープが液晶ディスプレーの付きのいままでの概念を覆した「液晶ビューカム」が登場したのです。
8ミリビデオが第二世代とすれば、ディジタルテープ(DV)の出現は第三世代ホームビデオの始まりです。小型テープに合わせて超小型に設計して、世間をあっと言わせたのはビクターの「GR-DV1」でした。何しろポケットにすっぽり入ってしまう大きさですから、これでまた行動範囲が広がりました。
その後、各社から長時間撮影可能なもの、デジカメ兼用のものなど、いろいろ特徴のある商品が発表されています。なかでも驚きは、いままでのハンディカメラの大きさでありながら3CCDシステムを組み込んだパナソニックの「NV-DJ100」です(写真4)。色彩がきれいで理想の方式といわれている3CCDですが、小型化が難しいといわれていました。これは業界の常識を破って実現した自慢の商品なのです。
このようにこの分野もパソコンやデジカメと同じように、最近はつぎつぎと新製品のラッシュが続いています。購入するときは、主にどのように使うかよく考えて決めることが肝心です。
(3) カメラを固定せよ
どのハイテク機器も同じですが、特にビデオカメラは基本的なことを守らないと見るに耐えない映像になります。最近の製品はオート機能が進んでいますので、重要なことはただ一つ「カメラの固定」です。これは簡単なようで実に難しいのです。
スチールカメラと違うと思うばかりに、どうしても振り回したくなります。それをじっと我慢すると、被写体の方が動いてくれるのです。といってもやはりパンニング(カメラを左右に動かす)することによって風景のつながりが出てきます。このときは必ずズームをワイドの位置にして、90度動かすのを10秒から20秒くらいかけてゆっくり回すことです。
カメラの固定する最良の方法は、三脚の使用です。しかしアマチュアでは場所や状況で使うのが難しいことが多いと思います。手持ち撮影の基本は、やはりレンズをワイドにして足を開いて両手で脇を締めてカメラを持つことです。そしてアイカップを眼に強く当てて固定することで安定度がずっと増します。
以上のことさえ守れば、誰が写してもゆっくり楽しむ画面を作ることができます。
(4) 旅ビデオ
筆者の場合はビデオカメラの目的がはっきりしています。それは旅行の記録なのです。スチールカメラと違って動画は臨場感があり、それに音が加わりますと旅の思い出が強く再現されます。二度と行けない辺地の記録などは、私にとっては貴重な財産なのです。
この場合はカメラの選択は、できるだけかさばらないカメラが最上です。いつでもどこでも簡単に撮影できるからです。しかしもう一つのチェック点は、電池の問題です。小型なカメラほど電池の使用時間が短いので、数本の予備が必要になります。
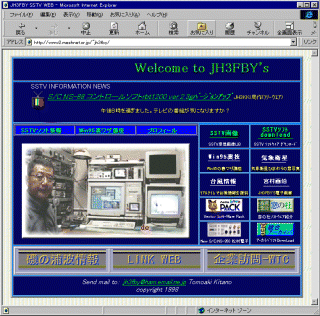 |
紙面の都合で今回はこれで終わりです。次回は変わった使い方や楽しみ方のヒントなどをお話ししてみましょう。

今月のホームページ
★ JH3FBY北野さんのページ
URL:http://www2.biglobe.ne.jp/~jh3fby/
JH3FBY北野さんのホームページです。ここにはいろいろな情報が詰め込まれています。「SSTVソフト情報」は、ほとんどのシステムが詳しく紹介されており、ここからダウンロードできるようになっています。パソコンいじりの好きな人には「Win95裏ワザ講座」が高度なテクニックを紹介しています。
このホームページの特筆はサーフィンのメッカ「磯の浦波情報」の画像で、毎日更新されており関西サーファー必見のページとなっています。
