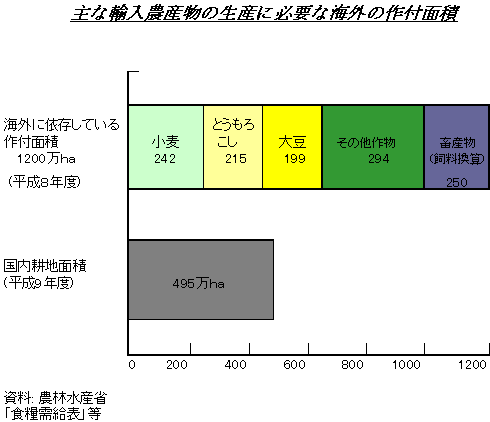食料自給率と食生活
◎ 食料自給率とは
国民の食生活が国内の食料でどれだけまかなわれているかを示す指標です。
自給率には、品目別自給率、穀物自給率、供給熱量自給率(カロリーベース)のほか金額自給率等がありますが、国民が実際に営んだ食生活を国産でどれだけ賄っているかを示す指標である。こうした観点からカロリー比率で計算する供給熱量自給率で総合的自給度会いを示すこととしている
『供給熱量自給率計算の方法』
国民1人1日当たり国産供給熱量
供給熱量自給率= ![]() × 100
× 100
国民1人1日当たり供給熱量
◎ 日本型食生活とは
日本人の食生活は日本型食生活とよばれ、伝統的な、米、魚、野菜、大豆をはじめとする素材に、肉、牛乳、乳製品、油脂、果実など豊富に加わって、多様性があり、栄養バランスが良い。こうした料理の組合せの栄養上の有効性が国際的にも認められている。
【昭和60年と平成9年の栄養バランス(PFC熱量比率)の比較(%)】
栄養バランス〔たん白質(P)・脂質(F)・炭水化物(C)のバランスを見ると崩れつつあります。
|
『』は適正比率 |
たん白質(P) 『12.3』 |
脂 質(F) 『25.0』 |
炭水化物(C) 『62.7』 |
|
昭和60年 |
15.1 |
24.5 |
60.4 |
|
平成 9年 |
16.0 |
26.6 |
57.4 |
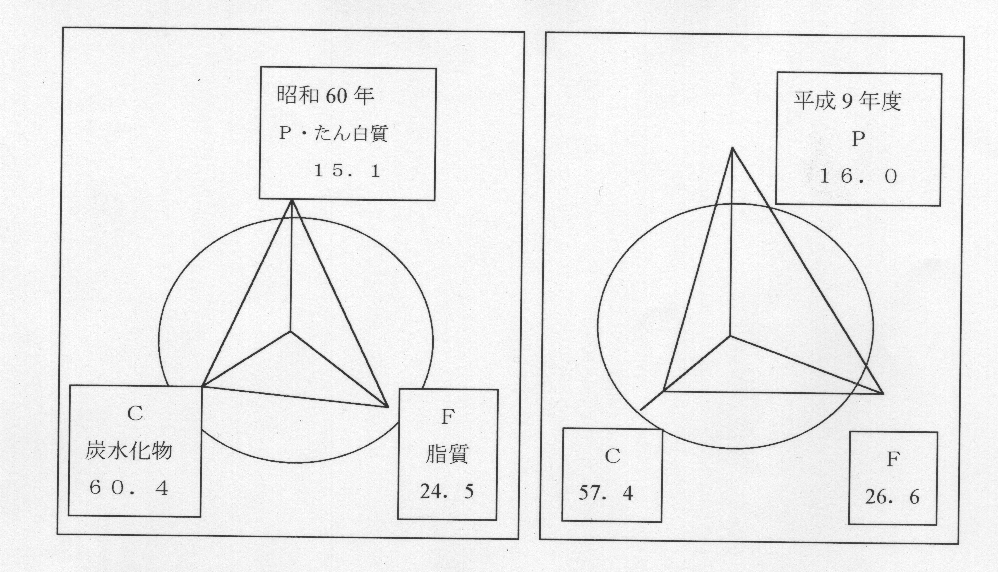
資料:厚生省「国民栄養調査」、「日本人の栄養所要量」より
和食の朝食は自給率100%であるお米(ごはん)が消費熱量の半分近くを占めることから、献立全体のの自給率は56%に達し、また、脂質熱量比率も適正比率の範囲内となります。
一方、洋食の朝食は、小麦、牛乳、乳製品、鶏卵等、自給率が低い食材が中心となることから、献立全体の自給率は14%にとどまり、また、脂質熱量比率も適正比率を大きく越える53%となります。
| メニューの構成 |
熱量 (Kcal) |
自給率 (%) |
国産熱量 (Kcal) |
PFC熱量比率(%) |
||
|
P 蛋白質 |
F 脂質 |
C 炭水化物 |
||||
|
和 食 |
561 |
56 |
317 |
22 |
25 |
52 |
|
洋 食 |
555 |
14 |
76 |
16 |
53 |
32 |
出典・食糧庁・(財)全国米穀協会
食料自給率が低下した大きな要因は、食生活の高度化、多様化が進む中で、自給率100%のお米の消費が減少する一方、畜産物や、油脂のように原料として大量の輸入農産物を必要とする食料の消費が増加し、農地が狭くて平坦でない日本での農業生産だけでは対応が困難になったことです。