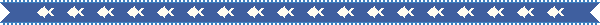|
美しい人魚の姫が人間の王子に恋をし、自分の声と引換えに魔法使いの力を借りて人間になりました。
二人は海辺で再会し、王子は話すことのできない人魚姫を哀れに思い、彼女を城へと連れ帰ります。
優しい王子をますます好きになる人魚姫でしたが、王子はすでに隣国の王女と婚約していたのでした。
それを知った人魚姫は嘆き悲しみました。
その悲しみに気づいた姉姫たちは、長く美しい髪と引換えに魔法使いから短剣を受け取り、人魚姫に渡します。その短剣で王子を刺し、その血を浴びれば人魚姫は元の人魚に戻ることができるのです。
人魚姫は短剣で王子を刺そうとしますが、愛しい人にはそれをすることができません。
そして、王子の愛を手に入れられなかった人魚姫は、海の泡となり、消えてしまいました。
◇◇◇
「ばっかよねぇ」
そう呟いたのは、穏やかな波に豊かな金色の髪を揺らめかせている人魚だった。
「ティアったらなんてこと言うの!」
碧(みどり)に光る岩の上に座っているシャラは大きな声を出した。
「だって自分を愛してくれなかった男のせいで死んでしまったんでしょ? この人魚の姫は」
呆れたようにティアはすぐ上の姉に言った。
「あなたにはこの人魚の気持ちはわからない?」
ティアの大きな瞳をまっすぐに見つめて、シャラは問う。
「姉様にはわかるの?」
「わかるわ。本当に愛した人なら殺せる筈がないでしょう」
「わたしはわからない。愛してくれないのならもういらない。わたしなら新しい恋をするためにその人を刺すわ」
シャラはふぅと静かに溜め息をついた。
「そうね。実際あなたはそうしてきたんだもの。もう片手では数えられなかったわよね?」
「両手ならおさまる数よ」
「あなたも本当の恋をするとわかるわ。自分が犠牲になってもその人の幸せを望むようになることを」
ティアにはシャラの言葉の意味を理解することはできなかった。
本当の恋?
わたしはいつだって本気で恋をしている。
人間の足をもらうのに自分の声を犠牲にする。薬はにがくて、死ぬほど苦しい。だけど本当に好きな人のためだからそれも我慢できる。それなのにわたしを愛してくれないのは許せない。死ぬのは当然だわ。
ティアは口には出さなかったが心の中でそう思った。
「ティア、もう陸に行くのはおやめなさい。所詮人魚は人間とは結ばれないのよ」
「でもわたしは行くわ。あの人に、明るい空の色をした瞳のあの人に逢いに行くわ。今度こそわたしを愛してくれる人なのよ!」
ティアは尾をひるがえし、素早く泳いだ。
「ティア! 泣くのはあなたなのよ!」
必死で止めるシャラの声はティアには聞こえない。たとえ聞こえたとしても行くのをやめるようなティアではなかった。
ティアは振り返りもせず、そのまま魔法使いのいる岩場へと向かって泳いだ。
「また来たね、ティア」
足元に届くくらいの長い銀髪の魔法使いは、苦笑まじりにティアを迎え入れた。
「人間になりたいの。薬をちょうだい」
早く出せと言わんばかりにティアは勢いよく右手を延ばす。
「さて、どうしたものか」
左手を口にあて、魔法使いは優雅に微笑む。
「いつものようにこの声をあげるわ。だから早くちょうだいったら!」
口調がだんだん荒くなっていく。
「そう言われてももう声はいらないよ。どうせ返さなければならないからね」
「あなたもわたしは人間と結ばれないと思っているの? だからそう言うのね!!」
「今までだってそうだったろう? 君は何度も陸に行ったが結局は戻ってきた。今度もそうなるのではないのか?」
若く、端整な顔立ちの魔法使いは、ティアの心に痛くつき刺さる言葉を口にした。
「そ、そんなことないわ! 今度こそ……」
ティアは反論しようとしたが口ごもってしまった。ついさっきまでの勢いが嘘のように。
「まあ、いいだろう。しかし薬を渡すのも今回限りだ。その可愛らしい声もそのままでいい。ただし、その声で自分の正体を言ってはいけない。もし自分からそれを口にしたら、その時はすぐに体は消えてなくなるぞ。それでもかまわないか?」
「……ええ。陸に行けるのならどんな条件でものむ。それに声が出るのなら、きっとうまくいくはずだもの」
すがるように魔法使いの服をつかみながら、ティアは紅(あか)い瞳を見上げた。
「ほら、薬だ」
魔法使いは親指ほどの小さな透明な瓶を取り出した。その中には深い海の底の色をした液体が入っている。
「今度こそ失敗はしない……」
ティアは渡された小瓶をしっかりと握り締めると、陸に向かって泳ぎ出した。
「さて、そううまくいくかな」
魔法使いは楽しむように口元に笑みを浮かべながら、ティアの後ろ姿を目で追った。
◇◇◇
喉が焼けつくように熱い。腰の下の尾がある部分が痛い。体が引き裂かれるよう。
これは人間になる時の感覚。あと少し我慢をすれば、尾は二本の『足』となる。
あと少し。あと少しだけの我慢……。
「……」
痛みがひき始め、ティアはゆっくりと目を開けた。
「気がついたかい?」
まだはっきりしない意識の中、男の低い声が耳に入ってきた。
声のする方へ目線を移してみる。ティアの碧色の瞳に自分を見つめる空色の瞳が映った。
見覚えのあるやさしい空色の瞳。
「?!」
ティアはハッとして飛び起きた。
今まさに目の前にいる青年こそ、ティアの想い人だった。
この瞳に逢いたくて、苦しい思いをしたのだ。
しかし、どうして逢いたいと思っていたこの人が目の前にいるのかわからなかった。
人影のない岩場で魔法使いからもらった薬を飲んだのまでは覚えている。前回までなら、人間になったのを確認してから恋する相手の元へ行った。一体どういうことなのか……?
ティアは予想していなかった出来事に直面して驚いていた。
そんな彼女に、青年は尋ねた。
「どうしてあんな人の来ないところで倒れていたんだい?」
瞳と同じく優しい雰囲気の声だった。
しかしティアはその質問に答えられない。
「気分が悪くなっただけなのか?」
何も言わずに頭を左右に振る。
「じゃあどうして……?」
答えを口にすることはできず、ただティアは黙っていた。
「君の名前は?」
困ったように青年は再び尋ねた。
この質問になら答えることはできる。紅い小さな唇がゆっくりと動いた。
「……ティア」
「ティアはどこからきたんだい?」
「……」
再びティアは口を閉じた。
名前以外何も言わない少女に、青年は不思議そうにしながらもいくつか質問を続けた。しかし、どれもティアには答えられなかった。
「困ったなぁ」
青年は右手で頭をかきながら、枕元の椅子に座った。
「だめですよ。リーフ様。一度にそんなに聞いたりしては」
ドアを開けて、そう言いながら部屋へ入ってきたのは、少し年配の女だった。
「ああ、セラか」
「まだ病人なんですよ、このお嬢さんは。質問ならあとになさいませ」
「わかったよ。それじゃ後はセラにまかせるかな」
リーフと呼ばれた青年はティアの額に手を当てながら微笑んだ。
「熱はないようだね。でももう少しゆっくりと休むといい。また後でくるよ」
リーフはそう言い残して部屋をあとにした。
ティアは今だ自分のおかれている状況が理解できなかった。
どうして愛しいあの人が目の前にいるのか。
どうして自分がふんわりとやわらかい白いベッドの上にいるのか。
ティアは改めてあたりを見回してみた。そこは大きな窓のある広い部屋だった。眩しい陽光がさしこんでいる。
「あの、ここは……」
思い切ってセラに尋ねてみた。
「ここはリーフ様のご実家のレングヴィ家の別荘ですよ」
セラはにっこりと笑いながら答えてくれた。
「今朝、散歩に出られたリーフ様があなたを連れて戻ってきたときは驚きましたよ」
「あの人がわたしを……?」
「ええ。リーフ様はずぶ濡れだったあなたを抱えてね。どうしたもんかと思ったけど、まあ、まずはゆっくりとお休みなさい。ここはリーフ様と私しかいないからね」
セラはおおらかな性格なのか、突然舞い込んできた少女に対し、特に不信に思ったりしていなかった。
「ちゃんと寝てるんですよ」
布団をかけ直し、セラは部屋から出ていった。
ティアはまだ変な感じがしていた。しかし太陽の匂いのするふかふかのベッドは気持ちよく、再び眠りに落ちてしまった。
海辺に建つレングヴィ家の別荘は、部屋数も多く、とても広かった。廊下に飾られた絵画や調度品も高価なものばかり。別荘とはいえ、外も内も豪奢な造りだった。
ティアはその別荘に住むことになった。名前以外何も言えない少女に同情したのか、リーフとセラは優しく迎え入れてくれた。
気ままに暮らす若い主人とその乳母。
どうしてこんな広い場所で二人だけが暮らしているのか、そしてどんな事情があるのか、ティアは少し気になったが、それ以上にどうしたら愛しい人の心をつかむことができるのかを考えるのに頭がいっぱいだった。
それでも、普段は食事のしたくや掃除などセラの手伝いをしていた。セラもいろいろと教えてくれ、料理などしたことのないティアでも半月たった今では、リーフの好物の焼菓子などを作れるようになっていた。
「そろそろお茶にでもしようかね。ティア、リーフ様を呼んできておくれ。二階のいつもの部屋にいると思うから」
「はーい」
ティアは元気よく返事をして、台所を出た。長い廊下を通り、階段を上って、リーフがいる筈の部屋に向かった。
コンコン。
扉をノックしてみるが、返事はない。
もう一度ノックしたが、結果は同じだった。
ティアはそっと扉を開けて中に入ってみる。
南向きのその部屋は日当たりがよかった。
大きなガラス窓からあたたかな陽光が差し込んでいる。その窓辺には、寝椅子の上で静かな寝息をたてているリーフがいた。
ティアはリーフが起きないように静かに近づいた。
気持ち良さそうなその寝顔はなんだか子供のようで、そして愛しくて、ティアはずっと見ていたかった。
その時、リーフの唇がかすかに動いた。
「……アナ」
はっきりとは聞こえなかったが、誰かを呼んでいるようだった。
「行くな、ディアナ」
ティアの鼓動が早くなる。
今度ははっきりと聞こえた。
ディアナ。
それは女性の名前のようだった。
誰なの?
その名前の人はリーフにとってどんな関係がある人なの?
まさか……?
ティアの心に苦い思い出がよみがえる。
不安になりながら右手を握り締め、足を一歩後ろに引いた。その時、寝椅子の横にあった小さなテーブルにぶつかり、置いてあった本が床に落ちた。その音が聞こえたのか、リーフは目を覚まし、ゆっくりと瞳を開けた。
「……ティア?」
愛しい人は何事もなかったかのように、優しく微笑んだ。
いつも憧れていた空と同じ色の瞳。
いつまでもこの瞳に見つめられていたい。
ティアはリーフに抱きついた。
「お、おい。どうしたんだい」
ティアの突然の行動に多少驚きながらも、リーフは優しく抱きとめた。
左手はゆっくりと金色の髪を撫でている。
「子供みたいだな、ティアは」
ティアはそう言われても、しがみついて離れなかった。
誰にも渡したくない。渡さない。
この人だけは誰にも渡さない。
今までにないほどの強い想いが、ティアの中に生まれていた。
ディアナという名が気になってはいたけれど、ティアは誰にも聞けなかった。
しかし思いがけずにある日突然、欲しかったその答えを手に入れることになる。
それは、セラと一緒に、今まで使っていなかった部屋の掃除をした時だった。少しだけ埃をかぶったクローゼットの中を整理していた時、その片隅に1枚の写真が落ちていたのにティアは気がついた。
拾い上げたその写真には、金色の長い髪、そして碧色の瞳の女性が写っていた。
ティアよりも年上の女性。ちょうどリーフと同じくらいの年齢にみえる。
年齢こそ違うものの、その女性はティアの容貌によく似ていた。
「あの、これは……」
ティアはその写真をセラに見せた。
セラは一瞬顔をしかめた後、ティアにそれを捨てるように言った。
しかしどうしても気になったティアは、恐る恐るその女性が誰なのかを尋ねた。セラは仕方がないといった感じで口を開いた。
「リーフ様が昔お好きだった方だよ。この浜辺で出会って恋に落ちて、でもあっさり別の男とここを出て行った。リーフ様にとっては触れてほしくないことだから、その写真は決してリーフ様に見せてはいけないよ」
この人がディアナだ。
直感で感じ取った。
リーフはまだこの人を忘れてない。この間の、切ないようにリーフの口から漏れたのはこの人の名前だったのだ。自分でもディアナに似ていると思った。自分でもそう思うくらいなのだ、きっとリーフもそう思っているに違いない。
わたしはディアナの身代わりだっただけなの?
リーフが愛している人に似ているからここに置いてくれたの?
リーフはわたしを見ていなかった。わたしを通り越して、ディアナを見ていた。あの優しさはわたしに向けられたものではなかった。
ティアはその写真を思わず握りしめた。
そんなティアに追い討ちをかけるかのように、セラは続けて言った。
「それにリーフ様にはご婚約のお話が決まっているから、もう必要のないものだしね」
「ご婚約……?」
「そう。来週ここを発って本宅に戻られたら披露パーティーが行われるんだよ。リーフ様はあまり気が進まなかったようだけれど、その方と結婚されたほうがおしあわせになれる筈。旦那様も奥様もお喜びになっているからね」
リーフに婚約者がいた。
このままではまた好きな人と一緒になることができない。
胸の奥がずきずきと痛む。
悲しみが全身を襲う。
二重のショックを受けたティアはその日、自室にこもったまま、出てこなかった。
◇◇◇
満月に一歩手前の月が南の夜空に輝いている頃。ティアはそっと部屋を出た。
気配を消しながら、迷わずまっすぐに目的の場所へと向かう。
茶色の扉の前で立ち止まった。
豪奢なレリーフを施した扉。この扉の向こうで彼は眠っている筈。
ティアは一呼吸した後、静かに扉を開けて中へ入った。
後編へ続く
|
 小 説
小 説 小 説
小 説