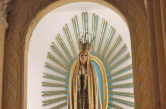到着・市街 中国2回目は、香港とマカオにした。とにかく安いことと近いので気軽にいける。また世界遺産やカジノがある。仕事の関係もありカジノ体験もしたく是非ともいきたかったところである。それに上海とどう違うか楽しみであった。 日本からの飛行機の中では機内食もきちんとでた。ワインを2本ほど飲んでしまった。 思ったより早く香港国際空港についた。クリスマスが近いので雪だるまが迎えてくれた。 実は、空港が香港市街の近くにあるときに来たかったのである。写真でよく見た、香港の中心地から近くの九龍にあった啓徳空港から飛び立つ飛行機の、高層ビルの上すれすれに飛ぶ「香港アプローチ」を見たかったが、今は移転し人工の島の上にある。空港からバスでホテルに向かったが、上海と同じように宿泊ホテル別に観光客をおろしていった。 ホテルからほど近いところに海があり、窓からは海をゆく船がよく見え、たくさんの船が行き来していた。   ホテルの前のビルはどれもがかなり古い。洗濯物を無造作に干している。 こんな中国独特の雑雑とした面白さが好きである。ホテルの前から香港名物の二階建て電車が走っていくのが見えた。 これにも乗りたかったのである。 ホテルのフロントで両替をしたが、英語しか通じなかった。 「日本語を勉強してほしいね」と思っているが、向こうとすれば、「外国へ来るのならせめて英語くらい話せるようになってから来てほしいね」と思っているかもしれない。 日本国内でも私の日本語は、時として通じなくて「意味不明」といわれる。それが外国語となると言わずもがなである。 もう少し英語が話せたらと、ずっと思いながらアラカンとなってしまったのである。ホテルはアイランドパシフィックといって、ごく普通のホテルであった。接客もそれなりであった。部屋からの景色はまずまずであった。正面玄関からの景色は、洗濯物の多いビルで、香港そのものという感じがした。 夕食を食べに街に繰り出した。大通りに出て念願のトラムに乗った。電車の造りそのものはやや時代遅れの感は否めないけれど、2階立てでありスピードもゆっくりで景色を楽しみながら移動できる。2階に座り窓を開けて風を感じながら行くのは楽しい。しかしよく揺れる。 見たかった2階建て電車。それも路面電車である。いいなー。 今、日本各地でこんな路面電車があればいい観光資源になると思う。特に和歌山などは和歌浦との間をこうした電車で行き来出来たら楽しいのにと思う。それにしても中国の人のパワーは目を見張るものがある。 私たちは、夕食にガイドブックに載っている中華料理店(当然であるが)に向かったのだが、トラムに乗り間違ってというより行き過ぎてしまい駅員に身振り手振りガイドブック参照で聞き、乗り換えた。 トラムを降りてから店を探して歩き回った。町ゆく人々は活気にあふれていた。観光客も多くいろいろな言葉が町を飛び交っていた。日本のデパートもあちこちにあった。この喧噪の中にいると、40年ほど前の大阪の商店街を思い出した。中国は大阪の雰囲気で親しめる。  歴史的にも古くから交流があったからだろうか。とにかく中国の元気さを感じた。料理店は程なく見つかった。やっとたどり着いた店は、かなり高級な雰囲気が漂っていた。席がなく表で順番を待った。結婚式の披露宴らしきものもやっていた。こうなると中国の人は皆にぎやかである。 歴史的にも古くから交流があったからだろうか。とにかく中国の元気さを感じた。料理店は程なく見つかった。やっとたどり着いた店は、かなり高級な雰囲気が漂っていた。席がなく表で順番を待った。結婚式の披露宴らしきものもやっていた。こうなると中国の人は皆にぎやかである。ふつうに待つのはさほど苦にはならないが、腹ぺこで順番を待つというのはあまりしない。 しかしここまで来てそのまま帰るわけにはいかないので待った。 スリットの深い中国服を着たきれいな女性が行ったり来たり忙しくしていた。 退屈なので動きを追っていたら、娘に「あまりじろじろ見ないで」といわれた。 少し目線がオジンモードに入っていたかなと反省。 やっとお呼びがかかり席に着いた。きれいなスペースであった。 普段日本では食べられない料理でなおかつ比較的リーズナブルなものを注文した。 味は、さすがガイドブックにも載るだけのものがあった。 しかし中国のひとはよく食べる。私たちが腹いっぱい食べた量を遙かqにしのいでいる。 パワーの源はこんなところにあるのだろう。 その割にはアメリカやイギリスのように超肥満体というひとがいない。 やはり肥満のDNAが少ないのかもしれない。
マカオへ 香港での初めての朝食を食べたが、思ったよりたくさんお人が泊まっていた。日本人がもっといるかなと思ったが少なかった。ドイツ人らしき夫婦が食べていたが、終わった後はきっちりパンやリンゴなどいろいろなものを持って行った。 私も負けずに、パンとリンゴを持ち帰った。 朝、バスが迎えに来て高速船に乗り込んだ。マカオに向かうためである。ここでは、同じ中国なのにパスポートが必要であった。結構たくさんの人が順番を待っていた。のりこんだ007映画に出てきたような真っ赤なカタマラン船は、めちゃ速かった。
聖ポール天主堂(世界遺産) 聖ポール天主堂への階段。 ファサードを背にしてあちこちで記念撮影がされていた。世界中からの観光客で賑わっていた。  「このファザードには、多くの菊の花が彫り込まれており、これは、暗にキリシタンの迫害を逃れて日本からマカオにやってきた日本人の存在を示しているといわれている」 「このファザードには、多くの菊の花が彫り込まれており、これは、暗にキリシタンの迫害を逃れて日本からマカオにやってきた日本人の存在を示しているといわれている」とガイドさんが教えてくれた。 日本からの「キリシタン難民」が、当時のマカオで教会建設の重要な担い手になったといわれている。そのためがどうかわからないが、堂の中程には狛犬もあり、何となく和洋折衷の雰囲気があって面白い。 この聖ポール天主堂の完成した1637年は、日本ではちょうど島原の乱(天草四郎の乱)が起きた年である。マカオと日本は非常に強いつながりがある。というより、中国と日本は古来切っても切れない関係にあったといえる。  天主堂の周辺には土産物売り場があり、そこで中国のまんじゅうを買って食べた。なかなかおいしかった。 天主堂の周辺には土産物売り場があり、そこで中国のまんじゅうを買って食べた。なかなかおいしかった。このとき私はカメラは、ベッサRにオリンパスの28mmをつけていた。 近くの中国人らしき男性がニコンFMを持っていたので、 「Goog camera」 と話しかけると、うれしそうに 「Yes」 と返事してくれた。 私のベッサを見て、ライカを持ってるといってうらやましそうであった。フォクトレンダーと説明しても、彼にとってはやっぱりライカであった。きちんと説明できる英語力もないのでベッサはライカになってしまった。ま、いいか。 和製ライカタイプだものね。
ナーチャ廟、旧城壁、仁慈堂(いずれも世界遺産) 聖ポール天主堂の西側にナーチャ廟がある。1888年に神童ナーチャを祀るために造られた中国式の寺院で、ナーチャは有名な「西遊記」にも登場する道教の神ということであるが、西遊記を読んだが覚えていない。  ガイドさんの説明では、ナーチャは、母親のお腹に三年半もいて、その間に道教の僧から特別な力を与えられたいう。 西遊記は玄奘三蔵の話で、仏教だがナーチャの師は道教という、このあたりがややこしい。 いずれにしろ違う宗教が平和共存していたということで、いいことである。この廟の周辺の土塀が、ポルトガルが16世紀後半に築いたもので、懐かしい雰囲気を醸し出している。何百年もこうして存在しているのが不思議なくらいである。これも世界遺産である。 このあと、セナド広場、仁慈堂、民政總署大楼を順に歩いた。このあたりは古くから街の中心であり、いまもイベントや祝典の開催場所として利用されているという。 かなり長い距離が歩行者天国になっている。かつてはコンクリート敷きでクルマが通り、バス路線が敷かれていたらしい。 1990年代前半に、ポルトガル本国から敷石職人を呼び、ポルトガルの石を使って現在のモザイク模様のカルサーダス(石畳)が敷設されたという。中央には噴水があり、「噴水池」という。 仁慈堂、民政総署、ビジネス・ツーリズム・センター、郵政局などが周囲を取り囲み、華やかな雰囲気の広場である。 特にセナド広場に面する純白の建物が、日本や中国を管轄した初代マカオ司教ドン・ベルキオール・カルネイロが1569年にアジア初の慈善福祉施設として設立したもので、西洋医療を取り入れた病院や、孤児院、養老院も備えていたいう。 現在は建物の1階が公証役場となっている。
聖ドミニコ教会(世界遺産) メキシコのアカプルコから来たドミニコ会スペイン人修道士によって1587年に建てられた礼拝所がその始まりで、現在の教会は1828年に再建されたものといわれている。  コロニアル風バロック様式の(正面外壁は、クリーム色のあざやかな壁に純白の漆喰で繊細な装飾が施され美しい。濃いグリーンの鎧戸が、いいアクセントになっている。 「バラの聖母像」と呼ばれる聖母マリア像が祀られているが、これが中国語で「バラの教会」と呼ばれる所以だという。 アカプルコから来た修道士によって建てられたというところが面白い。古くからの国際都市、香港の面目躍如というところである。マカオ半島は、少なくとも5世紀以降、広州と東南アジアを行き来する商船などが、船の修理や水・食料の補給のために立ち寄った場所であり、海のシルクロードの一部を担う港町として、ローマに向けシルクを運ぶ交易船でにぎわっていたという。 1277年には蒙古の襲来から逃れて、南宋(1127年〜1279年)の難民5万人がこの地に移り住んできたという記録もある。明朝(1368年〜1644年)では民間貿易が禁止されたが、広州は南海諸国との朝貢貿易(政府が管理する交易)の入港地だったことから、地域から人々が集まり、そして住み着き、半島を意味する澳門(オウムン)と呼ばれる地域が形成されていった。当時、日本といえばは室町時代。海禁令によりあちこちに出没していた海賊と区別するため、幕府は明朝との間で勘合符を使った「勘合貿易」を行っていたという。 このようなことは、学校の歴史で習ったはずだけれどここに来てはじめて知った。 航海者ヴァスコ・ダ・ガマによりアフリカ喜望峰ルートが発見され、海制権を得たポルトガルが、さらなる富を目指して交易船を中国から日本へと差し向けその貿易のエリアを大きく広げたのである。 こうして他国に来て、歴史をひもとき日本と対比するとよく分かる。日本の歴史教育は、その方法が少し間違っているのではないかといつも思う。よその国とどうだったかという視点が抜けている感じがする。元寇にしろ広州・香港などとの対比があればよりわかりやすく、もし攻め入れられたらどうなるかという、想像も働かせられる。学校ではそこまで教えてくれなかった。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||