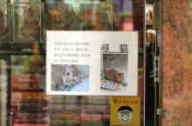| 香港・マカオ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香港 (2008年12月5日〜) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
媽閣廟(世界遺産) バスに揺られていった先は、媽閣廟であった。マカオ半島の南端の「媽閣山」のふもとにある。とはいわれてもどこがどこかさっぱりわからなかったのだが、マカオ内港の入り口に当たるといわれて初めて大体の位置がわかった。 媽閣廟の創建は1488年と言われおり、マカオで最も古い寺で外観からもその歴史の古さが伺われる。  日本では室町時代の後期で、加賀一向一揆が蜂起し、加賀国守護・ 日本では室町時代の後期で、加賀一向一揆が蜂起し、加賀国守護・ 冨樫政親を滅ぼした年である。 冨樫政親を滅ぼした年である。世界では喜望峰が発見された年である。 さて媽閣廟は広い敷地に、大殿、石殿、弘仁殿、観音殿などがある。 媽閣廟の由縁は、福建や台湾で信奉されている「媽祖」伝説によるものという。 「媽祖」は福建の漁民の娘で、心優しく、人助けをいとわなかったため、死後仙女になった。 仙女になった「媽祖」は、難破しそうな漁船の上に現れて幾度も危機を救ったため、漁民の安全を守る神として福建や台湾の沿岸沿いを中心に信奉されていた。マカオの媽閣廟は、明代に1艘の商船が難破しそうになったとき、神女がマカオ半島の上に現れ、安全に船を導いたという伝説がもとになっているという。難破を免れた船の乗組員たちが、後に神女が立っていた場所に建てた寺院が、現在の媽閣廟という訳である。 ガイドさんが、ポルトガル人が、はじめてマカオの地に上陸した場所も、この媽閣廟の岸ということを説明してくれた。 ポルトガル人が、上陸し現地人に地名を聞いたところ、「媽閣」(マーコウ)と返事をしたため、以後ポルトガル人は、この地域全体をマーコウ→「Macau」と称すようになったと言われ、言わばここがマカオ発祥の地であるといえる。 廟はたくさんの観光客や地元の人々でにぎわっていた。
ベネチアンマカオ(カジノ)・マカオタワー  昼食は、小高い丘の上にあるホテルであった。周辺はいかにもお金持ちの邸宅という感じの建物が立ち並んでいる。 ホテルはそんな丘の頂上近くにある。玄関を入ると、クリスマスが近いので、クリスマスツリーが飾られてあった。 料理はおいしかった。台湾、上海、そしてここ香港。マカオと食べたがいずれもおいしい。 日本人にあうのかもしれない。 昼食後ベネチアンカジノに行った。 会社で大阪にカジノを誘致しようと取り組む中で、一度行かなければと思っていたところである。途中の道の両側にたくさんのカジノがあった。建設途中のもいくつかあったが、建設がストップしていた。聞けば経済ショックで資金がなくなったのと入場客が減ったからだという。香港の建築現場の足場は竹であるため、建設をしていないとなんとなくわびしい感じとなる。それでもベネチアンはにぎわっていた。人工のベネチア風景がおもしろい。ゴンドラもあり舵取りが歌を歌っていた。 カジノゲームではスロットを少しやったが当然外ればかりで負けてしまった。 たしかに楽しくわくわくするスペースであるが、はまれば大変なことになるのは間違いない。 しかし観光資源としてはすごいポテンシャルを秘めている。沖縄にカジノを作れば観光客誘致と雇用確保ができる。 大阪にもほしい施設である。ただし、日本はいい施設があってもそれを維持する能力が足りないので、それを心配する。 マカオタワーは南灣湖の埋め立て地に2001年12月19日にオープンし、高さ338mある。東京タワーより背が高いのである。 地上233mの展望台からは、晴れた日なら中国本土、香港を遠く見渡せるというが、普段はスモッグでまず見えないのじゃないかと思う。テレビでよく見る世界最高位置からのバンジージャンプなどのアトラクションはここなのであるが、この高さを見るととても飛び降りる勇気はない。タワー下の建物の中には、レストランやカフェ、ショップ、映画館などもあり、私たちが行った折には何かファッションショーのようなもののリハーサルをしていた。
街角 二日目の夜は、大衆食堂へ入った。娘はせっかく香港まで来たのだからガイドブックにあるような高級店へ行こうと抵抗したが、やはりその街のことを知るには、大衆食堂が一番いいということで、飛び込みでそれらしきお店に入った。 店はすごく流行っていた。入れ替わり立ち替わりお客が来ていた。品物は適当に注文した。揚げ豆腐や餃子などいろいろ注文した。魚も注文したが、これは日本の方が美味かった。何となく泥臭さが抜けていない感じである。これは、東南アジアの川魚の特徴である。日本の鮎を初めて食べると青臭くて抵抗があるのと一緒で、なれれば特に問題ないだろう。とにかくどの料理もおいしかった。最後にお粥を注文した。食後は、大通りを歩いてホテルまで帰った。途中コンビニに立ち寄り、焼酎とお菓子などを買った。 三日目はショッピングからはじめた。ガイドブックを見ながら歩いた。ビルのデザインの奇抜なものが多く、それをウォッチングするもの面白い。朝の香港は活気に満ちあふれている。いかにも中国という感じである。
文武廟  香港がイギリス領になって間もない頃に建てられたという文武廟。香港の街の中ある。廟までの道は、少しわかりづらいがきっちりと案内板が出ているので迷わなかった。文武廟には、学問の神である文昌帝と三国志の英雄・関羽が祭られている。 文武廟の本堂内は、たくさん小善男善女がお参りしていた。 文武廟を見終わり、坂を下り、混沌というのがふさわしいアンチックな雑貨ばかりを売っている街を抜けた。世界中の雑貨があるのではないかと思えるほどの品揃えである。しかし、何となく満足に使えるものがなさそうな。そして、その商品の、値段が高いのか安いのか、さっぱりわからないものばかり。カメラにしても、カビだらけで使えそうもないものが並んでいる。  誰が買うのかなと、そういう想像を巡らしながら回るとまた楽しい。 三日目の昼食は、ガイドブックにも載っている名の知れた店にした。こうした店に来るとメニューは割とスタンダードなものを注文してしまう。店内はゆったりとしていて、お客さんの雰囲気もよかった。味はよかった。 でも東南アジアの料理はどの国もおいしい。それにメニューが多彩である。 イギリスなどはほとんどがフィッシュアンドチップスだったことを思えば遙かにたくさんのメニューを楽しむことが出来る。  お茶を頼んだが茶柱が立っていた。 お茶を頼んだが茶柱が立っていた。朝、時間があったのでメインストリートや裏道を歩いたが、食品卸売りの街なのか、いろんな食材が大量に売られていた。豚や魚には余り驚かないが、ヒトデなども立派な商品としてあり、今度食べてみたいと思った。 いったんホテルに戻り、トリムに乗ったが地元のおばさんが運賃の2元のことを身振り手振りで教えてくれた。愉快なひとときであった。もっと長く乗っていればさらに面白かっただろう。 トリムを降りてケーブルカーまで歩いたが、あちこちに露天商がある。どこの国でもあるが、こうした情景は、生活感があふれていて好きで、ぶらぶらしながら写真を撮るのが楽しい。
ビクトリアピーク 香港でもっとも有名な観光スポットといえばビクトリアピークである。そのビクトリアピークに登ることにした。 ピークからから見下ろす100万ドルの夜景はすばらしく、ザ・香港という感じである。その100万ドルの夜景が見える夜ではなく昼間であるが・・ ピークまで行くには、ピークトラムに乗る。ピークトラムは、山麓駅と山頂駅を約10分かけて上るが、その間にもビクトリアハーバーを窓から望むことができる。また非常に急な勾配を上っていくので、日常では体験できないことも味わえる。 このピークトラムは1888年に開業したという歴史あるケーブルカーで、香港で最初に開業した公共交通機関であるという。 現在はすっかり観光用になり、わずか1.4kmで標高差300mを登るという最大斜度23%のとんでもない登山鉄道として有名である。 映画『慕情』の舞台というのはあまりにも有名である。 50年代の香港を舞台に描かれた不朽のラブストーリーで、イギリス人と中国人のハーフで未亡人の女医スーインはアメリカ人の従軍記者と偶然知り合い、恋に落ちる。実は男は結婚していたが、スーインに出会って離婚を決意。しかし朝鮮戦争の勃発で男は間もなく戦地へ飛ぶことになってしまうのだった。 甘く切ない音楽に乗って映しだされる香港の叙情的な風景。50年代の香港をゆったりと美しく描いた映画であった。 映画館で一度、DVDで一度見た。ホールデンに止まる蝶は作品のすばらしいポイントで、ラストでも蝶は現れ、思い出の木にとまる。こういう描き方は当時の日本映画にはなく、感動した。 香港・マカオは上海同様活気あふれる街であった。上海に行った折は区画整理でビルなどの解体がすごかったが、香港は古さと新しさが同居している。トリムも面白く、こうした交通機関が日本にほしいと思った。帰りは旅行会社のバスを乗り合わせた。 マカオからの乗客を拾うルートであったが、これが大きく遅れて、飛行機に搭乗する時間がなくなりそうであった。 バスに乗り込むとすぐに、隣でツアーコンのような男が携帯で話を始めた。娘が電話をするなと注意をしたが、香港ではあちこちで傍若無人な電話のやりとりを聞いた。中国では、割に周りの空気を見ない人がいる。それが中国特有のパワーになっているのかも知れない。 何とか飛行機には間に合ったが、時間がなかったので土産物もじっくり見ることが出来ず、ほとんど手ぶらで日本に帰った。 今回の旅では、九龍島にいけなかったので、もし次回機会があれば今度は、じっくり見てみたい。 自宅への土産は京劇の面を模したかぶり物にした。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||