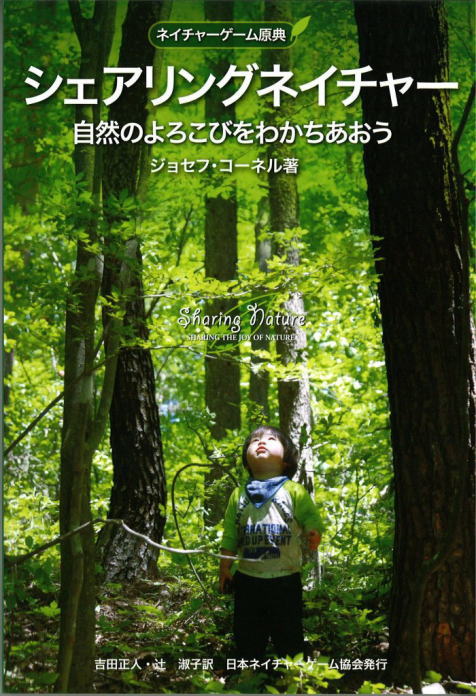
競争から共生へ・ディープエコロジーの勧め
聖書には「人は土の塵から産まれ、塵に還る。」「その塵に神の息吹が
吹き込まれ 人は生きたものとなる」と記されています。
息の仕方は生き方とも言われます。私たちは 瞬間瞬間呼吸をし、新陳
代謝を繰り返します。死と再生を生き続ける存在です。
私はあなたであり、地球であり、全てです。循環しながら一つです。
普遍的無意識が地球意識として一つであることはよく知られています。
聖書はまた「鎌を鋤に持ちかえる」ことを勧めます。
この勧めは大自然から刈り取るのでなく 大地を耕し 良き土壌を育て
ること、狩猟生活から農耕生活への変換。「競い取る,競争原理」から
「心を耕し共に育ち合う共生原理」に変容することを促すとも取れます。
コズミックホリステイック医療では地球家族の視点、ネイチャーゲー
ムの視点、環境問題の視点、南北の格差の視点、鎌を鋤に持ちかえる
(自立援助)視点、ウイン・ウイン、トロプスなどの視点から様々なワー
クショップを提供いたします。
 |
資料:ディープエコロジー ~ウィキペディアより~
ディープエコロジーは、1973年にノルウェーの哲学者アルネ・
ネスが提唱したエコロジーの概念である。
ネスはそれまでに存在した環境保護の活動を「シャローエコロ
ジー」(Shallow ecology)とし、欠けている分野を深めたも
のを「ディープエコロジー」と名づけた。
ネスによると、すべての生命存在は、人間と同等の価値を持つ
ため人間が生命の固有価値を侵害することは許されない。
従来の環境保護運動では、環境保護は人間の利益のためでも
あると理由づけされていたが、ディープエコロジーにおいて
は環境保護それ自体が目的であり、人間の利益は結果にすぎな
い。
1970年代は公害反対運動など産業面での環境対策活動が主体
であり、生活者個人の生き方にまで目を向けることは少なかっ
た。
ディープエコロジーは、環境保護は究極的には個人の自覚と覚
醒が重要であることを示し、1990年代以降の全地球規模の環境
保護運動に直接・間接に大きな影響を与えている。
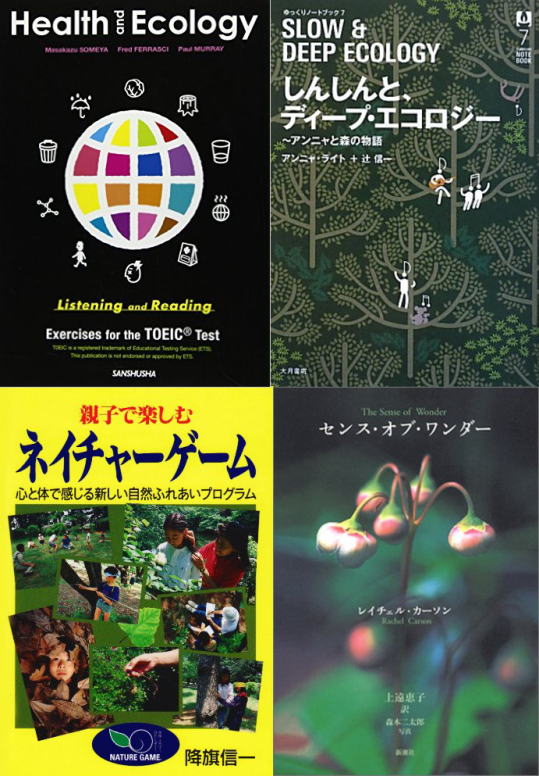
http://www.ne.jp/asahi/village/good/ecology.htm
エコロジーと共生の倫理(抜粋)
1)地球全体主義
「もし世界が100人の村だったら」というかつて世界を駆け
巡ったメールがある。そこではこう言われている。
「20人は栄養不足で、1人は飢え死にしそうですが、15人
は太りすぎです。
この村の全ての富を、6人が59%持っていて、74人が39%
を持ち、20人が残りの2%を分け合っています。
この村の全てのエネルギーのうち、20人が80%を消費し、
80人は残りの20%を分け合っています。
…一年で、村では1人が死にますが、一年で2人が生まれます。
ですから来年は村人の数は101人になります。」
https://www.youtube.com/watch?v=RcEqVPbXMSM
2)エコロジーと共生
DDTなどの化学薬品(農薬)に関して環境への危機を最初に
指摘したのは、レイチェル・カーソン『沈黙の春』(1962)
である。
「自然は、沈黙した。うす気味悪い。鳥たちはどこへ行って
しまったのか。みんな不思議に思い、不吉な予感におびえた。
裏庭の餌箱は、からっぽだった。
ああ鳥がいた、と思っても、死にかけていた。
ぶるぶるからだをふるわせ、飛ぶこともできなかった。
春がきたが、沈黙の春だった。」(青樹簗一訳)
自然は、複雑に絡み合った有機体だから、虫だけを殺すと
思われていたDDTが、予期せぬ結果をもたらすという危険は、
その後も、いろいろ指摘されている。
生態系の崩壊、食物連鎖による濃縮作用、遺伝子の損傷など、
危惧される問題は多い。
それらは単純な原因と結果の因果関係で繋がっているのでは
なく、絡み合った副次的な連鎖作用の総体であるから、
複合的な因果関係をもつエコロジーという観点から考えられ
なければならない。
 |