閉鎖生態系の動態 ―― 酸素濃度21%は偶然か?
森山 茂*・高原光子 (日本大学生産工)
われわれはミニ地球と呼ばれる閉鎖生態系をつくり、環境―生命系の織り成す動態を調べている。今回の3号機は、底に小石が敷き詰められた直径40−60cmほどの装置であり、完全に閉鎖され、その中に水が半分ほど満たしてある。水草、貝とえび、それに熱帯魚数匹がその中で生きている(当初)が、この系の主役は藻類と細菌類である。容器は常時25度Cに保たれ、人工太陽灯の照射を受けている。
1. 実験
(a)実験当初: この系を外部と気体交換できる状態(開放系)にして約半年間放置し、その後完全閉鎖した。閉鎖系では系は直ちに一見安定な“共貧共栄”状態へ移行する。系内では、窒素循環をはじめとして、エネルギーや物質を巧妙に循環させる様々なシステムが動いている。光合成によって、CO2が消費されるため系の気圏のCO2濃度は測定下限値である0.01%以下となる。O2濃度は、気圏・水圏とも21%前後で安定している。なお、太陽灯照射条件は24時間連続である。この状態を約半年間持続させた。その後、突如、太陽灯照射を切断した。
(b)暗期実験: 照射切断とともにpH値は減少し、ATP測定から知られる水圏での菌数変化からは、ほぼ1週間周期変動を繰り返しつつ、好気ワールドから嫌気ワールドへ移行したのが観察できる。照明の切断によって、光合成活動が阻害されたため、気圏のCO2濃度は徐々に増加し、最終的に2%前後の値に落ち着く。なお、2号機での暗期実験でもCO2濃度はほぼこの付近の値に落ち着くので、無光量状態(嫌気ワールド)では、(これまで言われていたよりも多い)2%という、CO2大気状態があり得ることを閉鎖生態系実験が教えている。気圏酸素濃度は10%で水圏上層と平衡状態になった。これは水圏の攪拌がないためである。水圏での溶存酸素量は、厚さ数cmという表層部分の薄層内で、10%から急激に水底での0%へ向けての曲線を描く。
(c)明期実験: 暗期から6ヶ月後、この系に対し再び24時間の太陽灯照射を行った。当然気圏のCO2濃度は減少するが、ほぼ1ヶ月で測定下限値0.01%に達した。特記すべきは、酸素濃度変化である。水圏溶存酸素量は1ヶ月で一時28%にも達したが、その後、我々が“爆発”現象と呼ぶ、水槽底部に沈んだ厚い藻類絨毯の急浮上により、その藻類絨毯の蓋が取れるという水圏攪拌が自発的に起こって、酸素濃度が4日ほどで急降下し、その後結局21%前後に落ち着いた(下図)。これは絨毯下に閉塞されていた還元ガス(メタン?)と溶存酸素が反応したためである。水圏での溶存酸素濃度垂直分布はもちろん一定である。それと平衡な気圏の酸素濃度も21%ほどである。水圏pHは8.3ほどに回復した。暗期・明期でATP値の変化が殆どないことは、(生菌数・死菌数を含めて)嫌気菌数と好気菌数の、全体数が変わらずに種の入れ替えだけが起こったことを示している。また、藻類絨毯に大規模な石灰化が見られることも特徴である。“爆発”や石灰化も含めて、酸素濃度21%というホリスティックなシステム動作による復元が成されていることを示している。
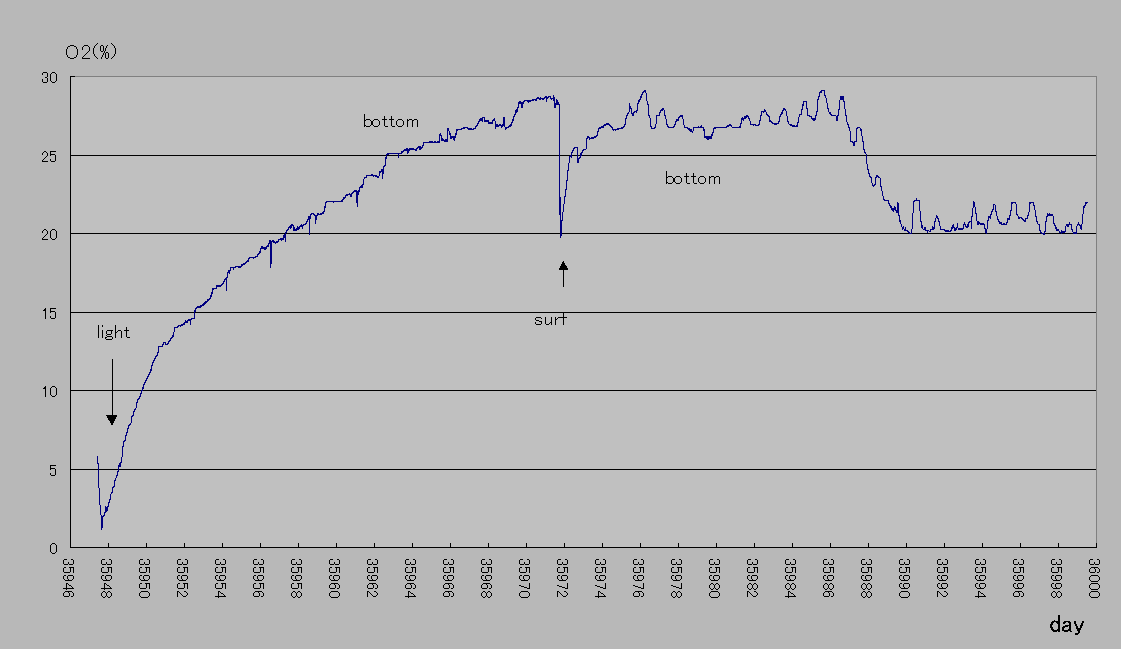 2. 問題
2. 問題
微生物も含めて生命圏の構成要素の質や量が同じはずはなく、また、6ヶ月という暗期間中で、完全に破壊された好気ワールドが、再度の照射によって21%酸素濃度に戻る必然性は何もないように思われるが、本実験の示す復元事実は、現実大気の酸素濃度21%にも本来何か必然的な意味があることを示唆するのだろうか?地球という巨大な閉鎖生態系の特質を知ることは、気候変動や地球環境の生成を論じる上で全く不可欠のことであると考えるが、その実態はいまのところ不明である。閉鎖生態系という視点から、理論と実験の地球研究が必要とされる所以である。
この執筆現在も興味深い変化が起こっているので、それも含めて発表したい。