次ページにも研究報告があります。
閉鎖生態系を用いた地球環境の生成に関する研究(その6)
*森山 茂・高原光子(日大・生産工)
【はじめに】 地球は一つの巨大な閉鎖生態系をなしている。それは宇宙基地型のそれではない。自律的、共変的秩序を持って生成展開してきた現実の地球生命圏を考えると、ミクロコズム型閉鎖生態系こそが地球のモデルとしてふさわしい。我々は、数年前からこの様なミクロコズム型の閉鎖生態系実験装置を使って種々の実験を行っている。
今回はとくに、2号機における“明暗実験”と3号機での開放系から閉鎖系への遷移実験を中心に発表する。3号機の開放実験では、“ミニ地球”の蓋を、1年半以上およそ5cmほど開けておくという開放系で先ず実験した。その後、閉鎖し、開放・閉鎖両系の振る舞いから、閉鎖生態系の動態を検討している。この開放系から閉鎖系への遷移実験では既に2号機でのデータがあるのでそれとの比較も行うことができる。
【結果】 これまでの結果(8月初旬現在)をまとめておく。
- 閉鎖系でも開放系でも、生態系内の水質はとても清浄である。閉鎖系内では、生命は勝手にその能力のすべてを発揮するのではなく、「共貧共栄」状態を築いている。
- 開放系は無限量資源に支えられ、それを適当に使用して、安定に系を維持することができる。無限量の外気から二酸化炭素を入力、光合成し、閉鎖系に較べて、かなりな生物量を生かしつつ、より多くを排出する。これが開放系では安定に続くのである。尚、牛のルーメンやハイポニカのシステムもこの範疇であることが理解される。
- 閉鎖直後、2号機では水圏での溶存酸素濃度が一端急降下した。水底近くで、それまでの12ppm付近から4日ほどで一挙に0〜0.8ppmに急減した(だが、その後ゆっくり回復し、一ヶ月で10ppmほどの値に戻った)。また、気圏の酸素量は閉鎖後一気に約1%降下したが、3日ほどで元へ回復した。更に、二酸化炭素量は0.02%付近の値からおよそ0%付近(測定下限)へ落ちこんだ。これらが突然の閉鎖という擾乱に対する系の調整的反応であった。また、変動周期のフーリエ解析も系間の遷移による変化を示している。
- しかし、3号機ではその測定物理量は、現在の所(閉鎖後50日余)閉鎖によっても依然として開放時とほとんど変わらぬバランス状態にある。エビのような大型生物も開放系から20ヶ月も健在である。これらは始めから動物まで含めて、理想的なバランス状態にあり、他の状態への遷移が必要とされていないということである。
- だが、我々の前に顕現している閉鎖生態系は、実はとても不安定なものかもしれない。何ヶ月もほぼ一定の環境を維持している閉鎖系への微少攪乱、例えば、閉鎖系2号機におけるほんの1時間ほどの突然の開放や、わずか1日間の停電により見られた水中の溶存酸素濃度の急減および、付随して起こった濃度1%以上という急速な二酸化炭素大気の顕現現象は、かつての地球大気の生成問題や、無酸素海洋と生物の激変、あるいは気候変化といった興味深い問題にとってとても示唆的なものであった。
- だが、これら閉鎖系はまた一方で、大変執拗な回復力をも有している。2号機の実験で見られたほとんど壊滅的状態からでも、再び元の状態へ遷移することができる。
- 攪乱によって、pH値は9.4付近から6近くへと壊滅的打撃を受けるし、ATP値から推量される微生物量も生菌数が10倍以上激増することから、窒素循環を賄う硝化細菌や、好気菌から嫌気菌レベルでの微生物的組み替えが行われ、さらにそれらが元に復する動きを持つことになる。こうして、閉鎖系の永続的再建が執拗になされていることを我々の測定は示している。
- 上記実験4.〜6.から約10ヶ月後の2号機での強制的明暗期負荷実験では、水圏の溶存酸素濃度の激変と、それに対し位相の遅れを伴った酸素濃度変化の気圏への伝播が見られた。また、旧態への復元も依然として特記すべき事項である。下図は、人工太陽灯の連続照射中に対する4日間の完全暗期設定実験での水中溶存酸素濃度の変化を示している。
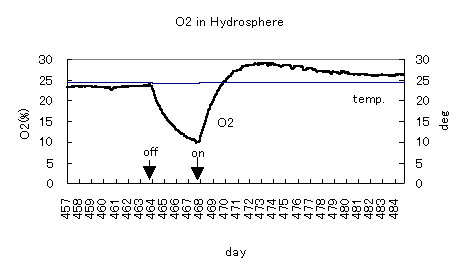
【結語】 この様な生命によるダイナミックな環境の創造と改変。閉鎖系の持つ固有な振る舞いの存在。システムの急変とそれを回復する生命圏の動き。こうした環境と生命圏との共変的作動システム。この様なリビング・システムとしての閉鎖生態系の振る舞いを知ることが、過去・現在・未来の地球生命システムの本質的作動を把握していくために緊要なことである。