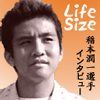稲本潤一選手 スペシャルインタビュー
LIFE SIZE 等身大のプレミア生活 |
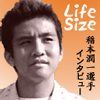 |
| 1/3 |
 |
| 写真提供=ジェブエンターテイメント |
「こんなことがありました。あれは、東京だったか、大阪だったか。とにかくワールドカップが終わってやっと気兼ねなく本当に久しぶりにリラックスしてコンビニにも行けるんやって、うれしくて入ったんです。そうしたら、ある女性週刊誌の大きな見出しが目に飛び込んできて、そこには太い字でこう書いてありましたね。『稲本、8年越しの恋!』って。俺が? 8年越しの恋ってどういうことや、って慌てて週刊誌を手に取って読みましたよ。確かに自分はワールドカップというサッカーの試合で2点を取ったけれどそれだって自分一人の力じゃない。起きている事があのとき本当の意味でようやくわかったというか、目が覚めた感じがしました。鹿児島のおじいちゃんがテレビに出ていたのにも驚きました。2年くらい前かな、電話で話したんだと思うんやけど、テレビに出ているおじいちゃんを見ながら、大変だなあ、何が起きてんだ、って。女性週刊誌にはどうしてあんな記事が載ったのか、わからないんやけど、とにかく『彼女』は顔写真付き、目線まで入ってるし、コメントしてるんです。記事を読みながら、こっちが知りたいくらいや、と。自分のことなのに、自分が知らないなんて。とにかくワールドカップってもんの重大さに気がついたのはあの時でした。ああいう異常な毎日から、一日でも早く普通に戻らな、という気持ちでここまで来ましたね。あの2点のことは心のどこかでもう終わってましたし、むしろ悔しい思いばかり残るから。ちょっとでも早く別のところで、目に見える結果が欲しいと思った。普通の毎日というか、練習と試合だけ集中しようって。雑誌? 買いませんよ、立ち読みです、買わんと帰りました」
稲本潤一(フルハム)の愛車、黒のビートルは、ロンドンの北から、フルハムが改装を計画しているスタジアム、クレイブンコテージに向かって南下している。撮影に出かけることになり、一緒に車に乗り込んだ。今日は珍しく晴れてますねえ、気持ちがいいやと、運転席のウインドウから夏空を見上げた。
「安全運転だね」
「まあねえ、お客さんが乗っているから。でもほんと、こっちが日本と同じ左側通行で助かりましたよ。これが右やったらかなりきつかったかな、って。特に困ったことも、慣れるって感じもしなかったのは運転が楽だったからかなあなんて思うんですよ。そうそうこの前、伸二と話してたらね」
よく連絡を取っている小野伸二(フェイエノールト)の名前に含み笑いをする。交通量が増え始め、合流する車に合図を促す。
「伸二に聞いたらね、結構、やってるらしいですよ、ギャ・ク・ソウ」
慌ててバックしている小野が目に浮かび、一緒に噴き出した。
「ああ、オレって旬な男、の情報提供者ですね……あの会見はウケたんだ。小野君、言った後に、ああ、怒られるから皆さん書かないで下さいね、って口に手を当てて」
「遅いわあ、ホンマですよお、もう余計なこと言うんやから。気にしてませんけどね」
「でもね、あの囲み会見で小野君が言ったのは、このW杯で稲本君が羨ましいって話だった。堂々としてる、いいポジションにいる、ゴールも奪う、3拍子揃って凄いと」
稲本は黙っていた。小野だけではない。中田英寿(パルマ)、戸田和幸(清水)、明神智和(柏)らの犠牲なくして奪えたゴールではなかったことを、深く理解しているのだ。
「堂々っていうか、普通でした。自分は普通にやれたんだと思います。あんなに普通にできるとは思わんかったけれど」
8月17日のリーグ開幕戦(ボルトン、3−1)で日本人初のプレミアリーグ出場を果たし、インタートト杯ではハットトリックを含む4得点で123年の歴史を持つチームをUEFA杯に初めて導いた。そんな「ラッキーチャーム(お守り)」とともに、晴れ渡ったロンドンで過ごした2日間には、特別なことは何も起きなかった、と書いたら読者はがっかりするだろうか。
雑誌の「独占インタビュー」であるとか、「密着ドキュメント」といった見出しは、内容を必ずしも言い表してはいない。見出しや内容が嘘だと言いたいのではない。選手たちがホームページを読者に提供している現在、選手とメディアが置かれた状況の接点とは、もはや独占や単独、密着といった実態のない言葉で的確に表現できないという、危機感である。
今や、選手と多くの時間を共有することなど、贅沢な話となってしまった。無論、特にシーズン中はタイトなスケジュールに追われていることもよく理解しているつもりだ。挨拶程度の話が、立場上も、ビジネス上でも、どれほど大きなインパクトを持つかを考えれば、警戒もするだろう。
海外に移籍する選手が増え、メディアにとっての事態は深刻化しているが、それでも、1時間、2時間の貴重な時間を割いて互いの接点を持つ労を、彼らは厭わず、勤勉に取材をこなしてくれる。しかし、ホテルやクラブハウスでの特別な1時間以上に、アスリートとしての生活の、ほんの一部でもいいから、共に過ごすことができればと願って来た。
私は彼らのパフォーマンスを支える練習を見るのが好きであるし、これといって何もない日、一行も原稿が必要でない日に交わす会話や彼らの素朴さを愛している。独占でも単独でもなく、彼らのタイムテーブルの中に出かけて、その中に溶け込んで話ができればこんな幸せはないと断言できる。
コメントの伝聞、憶測や他人の記事を根拠にするのではなく、自分が相手の隣で、表情や空気とともに見聞きしたものを根拠に書けることは、2つめの幸せと言える。
こんな面倒のかかる取材を続けて来られたとすれば、選手や関係者の寛大さに助けられたからである。今回も、そうした寛大さによって、ロンドンで、何も起きない「特別な一日」が取材できるという。
告げられた住所に車を走らせた。
ロンドンの中心から少し離れた、こじんまりとした住宅街に着くと、目印になるはずですから、と言われた黒の「ビートル」が見えた。小さな庭があり、2階建て、ロフト付きの一軒屋で稲本が迎えてくれる。
照れくさそうに、「いらっしゃい。すみません、スリッパは一足しかないんで適当に履いてください」と笑い、右手を差し出した。右手を出す代わりに、土産を差し出す。和菓子を手に、「マジっすか? うれしいです」と、なぜかロフトに持って行ってしまった。どこか茶目っ気の漂う笑顔と一緒に。
 |
| 写真提供=ジェブエンターテイメント |
ベージュのカーペットを敷き詰めた廊下から階段を上がると、明るい、10畳ほどのリビングに段ボールが並ぶ。リーグが始まり引越しの準備をしているところだ。
「バナナ1本もらってもいいですか?」
「どうぞ、何本でも」
「それにしても、ずいぶんと小綺麗なキッチンだね、料理もしているんだ」
調理台には炊飯器、「最高級魚沼産」と書かれたコシヒカリ3キロ詰めの袋。米は炊いて、朝食にはシリアル類を取り、卵料理も作る。練習場には選手用の食堂があり、そこで栄養バランス、カロリーを考えたランチを摂っていると聞いた。
「有機栽培」と大きく書かれたバナナをちぎると、リビングから笑い声が弾んでくる。
「小綺麗に、さっきしたばかりですよ。だからベッドルームははかなり危険な状態です。上の写真だけは、勘弁してください」
撮影が終わり、マネジメントを担当する井上 亮氏が用意してくれた飲み物を皆で口にする。一瞬、家中が静けさに包まれ、レースのカーテンが風に揺られてリビングで踊るのを見ながら、一人には広過ぎると、ふと思った。一年間の寂しさ、孤独、すべてがこの家に染みているのだろうか。
「いや」
稲本は首を振った。
「サッカー選手の生活は、結局どこでも変わらない。練習とその往復が一日のほとんどで、終われば一日も終わり。確かに去年は試合がなかったことが難しかったけれど、基本的には大阪にいても、日本代表でも、ここでも同じ。寂しくはなかった」
この一年で読書が好きになったと笑う。
試合に出ないことを心配する心優しきファンからは、「決して落ち込まないで」「苦境に立ち向かうには」といった人生訓を語る書籍が届けられたが、杞憂だった。実際は、英国発の世界的ベストセラー「ハリー・ポッター」2巻を読んだと笑い、「あ、日本語ですよ、英語じゃないです」と付け加えた。
断らなくてもいいのに。
ジュースを飲み終わると、稲本が先に立ち上がり、全員の空き容器に手をかけた。
「僕が捨てて来ます。ください」
日本人初のプレミアリーガーとしての意気込みや、W杯で2得点をあげた「旬な男」の告白であるとか、フルハム初のUEFA杯へハットトリックをした衝撃、そうしたものは何もない。しかし隣で聞いた話からは、彼の今の体温が伝わるかもしれない。
実際のところ、稲本に限らず、彼らアスリートの競技力を支えるもっとも強く、太い根が、何もない、普段の生活に張っていることだけは間違いがない。そして、この夏の日、私が傍で感じていたのは、枯れから放たれていた空気の軽妙さである。
人々の注目を、良くも悪くも一身に受けるような毎日を経た今、力みや過度な緊張感、プレッシャーとの付き合い方は十分にマスターしたはずである。しばらく会っていない祖父がテレビに出演し、知らないうちに大恋愛をさせられ、いつの間にか「稲本潤一物語」が出来上がっている。
W杯の体験は、逆説的だが、つま先立ちすることのない、言ってみれば今の自分と、それにふさわしい環境に囲まれた日々の尊さを教えてくれたのではないだろうか。競技者として現状に満足したわけではなく、着実に自分と並び歩む充実感は、「LIFESIZE」(等身大)と表現するのがふさわしいかもしれない。
ああ、そうだ、慣れないことがひとつだけありましたね。自宅の玄関を出るとき、稲本はそう言ってふと立ち止まった。
「僕はやっぱり土足は嫌いです。人のウチに行ってもそれだけは慣れませんね。靴は、ちゃんと脱いで揃えんと」
廊下には、泥を落とすマットの横に靴が整理され、2列に並べられていた。ここだけは、急いで片付けたのではなかった。
|