アート・ドキュメンタリー映画祭2
映像フェスティバル98
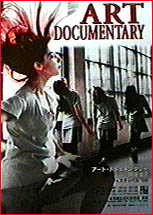
|
道立近代美術館で「アート・ドキュメンタリー映画祭2 映像フェスティバル98」が、9月17-27日にわたり開かれた。96年に行ったアート・ドキュメンタリー特集の続編。今回は計16作品を取り上げた。全作ビデオで、しかも視聴覚設備は満足のいくものではなかったが、貴重な映像がそろっているので、全上映作品を紹介する。 「ダブル・ブラインド」は、1992年のアメリカ映画(74分)。監督と出演がソフィ・カル(Sophie Calle)、グレッグ・シェパード。恋人同士でビデオを撮り合いながらカリフォルニアを目指すロードムービーのスタイルだが、二人のすれ違いが毒のある笑いの中で浮き彫りにされる。ディスコミュニケーションの映画というよりも、恋愛のこっけいさと切実さのはざまに揺れる現代における女性の勝利を歌い上げているように思える。ソフィの高笑いが響いている。 「写真家・ペール・マニング」(スティグ・アンデルセン監督、1994年、ノルウェー、26分)は、ノルウェーの動物写真家ペール・マニング(Per Maning)が、撮影の動機と思いを語ったドキュメント。犬、あざらし、豚、牛が撮られている。しかし、これほど動物に近づいて撮影された写真は稀だ。動物の内側から写しているようだ。「人間と動物の共通点は動物の中にある」というマニングの言葉が印象的。 「ウェグマンの世界」(チェリー・デュインズ監督、1996年、オランダ、60分)は、動物の擬人化を通じて、既成観念を笑い飛ばすウィリアム・ウェグマン(Wegman)の姿を追った作品。色とりどりの服を着せられさまざまなポーズをとる犬たちもおかしいが、初期のウェグマンが撮った「腹芸」も笑えた。マニングの真摯さとウェグマンの軽妙さは対照的だ。 50年間、フアッションなど写真界に大きな刺激を与えてきたリチャード・アヴェドン(Richard Avedon)の歴史をまとめた「リチャード・アヴェドン:闇と光」(ヘレン・ホイットニー監督、1996年、アメリカ、86分)は、撮影風景、写真、賛辞と批判をテンポ良く構成し、大変に分かりやすく写真家の内面を紹介している。矛盾を矛盾のままとらえ続け、シャープな世界を築いてきた強靱さと柔軟さに驚かされる。むろんアヴェドンの本当の秘密は隠されたままだ。 「フラメンコ」は、1995年のスペイン映画(98分)。カルロス・サウラ(Carlos Saura)監督版フラメンコの教科書とでも呼ぼうか。「カルメン」のような物語性はなく、章ごとにひたすらフラメンコを紹介する。それぞれの歌も踊りも確かにうまい。しかし変化のない構成なので、集中力を維持するのが難しくなってくる。30分程度ならいいが、このくらいの長さになると何らかのめりはりが必要だろう。 「イアン・ケルコフによるパフォーマンス・アーティストたちの肖像」(オランダ)は、イアン・ケルコフ(Ian Kerkhof)監督が選んだ3人のパフォーマーを紹介している。ロン・エイシー(Ron Athey)は、身体を傷つける降霊術を基本にしたパフォーマンス。挑発性はあるが、独創性はない。本人が何と言おうと「見せ物」的すぎる。マシュー・バーニー(Matthew Barney)は、グロテスクと華麗さをブレンドした仮装パーティの映像。既成の境界線、壁を超えようとする意図は伝わってくるものの、単なる「お祭り」に終る危険もある。ベイビー・ケイン(Baby Kain)は、黒人の歴史を背負ったポエトリー・リーディングの記録。ラッパーや詩人というよりは、セラピストに近い。いずれも20数分の作品で、ひとり一人の創作の核に迫るには短すぎる。 テリー・ズウィゴフ監督の「クラム」(1994年、アメリカ、119分)は、すでに昨年劇場で公開され、紹介している。ロバート・クラムに迫る衝撃のドキュメントだ。ビデオで見ても、ラストの辛さは変わらない。 「イヴ・サンローラン」(ジェローム・ド・ミソルツ監督、1994年、フランス、45分)は、イヴ・サンローラン(Yves Saint Laurent)の豪勢な私邸を舞台に、モデルたちがコレクションを身につけ風のように通り過ぎる。美しい。微睡みのようなうつろいやすい耽美。しかし終始サンローランのペースで展開しているので、彼の危うさの魅力にまでは踏み込めていない。 「ONE ENO」(ジェローム・レフデュップ監督、1993年、フランス、22分)は、いかにも柔軟なブライアン・イーノの魅力があふれたクリップ。この作品だけはビデオでも違和感はない。イーノのCGは古さを感じさせるものもあるが、今でも新鮮な作品が多く、アイデアの密度の高さを改めて味わった。 今回最も感銘を受けたのが「ジャン=ピエール・レイノーの家 1969-1993」(ミシェール・ポルト監督、1993年、フランス、31分)。ジャン=ピエール・レイノー(Jean-Pierre Raynaud)は、1969年から自宅の改造を始め、床、壁、天井、家具を15センチ四方の白いタイルで覆い尽くした。窓にはステンドグラスを入れ外部との距離感を保っている。レイノーは「タイルは熱く激しい」と、家との愛の交流を語る。1988年に家は完成し、4年間の熟考の後、メタモルフォーゼのために家の破壊を決意する。無慈悲に壊されていく家のタイルを撫でる姿が胸に染みる。タイルの破片を容器に入れ幾何学的に並べたラストシーンには、宗教的な崇高さがただよっていた。 レイノーが外部との距離を持ち自分の空間を生み出したのに対し、フランク・ロイド・ライト(Frank Lloyd Wright)は自然環境に開かれた家を目指した。その最も美しい達成が落水荘だろう。「落水荘:ライトと弟子たち」(ケネス・ラブ監督、1996年、アメリカ、56分)は、2年前の映画祭で上映された「フランク・ロイド・ライトの落水荘」の続編に当たる。今回はタリアセン・フェローシップという学校をつくり有機建築を教育したライトの姿を追いつつ、落水荘がライトと若き建築家たちの共同作業であることが明らかにされていく。貴重な記録フイルムを多用し興味深いが、もう少し落水荘の美しい映像がほしかった。 「バルテュス」(マーク・カイデル監督、1996年、イギリス、51分)は、画家バルテュス(Balthus バルタザール・クロソフスキー・ド・ローラ)の数少ないインタビューとしてだけでも意義が大きい。その語り口から、少女を描く彼の指向、破壊を予感させる静かな画風が自然に解き明かされるようだ。そして勝新太郎の芸がバルテュスと共振する希有な体験もできる。 作家のクロソフスキーはバルテュスの兄。「ピエール・クロソフスキー-イマージュの作家」(アラン・フレッシャー監督、1996年、フランス、47分)は、静かないらだちとともに歴史を自在に横断するピエール・クロソフスキー(Pierre Klossowski)をとらえる。この巨人の全貌に迫るのではなく、その映像的な仕事と老いた雰囲気を伝えることに徹している。懸命な態度だと思う。 「ブルース・ナウマン-MAKE ME THINK」(ハインツ=ペーター・シュヴェルフェル監督、1996年、フランス・ドイツ・イギリス、51分)には、ブルース・ナウマン(Bruce Nauman)のインタビューは登場しない。鋭い問題意識の作品と評論家たちの批評が繰り返されるばかりだ。そのもどかしい体験こそ、ナウマンへの関わり方の一つだろう。ドキュメンタリーとしてのまとまりを拒否しながら。 パイクの先駆性は今日誰もが認めるところだろう。「エレクトロニック・スーパーハイウェイ:90年代のナムジュン・パイク」(ジャド・ヤルカット監督、1995年、アメリカ、40分)は、卓越した時代認識を持ちつつ、軽妙なフットワークをみせるナムジュン・パイク(Nam June Paik)の特徴をうまくつかまえている。インターネット時代のパイクの挑発に注目したい。 |
 「ローザス・ダンス・ローザス」(ティエリー・ドゥ・メイ監督、1997年、ベルギー、57分)は、廃校化した学校を舞台に振り付け師ケースマイケル率いるローザス(Rosas)の第1作を映像化した。少女たちの日常的な身ぶりを鋭く切り取り反復化するダンスは、ぞくぞくするほど魅力的。前半は計算された巧みな映像がダンスを盛り上げていたが、後半はやや緊張が弛んだ感じ。その分閉塞的な雰囲気が染み出てしまった。
「ローザス・ダンス・ローザス」(ティエリー・ドゥ・メイ監督、1997年、ベルギー、57分)は、廃校化した学校を舞台に振り付け師ケースマイケル率いるローザス(Rosas)の第1作を映像化した。少女たちの日常的な身ぶりを鋭く切り取り反復化するダンスは、ぞくぞくするほど魅力的。前半は計算された巧みな映像がダンスを盛り上げていたが、後半はやや緊張が弛んだ感じ。その分閉塞的な雰囲気が染み出てしまった。