|
--2002�E09�c��--
|
| �s�N�Ɖƈ琬�x��(�ݷ��ް��ݎ��Ɗ֘A)�t |
�@���߂ɁA�N�ƉƂ̄����N�ƉƁA�N�����ƂƏ������ł����ǂ��A�N�ƉƂ̈琬�x���ɂ��Čo�ϕ����Ɏ��₢�����܂��B
�@���c��ɏ������Ă��܂���\�Z�Ă̏��H��ɐV�Y�Ƒn�o�Ƃ��ăC���L���x�[�V�������Ɣ�S�C�Q�O�O���~���v�コ��Ă��܂��B���̓��e�͈����̎��ⓙ�ł��G����Ă��܂��̂ŏȗ����܂����A�N�ƉƂ��琬���Ă������߂̃r�W�l�X�E�C���L���x�[�V�����A�����������ӗ���Ƃ������̂ɑ�������{�݂ł����ǂ��A���̕K�v�������˂Ă��i���Ă������̂Ƃ��āA�悤�₭�����̂߂ǂ����Ƃ��Ƃ������Ƃɑ�ϊ�т������Ă���܂��B
�@�Y�Ɛ��邢�͒�����Ǝ{��Ƃ��ẴC���L���x�[�V�����̈ʒu�Â��͂���قǐV�������̂ł͂Ȃ��Ǝv���܂����A�{��̒��S��������Ƃւ̐��x�Z����Ő��[�u�A��ƗU�v�A��ƒc�n���������嗬�̎��オ�������ŁA���̕K�v���͔F������Ȃ�����A�Ȃ��Ȃ����̖ڂ����Ȃ��������̂ł���܂��B���{�̖{�i�I�ȃC���L���x�[�^�[�Ƃ��Ă͐��s�ɂ���T�C�G���X�p�[�N���m���Ă���A��p�z�e���܂ł����^�̌����J���^�C���L���x�[�^�[�Ƃ��ĂP�X�W�X�N�ɒa�����Ă��܂��B���Ẳ䂪�s�̎Y�ƈψ���ł����@���s�������Ƃ�����܂��B���̌�A�䑶���̂Ƃ���A�\�t�g�s�A�W���p���A�e�N�m�v���U�Ƃ�����K�͂ȃC���L���x�[�V�����E�C���t����L������̂��o�Ă܂���܂����B�h�s�E��Z�p�̋}���Ȑi�W�������݊W��Ƃ̗U�v��}��ƂƂ��ɁA�����S���V�����Y�ƁA�ƑԂƂ��ċN�ƉƂ��琬���Ēn��o�ςɊ��͂ݏo�����Ƃ������̂��ƍl���܂��B
�@�����āA����C���L���x�[�V�����́A�S���̎����ł͂������܂����ǂ��A��Q���Ƃ������ׂ�����ɓ������Ǝv���܂��B����͓s�s���S���̋��ŋr���A�e�i���g���ӂ��A��������p�������x�̒ʐM�̃u���[�h�o���h����p�ӂ��đn�ƎҎx�����s���Ƃ������̂ł��B�������琶�܂�Ă��鎖�ƌ`�ԂƂ������̂͂r�n�g�n�����X���[���I�t�B
�X�E�z�[���I�t�B�X�����̑�\��Ƃ������������܂����A�`�������W�V���b�v��R�~���j�e�B�[�B�r�W�l�X�Ƃ������悭�����Љ����̂��Y������̂ł͂Ȃ����ƍl���܂��B���������w�i�ɂ͎Y�Ƃ̋��������A�����āA��̌����Ȃ��o�ϊ��̒��ő��Ƃ��n���i�o�Ƃ����]�͂������Ă���B�����������ŁA������n���s�s�����S�ƂȂ�܂��ē����I�ȎY�ƐU����V���Ƃ̑n�o������̕K�R�Ƃ��ĔF�������悤�ɂȂ��Ă������炾�Ǝ��͎v���Ă���܂��B
�@�n��o�ς��������Ă����n��Y�Ƃ����n���Đ��ނ��A���̒n��Y�Ƃ��g���Ă����C���t���Ƃ��Ẵr����ݔ������p���Ď����S���V�����Y�Ƃ����܂��Ƃ����v���Z�X�́A����Ӗ��ő�ώ��R�Ȃ��Ƃł���܂��āA�C���L���x�[�V�����{�݂����̃v���Z�X�̒��ɑg�ݍ��݈ʒu�Â��ċN�Ƃ̓������x���A���邢�͑��i���邱�Ƃ͑�ό����ȕ��@�Ǝv���܂��B�o�ύ������̏ォ����A����ȓ��������ă��X�N�̍����V���ȃC���L���x�[�V�����{�݂����݂����肷����Ă����ł͂Ȃ����Ƃ������͎v���܂��B
�@�S���I�ɁA�����Č����ł��r�����p�̃C���L���x�[�V����������o�Ă��Ă���܂��B��ό��\�Ȃ��ƂƂ͎v���܂����A�������A���ɂ̓C���L���x�[�V�����Ƃ������͒P�Ȃ�Ƒ�Ƃ��Ă݂̑��ًƂɂ����Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv�����̂��ڗ����n�߂Ă���܂��B�������炻������������͂Ȃ������낤�Ƃ͎v���܂����ǂ��A���̑����͖��Ԍo�c�ɒʒB�����l�ނ��Ȃ�������A�C���L���x�[�V�����̃m�E�n�E�s�������̂悤�ɓ����Ă��܂����������Ǝ��͎v���Ă���܂��B�����Ȃ�Ȃ����߂ɂ��N�ƉƎx���̒��g���悭�ϋl�߂āA�N�ƉƂ�ڎw���l�����ۂɊJ�Ƃ��Ɨ����Ă������悤�Ȏ����ȏ����ƍH�v��v����ƁA���̓_�͋����\���グ�����Ǝv���Ƃ��ł���܂��B
�����⁄
�@�C���L���x�[�V�����{�݂̓��F�ƈ琬�x��
�@�����ŁA����ɓ���܂����A�s�Ƃ��ẴC���L���x�[�V�����̓��F�A���邢�͊O�ƈႤ���ʉ��A�����Ƃ��������̂��ǂ��ɒu���Ă���̂��B�����āA�N�Ɖƈ琬�x���̓��e�[���̂��߂ɂǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��d�v�Ƃ��l���Ȃ̂��A�����������肢�����Ǝv���܂��B
�A����̑n�Ǝx���̓W�J�ƌo�ϐU���{��
�@�Q�_�ڂƂ��āA�C���L���x�[�V�����̊g�[���ʂ��ȂǁA����̋N�ƉƎx���̓W�J�ƐV�Y�Ƒn�o�Ɍ��������g�݂ɂ��Ă��f�����܂��B
|
|
|
| �s�q�ǂ��̓Ǐ��������i�Ɗw�Z�}���ِ�����(�w�Z�}���ّ����ް��ް��\�z�֘A)�t |
�@���ɁA���c��ɕ�\�Z�ĂƂ��Ē�Ă���Ă��܂��u�w�Z�}���ق̑����ް��ް��\�z�v�Ɋ֘A���܂��āu�q�ǂ��̓Ǐ��������i�Ɗw�Z�}���ِ������v�ɂ��ċ��璷�ɂ��q�˂��܂��B
�@���݁A�u�Ǐ��̌��p�v�������ȂƂ���Ō�������Ă���܂��B���̓Ǐ����������H���Ă���w�Z�ł́u�{��ǂނƂ������Ƃ́A�������g�ƑΘb���邱�ƁB�Ǐ��̎��Ԃ͎��������l�߂��鎞�ԂŁA���̓Ǐ�������Ă���q�͗��������܂������Ⴄ�v�ƕ]������Ă��܂����A�܂��u�b�N�X�^�[�g�ɂ��Ă��傫�ȍL���肪�����܂��B
�@�����������ŁA��N�P�Q���Ɂu�q�ǂ��Ǐ������̐��i�Ɋւ���@���v���{�s����܂������A�����Q�����@�ɂ��Ƃ����u�q�ǂ��̓Ǐ������̐��i�Ɋւ����{�I�Ȍv��v���t�c���肳��܂����B���v��́A�P�J���Ɉ�����{��ǂ܂Ȃ����k�����Z�łU�V���ɏ��ȂǁA�q�ǂ��́u�Ǐ�����v�����O����Ă��邱�Ƃ܂�����ŁA�Ǐ������ɂ��āu�q�ǂ����A���t���w�сA�������A�\���͂����߁A�n���͂�L���Ȃ��̂ɂ��A�l�������[��������͂�g�ɕt���Ă�����Ō������Ƃ��ł��Ȃ����́v�Ƌ������āA�����ނ˂T�N�Ԃɂ킽�����荞��ł��܂��B��̓I�Ȏ{��Ƃ��Ắi�P�j�ƒ�A�n��A�w�Z�ɂ�����Ǐ������̐��i�i�Q�j�Ǐ��������i�̂��߂̎{�݂�ݔ��Ȃǂ̐����E�[���i�R�j�}���يԋ��͂̐��i�\�\�Ȃǂ𒌂ɂ��Ă���A���̓��A�ƒ��n��A�w�Z�ɂ�����Ǐ������̐��i�ɂ��ẮA�s���������{���Ă��鋳��u���Ȃǂ�ʂ��ēǏ��̏d�v���Ɋւ���ƒ�̗����𑣐i����ƂƂ��ɁA�u�q�ǂ���ߊ���v�̊��p�Ȃǂɂ���Ēn��Ŋ������閯�Ԓc�̂��x������B����ɁA�w�Z�ł́u���̓Ǐ��v�Ȃǂ̎��g�݂���w���y������ق��A�ӊw�Z�Ȃǂ̎����E���k�ɑ���Ǐ����������i����ȂǂƂ��Ă��܂��B
�@�s�̊�{�v��Â���̗͓_
�@���̌v��łӂ��ꂽ���ƂȂǂ𒆐S�Ɉȉ�����ɓ���܂��A�悸�A���ꂩ����肪���߂��܂��s�́u�q�ǂ��̓Ǐ������̐��i�Ɋւ����{�v��v����ɂ��Ăł���܂��B�Љ�܂����Ƃ���A���̊�{�v��͍L�͂ɂ킽���Ă���̂ł���܂����A���R�A�n�������̂ō쐬�����{�v��́A�n��̎�����ӂ܂��Čv������Ă���̂ł��傤���A�ǂ̂悤�ȓ_�ɗ͓_������������Ȃ̂������_�ł̂��l�������q�˂��܂�
�A�w�Z�}���ق̑����ɂ���
�@�Q�_�ڂƂ��Ċw�Z�}���ق̑����ɂ��Ăł���܂��B�����Ȋw�Ȃł͌����`�����珔�w�Z�̊w�Z�}���ّ������̖ڈ��ƂȂ�u�}���W���v���߂Ă��܂��B����ɏƂ炵�܂��Ɗs�ł͏��w�Z�ł͕��ςłP�Q�X���Ɛ}���W�����Ă��܂����A���w�Z�ł͕��ςłX�R���Ɖ�����Ă���̂ł���܂��B�s���Q�Q�Z���P�R�Z�����B���łU�O���̂Ƃ��낪�R�Z����܂��B��K�͍Z��ݗ��̐V�������w�Z�ɑ����Ƃ������ʂɂȂ��Ă���܂��B
�@���N�x����u�����I�Ȋw�K�v�ȂǐV��������ے����������ꂽ���Ƃɔ����A�w�Z�}���ق͓Ǐ������̋��_�ƂȂ邱�Ƃɉ����āu�w�K���Z���^�[�v�Ƃ��Ă̖��������҂���Ă��܂��B�u���w�K�v������ɂ��Ă��}���ق̑������n��ł͘b�ɂȂ�Ȃ��Ǝv�����̂ł���A���̓_�ǂ̂悤�ɏ[�������Ă����̂����q�˂����܂��B
�@�icf.���z��650���~�̊w�Z�}���ِ}��������n����t�łő[�u�B�T�J�N�v���4000�������j
�B�w�Z�}���َ�C�Ƃ��Ă̎i�����@�Ɛ}��������
�@�R�_�ڂł����w�Z�}���ق̉^�c�E���p�̒��S�I�Ȗ�����S���i�����@�Ɛ}���������ɂ��Ăł���܂��B�w�Z�}���ٖ@�̉����ɂ�藈�N�x�i2003�N�j�ȍ~�A�P�Q�w���ȏ�̊w�Z�́i�������Ȃǁj�i�����@��z�u�����邱�Ƃ��`���Â����܂��B���������܂����Ƃ���s�ł͒B���ł���Ƃ̂��Ƃł����A�������@�����C���邩�����������ł��̂ŁA�s�ł͈��������}���������̉ʂ����������傫���Ǝv���܂��B�}���������́A�����T���Ԃ̋Ζ��ł��������̂��A�P�R�N�x����S���ԋΖ��ƂȂ����o�܂�����܂��B�Z�����̋����v��������A���N�x���班���Ζ����Ԑ��������ƂȂ����ƕ����܂����A�S�ʓI�ɖ߂����킯�ł���܂���B�}���ق𗘗p���鎙���Ɛڂ��鎞�Ԑ����m�ۂ��邱�Ƃ͑�Ϗd�v�Ǝv���܂��̂Ő���A�Ζ����Ԃ̉�����A�i�����@�̋@�\�����A���̂��߂ɂ͎��ʏ���Ƃ̌y�����K�v��������܂��A����Ή��������������Ǝv���܂��B�����Đ}���������A�i�����@�Ԃ̘A�g��x���A�b�v�̂��߂̌��C���d�v�Ȃ��Ƃł���A���Ɂu�}����C��v�Ƃ����g�D�������Ă��̖ʂ̖�����S���Ă���ƕ����܂����A���̈�w�̏[���Ȃǐ}���ًƖ��̃}���p���[�̏[���ɂ��Ă��f�����鎟��ł��B
�C�w�Z�}�����̃l�b�g���[�N�Â���ɂ���
�@�S�_�ڂł�������̕�\�Z�Ăɂ��鏬�w�Z�ɂ�����u�w�Z�}���ّ����f�[�^�x�[�X�\�z�v�Ɓu�Z���k�`�m�����v�ɂ��Ăł���܂��B���łɒ��w�Z�ł͂k�`�m�����͏I����Ă��܂����A���̂k�`�m���g�����w�Z�}���ّ����f�[�^�x�[�X�ւ̃A�N�Z�X�͂܂��ł��Ȃ��悤�ł����A�Z���̂ǂ̃p�\�R��������}���ق̑�����T���o����悤�Ȋ����́A���k�̊w�K�����ɍł��𗧂��Ƃƍl���܂��B�����čł��k�`�m�����̃����b�g���ł��������₷������Ǝv���܂��ő����Ɍv�悢�������������Ƃł��B�����čX�Ɏ��Z�̐}���قɕK�v�Ȑ}����������Ȃ������ꍇ�́A���Z�̐}���������ł��āA�����悤�ȃl�b�g���[�N�Â�����厖�łȂ����ƌ������Ƃł��B���ɁA�s�ł͕����Ȋw�ȁE�����ȘA�g�́u�w�Z�C���^�[�l�b�g���Ɓv�̎w����Ă���w��Z�Ԃ̃l�b�g���[�N���ł��Ă��܂��̂ŁA���̃V�X�e���̊g��ʼn\�Ǝv���܂������̌v��A�܂��͌��ʂ��͂ǂ��Ȃ̂����q�˂��܂��B
|
|
|
| �s�d���g�ɂ�錒�N��Q�t |
�@���Ɂu�d���g�ɂ�錒�N��Q�v�ɂ��ĕی����������Ɏ��₵�܂��B
�@�d���g�ɂ��l�̉e���ɂ��Ă͉Ȋw�I�ɕs���m�Ȃ��Ƃ������A���̋K���l���l�����ɂ���Ă܂��܂��Ȃ̂����Ԃł��B�A
�@�Ƃ��낪�挎�W���Q�S���̒����V�������P�ʃg�b�v�Ɂu�����d���g ���N�։e���v�u���������a���{���v�Ƃ����V���b�L���O�Ȍ��o���̂����L�����f�ڂ���܂����B
�@�������������Ȃǂɂ�鏉�߂Ă̑S���u�w�I�����̒��ԉ�͂̌��ʁA�������d����d�C���i����o�钴����g�̓d���g���y�Ԋ��ł́A�q�ǂ��̔����a�̔��Ǘ����Q�{�ɂȂ����Ƃ������̂ł��B���ɐ��E�ی��@��(WHO)�Ȃǂ͍�N�A�d���g�ŏ��������a�̔��ǂ��{������Ƃ����������ʂ\���Ă��������ɁA������ׂ���̐ݒ�Ɖ��ĕ��݂̓d���g�ጸ��𑁋}�ɍu����ׂ��ƍl������̂ł���܂��B
�@�d���g���́A�����ł͂��܂���グ���܂��A���Ăł́u�Q�P���I�̌��Q�v�ƌ�����قNJ��S���������̂ł���܂��B�����̓d���g�͋ߔN�A����I�ɑ����Ă��܂��B���\���ꂽ�d���g�Ɣ��K�����̊W�́A���d���Ȃǂ���o�钴����g�̓d���g�ł����A�d���g�̓e���r�A�①�ɁA�d�C�J�~�\���Ȃǂ̉ƒ�d�����i�̂قƂ�ǂ��甭��������̂ł����A�}���ɕ��y�����g�ѓd�b�A����͒���g�łȂ��}�C�N���g�Ƃ����d�q�����W�Ɠ����̈�̓d�g���g���܂����������o�܂��B��Ë@���y�[�X���[�J�Ȃǂւ̉e�������ɂȂ��Ă��܂����A�g�ѓd�b�͒��ځA���ɓ��ĂĎg�����߁A�ŋ߂͓��ɔ]��ᇂȂǔ]��ڂɑ���e�����뜜����Ă��܂��B���������҂������ԁA�g���p��ǂ��ڂɂ��邾���ɐS�z�ł��B
�@�����ԁA�g���ƌ����Ӗ��ł̓p�\�R���̃f�B�X�v���[�ɂ��Ă��l�̂ɋߐڂ��Ďg�������ɉe�����S�z����܂��B��������X�E�F�[�f���ł͂b�q�s�f�B�X�v���[�ɂ��Č������d���g�����l��݂��Ă��邱�Ƃ͓��{�̃p�\�R���p���[���[�U�Ԃł͒m���Ă���܂����B��̓I�ɂ͉�ʂ���T�O�p�łQ�D�T�~���K�E�X�i���f�j�ȉ��Ƃ����K�i�ł��B���q�̂��߃X�E�F�[�f�����̐��i��X�E�F�[�f���ւ̗A�o���[�J�[�̂��̂��g���������\�����܂����B���̌�A�t���f�B�X�v���[���嗬�ɂȂ����̂Ŋ댯���͌������Ƃ͎v���܂����A�w�Z��Ɩ��p�ł͂܂��܂��ł��̂ŁA�����Ĉ��S�ł���Ƃ͎v���܂���B
�@����ɋ}���ɕ��y������d��������ɂ��Ă��䏊�ɗ����Ƃ̑�����w�A�Ƃ�킯�D�w�ւ̉e���͉ʂ����đ��v�Ȃ̂��Ǝv���܂��B
�@�G���N�g���j�N�X�Z�p�̋}���Ȕ��W��w�i�Ƃ���ŋ߂̓d�C���i�̊J���́A�����܂ł��Ȃ��A�������̐�����֗��ɉ��K�ɂ�����̂ł���A���͂�A�g��Ȃ��Ƃ�����߂�̑I���͕s�\�̂悤�Ɏv���܂��B�������A���ꂪ�������̌��N�ƈ����ւ��̂��̂ł���Ƃ�����ǂ��Ȃ̂ł��傤���B
�@���̖��ւ̃q���g�ƂȂ�l����������܂��B����́A�u�\�h�����v���邢�́u�T�d�Ȃ����v�ƌ������[���b�p�𒆐S�ɒ���A���s����Ă�����̂ł���܂��B�����Ȋw�I�ɏؖ�����Ă��Ȃ��s�m���Ȏ��Ԃ�O�ɂ����Ƃ��A���ꂪ���ݓI�ɏd��ȃ��X�N��������\��������ꍇ�́A�Ȋw�I�Ȍ��_���o�Ă��Ȃ��Ă��A�\�h�̂��߂̐ϋɓI�ȑ���Ƃ��Ă����ׂ��ł���A���邢�͏����ł��^�킵���\��������A�l�����郊�X�N�͉�����Ă������ƌ����咣�A�ԓx���w���܂��B���z�������ȂǂƂƂ��ɓd���g�ɂ��Ă��K�p����Ă���A�Ⴆ�C�M���X�ł́u�]�̔��B�i�K�̎q�ǂ��͓d���g�̉e�����₷���v�Ƃ��ċ���Ȃ͂P�U�Έȉ��ɂ��ẮA�ً}���ȊO�͌g�ѓd�b���g�p���Ȃ��悤�ɁA�e�w�Z�ɒʒm�����Ƃ����Ƃł��B����ɃI�[�X�g�����A�̂����ŋ߂̗�ł����u���X�x���x�O�Ɉʒu���郍�|�K���s�̓��ǂ͕ϓd����d�͐��i���E�z�d���j����o�鎥����S���f(�~���K�E�X�j��ɂ��邱�ƂŃG�i�W�F�b�N�X(Energex�j�d�͉�Ђƍ��ӂ����Ƃ������Ƃł��B����͂P�O�O�O���f�ň��S�Ƃ���d�͉�Ђ̎咣�ɑ��ďZ���̋�������������A�ŏI�I�ɗ\�h�I���I��Ƃ��ĂS���f��d�͉�Ђ�����u�T�d�Ȃ����v�����s�������̂ł��B���̂��߃G�i�W�F�b�N�X�́A�u�����I�Ɏ��s�\�ȏꏊ�v�łS���f�ȉ��ɉ����邽�ߓd�͐���n��������Ȃǂ̑���n�߂邱�ƂɂȂ������̂ł��B
�@���A�Z���Ɉ�ԋ߂������̂Ƃ��Ďs���̌��N����邽�߂Ƃ�ׂ��ԓx�́A�܂��ɂ��́u�\�h�����v���邢�́u�T�d�Ȃ����v�Ɋ�Â��s���Ǝv�����̂ł���܂��B
�@�H�̈��S���̖��A���邢�͓����d�͂̓_���E��C��Ƃ̃g���u���B���ȂǂɌ�����悤�ɁA�������̐����ɂ�������S�ɂ��Ċ�Ƃ����łȂ����ւ̐M�����傫���h�炢�ł��鍡�A�n�������̂������s���̈��S�����ԂƂȂ�ׂ��Ǝv���܂��B
�@�d���g�͖ڂɂ͌����܂���B���̓_�A����܂ł̐��A��C�̉����̂悤�ɂ͂��̋��낵�����������ɂ������̂ł��B�u�Q�P���I�̌��Q�v���邢�́u���̌��Q�v�ƂȂ�Ȃ����߂̌����ȑΉ������߂��Ă���ƍl������̂ł��B
�@�s�s���ǂł́A���N��Q�̊댯���������邱�̓d���g�ɂ����ɂ��Ăǂ̂悤�ɔF�����Ă���̂��A�����č���̑�̕������ɂ��Ă��q�˂������܂��B
|
|
|
| �s�s�D���Îx���t |
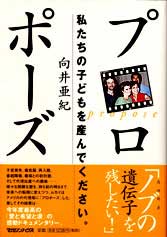 �@�Ō�Ɂu�s�D���Âɑ�����I�x���v�ɂ��ĕی����������Ɏ��₵�܂��B �@�Ō�Ɂu�s�D���Âɑ�����I�x���v�ɂ��ĕی����������Ɏ��₵�܂��B
�@���A�{������̐V���R�[�i�[�ɂ́u�v���|�[�Y�v�|�������̎q�ǂ����Y��ł��������|�Ƃ����{������ł��܂��B
�@�e���r�̎i��A���W�I�ԑg��DJ�Ȃǂł��Ȃ��݂̌��䈟�I�����҂ŁA�q�{��K���ɂ�����A��p���Ă��Ȃ��̒��ň���Ă����P�U�T�̐Ԃ����ƈꏏ�Ɏq�{�������������g�̂炢�̌���������Ă��܂��B�������A���䂳��͗��������͎c���Ăق����Ƃ̈�҂Ƃ̊i���ɋ߂��悤�Ȃ��Ƃ���o�Ċ肢�����Ȃ��A�����@�\���߂�A�㗝�o�Y�Ɋ�]�����������܂����B�������A�����d���ɑ̗͂������Ȃ�������A���@�A���Â̂̌J��Ԃ��ɂ���ɁA����ɑ㗝�o�Y�ɑ�����A�������������Ă��̓��̂�͈�l�łȂ��������Ƃ�������Ă��܂��B����A�j���[�X�œn�Ă��Ē��킳�ꂽ���̂̂��܂������Ȃ��������Ƃ�����Ă��܂����B��ËZ�p�I�ȓ����������̂ł��������Ɍ��䂳��̒���́u�㗝��Ƃ������̂����{�ł��K�v�Ȑl�����āA���̐l�B�̂��Ƃ��l���Ăق����v�Ƃ������b�Z�[�W�𑗂������̂Ƃ��Ď��͕]�����܂��B
�@���āA�D�P��]�݂Ȃ���s�D�ɔY�ޕv�w�͂P�O�g�ɂP�g�̊����Ƃ����Ă��܂��B�s�D���Â̂����A�r���U���܂Ȃǂ̖��Â�nj`���p�Ȃǂ͈�Õی��̑ΏۂƂȂ��Ă���̂ł����A�l�H������̊O�E��i�͂��j�ڐA�A���������Ȃǂɂ͓K�p����Ă���܂���B
�@�P�X�X�X�N�ɓ����̌����Ȃ��s�����A���P�[�g�����ł́A�s�D�ɔY�ޏ��������Âɔ�₷���Ԃ͕��ςS.�U�N�ŁA�R�J���߂��̕a�@��K�₵�A��S���͎��Ô�ɂP�O�O���~�ȏ�������Ă���A�������������ȂNjꂵ�����J��𑱂��Ă���v�w�����Ȃ��Ȃ��Ƃ������Ԃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B����������J���d�˂Ȃ�����X�X�N�ɂ́A����łQ�W���T�O�O�O�l�����Â��A�̊O�E��ڐA�Ȃǂɂ���ĂP�N�ԂɂP���P�X�Q�X�l�̎q�ǂ������܂�Ă��܂��B�킪�����̑̊O�����W�R�N�ɒa�����Ĉȗ��A�ی��K�p�O�̕s�D���Â������ɕ��y���Ă��邱�Ƃ�������̂ł���܂��B
�@����Ɍ��I�x���̒ǂ���������Όo�ϓI���S���y������A�s�D���Âɓ��ݐ鏗�����啝�ɑ����邱�Ƃ͏\���ɗ\�z�ł��܂��B�܂��ĕs�D���ẤA�ł��邾���Ⴂ�����Ɏ������������������Ƃ���Ă��܂��B�o�ϕ��S���y�����邱�ƂŁA��r�I�����̒Ⴂ��N�v�w�ł��e�ՂɎ��Â�����悤�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���́A���A�ł��d�v�ȁu���q����v�Ƃ��Ă����m�Ɉʒu�Â��A�s�D���Âւ̕ی��K�p��J�E���Z�����O�̐��̋����ȂǁA�o�ϓI�A���_�I�Ȏx������u����K�v����Ɋ����܂��B
�@�ŋ߁A�o�ώx�������߂�s�D�NJ��҂̐؎��Ȑ����A�s�������x���ŕs�D���Ô�ɏ������s���������L�����Ă��܂��B���N�S���P������J�n���������̂͐V������z�s�n�߂S�����́A��N�P�N�Ԃł͒��쌧���{�s�ȂǂV�����̂ł��B
�@�����̑Ώۂ́A�l�H������̊O�ȂǕی��K�p�O�̎��Ô�݂̂̏ꍇ�ƁA�ی��f�Â̎��ȕ��S���܂߂����Ô�̏ꍇ�Ƃ�����܂��B
�@�����z�́A�����Ƃ���ł͎��Ô�P�O�O���~�ɑ��āA�T���܂��͂V���ɑ�������T�O���~�܂��͂V�O���~�����x�Ƃ���Ƃ���܂ł���܂��B�܂��A�P���\���ł��Ȃ��Ƃ��납��A���N�A�\���ł���Ƃ���܂ł���A�������x�͎s�����̎���ɍ��킹�Ă��܂��܂ł��B
�@���ɂ����Ă��s�D���ÂɊւ���x���{��𑁋}�Ɋm������ׂ��Ǝv���܂����A��������J����b���^�E���~�[�e�B���O�őO�����Ȕ������������Ƃ������Ă���܂����A�i�ق̉ۑ�ł��鏭�q����̏ォ��A�܂��͎����̂̐ϋɓI�Ȏp�������߂��ׂ��Ǝv���܂����A���̓_�ǂ̂悤�ɂ��l���Ȃ̂����q�˂��������܂�
|
|
|