

| 2002年4月例会 |
| 4月21日 南座歌舞伎鑑賞教室と上村吉弥さん交流会 | ||
 ■昨年4月の「講演と散策と先斗町宴席の1日」の例会以来、2度目の京都例会である。集合場所も昨年同様「南座」前。とはいえ南座は、今回のテーマである歌舞伎鑑賞教室の会場でもある。ゆとりを持って早めの1時に到着。生憎の小雨交じりの中、2時開演にもかかわらず、南座前は雨傘が林立している。デジカメの液晶モニター越しに眺める南座の、380年の伝統を今に伝える威風はさすが。 ■昨年4月の「講演と散策と先斗町宴席の1日」の例会以来、2度目の京都例会である。集合場所も昨年同様「南座」前。とはいえ南座は、今回のテーマである歌舞伎鑑賞教室の会場でもある。ゆとりを持って早めの1時に到着。生憎の小雨交じりの中、2時開演にもかかわらず、南座前は雨傘が林立している。デジカメの液晶モニター越しに眺める南座の、380年の伝統を今に伝える威風はさすが。■雑踏の中、チケット売場前でようやく井上さんを発見。そうこうする内、本日のお世話役の川島さんをはじめ、森さん、岸さん、吉川さんのメンバーの面々が合流。筧田さんと高橋さんは奥さん同伴の参加である。井上さん紹介の初対面の副田さん(デザイン事務所経営)は急病欠席の竹内さんのピンチヒッターとのこと。同じく井上さん紹介の富岡さんご夫婦(白露サッカークラブ代表)、川島さん紹介の福井さん(PHP研究所)を含めて総勢14名が今回の第1部参加者である。筧田さんご夫妻は第2部は不参加とのこと。 川島さんから今回例会の案内書、第2部の会場地図や第2部ゲストの上村吉弥さんの紹介パンフを渡される。 ■開演前の長蛇の列に劇場側も予定を繰り上げ1時20分に入場開始。 初めて見る南座の舞台は思いのほか広く、3階まで吹抜けの高い天井が伝統的な装飾と相まって迫力のある空間をつくりだしている。 入場後、岸さんと一緒に一旦は1階席前側で空いていた右端の席に着席したもののどうも落ち着かない。館内を見学がてら2階席や3階席にも回ってみる。2階席左端の花道を見下ろす席に森さんや副島さんが陣取っている。森さん曰く「この席が芝居なれた人の上席」。「なるほど、納得」。すぐに岸さん共々席替え実行。 |
||
 ■第1部の「南座と歌舞伎」が開幕。幕が上がと、平伏している入道頭の裃姿が目に飛込み観客は一瞬息を呑む。歌舞伎鑑賞教室の解説役・落語家「桂九雀」さんである。 ■第1部の「南座と歌舞伎」が開幕。幕が上がと、平伏している入道頭の裃姿が目に飛込み観客は一瞬息を呑む。歌舞伎鑑賞教室の解説役・落語家「桂九雀」さんである。南座の裏表の案内や以下のような歌舞伎のイロハの面白おかしい解説が落語家ならではの口調で語られる。 ◇役者が心づけ「花」を受け取る道のことを「花道」といった。 ◇昔の屋外の歌舞伎上演で夜の帳が下りるとともに有無を言わさず舞台を打ち切る時の口上を「切口上」といった。 ◇花道にある「せり」のことをすっぽんとも言い、亡霊、妖術使い、狐などの人間以外の出没に使われた等々 日頃の舞台では表に出ることのない鳴物の裏方さんの紹介があり、客席から中学生の女の子が飛入りで太鼓の演奏に挑戦するといった凝った演出が披露される。 ■15分の休憩の後、第2部の歌舞伎上演。今回の演目は「積恋雪関扉(つもるこい ゆきのせきのと)」である。 ストーリーを綴るにはあまりにも複雑。ここは観劇者の感想程度に留めよう。 ■前半は、中村亀鶴さん演ずる関守と上村吉弥さん演じる傾城墨染の掛け合いである。亀鶴さんの荒々しい動きが瞬間の静止に移り、隈取された役者顔がクローズアップされたかのような見得が切られる。舞台中央の桜の古木から登場した吉弥さんの艶姿はぞっとするほど美しい。 関守と墨染がそれぞれに本性を表して、大伴黒主と小町桜の精に早変わりする。その後は二人が絡み合うアップテンポな立廻り中心の舞台となる。歌舞伎の見せ場を随所に織り込んだサービス精神旺盛な舞台だったのではないか。 |
||
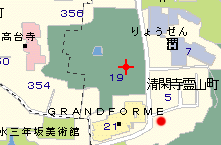  ■4時前に閉幕した南座を後に、例会二次会の会場に向う。 ■4時前に閉幕した南座を後に、例会二次会の会場に向う。タクシーの運転手さんに川島さんからもらった「三塔庵」の地図を見せる。「おそらくここは山村美紗の家のすぐそばじゃないかな」とのこと。「エ〜ッそれじゃその隣は西村京太郎の家?」と思わず小生がミーハーな感嘆詞を発する。 昨年の例会会場でもあった霊山歴史館を100mばかり過ぎた所のとある閑静な住まいを示して運転手さんが言う。「ここが山村美紗の家」(地図の赤丸印)。そしてそのすぐ横には寄り添うように似たような家が建っていた(ヤッパリ、ミーハー)。 ■とはいえ肝心の「三塔庵」が見つからない。やむなく「適当に捜すから」と下車してようやく辿り着いたのがどうみても旧家風の民家とおぼしきところだった(地図の十字印と右画像)。辛うじて石段下の標識用の石にグリーンのペンキで「三塔庵」も文字が読取れる。 ■石段を登り、古い格子戸の門をくぐる。木立の生い茂る庭の踏み石を伝った先に民家がたたずむ。玄関を入ってすぐ左の客間に宴席が準備されていた。 二次会からは新婚の吉川さん(デザイン事務所・ムーンバランス)夫妻が合流。井上さんの突然  の誘いにも関わらず急遽参加してもらった。副田さんの元の仲間だそうだ。 の誘いにも関わらず急遽参加してもらった。副田さんの元の仲間だそうだ。一同着席してほどなくこの家の主が登場。人の良い田舎の親父さん風。聞けばここはあるじの代々の住いだったそうな。サラリーマン勤めの後、脱サラして住いを利用して始めたのがペンション「三塔庵」。川島さんとはサラリーマン時代の労組役員の際の付き合い以来とのこと。 それにしても東山の一等地の広大な敷地の見事な庭園に囲まれた豪邸である。こんな豪邸を引き継いだあるじは、さぞや由緒ある名家の折り目正しいお人柄かとの期待を真っ向から裏切られるキャラの持ち主だった。 落語家・月の家円鏡似の風貌は、トークでもその共通性がいかんなく発揮され、止まるところを知らない。追加のないテーブルのビールは空瓶の山となる。そこで我が名幹事・井上さんは「ご主人!ビールをお願いしますッ」と、覚えたての「切口上」で対抗する。 ■ところでこの家のあるじ横田さんは、実は小生の労組役員時代の知人でもあった。京都中立労協という共通の地域組織で京都岐阜近鉄百貨店労組の役員だった横田さんとは同じ流通グループでしばしば杯を交わしたものだった。思いがけない久々の邂逅だった。 |
||
 |
||
 さくら会のつわもの達と円鏡さんの楽しい掛け合いバトルも一段落した5時半頃、二次会のメインゲストが登場。本日の南座の主役でもある歌舞伎俳優・上村吉弥さんの川島さんに案内されての入場である。 さくら会のつわもの達と円鏡さんの楽しい掛け合いバトルも一段落した5時半頃、二次会のメインゲストが登場。本日の南座の主役でもある歌舞伎俳優・上村吉弥さんの川島さんに案内されての入場である。■化粧を落としたスッピンの吉弥さん同様に、その飾り気のない控えめなトークが、好印象を与える。2000円という破格の料金で南座の使用料、出演者スタッフの人件費他の全て費用を賄わねばならない歌舞伎鑑賞教室の経営上の苦労。それでも敷居を低くすることで少しでも歌舞伎ファンを増やしたいという情熱。高目の身長を低く見せたりなで肩に見せるため工夫等の女形としての立居振舞いのハウツーが明かされる。 ■後半の舞台は、森さんを始めとする、富岡夫人、高橋夫人等女性陣の吉弥さんとの応酬がメインとなる。隙あらばと構えていた円鏡師匠の満を持した突っ込みも中々のものだった。そんなこんなの2時間があっという間に過ぎ去り、全員無事、恒例の記念写真に納まる。 ■7時45分頃、吉弥さん、川島さん、福井さんに小生を加えたメンバーがタクシーに乗り込む。吉弥さんの定宿のホテル経由で無事小生も地下鉄「四条」駅に辿り着く。 ■川島さん設営の4月例会は、長時間でありながらあっという間に過ごした異体験の楽しい1日だった。関西・歌舞伎を愛する会事務局長の川島さん抜きには不可能な貴重な体験と交流だった。感謝。 |