| 2007.10.04 | |||||
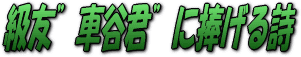 |
|||||
| 2007.10.04 | |||||
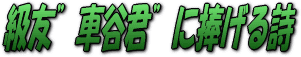 |
|||||
|
|
直木賞作家ご学友への招待状
|
|
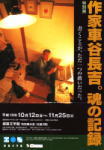 休日の昼過ぎ、郵便受に入っていた郵便物の中に「姫路文学館」差出の封書が目に留まった。開けてみると文学館主催の「作家・車谷長吉、魂の記録」と題する特別展への案内状に招待券が同封されていた。同封の案内状は車谷氏と同じ出身高校の同級の同窓生が宛先だった。 休日の昼過ぎ、郵便受に入っていた郵便物の中に「姫路文学館」差出の封書が目に留まった。開けてみると文学館主催の「作家・車谷長吉、魂の記録」と題する特別展への案内状に招待券が同封されていた。同封の案内状は車谷氏と同じ出身高校の同級の同窓生が宛先だった。
姫路市出身の直木賞作家・車谷長吉氏は、私の小学、中学、高校の同級生である。彼の作品にはしばしば出身地の風景が描写され、親族や知人・友人が赤裸々で生々しく語られる。かくいう私も彼の作品のひとつに腑抜けのチャンピオンのような人物として登場している・・・と思われる。彼にとって出身地・姫路の風景は唾棄すべきものであるかのようだ。 その出身地の市立の文学館が、ふるさとの大作家の特別展を一ヵ月半に渡って開催する。日記や創作ノート、ボツ原稿、万年筆等の「物」の展示を通して車谷長吉の世界に触れてもらおうとのことだ。期間中3度のご本人出演の講演会や対談やトークショーも企画されている。 「最後の私小説作家」「最後の文士」の幼少から思春期までを同じ学び舎で過ごし、何度か互いの実家を行き来した仲でもある。展示品を通して私自身の幼少期の景色を覗き見るかもしれない。ここはぜひとも招待券を活用することにしよう。 |
||
| 10月28日(日) | 大作家・車谷長吉氏の「この世の外」 | |
 直木賞作家・車谷長吉氏の特別展示会と対談会に出かけた。1カ月ほど前に主催者の姫路文学館から氏の高校の同級生宛に招待券を添えた案内状が届いた。期間中には氏が出演する記念イベントも開催されるようだ。著名な作家として成功した幼友達との再開は胸躍らせるものがある。今日開催の記念イベントの参加に応募したところ、主催者から入場整理券が届けられた。展示会訪問の日程が確定した。 直木賞作家・車谷長吉氏の特別展示会と対談会に出かけた。1カ月ほど前に主催者の姫路文学館から氏の高校の同級生宛に招待券を添えた案内状が届いた。期間中には氏が出演する記念イベントも開催されるようだ。著名な作家として成功した幼友達との再開は胸躍らせるものがある。今日開催の記念イベントの参加に応募したところ、主催者から入場整理券が届けられた。展示会訪問の日程が確定した。
朝9時過ぎに家を出て会場最寄りの「山陽電車・姫路駅」に着いたのは11時半頃だった。2時間余りの電車の車内では彼の単行本「鹽壷の匙」に収められた小説「吃りの父が歌った軍歌」を読み返すことで費やした。私らしき人物「三宅」が登場する私小説である。  駅構内で昼食用のお弁当を調達した後、駅前から観光用のレトロなループバスに乗車した。駅前の大通りから大手前で右回りにお城を一巡する定期観光バスだ。姫路城の北西に位置するバス停・清水橋で下車し石畳の小路を西に数分歩いた。突然視界が開け、モダンで大きな建物が現われた。会場の姫路文学館だった。 駅構内で昼食用のお弁当を調達した後、駅前から観光用のレトロなループバスに乗車した。駅前の大通りから大手前で右回りにお城を一巡する定期観光バスだ。姫路城の北西に位置するバス停・清水橋で下車し石畳の小路を西に数分歩いた。突然視界が開け、モダンで大きな建物が現われた。会場の姫路文学館だった。 北館2階の特別展示室受付で招待券を提示し会場に入る。氏の出生以降の本人や家族の写真、通信簿、原稿下書き、作品に登場する愛用品等の様々な展示品が年代順に展示されている。作家・車谷長吉の「魂の記録」をテーマに、見る者に氏の創作活動の全貌を提示する。幼い頃の写真が一緒に遊んだ頃の風景を呼び起こす。 1時間ばかりを展示会場で過ごし、屋外のベンチで弁当を食べた。昔なじみの「まねき食品の穴子めし弁当」が郷愁を誘う。13時前に対談の会場「北館3階講堂」に入った。30分前の会場はまだ入場者も少ない。5列目辺りのパイプ椅子に着席し、「鹽壷の匙」に目を通しながら対談の開始を待った。対談の始まる頃には会場は溢れんばかりの聴衆で埋められ、定員200名の募集人員を超えていたようだ。直前に最前列の関係者の貼り紙のある席に係員に引率されたオバアサンが着  した。展示会場の写真に写された車谷氏のお母さんだ。私にとっても遠い昔に「車谷(シャタニ)のオバチャン」と呼んでいた人だった。 した。展示会場の写真に写された車谷氏のお母さんだ。私にとっても遠い昔に「車谷(シャタニ)のオバチャン」と呼んでいた人だった。 「『鹽壷の匙』と『赤目四十八滝心中未遂』について」というテーマで対談が始まった。車谷氏と対談のパートナーである哲学者で大阪大学総長の鷲田清一氏の登場である。車谷氏は相変わらずトレードマークともいえそうな粗末な甚平を羽織っての登場だ。 冒頭、西部流通グループ主宰の「現代社会文化研究会」のメンバーだった鷲田氏と事務局担当の車谷氏という関係に始まる二十数年来の付き合いが披露される。研究会のテーマのひとつだった「この世の外」というキーワードが紹介され、車谷氏から、これが「赤目四十八滝心中未遂」のテーマであり、自分は「世間の外で生きてきた」自信があるという心情が吐露される。 鷲田氏から「赤目四十八滝心中未遂」が何故、芥川賞でなく直木賞なのかという多くの読者が抱いた疑問を代表するかのような質問があった。車谷氏の回答は意表を突くものだった。「両賞を主宰している文芸春秋社では原稿用紙250枚以上は直木賞、それ以下は芥川賞という基準がある。それで長編の赤目は直木賞になった。芥川賞候補だった『鹽壷の匙』は癩病という不快用語を使用していたことが選考基準の内規に触れて外された」ということだった。釈然としない解説だったが真偽のほどは分らない。 そのほか「『鹽壷の匙』は元々2200枚の作品だったが編集者の求めに応じて80枚にまで削ったものだ」「赤目は90%モデルのないフィクションだが鹽壷は99%実際の話しだ」「私小説も物語も小説を書くということでは同じことだ。私にとっては文体を確立するということがテーマだ」等々の作家であり作者ならではの重みのある発言は興味深いものだった。 それにしても堂々たるトークというほかはない。4歳年下とはいえ大阪大学総長を相手の対談でる。物怖じしない威風堂々の語りっぷりであった。聴衆の笑いを誘うネタも随所に披露する如才なさも見事である。氏の癖なのだろうか、対談中に頻繁に発せられる「チッ」という舌打ちの音がマイクで増幅された。それすらも「世間の外で生きてきた」とい氏のパフォーマンスに思えてしまう。  90分の対談が終わった。この後、氏のサイン会が同じ場所であるとアナウンスされる。帰宅するつもりだったが、「著名人となった幼なじみと40数年ぶりに言葉を交わせる絶好の機会」の誘惑には逆らえなかった。またたくまに長い行列ができている。前列近くの席だった私も10人目位に並んだ。 90分の対談が終わった。この後、氏のサイン会が同じ場所であるとアナウンスされる。帰宅するつもりだったが、「著名人となった幼なじみと40数年ぶりに言葉を交わせる絶好の機会」の誘惑には逆らえなかった。またたくまに長い行列ができている。前列近くの席だった私も10人目位に並んだ。
私の前の人の順番がきた時、瞬間的に氏の眼差しと私の目が合った。思いがけなく見覚えのある顔に合った時に咄嗟に浮かべる表情が浮んだように思った。私の順番が来た時、サインの宛名用にと自作の個人名刺を差し出した。これで彼も顔と名前が一致した筈だ。にもかかわらず氏からは言葉はおろか表情にさえ、密かに期待した旧交を懐かしむ発信は何もない。 「『吃りの父が歌った軍歌』の中に私がモデルらしき人物が登場してるんですね」。思い切って声を掛けてみた。「アア三宅さんネ。でも三宅という名前はよくある名前だから・・・」という言葉が返ってきた。ヤッパリ頭がいいんだと思った。咄嗟の出来事の中で瞬時に「私」と「三宅」を結びつけられるのだから。とはいえ返された言葉の意味は深い。幼なじみと認識した私から発せられた作中モデルのことを「三宅」と呼んだことで、彼自身が私をモデルと考えていたことをはからずも吐露したことになりはしまいか。にもかかわらず「三宅という名前はよくある名前だから」と否定する意図は何か。「腑抜けのチャンピオンのような三宅」として描いたことの弁解なのか。「お前ごときが自分の小説の登場人物のモデルであるわけがない」ということを言外に知らしめたのか。 私の単行本の扉に書かれた氏のサインは見事なものだった。芸能人たちの書く一筆の時間節約型で無造作なサインとは較ぶべくもない。一文字一文字が独特のタッチで丁寧に書かれている。文字にこだわる「最後の文士」の矜持なのか。 いずれにしても私なりにあらためて認識させられたのは次のことだ。「この世の外」で生き抜いてきた果てに今日の栄達を遂げた大作家・車谷長吉氏にとっては、親戚も幼なじみも所詮「この世の内」の情の呼び名でしかない。本質的な部分で「この世の外」で生き続けることを決意した氏は、「この世の内の情」をもって交わることを許さない。あるのは作家と読者の透明な関係だけである。このように整理してみて、氏との再会後のザラついた気持ちがすっきりしたものだ。あらためて作家・車谷氏の一読者として今後の活躍を祈ろう。 帰りの2時間余りの車中には、車谷作品に読み耽るオヤジの姿があった。 |
||
| 1部へ |